4 / 6
ふたりの夏
しおりを挟む
あの日から私の一日ががらりと変わった。
「あさはんだよ」
カナメの声に誘われ、食卓に座る。真向かいで一緒に手を合わせて「いただきます」と頭を下げれば、足元ではミドリさんがキャットフードをカリカリ頬張る音がする。
味噌汁の湯気が鼻先を湿らせる。味噌の匂いをめいっぱい吸い込んだ後は、納豆を混ぜ、サラダのきゅうりを噛むのだ。
「ねぇ、明日はパンのあさはんがいいなぁ」
「ふぅちゃん、パン派なの?」
「どっちでもいいけど、分厚いトーストって食べてみたい。アイスとメープルシロップ乗ってるやつ」
「ふぅちゃん、我がままだなぁ。それ、あさはんっていうよりデザートだよ」
「甘えていいって言ったの、カナメだよ」
「しょうがないなぁ。後でパン屋さんに行こうか」
カナメが糠漬けに箸を伸ばしながら笑っていたが、ふと私を見た。
「そういえば、ふぅちゃんは糠漬け食べないね」
「食べられないことはないけど、あんまり匂いが好きじゃない。でも、死んだおばあちゃんの糠漬けは美味しかった気がする」
そう、祖母の糠漬けはほどよく塩気があり、それでいて味がしっかりしていて美味しかった。とは言っても、小学生のときに祖父の葬儀で会ったとき以来の記憶だけれど。すると、カナメがにんまり口角を上げた。
「それなら大丈夫。これ、ばあちゃんの糠床で漬けたから」
「え?」
驚いてアスパラの糠漬けを見ると、彼はしんみりと言った。
「ばあちゃんが死んだときさ、誰も糠床なんていらないって言うもんだから俺が引き受けたんだ」
確かにうちの母は糠床なんてすぐにカビだらけにしてしまうだろうし、カナメのお母さんだって確かずっと前に離婚していないんだった。
そっと箸を伸ばして糠漬けを口に入れると、なんだか懐かしい味がした。
「どう?」
そう言う割に自信ありげなカナメに、小さく頷く。
「悪くない」
いつもならあまり美味しいと思えない糠漬けなのに、カナメの漬けたものはすんなりと喉を通ったんだ。
「ふぅちゃん、上から目線!」
ちょっと拗ねるカナメだが、まんざらでもない顔をしている。
不思議なものだと思う。誰かとこうして言葉を交わしながら朝食を摂るだけで、その日一日がきちんとしたものになる気がするのだった。
家事を手伝うようになっていた私は、彼から糠床の管理の仕方やダシのとり方を習ったりもした。
「そう、周りはそのつど綺麗に拭いてね。こうして平らにならしてからね」
丁寧に教えてくれるカナメに、ふと訊いてみる。
「カナメはおばあちゃんに習ったの?」
「うん、ここで暮らしていたときにね」
そのとき浮かべた笑みはどことなく切なげで、それ以上何も言えなくなってしまった。詳しくは聞いたことがないけれど、彼にとって祖母は特別な存在であることは確かなようだった。
私は夏休みの課題を、彼はパソコン作業やボタニカルアートを楽しむとお昼ご飯を食べ、そして午後は二人して縁側でくつろぐことが増えた。
庭を見渡せる縁側はカナメとミドリさんのお気に入りのようで、そこに藤色の座布団を敷き、ずっと飽きもせず庭を見ているのだった。脇に置いたお盆には日本茶とカナメの好きな煎餅、そして糠漬け。
扇風機に吹かれるカナメの髪が日差しに茶色く透けているのが綺麗だった。蚊取り線香の匂いを嗅ぎながら、お盆を挟んでカナメと座り、ふと訊いてみる。
「ねぇ、カナメ。どうしてここにずっと座っているの?」
すると、彼はふっとあのどことなく切なげな笑みをまた浮かべる。
「ばあちゃんがね、ミドリさんとよくこうしていたから」
ミドリさんは祖母がカナメと暮らしている間に、庭に居ついた野良猫だったのを家に上げたらしいとそのとき知った。
あまり質問の答えにはなっていない気がしたけれど、とにかくカナメは晴れた日も雨の日もここで庭を見たり読書をしたり、ときにはボタニカルアートを描くのだった。
私はその隣で同じように読書と課題をし、気が向くと見よう見真似でボタニカルアートに挑戦してみたりした。ひどい出来栄えだったけれど。
そして晩ごはんを食べ、一緒に片付けた後にトランプをしたり映画を観て過ごすと、お風呂上りにカキ氷。
なんの変哲もない毎日。だけど三食をきちんと摂り、誰かと笑っているだけで丁寧に一日一日を過ごしている気がして、心が何かで満ちていくのがわかった。
ときには縁側に座らずに、彼のミニクーパーで出かけることもあった。買い物だったり、季節の花を観にいったり。駐車場が見つけにくい目的地のときは、二人であの無人駅からワンマン電車に乗ることもあった。
ある日、私たちは神社の境内で開かれる骨董市に出かけるため家を出た。
「おはよう。今日はどこにお出かけ?」
駅へと向かう途中、太田さんが草むしりの手を止めて声をかけてくれた。
「おはようございます。骨董市に行こうと思って」
カナメがにこやかに声をかける隣で、会釈をした。あの一件以来、挨拶くらいは出来るようになったけれどまだ少し照れくさい。
「……いってきます」
こわごわ声をかけると、太田さんがにっこり微笑んでくれた。
「まぁ、いいわねぇ。楽しんできて。あそこは面白いわよ」
「あ、ありがとうございます」
太田さんに見送られながら、カナメがふっと噴き出した。
「ふぅちゃん、ちゃんと喋れるようになったねぇ」
「もう、子ども扱いするんだから」
ぷうっと口を尖らせたけれど、以前のようには悪い気はしない。カナメだったらいいかなぁと思えるのが不思議だった。
神社の境内では露天がひしめき合い、古本や昭和の国産タイル、着物、瀬戸物、キセルや井戸のポンプまでいろんなものが並んでいた。人ごみでごった返す中、辺りを見回して胸を弾ませる。
「ねぇ、あの丸いのなぁに?」
「あぁ、あれはトンボ玉だよ」
「見たい!」
はしゃぐ私に目を細めるカナメが、すっと私の右手をとった。どくんと爆ぜる心臓。
「迷子になっちゃうよ」
カナメはそう素っ気無く言いながら、私の手を引いてトンボ玉の店に歩み寄る。カナメの手は思ったより大きくてごつい。ぐっと握られた感触に、どぎまぎしてきた。
「あ、あの……」
こんなところ誰かに見られたら恥ずかしいんだけど。そう言おうとしたけれど、声が出ない。
「ほら、これ綺麗じゃない? ふぅちゃんに似合うなぁ」
彼がつまんだのは緋色のトンボ玉だった。こんなに綺麗な物が私に似合うと思ってくれているんだと、なんだか嬉しくなった。彼は店のおじさんに声をかける。
「おじさん、これ頂戴」
すっと離れる手。その瞬間、ハッとした。それを残念に思う自分に気づいたからだ。カナメが財布を取り出し、店のおじさんに代金を渡すのを見ながら、ぐっと手を握り締める。
「はい、これ」
彼は私に小さな紙袋を差し出して、何も知らずに笑う。
「あげる」
「あ、ありがとう……」
従兄弟とはいえ、父以外の男の人からプレゼントをもらうなんて初めてかもしれない。どぎまぎしながらトンボ玉をしまった私の手をまたカナメが引いてくれたのが嬉しかった。広い背中。力強い足取り。じんわりぬくもる手に、思わずはにかんでしまった。
翌日、買い物帰りにばったり太田さんに出くわすと、彼女は嬉々として骨董市の良さを語ってくれた。
「私はね、着物の端切れを探すのが好きなの。ふぅちゃんは何を買ったの?」
「トンボ玉。でも、どう使えばいいのかわからなくって」
すると、彼女が「はぁ」と唸る。
「昔はかんざしに通したり、帯止めにしたもんだけど。紐に通してネックレスとかブレスレットにしたり、バッグのチャームにしたり」
「……でも、ずっと持っていたいから」
そう、お守りのように。アクセサリーにするとぶつけて割ってしまいそうだし、学校にしていけば校則違反になる。
すると、彼女が「よし」と大きく頷いた。
「じゃあ、おばさんがいいもの作ってあげる」
「え?」
「近いうちに渡せると思うわ」
「はい……ありがとうございます」
なんのことやらわからないけれど、御礼を言う。太田さんはなにやらえらく張り切っていた。家に帰った私は台所にいたカナメに駆け寄る。
「ただいま。あのね……」
「ん?」
さっき、太田さんがね……そう言いかけて口をつぐむ。カナメがくれたトンボ玉をお守り代わりに持っていたいなんて言うのが、なんだか恥ずかしく思えたのだ。
「ううん。なんだかいい匂いね」
「今日はふぅちゃんの好きなトンテキだよ」
「本当? やった」
「明日から学校だからね。気合入れなきゃ」
ふっと私の顔から笑みが消える。そうなんだ。明日は高校の始業式。また孤独な日々が始まる。いや、孤独を招いたのは自分自身なんだけども。
すると、それを見透かしたのかカナメが眉尻を下げた。
「今のふぅちゃんなら、きっとすぐにお友達できると思うけどな」
「……いいよ」
だって、みんないつかは離れていくんだもの。最初からいなければ、あんな想いをしなくて済む。なのに、どうしてこんなに寂しいんだろう。一人で座ったまま過ごす教室は牢獄のようで、体育や学校行事なんて苦行以外の何ものでもない。孤独な自分はひどく惨めだ。
すると、カナメがコンロの火をつけながら言う。
「ふぅちゃん、今日はご飯食べたら、温泉に行くからね」
「温泉?」
「うん。ここから車ですぐだから。あったまってこよう」
思わず俯く。カナメがさりげなく私を励まそうとしているのが伝わったからだ。だけど、前のように同情だと気分が尖る自分はいない。その代わり、何故か目の周りがじんわりとしみて、今にも泣き出しそうな自分がいた。
日帰り温泉はカナメが言うように、車で10分ほどのところにあった。靴を預けると、カラオケや食堂、売店のあるホールに出る。そこから男湯と女湯に分かれており、それぞれに露天風呂もついているらしい。
「はい、ふぅちゃん」
温泉への入り口の前で、カナメは100円玉を手渡してくれた。
「これ、ロッカーで使うからね」
「どうやって?」
「100円入れて鍵を閉めるんだよ。で、鍵を開けたらお金は戻ってくるから。ふぅちゃん、こういうの初めて?」
「うん。銭湯とか温泉って入ったこと、あんまりない」
「そうなの?」
「だって、家のお風呂壊れたことないし」
「そうなんだ」
カナメは驚いたようだったけれど、ぽんと私の頭を撫でた。
「ちゃんと体を洗ってから湯船に入るんだよ。タオルは湯船に入れちゃだめだからね。俺、サウナに入ってくるからゆっくりでいいよ。このへんで待ってるから」
「……うん、わかった」
一人で入るのも心細いけれど、まさか一緒に入るわけにいかないし。ちょっと気後れしながら暖簾の向こうに入っていった。
辺りには年齢層の高い女性ばかり。みんな、胸も大きいし、お腹も大きいし、皺だらけ。なんだか脱ぐのが恥ずかしい。
ロッカーを開けた私に、ふと見知らぬおばさんが竹の棒を差し出してくれた。制服を着ているところを見ると清掃か何かのスタッフらしい。竹の棒にきょとんとすると、おばさんが笑う。
「ロッカーのつっかえ棒よ。この扉、手を離すとバタンってしまっちゃうから」
よく見ると、近くに竹の棒がたくさん置いてある。
「あ、ありがとうございます」
会釈すると、おばさんがケラケラと笑った。
「あんた、さっき入り口んとこで男の人と話してたでしょ? 新婚さん?」
「新婚!?」
思わず目を丸くした私に、おばさんがケラケラ笑う。
「初々しいねぇ」
従兄弟です。そう口を開く前に、おばさんが「じゃあね」と掃除用具を手に出て行く。
私はのそりのそり人目を気にしながら服を脱ぐと温泉に入っていった。体を流してから湯船に浸かると、じんじんと体の芯に熱が伝わるのがわかる。でも、頬が火照っているのはきっと、温泉のせいではない。
カナメと私。新婚さんに見えたのか。
「従兄弟なのに」
誰にも聞こえないような小声で呟く。私の囁きはどどっと音をたてて流れ込む湯口の音にかき消されていた。
入浴を済ませて暖簾をくぐると、少し先のソファにカナメが足を組んで座っている。その傍に髪を結い上げた見知らぬ女性。湯上りの少し濡れたうなじが綺麗だ。私が歩み寄ると、カナメは彼女に「連れが来たから、またね」と手を振る。
「妹さんいたっけ?」
「従姉妹だよ」
「そうなんだ。連絡するね」
彼女はちらりと私に視線を走らせて踵を返した。
「カナメ、知り合い?」
「高校の同級生。ばったり会ってさ」
そう言って腰を上げると、彼は私の頭をぽんぽんと撫でる。
「ちゃんと髪乾かしてきた?」
「……子ども扱いしないでよ」
今度は何故か無性にむっとする。だが、カナメはそんなことに気づきもしない様子で歩き出した。
「さぁ、帰ろう」
痩せた背中に私はちょっと恨めしい視線を送った。
ねぇ、カナメ。わかってる? 私、今、妬いてるのよ。従兄弟なのにね。
翌朝、制服姿で食卓についた私をカナメが目を細めて見た。
「ふぅちゃんの制服姿、初めて見たね」
あさはんを見ると、私の好きなおかずばかり乗っている。カナメなりの激励がそこにあった。いつもならすすむ箸も、この姿だとご飯が喉を通らない。
「……いってきます」
足元にからみついてくるミドリさんをちょっと撫でてから玄関を出ると、カナメの声が飛んできた。
「ふぅちゃん、大丈夫! うちのあさはん食べたら百人力だよ」
なにが大丈夫なんだかわからないよ。呆れて振り返ると、底抜けに明るい笑みを浮かべたカナメが大きく手を振ってくれていた。
そっとスカートのポケットに忍ばせたトンボ玉を握る。つるんとした冷たい感触が自分の体温でぬくもっていく。
……うん、大丈夫かもね。
そのときだ。
「高崎さん?」
声がした方を見ると、背の高い女の子がいる。同じ制服だけど、顔は見たことがない。
「は、はい」
おずおず答えると、彼女が「はい」と何かを差し出した。見ると、着物の端切れで作ったらしい小さな巾着だ。
「うちのお母さんから。トンボ玉入れなってさ」
「え?」
「あたし、太田。太田冴子」
「……あ、もしかして」
「あんたんちの隣」
知らなかった。太田さんに娘がいて、しかも私と同じ高校だなんて。目を丸くしていると、彼女がもう一度巾着をぐっと差し出す。おずおず「ありがと」と受け取ると、彼女が「行こう」と先を促した。
「最近、お母さんがあんたの話するんだよね。あたし今まで部活の朝練習があって電車の時間が違ったんだけどさ」
聞きながら顔を引きつらせていたけれど、思わず声を上げた。
「あ!」
「どうした?」
「英語の辞書忘れた」
どうしよう、3時間目に使うのに。今から戻ったら電車に間に合わない。血の気が引いた私に、彼女が「なんだ」と笑った。
「あんた、1組でしょ? あたし5組だから終わったら貸すよ」
「いいの?」
「うん。近所のよしみ」
「……ありがとう」
彼女は私を見て母親そっくりの顔で笑った。
「あんたのクラスの子は暗いって言ってたけど、そうでもないじゃん」
ずいぶんはっきり物を言う子だ。けれど悪くないと思った。
その日の夕食で、私はカナメに太田さんの娘の話をした。
「あぁ、そういえば冴子ちゃんとふぅちゃんは同い年だね。友達になれそう?」
「……わかんない。だってクラスも違うし、普段はあの子、部活の朝練習があるから電車の時間も違うし、それに……」
どうせいつか嫌われるなら、仲良くならなくていいよ。でも、それを口にすることが出来なかった。何故って? 正直に言うと嬉しかったんだ。久しぶりに話せる子が出来たこと。英語の辞書を返しに行ったとき、笑顔で「またいつでも貸すよ」って言ってくれたこと。たったそれだけのことで帰りは走り出しそうだった。
本当は仲良くなってみたい。口をつぐんだ私に、カナメはこう呟いた。
「いつか、話したくなったら聞くよ」
「……うん」
カブのあんかけを箸で崩しながら、私はそっと頷いた。そうだね。いつか、カナメになら話してもいいかもしれないね。
だって、ずっとポケットであのトンボ玉を握り締めていると、なんの保障もなく『大丈夫』って思えたんだもの。後ろからカナメがそっと背中を押してくれるような、そんな気がしていた。
真向かいで味噌汁をすするカナメを盗み見る。
味噌汁の湯気で少し曇った眼鏡。今日はちょっと髭剃りを失敗したらしく、顎に小さい切り傷。きちんと背筋を伸ばして食べる彼の姿が好きだ。穏やかな声も、物腰の柔らかさも、なんだかお父さんみたいに見守ってくれるところも。
私、カナメが好き。他の女の人と話しているだけで妬く程度には好きだと思う。
けどね、従兄弟って難しいんだよ。だって、親戚だもの。身内なんだよ。想いを打ち明けて駄目だったら二度と会わないって訳にいかない。気持ち悪いって思われたら? この心地いい時間が踏みにじられる気がして怖かった。
ちょっとはカナメと暮らして変わったと思ってた。
人と歩み寄ってみてもいいのかもしれないって思えそうな気がしてた。だけど、臆病なのはちっとも変わっていない。
なのにカナメはずるいんだ。カナメなら何を言っても『大丈夫』って錯覚させちゃうんだもの。
ねぇ、カナメ。あんまり優しいと罪になるんだぞ。
カブに箸をぶすりと刺して、わしわしと噛み砕いてやった。
「あさはんだよ」
カナメの声に誘われ、食卓に座る。真向かいで一緒に手を合わせて「いただきます」と頭を下げれば、足元ではミドリさんがキャットフードをカリカリ頬張る音がする。
味噌汁の湯気が鼻先を湿らせる。味噌の匂いをめいっぱい吸い込んだ後は、納豆を混ぜ、サラダのきゅうりを噛むのだ。
「ねぇ、明日はパンのあさはんがいいなぁ」
「ふぅちゃん、パン派なの?」
「どっちでもいいけど、分厚いトーストって食べてみたい。アイスとメープルシロップ乗ってるやつ」
「ふぅちゃん、我がままだなぁ。それ、あさはんっていうよりデザートだよ」
「甘えていいって言ったの、カナメだよ」
「しょうがないなぁ。後でパン屋さんに行こうか」
カナメが糠漬けに箸を伸ばしながら笑っていたが、ふと私を見た。
「そういえば、ふぅちゃんは糠漬け食べないね」
「食べられないことはないけど、あんまり匂いが好きじゃない。でも、死んだおばあちゃんの糠漬けは美味しかった気がする」
そう、祖母の糠漬けはほどよく塩気があり、それでいて味がしっかりしていて美味しかった。とは言っても、小学生のときに祖父の葬儀で会ったとき以来の記憶だけれど。すると、カナメがにんまり口角を上げた。
「それなら大丈夫。これ、ばあちゃんの糠床で漬けたから」
「え?」
驚いてアスパラの糠漬けを見ると、彼はしんみりと言った。
「ばあちゃんが死んだときさ、誰も糠床なんていらないって言うもんだから俺が引き受けたんだ」
確かにうちの母は糠床なんてすぐにカビだらけにしてしまうだろうし、カナメのお母さんだって確かずっと前に離婚していないんだった。
そっと箸を伸ばして糠漬けを口に入れると、なんだか懐かしい味がした。
「どう?」
そう言う割に自信ありげなカナメに、小さく頷く。
「悪くない」
いつもならあまり美味しいと思えない糠漬けなのに、カナメの漬けたものはすんなりと喉を通ったんだ。
「ふぅちゃん、上から目線!」
ちょっと拗ねるカナメだが、まんざらでもない顔をしている。
不思議なものだと思う。誰かとこうして言葉を交わしながら朝食を摂るだけで、その日一日がきちんとしたものになる気がするのだった。
家事を手伝うようになっていた私は、彼から糠床の管理の仕方やダシのとり方を習ったりもした。
「そう、周りはそのつど綺麗に拭いてね。こうして平らにならしてからね」
丁寧に教えてくれるカナメに、ふと訊いてみる。
「カナメはおばあちゃんに習ったの?」
「うん、ここで暮らしていたときにね」
そのとき浮かべた笑みはどことなく切なげで、それ以上何も言えなくなってしまった。詳しくは聞いたことがないけれど、彼にとって祖母は特別な存在であることは確かなようだった。
私は夏休みの課題を、彼はパソコン作業やボタニカルアートを楽しむとお昼ご飯を食べ、そして午後は二人して縁側でくつろぐことが増えた。
庭を見渡せる縁側はカナメとミドリさんのお気に入りのようで、そこに藤色の座布団を敷き、ずっと飽きもせず庭を見ているのだった。脇に置いたお盆には日本茶とカナメの好きな煎餅、そして糠漬け。
扇風機に吹かれるカナメの髪が日差しに茶色く透けているのが綺麗だった。蚊取り線香の匂いを嗅ぎながら、お盆を挟んでカナメと座り、ふと訊いてみる。
「ねぇ、カナメ。どうしてここにずっと座っているの?」
すると、彼はふっとあのどことなく切なげな笑みをまた浮かべる。
「ばあちゃんがね、ミドリさんとよくこうしていたから」
ミドリさんは祖母がカナメと暮らしている間に、庭に居ついた野良猫だったのを家に上げたらしいとそのとき知った。
あまり質問の答えにはなっていない気がしたけれど、とにかくカナメは晴れた日も雨の日もここで庭を見たり読書をしたり、ときにはボタニカルアートを描くのだった。
私はその隣で同じように読書と課題をし、気が向くと見よう見真似でボタニカルアートに挑戦してみたりした。ひどい出来栄えだったけれど。
そして晩ごはんを食べ、一緒に片付けた後にトランプをしたり映画を観て過ごすと、お風呂上りにカキ氷。
なんの変哲もない毎日。だけど三食をきちんと摂り、誰かと笑っているだけで丁寧に一日一日を過ごしている気がして、心が何かで満ちていくのがわかった。
ときには縁側に座らずに、彼のミニクーパーで出かけることもあった。買い物だったり、季節の花を観にいったり。駐車場が見つけにくい目的地のときは、二人であの無人駅からワンマン電車に乗ることもあった。
ある日、私たちは神社の境内で開かれる骨董市に出かけるため家を出た。
「おはよう。今日はどこにお出かけ?」
駅へと向かう途中、太田さんが草むしりの手を止めて声をかけてくれた。
「おはようございます。骨董市に行こうと思って」
カナメがにこやかに声をかける隣で、会釈をした。あの一件以来、挨拶くらいは出来るようになったけれどまだ少し照れくさい。
「……いってきます」
こわごわ声をかけると、太田さんがにっこり微笑んでくれた。
「まぁ、いいわねぇ。楽しんできて。あそこは面白いわよ」
「あ、ありがとうございます」
太田さんに見送られながら、カナメがふっと噴き出した。
「ふぅちゃん、ちゃんと喋れるようになったねぇ」
「もう、子ども扱いするんだから」
ぷうっと口を尖らせたけれど、以前のようには悪い気はしない。カナメだったらいいかなぁと思えるのが不思議だった。
神社の境内では露天がひしめき合い、古本や昭和の国産タイル、着物、瀬戸物、キセルや井戸のポンプまでいろんなものが並んでいた。人ごみでごった返す中、辺りを見回して胸を弾ませる。
「ねぇ、あの丸いのなぁに?」
「あぁ、あれはトンボ玉だよ」
「見たい!」
はしゃぐ私に目を細めるカナメが、すっと私の右手をとった。どくんと爆ぜる心臓。
「迷子になっちゃうよ」
カナメはそう素っ気無く言いながら、私の手を引いてトンボ玉の店に歩み寄る。カナメの手は思ったより大きくてごつい。ぐっと握られた感触に、どぎまぎしてきた。
「あ、あの……」
こんなところ誰かに見られたら恥ずかしいんだけど。そう言おうとしたけれど、声が出ない。
「ほら、これ綺麗じゃない? ふぅちゃんに似合うなぁ」
彼がつまんだのは緋色のトンボ玉だった。こんなに綺麗な物が私に似合うと思ってくれているんだと、なんだか嬉しくなった。彼は店のおじさんに声をかける。
「おじさん、これ頂戴」
すっと離れる手。その瞬間、ハッとした。それを残念に思う自分に気づいたからだ。カナメが財布を取り出し、店のおじさんに代金を渡すのを見ながら、ぐっと手を握り締める。
「はい、これ」
彼は私に小さな紙袋を差し出して、何も知らずに笑う。
「あげる」
「あ、ありがとう……」
従兄弟とはいえ、父以外の男の人からプレゼントをもらうなんて初めてかもしれない。どぎまぎしながらトンボ玉をしまった私の手をまたカナメが引いてくれたのが嬉しかった。広い背中。力強い足取り。じんわりぬくもる手に、思わずはにかんでしまった。
翌日、買い物帰りにばったり太田さんに出くわすと、彼女は嬉々として骨董市の良さを語ってくれた。
「私はね、着物の端切れを探すのが好きなの。ふぅちゃんは何を買ったの?」
「トンボ玉。でも、どう使えばいいのかわからなくって」
すると、彼女が「はぁ」と唸る。
「昔はかんざしに通したり、帯止めにしたもんだけど。紐に通してネックレスとかブレスレットにしたり、バッグのチャームにしたり」
「……でも、ずっと持っていたいから」
そう、お守りのように。アクセサリーにするとぶつけて割ってしまいそうだし、学校にしていけば校則違反になる。
すると、彼女が「よし」と大きく頷いた。
「じゃあ、おばさんがいいもの作ってあげる」
「え?」
「近いうちに渡せると思うわ」
「はい……ありがとうございます」
なんのことやらわからないけれど、御礼を言う。太田さんはなにやらえらく張り切っていた。家に帰った私は台所にいたカナメに駆け寄る。
「ただいま。あのね……」
「ん?」
さっき、太田さんがね……そう言いかけて口をつぐむ。カナメがくれたトンボ玉をお守り代わりに持っていたいなんて言うのが、なんだか恥ずかしく思えたのだ。
「ううん。なんだかいい匂いね」
「今日はふぅちゃんの好きなトンテキだよ」
「本当? やった」
「明日から学校だからね。気合入れなきゃ」
ふっと私の顔から笑みが消える。そうなんだ。明日は高校の始業式。また孤独な日々が始まる。いや、孤独を招いたのは自分自身なんだけども。
すると、それを見透かしたのかカナメが眉尻を下げた。
「今のふぅちゃんなら、きっとすぐにお友達できると思うけどな」
「……いいよ」
だって、みんないつかは離れていくんだもの。最初からいなければ、あんな想いをしなくて済む。なのに、どうしてこんなに寂しいんだろう。一人で座ったまま過ごす教室は牢獄のようで、体育や学校行事なんて苦行以外の何ものでもない。孤独な自分はひどく惨めだ。
すると、カナメがコンロの火をつけながら言う。
「ふぅちゃん、今日はご飯食べたら、温泉に行くからね」
「温泉?」
「うん。ここから車ですぐだから。あったまってこよう」
思わず俯く。カナメがさりげなく私を励まそうとしているのが伝わったからだ。だけど、前のように同情だと気分が尖る自分はいない。その代わり、何故か目の周りがじんわりとしみて、今にも泣き出しそうな自分がいた。
日帰り温泉はカナメが言うように、車で10分ほどのところにあった。靴を預けると、カラオケや食堂、売店のあるホールに出る。そこから男湯と女湯に分かれており、それぞれに露天風呂もついているらしい。
「はい、ふぅちゃん」
温泉への入り口の前で、カナメは100円玉を手渡してくれた。
「これ、ロッカーで使うからね」
「どうやって?」
「100円入れて鍵を閉めるんだよ。で、鍵を開けたらお金は戻ってくるから。ふぅちゃん、こういうの初めて?」
「うん。銭湯とか温泉って入ったこと、あんまりない」
「そうなの?」
「だって、家のお風呂壊れたことないし」
「そうなんだ」
カナメは驚いたようだったけれど、ぽんと私の頭を撫でた。
「ちゃんと体を洗ってから湯船に入るんだよ。タオルは湯船に入れちゃだめだからね。俺、サウナに入ってくるからゆっくりでいいよ。このへんで待ってるから」
「……うん、わかった」
一人で入るのも心細いけれど、まさか一緒に入るわけにいかないし。ちょっと気後れしながら暖簾の向こうに入っていった。
辺りには年齢層の高い女性ばかり。みんな、胸も大きいし、お腹も大きいし、皺だらけ。なんだか脱ぐのが恥ずかしい。
ロッカーを開けた私に、ふと見知らぬおばさんが竹の棒を差し出してくれた。制服を着ているところを見ると清掃か何かのスタッフらしい。竹の棒にきょとんとすると、おばさんが笑う。
「ロッカーのつっかえ棒よ。この扉、手を離すとバタンってしまっちゃうから」
よく見ると、近くに竹の棒がたくさん置いてある。
「あ、ありがとうございます」
会釈すると、おばさんがケラケラと笑った。
「あんた、さっき入り口んとこで男の人と話してたでしょ? 新婚さん?」
「新婚!?」
思わず目を丸くした私に、おばさんがケラケラ笑う。
「初々しいねぇ」
従兄弟です。そう口を開く前に、おばさんが「じゃあね」と掃除用具を手に出て行く。
私はのそりのそり人目を気にしながら服を脱ぐと温泉に入っていった。体を流してから湯船に浸かると、じんじんと体の芯に熱が伝わるのがわかる。でも、頬が火照っているのはきっと、温泉のせいではない。
カナメと私。新婚さんに見えたのか。
「従兄弟なのに」
誰にも聞こえないような小声で呟く。私の囁きはどどっと音をたてて流れ込む湯口の音にかき消されていた。
入浴を済ませて暖簾をくぐると、少し先のソファにカナメが足を組んで座っている。その傍に髪を結い上げた見知らぬ女性。湯上りの少し濡れたうなじが綺麗だ。私が歩み寄ると、カナメは彼女に「連れが来たから、またね」と手を振る。
「妹さんいたっけ?」
「従姉妹だよ」
「そうなんだ。連絡するね」
彼女はちらりと私に視線を走らせて踵を返した。
「カナメ、知り合い?」
「高校の同級生。ばったり会ってさ」
そう言って腰を上げると、彼は私の頭をぽんぽんと撫でる。
「ちゃんと髪乾かしてきた?」
「……子ども扱いしないでよ」
今度は何故か無性にむっとする。だが、カナメはそんなことに気づきもしない様子で歩き出した。
「さぁ、帰ろう」
痩せた背中に私はちょっと恨めしい視線を送った。
ねぇ、カナメ。わかってる? 私、今、妬いてるのよ。従兄弟なのにね。
翌朝、制服姿で食卓についた私をカナメが目を細めて見た。
「ふぅちゃんの制服姿、初めて見たね」
あさはんを見ると、私の好きなおかずばかり乗っている。カナメなりの激励がそこにあった。いつもならすすむ箸も、この姿だとご飯が喉を通らない。
「……いってきます」
足元にからみついてくるミドリさんをちょっと撫でてから玄関を出ると、カナメの声が飛んできた。
「ふぅちゃん、大丈夫! うちのあさはん食べたら百人力だよ」
なにが大丈夫なんだかわからないよ。呆れて振り返ると、底抜けに明るい笑みを浮かべたカナメが大きく手を振ってくれていた。
そっとスカートのポケットに忍ばせたトンボ玉を握る。つるんとした冷たい感触が自分の体温でぬくもっていく。
……うん、大丈夫かもね。
そのときだ。
「高崎さん?」
声がした方を見ると、背の高い女の子がいる。同じ制服だけど、顔は見たことがない。
「は、はい」
おずおず答えると、彼女が「はい」と何かを差し出した。見ると、着物の端切れで作ったらしい小さな巾着だ。
「うちのお母さんから。トンボ玉入れなってさ」
「え?」
「あたし、太田。太田冴子」
「……あ、もしかして」
「あんたんちの隣」
知らなかった。太田さんに娘がいて、しかも私と同じ高校だなんて。目を丸くしていると、彼女がもう一度巾着をぐっと差し出す。おずおず「ありがと」と受け取ると、彼女が「行こう」と先を促した。
「最近、お母さんがあんたの話するんだよね。あたし今まで部活の朝練習があって電車の時間が違ったんだけどさ」
聞きながら顔を引きつらせていたけれど、思わず声を上げた。
「あ!」
「どうした?」
「英語の辞書忘れた」
どうしよう、3時間目に使うのに。今から戻ったら電車に間に合わない。血の気が引いた私に、彼女が「なんだ」と笑った。
「あんた、1組でしょ? あたし5組だから終わったら貸すよ」
「いいの?」
「うん。近所のよしみ」
「……ありがとう」
彼女は私を見て母親そっくりの顔で笑った。
「あんたのクラスの子は暗いって言ってたけど、そうでもないじゃん」
ずいぶんはっきり物を言う子だ。けれど悪くないと思った。
その日の夕食で、私はカナメに太田さんの娘の話をした。
「あぁ、そういえば冴子ちゃんとふぅちゃんは同い年だね。友達になれそう?」
「……わかんない。だってクラスも違うし、普段はあの子、部活の朝練習があるから電車の時間も違うし、それに……」
どうせいつか嫌われるなら、仲良くならなくていいよ。でも、それを口にすることが出来なかった。何故って? 正直に言うと嬉しかったんだ。久しぶりに話せる子が出来たこと。英語の辞書を返しに行ったとき、笑顔で「またいつでも貸すよ」って言ってくれたこと。たったそれだけのことで帰りは走り出しそうだった。
本当は仲良くなってみたい。口をつぐんだ私に、カナメはこう呟いた。
「いつか、話したくなったら聞くよ」
「……うん」
カブのあんかけを箸で崩しながら、私はそっと頷いた。そうだね。いつか、カナメになら話してもいいかもしれないね。
だって、ずっとポケットであのトンボ玉を握り締めていると、なんの保障もなく『大丈夫』って思えたんだもの。後ろからカナメがそっと背中を押してくれるような、そんな気がしていた。
真向かいで味噌汁をすするカナメを盗み見る。
味噌汁の湯気で少し曇った眼鏡。今日はちょっと髭剃りを失敗したらしく、顎に小さい切り傷。きちんと背筋を伸ばして食べる彼の姿が好きだ。穏やかな声も、物腰の柔らかさも、なんだかお父さんみたいに見守ってくれるところも。
私、カナメが好き。他の女の人と話しているだけで妬く程度には好きだと思う。
けどね、従兄弟って難しいんだよ。だって、親戚だもの。身内なんだよ。想いを打ち明けて駄目だったら二度と会わないって訳にいかない。気持ち悪いって思われたら? この心地いい時間が踏みにじられる気がして怖かった。
ちょっとはカナメと暮らして変わったと思ってた。
人と歩み寄ってみてもいいのかもしれないって思えそうな気がしてた。だけど、臆病なのはちっとも変わっていない。
なのにカナメはずるいんだ。カナメなら何を言っても『大丈夫』って錯覚させちゃうんだもの。
ねぇ、カナメ。あんまり優しいと罪になるんだぞ。
カブに箸をぶすりと刺して、わしわしと噛み砕いてやった。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

児童絵本館のオオカミ
火隆丸
児童書・童話
閉鎖した児童絵本館に放置されたオオカミの着ぐるみが語る、数々の思い出。ボロボロの着ぐるみの中には、たくさんの人の想いが詰まっています。着ぐるみと人との間に生まれた、切なくも美しい物語です。

フツーさがしの旅
雨ノ川からもも
児童書・童話
フツーじゃない白猫と、頼れるアニキ猫の成長物語
「お前、フツーじゃないんだよ」
兄弟たちにそうからかわれ、家族のもとを飛び出した子猫は、森の中で、先輩ノラ猫「ドライト」と出会う。
ドライトに名前をもらい、一緒に生活するようになったふたり。
狩りの練習に、町へのお出かけ、そして、新しい出会い。
二匹のノラ猫を中心に描かれる、成長物語。

イケメン男子とドキドキ同居!? ~ぽっちゃりさんの学園リデビュー計画~
友野紅子
児童書・童話
ぽっちゃりヒロインがイケメン男子と同居しながらダイエットして綺麗になって、学園リデビューと恋、さらには将来の夢までゲットする成長の物語。
全編通し、基本的にドタバタのラブコメディ。時々、シリアス。

RICE WORK
フィッシュナツミ
経済・企業
近未来の日本、長時間労働と低賃金に苦しむ社会で、国民全員に月額11万円を支給するベーシックインカムが導入され、誰もが「生活のために働かなくても良い」自由を手にしたかに見えました。希望に満ちた時代が到来する中、人々は仕事から解放され、家族との時間や自分の夢に専念できるようになります。しかし、時が経つにつれ、社会には次第に違和感が漂い始めます。
『RICE WORK』は、経済的安定と引き換えに失われた「働くことの意味」や「人間としての尊厳」を問いかける物語。理想と現実の狭間で揺れる人々の姿を通して、私たちに社会の未来を考えさせるディストピア小説です。
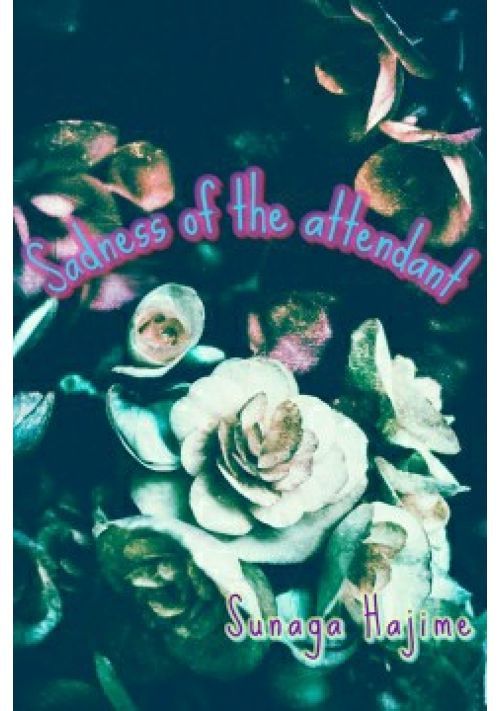
Sadness of the attendant
砂詠 飛来
児童書・童話
王子がまだ生熟れであるように、姫もまだまだ小娘でありました。
醜いカエルの姿に変えられてしまった王子を嘆く従者ハインリヒ。彼の強い憎しみの先に居たのは、王子を救ってくれた姫だった。

月神山の不気味な洋館
ひろみ透夏
児童書・童話
初めての夜は不気味な洋館で?!
満月の夜、級友サトミの家の裏庭上空でおこる怪現象を見せられたケンヂは、正体を確かめようと登った木の上で奇妙な物体と遭遇。足を踏み外し落下してしまう……。
話は昼間にさかのぼる。
両親が泊まりがけの旅行へ出かけた日、ケンヂは友人から『旅行中の両親が深夜に帰ってきて、あの世に連れて行く』という怪談を聞かされる。
その日の放課後、ふだん男子と会話などしない、おとなしい性格の級友サトミから、とつぜん話があると呼び出されたケンヂ。その話とは『今夜、私のうちに泊りにきて』という、とんでもない要求だった。

佐藤さんの四重奏
makoto(木城まこと)
児童書・童話
佐藤千里は小学5年生の女の子。昔から好きになるものは大抵男子が好きになるもので、女子らしくないといじめられたことを機に、本当の自分をさらけ出せなくなってしまう。そんな中、男子と偽って出会った佐藤陽がとなりのクラスに転校してきて、千里の本当の性別がバレてしまい――?
弦楽器を通じて自分らしさを見つける、小学生たちの物語。
第2回きずな児童書大賞で奨励賞をいただきました。ありがとうございます!

蒸気都市『碧霞傀儡技師高等学園』潜入調査報告書
yolu
児童書・童話
【スチパン×スパイ】
彼女の物語は、いつも“絶望”から始まる──
今年16歳となるコードネーム・梟(きょう)は、蒸気国家・倭国が設立した秘匿組織・朧月会からの任務により、蒸気国家・倭国の最上級高校である、碧霞(あおがすみ)蒸気技巧高等学園の1年生として潜入する。
しかし、彼女が得意とする話術を用いれば容易に任務などクリアできるが、一つの出来事から声を失った梟は、どう任務をクリアしていくのか──
──絶望すら武器にする、彼女の物語をご覧ください。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















