3 / 6
飛び散った糠漬け
しおりを挟む
「あさはん、できたよ」
あれから何日過ぎただろう。今日も聞こえるカナメの声。
「いらないってば」
吐き捨てるような私の声。もう何度目かわからない同じやりとり。そのたびに彼は切なげに眉を下げ、しゃもじを置くんだ。
どうして彼はいらないと言っているのに、こうも頑なに『あさはん』を用意するのか。私は夏休みの課題をする手を休め、机に頬杖をついた。
「ミドリさん、外に出ちゃだめだよ」
ふと、窓の外から声がする。そろそろと覗いてみると、カナメがホースで庭に水撒きをしているようだった。
カナメはミドリさんに人間と同じように話しかける。いかにもお人よしな声で。かと思えば、晴れた日に庭先でボタニカルアートに興じているときは話しかけるのもためらわれるような鋭い顔をすることもあった。
親戚の間ではちょっと変わった子という評判だった。午前中はパソコンでなにやら打ち込みをしたりボタニカルアートを描いたりしているが、午後になると縁側でミドリさんと一緒に座って庭を見ているのだ。
脇にお茶と糠漬けと好物の煎餅を乗せたお盆を置き、ただ何をするでもなく、ひたすら池の辺りを見つめている。
20歳を過ぎたばかりの男が、朝昼晩に糠床を混ぜることを決して忘れないというのも珍しいように感じた。そう、あの夏時雨のときに持っていた重そうな手提げ袋。あの中には糠床が入っていたのだ。最低限の着替えと髭剃り、そしてボタニカルアートの画材くらいしか車にはなく、大事な猫と糠床を真っ先に玄関に運んだらしい。
あいにく私は糠漬けが苦手だった。どうも糠の匂いというのが受け付けない。それもあって、必ず食卓の脇に糠漬けが登場するカナメのあさはんは尚更気が向かないのだった。
けれど、私は知っている。一度だけトイレに起きたときに見てしまったんだ。私が寝静まった頃に糠床をかき混ぜ、昆布とカツオでダシをとっているカナメを。きっと、彼の日課なのだろう。
どうして彼はそこまでして『あさはん』にこだわるのか。何故、いらないというものを押し付けてくるのか。
強引な善意など迷惑だ。この家にはこの家のやり方がある。そう、たとえ父が飲み屋の女とできて家を出ても。母が仕事ばかりで家にいないのが当たり前だとしても。世間的には朝食があった方が好ましいとされているとしても。この家には私たちが築いてきたやり方があるんだよ。それを土足で踏みつけられているようで、無性に苛立った。
そんな不満が爆発したのは、カナメが来て半月ほど経った頃だった。
「あさはんだよ」
いつもの掛け声。湯気の上がる食卓を見下ろし、私はぐっと拳を握り締めた。
「……もう嫌」
頭にかぁっと血が上っていくのがまざまざと伝わる。きょとんとしたカナメに向かって吐く私の声は震えていた。
「なんでいらないってのに用意するの? どうして善意の押し売りするの? お母さんからバイト代をもらってるから? 迷惑なのよ。なんでそれがわからないのよ? 自分がいつだって正しいと思ってるの?」
一度あふれ出した言葉はまるで破れた防波堤から鉄砲水が飛び出すように止められなかった。怒りの限度を越えるとわなわなと体も声も震えるものらしい。それに、怒鳴るわけでもなく、ただただ抑揚の効いた声しか出ない。わめいたら血管が破裂しそうだからかもしれない。
すると、カナメはいつものように眉を下げるだけでなく小さくため息を漏らした。
「バイト代なんて関係ないよ。悲しいこと言うなよ」
「じゃあ、なんでよ?」
「あさはんはね、一日を大切に過ごすためのおまじないだからだよ」
「はぁ?」
なんとも平和ボケした答えに、あんぐり口が開いた。それでもカナメはひるまない。
「一日を大切に過ごせば、誰かも大切にできるから。自分もね」
「偉そうなこと言わないでよ。何も知らないくせに!」
その刹那、頭が真っ白になった。なんと私は目についた糠漬けを鷲づかみにし、カナメに向かって投げつけたのだ。
飛び散る糠漬けが床に落ちるペタペタンという情けない音を、肩で息をしながら聞いた。その瞬間、さっきまで頭に上っていた血がさぁっと引いていく。
私……今、何をしたの?
そして恐る恐るカナメの顔を見つめたんだ。カナメは何も言わず、私の目の前に歩み寄った。すっと彼の手が動く。
怒られる……!
咄嗟にきつく目を閉じた私の頬に、むにっという感触が走った。恐る恐る目を開けると、カナメが私の頬を両手で挟んでじっと見つめているのだ。
「……食べ物を粗末にしたらいけないよ」
そのときのカナメの声に帯びた悲しそうな響きが、ぐっと私の胸を狭くした。そう、彼の目は怒っていなかった。ただひたすら悲しげで、それがかえって私を責めている気がして恥ずかしくなった。
「あ! ふぅちゃん!」
気がつけば私は彼の手を振りほどいて外に飛び出していたのである。うまく履けないままの靴で転びそうになりながら、走る。無性に叫びたいのをぐっと堪え、どこでもいいから消えてしまいたかった。
「あらぁ、高崎さんとこの」
道の向こうから買い物袋を手に提げて歩いてくるのは、太田さんだ。
「おばさん……!」
私が彼女を呼んだのが初めてだからか、それとも私の顔がひどいのか、太田さんは目をまん丸にしている。
「どうしたの。何かあったの?」
「おばさん、東京行きの電車って何時から?」
「え?」
「もう行ける?」
「え、えぇ。この時間ならもう動いているはずだけど」
私はそれを聞いて咄嗟に走り出した。
「あ、ちょっと!」
後ろで太田さんが呼び止める声を無視し、坂道を駆けていく。もう嫌だ。どこでもいい。ここじゃないところへ行きたい。どうせどこにも居場所がないのなら、ここじゃなくてもいいはずだ。
八月の焼け付くような日差しの中を駆ける。汗がにじみ、息が切れ、顔を醜くしかめた。ただただ、胸が苦しい。呼吸ができない。
そうしてたどり着いた無人駅で、私は途方に暮れて立ち尽くした。
なんでって? 財布も携帯電話も持たずに走ってきてしまったことに気がついたからだ。お金がなければ何もできない。どこに行くこともできない。誰にも連絡できない。
今の私は、床に落ちた糠漬けよりもずっとずっと惨めだ。じわっと涙が溢れ、ひっと息が引きつる。たまらなくなった私は声を漏らし、その場でうずくまって泣き喚いたのだった。
どれくらい泣いたのだろう。ハッとして我にかえると、逃げるようにその場を立ち去った。誰に見られているかもわからないのになんて迂闊な。顔から火が出そうな恥ずかしさに見舞われながら、駅から遠ざかる。
ふと、耳をつんざくような蝉時雨に気がついた。見上げると、坂の上にこんもりと木々の梢が見える。あぁ、こんなところに神社があったんだ。
ふらりと誘われるように石段を登る。鎮守の杜の木陰はぐっと涼しく、火照った体と頭を冷ましていく。
喉が焼け付くようだったけれど、手水舎の水は飲む気にはなれず口をすすぐだけにした。日陰の石段に腰を下ろして顔を膝にうずめる。
私はとんだ子どもだ。怖くて閉じこもることしかできないくせに、わめくことだけは一丁前だ。
脳裏によぎるのはカナメの悲しそうな顔。そして、負の感情は心の奥底にしまいこんだ見たくないものを誘いだす。
「フウカって最低。そんな人だと思わなかった」
あぁ、あの子の声がまた木霊する。まるで汚いものを見るような冷たい目つき。そして、あの歪んだ唇。
「うっ」
真夏の暑さの中を走り回ったせいか、それとも思い出したくない記憶のせいか、吐き気がこみあげた。なんとかしようと慌てて深呼吸する。
助けて。
涙がふるふると音もなく溢れてくる。時計もない静寂の世界。ときどき風に吹かれた木々がざわめくだけで、心もとなかった。あぁ、そこで座り込んでいた時間はとても長く感じたっけ。
寂しい。
自分の膝に額を当て、どうしようもない孤独を知った。世界中に一人ぼっちのクラゲになって漂っているよう。見えない波間に潜む冷たい闇に怯える、ちっぽけな存在なんだと。
ねぇ、お願いだからずかずかと入り込んでこないで。怖いんだよ。本当は優しくされたい。けれど、裏切られるのが怖い。壊れるのが怖い。失うのが怖い。怖くて動けないの。
言葉にならない声で、私は叫んでいる。
家事は、この家にいる存在意義をかろうじて保てるものだった。でも、今は私より料理も洗濯も掃除も上手で、ご近所さんにも好かれるカナメがいる。
じゃあ、私、いらないじゃない。どこにもいらないじゃない。
また吐き気がこみあげ、顔をしかめたときだった。
「ふぅちゃん!」
ハッと顔を上げると、石畳の向こうに肩で息をするカナメが立っていた。
「カナメ……」
凍りつく私に、彼がもつれた足で駆け寄る。
「ふぅちゃんのばかぁ!」
……驚いて言葉が出ない。だって、カナメは汗だくの顔で私を見つめ、ぼろぼろと涙をこぼしたからだ。20歳を過ぎた男が目の前で泣いている。
「どこに行ったかと思ったでしょ。心配したよ」
ぐずっと鼻をすすり、彼はきゅっと唇を引き締めた。
「さぁ、帰ろう。太田さんも一緒に探してくれたんだよ」
ぽかんとしている私の胸に『帰ろう』という言葉が染み入った。
「カナメ」
わなわなと震える唇の隙間から、小さく名を呼ぶ。
「私……私ね……怖いの」
ぽろっとこぼれる涙。はらはらと温い涙が頬を落ちる。カナメは黙ったまま、じっと私の顔をのぞきこんでいた。
「私ね、いい人、やめたって決めたの」
「うん」
カナメが静かに頷いて、話を促す。
「いい人でいても、いつか失うなら、最初からない方がいいって。だって、お父さんも出て行ったし、それに……」
あんなに仲良かったあの子も私を嫌いになった。
言葉にすることができない。嗚咽が漏れて苦しい。
すると、カナメの手が伸びて、私の頭をぽんと撫でた。
「いい人じゃなくていいよ。家では我がままで嫌なふぅちゃんでいいよ。俺はふぅちゃんに無条件に甘くしてやるから」
そして、私の手を引っ張って、立つよう促した。石段から立ち上がると、カナメの胸元が目の前にぐっと迫る。彼の背が思ったより高いことに、今になって気づく。
「ふぅちゃん、どうしてそんなにあさはん嫌いなの?」
責めるような声ではなかった。ただ、淡々とした声で彼はきいた。
「だってね、朝食なんてないのがうちの当たり前だったの」
ゆっくりと呟く。
「だけど、カナメがあさはんを出すたびに、もううちってないんだって思って。お父さんがいなくなって、うちの形が変わっちゃうんだって思って。このまま消えちゃうんだって」
本当はお父さんについて行きたかった。けれど、お父さんには新しい女の人がいて、強がっているけれど枕に顔をうずめて泣くお母さんを見てほっとけなくて。でも、そんなボロボロのうちでも、消えてほしくないんだ。
すると、カナメは首を静かに振った。
「消えないよ。家族は離れててもやっぱり家族だから。いつかふぅちゃんがお父さんにあさはんを作ってあげられるときもあるかもしれないよ」
彼は手に力をこめ、歩調を合わせてゆっくり歩いてくれた。
「叔母さんから聞いてるよ。ふぅちゃん、いつも家事を一生懸命してくれてるって。確かに俺は家事手伝いのバイト代をもらってるけれど、それでふぅちゃんが居場所を失ったように感じることはないんだよ」
なんでお見通しなんだろう。かぁっと顔を赤くした私に、ふふっとカナメが微笑む。
「たくさん時間ができるんだから、お友達と遊びに行ったり、好きなことして欲しいんだ」
思わず俯いてぼそっと呟く。
「……友達なんて、いないもん」
少しの間沈黙があったが、やがて彼は「そうか」と頷く。
「昔の俺とおんなじだなぁ」
ハッとして彼を見上げると、カナメは眼鏡の奥でいつもの優しい笑みを浮かべていた。
「じゃあ、俺といろんなところに行こう。俺さ、ふぅちゃんに群馬の良さを知ってほしいんだ」
「……ねぇ、カナメ」
「うん?」
「あのね、私、ここにいていいのかな?」
「うん」
「カナメは私がいなくなったら悲しい?」
「うん」
ぐっと握った手に力がこめられるのが伝わってきた。そのとき流れた涙はさっきまでのものとはどこか違っていた。まるで傷あとをそっと撫でる指先のように、頬を伝う。
人は安心しても泣けるんだ。そう知ったのだった。
家の辺りまで来ると、太田さんが私の姿を見て駆け寄ってきた。
「ふぅちゃん! どこに行ってたん?!」
いつの間にふぅちゃんって呼ばれるようになったの? と呆気にとられている私を見て、太田さんはケラケラと笑い飛ばす。
「あら、やだ。カナメ君のがうつっちゃった。でもふぅちゃん、心配したのよぉ」
「……ごめんなさい」
素直に頭を下げると、太田さんが優しく肩を撫でてくれた。
「カナメ君ったら取り乱してねぇ。子どもじゃないんだから大丈夫よって言ったんだけど、子どもじゃないから心配なんですっておろおろして」
「うわぁ、太田さん余計なこと言わないで」
顔を真っ赤にするカナメに、太田さんはにやにやしている。
「大切にされてるのねぇ」
「当たり前でしょう、従姉妹なんですから」
むうっと口を尖らせるカナメに、思わず笑ってしまった。すると、どうしたことか太田さんもカナメも目をひん剥いて私を凝視している。
「どうしたの?」
きょとんとした私に、太田さんがふふっと笑った。
「いえね、初めて笑ったなぁと思って」
思わず顔を赤くすると、カナメがわしわしと頭を乱暴に撫でた。
「ふぅちゃん、今日はよく喋ったしねぇ」
「もう、二人して子ども扱いして」
小声で口を尖らせると、太田さんが噴き出した。
「んまぁ、ふくれっ面がカナメ君そっくり。さすが従姉妹ね」
カナメと顔を見合わせ、そしてつられて笑う。笑いながら、夢のようだと思った。最後に声を上げて笑ったのがいつか思い出せないくらい、本当に久しぶりの笑顔だったんだ。
家に戻ると、玄関でまるで待ち構えていたようにミドリさんが寝そべっていた。
「……ただいま」
恐る恐る、まるでカナメがそうするように話しかけてみる。彼女は『やっと帰ってきたの』と言いたげに目を開け、尻尾をぱたりと揺らして応えてくれた。
食卓の上には私が出て行ったまま『あさはん』が乗っている。さすがに床に落ちた糠漬けは片付けられているけれど。すっかり冷えただし巻き卵。ほうれん草のおひたしに乗った鰹節はへなへなと萎れていた。
「ふぅちゃん、お腹すいたでしょ? 今、作り直すからちょっと待って」
時計の針は午後にさしかかっている。私はけっこうな時間を神社で過ごしていたらしい。視線を食卓に戻し、椅子を引く。いつもカナメがそうするように手を合わせ「いただきます」と囁いて箸をとる。冷たいだし巻き卵の味がじゅわっと口の中に染みた。そんな私を呆気にとられて見ていたカナメは、慌てて叫ぶ。
「待って、お味噌汁温めなおすから! ご飯もよそうからね」
その声が嬉しそうで、なんだか照れくさくなった。ネギ入りの納豆ご飯があんなに美味しく感じたことって今までなかったよ。
あれから何日過ぎただろう。今日も聞こえるカナメの声。
「いらないってば」
吐き捨てるような私の声。もう何度目かわからない同じやりとり。そのたびに彼は切なげに眉を下げ、しゃもじを置くんだ。
どうして彼はいらないと言っているのに、こうも頑なに『あさはん』を用意するのか。私は夏休みの課題をする手を休め、机に頬杖をついた。
「ミドリさん、外に出ちゃだめだよ」
ふと、窓の外から声がする。そろそろと覗いてみると、カナメがホースで庭に水撒きをしているようだった。
カナメはミドリさんに人間と同じように話しかける。いかにもお人よしな声で。かと思えば、晴れた日に庭先でボタニカルアートに興じているときは話しかけるのもためらわれるような鋭い顔をすることもあった。
親戚の間ではちょっと変わった子という評判だった。午前中はパソコンでなにやら打ち込みをしたりボタニカルアートを描いたりしているが、午後になると縁側でミドリさんと一緒に座って庭を見ているのだ。
脇にお茶と糠漬けと好物の煎餅を乗せたお盆を置き、ただ何をするでもなく、ひたすら池の辺りを見つめている。
20歳を過ぎたばかりの男が、朝昼晩に糠床を混ぜることを決して忘れないというのも珍しいように感じた。そう、あの夏時雨のときに持っていた重そうな手提げ袋。あの中には糠床が入っていたのだ。最低限の着替えと髭剃り、そしてボタニカルアートの画材くらいしか車にはなく、大事な猫と糠床を真っ先に玄関に運んだらしい。
あいにく私は糠漬けが苦手だった。どうも糠の匂いというのが受け付けない。それもあって、必ず食卓の脇に糠漬けが登場するカナメのあさはんは尚更気が向かないのだった。
けれど、私は知っている。一度だけトイレに起きたときに見てしまったんだ。私が寝静まった頃に糠床をかき混ぜ、昆布とカツオでダシをとっているカナメを。きっと、彼の日課なのだろう。
どうして彼はそこまでして『あさはん』にこだわるのか。何故、いらないというものを押し付けてくるのか。
強引な善意など迷惑だ。この家にはこの家のやり方がある。そう、たとえ父が飲み屋の女とできて家を出ても。母が仕事ばかりで家にいないのが当たり前だとしても。世間的には朝食があった方が好ましいとされているとしても。この家には私たちが築いてきたやり方があるんだよ。それを土足で踏みつけられているようで、無性に苛立った。
そんな不満が爆発したのは、カナメが来て半月ほど経った頃だった。
「あさはんだよ」
いつもの掛け声。湯気の上がる食卓を見下ろし、私はぐっと拳を握り締めた。
「……もう嫌」
頭にかぁっと血が上っていくのがまざまざと伝わる。きょとんとしたカナメに向かって吐く私の声は震えていた。
「なんでいらないってのに用意するの? どうして善意の押し売りするの? お母さんからバイト代をもらってるから? 迷惑なのよ。なんでそれがわからないのよ? 自分がいつだって正しいと思ってるの?」
一度あふれ出した言葉はまるで破れた防波堤から鉄砲水が飛び出すように止められなかった。怒りの限度を越えるとわなわなと体も声も震えるものらしい。それに、怒鳴るわけでもなく、ただただ抑揚の効いた声しか出ない。わめいたら血管が破裂しそうだからかもしれない。
すると、カナメはいつものように眉を下げるだけでなく小さくため息を漏らした。
「バイト代なんて関係ないよ。悲しいこと言うなよ」
「じゃあ、なんでよ?」
「あさはんはね、一日を大切に過ごすためのおまじないだからだよ」
「はぁ?」
なんとも平和ボケした答えに、あんぐり口が開いた。それでもカナメはひるまない。
「一日を大切に過ごせば、誰かも大切にできるから。自分もね」
「偉そうなこと言わないでよ。何も知らないくせに!」
その刹那、頭が真っ白になった。なんと私は目についた糠漬けを鷲づかみにし、カナメに向かって投げつけたのだ。
飛び散る糠漬けが床に落ちるペタペタンという情けない音を、肩で息をしながら聞いた。その瞬間、さっきまで頭に上っていた血がさぁっと引いていく。
私……今、何をしたの?
そして恐る恐るカナメの顔を見つめたんだ。カナメは何も言わず、私の目の前に歩み寄った。すっと彼の手が動く。
怒られる……!
咄嗟にきつく目を閉じた私の頬に、むにっという感触が走った。恐る恐る目を開けると、カナメが私の頬を両手で挟んでじっと見つめているのだ。
「……食べ物を粗末にしたらいけないよ」
そのときのカナメの声に帯びた悲しそうな響きが、ぐっと私の胸を狭くした。そう、彼の目は怒っていなかった。ただひたすら悲しげで、それがかえって私を責めている気がして恥ずかしくなった。
「あ! ふぅちゃん!」
気がつけば私は彼の手を振りほどいて外に飛び出していたのである。うまく履けないままの靴で転びそうになりながら、走る。無性に叫びたいのをぐっと堪え、どこでもいいから消えてしまいたかった。
「あらぁ、高崎さんとこの」
道の向こうから買い物袋を手に提げて歩いてくるのは、太田さんだ。
「おばさん……!」
私が彼女を呼んだのが初めてだからか、それとも私の顔がひどいのか、太田さんは目をまん丸にしている。
「どうしたの。何かあったの?」
「おばさん、東京行きの電車って何時から?」
「え?」
「もう行ける?」
「え、えぇ。この時間ならもう動いているはずだけど」
私はそれを聞いて咄嗟に走り出した。
「あ、ちょっと!」
後ろで太田さんが呼び止める声を無視し、坂道を駆けていく。もう嫌だ。どこでもいい。ここじゃないところへ行きたい。どうせどこにも居場所がないのなら、ここじゃなくてもいいはずだ。
八月の焼け付くような日差しの中を駆ける。汗がにじみ、息が切れ、顔を醜くしかめた。ただただ、胸が苦しい。呼吸ができない。
そうしてたどり着いた無人駅で、私は途方に暮れて立ち尽くした。
なんでって? 財布も携帯電話も持たずに走ってきてしまったことに気がついたからだ。お金がなければ何もできない。どこに行くこともできない。誰にも連絡できない。
今の私は、床に落ちた糠漬けよりもずっとずっと惨めだ。じわっと涙が溢れ、ひっと息が引きつる。たまらなくなった私は声を漏らし、その場でうずくまって泣き喚いたのだった。
どれくらい泣いたのだろう。ハッとして我にかえると、逃げるようにその場を立ち去った。誰に見られているかもわからないのになんて迂闊な。顔から火が出そうな恥ずかしさに見舞われながら、駅から遠ざかる。
ふと、耳をつんざくような蝉時雨に気がついた。見上げると、坂の上にこんもりと木々の梢が見える。あぁ、こんなところに神社があったんだ。
ふらりと誘われるように石段を登る。鎮守の杜の木陰はぐっと涼しく、火照った体と頭を冷ましていく。
喉が焼け付くようだったけれど、手水舎の水は飲む気にはなれず口をすすぐだけにした。日陰の石段に腰を下ろして顔を膝にうずめる。
私はとんだ子どもだ。怖くて閉じこもることしかできないくせに、わめくことだけは一丁前だ。
脳裏によぎるのはカナメの悲しそうな顔。そして、負の感情は心の奥底にしまいこんだ見たくないものを誘いだす。
「フウカって最低。そんな人だと思わなかった」
あぁ、あの子の声がまた木霊する。まるで汚いものを見るような冷たい目つき。そして、あの歪んだ唇。
「うっ」
真夏の暑さの中を走り回ったせいか、それとも思い出したくない記憶のせいか、吐き気がこみあげた。なんとかしようと慌てて深呼吸する。
助けて。
涙がふるふると音もなく溢れてくる。時計もない静寂の世界。ときどき風に吹かれた木々がざわめくだけで、心もとなかった。あぁ、そこで座り込んでいた時間はとても長く感じたっけ。
寂しい。
自分の膝に額を当て、どうしようもない孤独を知った。世界中に一人ぼっちのクラゲになって漂っているよう。見えない波間に潜む冷たい闇に怯える、ちっぽけな存在なんだと。
ねぇ、お願いだからずかずかと入り込んでこないで。怖いんだよ。本当は優しくされたい。けれど、裏切られるのが怖い。壊れるのが怖い。失うのが怖い。怖くて動けないの。
言葉にならない声で、私は叫んでいる。
家事は、この家にいる存在意義をかろうじて保てるものだった。でも、今は私より料理も洗濯も掃除も上手で、ご近所さんにも好かれるカナメがいる。
じゃあ、私、いらないじゃない。どこにもいらないじゃない。
また吐き気がこみあげ、顔をしかめたときだった。
「ふぅちゃん!」
ハッと顔を上げると、石畳の向こうに肩で息をするカナメが立っていた。
「カナメ……」
凍りつく私に、彼がもつれた足で駆け寄る。
「ふぅちゃんのばかぁ!」
……驚いて言葉が出ない。だって、カナメは汗だくの顔で私を見つめ、ぼろぼろと涙をこぼしたからだ。20歳を過ぎた男が目の前で泣いている。
「どこに行ったかと思ったでしょ。心配したよ」
ぐずっと鼻をすすり、彼はきゅっと唇を引き締めた。
「さぁ、帰ろう。太田さんも一緒に探してくれたんだよ」
ぽかんとしている私の胸に『帰ろう』という言葉が染み入った。
「カナメ」
わなわなと震える唇の隙間から、小さく名を呼ぶ。
「私……私ね……怖いの」
ぽろっとこぼれる涙。はらはらと温い涙が頬を落ちる。カナメは黙ったまま、じっと私の顔をのぞきこんでいた。
「私ね、いい人、やめたって決めたの」
「うん」
カナメが静かに頷いて、話を促す。
「いい人でいても、いつか失うなら、最初からない方がいいって。だって、お父さんも出て行ったし、それに……」
あんなに仲良かったあの子も私を嫌いになった。
言葉にすることができない。嗚咽が漏れて苦しい。
すると、カナメの手が伸びて、私の頭をぽんと撫でた。
「いい人じゃなくていいよ。家では我がままで嫌なふぅちゃんでいいよ。俺はふぅちゃんに無条件に甘くしてやるから」
そして、私の手を引っ張って、立つよう促した。石段から立ち上がると、カナメの胸元が目の前にぐっと迫る。彼の背が思ったより高いことに、今になって気づく。
「ふぅちゃん、どうしてそんなにあさはん嫌いなの?」
責めるような声ではなかった。ただ、淡々とした声で彼はきいた。
「だってね、朝食なんてないのがうちの当たり前だったの」
ゆっくりと呟く。
「だけど、カナメがあさはんを出すたびに、もううちってないんだって思って。お父さんがいなくなって、うちの形が変わっちゃうんだって思って。このまま消えちゃうんだって」
本当はお父さんについて行きたかった。けれど、お父さんには新しい女の人がいて、強がっているけれど枕に顔をうずめて泣くお母さんを見てほっとけなくて。でも、そんなボロボロのうちでも、消えてほしくないんだ。
すると、カナメは首を静かに振った。
「消えないよ。家族は離れててもやっぱり家族だから。いつかふぅちゃんがお父さんにあさはんを作ってあげられるときもあるかもしれないよ」
彼は手に力をこめ、歩調を合わせてゆっくり歩いてくれた。
「叔母さんから聞いてるよ。ふぅちゃん、いつも家事を一生懸命してくれてるって。確かに俺は家事手伝いのバイト代をもらってるけれど、それでふぅちゃんが居場所を失ったように感じることはないんだよ」
なんでお見通しなんだろう。かぁっと顔を赤くした私に、ふふっとカナメが微笑む。
「たくさん時間ができるんだから、お友達と遊びに行ったり、好きなことして欲しいんだ」
思わず俯いてぼそっと呟く。
「……友達なんて、いないもん」
少しの間沈黙があったが、やがて彼は「そうか」と頷く。
「昔の俺とおんなじだなぁ」
ハッとして彼を見上げると、カナメは眼鏡の奥でいつもの優しい笑みを浮かべていた。
「じゃあ、俺といろんなところに行こう。俺さ、ふぅちゃんに群馬の良さを知ってほしいんだ」
「……ねぇ、カナメ」
「うん?」
「あのね、私、ここにいていいのかな?」
「うん」
「カナメは私がいなくなったら悲しい?」
「うん」
ぐっと握った手に力がこめられるのが伝わってきた。そのとき流れた涙はさっきまでのものとはどこか違っていた。まるで傷あとをそっと撫でる指先のように、頬を伝う。
人は安心しても泣けるんだ。そう知ったのだった。
家の辺りまで来ると、太田さんが私の姿を見て駆け寄ってきた。
「ふぅちゃん! どこに行ってたん?!」
いつの間にふぅちゃんって呼ばれるようになったの? と呆気にとられている私を見て、太田さんはケラケラと笑い飛ばす。
「あら、やだ。カナメ君のがうつっちゃった。でもふぅちゃん、心配したのよぉ」
「……ごめんなさい」
素直に頭を下げると、太田さんが優しく肩を撫でてくれた。
「カナメ君ったら取り乱してねぇ。子どもじゃないんだから大丈夫よって言ったんだけど、子どもじゃないから心配なんですっておろおろして」
「うわぁ、太田さん余計なこと言わないで」
顔を真っ赤にするカナメに、太田さんはにやにやしている。
「大切にされてるのねぇ」
「当たり前でしょう、従姉妹なんですから」
むうっと口を尖らせるカナメに、思わず笑ってしまった。すると、どうしたことか太田さんもカナメも目をひん剥いて私を凝視している。
「どうしたの?」
きょとんとした私に、太田さんがふふっと笑った。
「いえね、初めて笑ったなぁと思って」
思わず顔を赤くすると、カナメがわしわしと頭を乱暴に撫でた。
「ふぅちゃん、今日はよく喋ったしねぇ」
「もう、二人して子ども扱いして」
小声で口を尖らせると、太田さんが噴き出した。
「んまぁ、ふくれっ面がカナメ君そっくり。さすが従姉妹ね」
カナメと顔を見合わせ、そしてつられて笑う。笑いながら、夢のようだと思った。最後に声を上げて笑ったのがいつか思い出せないくらい、本当に久しぶりの笑顔だったんだ。
家に戻ると、玄関でまるで待ち構えていたようにミドリさんが寝そべっていた。
「……ただいま」
恐る恐る、まるでカナメがそうするように話しかけてみる。彼女は『やっと帰ってきたの』と言いたげに目を開け、尻尾をぱたりと揺らして応えてくれた。
食卓の上には私が出て行ったまま『あさはん』が乗っている。さすがに床に落ちた糠漬けは片付けられているけれど。すっかり冷えただし巻き卵。ほうれん草のおひたしに乗った鰹節はへなへなと萎れていた。
「ふぅちゃん、お腹すいたでしょ? 今、作り直すからちょっと待って」
時計の針は午後にさしかかっている。私はけっこうな時間を神社で過ごしていたらしい。視線を食卓に戻し、椅子を引く。いつもカナメがそうするように手を合わせ「いただきます」と囁いて箸をとる。冷たいだし巻き卵の味がじゅわっと口の中に染みた。そんな私を呆気にとられて見ていたカナメは、慌てて叫ぶ。
「待って、お味噌汁温めなおすから! ご飯もよそうからね」
その声が嬉しそうで、なんだか照れくさくなった。ネギ入りの納豆ご飯があんなに美味しく感じたことって今までなかったよ。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

児童絵本館のオオカミ
火隆丸
児童書・童話
閉鎖した児童絵本館に放置されたオオカミの着ぐるみが語る、数々の思い出。ボロボロの着ぐるみの中には、たくさんの人の想いが詰まっています。着ぐるみと人との間に生まれた、切なくも美しい物語です。

フツーさがしの旅
雨ノ川からもも
児童書・童話
フツーじゃない白猫と、頼れるアニキ猫の成長物語
「お前、フツーじゃないんだよ」
兄弟たちにそうからかわれ、家族のもとを飛び出した子猫は、森の中で、先輩ノラ猫「ドライト」と出会う。
ドライトに名前をもらい、一緒に生活するようになったふたり。
狩りの練習に、町へのお出かけ、そして、新しい出会い。
二匹のノラ猫を中心に描かれる、成長物語。

RICE WORK
フィッシュナツミ
経済・企業
近未来の日本、長時間労働と低賃金に苦しむ社会で、国民全員に月額11万円を支給するベーシックインカムが導入され、誰もが「生活のために働かなくても良い」自由を手にしたかに見えました。希望に満ちた時代が到来する中、人々は仕事から解放され、家族との時間や自分の夢に専念できるようになります。しかし、時が経つにつれ、社会には次第に違和感が漂い始めます。
『RICE WORK』は、経済的安定と引き換えに失われた「働くことの意味」や「人間としての尊厳」を問いかける物語。理想と現実の狭間で揺れる人々の姿を通して、私たちに社会の未来を考えさせるディストピア小説です。

月神山の不気味な洋館
ひろみ透夏
児童書・童話
初めての夜は不気味な洋館で?!
満月の夜、級友サトミの家の裏庭上空でおこる怪現象を見せられたケンヂは、正体を確かめようと登った木の上で奇妙な物体と遭遇。足を踏み外し落下してしまう……。
話は昼間にさかのぼる。
両親が泊まりがけの旅行へ出かけた日、ケンヂは友人から『旅行中の両親が深夜に帰ってきて、あの世に連れて行く』という怪談を聞かされる。
その日の放課後、ふだん男子と会話などしない、おとなしい性格の級友サトミから、とつぜん話があると呼び出されたケンヂ。その話とは『今夜、私のうちに泊りにきて』という、とんでもない要求だった。

イケメン男子とドキドキ同居!? ~ぽっちゃりさんの学園リデビュー計画~
友野紅子
児童書・童話
ぽっちゃりヒロインがイケメン男子と同居しながらダイエットして綺麗になって、学園リデビューと恋、さらには将来の夢までゲットする成長の物語。
全編通し、基本的にドタバタのラブコメディ。時々、シリアス。
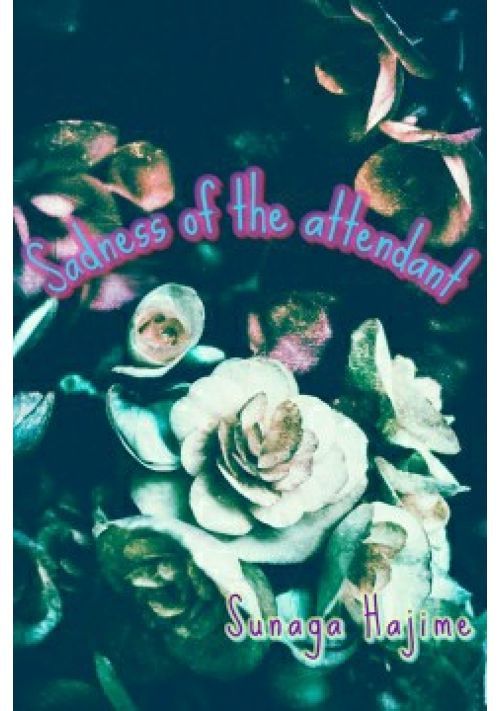
Sadness of the attendant
砂詠 飛来
児童書・童話
王子がまだ生熟れであるように、姫もまだまだ小娘でありました。
醜いカエルの姿に変えられてしまった王子を嘆く従者ハインリヒ。彼の強い憎しみの先に居たのは、王子を救ってくれた姫だった。

空をとぶ者
ハルキ
児童書・童話
鳥人族であるルヒアは村を囲む神のご加護のおかげで外の人間による戦争の被害を受けずに済んでいる。しかし、そのご加護は村の人が誰かひとりでも村の外に出るとそれが消えてしまう。それに村の中からは外の様子を確認できない決まりになっている。それでも鳥人族は1000年もの間、神からの提示された決まりを守り続けていた。しかし、ルヒアと同い年であるタカタは外の世界に興味を示している。そして、ついに、ご加護の決まりが破かれる・・・

佐藤さんの四重奏
makoto(木城まこと)
児童書・童話
佐藤千里は小学5年生の女の子。昔から好きになるものは大抵男子が好きになるもので、女子らしくないといじめられたことを機に、本当の自分をさらけ出せなくなってしまう。そんな中、男子と偽って出会った佐藤陽がとなりのクラスに転校してきて、千里の本当の性別がバレてしまい――?
弦楽器を通じて自分らしさを見つける、小学生たちの物語。
第2回きずな児童書大賞で奨励賞をいただきました。ありがとうございます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















