5 / 19
丸いサイコロ4
しおりを挟む
9.循環する呪縛
──ね、すごいでしょ、今日はここであそぼう!
──えっと、いいのかな? ここ、おじさんたちの家じゃないの?
──ちーがーう、ここは、とくべつなおきゃくさんのおうちなの、だからなとなとは、いいんだよー。
───ナナトだって、何回も言ってるだろ?
──な……? と……と。んー、わかんない。それよりさ、入ろう!
──うん。そうだね。
──……おじさんは?
──え?
──おじさん。おじさんは? とうさまは?
──どうした?
──……わかんない!
──なに?
──あれ。どうして、ここに、連れて来たのかな?
どうして? いいや、ナナトくんは、確かに、大切な……でも、でも、どうして?
さっきまで、違うだれかと一緒にいたような。
──え?
──ねぇ、聞いていい?
『まつりとナナトくんは、いつも、こうして一緒に遊んでるのかな?』
それは、どんな気分なのだろう。考えてみるが、ありきたりな例えしか浮かばない。
それも絶望には違いないが、しかし、きっとさらに想像を絶するのだろう。
さっきまで、食べていたご飯が、いつの間にかまずくなっている感じだろうか。
覚えているはずなのに、それに、確信が持てないような。
プライドが傷付くどころじゃないのかもしれない。自分にさえ、自分の記憶を支配出来ないというのは。
しかしそれも、ぼくがあくまで表面上で考えてみたことで、やっぱり、違う誰かの痛みを、感情を、完全にわかることは、ぼくに出来ないけれど。
「おーい! おーい! お客様だよー!」
「そんな大声ださなくたって、聞こえるだろ?」
まつりにとっては、なにか、面白いことなのだろう。館内で無邪気に手を振って叫んでいるので、ぼくは、誰か先客がいるのかと、首をかしげた。ケイガちゃんに至っては、すでにどこか元気がない。「お腹すいた」とこぼしていて、そういえば、もう夕飯の時間になるのかもと思った。そのときだった。
入り口のドアを開けた先のドア――というか、真ん前のホールのドアが突如開き、そこから出てきた彼女──コウカさんは、そう言って、こちらに向かってゆっくり歩いてくる。
「いらっしゃい。待ってたよ」
さらさらの長い髪に、白のニットワンピース。水色の石がついたロケットペンダントを付けていて、穏やかそうな目をした、大人のお姉さん、という感じだった。そしてその声は、聞いたことのあるものだった。そう、さっき、車を運転していた《彼》の声。兄が出てくるのかと、一瞬思ったほどだ。よくよく聞いて見ると、確かに、女性らしい声なのだが、不思議なものだ。全然違うじゃないか。
歩き方も、女性らしい歩幅で、ゆらゆら歩いている。ぼくはなんだか、少し納得したような気分になった。一番、一歩前に出て、口を開く。目が合って微笑まれる。
「──どうして、さっきは、変装を?」
「あら、バレバレだったの」
コウカさんは、やはり穏やかそうに笑って応えてくれた。
「そりゃ、家族……の、ことですし、誤魔化せませんよ。どこで兄の最近のセンスを知ったのか知りませんが」
「あれは私、男装するならやってみたかった格好なのよー! 似合ってた?」
「ええ、本当に、最初は兄かと思いました……その、自然で」
一瞬だけ、コウカさんが、寂しそうな顔をした気がしたが、ぼくにはその真意が読めない。
彼女はなにかを取り繕うように、ぼくに聞いた。
「疑ったのは、どこから?」
「どこでしょう? 《実験》を知ってたのも驚きですし、信用しかけてましたよ。だから……本当に、さっきです。でも、まあ、近くに住んでた人から聞くか、ぼくの情報を集める物好きがいるなら、知っててもおかしくない話ではありましたし……まさかって思って」
「あーあ、結構自信あったけどなー。演技にも熱を入れたんだけどなー」
「優しい、から」
「え?」
「その……なんか、態度、っていうか。優しかったから」
彼に向けられ慣れていた、ゴミの塊を見るような、そんな眼差しでなかったから。
だから、ぼくはすぐに疑えなかった。その光景に僅かな夢を見た。憧れて、否定する気になれなかったのだ。
気まずくなって、ふと、まつりを見る。なんだかちょっと困った顔をしていた。
次に、コウカさんは、ケイガちゃんに目を向けた。なんだか、少し、不思議そうだった。
「その子……」
ケイガちゃんは、びくついてまつりの後ろに隠れる。まつりは表情を変えないで、説明した。
「……ふたごの姉を探してる、って言って、ある日、メールをくれました」
「――探してたのは、エイカなのね。私ではなくて」
「待てよ、話が、見えない」
ぼくは思わずそう言った。まつりは冷たく笑った。まさしく他人に向けるような、社交的な笑顔だった。
「……うん、覚えて、ないかい?」
「覚えてるって、何を、どれをだ……」
なんだか胸が苦しくなってきて、こめかみがぎゅっと痛んだ。息がしづらい。頭がふらふらする。そんな目で見るなよ。また、ぼくが、わからなくなるのか?
そんなの、何度も経験したってのに。
「そうだねぇ、何年前になるのかな?」
まつりはそう言って少し首を傾げる。後ろにいるケイガちゃんは、ぼんやりと床の敷石を見ている。
コウカさんは、堂々と、立っていた。
「――外にいた男の子がね、向かいにあるお屋敷から外に出ていたメイドさんを見つけて、何かを言われて、ついて行くんだ。メイドさんは、突然その子をさらったそうだ」
『ねぇ、その傷、どうしたの?』
『……転んだ』
『うそ、こんなに、こんなところにまであるじゃない』
頭の中に、突然台詞が次々と浮かんできた。芝生の庭が見える。家が見える。
メイドさんも。
「その子は、そのまましばらく家に帰らなかった。その子の親は激怒した。お屋敷の主人が、健康な男の子に恵まれなかったからと、跡を継ぐ者に悩んでいたのを、知っていたから、よりいっそう怪しんだ」
『逃げなさい。こんなところにいちゃ、だめよ』
『でも、だけど、ぼくは……一人じゃ、なにも、ごはんだって、待ってなきゃ』
『ここに隠れていたのは、あなたが、苦しんでいるからじゃないの?』
そのときは、そう表現されたことに、腹が立ったし、悲しかった。別に苦しんでいるわけではなかったと、ぼくは思う。苦しむ、という感情は、弱いから、生まれるのだと思い込んでいたから、かもしれないが。そんなに弱くない、とぼくは拗ねた。
そもそも、疲れた、ですべて片付くから考えない。だから、心配されるというよりも、ただ単に、面白がられて、挑発されているように感じたのだ。
『あなた、あんなひどい家、もう、帰らなくていいわ』
『あんな人に会わなくていい』
彼女は言った。それは、善意だったのだろう。だけど、どんな理由であれ、自分の住まわせてもらった場所を、悪く言われたいと、ぼくには、思えない。そんな風に、他を容易く否定してまで、自分をかばわれてしまったことが、怖くなった。誰に向く敵意であっても、それは、臆病で幼い自分に向かってくるような、気がした。──だからぼくは、彼女の優しさが、怖かったのかもしれない。
彼らに対して恨みを持ったことだけは、ない。やってみたこともあるが、一日で惨めな気分に変わるだけだった。
誰かを拒絶すること、誰かを悪く思うこともまた、当時のぼくにとって、最も辛いことで、すべてを、好きで居たかった。
閉じきった世界を『それは間違いだ』と否定し、正しさを強要されて壊されるのは、ただただ、苦痛で、果てしない恐怖でしかない。
生まれたときから作り続けてきた認識、生まれたときからの膨大な《すべて》は、愛すべきものでありたかった。どんなに過去でも、構わなかった。
自分の手で否定し、書き換え、抹消しなければならなくなるから。今日までが、ぼくの『昨日』。昨日のことは、今日まで続く。ぼくが《被害者》になれば、ぼく自身が、ぼくにとどめを刺してしまう。
『そんな世界はもう終わった』と。
だけど、彼女は一応、自分を、少し何かがずれていながらも、心配し、説得してくれたのだ。驚いて戸惑って、どうしていいかもわからなかったのもある。
不愉快になってきたぼくは、おそらくとても悪い目付きで、彼女を見た。そして、聞いた。
『……お姉さんは、だれですか?』
『私は、ほら、あそこのお屋敷の―――いつも、あなたが窓から見えたわ』
『……えっと』
『違う違う、小さい子は好きだけど、そういうことじゃないの! 確かに可愛いけど、そういうことじゃ』
『……わかってます』
――そもそも、好きだとか、嫌いだとか、それは具体的にどこがどう違うのだろうか? それは、どんな意味を持つんだろう。
「思い――出した。どうしてだ。忘れることなんて、一切無いと思っていたのに」
「……いろいろ、あったからね」
「お前は、そのとき、どうしてたんだ? どうして、そんなことを、知ってる?」
「お茶を、飲んでいたかな。外が、急に騒がしくなって、みんなが上に行ったから、代わりに、地下の書庫に行こうとしていた」
ぼくらが話している間、しばらく黙っていたヒビキちゃんは、もう一度だるそうに、お腹すいたと訴える。
「──まあ、難しい話は、何か食べながらにしましょう?」
コウカさんがそう言ったので、話は一旦切られた。
食堂へと案内してくれる。内装は、昔来たときとあまり変わらないと思っていたが、そういえば、ちょっと変わった部分もあるようだった。
入ってすぐ右の、階段の手すりに、薄くだが、何かで引っ掻いた新しい傷があるし、床にも、昔はなかったワインか何かの染みが僅かにある。
廊下は薄暗くて、だけどほんのり灯りがあった。
何かメヌエットっぽい楽譜のようなものが描かれた壁を照らしている。
──一体誰の趣味なのだろう。
移動中は誰も話さなかった。
食べるときに真面目に話をするのは苦手だ、と言いづらくなってしまってちょっと焦る。
テレビを見ながら食べたり、会話しながら食べる人は器用だなあ、と思うけれど、ささっと食べてからする方が、楽じゃないのかな? と個人的には疑問だ。
食事を楽しむ 、という概念はどうもぼくにない。
下手に、食べながら話したり遊んだりすると、頭の中がそれでいっぱいになって、目の前の食べ物の味を感じるどころじゃなく、吐き気がする。そういう部分が、変に繊細なのだ。
10.そろわない役者
扉を開けた先の食堂には、昔と変わらない、長い木の机が置かれていた。
綺麗に布がかかっている。真ん中にろうそくがあるが、ここに来る人は(ぼくが関係者パーティーなどで、ときどき招かれた際に見た限りでは)夜でもなんでも、だいたいは、あかりを付けていた気がする。主に、シャンデリアじゃない方だけを。節約は大事だ。
机の上には美味しそうなビーフシチューが、人数分どーんと並べられていて、かと思えば皮を剥いたニンジンとか、皮を向いたきゅうりとかじゃがいも、とうもろこしも並べられていた。バスケットに入ったパンもあった。野菜はおそらくは茹でてある。
……思ったよりも素材感、だった。塩茹でなのかどうかはちょっとだけ気になる。どちらでも好きだけど。焼き芋もあった。
ナイフとフォークがあるが、なぜかスプーンがない。ビーフシチューはこのまま飲めば良いのだろうか?
聞くべきかに迷ってしまう。
「相変わらず、まざーのご飯は、全部ごろごろしてる! ひゃはは!」
まつりが笑った。ぼくには見せない感じの笑顔だ。
「あなたに誉めていただいて、光栄です。野菜が食べたいって、あなたがいったじゃない」
「感想だよー。たしかに野菜って言ったけどさ、こんなにふんだんに使ってくれるとは、予想してなかったんだ」
「美味しそう、野菜だ、シチューもいいなあ……」
ぼくが感動していると、他三人が一瞬黙った。
なんだ?
変なことは言っていない。全く。
「……どうかした?」
「気に入ってもらえたみたいだね」
まつりはなんだか苦笑いだった。ちょっと不本意だぞ。
「ええ。もちろん」
「私、ご飯が食べたいぞ……」
「ご飯も用意してます、とって来ますね」
コウカさんは、先にどうぞ、と言い残して、ぱたぱたとどこかの部屋にかけていった。
とりあえず椅子に、ぼく、ケイガちゃん、まつり、の順に座った。入り口近くの角から見て、隅から左へ詰めている。
「コウカさんって、まざーって呼んでた人だったんだな」
「うん。電話の声と、実際の声が、ちょっと違うって思った?」
「いや、確かにそれもあるけど、綺麗なお姉さんだったから驚いてる」
「もっとおばさんだと思ったんだ……」
「うーん。どうも、名前とかイメージが先に来てしまうみたいで、実際の声と、ぼくが聞く声が、ずれるみたい。今回も、あだなの影響かなあ」
「猫だよ、ってきいてから、実際はカラスの声聴かされたら」
「たぶん気が付かない。わあ猫だ、って思う」
「にゃー。そういえば、中学生時代、校内放送で、名乗らないで職員室に呼び出す先生がいると頻繁に迷ってたらしいね、どなたが呼んだんですか? って言って」
「え、そんなことも知られてるのか。あれはーちょっと、焦ったかな。ぼくをからかうイタズラなのかと思って、ときめいたりもして」
「……ときめくなよ」
ぼくはそれにはこたえずに、きゅうりにかじりついた。ナイフとフォークはこの場面に、使うんだろうか?
唐突に、足を踏まれた。どうやら、間にいたケイガちゃんだった。退屈そうに、こちらをにらんでいる。
「どうかしたの?」
「……どうかした! どうかしてるのはお前だ!」
突然、機嫌が悪そうに怒られてしまった。わからない。
「んー、それは、よく言われるんだけど、えっと、そうではなくて……」
「なんだか腹が立ったから踏んだんだ」
「ああ……よくあるよね。でも、靴に何か仕込んでたら、きみが危ないだろ? ぼくは、きみが怪我をする方が不安だ」
「え……あ、ありがとう、じゃなくて、仕込んでたのか!」
ケイガちゃんが、びっくりした顔をする。これは確かに、いじりたくなる。
「昔、脱走癖があって、靴に刃物とか、こう……仕込んでたんだよ。縄を切れるように」
「縄?」
「ぼくの腹筋を割ろうとの企てが」
「──聞かなくていいよ」
ぼくが調子に乗ったあたりでまつりがケイガちゃんにまともなアドバイスをした。
「なんだ、では、靴に何か仕込んでたのは嘘か!」
「──いや、靴に仕込んでたのは、嘘だけど、ズボンとかには仕込んでたよ。花火とか」
「一切れのパンとか?」
「そうそう。バターナイフとかね」
……なんだろう、この子。ボケてるのかそうじゃないのかが掴みにくいぞ。
「あ、そうだ、ちょっと、探し物があるから、行ってくる」
思い付きで、以前から、《いつかここに来たときに》しようと考えていて、今日、食べてからしようと思っていたことを、今からに変更した。そこに至る過程は特に無い。
「でも食べかけのきゅうりくらいは食べたらー?」
「あ、うん」
きゅうりをかじりながら、これ、調味料はついてないんだなあ、と、さっきから思っていたが確信した。
きゅうりを食べ終えて、廊下をまっすぐ歩く。シチューも食べれば良かったなあ、とちょっと思った。
なので『食べたよ』と、頭に言い聞かせておくことにした。
(これで、単純なぼくは、数時間後に食べた気になるだろうと信じている)
このまま行くと床がだんだん斜めになってきそうな感じだけど、ここに、そんなトリックらしいものはない。
まっすぐまっすぐ行くと、左と右にも曲がれるようになってきて、ぼくは左に曲がって、階段をのぼった。目指すは客間、のちょっと先にある部屋だ。宿泊出来る場所。その一室。
地図は覚えているけれど、やはり、数年来ていないと、ちょっと色が記憶と違う気がした。何もかもが、色褪せている気がする。そういえばコウカさんは、ここに客として呼ばれているのだろうか? どうしてか、と考えても無意味なのだろうけど、なんだか、これじゃ、なにかが繋がらない。もやもやする。
結構前からここに居着いているような印象だったし……料理も、彼女が用意したらしいし。
部屋まで行く間、誰にも出会わなかった。
誰かとすれ違えたらいいな、とか思っていたわけではないが、なんとなく、曲がり角や、視界を遮る観葉植物を、たびたび見かけると、誰かいる気がしてしまうのだ。
いなかったけれど。二番目に大きい宿泊部屋(洋)につくと、小さく、ドアをノックしてみた。
返事はない。誰もいない。ちょっと押してみる。
――なんと、鍵は開いていた。
なんと、と思いながらも、なんとなくの目安というか、泊ってるならここだろうなあ、というのはあったわけだが。うまく説明できない。
とにかく、やっぱり、という感じでもある。
――コウカさんも、この部屋に泊っているらしい。
ぼくはとくに覚悟もなく、さっさと部屋に踏み込んだ。
目の前の机に、飲みかけな紅茶が置かれている。いいにおいがした。もちろん飲んだりはしない。踏み込んでから、ようやく、これって、どうなんだろう、と思った。見つかったら明らかに不審者だ。変態扱いだ。
「そうは言っても、まさか以前のぼくと同じ部屋に泊っているとはね……というか、やっぱりあの人も、大切なお客様ってことなのか」
実は昔、ここに泊ったことがある。
そのときは、まつりがここに泊めてくれたが、本人には、もうその記憶はないだろう。
確か、勝手に入ったのだ。
二人で遊べる場所を探していて、まつりが提案して、なぜか、ここの鍵を持ってきていて――それで、二人で別々に過ごす部屋を選んだ。まつりは一番豪華な部屋で、ぼくは二番目だった。
なぜ部屋を選んだかといえば、二人とも泊まったからで、なぜ泊まるかというと、そこに来た時点で結構日が暮れてしまっていて、こっそり来たことが家にバレたくない、とまつりが嫌がるし、ぼくも家は苦手で、あまり帰りたくなかったから。
一言でいえば、暗くて帰り道に迷いそうだったので。
とりあえず、二人で買い物に行って、ここで夕食を食べた。残念ながら一日でいろんな方にばれたが、まつりを心配する方が先になり、あやふやというか、おとがめなしだった。
「コウカさんは、ぼくが入ったって気付くのかな……それか、まさか最初から気付いていたりして」
……あれ?
今さらだけど。
思い出すのに時間を使ってて、ピンと来てなかったけど。
──ケイガちゃんが探していたのは、コウカさんではなくて、エイカさんだって話と、ぼくの過去と。
「──どう、関係が?」
とりあえずは、ベッドの左側の机の引き出しを迷いなく開ける。(嘘。少し、迷った)すると、あった。
片方のウサギさん。あのときに、忘れたヘアゴムの片方だ。ここに置いていったものだ。そう、ぼくが。
欲しかったんじゃないし、ぼくの持ち物ではない。見つけたときに怖かったから、ずっと、見えないように隠していたのだ。あまり格好いい言い訳じゃないが。(言い訳自体、格好いいことでもないか)
もともとは、片方が、部屋のベッドの中に、落ちていて、もう片方が、廊下に落ちていた。そしてぼくは、当時、廊下にあったのを咄嗟にポケットに入れ、そしたらベッドにあったのを、見つけて、引き出しに隠したのだ。見たくなかった。それだけが理由で。それを、誰かが持っているのを見るのも、届く範囲に置いてあるのも昔は特に耐えられなかった。ポケットに入れたまま、片方を持ち帰ってしまったことに気付いたときから、ずっと罪悪感が残っていた。ああ、これでようやく、二つそろうな。
──片方を持って来ていれば。
なんで忘れてきたんだよ! と思ったが、クラッカーを留めるのに使われたから、そのまま棚に戻しちゃったのだ。まつりが、あのゴムを使ったことには、意味があるのかなあ。ちょっと気になる。
□
探していたものの確認もできたことだし、ゆっくり部屋を出て、戻ることにした。
帰り道の足取りは、軽くも重くもないが、少し、ぐるっと一周したい気分でもあったが結局、せっかくなのに、と思いつつ、まっすぐ戻る。冷めちゃって申し訳ないなあ、と思いながらも、ぼくは食堂のドアを開けた。いや、開けようとして、しかし様子が、おかしいのに気付く。
「──あれ?」
扉の隙間から見るに、ケイガちゃんが、どこにあったのか、包丁を握っていて、振り回している。
どうして?
(何かあったのかな……)
白っぽかった後ろの壁には、今、赤い色が、数滴飛び散っている。赤? 絵の具だろうか。
──これは、何かのイベントフラグ? 机でよく見えない隙間から、赤い手が、ひらひらと、こちらに揺れた。
こういうホラーがあった気がする。顔が、ちらりと、こちらを見て、また倒れていた。何やってるんだ、あいつ。──佳ノ宮まつり。派手な遊びだなあ。
あははは。
「……貴様を、殺したいと、常々思っていた!」
派手な。演出。
まるで、本当に、そうであるみたい。
こんなときのリアクションが取れない。反応が、極端に鈍い。
ただ、まっすぐに、それを見つめた。無関心なのではなく、いろんなことを考えて、必死にいろんな可能性を考えて、表に感情を出すことさえ、忘れているのだ。
──こういう状況のときは、どう思うのが、正しいのだろう?
昔から、いくら苦しんでも、泣いても、状況が変わるようなことは、何もなかった。だから、いつも、悲しんだり、苦しんだりは、ぼくに無意味だった。
ずっとそうだったから、こんな状況を用意されても、ぼくはどうしていいかわからない。『心から』が要求される場面で、心から、感情を出せない。
頭に、何に対してかもわからない疑問符を浮かべるのが、精一杯。
気持ちを切り替えることにした。きっと今も、ぼくが悲しんだり苦しんだり取り乱すのは、無意味なのだ。
逃避せずに、ちゃんと状況を理解しないと。
叫ぶことも、笑ったり、泣くこともなく。ただ、不思議そうに、ぼくは、彼女らを、見る。
何をしてるんだろう?思考回路が繋がらない。きっと、モノローグというより、箇条書き。
ぼくは扉を開ける。とても自然に。口から出たのは、ただの挨拶。
「ごめん、遅くなっちゃった」
ケイガちゃんは、ちらっとこちらを見たが、すぐに、その足元に視線を戻す。
少し気まずそうだった。ぼくを気にしたのか、手が止まっている。
大丈夫そうだと判断して、彼女のそばの、倒れている人物に、話しかけた。
「おいおい……お前、なにやらせてんだよ? 小さな女の子に」
まつりは、にや、と笑った。腹の辺りが、やけに赤色でびしょびしょだけど、意外に、まだ元気そうだ。なんとなく、納得したような、緊張がほどけた気分。
「ハッ……りふじん、だなあ」
「お前に理不尽って言われたくないね。どう、痛い? 心配してやろうか?」
「いらないよ。痛くはない……それより、気にすることが、たくさんあるだろ」
「んー、あったかな。あ、シチュー、まだ食べてないや」
「…………」
「冗談だよ」
それだけ言って、二人のどちらに話を聞こうかと少し考えた。それから、ケイガちゃんを見る。
返り血かなにかで、手が真っ赤だ。
結構力を入れたのだろうか。
まさか、ビーフシチューではないだろうけど。
──ね、すごいでしょ、今日はここであそぼう!
──えっと、いいのかな? ここ、おじさんたちの家じゃないの?
──ちーがーう、ここは、とくべつなおきゃくさんのおうちなの、だからなとなとは、いいんだよー。
───ナナトだって、何回も言ってるだろ?
──な……? と……と。んー、わかんない。それよりさ、入ろう!
──うん。そうだね。
──……おじさんは?
──え?
──おじさん。おじさんは? とうさまは?
──どうした?
──……わかんない!
──なに?
──あれ。どうして、ここに、連れて来たのかな?
どうして? いいや、ナナトくんは、確かに、大切な……でも、でも、どうして?
さっきまで、違うだれかと一緒にいたような。
──え?
──ねぇ、聞いていい?
『まつりとナナトくんは、いつも、こうして一緒に遊んでるのかな?』
それは、どんな気分なのだろう。考えてみるが、ありきたりな例えしか浮かばない。
それも絶望には違いないが、しかし、きっとさらに想像を絶するのだろう。
さっきまで、食べていたご飯が、いつの間にかまずくなっている感じだろうか。
覚えているはずなのに、それに、確信が持てないような。
プライドが傷付くどころじゃないのかもしれない。自分にさえ、自分の記憶を支配出来ないというのは。
しかしそれも、ぼくがあくまで表面上で考えてみたことで、やっぱり、違う誰かの痛みを、感情を、完全にわかることは、ぼくに出来ないけれど。
「おーい! おーい! お客様だよー!」
「そんな大声ださなくたって、聞こえるだろ?」
まつりにとっては、なにか、面白いことなのだろう。館内で無邪気に手を振って叫んでいるので、ぼくは、誰か先客がいるのかと、首をかしげた。ケイガちゃんに至っては、すでにどこか元気がない。「お腹すいた」とこぼしていて、そういえば、もう夕飯の時間になるのかもと思った。そのときだった。
入り口のドアを開けた先のドア――というか、真ん前のホールのドアが突如開き、そこから出てきた彼女──コウカさんは、そう言って、こちらに向かってゆっくり歩いてくる。
「いらっしゃい。待ってたよ」
さらさらの長い髪に、白のニットワンピース。水色の石がついたロケットペンダントを付けていて、穏やかそうな目をした、大人のお姉さん、という感じだった。そしてその声は、聞いたことのあるものだった。そう、さっき、車を運転していた《彼》の声。兄が出てくるのかと、一瞬思ったほどだ。よくよく聞いて見ると、確かに、女性らしい声なのだが、不思議なものだ。全然違うじゃないか。
歩き方も、女性らしい歩幅で、ゆらゆら歩いている。ぼくはなんだか、少し納得したような気分になった。一番、一歩前に出て、口を開く。目が合って微笑まれる。
「──どうして、さっきは、変装を?」
「あら、バレバレだったの」
コウカさんは、やはり穏やかそうに笑って応えてくれた。
「そりゃ、家族……の、ことですし、誤魔化せませんよ。どこで兄の最近のセンスを知ったのか知りませんが」
「あれは私、男装するならやってみたかった格好なのよー! 似合ってた?」
「ええ、本当に、最初は兄かと思いました……その、自然で」
一瞬だけ、コウカさんが、寂しそうな顔をした気がしたが、ぼくにはその真意が読めない。
彼女はなにかを取り繕うように、ぼくに聞いた。
「疑ったのは、どこから?」
「どこでしょう? 《実験》を知ってたのも驚きですし、信用しかけてましたよ。だから……本当に、さっきです。でも、まあ、近くに住んでた人から聞くか、ぼくの情報を集める物好きがいるなら、知っててもおかしくない話ではありましたし……まさかって思って」
「あーあ、結構自信あったけどなー。演技にも熱を入れたんだけどなー」
「優しい、から」
「え?」
「その……なんか、態度、っていうか。優しかったから」
彼に向けられ慣れていた、ゴミの塊を見るような、そんな眼差しでなかったから。
だから、ぼくはすぐに疑えなかった。その光景に僅かな夢を見た。憧れて、否定する気になれなかったのだ。
気まずくなって、ふと、まつりを見る。なんだかちょっと困った顔をしていた。
次に、コウカさんは、ケイガちゃんに目を向けた。なんだか、少し、不思議そうだった。
「その子……」
ケイガちゃんは、びくついてまつりの後ろに隠れる。まつりは表情を変えないで、説明した。
「……ふたごの姉を探してる、って言って、ある日、メールをくれました」
「――探してたのは、エイカなのね。私ではなくて」
「待てよ、話が、見えない」
ぼくは思わずそう言った。まつりは冷たく笑った。まさしく他人に向けるような、社交的な笑顔だった。
「……うん、覚えて、ないかい?」
「覚えてるって、何を、どれをだ……」
なんだか胸が苦しくなってきて、こめかみがぎゅっと痛んだ。息がしづらい。頭がふらふらする。そんな目で見るなよ。また、ぼくが、わからなくなるのか?
そんなの、何度も経験したってのに。
「そうだねぇ、何年前になるのかな?」
まつりはそう言って少し首を傾げる。後ろにいるケイガちゃんは、ぼんやりと床の敷石を見ている。
コウカさんは、堂々と、立っていた。
「――外にいた男の子がね、向かいにあるお屋敷から外に出ていたメイドさんを見つけて、何かを言われて、ついて行くんだ。メイドさんは、突然その子をさらったそうだ」
『ねぇ、その傷、どうしたの?』
『……転んだ』
『うそ、こんなに、こんなところにまであるじゃない』
頭の中に、突然台詞が次々と浮かんできた。芝生の庭が見える。家が見える。
メイドさんも。
「その子は、そのまましばらく家に帰らなかった。その子の親は激怒した。お屋敷の主人が、健康な男の子に恵まれなかったからと、跡を継ぐ者に悩んでいたのを、知っていたから、よりいっそう怪しんだ」
『逃げなさい。こんなところにいちゃ、だめよ』
『でも、だけど、ぼくは……一人じゃ、なにも、ごはんだって、待ってなきゃ』
『ここに隠れていたのは、あなたが、苦しんでいるからじゃないの?』
そのときは、そう表現されたことに、腹が立ったし、悲しかった。別に苦しんでいるわけではなかったと、ぼくは思う。苦しむ、という感情は、弱いから、生まれるのだと思い込んでいたから、かもしれないが。そんなに弱くない、とぼくは拗ねた。
そもそも、疲れた、ですべて片付くから考えない。だから、心配されるというよりも、ただ単に、面白がられて、挑発されているように感じたのだ。
『あなた、あんなひどい家、もう、帰らなくていいわ』
『あんな人に会わなくていい』
彼女は言った。それは、善意だったのだろう。だけど、どんな理由であれ、自分の住まわせてもらった場所を、悪く言われたいと、ぼくには、思えない。そんな風に、他を容易く否定してまで、自分をかばわれてしまったことが、怖くなった。誰に向く敵意であっても、それは、臆病で幼い自分に向かってくるような、気がした。──だからぼくは、彼女の優しさが、怖かったのかもしれない。
彼らに対して恨みを持ったことだけは、ない。やってみたこともあるが、一日で惨めな気分に変わるだけだった。
誰かを拒絶すること、誰かを悪く思うこともまた、当時のぼくにとって、最も辛いことで、すべてを、好きで居たかった。
閉じきった世界を『それは間違いだ』と否定し、正しさを強要されて壊されるのは、ただただ、苦痛で、果てしない恐怖でしかない。
生まれたときから作り続けてきた認識、生まれたときからの膨大な《すべて》は、愛すべきものでありたかった。どんなに過去でも、構わなかった。
自分の手で否定し、書き換え、抹消しなければならなくなるから。今日までが、ぼくの『昨日』。昨日のことは、今日まで続く。ぼくが《被害者》になれば、ぼく自身が、ぼくにとどめを刺してしまう。
『そんな世界はもう終わった』と。
だけど、彼女は一応、自分を、少し何かがずれていながらも、心配し、説得してくれたのだ。驚いて戸惑って、どうしていいかもわからなかったのもある。
不愉快になってきたぼくは、おそらくとても悪い目付きで、彼女を見た。そして、聞いた。
『……お姉さんは、だれですか?』
『私は、ほら、あそこのお屋敷の―――いつも、あなたが窓から見えたわ』
『……えっと』
『違う違う、小さい子は好きだけど、そういうことじゃないの! 確かに可愛いけど、そういうことじゃ』
『……わかってます』
――そもそも、好きだとか、嫌いだとか、それは具体的にどこがどう違うのだろうか? それは、どんな意味を持つんだろう。
「思い――出した。どうしてだ。忘れることなんて、一切無いと思っていたのに」
「……いろいろ、あったからね」
「お前は、そのとき、どうしてたんだ? どうして、そんなことを、知ってる?」
「お茶を、飲んでいたかな。外が、急に騒がしくなって、みんなが上に行ったから、代わりに、地下の書庫に行こうとしていた」
ぼくらが話している間、しばらく黙っていたヒビキちゃんは、もう一度だるそうに、お腹すいたと訴える。
「──まあ、難しい話は、何か食べながらにしましょう?」
コウカさんがそう言ったので、話は一旦切られた。
食堂へと案内してくれる。内装は、昔来たときとあまり変わらないと思っていたが、そういえば、ちょっと変わった部分もあるようだった。
入ってすぐ右の、階段の手すりに、薄くだが、何かで引っ掻いた新しい傷があるし、床にも、昔はなかったワインか何かの染みが僅かにある。
廊下は薄暗くて、だけどほんのり灯りがあった。
何かメヌエットっぽい楽譜のようなものが描かれた壁を照らしている。
──一体誰の趣味なのだろう。
移動中は誰も話さなかった。
食べるときに真面目に話をするのは苦手だ、と言いづらくなってしまってちょっと焦る。
テレビを見ながら食べたり、会話しながら食べる人は器用だなあ、と思うけれど、ささっと食べてからする方が、楽じゃないのかな? と個人的には疑問だ。
食事を楽しむ 、という概念はどうもぼくにない。
下手に、食べながら話したり遊んだりすると、頭の中がそれでいっぱいになって、目の前の食べ物の味を感じるどころじゃなく、吐き気がする。そういう部分が、変に繊細なのだ。
10.そろわない役者
扉を開けた先の食堂には、昔と変わらない、長い木の机が置かれていた。
綺麗に布がかかっている。真ん中にろうそくがあるが、ここに来る人は(ぼくが関係者パーティーなどで、ときどき招かれた際に見た限りでは)夜でもなんでも、だいたいは、あかりを付けていた気がする。主に、シャンデリアじゃない方だけを。節約は大事だ。
机の上には美味しそうなビーフシチューが、人数分どーんと並べられていて、かと思えば皮を剥いたニンジンとか、皮を向いたきゅうりとかじゃがいも、とうもろこしも並べられていた。バスケットに入ったパンもあった。野菜はおそらくは茹でてある。
……思ったよりも素材感、だった。塩茹でなのかどうかはちょっとだけ気になる。どちらでも好きだけど。焼き芋もあった。
ナイフとフォークがあるが、なぜかスプーンがない。ビーフシチューはこのまま飲めば良いのだろうか?
聞くべきかに迷ってしまう。
「相変わらず、まざーのご飯は、全部ごろごろしてる! ひゃはは!」
まつりが笑った。ぼくには見せない感じの笑顔だ。
「あなたに誉めていただいて、光栄です。野菜が食べたいって、あなたがいったじゃない」
「感想だよー。たしかに野菜って言ったけどさ、こんなにふんだんに使ってくれるとは、予想してなかったんだ」
「美味しそう、野菜だ、シチューもいいなあ……」
ぼくが感動していると、他三人が一瞬黙った。
なんだ?
変なことは言っていない。全く。
「……どうかした?」
「気に入ってもらえたみたいだね」
まつりはなんだか苦笑いだった。ちょっと不本意だぞ。
「ええ。もちろん」
「私、ご飯が食べたいぞ……」
「ご飯も用意してます、とって来ますね」
コウカさんは、先にどうぞ、と言い残して、ぱたぱたとどこかの部屋にかけていった。
とりあえず椅子に、ぼく、ケイガちゃん、まつり、の順に座った。入り口近くの角から見て、隅から左へ詰めている。
「コウカさんって、まざーって呼んでた人だったんだな」
「うん。電話の声と、実際の声が、ちょっと違うって思った?」
「いや、確かにそれもあるけど、綺麗なお姉さんだったから驚いてる」
「もっとおばさんだと思ったんだ……」
「うーん。どうも、名前とかイメージが先に来てしまうみたいで、実際の声と、ぼくが聞く声が、ずれるみたい。今回も、あだなの影響かなあ」
「猫だよ、ってきいてから、実際はカラスの声聴かされたら」
「たぶん気が付かない。わあ猫だ、って思う」
「にゃー。そういえば、中学生時代、校内放送で、名乗らないで職員室に呼び出す先生がいると頻繁に迷ってたらしいね、どなたが呼んだんですか? って言って」
「え、そんなことも知られてるのか。あれはーちょっと、焦ったかな。ぼくをからかうイタズラなのかと思って、ときめいたりもして」
「……ときめくなよ」
ぼくはそれにはこたえずに、きゅうりにかじりついた。ナイフとフォークはこの場面に、使うんだろうか?
唐突に、足を踏まれた。どうやら、間にいたケイガちゃんだった。退屈そうに、こちらをにらんでいる。
「どうかしたの?」
「……どうかした! どうかしてるのはお前だ!」
突然、機嫌が悪そうに怒られてしまった。わからない。
「んー、それは、よく言われるんだけど、えっと、そうではなくて……」
「なんだか腹が立ったから踏んだんだ」
「ああ……よくあるよね。でも、靴に何か仕込んでたら、きみが危ないだろ? ぼくは、きみが怪我をする方が不安だ」
「え……あ、ありがとう、じゃなくて、仕込んでたのか!」
ケイガちゃんが、びっくりした顔をする。これは確かに、いじりたくなる。
「昔、脱走癖があって、靴に刃物とか、こう……仕込んでたんだよ。縄を切れるように」
「縄?」
「ぼくの腹筋を割ろうとの企てが」
「──聞かなくていいよ」
ぼくが調子に乗ったあたりでまつりがケイガちゃんにまともなアドバイスをした。
「なんだ、では、靴に何か仕込んでたのは嘘か!」
「──いや、靴に仕込んでたのは、嘘だけど、ズボンとかには仕込んでたよ。花火とか」
「一切れのパンとか?」
「そうそう。バターナイフとかね」
……なんだろう、この子。ボケてるのかそうじゃないのかが掴みにくいぞ。
「あ、そうだ、ちょっと、探し物があるから、行ってくる」
思い付きで、以前から、《いつかここに来たときに》しようと考えていて、今日、食べてからしようと思っていたことを、今からに変更した。そこに至る過程は特に無い。
「でも食べかけのきゅうりくらいは食べたらー?」
「あ、うん」
きゅうりをかじりながら、これ、調味料はついてないんだなあ、と、さっきから思っていたが確信した。
きゅうりを食べ終えて、廊下をまっすぐ歩く。シチューも食べれば良かったなあ、とちょっと思った。
なので『食べたよ』と、頭に言い聞かせておくことにした。
(これで、単純なぼくは、数時間後に食べた気になるだろうと信じている)
このまま行くと床がだんだん斜めになってきそうな感じだけど、ここに、そんなトリックらしいものはない。
まっすぐまっすぐ行くと、左と右にも曲がれるようになってきて、ぼくは左に曲がって、階段をのぼった。目指すは客間、のちょっと先にある部屋だ。宿泊出来る場所。その一室。
地図は覚えているけれど、やはり、数年来ていないと、ちょっと色が記憶と違う気がした。何もかもが、色褪せている気がする。そういえばコウカさんは、ここに客として呼ばれているのだろうか? どうしてか、と考えても無意味なのだろうけど、なんだか、これじゃ、なにかが繋がらない。もやもやする。
結構前からここに居着いているような印象だったし……料理も、彼女が用意したらしいし。
部屋まで行く間、誰にも出会わなかった。
誰かとすれ違えたらいいな、とか思っていたわけではないが、なんとなく、曲がり角や、視界を遮る観葉植物を、たびたび見かけると、誰かいる気がしてしまうのだ。
いなかったけれど。二番目に大きい宿泊部屋(洋)につくと、小さく、ドアをノックしてみた。
返事はない。誰もいない。ちょっと押してみる。
――なんと、鍵は開いていた。
なんと、と思いながらも、なんとなくの目安というか、泊ってるならここだろうなあ、というのはあったわけだが。うまく説明できない。
とにかく、やっぱり、という感じでもある。
――コウカさんも、この部屋に泊っているらしい。
ぼくはとくに覚悟もなく、さっさと部屋に踏み込んだ。
目の前の机に、飲みかけな紅茶が置かれている。いいにおいがした。もちろん飲んだりはしない。踏み込んでから、ようやく、これって、どうなんだろう、と思った。見つかったら明らかに不審者だ。変態扱いだ。
「そうは言っても、まさか以前のぼくと同じ部屋に泊っているとはね……というか、やっぱりあの人も、大切なお客様ってことなのか」
実は昔、ここに泊ったことがある。
そのときは、まつりがここに泊めてくれたが、本人には、もうその記憶はないだろう。
確か、勝手に入ったのだ。
二人で遊べる場所を探していて、まつりが提案して、なぜか、ここの鍵を持ってきていて――それで、二人で別々に過ごす部屋を選んだ。まつりは一番豪華な部屋で、ぼくは二番目だった。
なぜ部屋を選んだかといえば、二人とも泊まったからで、なぜ泊まるかというと、そこに来た時点で結構日が暮れてしまっていて、こっそり来たことが家にバレたくない、とまつりが嫌がるし、ぼくも家は苦手で、あまり帰りたくなかったから。
一言でいえば、暗くて帰り道に迷いそうだったので。
とりあえず、二人で買い物に行って、ここで夕食を食べた。残念ながら一日でいろんな方にばれたが、まつりを心配する方が先になり、あやふやというか、おとがめなしだった。
「コウカさんは、ぼくが入ったって気付くのかな……それか、まさか最初から気付いていたりして」
……あれ?
今さらだけど。
思い出すのに時間を使ってて、ピンと来てなかったけど。
──ケイガちゃんが探していたのは、コウカさんではなくて、エイカさんだって話と、ぼくの過去と。
「──どう、関係が?」
とりあえずは、ベッドの左側の机の引き出しを迷いなく開ける。(嘘。少し、迷った)すると、あった。
片方のウサギさん。あのときに、忘れたヘアゴムの片方だ。ここに置いていったものだ。そう、ぼくが。
欲しかったんじゃないし、ぼくの持ち物ではない。見つけたときに怖かったから、ずっと、見えないように隠していたのだ。あまり格好いい言い訳じゃないが。(言い訳自体、格好いいことでもないか)
もともとは、片方が、部屋のベッドの中に、落ちていて、もう片方が、廊下に落ちていた。そしてぼくは、当時、廊下にあったのを咄嗟にポケットに入れ、そしたらベッドにあったのを、見つけて、引き出しに隠したのだ。見たくなかった。それだけが理由で。それを、誰かが持っているのを見るのも、届く範囲に置いてあるのも昔は特に耐えられなかった。ポケットに入れたまま、片方を持ち帰ってしまったことに気付いたときから、ずっと罪悪感が残っていた。ああ、これでようやく、二つそろうな。
──片方を持って来ていれば。
なんで忘れてきたんだよ! と思ったが、クラッカーを留めるのに使われたから、そのまま棚に戻しちゃったのだ。まつりが、あのゴムを使ったことには、意味があるのかなあ。ちょっと気になる。
□
探していたものの確認もできたことだし、ゆっくり部屋を出て、戻ることにした。
帰り道の足取りは、軽くも重くもないが、少し、ぐるっと一周したい気分でもあったが結局、せっかくなのに、と思いつつ、まっすぐ戻る。冷めちゃって申し訳ないなあ、と思いながらも、ぼくは食堂のドアを開けた。いや、開けようとして、しかし様子が、おかしいのに気付く。
「──あれ?」
扉の隙間から見るに、ケイガちゃんが、どこにあったのか、包丁を握っていて、振り回している。
どうして?
(何かあったのかな……)
白っぽかった後ろの壁には、今、赤い色が、数滴飛び散っている。赤? 絵の具だろうか。
──これは、何かのイベントフラグ? 机でよく見えない隙間から、赤い手が、ひらひらと、こちらに揺れた。
こういうホラーがあった気がする。顔が、ちらりと、こちらを見て、また倒れていた。何やってるんだ、あいつ。──佳ノ宮まつり。派手な遊びだなあ。
あははは。
「……貴様を、殺したいと、常々思っていた!」
派手な。演出。
まるで、本当に、そうであるみたい。
こんなときのリアクションが取れない。反応が、極端に鈍い。
ただ、まっすぐに、それを見つめた。無関心なのではなく、いろんなことを考えて、必死にいろんな可能性を考えて、表に感情を出すことさえ、忘れているのだ。
──こういう状況のときは、どう思うのが、正しいのだろう?
昔から、いくら苦しんでも、泣いても、状況が変わるようなことは、何もなかった。だから、いつも、悲しんだり、苦しんだりは、ぼくに無意味だった。
ずっとそうだったから、こんな状況を用意されても、ぼくはどうしていいかわからない。『心から』が要求される場面で、心から、感情を出せない。
頭に、何に対してかもわからない疑問符を浮かべるのが、精一杯。
気持ちを切り替えることにした。きっと今も、ぼくが悲しんだり苦しんだり取り乱すのは、無意味なのだ。
逃避せずに、ちゃんと状況を理解しないと。
叫ぶことも、笑ったり、泣くこともなく。ただ、不思議そうに、ぼくは、彼女らを、見る。
何をしてるんだろう?思考回路が繋がらない。きっと、モノローグというより、箇条書き。
ぼくは扉を開ける。とても自然に。口から出たのは、ただの挨拶。
「ごめん、遅くなっちゃった」
ケイガちゃんは、ちらっとこちらを見たが、すぐに、その足元に視線を戻す。
少し気まずそうだった。ぼくを気にしたのか、手が止まっている。
大丈夫そうだと判断して、彼女のそばの、倒れている人物に、話しかけた。
「おいおい……お前、なにやらせてんだよ? 小さな女の子に」
まつりは、にや、と笑った。腹の辺りが、やけに赤色でびしょびしょだけど、意外に、まだ元気そうだ。なんとなく、納得したような、緊張がほどけた気分。
「ハッ……りふじん、だなあ」
「お前に理不尽って言われたくないね。どう、痛い? 心配してやろうか?」
「いらないよ。痛くはない……それより、気にすることが、たくさんあるだろ」
「んー、あったかな。あ、シチュー、まだ食べてないや」
「…………」
「冗談だよ」
それだけ言って、二人のどちらに話を聞こうかと少し考えた。それから、ケイガちゃんを見る。
返り血かなにかで、手が真っ赤だ。
結構力を入れたのだろうか。
まさか、ビーフシチューではないだろうけど。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説


校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る
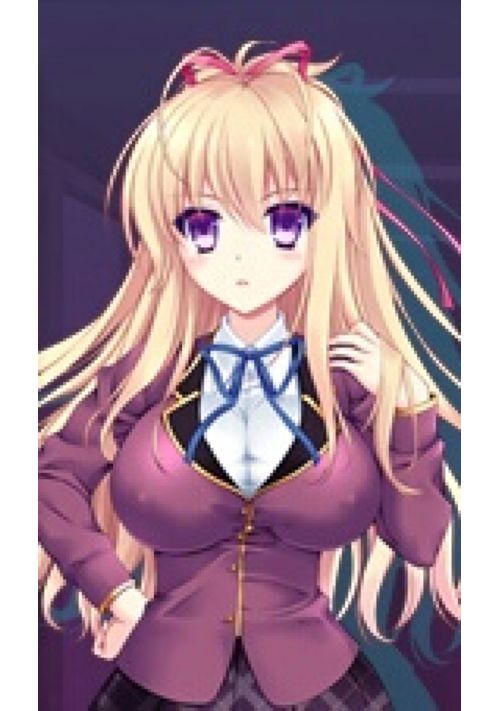
A Ghost Legacy
神能 秀臣
ミステリー
主人公である隆之介と真里奈は地元では有名な秀才の兄妹。
そんな二人に、「人生は楽しんだもの勝ち!」をモットーにしていた伯父の達哉が莫大な遺産を残したことが明らかになった。
ただし、受け取る為には妙な条件があった。それは、ある女性の為に達哉の「幽霊」を呼び出して欲しいと言うもの。訳が分からないと戸惑いながらも、二人は達哉の遺言に従って行動を開始する。

月夜のさや
蓮恭
ミステリー
いじめられっ子で喘息持ちの妹の療養の為、父の実家がある田舎へと引っ越した主人公「天野桐人(あまのきりと)」。
夏休み前に引っ越してきた桐人は、ある夜父親と喧嘩をして家出をする。向かう先は近くにある祖母の家。
近道をしようと林の中を通った際に転んでしまった桐人を助けてくれたのは、髪の長い綺麗な顔をした女の子だった。
夏休み中、何度もその女の子に会う為に夜になると林を見張る桐人は、一度だけ女の子と話す機会が持てたのだった。話してみればお互いが孤独な子どもなのだと分かり、親近感を持った桐人は女の子に名前を尋ねた。
彼女の名前は「さや」。
夏休み明けに早速転校生として村の学校で紹介された桐人。さやをクラスで見つけて話しかけるが、桐人に対してまるで初対面のように接する。
さやには『さや』と『紗陽』二つの人格があるのだと気づく桐人。日によって性格も、桐人に対する態度も全く変わるのだった。
その後に起こる事件と、村のおかしな神事……。
さやと紗陽、二人の秘密とは……?
※ こちらは【イヤミス】ジャンルの要素があります。どんでん返し好きな方へ。
「小説家になろう」にも掲載中。

『レイニー・マーダー』
篠崎俊樹
ミステリー
書き下ろしの連載ミステリー小説です。福岡県T市を舞台に、殺人事件が勃発して、刑事たちが活躍する、ハードボイルド的な小説です。第6回ホラー・ミステリー小説大賞にエントリーいたします。大賞を狙いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

Strange Days ―短編・ショートショート集―
紗倉亞空生
ミステリー
ミステリがメインのサクッと読める短編・ショートショート集です。
ときどき他ジャンルが混ざるかも知れません。
ネタを思いついたら掲載する不定期連載です。
※2024年8月25日改題しました


パラダイス・ロスト
真波馨
ミステリー
架空都市K県でスーツケースに詰められた男の遺体が発見される。殺された男は、県警公安課のエスだった――K県警公安第三課に所属する公安警察官・新宮時也を主人公とした警察小説の第一作目。
※旧作『パラダイス・ロスト』を加筆修正した作品です。大幅な内容の変更はなく、一部設定が変更されています。旧作版は〈小説家になろう〉〈カクヨム〉にのみ掲載しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















