15 / 15
十五 (及び参考文献)
しおりを挟む
大山の前妻、沢子の喪が明けてすぐの婚儀を望んでいたふたりだったが、ことはそううまくは運ばなかった。
七月に政府の重鎮、岩倉具視が、九月には齢三つの第三皇女と、生まれたばかりの第四皇女がそれぞれに薨去した。
このため、陸軍卿である大山の婚儀は晩秋まで延期と相成った。
十月末に提出された結婚願いには、五日後、十月のうちに許可が下りた。天皇への奏上も無事に終え、十一月八日には、日本式での結婚式が執り行われた。
こうして、帰朝して一年経たぬうちに、日本初の女子官費留学生のひとりであった捨松は、大山巌夫人と成った。
大山と捨松の結婚から二十日経った十一月二十八日は、日本の欧化政策における重要な転換点と言われる。
この日、とある場所で、盛大な夜会が開かれた。
夜会の会場である白い煉瓦づくりの建物は、アーケードのあるベランダや窓にルネッサンス調のアーチが施され、柱はイスラム風で、とっくり型のくびれがある。エキゾチックで、目にも新しい洋風建築だった。お雇い外国人の若き建築家ジョサイア・コンドル設計のその建物は、外国人接待所──通称「鹿鳴館」と名付けられていた。
当夜は、ここで、鹿鳴館の落成を祝う夜会が催される。
夜会には、外務卿井上馨とその妻、武子の名で約千二百人が招待された。日本人ばかりではない。外国人の姿も多く見られた。いずれも政府高官や政界、経済界などの名士ばかりが夫婦そろって続々と現れた。
招待客のなかに、捨松たちの姿もあった。
その夜の捨松は、いつにもましてうつくしく装っていた。高々と結い上げた髪には、星形のダイヤの髪飾りをいくつも挿した。ワインカラーの天鵞絨のドレスに身を包み、高揚する気持ちを抑えようと、深く息を吸う。
この場に集まったどの女性よりも堂々と振る舞える自信はあったが、扇を持つ手は小刻みに震え、手袋のなかの指は緊張で汗ばみ、冷えていた。
「武者震いですか」
捨松の震えは、その手を取る大山にも当然伝わっている。耳元でいじわるく言う大山を軽くにらんでたしなめ、捨松は二階の舞踏室への階段を慎重にあがった。
手袋に隠した指には、大山からもらった指輪がある。ドレスに用いたとろりとした光沢のある天鵞絨は、大山が捨松のためにと、遠くフランスから取り寄せた品だ。そうしたものを身につけていることが、どれだけこころの支えとなることか。極めつけに夫である大山本人が隣にいて、自分の手を取ってくれることが、捨松にとっては何よりこころ強かった。
三つ折れの階段を前の客に続いて登りきると、広い舞踏室の全容が見えた。
板張りの舞踏室の床は、鏡のように磨かれて白く光ってさえおり、まだだれもそのうえで踊ったことがないのは、目にも明らかだった。白い漆喰の天井から床を照らすシャンデリアのなんとまぶしくうつくしいことか! ルネッサンス調にS字のカーブを描く腕木の先には、可憐なスズラン型のガラスシェードがあり、その灯りは舞踏室全体を明るくきらめかせている。
ほうっと見とれている捨松の右手を支えながら、大山が下から軽く指を握った。捨松は彼を見上げ、彼が自分ではなく、舞踏室でもない遙か先を見つめているような気がした。彼と同じものが見たいと思った。
「さあ、行きましょう。あなたが思い描いた夢は、自分の手でつかみとりなさい」
前をむいたまま、つぶやくように大山は言った。踏みだして、捨松もまた前へとむきなおった。舞踏室に入ったとたん、通る声で名が呼ばれる。
居並ぶひとびとは、大山が娶ったばかりの年の離れた後妻に興味を抱いて、次々にふりむいた。捨松を女子留学生と知っている者もあるだろう。
好奇と期待に満ちた視線にさらされながら、捨松は大山に手を引かれて微笑む。胸を張り、歩きだす。
ここから、すべてがはじまるのだ。
鹿鳴館時代の幕開けとともに、捨松は大きな希望を抱いて、舞踏室の床を踏みしめた。
「……巌」
白木の墓標の立つ仮墓所に屈みこむようにして、捨松は呼びかける。
「巌。私にはもう、なすべきことはないのよ。私のかわりはおりますわ。嫁もおりますし、梅子が育てた女性たちが世に大勢おります。だから、私もいっしょに連れていってくださらなきゃ、嫌よ」
あの鹿鳴館で堂々と振る舞えたのは、大山が隣にいて、手を取ってくれていたからこそだ。自分たち夫婦の存在が、凝り固まっていた世間に一石を投じたのだと、信じたい。あとは、この流れの行く末を見守るだけだ。
時代は変わった。いまだに藩閥の名残はあれども、日本は、大日本帝国というひとつの国家として、世界に目を向けて動けるようになった。いずれ、藩閥のしがらみすら無くなって、民意が国を動かすようになるだろう。
そのときは、きっと女性も声をあげるのだ。
墓標に記された長々とした職名を見つめて、捨松はうっすらと微笑む。ほんとうは、法名をつけてもらいたかったろうに。
「神の御許にあなたがいらっしゃればよいのだけれども、どうかしら。私も神式で葬っていただかないと、お会いできないかしら」
仏教徒の大山とキリスト教徒の捨松、ふたりが神式で葬られてともに死後を過ごすだなんて、まるで自分たちの交わす会話のようだ。冗談めかして仏語でつぶやいた声を聞いたのは、きっと大山だけだったろう。
冬の風が吹く。頬の切れそうな冷たい風が肌を撫でていく。そのただなかで、捨松は目を伏せ、秋空を思った。
故郷会津の空ではなく、大山が拓いた西那須野の豊かな秋に包まれて、こころ静かに眠る日を。
参考文献
『会津史談』54 編:会津史談会出版部「アメリカの資料に見る山川捨松」久野明子 1981.5
『英学史研究』23 編:日本英学史学会 「会津藩女性と英学(1)─大山捨松を中心に─」松野良寅 1990
『公営企業』37(2) 編:地方財務協会 「書斎の窓 アリス・ベーコン著 矢口祐人・砂田恵里加共訳『明治日本の女たち』捨松と梅子の夢、アリスとの誓い、に関連して」沓抜覚 2005.5
『神戸女学院大学論集』31(3) 神戸女学院大学 「明治初期女子留学生の生涯─山川捨松の場合─」秋山ひさ 1985.3
『那須野 自然と農村と歴史文化』 磯忍 2009.5 下野新聞社
『西那須野町史』 編:西那須野町史編纂委員会 1963
『歴史春秋』13号 編:会津史学会 「《会津女性史考6》山川捨松の光と影─明治に開花した国際的才媛─」宮崎十三八
『歴史への招待』29 編: 日本放送協会「大山公爵夫人 秘められた手紙」大庭みな子 日本放送出版協会
『鹿鳴館の貴婦人 大山捨松』久野明子 1993.5 中公文庫
作中引用
『ヴェニスの商人』 シェイクスピア 翻訳:安西徹雄 2000.6 光文社古典新訳文庫
七月に政府の重鎮、岩倉具視が、九月には齢三つの第三皇女と、生まれたばかりの第四皇女がそれぞれに薨去した。
このため、陸軍卿である大山の婚儀は晩秋まで延期と相成った。
十月末に提出された結婚願いには、五日後、十月のうちに許可が下りた。天皇への奏上も無事に終え、十一月八日には、日本式での結婚式が執り行われた。
こうして、帰朝して一年経たぬうちに、日本初の女子官費留学生のひとりであった捨松は、大山巌夫人と成った。
大山と捨松の結婚から二十日経った十一月二十八日は、日本の欧化政策における重要な転換点と言われる。
この日、とある場所で、盛大な夜会が開かれた。
夜会の会場である白い煉瓦づくりの建物は、アーケードのあるベランダや窓にルネッサンス調のアーチが施され、柱はイスラム風で、とっくり型のくびれがある。エキゾチックで、目にも新しい洋風建築だった。お雇い外国人の若き建築家ジョサイア・コンドル設計のその建物は、外国人接待所──通称「鹿鳴館」と名付けられていた。
当夜は、ここで、鹿鳴館の落成を祝う夜会が催される。
夜会には、外務卿井上馨とその妻、武子の名で約千二百人が招待された。日本人ばかりではない。外国人の姿も多く見られた。いずれも政府高官や政界、経済界などの名士ばかりが夫婦そろって続々と現れた。
招待客のなかに、捨松たちの姿もあった。
その夜の捨松は、いつにもましてうつくしく装っていた。高々と結い上げた髪には、星形のダイヤの髪飾りをいくつも挿した。ワインカラーの天鵞絨のドレスに身を包み、高揚する気持ちを抑えようと、深く息を吸う。
この場に集まったどの女性よりも堂々と振る舞える自信はあったが、扇を持つ手は小刻みに震え、手袋のなかの指は緊張で汗ばみ、冷えていた。
「武者震いですか」
捨松の震えは、その手を取る大山にも当然伝わっている。耳元でいじわるく言う大山を軽くにらんでたしなめ、捨松は二階の舞踏室への階段を慎重にあがった。
手袋に隠した指には、大山からもらった指輪がある。ドレスに用いたとろりとした光沢のある天鵞絨は、大山が捨松のためにと、遠くフランスから取り寄せた品だ。そうしたものを身につけていることが、どれだけこころの支えとなることか。極めつけに夫である大山本人が隣にいて、自分の手を取ってくれることが、捨松にとっては何よりこころ強かった。
三つ折れの階段を前の客に続いて登りきると、広い舞踏室の全容が見えた。
板張りの舞踏室の床は、鏡のように磨かれて白く光ってさえおり、まだだれもそのうえで踊ったことがないのは、目にも明らかだった。白い漆喰の天井から床を照らすシャンデリアのなんとまぶしくうつくしいことか! ルネッサンス調にS字のカーブを描く腕木の先には、可憐なスズラン型のガラスシェードがあり、その灯りは舞踏室全体を明るくきらめかせている。
ほうっと見とれている捨松の右手を支えながら、大山が下から軽く指を握った。捨松は彼を見上げ、彼が自分ではなく、舞踏室でもない遙か先を見つめているような気がした。彼と同じものが見たいと思った。
「さあ、行きましょう。あなたが思い描いた夢は、自分の手でつかみとりなさい」
前をむいたまま、つぶやくように大山は言った。踏みだして、捨松もまた前へとむきなおった。舞踏室に入ったとたん、通る声で名が呼ばれる。
居並ぶひとびとは、大山が娶ったばかりの年の離れた後妻に興味を抱いて、次々にふりむいた。捨松を女子留学生と知っている者もあるだろう。
好奇と期待に満ちた視線にさらされながら、捨松は大山に手を引かれて微笑む。胸を張り、歩きだす。
ここから、すべてがはじまるのだ。
鹿鳴館時代の幕開けとともに、捨松は大きな希望を抱いて、舞踏室の床を踏みしめた。
「……巌」
白木の墓標の立つ仮墓所に屈みこむようにして、捨松は呼びかける。
「巌。私にはもう、なすべきことはないのよ。私のかわりはおりますわ。嫁もおりますし、梅子が育てた女性たちが世に大勢おります。だから、私もいっしょに連れていってくださらなきゃ、嫌よ」
あの鹿鳴館で堂々と振る舞えたのは、大山が隣にいて、手を取ってくれていたからこそだ。自分たち夫婦の存在が、凝り固まっていた世間に一石を投じたのだと、信じたい。あとは、この流れの行く末を見守るだけだ。
時代は変わった。いまだに藩閥の名残はあれども、日本は、大日本帝国というひとつの国家として、世界に目を向けて動けるようになった。いずれ、藩閥のしがらみすら無くなって、民意が国を動かすようになるだろう。
そのときは、きっと女性も声をあげるのだ。
墓標に記された長々とした職名を見つめて、捨松はうっすらと微笑む。ほんとうは、法名をつけてもらいたかったろうに。
「神の御許にあなたがいらっしゃればよいのだけれども、どうかしら。私も神式で葬っていただかないと、お会いできないかしら」
仏教徒の大山とキリスト教徒の捨松、ふたりが神式で葬られてともに死後を過ごすだなんて、まるで自分たちの交わす会話のようだ。冗談めかして仏語でつぶやいた声を聞いたのは、きっと大山だけだったろう。
冬の風が吹く。頬の切れそうな冷たい風が肌を撫でていく。そのただなかで、捨松は目を伏せ、秋空を思った。
故郷会津の空ではなく、大山が拓いた西那須野の豊かな秋に包まれて、こころ静かに眠る日を。
参考文献
『会津史談』54 編:会津史談会出版部「アメリカの資料に見る山川捨松」久野明子 1981.5
『英学史研究』23 編:日本英学史学会 「会津藩女性と英学(1)─大山捨松を中心に─」松野良寅 1990
『公営企業』37(2) 編:地方財務協会 「書斎の窓 アリス・ベーコン著 矢口祐人・砂田恵里加共訳『明治日本の女たち』捨松と梅子の夢、アリスとの誓い、に関連して」沓抜覚 2005.5
『神戸女学院大学論集』31(3) 神戸女学院大学 「明治初期女子留学生の生涯─山川捨松の場合─」秋山ひさ 1985.3
『那須野 自然と農村と歴史文化』 磯忍 2009.5 下野新聞社
『西那須野町史』 編:西那須野町史編纂委員会 1963
『歴史春秋』13号 編:会津史学会 「《会津女性史考6》山川捨松の光と影─明治に開花した国際的才媛─」宮崎十三八
『歴史への招待』29 編: 日本放送協会「大山公爵夫人 秘められた手紙」大庭みな子 日本放送出版協会
『鹿鳴館の貴婦人 大山捨松』久野明子 1993.5 中公文庫
作中引用
『ヴェニスの商人』 シェイクスピア 翻訳:安西徹雄 2000.6 光文社古典新訳文庫
0
この作品の感想を投稿する
みんなの感想(2件)
あなたにおすすめの小説
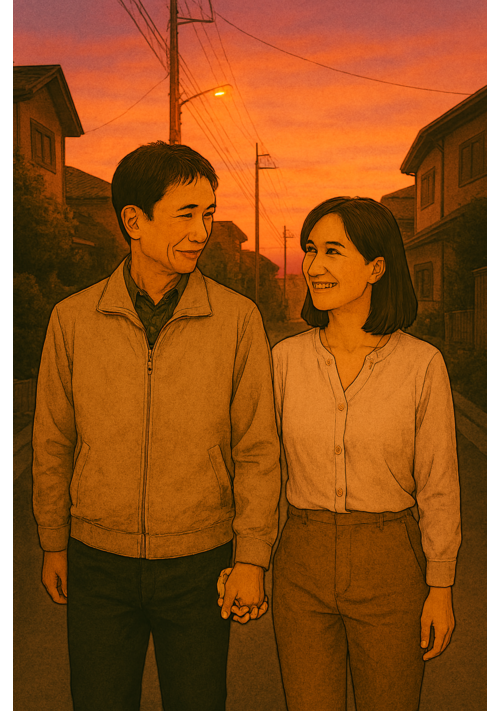
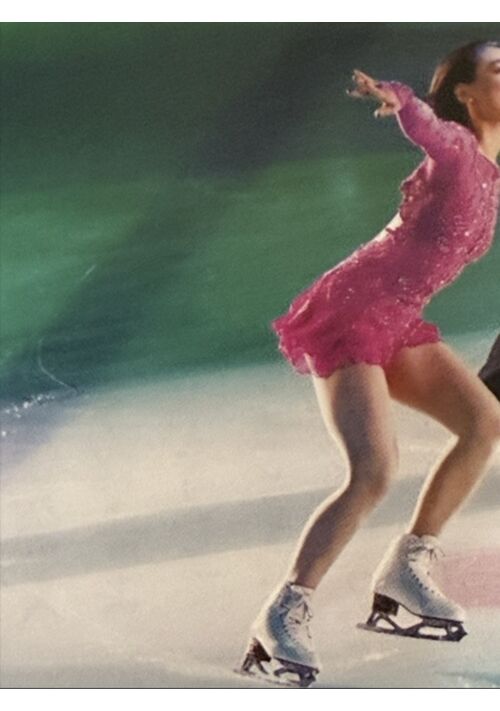
あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

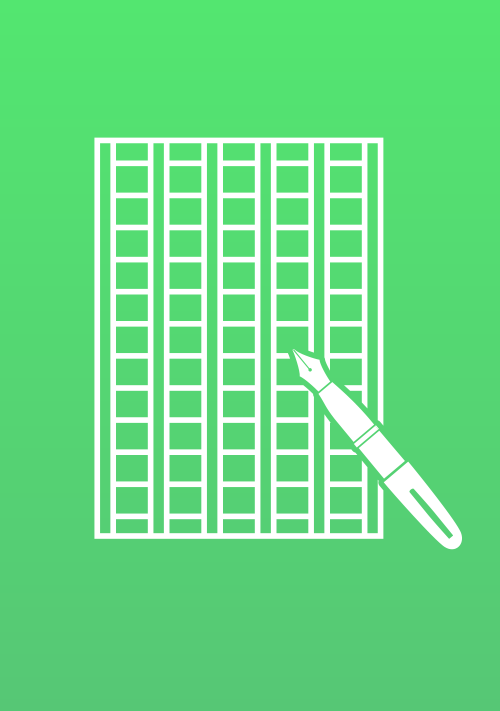

甲斐ノ副将、八幡原ニテ散……ラズ
朽縄咲良
歴史・時代
【第8回歴史時代小説大賞奨励賞受賞作品】
戦国の雄武田信玄の次弟にして、“稀代の副将”として、同時代の戦国武将たちはもちろん、後代の歴史家の間でも評価の高い武将、武田典厩信繁。
永禄四年、武田信玄と強敵上杉輝虎とが雌雄を決する“第四次川中島合戦”に於いて討ち死にするはずだった彼は、家臣の必死の奮闘により、その命を拾う。
信繁の生存によって、甲斐武田家と日本が辿るべき歴史の流れは徐々にずれてゆく――。
この作品は、武田信繁というひとりの武将の生存によって、史実とは異なっていく戦国時代を書いた、大河if戦記である。
*ノベルアッププラス・小説家になろうにも、同内容の作品を掲載しております(一部差異あり)。

壊れていく音を聞きながら
夢窓(ゆめまど)
恋愛
結婚してまだ一か月。
妻の留守中、夫婦の家に突然やってきた母と姉と姪
何気ない日常のひと幕が、
思いもよらない“ひび”を生んでいく。
母と嫁、そしてその狭間で揺れる息子。
誰も気づきがないまま、
家族のかたちが静かに崩れていく――。
壊れていく音を聞きながら、
それでも誰かを思うことはできるのか。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。





















大山巌と山川捨松については、前々から興味深い歴史上のカップルだと思っていたので、大変楽しく読めました。捨松の立場の難しさ、彼女の感情の揺れ……繊細な描写がとても良かったです。
素敵な物語をありがとうございます。
読了ありがとうございます!
こちらのカップルの馴れ初めは、「ほんとうに実話?」と驚くほどでしたので、わたしも資料漁りがたいへん楽しかったです。
拙作に触れた時間が、東郷さまにとって快いものであったなら、作り手としてもうれしいです。
大山捨松夫人の継娘の語った思い出話が好きだったので、このおはなしの続きが楽しみです。
ありがとうございます!
完結までは毎晩9時ごろに掲載できるようにがんばっていきますので、続きもぜひご覧くださいませ。