26 / 39
26
しおりを挟む
「おそらく彼女は……」
「レストランの従業員、近藤さんでしょうね」
不二三はさらりとそういった。
「か……近藤さんが」
谷口は、がくんと膝をついた。
「どうしてうちの従業員が、しかも女性だけが次々と……」
樫杉も愕然としながら涙を流した。昭道はそんな樫杉の背中をさすって目を伏せている。
「これからそれを推理します」
不二三は、淡々とそういって近藤のガムテープをはがし終えた。
「おい、不二三」
雪知は、事件になると喋るようになる不二三を見ていつもハラハラしている。
他人への配慮は普段もあまりないというか、関わり自体持ちたくない不二三だが、事件になると事件へと目線が向かいすぎて、周りへの気遣いとかそういうものが霧のように霞んでしまうのが心配になるのだ。
本当は心の優しい不二三を、事件を解決していく淡々としている不二三からは見て取れないように思う。
「……香苗だ」
菅原は、顔が赤く腫れあがりぐったりしている死体を見て目を伏せた。全員で近藤を部屋の居間まで運んで寝かせた。
「誰か皆さんを……フロントに集めてください」
「わかりました!僕が呼んできます」
不二三の指示に、昭道が頷いてどたどたと廊下を走っていった。
「警察を呼ぶことができないのが歯がゆいですね」
谷口が片手で口を押えながら眉をひそめた。
「呼べない?雪でですか?」
「不二三はまだ知らないんだったな、電話線が切られているのか電波が入らないらしいんだ」
雪知が説明すると、不二三は口元に手を当てて何かを考えている。そんな不二三を見下ろしながら、谷口が手をあわあわと動かした。
「警察が捜査とかできないわけですよね……連絡がつくまで犯人とずっと一緒ってことですよね?」
不二三が死体を触りながら首を傾げた。
「捜査は、できますよ、雪がやんだら逮捕する犯人を差し出せばいいんです」
谷口はぽかんとして不二三の顔を見た。
「僕はこうみえて探偵ですから」
「た、探偵……?え?」
谷口は、目をぱちくりさせながら雪知と不二三を交互に見た。
「探偵は、俺じゃなくて彼なんですよ、実は」
雪知はそういって愛想笑いを浮かべた。どうやら不二三ではなく雪知が探偵だと思っていたらしい。
「谷口、不二三さんは東京の少し名の知れた探偵さんなんだよ!」
「いえいえ、そんなことは」
興奮気味にいう樫杉に不二三は無表情のまま、謙遜して首を振った。
「……死亡推定時刻が絞れないな」
不二三は、近藤の様子を観察しながら死体を触っていく。
「ずっと熱湯にいれられていたら、死後硬直の時間がわからない……あ」
「どうした?」
「頭に打撲痕がある、さっき落ちていた灰皿で殴られたのかもしれないな」
手袋をはめると、灰皿と打撲痕が一致しているのを確認し、不二三は考えた。
「被害者は、一度殴られてから、体をぐるぐる巻きにされて浴室に連れていかれ、その後身動きがとれない状態で浴槽に熱湯を張られ、さらに浴室をガムテープで目張りし、さらに電気まで消している」
「逃げられると思ったんだろうか?」
雪知が問いかけると、不二三は頬をかいた。
「いや、それにしては……徹底的に“閉じ込めている”ように感じる」
「閉じ込める……」
菅原が聞こえないくらいの声で呟いて、
「あの、メモに書いてあった通り、もう復讐は終わったんだから殺人は起きないってことですよね」
「メモ?」
樫杉と谷口が不審な顔で菅原を見た。
「これです」
不二三が、昭道が飛び降りた時に持っていたメモを2人に差し出した。まだ確認していない雪知も並んでメモの中を確認する。
「復讐は完遂した 102号室……ここですね」
雪知の呟きに、安心を得たい様子の菅原は、雪知と不二三を交互に見た。
「復讐は完遂したということは、もう終わったということですよね」
「いえ、その可能性は低いかと」
「え?」
しかし、そんな菅原の安心を取り払うように不二三は冷静に告げた。
「復讐を完遂したなら、電話線を切ってまで連絡を絶つことはないんじゃないでしょうか、我々を閉じ込めた今の現状は次の殺人が起きる可能性があるか、何かまた他に犯人に意図があるのかどちらかでしょうね」
「そんな……次の殺人だなんて」
樫杉は、頭を抱えてぶるぶる震え出した。
「まあ、大丈夫です。必ず犯人を見つけ出してこれ以上犯人に殺人を起こさせないように努めますので、とりあえず皆さんもフロントに」
不二三は立ち上がって、部屋から風呂場へと向かった。
「皆一箇所にいた方が殺人は起きにくいんです。ほら推理小説、ミステリー映画などで「殺人犯と一緒になんかいられるか!」 という人が部屋で死んでいたりするでしょう?」
浴室の扉から首を半分だけ出して、不二三は続けた。
「次の殺しが起こる可能性が少しでもある場合は、全員僕が捜査を終えるまで一箇所に集まっていてもらいます、トイレに行くときも2人以上で、食事は毒が入っているかもしれないので食べないでください」
「は、はい、行こう、谷口、菅原君」
それと、と付け加えて不二三はさらに続けた。
「僕も殺されるかもしれませんので一番信用のおける雪知をここに置いておこうと思います。まあ、推理小説、ミステリー小説において、探偵を殺すことが一番犯人にとって都合がいいのに、狙われないのもおかしいですからね」
「レストランの従業員、近藤さんでしょうね」
不二三はさらりとそういった。
「か……近藤さんが」
谷口は、がくんと膝をついた。
「どうしてうちの従業員が、しかも女性だけが次々と……」
樫杉も愕然としながら涙を流した。昭道はそんな樫杉の背中をさすって目を伏せている。
「これからそれを推理します」
不二三は、淡々とそういって近藤のガムテープをはがし終えた。
「おい、不二三」
雪知は、事件になると喋るようになる不二三を見ていつもハラハラしている。
他人への配慮は普段もあまりないというか、関わり自体持ちたくない不二三だが、事件になると事件へと目線が向かいすぎて、周りへの気遣いとかそういうものが霧のように霞んでしまうのが心配になるのだ。
本当は心の優しい不二三を、事件を解決していく淡々としている不二三からは見て取れないように思う。
「……香苗だ」
菅原は、顔が赤く腫れあがりぐったりしている死体を見て目を伏せた。全員で近藤を部屋の居間まで運んで寝かせた。
「誰か皆さんを……フロントに集めてください」
「わかりました!僕が呼んできます」
不二三の指示に、昭道が頷いてどたどたと廊下を走っていった。
「警察を呼ぶことができないのが歯がゆいですね」
谷口が片手で口を押えながら眉をひそめた。
「呼べない?雪でですか?」
「不二三はまだ知らないんだったな、電話線が切られているのか電波が入らないらしいんだ」
雪知が説明すると、不二三は口元に手を当てて何かを考えている。そんな不二三を見下ろしながら、谷口が手をあわあわと動かした。
「警察が捜査とかできないわけですよね……連絡がつくまで犯人とずっと一緒ってことですよね?」
不二三が死体を触りながら首を傾げた。
「捜査は、できますよ、雪がやんだら逮捕する犯人を差し出せばいいんです」
谷口はぽかんとして不二三の顔を見た。
「僕はこうみえて探偵ですから」
「た、探偵……?え?」
谷口は、目をぱちくりさせながら雪知と不二三を交互に見た。
「探偵は、俺じゃなくて彼なんですよ、実は」
雪知はそういって愛想笑いを浮かべた。どうやら不二三ではなく雪知が探偵だと思っていたらしい。
「谷口、不二三さんは東京の少し名の知れた探偵さんなんだよ!」
「いえいえ、そんなことは」
興奮気味にいう樫杉に不二三は無表情のまま、謙遜して首を振った。
「……死亡推定時刻が絞れないな」
不二三は、近藤の様子を観察しながら死体を触っていく。
「ずっと熱湯にいれられていたら、死後硬直の時間がわからない……あ」
「どうした?」
「頭に打撲痕がある、さっき落ちていた灰皿で殴られたのかもしれないな」
手袋をはめると、灰皿と打撲痕が一致しているのを確認し、不二三は考えた。
「被害者は、一度殴られてから、体をぐるぐる巻きにされて浴室に連れていかれ、その後身動きがとれない状態で浴槽に熱湯を張られ、さらに浴室をガムテープで目張りし、さらに電気まで消している」
「逃げられると思ったんだろうか?」
雪知が問いかけると、不二三は頬をかいた。
「いや、それにしては……徹底的に“閉じ込めている”ように感じる」
「閉じ込める……」
菅原が聞こえないくらいの声で呟いて、
「あの、メモに書いてあった通り、もう復讐は終わったんだから殺人は起きないってことですよね」
「メモ?」
樫杉と谷口が不審な顔で菅原を見た。
「これです」
不二三が、昭道が飛び降りた時に持っていたメモを2人に差し出した。まだ確認していない雪知も並んでメモの中を確認する。
「復讐は完遂した 102号室……ここですね」
雪知の呟きに、安心を得たい様子の菅原は、雪知と不二三を交互に見た。
「復讐は完遂したということは、もう終わったということですよね」
「いえ、その可能性は低いかと」
「え?」
しかし、そんな菅原の安心を取り払うように不二三は冷静に告げた。
「復讐を完遂したなら、電話線を切ってまで連絡を絶つことはないんじゃないでしょうか、我々を閉じ込めた今の現状は次の殺人が起きる可能性があるか、何かまた他に犯人に意図があるのかどちらかでしょうね」
「そんな……次の殺人だなんて」
樫杉は、頭を抱えてぶるぶる震え出した。
「まあ、大丈夫です。必ず犯人を見つけ出してこれ以上犯人に殺人を起こさせないように努めますので、とりあえず皆さんもフロントに」
不二三は立ち上がって、部屋から風呂場へと向かった。
「皆一箇所にいた方が殺人は起きにくいんです。ほら推理小説、ミステリー映画などで「殺人犯と一緒になんかいられるか!」 という人が部屋で死んでいたりするでしょう?」
浴室の扉から首を半分だけ出して、不二三は続けた。
「次の殺しが起こる可能性が少しでもある場合は、全員僕が捜査を終えるまで一箇所に集まっていてもらいます、トイレに行くときも2人以上で、食事は毒が入っているかもしれないので食べないでください」
「は、はい、行こう、谷口、菅原君」
それと、と付け加えて不二三はさらに続けた。
「僕も殺されるかもしれませんので一番信用のおける雪知をここに置いておこうと思います。まあ、推理小説、ミステリー小説において、探偵を殺すことが一番犯人にとって都合がいいのに、狙われないのもおかしいですからね」
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

化想操術師の日常
茶野森かのこ
キャラ文芸
たった一つの線で、世界が変わる。
化想操術師という仕事がある。
一般的には知られていないが、化想は誰にでも起きる可能性のある現象で、悲しみや苦しみが心に抱えきれなくなった時、人は無意識の内に化想と呼ばれるものを体の外に生み出してしまう。それは、空間や物や生き物と、その人の心を占めるものである為、様々だ。
化想操術師とは、頭の中に思い描いたものを、その指先を通して、現実に生み出す事が出来る力を持つ人達の事。本来なら無意識でしか出せない化想を、意識的に操る事が出来た。
クズミ化想社は、そんな化想に苦しむ人々に寄り添い、救う仕事をしている。
社長である九頭見志乃歩は、自身も化想を扱いながら、化想患者限定でカウンセラーをしている。
社員は自身を含めて四名。
九頭見野雪という少年は、化想を生み出す能力に長けていた。志乃歩の養子に入っている。
常に無表情であるが、それは感情を失わせるような過去があったからだ。それでも、志乃歩との出会いによって、その心はいつも誰かに寄り添おうとしている、優しい少年だ。
他に、志乃歩の秘書でもある黒兎、口は悪いが料理の腕前はピカイチの姫子、野雪が生み出した巨大な犬の化想のシロ。彼らは、山の中にある洋館で、賑やかに共同生活を送っていた。
その洋館に、新たな住人が加わった。
記憶を失った少女、たま子。化想が扱える彼女は、記憶が戻るまでの間、野雪達と共に過ごす事となった。
だが、記憶を失くしたたま子には、ある目的があった。
たま子はクズミ化想社の一人として、志乃歩や野雪と共に、化想を出してしまった人々の様々な思いに触れていく。
壊れた友情で海に閉じこもる少年、自分への後悔に復讐に走る女性、絵を描く度に化想を出してしまう少年。
化想操術の古い歴史を持つ、阿木之亥という家の人々、重ねた野雪の過去、初めて出来た好きなもの、焦がれた自由、犠牲にしても守らなきゃいけないもの。
野雪とたま子、化想を取り巻く彼らのお話です。

変な屋敷 ~悪役令嬢を育てた部屋~
aihara
ミステリー
侯爵家の変わり者次女・ヴィッツ・ロードンは博物館で建築物史の学術研究院をしている。
ある日彼女のもとに、婚約者とともに王都でタウンハウスを探している妹・ヤマカ・ロードンが「この屋敷とてもいいんだけど、変な部屋があるの…」と相談を持ち掛けてきた。
とある作品リスペクトの謎解きストーリー。
本編9話(プロローグ含む)、閑話1話の全10話です。

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

イケメン社長と私が結婚!?初めての『気持ちイイ』を体に教え込まれる!?
すずなり。
恋愛
ある日、彼氏が自分の住んでるアパートを引き払い、勝手に『同棲』を求めてきた。
「お前が働いてるんだから俺は家にいる。」
家事をするわけでもなく、食費をくれるわけでもなく・・・デートもしない。
「私は母親じゃない・・・!」
そう言って家を飛び出した。
夜遅く、何も持たず、靴も履かず・・・一人で泣きながら歩いてるとこを保護してくれた一人の人。
「何があった?送ってく。」
それはいつも仕事場のカフェに来てくれる常連さんだった。
「俺と・・・結婚してほしい。」
「!?」
突然の結婚の申し込み。彼のことは何も知らなかったけど・・・惹かれるのに時間はかからない。
かっこよくて・・優しくて・・・紳士な彼は私を心から愛してくれる。
そんな彼に、私は想いを返したい。
「俺に・・・全てを見せて。」
苦手意識の強かった『営み』。
彼の手によって私の感じ方が変わっていく・・・。
「いあぁぁぁっ・・!!」
「感じやすいんだな・・・。」
※お話は全て想像の世界のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※お話の中に出てくる病気、治療法などは想像のものとしてご覧ください。
※誤字脱字、表現不足は重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけると嬉しいです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・すみません。
それではお楽しみください。すずなり。
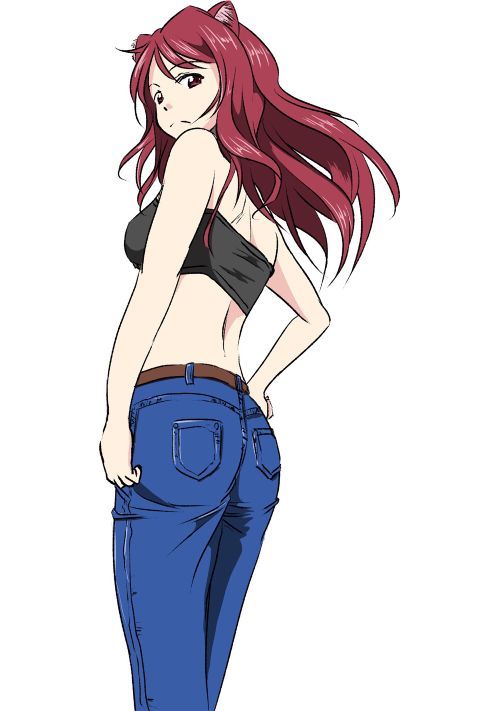
遥か
カリフォルニアデスロールの野良兎
キャラ文芸
鶴木援(ツルギタスケ)は、疲労状態で仕事から帰宅する。何も無い日常にトラウマを抱えた過去、何も起きなかったであろう未来を抱えたまま、何故か誤って監獄街に迷い込む。
生きることを問いかける薄暗いロー・ファンタジー。
表紙 @kafui_k_h


小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















