お気に入りに追加
1
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。


転校して来た美少女が前幼なじみだった件。
ながしょー
青春
ある日のHR。担任の呼び声とともに教室に入ってきた子は、とてつもない美少女だった。この世とはかけ離れた美貌に、男子はおろか、女子すらも言葉を詰まらせ、何も声が出てこない模様。モデルでもやっていたのか?そんなことを思いながら、彼女の自己紹介などを聞いていると、担任の先生がふと、俺の方を……いや、隣の席を指差す。今朝から気になってはいたが、彼女のための席だったということに今知ったのだが……男子たちの目線が異様に悪意の籠ったものに感じるが気のせいか?とにもかくにも隣の席が学校一の美少女ということになったわけで……。
このときの俺はまだ気づいていなかった。この子を軸として俺の身の回りが修羅場と化すことに。

パーフェクトアンドロイド
ことは
キャラ文芸
アンドロイドが通うレアリティ学園。この学園の生徒たちは、インフィニティブレイン社の実験的試みによって開発されたアンドロイドだ。
だが俺、伏木真人(ふしぎまひと)は、この学園のアンドロイドたちとは決定的に違う。
俺はインフィニティブレイン社との契約で、モニターとしてこの学園に入学した。他の生徒たちを観察し、定期的に校長に報告することになっている。
レアリティ学園の新入生は100名。
そのうちアンドロイドは99名。
つまり俺は、生身の人間だ。
▶︎credit
表紙イラスト おーい
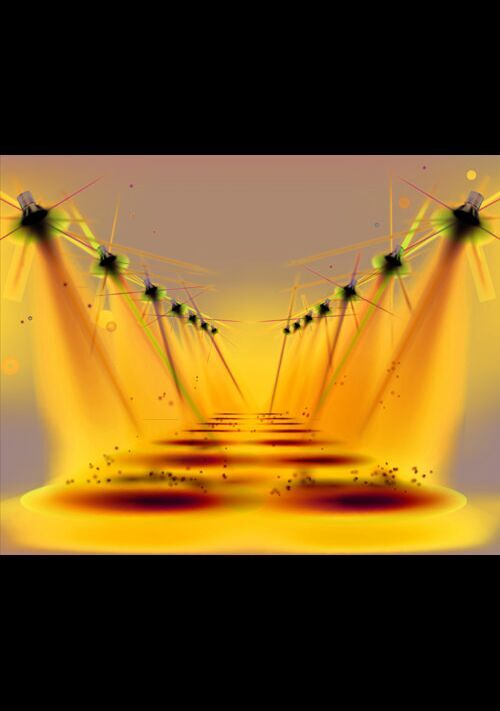
私のなかの、なにか
ちがさき紗季
青春
中学三年生の二月のある朝、川奈莉子の両親は消えた。叔母の曜子に引き取られて、大切に育てられるが、心に刻まれた深い傷は癒えない。そればかりか両親失踪事件をあざ笑う同級生によって、ネットに残酷な書きこみが連鎖し、対人恐怖症になって引きこもる。
やがて自分のなかに芽生える〝なにか〟に気づく莉子。かつては気持ちを満たす幸せの象徴だったそれが、不穏な負の象徴に変化しているのを自覚する。同時に両親が大好きだったビートルズの名曲『Something』を聴くことすらできなくなる。
春が訪れる。曜子の勧めで、独自の教育方針の私立高校に入学。修と咲南に出会い、音楽を通じてどこかに生きているはずの両親に想いを届けようと考えはじめる。
大学一年の夏、莉子は修と再会する。特別な歌声と特異の音域を持つ莉子の才能に気づいていた修の熱心な説得により、ふたたび歌うようになる。その後、修はネットの音楽配信サービスに楽曲をアップロードする。間もなく、二人の世界が動きはじめた。
大手レコード会社の新人発掘プロデューサー澤と出会い、修とともにライブに出演する。しかし、両親の失踪以来、莉子のなかに巣食う不穏な〝なにか〟が膨張し、大勢の観客を前にしてパニックに陥り、倒れてしまう。それでも奮起し、ぎりぎりのメンタルで歌いつづけるものの、さらに難題がのしかかる。音楽フェスのオープニングアクトの出演が決定した。直後、おぼろげに悟る両親の死によって希望を失いつつあった莉子は、プレッシャーからついに心が折れ、プロデビューを辞退するも、曜子から耳を疑う内容の電話を受ける。それは、両親が生きている、という信じがたい話だった。
歌えなくなった莉子は、葛藤や混乱と闘いながら――。
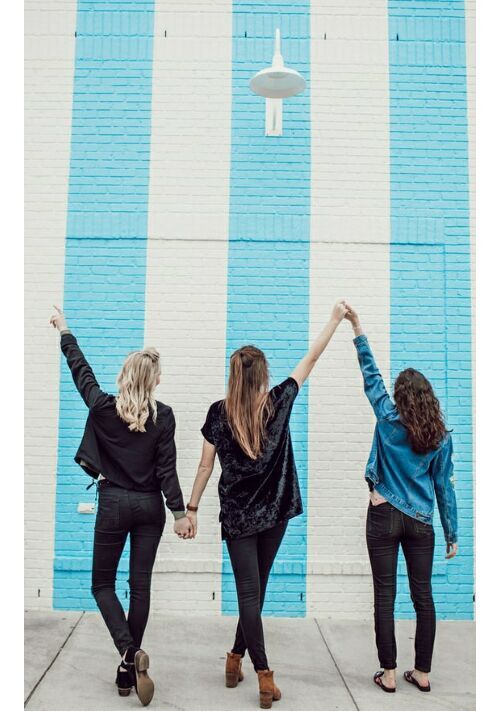
女子高生は小悪魔だ~教師のボクはこんな毎日送ってます
藤 ゆう
青春
ボクはある私立女子高の体育教師。大学をでて、初めての赴任だった。
「男子がいないからなぁ、ブリっ子もしないし、かなり地がでるぞ…おまえ食われるなよ(笑)」
先輩に聞いていたから少しは身構えていたけれど…
色んな(笑)事件がまきおこる。
どこもこんなものなのか?
新米のボクにはわからないけれど、ついにスタートした可愛い小悪魔たちとの毎日。


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















