74 / 116
第六章
第七十夜 【嘗ての約束】
しおりを挟む17時。和泉は大玄関で朱理の姿を見かけた。ダークスーツの男と、濃厚な口付けを交わしている。
くすくすと笑う朱理と男の遣り取りが、微かに聞こえてきた。
「ん、はァっ……篁さん……もうダメだってば……。そんなに焦らなくても、今夜会えるでしょ?」
「そうだが、まだ6時間以上もある。お前を前にすると、どうにも欲が出るのさ」
「ふふ……がっつくの、珍しくてイイね。でも、夜までに満足されちゃ厭だから、もう行くよ」
「こんな物で満足するとでも? 待て、あと1回だけ」
「もォー、さっきもそう言っ……ン、ふっ、んん……ぁっ」
和泉は小さく息を吐いて階段を上った。
朱理の様子は、いつも通りと言えばそうなのだが、やはりどこか歪んでいる。微妙な声音や表情の端々に、それが滲み出ているのだ。
総道中以来、自分も忙しくなった為に身動きが取れなかったが、今日こそはと腹を決め、ある部屋を目指す。
襖の前に立ち、ひとつ深呼吸してから声を掛けた。
「和泉です。いらっしゃいますか?」
ややあってから襖が開き、陸奥が顔を出した。
「よぉ。どうした、俺の部屋に来るなんて珍しい」
「お話しがあるのですが、少々、お時間頂けますか」
「良いぜ、入れよ。散らかってるけど」
「失礼します」
陸奥は和泉を招き入れると、正面の椅子に腰掛けて煙草に火を点けた。背後ではパソコンのモニターが6つ並び、それぞれ株のグラフや様々な数値を映し出している。
和泉は座らず、陸奥の正面に立って口火を切った。
「朱理の事で、ご相談があります」
「ん、なに?」
「近頃の彼奴は、明らかにおかしいと思いませんか」
「さあ、どうだろうな。おかしいってのは、何を基準にして言ってるんだ?」
「今までです。まるで別人じゃないですか。貴方が一番、よく分かっているでしょう」
陸奥はふう、と紫煙を吐きながら肘をついて首を傾げる。
「アレはアレで朱理だろ。悪い方に転んでりゃ心配するのも分かるが、近頃の人気は鰻のぼりじゃないか。どんな問題があるって言うんだ?」
「あんな状態で、長く持つ筈が無い。このまま放っておいては、いつか取り返しの付かない事になる気がしてならないんです」
「取り返しの付かない事……ねぇ。で? 今なら取り返せるとでも言うのか?」
「未だ、間に合うかも知れない……。だからご相談にあがったんです。彼奴があんな風になったのは、貴方との関係があってからだ。貴方なら、彼奴を元に戻せるんじゃないですか?」
眉根を寄せて訴える和泉に、陸奥は笑いながら目を閉じた。
「お前、酷い勘違いをしてるぜ。朱理を変えたのは俺じゃない。全くの無関係とは言わないが、主要因ではないんだよ」
「そんな訳が無いでしょう。だって、貴方に初めて買われてから、彼奴は……」
「ああ、確かに引き金はそれだったろうよ。だから無関係とは言ってない。ただ、俺はきっかけを作った、それだけの事だ」
和泉はぐっと唇を噛んだ。よくもそんな無責任な言い方が出来る物だ、と怒りが込み上げる。
怒鳴りたいのを必死で抑えつけ、言葉を絞り出した。
「……その言い方なら、主要因が何なのかご存知なんですよね」
「まぁ、見当は付いてる」
「なら教えて下さい、どうしたら彼奴を救えるのか。もう……あんな姿は見ていられないんです……」
油断すると滲みそうになる涙を堪えて俯く和泉を、陸奥はじっと見つめていた。
握りしめた両の拳は、僅かに震えている。普段は至って冷静な和泉がここまで取り乱すとは、余程、朱理を大事に想っているのだろう。
お願いします、と消え入りそうな声で言う姿は痛ましく、憐憫を誘う。暫くその様を眺めていた陸奥は、紫煙を吐きながら静かに答えた。
「厭だ」
「……は?」
微笑みを浮かべて発せられた言葉の意味が、和泉には直ぐに理解出来なかった。
呆然とする和泉を可笑しそうに見て、陸奥は再び口を開いた。
「聞こえなかったか? 厭だ、と言ったんだ」
「……な、ぜ……貴方は知っているんでしょう!? 教えてくれるだけで良いんです! 原因さえ分かれば、俺が──」
「和泉、俺はお前に勘違いしてると言わなかったか?」
「それは、貴方が原因ではないという事でしょう!? ですから──」
「お前の勘違いはひとつじゃない」
尽く和泉の言葉を遮る陸奥に、焦りと怒りが込み上げる。ついに和泉は堪えきれず、声を荒らげた。
「持って回った言い方は辞めて頂きたいッ!! 一体、何が言いたいんだ!」
「そうだなぁ、そもそも、お前が俺にそんな相談をして来たこと自体、勘違いも甚だしいな」
「……何を……言って……」
「だってお前、そりゃ俺が今の朱理を否定してる前提で来てるだろう。其処から大間違いなのさ」
「──……ッ」
和泉は二の句が継げなかった。そんな馬鹿な、と否定したがる心とは裏腹に、頭では理解しつつある陸奥の恐ろしい思考回路に、鳥肌が立つ。
「俺はね、和泉、今の朱理が至高で最高だと思ってるんだよ。あの子は嘆いて、哀しんで、苦しみに藻掻く姿が、一番美しいんだ」
ぞっとするほど綺麗な笑みを浮かべて言う陸奥に、和泉は思わず後退った。
狂っている。この男は完全に狂者だ。
「ハハ、そう怯えてくれるなよ。傷付くじゃないか」
陸奥は微塵もそんな事を思っていない様な笑顔で、紫煙を吐きながら続けた。
「それになぁ、原因が分かったところで、俺たちにはどうしようもないんだよ。まぁ、俺は戻すつもりなんて更々無いから、別に良いんだけど」
「…………」
その言葉には反論出来なかった。どうする事も出来ないだろう、という予感はあったからだ。
しかし、陸奥は違うと思っていた。この男なら、少しは事態を動かせるかもしれないと思ったからこそ、此処へ赴いたのだ。
それを真っ向から無理だと、出来たとしてもやらないと、明言されたのである。文句も、懇願も、罵倒も、この男には通じないと直感で解る。
和泉はもう何も言えなかった。目を細めて煙草を咥える陸奥に、己の想いなどひと欠片も伝わらないのだ。
思考の次元が根本から違う。彼の幸福と己の幸福とは、決して交わらぬ価値観のもとに形成されているのだと、思い知らされた。
和泉はそれから、どうやって自室へ戻ったか覚えていない。
一縷の望みと思っていた物は、絶望の深淵だった。その淵を覗き込んだ自分もまた、深淵から覗かれる事となってしまったのだ。
鬼と怪物を肚に抱えたこの見世が、無性に恐ろしく感じて堪らなかった。
────────────────
『ねえ奈央、一緒に花を植えようよ』
『はぁ? またお前はそうやって、思い付きで行動する……』
『良いじゃん、あんなデカい中庭あるんだしさ』
『だからって、なんで急に花?』
『なんとなく。二人で育てられる物なら、何でも良いんだ』
『ったく……分かったよ。何を植える?』
『そうだなぁ、これからの時期だと、向日葵なんか丁度良いんじゃない?』
『ああ、良いかもな。けどお前、ちゃんと水遣り出来んのか? なんか直ぐ枯らしそうだわ』
『奈央こそ、几帳面そうな顔してズボラなくせにぃ。だから一緒にやろうって言ったんだよ。ほら、お互いの監視要員的な?』
『たかが花育てるのに、そんな物騒な言い方するなよ……』
『あはは! じゃあ約束。朝、お客さん見送ったら中庭に集合ね』
『はいはい。絶対サボんなよ。言い出したの、朱理なんだからな』
『わーかってるって。大丈夫だよ。俺が奈央との約束、破った事あった?』
『ふん……。埋める場所、ちゃんと決めとけよ』
『はーい』
────────────────
午前5時半。朝靄の掛かる中庭の片隅に、和泉は一人で佇んでいた。
じっと見下ろす足元には、何も無い。ただ青々とした芝生が、露に濡れて光っていた。
あれは何年前の約束だったか。
共に種を植え、毎朝この場所で落ち合って水を遣った。芽が出た時には、まるで子供の様にはしゃいでいた姿が、今でも鮮明に思い出せる。
軈て花が咲き、それを見つめる横顔はとても満足そうだった。
咲いたね、と小さく呟かれた声は穏やかで。咲いたな、と答える自分もまた、同じ様な声音だった。
太陽の花の後ろから登る、本物の太陽が眩しくて。此方を見て笑う顔が眩しくて。
訳も無く泣きたくなった。
二人で植えた向日葵はとうに枯れ、あの日の事など、無かったかの様だ。
もし彼まで全て忘れてしまったら、どれほど寂しい事だろう。築き上げてきた思い出も、いつか薄れてしまうのだろうか。
彼の抱える愁いと、その心を蝕む苦悩が、どうか早く消え失せて欲しい。
そんな事を毎日、願っている。願う事しか出来ない無力な自分を、責め苛みながら。
いつまでも変わらないと信じてやまなかった日々は、気づいた時には跡形もなくなっていた。
変わらぬ物など無いと分かっている。自分とて変わってきた。
それでも今まで変わらなかった物が、変わって欲しくなかった物が、其所に在った。失くしたくない思い出が、人が、確かに在った。
まだ其処に居る筈なのに、まだ其処に在る筈なのに、黒い靄に包まれて手が届かない。
混沌とした暗闇から幾本もの手が伸びて来て、彼を捕えて連れて行ってしまう。
眩い世界から突然、奈落の底へ引き摺り込まれた彼を見失ってしまった。
急いで追いかけてはみたけれど、光ばかり見ていた目はその闇に慣れず、手探りで恐る恐る進んでみた。
漸く見えたと思った光明は、勘違いも甚だしくて。
より一層の深淵を知った自分は、足が竦んでもう動けない。
────────────────
『あーあ、やっぱり奈央が先に年季明けすんのかなぁ。厭だなぁ、置いて行かれるの』
『……もう少し歳くったら、10年後の約束でもするか』
『嗚呼、えっと……なんだっけ。サグラダファミリア?』
『ドゥオモだよ』
『それだ、それだ。何処にあるやつだっけ』
『ミラノ』
『奈央は本当にあの映画、好きだよねー。でもちょっと遠くない? 俺、一人で行ける気がしねぇんだけど』
『ははっ。じゃあ東都タワーにするか?』
『ベタだなー。都内の塔なら、もうひとつあるぜ』
『どっちでも良いさ』
『うん。何があっても絶対、また会おう。んで、ずっと一緒に居よう。しわくちゃの爺さんになるまでさ。そしたら縁側でお茶でも飲んで、もうお墓も一緒にしちゃおうよ』
『いや、墓は流石に……』
『えー、駄目? 俺は良いよ、奈央となら』
『ったく。いちいち大袈裟だな、お前は。……でも、必ずまた会うよ』
『うん、必ず』
────────────────
あの日の約束は、まだ有効だろうか。
例えお前が忘れてしまったとしても、この心に残る温もりは、決して消える事はない。
全て終わった時にはもう一度、10年後の約束をしよう。
30
お気に入りに追加
138
あなたにおすすめの小説
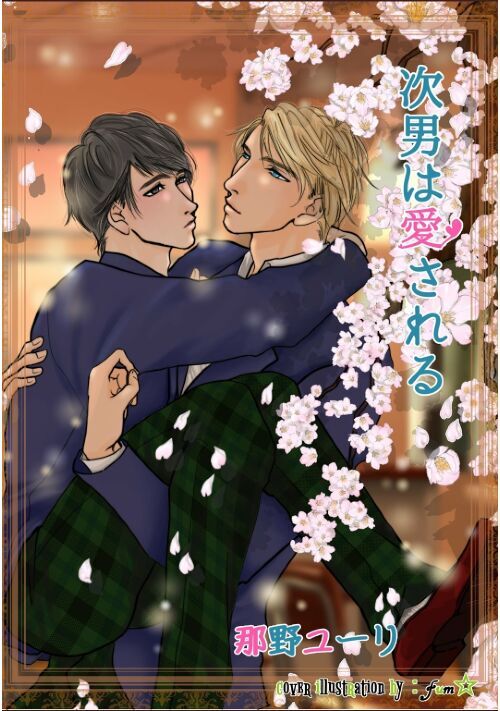
次男は愛される
那野ユーリ
BL
ゴージャス美形の長男×自称平凡な次男
佐奈が小学三年の時に父親の再婚で出来た二人の兄弟。美しすぎる兄弟に挟まれながらも、佐奈は家族に愛され育つ。そんな佐奈が禁断の恋に悩む。
素敵すぎる表紙は〝fum☆様〟から頂きました♡
無断転載は厳禁です。
【タイトル横の※印は性描写が入ります。18歳未満の方の閲覧はご遠慮下さい。】
12月末にこちらの作品は非公開といたします。ご了承くださいませ。
近況ボードをご覧下さい。

有能社長秘書のマンションでテレワークすることになった平社員の俺
高菜あやめ
BL
【マイペース美形社長秘書×平凡新人営業マン】会社の方針で社員全員リモートワークを義務付けられたが、中途入社二年目の営業・野宮は困っていた。なぜならアパートのインターネットは遅すぎて仕事にならないから。なんとか出社を許可して欲しいと上司に直談判したら、社長の呼び出しをくらってしまい、なりゆきで社長秘書・入江のマンションに居候することに。少し冷たそうでマイペースな入江と、ちょっとビビりな野宮はうまく同居できるだろうか? のんびりほのぼのテレワークしてるリーマンのラブコメディです

one night
雲乃みい
BL
失恋したばかりの千裕はある夜、バーで爽やかな青年実業家の智紀と出会う。
お互い失恋したばかりということを知り、ふたりで飲むことになるが。
ーー傷の舐め合いでもする?
爽やかSでバイな社会人がノンケ大学生を誘惑?
一夜だけのはずだった、なのにーーー。


年上の恋人は優しい上司
木野葉ゆる
BL
小さな賃貸専門の不動産屋さんに勤める俺の恋人は、年上で優しい上司。
仕事のこととか、日常のこととか、デートのこととか、日記代わりに綴るSS連作。
基本は受け視点(一人称)です。
一日一花BL企画 参加作品も含まれています。
表紙は松下リサ様(@risa_m1012)に描いて頂きました!!ありがとうございます!!!!
完結済みにいたしました。
6月13日、同人誌を発売しました。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。


Take On Me
マン太
BL
親父の借金を返済するため、ヤクザの若頭、岳(たける)の元でハウスキーパーとして働く事になった大和(やまと)。
初めは乗り気でなかったが、持ち前の前向きな性格により、次第に力を発揮していく。
岳とも次第に打ち解ける様になり…。
軽いノリのお話しを目指しています。
※BLに分類していますが軽めです。
※他サイトへも掲載しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる





















