お気に入りに追加
3
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説
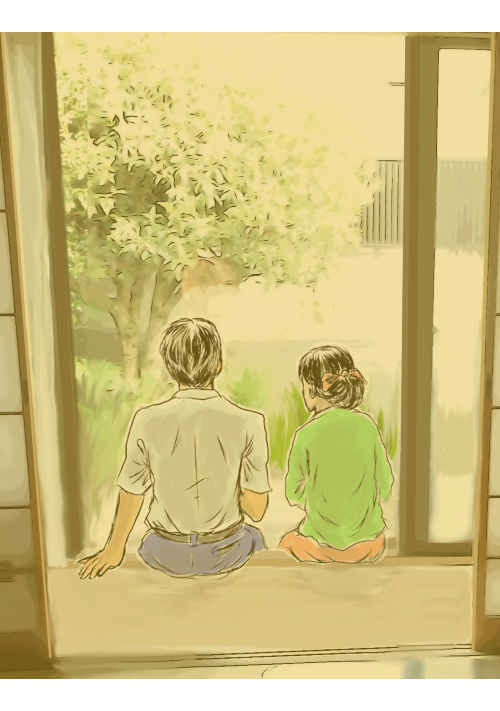
雨音
宮ノ上りよ
ライト文芸
夫を亡くし息子とふたり肩を寄せ合って生きていた祐子を日々支え力づけてくれたのは、息子と同い年の隣家の一人娘とその父・宏の存在だった。子ども達の成長と共に親ふたりの関係も少しずつ変化して、そして…。
※時代設定は1980年代後半~90年代後半(最終のエピソードのみ2010年代)です。現代と異なる点が多々あります。(学校週六日制等)

演じる家族
ことは
ライト文芸
永野未来(ながのみらい)、14歳。
大好きだったおばあちゃんが突然、いや、徐々に消えていった。
だが、彼女は甦った。
未来の双子の姉、春子として。
未来には、おばあちゃんがいない。
それが永野家の、ルールだ。
【表紙イラスト】ノーコピーライトガール様からお借りしました。
https://fromtheasia.com/illustration/nocopyrightgirl

アーコレードへようこそ
松穂
ライト文芸
洋食レストラン『アーコレード(Accolade)』慧徳学園前店のひよっこ店長、水奈瀬葵。
楽しいスタッフや温かいお客様に囲まれて毎日大忙し。
やっと軌道に乗り始めたこの時期、突然のマネージャー交代?
異名サイボーグの新任上司とは?
葵の抱える過去の傷とは?
変化する日常と動き出す人間模様。
二人の間にめでたく恋情は芽生えるのか?
どこか懐かしくて最高に美味しい洋食料理とご一緒に、一読いかがですか。
※ 完結いたしました。ありがとうございました。

冬馬君の夏休み
だかずお
青春
冬馬君の夏休みの日々
キャンプや恋、お祭りや海水浴 夏休みの
楽しい生活
たくさんの思い出や体験が冬馬君を成長させる 一緒に思い出を体験しよう。
きっと懐かしの子供の頃の思いが蘇る
さあ!!
あの頃の夏を再び
現在、You Tubeにて冬馬君の夏休み、聴く物語として、公開中!!
是非You Tubeで、冬馬君の夏休み で検索してみてね(^^)v

鎌倉古民家カフェ「かおりぎ」
水川サキ
ライト文芸
旧題」:かおりぎの庭~鎌倉薬膳カフェの出会い~
【私にとって大切なものが、ここには満ちあふれている】
彼氏と別れて、会社が倒産。
不運に見舞われていた夏芽(なつめ)に、父親が見合いを勧めてきた。
夏芽は見合いをする前に彼が暮らしているというカフェにこっそり行ってどんな人か見てみることにしたのだが。
静かで、穏やかだけど、たしかに強い生彩を感じた。

元おっさんの俺、公爵家嫡男に転生~普通にしてるだけなのに、次々と問題が降りかかってくる~
おとら@ 書籍発売中
ファンタジー
アルカディア王国の公爵家嫡男であるアレク(十六歳)はある日突然、前触れもなく前世の記憶を蘇らせる。
どうやら、それまでの自分はグータラ生活を送っていて、ろくでもない評判のようだ。
そんな中、アラフォー社畜だった前世の記憶が蘇り混乱しつつも、今の生活に慣れようとするが……。
その行動は以前とは違く見え、色々と勘違いをされる羽目に。
その結果、様々な女性に迫られることになる。
元婚約者にしてツンデレ王女、専属メイドのお調子者エルフ、決闘を仕掛けてくるクーデレ竜人姫、世話をすることなったドジっ子犬耳娘など……。
「ハーレムは嫌だァァァァ! どうしてこうなった!?」
今日も、そんな彼の悲鳴が響き渡る。

後宮の胡蝶 ~皇帝陛下の秘密の妃~
菱沼あゆ
キャラ文芸
突然の譲位により、若き皇帝となった苑楊は封印されているはずの宮殿で女官らしき娘、洋蘭と出会う。
洋蘭はこの宮殿の牢に住む老人の世話をしているのだと言う。
天女のごとき外見と豊富な知識を持つ洋蘭に心惹かれはじめる苑楊だったが。
洋蘭はまったく思い通りにならないうえに、なにかが怪しい女だった――。
中華後宮ラブコメディ。

【3】Not equal romance【完結】
ホズミロザスケ
ライト文芸
大学生の桂咲(かつら えみ)には異性の友人が一人だけいる。駿河総一郎(するが そういちろう)だ。同じ年齢、同じ学科、同じ趣味、そしてマンションの隣人ということもあり、いつも一緒にいる。ずっと友達だと思っていた咲は駿河とともに季節を重ねていくたび、感情の変化を感じるようになり……。
「いずれ、キミに繋がる物語」シリーズ三作目(登場する人物が共通しています)。単品でも問題なく読んでいただけます。
※当作品は「カクヨム」「小説家になろう」にも同時掲載しております。(過去に「エブリスタ」にも掲載)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















