お気に入りに追加
20
あなたにおすすめの小説

マキノのカフェ開業奮闘記 ~Café Le Repos~
Repos
ライト文芸
カフェ開業を夢見たマキノが、田舎の古民家を改装して開業する物語。
おいしいご飯がたくさん出てきます。
いろんな人に出会って、気づきがあったり、迷ったり、泣いたり。
助けられたり、恋をしたり。
愛とやさしさののあふれるお話です。
なろうにも投降中

如月さんは なびかない。~片想い中のクラスで一番の美少女から、急に何故か告白された件~
八木崎(やぎさき)
恋愛
「ねぇ……私と、付き合って」
ある日、クラスで一番可愛い女子生徒である如月心奏に唐突に告白をされ、彼女と付き合う事になった同じクラスの平凡な高校生男子、立花蓮。
蓮は初めて出来た彼女の存在に浮かれる―――なんて事は無く、心奏から思いも寄らない頼み事をされて、それを受ける事になるのであった。
これは不器用で未熟な2人が成長をしていく物語である。彼ら彼女らの歩む物語を是非ともご覧ください。
一緒にいたい、でも近づきたくない―――臆病で内向的な少年と、偏屈で変わり者な少女との恋愛模様を描く、そんな青春物語です。
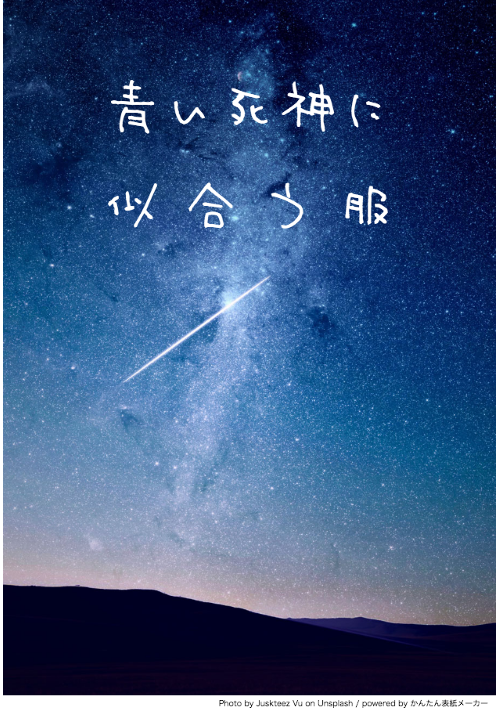
青い死神に似合う服
fig
ライト文芸
テーラー・ヨネに縫えないものはない。
どんな洋服も思いのまま。
だから、いつか必ず縫ってみせる。
愛しい、青い死神に似合う服を。
寺田ヨネは洋館を改装し仕立て屋を営んでいた。テーラー・ヨネの仕立てる服は特別製。どんな願いも叶える力を持つ。
少女のような外見ながら、その腕前は老舗のテーラーと比べても遜色ない。
アシスタントのマチとチャコ、客を紹介してくれるパイロット・ノアの協力を得ながら、ヨネは日々忙しく働いていた。
ある日、ノアの紹介でやってきたのは、若くして命を落としたバレエ・ダンサーの萌衣だった。
彼女の望みは婚約者への復讐。それを叶えるためのロマンチック・チュチュがご所望だった。
依頼の真意がわからずにいたが、次第に彼女が受けた傷、悲しみ、愛を理解していく。
そしてヨネ自身も、過去の愛と向き合うことになる。
ヨネにもかつて、愛した人がいた。遠い遠い昔のことだ。
いつか、その人のために服を縫いたいと夢を見ていた。
まだ、その夢は捨ててはいない。

月の女神と夜の女王
海獺屋ぼの
ライト文芸
北関東のとある地方都市に住む双子の姉妹の物語。
妹の月姫(ルナ)は父親が経営するコンビニでアルバイトしながら高校に通っていた。彼女は双子の姉に対する強いコンプレックスがあり、それを払拭することがどうしてもできなかった。あるとき、月姫(ルナ)はある兄妹と出会うのだが……。
姉の裏月(ヘカテー)は実家を飛び出してバンド活動に明け暮れていた。クセの強いバンドメンバー、クリスチャンの友人、退学した高校の悪友。そんな個性が強すぎる面々と絡んでいく。ある日彼女のバンド活動にも転機が訪れた……。
月姫(ルナ)と裏月(ヘカテー)の姉妹の物語が各章ごとに交錯し、ある結末へと向かう。

心の落とし物
緋色刹那
ライト文芸
・完結済み(2024/10/12)。また書きたくなったら、番外編として投稿するかも
・第4回、第5回ライト文芸大賞にて奨励賞をいただきました!!✌︎('ω'✌︎ )✌︎('ω'✌︎ )
〈本作の楽しみ方〉
本作は読む喫茶店です。順に読んでもいいし、興味を持ったタイトルや季節から読んでもオッケーです。
知らない人、知らない設定が出てきて不安になるかもしれませんが、喫茶店の常連さんのようなものなので、雰囲気を楽しんでください(一応説明↓)。
〈あらすじ〉
〈心の落とし物〉はありませんか?
どこかに失くした物、ずっと探している人、過去の後悔、忘れていた夢。
あなたは忘れているつもりでも、心があなたの代わりに探し続けているかもしれません……。
喫茶店LAMP(ランプ)の店長、添野由良(そえのゆら)は、人の未練が具現化した幻〈心の落とし物(こころのおとしもの)〉と、それを探す生き霊〈探し人(さがしびと)〉に気づきやすい体質。
ある夏の日、由良は店の前を何度も通る男性に目を止め、声をかける。男性は数年前に移転した古本屋を探していて……。
懐かしくも切ない、過去の未練に魅せられる。
〈主人公と作中用語〉
・添野由良(そえのゆら)
洋燈町にある喫茶店LAMP(ランプ)の店長。〈心の落とし物〉や〈探し人〉に気づきやすい体質。
・〈心の落とし物(こころのおとしもの)〉
人の未練が具現化した幻。あるいは、未練そのもの。
・〈探し人(さがしびと)〉
〈心の落とし物〉を探す生き霊で、落とし主。当人に代わって、〈心の落とし物〉を探している。
・〈未練溜まり(みれんだまり)〉
忘れられた〈心の落とし物〉が行き着く場所。
・〈分け御霊(わけみたま)〉
生者の後悔や未練が物に宿り、具現化した者。込められた念が強ければ強いほど、人のように自由意志を持つ。いわゆる付喪神に近い。
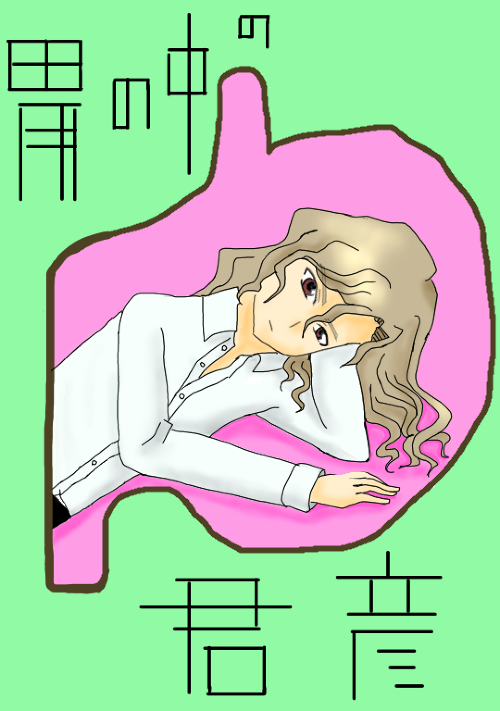
【1】胃の中の君彦【完結】
ホズミロザスケ
ライト文芸
喜志芸術大学・文芸学科一回生の神楽小路君彦は、教室に忘れた筆箱を渡されたのをきっかけに、同じ学科の同級生、佐野真綾に出会う。
ある日、人と関わることを嫌う神楽小路に、佐野は一緒に課題制作をしようと持ちかける。最初は断るも、しつこく誘ってくる佐野に折れた神楽小路は彼女と一緒に食堂のメニュー調査を始める。
佐野や同級生との交流を通じ、閉鎖的だった神楽小路の日常は少しずつ変わっていく。
「いずれ、キミに繋がる物語」シリーズ一作目。
※完結済。全三十六話。(トラブルがあり、完結後に編集し直しましたため、他サイトより話数は少なくなってますが、内容量は同じです)
※当作品は「カクヨム」「小説家になろう」にも同時掲載しております。(過去に「エブリスタ」「貸し本棚」にも掲載)

イナカマチ番犬奇譚~嫌われ獣人の恩返し~
石動なつめ
ファンタジー
――――世の中は世知辛い。
相良独楽は、異世界同士が切り取られ、繋ぎ合わされたこの世界では、忌避されている獣人だ。
独楽は獣人である事を隠しながら、連れの子ぎつねと共に、イナカマチ区画と呼ばれる場所へやって来る。
幼い頃の約束と恩返し、そして働く場所を得るためにやってきた独楽だったが、長閑そうな名前のこの場所は今、侵略を受けている真っただ中だった。
「見ず知らずの者を躊躇いなく助けたきみのお人好しっぷりに、俺は賭けた。――――イナカマチ区画から奴らを追い出したい。どうか助けて欲しい」
そう頼まれ、独楽はイナカマチ区画を守るために奮闘する。
これは一人の獣人の、恩返しの物語。
※小説家になろう、ノベルアップ+にも投稿しています。

ぼくたちのたぬきち物語
アポロ
ライト文芸
一章にエピソード①〜⑩をまとめました。大人のための童話風ライト文芸として書きましたが、小学生でも読めます。
どの章から読みはじめても大丈夫です。
挿絵はアポロの友人・絵描きのひろ生さん提供。
アポロとたぬきちの見守り隊長、いつもありがとう。
初稿はnoteにて2021年夏〜22年冬、「こたぬきたぬきち、町へゆく」のタイトルで連載していました。
この思い入れのある作品を、全編加筆修正してアルファポリスに投稿します。
🍀一章│①〜⑩のあらすじ🍀
たぬきちは、化け狸の子です。
生まれてはじめて変化の術に成功し、ちょっとおしゃれなかわいい少年にうまく化けました。やったね。
たぬきちは、人生ではじめて山から町へ行くのです。(はい、人生です)
現在行方不明の父さんたぬき・ぽんたから教えてもらった記憶を頼りに、憧れの町の「映画館」を目指します。
さて無事にたどり着けるかどうか。
旅にハプニングはつきものです。
少年たぬきちの小さな冒険を、ぜひ見守ってあげてください。
届けたいのは、ささやかな感動です。
心を込め込め書きました。
あなたにも、届け。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















