23 / 37
8話
8話「甘くないカレー」【2/3】
しおりを挟む
「ウチの場所覚えてたんだ」
「───ごめん」
「あっはは、何で謝んの?ストーカーに覚えられてるわけじゃないんだからさ」
ドア越しに聞こえる芽衣子の声は多少くぐもりながらもハッキリと聞き取ることが出来た。扉の向こうである程度声を張っているみたい。私も出来るだけドアに近づいて周りの迷惑にならない声量で話しかけていたけど、流石に腑に落ちなくて聞いてしまった。
「インターホン使わないの?」
「うん、まぁね」
「どうして?」
「だって、そうしたらさ……開けるか開けないかになっちゃうでしょ?」
ドっと何かがもたれかかるような音が扉から鳴った。間を挟んだ芽衣子との距離が近づいたことが分かって私も自然とドアに近づいていく。昨日、最後に見た時のような鋭い嫌悪感は鳴りを潜め、いつものように明るく快活な口調で話す芽衣子だけど、その言葉の端々は不自然にくらいに平坦だ。私がいつも「もっとそうであって欲しい」と思っていたほどに大人しく、彼女は扉越しのお喋りを続ける。
「それってどういう───」
「さっきごめんね、迷ってる間に彼氏が勝手に開けちゃったみたいで……挨拶もしなくて」
オートロックを開錠した男性、前から芽衣子との話で聞いていた交際中の彼の事なのだと思う。電話で連絡する関係だったこと事を考えると最近同棲を始めたのだろうか?なんて、自分との重なりにシンパシーを感じている場合でなんかないのに、こうして彼女と話しているとまるで勤務中のお店のホールの中にいるかのような、そんな気がしてきてしまいそうで……
「ホントはさ、来て欲しくなかったとかじゃない……んだけど……だけど、やっぱりもうこれ以上は本当に来ないで欲しい。店も辞めるって連絡したんだけど、三ツ矢は言ってなかったカンジ?」
「!?……そんなことは───」
「だよね、じゃあやっぱこれ以上は無理」
「どうして?……私が───」
「言わないで。言われたら、それが理由になっちゃう、から……」
不安からと焦りで高まり続けていた私の拍動はその一言で一気に静まる。胸のざわめきも、心の水面の揺れも収まって、気付けば私はドアの表面に耳を添わせる手前にまで近づいていた。紙一枚分しかない隙間、その向こうを遮る分厚い扉はまるで存在していないかのように、芽衣子の存在をその時私は肌で感じていた。
「……なんていうかさ、抵抗は無いんだよ?私も。でも、それだけじゃ駄目だからさ」
「なんで?」
「哀留はさ、昨日の私の最後の顔、覚えてる?」
動揺が堰を切ったように溢れ混乱しながら走り去る最中に向けた濁った瞳。まだ1日も経っていない出来事ではあっても、彼女のその言葉を聞いた瞬間に私は理解した。「アレ」はもう忘れられるモノじゃないという事を。
「だからさ、もしまた顔を合わせて、私が何事も無かったようしててもさ……哀留は私のあの時の顔、忘れられないでしょ?」
「それは───」
「自分とは違う世界の人なんだって思ってた。関わることも話すことも、ましてや仲良くなることなんて無い人たちで、向こうから見れば私の方が異常な人間に感じるんだろうなって……。でも違ってた。そんな人といつも意識しないくらいに近くに居て、覚えもしないくらいに何度も会って、感謝もしないくらいに助け合ってた。それでも気付かない、それくらい大差無い違いなのに……、気が付いたらもう、逃げ帰った後だった」
穏やかになりつつあった自分の心臓の鼓動にさえかき消されそうなほどに小さくなっていく芽衣子の声。扉を通して聞こえる彼女の告白、それを聞く私の内心はいつもであればここまで穏やかなままではいられなかったと思う。謝罪ではなくただ事実を伝えるだけの彼女の言葉。そこに哀れみや差別心のようなものが無いと分かるから。ただ起こってしまった事をこれ以上悪化させないために芽衣子はこのドアを開けないでいる。
「でも、なにも辞めなくたって……、シフトをずらして貰えば───」
「駄目。哀留は忘れなくちゃだめだよ。あんなヒドイ顔した奴の事なんてさ、一瞬でも思い出したら嫌な心になって、今楽しいことも全力で楽しめなくなるでしょ?」
「芽衣子」
「ごめん、色々準備もあって忙しいんだ。もう……帰って貰っても、良い?」
強引に引き上げられた芽衣子の声の端が微かに揺れる。そしてそれを聞いた私も、もうこれ以上言葉を交わすことはしたくなかった。最初から傷つけようなんて気持ちが彼女に無かった以上、もう私に芽衣子の行動をとやかく言う資格は無い。ここから先は彼女が決める事、その本意も心も自由になどできない。私はそれを身をもって知っているつもりだから。
「あ……、店長から預かってた物があるんだけど……」
「……どういう物?」
「……茶色い、粉みたいな……。『最期の一振り』って店長は言ってて───」
「──────クッふふ、そう……そっか」
その時の彼女の声は一瞬だけ明るさを取り戻したように聞こえた。まるで昨日私の家のキッチンに立っていたあの時のように。
「昨日のカレー、捨てちゃった?」
「ううん」
「じゃあそれ、お肉にまぶして焼いてみて。後は鍋で一緒に煮れば美味しくなるから」
「え?でも店長が……」
「同じ物、後で自分で取りに行くから……そう───」
そこまで言って言葉が途切れ、ドアの向こうで手を着いたような、そんな振動が伝わってきた。
「言っておく」
「……ありがと」
「じゃあ───」
「うん───」
「「お疲れ様」」
いつも通りの別れ、いつも通りの労いの言葉。いつの間にか地面についていた膝をゆっくりと引き上げる。離れていく扉との距離はそのまま彼女との距離だ。親友というほど親しかったわけじゃない、相棒というほど信頼していたわけじゃない。それでも最後まで「理解ある他人」でいてくれたかつての同僚の声が聞こえたドアに背を向けて、私は着た道をゆっくりと引き返す。振り返るような思い出も無い位に、私を嫌わないでいてくれたあの子の願いに応えるために。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
「あ……」
「ただいま……ですかね?ヘヘヘ……」
土曜日の昼下がり、店に戻った矢先に起こった事態について察しがついたらしい店長から直帰を薦められ、10日ぶりの出勤日をきわめて個人的なことに浪費して帰ってきた私の部屋に、今日は帰りを待っていてくれた人がいた。
「───大丈夫?」
榊さんはお休みの日にも関わらずYシャツにパンツスタイルという(私から見れば)かっちりした服装で心配そうな面持ちのまま出迎えてくれた。余り血色の良くない顔と額の汗から察するにとてもリラックスした休日を過ごしては居なさそうで申し訳なくなる。全て私が引き起こした面倒で、榊さんにはむしろ助けてもらってしまったのに。
「えぇ、まぁ」
「まぁって……、彼女とはどうなったの?!」
「大丈夫ですよ、ちゃんと……解決できましたから」
靴を脱ぎながら明るい口調で話そうとする私の後ろに立つ榊さんの気配、手術の結果を医者から聞き出そうとする家族と全く同じ気配だ。正直に話しても誤魔化しても疑われるのなら話したくない自分の気持ちに正直に行こうと思って当たり障りの無いように答えた。
「……本当なの?」
「彼女何時もあんな感じなんですよ、早とちりして1人で怒ってすぐにそれが冷めるっていう……瞬間湯沸かし器って言うんですかあぁいうの?今は言わないのか───」
「本当なの?!」
まぁそうだよね、自分が彼女ならこんな風な帰ってからの一言二言で納得なんてするわけがない。それがパートナーの身に関わる事ならなおさらだと。榊さんが私の事に対してこれほどまで親身になってくれている、その嬉しさで飛び回りたい気分にもなりそうだったけど、それはいけないんだ。少なくとも……今日の日が終わるまで。
「───お昼って食べました?」
「えっ?」
「いえ、まだ食べてないならもう3時近くですしご飯にしようかと思って。私的には、食べながらの方が話しやすいんですけど……」
「……まだよ」
「じゃあ、準備します!ちょっと待っててくださいね、直ぐに仕上げますから!」
返事を待たずに洗面台にまで駆け込んで手を洗い始める。指先から始めて手の平、甲、親指の周りから指と指の間を抜けて爪の内側まで入念に。仕事で慣れ親しんだ動作だったけど家ではそこまで入念にやることは無かった。洗ってもどうせ家で触るところは汚れてばかりというのもあったけど、第一にそこまで自分に厳しくする理由が無かったから。
『ちゃんと洗いなって!お客さんのご飯触るんだよ!』
脱衣所のドアを開けると榊さんはテーブルの傍でまだ立ったままだった。私が座って休んで欲しいと言ってもぼんやりとした相槌を打ってそのままだ。でもかと言って榊さんは向こうでの出来事についてもそれ以上迫ることも言及することも無いままにただ私が台所に立つのをじっと見つめていて、今の私にはそれが嬉しい。話したいことはたくさんあってもそれを言葉にする口は私にも1つだけだし、悲しい事よりも嬉しい事にこそ優先して使いたい。嫌なことをするには力がいるのだ。今は食べなきゃ、力は出ない。
『自分でも食べて味を覚えなきゃ。味が分からなきゃ見た目の違和感にも気づけないよ!』
鍋の蓋を開けて中身を確認する。ほんのり甘い香りのする薄茶色の液体の中ではジャガイモは角が無くなったぼやけたシルエットに変わり、玉ねぎはその姿自体が確認できないくらいに溶けて混ざっている。それが乗っているコンロに1日ぶりに火を入れて熱が戻ってくるのを待つ間、その隣で静かに眠っていたフライパンの上のお肉の準備も進めなくちゃいけない。火をつける前に持ち帰ってきた瓶の中を改めて見てみた。この中のフワリとした茶色の一粒一粒をまじまじと見てどういった物質なのかを解明しよう一瞬考えてはみたけど、やっぱり私には分からない。フライパンのコンロにも火をつけ、肉の焼ける音がうっすらと聞こえ始めたところで私はこの正体不明の茶色を振りかけた。瓶を1回振れば周りはあっという間に鼻を抜ける爽やかな香りで満たされて、気が付くと私はそれまでの疑心暗鬼を忘れたように何度も何度もその中身を振りかけていた。
『まかない美味しかった?……実はさ、今日のは私作ったんだよ!』
肉にも焦げ目がつき、貧弱な私の観察眼でも火が通ったと分かってそれを鍋の方に放り込む。水面はボコボコと熱気を吐き出し、中では煮溶けて小さくなった野菜が踊る。その中に落ちていく肉と野菜の大きさの差が目についてしまいそうになって、私はすぐ箱の裏面の説明書通りにコンロの火を止めて折って小さくしたルーをその中で溶かし始める。茶色が広がり、濃さが増し、とろみがつき始めた。これで完成、彼女から預かった最後の贈り物の出来上がりだ。
「良い匂い……」
「そうですね。じゃあ……食べましょう」
「そうね───あ!」
台所で鍋の中を覗き込む2人が同時に思い至ったこと、多分察しのつかない人はいないと思う。今回違うのはここからどうするべきかが分かっていることだ。
「あぁ健史郎?ごめんお釜貸して」
「───ごめん」
「あっはは、何で謝んの?ストーカーに覚えられてるわけじゃないんだからさ」
ドア越しに聞こえる芽衣子の声は多少くぐもりながらもハッキリと聞き取ることが出来た。扉の向こうである程度声を張っているみたい。私も出来るだけドアに近づいて周りの迷惑にならない声量で話しかけていたけど、流石に腑に落ちなくて聞いてしまった。
「インターホン使わないの?」
「うん、まぁね」
「どうして?」
「だって、そうしたらさ……開けるか開けないかになっちゃうでしょ?」
ドっと何かがもたれかかるような音が扉から鳴った。間を挟んだ芽衣子との距離が近づいたことが分かって私も自然とドアに近づいていく。昨日、最後に見た時のような鋭い嫌悪感は鳴りを潜め、いつものように明るく快活な口調で話す芽衣子だけど、その言葉の端々は不自然にくらいに平坦だ。私がいつも「もっとそうであって欲しい」と思っていたほどに大人しく、彼女は扉越しのお喋りを続ける。
「それってどういう───」
「さっきごめんね、迷ってる間に彼氏が勝手に開けちゃったみたいで……挨拶もしなくて」
オートロックを開錠した男性、前から芽衣子との話で聞いていた交際中の彼の事なのだと思う。電話で連絡する関係だったこと事を考えると最近同棲を始めたのだろうか?なんて、自分との重なりにシンパシーを感じている場合でなんかないのに、こうして彼女と話しているとまるで勤務中のお店のホールの中にいるかのような、そんな気がしてきてしまいそうで……
「ホントはさ、来て欲しくなかったとかじゃない……んだけど……だけど、やっぱりもうこれ以上は本当に来ないで欲しい。店も辞めるって連絡したんだけど、三ツ矢は言ってなかったカンジ?」
「!?……そんなことは───」
「だよね、じゃあやっぱこれ以上は無理」
「どうして?……私が───」
「言わないで。言われたら、それが理由になっちゃう、から……」
不安からと焦りで高まり続けていた私の拍動はその一言で一気に静まる。胸のざわめきも、心の水面の揺れも収まって、気付けば私はドアの表面に耳を添わせる手前にまで近づいていた。紙一枚分しかない隙間、その向こうを遮る分厚い扉はまるで存在していないかのように、芽衣子の存在をその時私は肌で感じていた。
「……なんていうかさ、抵抗は無いんだよ?私も。でも、それだけじゃ駄目だからさ」
「なんで?」
「哀留はさ、昨日の私の最後の顔、覚えてる?」
動揺が堰を切ったように溢れ混乱しながら走り去る最中に向けた濁った瞳。まだ1日も経っていない出来事ではあっても、彼女のその言葉を聞いた瞬間に私は理解した。「アレ」はもう忘れられるモノじゃないという事を。
「だからさ、もしまた顔を合わせて、私が何事も無かったようしててもさ……哀留は私のあの時の顔、忘れられないでしょ?」
「それは───」
「自分とは違う世界の人なんだって思ってた。関わることも話すことも、ましてや仲良くなることなんて無い人たちで、向こうから見れば私の方が異常な人間に感じるんだろうなって……。でも違ってた。そんな人といつも意識しないくらいに近くに居て、覚えもしないくらいに何度も会って、感謝もしないくらいに助け合ってた。それでも気付かない、それくらい大差無い違いなのに……、気が付いたらもう、逃げ帰った後だった」
穏やかになりつつあった自分の心臓の鼓動にさえかき消されそうなほどに小さくなっていく芽衣子の声。扉を通して聞こえる彼女の告白、それを聞く私の内心はいつもであればここまで穏やかなままではいられなかったと思う。謝罪ではなくただ事実を伝えるだけの彼女の言葉。そこに哀れみや差別心のようなものが無いと分かるから。ただ起こってしまった事をこれ以上悪化させないために芽衣子はこのドアを開けないでいる。
「でも、なにも辞めなくたって……、シフトをずらして貰えば───」
「駄目。哀留は忘れなくちゃだめだよ。あんなヒドイ顔した奴の事なんてさ、一瞬でも思い出したら嫌な心になって、今楽しいことも全力で楽しめなくなるでしょ?」
「芽衣子」
「ごめん、色々準備もあって忙しいんだ。もう……帰って貰っても、良い?」
強引に引き上げられた芽衣子の声の端が微かに揺れる。そしてそれを聞いた私も、もうこれ以上言葉を交わすことはしたくなかった。最初から傷つけようなんて気持ちが彼女に無かった以上、もう私に芽衣子の行動をとやかく言う資格は無い。ここから先は彼女が決める事、その本意も心も自由になどできない。私はそれを身をもって知っているつもりだから。
「あ……、店長から預かってた物があるんだけど……」
「……どういう物?」
「……茶色い、粉みたいな……。『最期の一振り』って店長は言ってて───」
「──────クッふふ、そう……そっか」
その時の彼女の声は一瞬だけ明るさを取り戻したように聞こえた。まるで昨日私の家のキッチンに立っていたあの時のように。
「昨日のカレー、捨てちゃった?」
「ううん」
「じゃあそれ、お肉にまぶして焼いてみて。後は鍋で一緒に煮れば美味しくなるから」
「え?でも店長が……」
「同じ物、後で自分で取りに行くから……そう───」
そこまで言って言葉が途切れ、ドアの向こうで手を着いたような、そんな振動が伝わってきた。
「言っておく」
「……ありがと」
「じゃあ───」
「うん───」
「「お疲れ様」」
いつも通りの別れ、いつも通りの労いの言葉。いつの間にか地面についていた膝をゆっくりと引き上げる。離れていく扉との距離はそのまま彼女との距離だ。親友というほど親しかったわけじゃない、相棒というほど信頼していたわけじゃない。それでも最後まで「理解ある他人」でいてくれたかつての同僚の声が聞こえたドアに背を向けて、私は着た道をゆっくりと引き返す。振り返るような思い出も無い位に、私を嫌わないでいてくれたあの子の願いに応えるために。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
「あ……」
「ただいま……ですかね?ヘヘヘ……」
土曜日の昼下がり、店に戻った矢先に起こった事態について察しがついたらしい店長から直帰を薦められ、10日ぶりの出勤日をきわめて個人的なことに浪費して帰ってきた私の部屋に、今日は帰りを待っていてくれた人がいた。
「───大丈夫?」
榊さんはお休みの日にも関わらずYシャツにパンツスタイルという(私から見れば)かっちりした服装で心配そうな面持ちのまま出迎えてくれた。余り血色の良くない顔と額の汗から察するにとてもリラックスした休日を過ごしては居なさそうで申し訳なくなる。全て私が引き起こした面倒で、榊さんにはむしろ助けてもらってしまったのに。
「えぇ、まぁ」
「まぁって……、彼女とはどうなったの?!」
「大丈夫ですよ、ちゃんと……解決できましたから」
靴を脱ぎながら明るい口調で話そうとする私の後ろに立つ榊さんの気配、手術の結果を医者から聞き出そうとする家族と全く同じ気配だ。正直に話しても誤魔化しても疑われるのなら話したくない自分の気持ちに正直に行こうと思って当たり障りの無いように答えた。
「……本当なの?」
「彼女何時もあんな感じなんですよ、早とちりして1人で怒ってすぐにそれが冷めるっていう……瞬間湯沸かし器って言うんですかあぁいうの?今は言わないのか───」
「本当なの?!」
まぁそうだよね、自分が彼女ならこんな風な帰ってからの一言二言で納得なんてするわけがない。それがパートナーの身に関わる事ならなおさらだと。榊さんが私の事に対してこれほどまで親身になってくれている、その嬉しさで飛び回りたい気分にもなりそうだったけど、それはいけないんだ。少なくとも……今日の日が終わるまで。
「───お昼って食べました?」
「えっ?」
「いえ、まだ食べてないならもう3時近くですしご飯にしようかと思って。私的には、食べながらの方が話しやすいんですけど……」
「……まだよ」
「じゃあ、準備します!ちょっと待っててくださいね、直ぐに仕上げますから!」
返事を待たずに洗面台にまで駆け込んで手を洗い始める。指先から始めて手の平、甲、親指の周りから指と指の間を抜けて爪の内側まで入念に。仕事で慣れ親しんだ動作だったけど家ではそこまで入念にやることは無かった。洗ってもどうせ家で触るところは汚れてばかりというのもあったけど、第一にそこまで自分に厳しくする理由が無かったから。
『ちゃんと洗いなって!お客さんのご飯触るんだよ!』
脱衣所のドアを開けると榊さんはテーブルの傍でまだ立ったままだった。私が座って休んで欲しいと言ってもぼんやりとした相槌を打ってそのままだ。でもかと言って榊さんは向こうでの出来事についてもそれ以上迫ることも言及することも無いままにただ私が台所に立つのをじっと見つめていて、今の私にはそれが嬉しい。話したいことはたくさんあってもそれを言葉にする口は私にも1つだけだし、悲しい事よりも嬉しい事にこそ優先して使いたい。嫌なことをするには力がいるのだ。今は食べなきゃ、力は出ない。
『自分でも食べて味を覚えなきゃ。味が分からなきゃ見た目の違和感にも気づけないよ!』
鍋の蓋を開けて中身を確認する。ほんのり甘い香りのする薄茶色の液体の中ではジャガイモは角が無くなったぼやけたシルエットに変わり、玉ねぎはその姿自体が確認できないくらいに溶けて混ざっている。それが乗っているコンロに1日ぶりに火を入れて熱が戻ってくるのを待つ間、その隣で静かに眠っていたフライパンの上のお肉の準備も進めなくちゃいけない。火をつける前に持ち帰ってきた瓶の中を改めて見てみた。この中のフワリとした茶色の一粒一粒をまじまじと見てどういった物質なのかを解明しよう一瞬考えてはみたけど、やっぱり私には分からない。フライパンのコンロにも火をつけ、肉の焼ける音がうっすらと聞こえ始めたところで私はこの正体不明の茶色を振りかけた。瓶を1回振れば周りはあっという間に鼻を抜ける爽やかな香りで満たされて、気が付くと私はそれまでの疑心暗鬼を忘れたように何度も何度もその中身を振りかけていた。
『まかない美味しかった?……実はさ、今日のは私作ったんだよ!』
肉にも焦げ目がつき、貧弱な私の観察眼でも火が通ったと分かってそれを鍋の方に放り込む。水面はボコボコと熱気を吐き出し、中では煮溶けて小さくなった野菜が踊る。その中に落ちていく肉と野菜の大きさの差が目についてしまいそうになって、私はすぐ箱の裏面の説明書通りにコンロの火を止めて折って小さくしたルーをその中で溶かし始める。茶色が広がり、濃さが増し、とろみがつき始めた。これで完成、彼女から預かった最後の贈り物の出来上がりだ。
「良い匂い……」
「そうですね。じゃあ……食べましょう」
「そうね───あ!」
台所で鍋の中を覗き込む2人が同時に思い至ったこと、多分察しのつかない人はいないと思う。今回違うのはここからどうするべきかが分かっていることだ。
「あぁ健史郎?ごめんお釜貸して」
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。
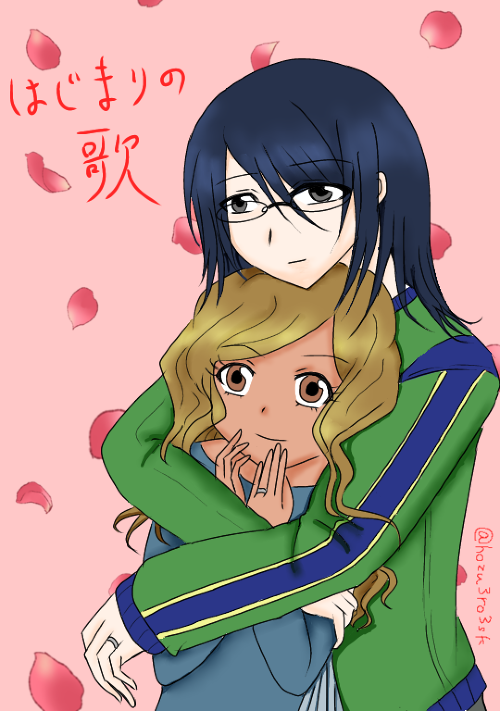
【10】はじまりの歌【完結】
ホズミロザスケ
ライト文芸
前作『【9】やりなおしの歌』の後日譚。
11月最後の大安の日。無事に婚姻届を提出した金田太介(カネダ タイスケ)と歌(ララ)。
晴れて夫婦になった二人の一日を軸に、太介はこれまでの人生を振り返っていく。
「いずれ、キミに繋がる物語」シリーズ10作目。(登場する人物が共通しています)。単品でも問題なく読んでいただけます。
※当作品は「カクヨム」「小説家になろう」にも同時掲載しております。


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく


坂の上の本屋
ihcikuYoK
ライト文芸
カクヨムのお題企画参加用に書いたものです。
短話連作ぽくなったのでまとめました。
♯KAC20231 タグ、お題「本屋」
坂の上の本屋には父がいる ⇒ 本屋になった父親と娘の話です。
♯KAC20232 タグ、お題「ぬいぐるみ」
坂の上の本屋にはバイトがいる ⇒ 本屋のバイトが知人親子とクリスマスに関わる話です。
♯KAC20233 タグ、お題「ぐちゃぐちゃ」
坂の上の本屋には常連客がいる ⇒ 本屋の常連客が、クラスメイトとその友人たちと本屋に行く話です。
♯KAC20234 タグ、お題「深夜の散歩で起きた出来事」
坂の上の本屋のバイトには友人がいる ⇒ 本屋のバイトとその友人が、サークル仲間とブラブラする話です。
♯KAC20235 タグ、お題「筋肉」
坂の上の本屋の常連客には友人がいる ⇒ 本屋の常連客とその友人があれこれ話している話です。
♯KAC20236 タグ、お題「アンラッキー7」
坂の上の本屋の娘は三軒隣にいる ⇒ 本屋の娘とその家族の話です。
♯KAC20237 タグ、お題「いいわけ」
坂の上の本屋の元妻は三軒隣にいる ⇒ 本屋の主人と元妻の話です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















