お気に入りに追加
206
あなたにおすすめの小説

忍者同心 服部文蔵
大澤伝兵衛
歴史・時代
八代将軍徳川吉宗の時代、服部文蔵という武士がいた。
服部という名ではあるが有名な服部半蔵の血筋とは一切関係が無く、本人も忍者ではない。だが、とある事件での活躍で有名になり、江戸中から忍者と話題になり、評判を聞きつけた町奉行から同心として採用される事になる。
忍者同心の誕生である。
だが、忍者ではない文蔵が忍者と呼ばれる事を、伊賀、甲賀忍者の末裔たちが面白く思わず、事あるごとに文蔵に喧嘩を仕掛けて来る事に。
それに、江戸を騒がす数々の事件が起き、どうやら文蔵の過去と関りが……

葉桜よ、もう一度 【完結】
五月雨輝
歴史・時代
【第9回歴史・時代小説大賞特別賞受賞作】北の小藩の青年藩士、黒須新九郎は、女中のりよに密かに心を惹かれながら、真面目に職務をこなす日々を送っていた。だが、ある日突然、新九郎は藩の産物を横領して抜け売りしたとの無実の嫌疑をかけられ、切腹寸前にまで追い込まれてしまう。新九郎は自らの嫌疑を晴らすべく奔走するが、それは藩を大きく揺るがす巨大な陰謀と哀しい恋の始まりであった。
謀略と裏切り、友情と恋情が交錯し、武士の道と人の想いの狭間で新九郎は疾走する。

アブナイお殿様-月野家江戸屋敷騒動顛末-(R15版)
三矢由巳
歴史・時代
時は江戸、老中水野忠邦が失脚した頃のこと。
佳穂(かほ)は江戸の望月藩月野家上屋敷の奥方様に仕える中臈。
幼い頃に会った千代という少女に憧れ、奥での一生奉公を望んでいた。
ところが、若殿様が急死し事態は一変、分家から養子に入った慶温(よしはる)こと又四郎に侍ることに。
又四郎はずっと前にも会ったことがあると言うが、佳穂には心当たりがない。
海外の事情や英吉利語を教える又四郎に翻弄されるも、惹かれていく佳穂。
一方、二人の周辺では次々に不可解な事件が起きる。
事件の真相を追うのは又四郎や屋敷の人々、そしてスタンダードプードルのシロ。
果たして、佳穂は又四郎と結ばれるのか。
シロの鼻が真実を追い詰める!
別サイトで発表した作品のR15版です。

深川あやかし屋敷奇譚
笹目いく子
歴史・時代
第8回歴史·時代小説大賞特別賞受賞。コメディタッチのお江戸あやかしミステリー。連作短篇です。
大店の次男坊・仙一郎は怪異に目がない変人で、深川の屋敷にいわく因縁つきの「がらくた」を収集している。呪いも祟りも信じない女中のお凛は、仙一郎の酔狂にあきれながらも、あやしげな品々の謎の解明に今日も付き合わされ……。

徳川家基、不本意!
克全
歴史・時代
幻の11代将軍、徳川家基が生き残っていたらどのような世の中になっていたのか?田沼意次に取立てられて、徳川家基の住む西之丸御納戸役となっていた長谷川平蔵が、田沼意次ではなく徳川家基に取り入って出世しようとしていたらどうなっていたのか?徳川家治が、次々と死んでいく自分の子供の死因に疑念を持っていたらどうなっていたのか、そのような事を考えて創作してみました。
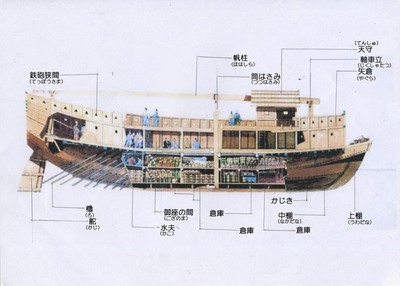

写楽、一両年にて止ム
坂本 光陽
歴史・時代
江戸の版元,蔦屋は絵師志望の男と出会う。彼は素人だったが、粗削りな才能を秘めていた。世間をあっと言わせるために、蔦屋は彼を鍛えに鍛える。その結果、彼らの手掛けた浮世絵は目論見通り、世間をあっと言わせたのだが……。これは永遠の謎とされている東洲斎写楽を巡る物語であり、創作に関わる者が全員抱えている葛藤の物語。

桜花 ~いまも記憶に舞い散るは、かくも愛しき薄紅の君~
碧
歴史・時代
軽やかに、華やかに、ひらひら舞い遊ぶ桜の花びら。鮮やかに目を奪って、手を伸ばしても指先をそっと掠めて掴めない。「あの桜の樹の下にはね、死体が埋まっているのよ」いまも脳裏に焼き付いて離れないあの娘はまるで薄紅の桜のようだった_______。弥生はかつて火事に見舞われた。現在は小間物屋「生駒屋」で女中として穏やかに暮らしながらも過去に囚われた少女とそんな彼女を取り巻く人々。不器用に拙く、それでも人は生きていく。記憶を呼び起こす桜が紡ぐ過去といま。儚く優しい江戸物語。◇◇毎日更新・土曜は二回更新有り◇◇
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















