17 / 58
危険なヒーロー②
しおりを挟む
「…さすがに飲みすぎじゃないですか?」
「そんなことないっ」
「そうかなぁ」
飲み会が始まってから、どれくらいの時間が経っただろうか。
気が付けば柳瀬さんは「おかわり」を繰り返していて、だいぶ酔っぱらったように感じていた。
室内のあかりがそんなに明るくないからか、顔が赤いとかはよくわからないけれど、さすがに少し心配になるほどだった。
だって…今のビールで一体何杯目なんだろう。
そしてまた気が付けば時刻は22時を過ぎていて、あと1時間で最終バスが来るような時間帯になっていた。
そろそろ帰んなきゃな…なんてあたしがそう思っていると、だいぶ酔っぱらった柳瀬さんが言う。
「鏡子ちゃん~ちょっとコッチ来て」
「?」
「こっちこっち。もっと近く」
「え、何ですか」
そう言われ、まともに入っていない力で腕を引っ張られる。
そして柳瀬さんはあたしを自身のすぐ隣に座らせると、あたしの頭を優しく抱き寄せて言った。
「俺ね、今日…鏡子ちゃんを誘ったのは、鏡子ちゃんに言いたいことがあったからなの」
「…言いたいこと?って、何ですか?て、てか…近いです」
だけど同時に少しだけ違和感を覚える。
あれ?いっぱい飲んでるはずなのに…柳瀬さんお酒臭くない…。
あたしがそう思って首をかしげていると、柳瀬さんが言葉を続けて言った。
「鏡子ちゃんには俺がいるよ。鏡子ちゃんに何があっても、俺が鏡子ちゃん守るから」
「!」
「だから遠慮とか全然、しないでいいから。鏡子ちゃんが笑ってると俺も嬉しいんだよ」
そこまで言って、頭を優しく抱き寄せたまま、あたしの顔を覗き込む柳瀬さん。
その瞬間物凄く顔が近くなって、目が合ったから…赤くなった顔を隠さなきゃって思ったけど、
それを許さない柳瀬さんが、「逃げないで」って甘く囁いた。
「う…あ、あの、近い、です。柳瀬さん」
「いや?」
「嫌とかじゃ、なくって」
「照れてんの?かわいい、」
「!」
そう言って、抱き寄せたままの手で、優しく頭を撫でられる。
だけどあたしはその状態のまま、どうしても気になって柳瀬さんに言った。
「あの…どうして、ですか?」
「?」
「柳瀬さんは、どうしてそんなにあたしのこと、大事にしてるみたいに、言ってくれるんですか?」
「どうして、って」
「だって、他に可愛いコなんていっぱいいるし、別にあたしじゃなくてもいいはずですよね。
それに、あたしが相手なんて…柳瀬さんにとって何の得もないっていうか」
「…」
あたしは勇気を出してそう言うと、でも柳瀬さんの方を見れなくて、うつ向いたまま。
でも実は本気で遊ばれていたらどうしよう…なんて、そんな不安を過らせていたら。
「…得かどうかなんて、そんなの大事かな?」
「?」
「あなたが時々寂しそうな顔をするたび、俺はあなたを守りたいって思った。ただそれだけなんだよ」
柳瀬さんはそう言うと、かけていた黒縁めがねを外す。
その行動にあたしがふと顔をあげると…
「…!!」
その瞬間、突如優しく唇が重なって、あたしは柳瀬さんにキスされた。
それがキスだとわかるまでに時間はかからなくて、だけど気づいてもあまりの心地よさにあたしも抵抗をしなかった。
…でも。
「鳥のから揚げおっ…!」
「!?…っ、」
次の瞬間、突然ガラ、と個室の引き戸が開いて…
キスしたままのこの光景を、店員さんに見られてしまった。
「っ、し、失礼しました…!」
ヤバい、と思って離れようとしても、柳瀬さんが離してくれなくて、時すでに遅し。
まさかの光景にビックリした店員さんは、再びドアを閉めてその場を後にしてしまう。
「んんっ…」
…柳瀬さんの気持ちをずっと疑っていたけど、でもそのキスで何だか柳瀬さんの気持ちが苦しいくらいに伝わってくるようで、あたしは思わず更に顔を真っ赤にしてしまう。
ようやく離れたときには柳瀬さんの顔なんて見れるはずもなくて、少し乱れた息を整えながら、「何で」と呟くことしかできなかった。
何で柳瀬さん、あたしなんかを…広喜くんにも、あんなキス、いや広喜くんどころか誰にもあんなキスはされたことがなかった。
柳瀬さんは照れたりしないのかな。恥ずかしがるあたしを面白がって顔を覗き込んでくるから、恥ずかしくてしかたない。
「顔真っ赤、」
「だ、だってあんな風にされたらっ…ってか店員さんに見られたじゃないですか!」
「ん、でも気持ちは伝わったでしょ?」
「…、」
…それは…物凄く伝わりましたけど。そう言いかけて、だけどその言葉を飲み込んだ。
だって柳瀬さん、酔っぱらってるからやったに違いないし。
あたしはそう思うと、そういえば、と時間のことを思い出して、言った。
「ってか、柳瀬さん、もう22時過ぎてますよ!」
「…あ、そだね。でも、」
「あたしの最終バスが出るまであと1時間もないし…あ!今日の支払いはあたしがするんで!任せて下さい」
「…」
あたしはそう言うと、帰る支度をする。
でもその向かいで、全然動かない柳瀬さん。
そんな柳瀬さんに「行きますよ」と言おうとしたら、その前に柳瀬さんが言った。
「いやごめん俺ちょっと無理」
「え、」
「歩けない」
******
「ほら、もうちょっとですよ」
「んー…」
あれから、あたしが支払うといったのに酔っぱらった柳瀬さんには通じなくて、結局あたしがまた奢ってもらってしまった。
だけどそこまではいいものの、泥酔状態の柳瀬さんは自力で家に帰れるような状態でもなさそうで、奢ってもらったお礼にあたしが家に送り届けることにした。
家の場所も、部屋の番号もまだ覚えてるし。
あたしが柳瀬さんの腰に腕を回して、柳瀬さんがあたしの肩に腕を回してなんとか歩くこと数十分。
普通に歩けばほんの数分で到着するはずの家にやっと到着して、あたしは柳瀬さんに言った。
「鍵、出してください。ほらもう部屋が目の前ですよ」
「んえ?…どこだっけ、」
そして、スーツのポケットを探った柳瀬さんがやっと家の鍵を探し出して、あたしが代わりに玄関のドアの鍵を開けた。
「ほら、着きましたよ」
「ん、ありがとー」
「…、」
じゃ、あたしは帰ろうかな。
しかし、そう思っていた矢先、あたしが帰ろうとしたら、その目の前で柳瀬さんがそのまま玄関で寝転がってしまう。
「え?あっ…柳瀬さん!」
まだここ玄関ですよ!と。言っても彼は「いーのいーの」とそのまま寝てしまう。
あたしはそんな柳瀬さんを前にこのまま帰るのはやっぱり気が引けて、寝室まで送ることにした。
だって、この前のあたしも、こんな感じだっただろうし。
「柳瀬さん、電気どれですか?暗い…」
「ん、テキトーでいいよ」
「テキトーって、…あ、これかな」
そう言って、暗闇で何とか廊下の電気を探し当てる。
これで少しはマシになった。そう思いながら何気なくスマホの時計を見ると、時刻は最終バス20分前。
そう考える横で、柳瀬さんも自身のスマホで時刻を確認していることに、あたしは気づかない…。
「そんなことないっ」
「そうかなぁ」
飲み会が始まってから、どれくらいの時間が経っただろうか。
気が付けば柳瀬さんは「おかわり」を繰り返していて、だいぶ酔っぱらったように感じていた。
室内のあかりがそんなに明るくないからか、顔が赤いとかはよくわからないけれど、さすがに少し心配になるほどだった。
だって…今のビールで一体何杯目なんだろう。
そしてまた気が付けば時刻は22時を過ぎていて、あと1時間で最終バスが来るような時間帯になっていた。
そろそろ帰んなきゃな…なんてあたしがそう思っていると、だいぶ酔っぱらった柳瀬さんが言う。
「鏡子ちゃん~ちょっとコッチ来て」
「?」
「こっちこっち。もっと近く」
「え、何ですか」
そう言われ、まともに入っていない力で腕を引っ張られる。
そして柳瀬さんはあたしを自身のすぐ隣に座らせると、あたしの頭を優しく抱き寄せて言った。
「俺ね、今日…鏡子ちゃんを誘ったのは、鏡子ちゃんに言いたいことがあったからなの」
「…言いたいこと?って、何ですか?て、てか…近いです」
だけど同時に少しだけ違和感を覚える。
あれ?いっぱい飲んでるはずなのに…柳瀬さんお酒臭くない…。
あたしがそう思って首をかしげていると、柳瀬さんが言葉を続けて言った。
「鏡子ちゃんには俺がいるよ。鏡子ちゃんに何があっても、俺が鏡子ちゃん守るから」
「!」
「だから遠慮とか全然、しないでいいから。鏡子ちゃんが笑ってると俺も嬉しいんだよ」
そこまで言って、頭を優しく抱き寄せたまま、あたしの顔を覗き込む柳瀬さん。
その瞬間物凄く顔が近くなって、目が合ったから…赤くなった顔を隠さなきゃって思ったけど、
それを許さない柳瀬さんが、「逃げないで」って甘く囁いた。
「う…あ、あの、近い、です。柳瀬さん」
「いや?」
「嫌とかじゃ、なくって」
「照れてんの?かわいい、」
「!」
そう言って、抱き寄せたままの手で、優しく頭を撫でられる。
だけどあたしはその状態のまま、どうしても気になって柳瀬さんに言った。
「あの…どうして、ですか?」
「?」
「柳瀬さんは、どうしてそんなにあたしのこと、大事にしてるみたいに、言ってくれるんですか?」
「どうして、って」
「だって、他に可愛いコなんていっぱいいるし、別にあたしじゃなくてもいいはずですよね。
それに、あたしが相手なんて…柳瀬さんにとって何の得もないっていうか」
「…」
あたしは勇気を出してそう言うと、でも柳瀬さんの方を見れなくて、うつ向いたまま。
でも実は本気で遊ばれていたらどうしよう…なんて、そんな不安を過らせていたら。
「…得かどうかなんて、そんなの大事かな?」
「?」
「あなたが時々寂しそうな顔をするたび、俺はあなたを守りたいって思った。ただそれだけなんだよ」
柳瀬さんはそう言うと、かけていた黒縁めがねを外す。
その行動にあたしがふと顔をあげると…
「…!!」
その瞬間、突如優しく唇が重なって、あたしは柳瀬さんにキスされた。
それがキスだとわかるまでに時間はかからなくて、だけど気づいてもあまりの心地よさにあたしも抵抗をしなかった。
…でも。
「鳥のから揚げおっ…!」
「!?…っ、」
次の瞬間、突然ガラ、と個室の引き戸が開いて…
キスしたままのこの光景を、店員さんに見られてしまった。
「っ、し、失礼しました…!」
ヤバい、と思って離れようとしても、柳瀬さんが離してくれなくて、時すでに遅し。
まさかの光景にビックリした店員さんは、再びドアを閉めてその場を後にしてしまう。
「んんっ…」
…柳瀬さんの気持ちをずっと疑っていたけど、でもそのキスで何だか柳瀬さんの気持ちが苦しいくらいに伝わってくるようで、あたしは思わず更に顔を真っ赤にしてしまう。
ようやく離れたときには柳瀬さんの顔なんて見れるはずもなくて、少し乱れた息を整えながら、「何で」と呟くことしかできなかった。
何で柳瀬さん、あたしなんかを…広喜くんにも、あんなキス、いや広喜くんどころか誰にもあんなキスはされたことがなかった。
柳瀬さんは照れたりしないのかな。恥ずかしがるあたしを面白がって顔を覗き込んでくるから、恥ずかしくてしかたない。
「顔真っ赤、」
「だ、だってあんな風にされたらっ…ってか店員さんに見られたじゃないですか!」
「ん、でも気持ちは伝わったでしょ?」
「…、」
…それは…物凄く伝わりましたけど。そう言いかけて、だけどその言葉を飲み込んだ。
だって柳瀬さん、酔っぱらってるからやったに違いないし。
あたしはそう思うと、そういえば、と時間のことを思い出して、言った。
「ってか、柳瀬さん、もう22時過ぎてますよ!」
「…あ、そだね。でも、」
「あたしの最終バスが出るまであと1時間もないし…あ!今日の支払いはあたしがするんで!任せて下さい」
「…」
あたしはそう言うと、帰る支度をする。
でもその向かいで、全然動かない柳瀬さん。
そんな柳瀬さんに「行きますよ」と言おうとしたら、その前に柳瀬さんが言った。
「いやごめん俺ちょっと無理」
「え、」
「歩けない」
******
「ほら、もうちょっとですよ」
「んー…」
あれから、あたしが支払うといったのに酔っぱらった柳瀬さんには通じなくて、結局あたしがまた奢ってもらってしまった。
だけどそこまではいいものの、泥酔状態の柳瀬さんは自力で家に帰れるような状態でもなさそうで、奢ってもらったお礼にあたしが家に送り届けることにした。
家の場所も、部屋の番号もまだ覚えてるし。
あたしが柳瀬さんの腰に腕を回して、柳瀬さんがあたしの肩に腕を回してなんとか歩くこと数十分。
普通に歩けばほんの数分で到着するはずの家にやっと到着して、あたしは柳瀬さんに言った。
「鍵、出してください。ほらもう部屋が目の前ですよ」
「んえ?…どこだっけ、」
そして、スーツのポケットを探った柳瀬さんがやっと家の鍵を探し出して、あたしが代わりに玄関のドアの鍵を開けた。
「ほら、着きましたよ」
「ん、ありがとー」
「…、」
じゃ、あたしは帰ろうかな。
しかし、そう思っていた矢先、あたしが帰ろうとしたら、その目の前で柳瀬さんがそのまま玄関で寝転がってしまう。
「え?あっ…柳瀬さん!」
まだここ玄関ですよ!と。言っても彼は「いーのいーの」とそのまま寝てしまう。
あたしはそんな柳瀬さんを前にこのまま帰るのはやっぱり気が引けて、寝室まで送ることにした。
だって、この前のあたしも、こんな感じだっただろうし。
「柳瀬さん、電気どれですか?暗い…」
「ん、テキトーでいいよ」
「テキトーって、…あ、これかな」
そう言って、暗闇で何とか廊下の電気を探し当てる。
これで少しはマシになった。そう思いながら何気なくスマホの時計を見ると、時刻は最終バス20分前。
そう考える横で、柳瀬さんも自身のスマホで時刻を確認していることに、あたしは気づかない…。
0
お気に入りに追加
28
あなたにおすすめの小説


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

捨てる旦那あれば拾うホテル王あり~身籠もったら幸せが待っていました~
霧内杳/眼鏡のさきっぽ
恋愛
「僕は絶対に、君をものにしてみせる」
挙式と新婚旅行を兼ねて訪れたハワイ。
まさか、その地に降り立った途端、
「オレ、この人と結婚するから!」
と心変わりした旦那から捨てられるとは思わない。
ホテルも追い出されビーチで途方に暮れていたら、
親切な日本人男性が声をかけてくれた。
彼は私の事情を聞き、
私のハワイでの思い出を最高のものに変えてくれた。
最後の夜。
別れた彼との思い出はここに置いていきたくて彼に抱いてもらった。
日本に帰って心機一転、やっていくんだと思ったんだけど……。
ハワイの彼の子を身籠もりました。
初見李依(27)
寝具メーカー事務
頑張り屋の努力家
人に頼らず自分だけでなんとかしようとする癖がある
自分より人の幸せを願うような人
×
和家悠将(36)
ハイシェラントホテルグループ オーナー
押しが強くて俺様というより帝王
しかし気遣い上手で相手のことをよく考える
狙った獲物は逃がさない、ヤンデレ気味
身籠もったから愛されるのは、ありですか……?
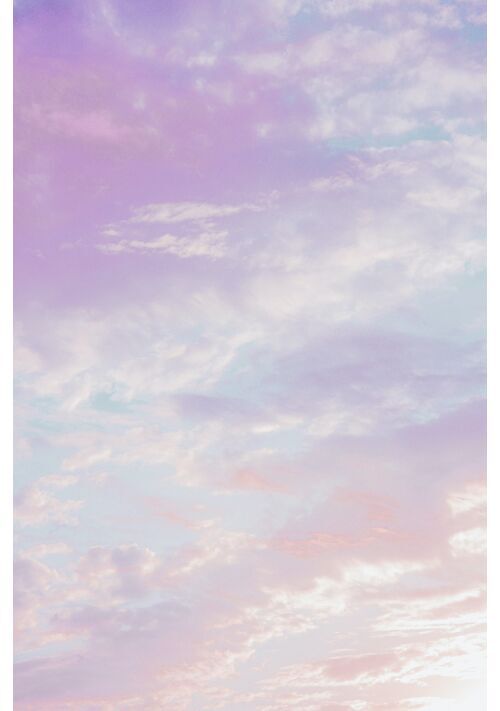
極道に大切に飼われた、お姫様
真木
恋愛
珈涼は父の組のため、生粋の極道、月岡に大切に飼われるようにして暮らすことになる。憧れていた月岡に甲斐甲斐しく世話を焼かれるのも、教え込まれるように夜ごと結ばれるのも、珈涼はただ恐ろしくて殻にこもっていく。繊細で怖がりな少女と、愛情の伝え方が下手な極道の、すれ違いラブストーリー。

FLORAL-敏腕社長が可愛がるのは路地裏の花屋の店主-
さとう涼
恋愛
恋愛を封印し、花屋の店主として一心不乱に仕事に打ち込んでいた咲都。そんなある日、ひとりの男性(社長)が花を買いにくる──。出会いは偶然。だけど咲都を気に入った彼はなにかにつけて咲都と接点を持とうとしてくる。
「お昼ごはんを一緒に食べてくれるだけでいいんだよ。なにも難しいことなんてないだろう?」
「でも……」
「もしつき合ってくれたら、今回の仕事を長期プランに変更してあげるよ」
「はい?」
「とりあえず一年契約でどう?」
穏やかでやさしそうな雰囲気なのに意外に策士。最初は身分差にとまどっていた咲都だが、気づいたらすっかり彼のペースに巻き込まれていた。
☆第14回恋愛小説大賞で奨励賞を頂きました。ありがとうございました。

公爵閣下の契約妻
秋津冴
恋愛
呪文を唱えるよりも、魔法の力を封じ込めた『魔石』を活用することが多くなった、そんな時代。
伯爵家の次女、オフィーリナは十六歳の誕生日、いきなり親によって婚約相手を決められてしまう。
実家を継ぐのは姉だからと生涯独身を考えていたオフィーリナにとっては、寝耳に水の大事件だった。
しかし、オフィーリナには結婚よりもやりたいことがあった。
オフィーリナには魔石を加工する才能があり、幼い頃に高名な職人に弟子入りした彼女は、自分の工房を開店する許可が下りたところだったのだ。
「公爵様、大変失礼ですが……」
「側室に入ってくれたら、資金援助は惜しまないよ?」
「しかし、結婚は考えられない」
「じゃあ、契約結婚にしよう。俺も正妻がうるさいから。この婚約も公爵家と伯爵家の同士の契約のようなものだし」
なんと、婚約者になったダミアノ公爵ブライトは、国内でも指折りの富豪だったのだ。
彼はオフィーリナのやりたいことが工房の経営なら、資金援助は惜しまないという。
「結婚……資金援助!? まじで? でも、正妻……」
「うまくやる自信がない?」
「ある女性なんてそうそういないと思います……」
そうなのだ。
愛人のようなものになるのに、本妻に気に入られることがどれだけ難しいことか。
二の足を踏むオフィーリナにブライトは「まあ、任せろ。どうにかする」と言い残して、契約結婚は成立してしまう。
平日は魔石を加工する、魔石彫金師として。
週末は契約妻として。
オフィーリナは週末の二日間だけ、工房兼自宅に彼を迎え入れることになる。
他の投稿サイトでも掲載しています。

今、夫と私の浮気相手の二人に侵されている
ヘロディア
恋愛
浮気がバレた主人公。
夫の提案で、主人公、夫、浮気相手の三人で面会することとなる。
そこで主人公は男同士の自分の取り合いを目の当たりにし、最後に男たちが選んだのは、先に主人公を絶頂に導いたものの勝ち、という道だった。
主人公は絶望的な状況で喘ぎ始め…

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















