12 / 59
三章 記憶と人間の街
街
しおりを挟む
「「……え?」」
「異能の持ち主はとっくに死んでいるが……「停滞」の異能が効いてるから、この街はずっと在り続けてるんだ」
リールは淡々と話す。
「「停滞」の異能の持ち主は自分が死んだ後もこの街が続くようにと異能の効果時間そのものさえ異能でいじってしまってる。……「停滞」を詳しく言うと、同じ時間を繰り返す──ループのようなものだ。つまり、この街──異能にこの異能を使えば、効果時間が永久に近くなるってことだ」
「じ、じゃあこの街の霧を晴らすことは無理ってこと?」
「………」
「なんとか言ってよ、リール」
ユーイオがそう言うと、リールは部屋の奥へと歩き出す。わけもわからないままついて行くと、部屋の最奥に薄紫色の石がショーケースに入れられていた。
「「停滞」の力が込められた石だ。ケース自体にも「停滞」の力が巡らされていて、簡単に壊せないようになってる。最下層から最上層までの各層に似たようなものがあるはずだ」
「……リール、「停滞」って異能を使ったものや相手の中で流れる時間を繰り返させる力、なんだよね」
「? ああ」
ユーイオは閃いてしまった。そんな永久の力を打ち破れる力があることに気付いてしまったのだ。
「ショーケースは触っても問題ないよね」
「ああ」
──時間の流れを意識して、そこに巡る命を手繰り寄せる。
「………『君の役目はもうとっくに終わってる。もう休もう』」
「「!」」
ユーイオがショーケースに手をかざしてそう言うと、ショーケースは粉々に割れてしまった。今ならこの薄紫の「魔法」は無防備に晒されている。
「あっ」
しかし、そう簡単に「停滞」の力が破られるわけにはいかない。薄紫の石から滲み出た「停滞」の力が再びショーケースになって薄紫の石を守るように佇んだ。
「まぁ……一発で上手くいかれても困るからな」
「えっユーイオ今の何!? パパ感激なんだけど!!」
「お前の異能は恐ろしいな……ユーイオ」
異形ふたりに関心を向けられたユーイオは少し照れ臭そうにしてから話す。
「これも「輪廻」の力。僕の異能は簡単に言うと生きてるものは死なせ、死んでるものは生かす力だから」
勿論、それ以外にも使いようはあるのだが。「輪廻」は循環させるもの、つまり応用すれば状態を逆転させることだって容易い。
「取り敢えず出来なくはないってことがわかっただけでも嬉しいよ」
ユーイオは満足していた。自分は何も出来ない無力な子供じゃない。それが実感出来て安心したのだ。
「ユーイオ……」
「あっはは、リーエイ酷い顔」
文字盤の顔は、ユーイオには歪んで見えていた。リーエイが不安でいっぱいになっている証だ。
「大丈夫だって、僕は死なない。何回でもやり直せるんだから」
「………そう、だね」
リーエイが不安でたくさんだったのは、ユーイオが死ぬかもしれないからとか、そんな理由ではない。霧の街の霧が晴れた後、異形が生きられなかった時にユーイオを置いて死んでしまうことになる。その時にユーイオがユーイオとして生きているかは別として、ユーイオの命を持った人を置いていくのがひどく辛い。
「さ、「停滞」の石はもう見せたから次はいつから、誰がそうしたかだ」
石から少し離れた場所にあるのは石碑のようなものだった。
「これは?」
「読めるなら読んでみたらいい」
──同じ人間から蔑まれ疎まれついには存在しないモノ扱いをされた。私の何がそんなに彼らを怒らせることになったかは分からないが、どうせ生きたとしても誰も関わってくれないのならこんな気持ちも存在も隠してしまえばいい。
「隠す……存在を?」
「ああ、これは霧の街の異能の主の一言だ」
「待ってよリール、隠すってどういうこと?」
リーエイが訊くと、リールは少し間をあけて話し始める。
「この街は世界から不要とされたものが集まる場所ってのは知ってるだろ。ただ、集められただけじゃ世界も困るんだ。どうしたか。初めて世界に不要とされたヒトは不要物を隠そうとした。隠せば無かったことにできる。無かったことにできるなら不要とされたものは初めからいなかったことにもできる」
「………」
「それがこの街──「秘匿」の異能だ」
「秘匿」に「停滞」がかけられたことによってこの街は何百何千もの年月を過ごしているという。それだけ「停滞」の力が強いということだ。
「世界から不要とされた理由はもちろん人様々だ。俺たちなら、戦争という不毛で悲惨なことはもう必要ないから。メアルたちなら数百年前のその願い──「もっと医療が発展していれば」なんてたらればはとっくに叶っているから。じゃあこの街で生まれたユーイオ、君みたいな子供たちはどうか。君みたいな人は不要物の末裔だから、必要かどうかの概念がまずない」
「?」
ユーイオがよくわからないと言わんばかりに首を傾げると、リーエイがつまり、と付け足す。
「不要物から生まれた子だから、世界に要るかどうか聞くまでもない……残酷だけど、でも、この異能はそういうことなんだよ」
「僕が………生まれた時点で世界そのものから必要とされていない……?」
ユーイオの目からすっと光が消えたのをリーエイは見逃さなかった。焦りながらもリーエイはフォローを入れる。
「せ、せせせ世界にはね! 俺たちは死ぬまでユーイオ必要だからね! ね!! リール!」
「ああ」
リールはリーエイと違って冷静に頷いた。
「そもそも俺にとってはこの異能自体存在することに意味が無いと思ってる」
「というと?」
リールは言った。
「本当に必要がないなら必要が無いものを集める場所もまた必要が無いだろう」
「──霧の街が世界から不要とされたものが集まる場所って知った時、僕はなんだかすごく安心したんだよ」
百四十六センチ、その小柄な背にはあまりにも似合わない、背の高すぎる玉座に座る少年は言った。「吸収」で能力を吸っても外見は完全にコピーしきれなかった。身長と顔つきと声。それらはどうやっても変えられないままだった。
「病気で……結核で身動きもろくに出来ずに、周りに迷惑をかけて生きることしか出来なかった僕は、やっぱり必要なかったんだって突きつけられて安心したんだ。変だと思う?」
「…………いいえ」
最上層。ふたりだけの空間。最上層者とその従者シルフィは時々こうやって、何もすることがない時に会話をする。その会話は大抵最上層者からの一方的なものなのだが。
「ですが一言だけ申し上げたいことが」
「?」
「少なくとも今の主様は私にとって必要不可欠ですので不要な存在ではありません」
「………」
従者の少女は物怖じすることなくきっぱりと言った。最上層者にはそれが珍しく思えて、しばらく黙って彼女を見たあと、
「っはははは!! シルフィもたまにはいいこと言うね」
と、高らかに笑った。
「………姉さん」
だが、数秒してすぐにその顔から笑顔は消えた。
「姉さんは、僕が結核を患っても態度を変えなかった。誰よりも僕に寄り添ってくれていた……と思う。正直、母さんは父さんを亡くしてから少し様子が変なことがあったから」
「……」
シルフィはそれを黙って聞く。今は主のターンだと理解しているからだ。
「姉さんさえ生きていれば、僕がここに来ることもなかったのかもしれない」
「……主様」
「ま、こんなたらればなんて言い出したらキリがない。僕が病気にならなかったら、父さんと姉さんが生きていれば、戦争なんてなかったら。僕は家という箱庭に閉じ込められた人生を送っただけだったけど、それでも外から伝わる音でこの世がどう動いてるのか、ちょっとはわかってたんだ」
戦争が起きたこと。今回も短期決戦でと踏み込んだその戦いは長期に渡り、物資が枯渇し、それでもラジオからの音声はひたすらに「我が国は勝っている」みたいなふざけたことしか言わなかったこと。物資が枯渇したのがどうしてわかったかって? ──簡単だよ。物を得るのにお金を使わなくなって、その代わりに切符を使い始めたのを母さんの手元から見て訊いたんだ。「それは何? お金じゃないよね?」って。
今の祖国がどうなっているのかは知らない、いや、知るつもりもない。きっと知ったところで僕は国の最新の状態を理解できない。
「僕が最上層に居るのも、全部姉さんの為。姉さんに会える可能性が一番高いのは……ううん、あらゆる可能性の幅を広げられるのは、一番偉い奴だろ?」
シルフィは小さく頷く。
「僕は姉さんに会えたら死んでもいい。もうこの世に生まれ変われなくてもいい」
だが、少年は知らなかった。死んだからと言って世界から不要とみなされたわけではないこと。つまり、ここが死後の世界と似たようなものではないということを。
「異能の持ち主はとっくに死んでいるが……「停滞」の異能が効いてるから、この街はずっと在り続けてるんだ」
リールは淡々と話す。
「「停滞」の異能の持ち主は自分が死んだ後もこの街が続くようにと異能の効果時間そのものさえ異能でいじってしまってる。……「停滞」を詳しく言うと、同じ時間を繰り返す──ループのようなものだ。つまり、この街──異能にこの異能を使えば、効果時間が永久に近くなるってことだ」
「じ、じゃあこの街の霧を晴らすことは無理ってこと?」
「………」
「なんとか言ってよ、リール」
ユーイオがそう言うと、リールは部屋の奥へと歩き出す。わけもわからないままついて行くと、部屋の最奥に薄紫色の石がショーケースに入れられていた。
「「停滞」の力が込められた石だ。ケース自体にも「停滞」の力が巡らされていて、簡単に壊せないようになってる。最下層から最上層までの各層に似たようなものがあるはずだ」
「……リール、「停滞」って異能を使ったものや相手の中で流れる時間を繰り返させる力、なんだよね」
「? ああ」
ユーイオは閃いてしまった。そんな永久の力を打ち破れる力があることに気付いてしまったのだ。
「ショーケースは触っても問題ないよね」
「ああ」
──時間の流れを意識して、そこに巡る命を手繰り寄せる。
「………『君の役目はもうとっくに終わってる。もう休もう』」
「「!」」
ユーイオがショーケースに手をかざしてそう言うと、ショーケースは粉々に割れてしまった。今ならこの薄紫の「魔法」は無防備に晒されている。
「あっ」
しかし、そう簡単に「停滞」の力が破られるわけにはいかない。薄紫の石から滲み出た「停滞」の力が再びショーケースになって薄紫の石を守るように佇んだ。
「まぁ……一発で上手くいかれても困るからな」
「えっユーイオ今の何!? パパ感激なんだけど!!」
「お前の異能は恐ろしいな……ユーイオ」
異形ふたりに関心を向けられたユーイオは少し照れ臭そうにしてから話す。
「これも「輪廻」の力。僕の異能は簡単に言うと生きてるものは死なせ、死んでるものは生かす力だから」
勿論、それ以外にも使いようはあるのだが。「輪廻」は循環させるもの、つまり応用すれば状態を逆転させることだって容易い。
「取り敢えず出来なくはないってことがわかっただけでも嬉しいよ」
ユーイオは満足していた。自分は何も出来ない無力な子供じゃない。それが実感出来て安心したのだ。
「ユーイオ……」
「あっはは、リーエイ酷い顔」
文字盤の顔は、ユーイオには歪んで見えていた。リーエイが不安でいっぱいになっている証だ。
「大丈夫だって、僕は死なない。何回でもやり直せるんだから」
「………そう、だね」
リーエイが不安でたくさんだったのは、ユーイオが死ぬかもしれないからとか、そんな理由ではない。霧の街の霧が晴れた後、異形が生きられなかった時にユーイオを置いて死んでしまうことになる。その時にユーイオがユーイオとして生きているかは別として、ユーイオの命を持った人を置いていくのがひどく辛い。
「さ、「停滞」の石はもう見せたから次はいつから、誰がそうしたかだ」
石から少し離れた場所にあるのは石碑のようなものだった。
「これは?」
「読めるなら読んでみたらいい」
──同じ人間から蔑まれ疎まれついには存在しないモノ扱いをされた。私の何がそんなに彼らを怒らせることになったかは分からないが、どうせ生きたとしても誰も関わってくれないのならこんな気持ちも存在も隠してしまえばいい。
「隠す……存在を?」
「ああ、これは霧の街の異能の主の一言だ」
「待ってよリール、隠すってどういうこと?」
リーエイが訊くと、リールは少し間をあけて話し始める。
「この街は世界から不要とされたものが集まる場所ってのは知ってるだろ。ただ、集められただけじゃ世界も困るんだ。どうしたか。初めて世界に不要とされたヒトは不要物を隠そうとした。隠せば無かったことにできる。無かったことにできるなら不要とされたものは初めからいなかったことにもできる」
「………」
「それがこの街──「秘匿」の異能だ」
「秘匿」に「停滞」がかけられたことによってこの街は何百何千もの年月を過ごしているという。それだけ「停滞」の力が強いということだ。
「世界から不要とされた理由はもちろん人様々だ。俺たちなら、戦争という不毛で悲惨なことはもう必要ないから。メアルたちなら数百年前のその願い──「もっと医療が発展していれば」なんてたらればはとっくに叶っているから。じゃあこの街で生まれたユーイオ、君みたいな子供たちはどうか。君みたいな人は不要物の末裔だから、必要かどうかの概念がまずない」
「?」
ユーイオがよくわからないと言わんばかりに首を傾げると、リーエイがつまり、と付け足す。
「不要物から生まれた子だから、世界に要るかどうか聞くまでもない……残酷だけど、でも、この異能はそういうことなんだよ」
「僕が………生まれた時点で世界そのものから必要とされていない……?」
ユーイオの目からすっと光が消えたのをリーエイは見逃さなかった。焦りながらもリーエイはフォローを入れる。
「せ、せせせ世界にはね! 俺たちは死ぬまでユーイオ必要だからね! ね!! リール!」
「ああ」
リールはリーエイと違って冷静に頷いた。
「そもそも俺にとってはこの異能自体存在することに意味が無いと思ってる」
「というと?」
リールは言った。
「本当に必要がないなら必要が無いものを集める場所もまた必要が無いだろう」
「──霧の街が世界から不要とされたものが集まる場所って知った時、僕はなんだかすごく安心したんだよ」
百四十六センチ、その小柄な背にはあまりにも似合わない、背の高すぎる玉座に座る少年は言った。「吸収」で能力を吸っても外見は完全にコピーしきれなかった。身長と顔つきと声。それらはどうやっても変えられないままだった。
「病気で……結核で身動きもろくに出来ずに、周りに迷惑をかけて生きることしか出来なかった僕は、やっぱり必要なかったんだって突きつけられて安心したんだ。変だと思う?」
「…………いいえ」
最上層。ふたりだけの空間。最上層者とその従者シルフィは時々こうやって、何もすることがない時に会話をする。その会話は大抵最上層者からの一方的なものなのだが。
「ですが一言だけ申し上げたいことが」
「?」
「少なくとも今の主様は私にとって必要不可欠ですので不要な存在ではありません」
「………」
従者の少女は物怖じすることなくきっぱりと言った。最上層者にはそれが珍しく思えて、しばらく黙って彼女を見たあと、
「っはははは!! シルフィもたまにはいいこと言うね」
と、高らかに笑った。
「………姉さん」
だが、数秒してすぐにその顔から笑顔は消えた。
「姉さんは、僕が結核を患っても態度を変えなかった。誰よりも僕に寄り添ってくれていた……と思う。正直、母さんは父さんを亡くしてから少し様子が変なことがあったから」
「……」
シルフィはそれを黙って聞く。今は主のターンだと理解しているからだ。
「姉さんさえ生きていれば、僕がここに来ることもなかったのかもしれない」
「……主様」
「ま、こんなたらればなんて言い出したらキリがない。僕が病気にならなかったら、父さんと姉さんが生きていれば、戦争なんてなかったら。僕は家という箱庭に閉じ込められた人生を送っただけだったけど、それでも外から伝わる音でこの世がどう動いてるのか、ちょっとはわかってたんだ」
戦争が起きたこと。今回も短期決戦でと踏み込んだその戦いは長期に渡り、物資が枯渇し、それでもラジオからの音声はひたすらに「我が国は勝っている」みたいなふざけたことしか言わなかったこと。物資が枯渇したのがどうしてわかったかって? ──簡単だよ。物を得るのにお金を使わなくなって、その代わりに切符を使い始めたのを母さんの手元から見て訊いたんだ。「それは何? お金じゃないよね?」って。
今の祖国がどうなっているのかは知らない、いや、知るつもりもない。きっと知ったところで僕は国の最新の状態を理解できない。
「僕が最上層に居るのも、全部姉さんの為。姉さんに会える可能性が一番高いのは……ううん、あらゆる可能性の幅を広げられるのは、一番偉い奴だろ?」
シルフィは小さく頷く。
「僕は姉さんに会えたら死んでもいい。もうこの世に生まれ変われなくてもいい」
だが、少年は知らなかった。死んだからと言って世界から不要とみなされたわけではないこと。つまり、ここが死後の世界と似たようなものではないということを。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

少年、その愛 〜愛する男に斬られるのもまた甘美か?〜
西浦夕緋
キャラ文芸
15歳の少年篤弘はある日、夏朗と名乗る17歳の少年と出会う。
彼は篤弘の初恋の少女が入信を望み続けた宗教団体・李凰国(りおうこく)の男だった。
亡くなった少女の想いを受け継ぎ篤弘は李凰国に入信するが、そこは想像を絶する世界である。
罪人の公開処刑、抗争する新興宗教団体に属する少女の殺害、
そして十数年前に親元から拉致され李凰国に迎え入れられた少年少女達の運命。
「愛する男に斬られるのもまた甘美か?」
李凰国に正義は存在しない。それでも彼は李凰国を愛した。
「おまえの愛の中に散りゆくことができるのを嬉しく思う。」
李凰国に生きる少年少女達の魂、信念、孤独、そして愛を描く。

化想操術師の日常
茶野森かのこ
キャラ文芸
たった一つの線で、世界が変わる。
化想操術師という仕事がある。
一般的には知られていないが、化想は誰にでも起きる可能性のある現象で、悲しみや苦しみが心に抱えきれなくなった時、人は無意識の内に化想と呼ばれるものを体の外に生み出してしまう。それは、空間や物や生き物と、その人の心を占めるものである為、様々だ。
化想操術師とは、頭の中に思い描いたものを、その指先を通して、現実に生み出す事が出来る力を持つ人達の事。本来なら無意識でしか出せない化想を、意識的に操る事が出来た。
クズミ化想社は、そんな化想に苦しむ人々に寄り添い、救う仕事をしている。
社長である九頭見志乃歩は、自身も化想を扱いながら、化想患者限定でカウンセラーをしている。
社員は自身を含めて四名。
九頭見野雪という少年は、化想を生み出す能力に長けていた。志乃歩の養子に入っている。
常に無表情であるが、それは感情を失わせるような過去があったからだ。それでも、志乃歩との出会いによって、その心はいつも誰かに寄り添おうとしている、優しい少年だ。
他に、志乃歩の秘書でもある黒兎、口は悪いが料理の腕前はピカイチの姫子、野雪が生み出した巨大な犬の化想のシロ。彼らは、山の中にある洋館で、賑やかに共同生活を送っていた。
その洋館に、新たな住人が加わった。
記憶を失った少女、たま子。化想が扱える彼女は、記憶が戻るまでの間、野雪達と共に過ごす事となった。
だが、記憶を失くしたたま子には、ある目的があった。
たま子はクズミ化想社の一人として、志乃歩や野雪と共に、化想を出してしまった人々の様々な思いに触れていく。
壊れた友情で海に閉じこもる少年、自分への後悔に復讐に走る女性、絵を描く度に化想を出してしまう少年。
化想操術の古い歴史を持つ、阿木之亥という家の人々、重ねた野雪の過去、初めて出来た好きなもの、焦がれた自由、犠牲にしても守らなきゃいけないもの。
野雪とたま子、化想を取り巻く彼らのお話です。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。
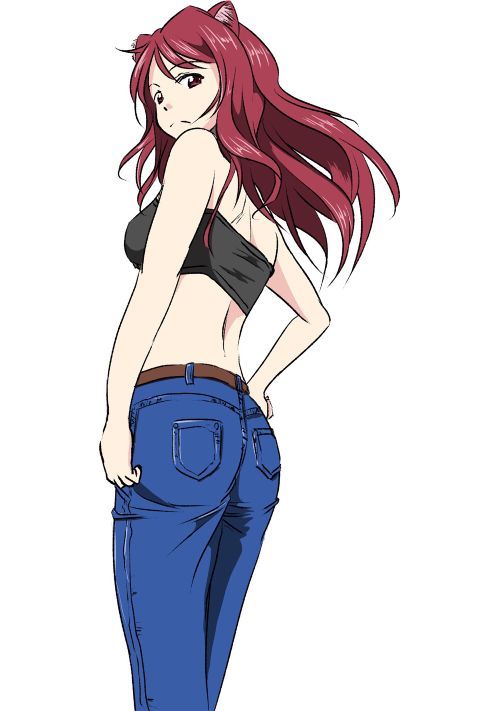
遥か
カリフォルニアデスロールの野良兎
キャラ文芸
鶴木援(ツルギタスケ)は、疲労状態で仕事から帰宅する。何も無い日常にトラウマを抱えた過去、何も起きなかったであろう未来を抱えたまま、何故か誤って監獄街に迷い込む。
生きることを問いかける薄暗いロー・ファンタジー。
表紙 @kafui_k_h

百合系サキュバス達に一目惚れされた
釧路太郎
キャラ文芸
名門零楼館高校はもともと女子高であったのだが、様々な要因で共学になって数年が経つ。
文武両道を掲げる零楼館高校はスポーツ分野だけではなく進学実績も全国レベルで見ても上位に食い込んでいるのであった。
そんな零楼館高校の歴史において今まで誰一人として選ばれたことのない“特別指名推薦”に選ばれたのが工藤珠希なのである。
工藤珠希は身長こそ平均を超えていたが、運動や学力はいたって平均クラスであり性格の良さはあるものの特筆すべき才能も無いように見られていた。
むしろ、彼女の幼馴染である工藤太郎は様々な部活の助っ人として活躍し、中学生でありながら様々な競技のプロ団体からスカウトが来るほどであった。更に、学力面においても優秀であり国内のみならず海外への進学も不可能ではないと言われるほどであった。
“特別指名推薦”の話が学校に来た時は誰もが相手を間違えているのではないかと疑ったほどであったが、零楼館高校関係者は工藤珠希で間違いないという。
工藤珠希と工藤太郎は血縁関係はなく、複雑な家庭環境であった工藤太郎が幼いころに両親を亡くしたこともあって彼は工藤家の養子として迎えられていた。
兄妹同然に育った二人ではあったが、お互いが相手の事を守ろうとする良き関係であり、恋人ではないがそれ以上に信頼しあっている。二人の関係性は苗字が同じという事もあって夫婦と揶揄されることも多々あったのだ。
工藤太郎は県外にあるスポーツ名門校からの推薦も来ていてほぼ内定していたのだが、工藤珠希が零楼館高校に入学することを決めたことを受けて彼も零楼館高校を受験することとなった。
スポーツ分野でも名をはせている零楼館高校に工藤太郎が入学すること自体は何の違和感もないのだが、本来入学する予定であった高校関係者は落胆の声をあげていたのだ。だが、彼の出自も相まって彼の意志を否定する者は誰もいなかったのである。
二人が入学する零楼館高校には外に出ていない秘密があるのだ。
零楼館高校に通う生徒のみならず、教員職員運営者の多くがサキュバスでありそのサキュバスも一般的に知られているサキュバスと違い女性を対象とした変異種なのである。
かつては“秘密の花園”と呼ばれた零楼館女子高等学校もそういった意味を持っていたのだった。
ちなみに、工藤珠希は工藤太郎の事を好きなのだが、それは誰にも言えない秘密なのである。
この作品は「小説家になろう」「カクヨム」「ノベルアッププラス」「ノベルバ」「ノベルピア」にも掲載しております。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















