5 / 59
一章 光と霧の街
とけいや
しおりを挟む
翌日、本当にリーエイは一通り家事を済ませてから「じゃ、何かあったら隣の時計屋に来てね」と言って家に僕を置いて仕事に行ってしまった。初めてこの家に一人でいる。ひとりは慣れているから、大丈夫。
「………」
それにしても静かだ。外の車が走っていく音が聞こえて、改めてリーエイは賑やかなヒトだと感じた。思えばまだ今日でまだ三日しか経っていないというのに、最下層での暮らしが遠い昔のことに思えてきた僕がいる。それだけリーエイは僕が退屈しないようにしてくれていたのだろうか。普段ならこの時間は文字を覚える時間だ。時計はもう覚えたから読めるし、おやつがどこにあるのかも聞いている。今日読むはずだった本は本棚の低いところにあった。
「Alice in wonderland……うん、読める。ちゃんと読めるよ、リーエイ」
ばっと後ろを振り返る。しんとした広いリビングは余計に広く感じた。
「……いいよ、別にリーエイが僕を一人で置いておくなら僕だって」
ばふっ、と豪快にふかふかのソファに座り、そこからうつ伏せになって本を読み始める。「一応異能で傷みにくくしてるけれど、丁寧に扱ってね」と言われていた本を雑に開く。店の看板のイラストを見たことがある僕は最初、この絵本の絵のテイストが古いと思った。リーエイに訊くと「ああ、俺が子供の頃のやつだよ」と言っていたので実際にかなり古いらしい。
「……」
ちくたくと時計が時を刻む音を聞きながらぺらぺらとページをめくる。
「………」
絵本は話がそこまで長くない。すぐに読み終わってしまった。
「たまには少しくらい難しい本を読んでもいいよね」
本棚にさっきまで読んでいた本をしまって、少し上の段にある本を手に取ってみる。絵本よりは分厚く重たい。適当に真ん中あたりを開いてみる。
「え、と……ん? これ横書きじゃない。……知らない文字ばっかりだし、読めない」
時計屋に訊きに行ってもいいが、勝手に他の本を読んで怒られはしないだろうか。──いや、彼が怒るはずがない。
「リーエイ」
からんからん、と勢いよく時計屋の扉を開けた。
「ん、どうかした?」
「絵本、すぐに読み終わったから他の本を読んでみようと思ったんだけどこの本全然何書いてるか読めなくて」
「ああ」
「タイトルも読めないんだけど」
「そうだね。うーんと……うん、今日は二日ぶりだけどまだ忙しくない日だからいいよ、教えよっか」
リーエイはカレンダーを見てからそう言った。仕事、とかいうのは面倒そうだ。
「この本のタイトルは『西遊記』──繰り返して、さいゆうき」
「さいゆうき」
「そう。っていっても今の発音は別の国の……日本、の発音なんだけど。この『西遊記』はかなり長い話だよ」
「面白い?」
「ああ、とても」
カウンター越しに話していると、リーエイがおいで、と手招きをした。僕がカウンターの中に入るとリーエイは小さな椅子を出してくれた。
「この文字は俺のご先祖さまが住んでいた国で使われてる文字だよ」
「えいご、とは違うんだ」
「うん、俺は英語が母語──最初に話して覚えた言葉なんだけど、ご先祖さまは別の国にいたからこの文字を使う言葉が母語だったんだね」
学校に行っていないから僕は文字にそんなに種類があるなんて思わなかった。そういえば、この街で見かける文字は英語と同じ文字だったはずだ。
「この街の名前って英語だよね」
「霧の街、そうだね。それにしてもそのまんますぎるかな」
最上層から最下層までこの街は坂道で繋がっていて、そのどの層も深い霧に覆われている。他の層に入っても気付かないのでは、と思っても安心だ。きちんと層ごとに石畳のデザイン、色が違う。最下層はでこぼこで整備がほとんどされていないため車もろくに走れない道だったが、下層になるとそのでこぼこが少しマシになって馬車は走らせられるようになる。ここ中層だと車が走り始める。後からリーエイに聞いたのだが、中層は石畳の石が小さいと思っていたらそれはレンガ、というらしい。
「さ、話を戻そうか。西遊記に使われている文字は漢字。漢字だけを使う俺のご先祖さまの母語は中国語っていうよ」
「リーエイも話せる?」
「すこーしだけ」
リーエイは「親戚が中国にいたからね」と付け加えた。
「話してみてよ」
「えっ」
「喋ってみて。リーエイ、言葉を覚える時は発音からって言ってたでしょ」
「え、ええ~……」
困っている。ある程度のことなら「全然いいよ」とやってくれたり、許してくれるあのリーエイが。
「話せないの?」
「もう全然中国語使ってないから……」
「そっか、残念」
僕が少し大袈裟にしゅんとしていると、ぺらりとはじめのページをリーエイがめくっていた。
「…………えーと。………うん。今から読むよ、英語と違って「わけわからん」ってなると思うけれど、とりあえず一回聴いてね」
僕が頷いたのを見ると、リーエイはすう、と息を吸った。
「最初の一文だけね。混沌未分天地亂,茫茫渺渺無人見」
「……………は?」
リーエイ、ごめん。頼んでおいてごめん。
「ちょっと何言ってるか分からない」
「だから言ったじゃん、「わけわからん」ってなると思うって」
嘘だろ? 同じ人間が使う言葉で、一体何がどうやって、どうしてここまで発音も文字も違うものになれるのか。
「今のは「天と地がいつどうして作られたのか誰も知らない」って始まりを読んだんだよ」
「へ、へえ……」
「喋ってみる? 発音してみる? 四声っていう発音から覚えないといけないけれど」
「いや、いい」
僕が被せ気味に拒否すると、リーエイは「そっか」とだけ言って西遊記を僕に返した。「西游记」と書かれた本を僕は二度と開くまい。いくら面白いと言われても、僕の頭じゃ何年かかっても読めそうにはない。
「それにしても誰も来ないけど暇じゃないの?」
「え? 暇だよ?」
本当にこいつが店主で大丈夫か。僕が頭の中でそうツッコミを入れているとからんからん、と誰かが入ってきた。
「リーエイ、家の時計が壊れちゃってさ」
「ああ、見せてみて」
来店したのは異形のヒト。頭が薬の錠剤の形をした、いかにも治療系の異能を使ってくれそうなヒトだ。
「……ん? リーエイ、人間なんて拾ったんだ?」
「うん、最下層に散歩しに行ったら衰弱しきってたからねー。身よりもなさそうだったから拾って昨日ちゃんと家族になったよ」
「へえ。ねぇ、名前は?」
「っ」
リーエイ以外の異形に話しかけられることに慣れていない僕は、いきなり話しかけられてビクッと驚いてしまった。
「ああごめんね、怖がらせるつもりはないんだよ」
慌てて錠剤の異形のヒトが両手を前に出して謝る。指は絆創膏がたくさん巻かれている。
「……ううん、僕こそごめんなさい。僕はユーイオ」
「ユーイオって言うんだね。あたしはイノヴァン。双子の弟がいるよ」
この異形のヒトは悪いヒトじゃない、とすぐにわかった。リーエイに出会うまでの僕の異形のイメージ──というより会った異形のヒトたちは人間を見下して奴隷にしていた奴らだった。そういう奴らの言葉には、毒がある。嫌な音がする。奴らがなにか話す度に殺したくなるような、そんな音がする。でも、イノヴァンにそれは感じられない。
「イノヴァンって薬屋?」
「そうだよー。異能が「神癒調合」っていってね、あたしにかかればどんな病気も薬で一発よ。あ、その代わり怪我は治せないしあたしにはどの薬も効かなくなっちゃったんだけど」
「便利な異能ってやっぱり代償が大きいんだな」
「基本的にはそうなるね! あ、あたしの薬屋はここよりもう少し上の中層部内だから、病気したらいつでも来てね。ユーイオとリーエイにはオマケしてあげる。じゃあね」
直ったよ、とリーエイから渡された時計を嬉々として受け取り代金を支払って、イノヴァンは帰っていった。
「イノヴァンは昔からの知り合いだよ。彼女は先天性異形だから、俺みたいに人間の時代がない異形だね」
「見た目に人間の頃の痕跡が出る以外で何か差はある?」
「そうだね………基本的にあまり無いかな。強いて言うなら先天性異形は生まれた時から異能が使えて当たり前って感覚だから、やっぱり俺たちより人間を見下しやすい傾向にはあるかもしれないね」
リーエイは時計修理に使った工具を整理しながら話を続ける。
「イノヴァンやその弟は治療系の異能持ちだから、人間とも関わる機会が多くて人間を見下さない異形になってるけれど、ああいうのは多くないからねぇ」
はい、とリーエイが紅茶を淹れてくれた。退屈そうに見えたのだろうか。それなら申し訳ない。──それにしても。
「リーエイは時計に異能、使わないの?」
「使ったらお金稼げなくなっちゃうから使わないね。あと、後天性異形は異能を使いすぎると魔力切れでぶっ倒れて最悪死んじゃうんだよね。俺の友達もそれで一人死んでたかな。あっ先天性異形はそんなこと起きないらしいからね、イノヴァンとか毎日アホみたいに薬作ってるよ」
ちなみに魔力の量も後天性の中で個人差があるらしい。リーエイはかなり多い方らしく、あの写真を見せなければ先天性異形と間違われるほどだという。もっとも、人間の僕には魔力なんて感知できないし持ってすらないのだが。
「友達ってどんな人だった?」
「今の最上層に君臨する奴を殺そうとしたね!」
「は?」
「本当だよ。友達の持つ異能は「消滅」──消したいものなんでも消せるチート異能だね! もちろん代償も重くて、友達の持つ個性が消えた。だから俺も友達のことは外見とか性格は全然思い出せないんだ」
それでも異能だけが記憶に留まっている理由をリーエイは話し続ける。客は来ない。よく見ると外にいる人の動きが止まっている。話が中断されないよう、リーエイがこの部屋以外の空間の時間を止めているのだと気付いた。
「最上層にいる奴の元々持ってた異能が「吸収」──それで友達の「消滅」を文字通り吸収して、自分のモノにしたんだ。そうすると、友達は代償で個性を無くしていたから異能っていう最大で唯一の特徴を奪われて存在が保てなくなっちゃったんだ」
「存在が保てなくなるって……」
「身体も無くなるし、当然人の記憶からも存在が抜け落ちていくね。俺は友達が消えていくのを目の前で見てたからすぐに日記に書き留めたんだ」
「え? 目の前?」
「うん、「時間詐称」でサポートしてくれって頼まれてた気がするから、多分それでいたはずだよ。最上層の奴は俺まで殺そうとしてきたけれど今までで一番強い「時間詐称」を使って何とか俺は帰ってきた。あの瞬間だけはどうしても忘れたらダメだと思ってね、俺はあの日の記憶に「時間詐称」を使って記憶が抜け落ちないように残してるんだ」
──そういえば、一度だけリーエイが寝ている間にこっそりキャビネットに入っている古い日記を見たことがある。たまたま開いたページに「またひとり大切な人がいなくなってしまった。名前も顔も性格も異能のせいで誰にも覚えて貰えない彼は無謀だったけれども勇敢な行動をした。僕だけは忘れない。忘れてはいけない。「完全記憶」の異能を持っている図書館の知り合いでさえ彼を忘れてしまっていた。僕だけだ。僕しかこのことを、彼を覚え続けていられる人がいない。アイツは彼の異能を吸収したから、きっと顔も身体付きも、性格以外の何もかもが彼のものに上書きされてしまっただろう。この街の霧を晴らす次の太陽は誰になるのだろう。」とリーエイらしくない、ずるずると力の抜けた文字が続いていたのを思い出した。
「………リーエイ」
「ん?」
「人間にも異能を使える人っている?」
「俺は見たことないしそんな人の話は聞いたこともないなぁ」
「そっか」
「どうしたの?」
「……数年前、最上層の奴が最下層に来たことがあった」
「えっ」
その日は天気が荒れて、霧が晴れた代わりに暴風雨だった。ボロボロのビニールシートを被って雨は凌いだが風が酷かった。なにか良くないことが起きると思っていたら、本当にそんなことが起きた。最上層の奴──この街の全てを束ねるボスが最下層に来ていたのだ。
「汚い、が見たところ人間しかここにはいなそうだ。じゃあここを復興する必要は無いな」
フードを深く被っていた奴はそう言って秘書みたいなのと一緒に帰っていった。
「僕はその時の奴の顔も声も格好も覚えてる。だから多分、その異能の代償って人間には効いてないんじゃないかな」
「……! ……それが本当なら奴は友達の異能を完全にはコピー出来てないことになるよ」
「友達は知り合いの人間にも忘れられてるって?」
「そう、何でも消せた俺の友達は誰にも覚えて貰えなかった。でも、奴はその異能を吸収して今の自分の異能にしているにもかかわらず人間に覚えられてるってことは何でも消せるわけじゃないってことになるよ」
ずしっ、と一瞬身体が重くなった気がして、外を見ると止まっていた人たちが動き出していた。リーエイが「時間詐称」を解除したんだ。
「………はぁ、そうなると「吸収」は完璧にコピー出来るわけじゃないんだろうね。多分代償は純粋な学習能力の欠損、とかになるはず。だとすると異能を使うことでしか奴は何も学習できないんじゃ……? うーんダメだな、客が来て考え事が中断させられるのも困る。五時前だし今日は閉店にしよう」
「そんな簡単に閉店していいんだ?」
「え? うん。別にこっちが閉まってても本当に急用のときは家にも来るはずだからね」
「そんなもんか」
「そんなもんだよ」
ドアの札を「Open」から「Closed」に裏返して家に戻る。西遊記を元あった場所に戻して、冷蔵庫のおやつを取り出す。リーエイはぶつぶつ呟きながら書斎に入った。一緒におやつを食べようと思っていたのに、あれでは声もかけられない。仕方ないから、ひとつを冷蔵庫に入れたまま僕は一人でチーズクリームのトライフルを食べ始めた。
「………」
それにしても静かだ。外の車が走っていく音が聞こえて、改めてリーエイは賑やかなヒトだと感じた。思えばまだ今日でまだ三日しか経っていないというのに、最下層での暮らしが遠い昔のことに思えてきた僕がいる。それだけリーエイは僕が退屈しないようにしてくれていたのだろうか。普段ならこの時間は文字を覚える時間だ。時計はもう覚えたから読めるし、おやつがどこにあるのかも聞いている。今日読むはずだった本は本棚の低いところにあった。
「Alice in wonderland……うん、読める。ちゃんと読めるよ、リーエイ」
ばっと後ろを振り返る。しんとした広いリビングは余計に広く感じた。
「……いいよ、別にリーエイが僕を一人で置いておくなら僕だって」
ばふっ、と豪快にふかふかのソファに座り、そこからうつ伏せになって本を読み始める。「一応異能で傷みにくくしてるけれど、丁寧に扱ってね」と言われていた本を雑に開く。店の看板のイラストを見たことがある僕は最初、この絵本の絵のテイストが古いと思った。リーエイに訊くと「ああ、俺が子供の頃のやつだよ」と言っていたので実際にかなり古いらしい。
「……」
ちくたくと時計が時を刻む音を聞きながらぺらぺらとページをめくる。
「………」
絵本は話がそこまで長くない。すぐに読み終わってしまった。
「たまには少しくらい難しい本を読んでもいいよね」
本棚にさっきまで読んでいた本をしまって、少し上の段にある本を手に取ってみる。絵本よりは分厚く重たい。適当に真ん中あたりを開いてみる。
「え、と……ん? これ横書きじゃない。……知らない文字ばっかりだし、読めない」
時計屋に訊きに行ってもいいが、勝手に他の本を読んで怒られはしないだろうか。──いや、彼が怒るはずがない。
「リーエイ」
からんからん、と勢いよく時計屋の扉を開けた。
「ん、どうかした?」
「絵本、すぐに読み終わったから他の本を読んでみようと思ったんだけどこの本全然何書いてるか読めなくて」
「ああ」
「タイトルも読めないんだけど」
「そうだね。うーんと……うん、今日は二日ぶりだけどまだ忙しくない日だからいいよ、教えよっか」
リーエイはカレンダーを見てからそう言った。仕事、とかいうのは面倒そうだ。
「この本のタイトルは『西遊記』──繰り返して、さいゆうき」
「さいゆうき」
「そう。っていっても今の発音は別の国の……日本、の発音なんだけど。この『西遊記』はかなり長い話だよ」
「面白い?」
「ああ、とても」
カウンター越しに話していると、リーエイがおいで、と手招きをした。僕がカウンターの中に入るとリーエイは小さな椅子を出してくれた。
「この文字は俺のご先祖さまが住んでいた国で使われてる文字だよ」
「えいご、とは違うんだ」
「うん、俺は英語が母語──最初に話して覚えた言葉なんだけど、ご先祖さまは別の国にいたからこの文字を使う言葉が母語だったんだね」
学校に行っていないから僕は文字にそんなに種類があるなんて思わなかった。そういえば、この街で見かける文字は英語と同じ文字だったはずだ。
「この街の名前って英語だよね」
「霧の街、そうだね。それにしてもそのまんますぎるかな」
最上層から最下層までこの街は坂道で繋がっていて、そのどの層も深い霧に覆われている。他の層に入っても気付かないのでは、と思っても安心だ。きちんと層ごとに石畳のデザイン、色が違う。最下層はでこぼこで整備がほとんどされていないため車もろくに走れない道だったが、下層になるとそのでこぼこが少しマシになって馬車は走らせられるようになる。ここ中層だと車が走り始める。後からリーエイに聞いたのだが、中層は石畳の石が小さいと思っていたらそれはレンガ、というらしい。
「さ、話を戻そうか。西遊記に使われている文字は漢字。漢字だけを使う俺のご先祖さまの母語は中国語っていうよ」
「リーエイも話せる?」
「すこーしだけ」
リーエイは「親戚が中国にいたからね」と付け加えた。
「話してみてよ」
「えっ」
「喋ってみて。リーエイ、言葉を覚える時は発音からって言ってたでしょ」
「え、ええ~……」
困っている。ある程度のことなら「全然いいよ」とやってくれたり、許してくれるあのリーエイが。
「話せないの?」
「もう全然中国語使ってないから……」
「そっか、残念」
僕が少し大袈裟にしゅんとしていると、ぺらりとはじめのページをリーエイがめくっていた。
「…………えーと。………うん。今から読むよ、英語と違って「わけわからん」ってなると思うけれど、とりあえず一回聴いてね」
僕が頷いたのを見ると、リーエイはすう、と息を吸った。
「最初の一文だけね。混沌未分天地亂,茫茫渺渺無人見」
「……………は?」
リーエイ、ごめん。頼んでおいてごめん。
「ちょっと何言ってるか分からない」
「だから言ったじゃん、「わけわからん」ってなると思うって」
嘘だろ? 同じ人間が使う言葉で、一体何がどうやって、どうしてここまで発音も文字も違うものになれるのか。
「今のは「天と地がいつどうして作られたのか誰も知らない」って始まりを読んだんだよ」
「へ、へえ……」
「喋ってみる? 発音してみる? 四声っていう発音から覚えないといけないけれど」
「いや、いい」
僕が被せ気味に拒否すると、リーエイは「そっか」とだけ言って西遊記を僕に返した。「西游记」と書かれた本を僕は二度と開くまい。いくら面白いと言われても、僕の頭じゃ何年かかっても読めそうにはない。
「それにしても誰も来ないけど暇じゃないの?」
「え? 暇だよ?」
本当にこいつが店主で大丈夫か。僕が頭の中でそうツッコミを入れているとからんからん、と誰かが入ってきた。
「リーエイ、家の時計が壊れちゃってさ」
「ああ、見せてみて」
来店したのは異形のヒト。頭が薬の錠剤の形をした、いかにも治療系の異能を使ってくれそうなヒトだ。
「……ん? リーエイ、人間なんて拾ったんだ?」
「うん、最下層に散歩しに行ったら衰弱しきってたからねー。身よりもなさそうだったから拾って昨日ちゃんと家族になったよ」
「へえ。ねぇ、名前は?」
「っ」
リーエイ以外の異形に話しかけられることに慣れていない僕は、いきなり話しかけられてビクッと驚いてしまった。
「ああごめんね、怖がらせるつもりはないんだよ」
慌てて錠剤の異形のヒトが両手を前に出して謝る。指は絆創膏がたくさん巻かれている。
「……ううん、僕こそごめんなさい。僕はユーイオ」
「ユーイオって言うんだね。あたしはイノヴァン。双子の弟がいるよ」
この異形のヒトは悪いヒトじゃない、とすぐにわかった。リーエイに出会うまでの僕の異形のイメージ──というより会った異形のヒトたちは人間を見下して奴隷にしていた奴らだった。そういう奴らの言葉には、毒がある。嫌な音がする。奴らがなにか話す度に殺したくなるような、そんな音がする。でも、イノヴァンにそれは感じられない。
「イノヴァンって薬屋?」
「そうだよー。異能が「神癒調合」っていってね、あたしにかかればどんな病気も薬で一発よ。あ、その代わり怪我は治せないしあたしにはどの薬も効かなくなっちゃったんだけど」
「便利な異能ってやっぱり代償が大きいんだな」
「基本的にはそうなるね! あ、あたしの薬屋はここよりもう少し上の中層部内だから、病気したらいつでも来てね。ユーイオとリーエイにはオマケしてあげる。じゃあね」
直ったよ、とリーエイから渡された時計を嬉々として受け取り代金を支払って、イノヴァンは帰っていった。
「イノヴァンは昔からの知り合いだよ。彼女は先天性異形だから、俺みたいに人間の時代がない異形だね」
「見た目に人間の頃の痕跡が出る以外で何か差はある?」
「そうだね………基本的にあまり無いかな。強いて言うなら先天性異形は生まれた時から異能が使えて当たり前って感覚だから、やっぱり俺たちより人間を見下しやすい傾向にはあるかもしれないね」
リーエイは時計修理に使った工具を整理しながら話を続ける。
「イノヴァンやその弟は治療系の異能持ちだから、人間とも関わる機会が多くて人間を見下さない異形になってるけれど、ああいうのは多くないからねぇ」
はい、とリーエイが紅茶を淹れてくれた。退屈そうに見えたのだろうか。それなら申し訳ない。──それにしても。
「リーエイは時計に異能、使わないの?」
「使ったらお金稼げなくなっちゃうから使わないね。あと、後天性異形は異能を使いすぎると魔力切れでぶっ倒れて最悪死んじゃうんだよね。俺の友達もそれで一人死んでたかな。あっ先天性異形はそんなこと起きないらしいからね、イノヴァンとか毎日アホみたいに薬作ってるよ」
ちなみに魔力の量も後天性の中で個人差があるらしい。リーエイはかなり多い方らしく、あの写真を見せなければ先天性異形と間違われるほどだという。もっとも、人間の僕には魔力なんて感知できないし持ってすらないのだが。
「友達ってどんな人だった?」
「今の最上層に君臨する奴を殺そうとしたね!」
「は?」
「本当だよ。友達の持つ異能は「消滅」──消したいものなんでも消せるチート異能だね! もちろん代償も重くて、友達の持つ個性が消えた。だから俺も友達のことは外見とか性格は全然思い出せないんだ」
それでも異能だけが記憶に留まっている理由をリーエイは話し続ける。客は来ない。よく見ると外にいる人の動きが止まっている。話が中断されないよう、リーエイがこの部屋以外の空間の時間を止めているのだと気付いた。
「最上層にいる奴の元々持ってた異能が「吸収」──それで友達の「消滅」を文字通り吸収して、自分のモノにしたんだ。そうすると、友達は代償で個性を無くしていたから異能っていう最大で唯一の特徴を奪われて存在が保てなくなっちゃったんだ」
「存在が保てなくなるって……」
「身体も無くなるし、当然人の記憶からも存在が抜け落ちていくね。俺は友達が消えていくのを目の前で見てたからすぐに日記に書き留めたんだ」
「え? 目の前?」
「うん、「時間詐称」でサポートしてくれって頼まれてた気がするから、多分それでいたはずだよ。最上層の奴は俺まで殺そうとしてきたけれど今までで一番強い「時間詐称」を使って何とか俺は帰ってきた。あの瞬間だけはどうしても忘れたらダメだと思ってね、俺はあの日の記憶に「時間詐称」を使って記憶が抜け落ちないように残してるんだ」
──そういえば、一度だけリーエイが寝ている間にこっそりキャビネットに入っている古い日記を見たことがある。たまたま開いたページに「またひとり大切な人がいなくなってしまった。名前も顔も性格も異能のせいで誰にも覚えて貰えない彼は無謀だったけれども勇敢な行動をした。僕だけは忘れない。忘れてはいけない。「完全記憶」の異能を持っている図書館の知り合いでさえ彼を忘れてしまっていた。僕だけだ。僕しかこのことを、彼を覚え続けていられる人がいない。アイツは彼の異能を吸収したから、きっと顔も身体付きも、性格以外の何もかもが彼のものに上書きされてしまっただろう。この街の霧を晴らす次の太陽は誰になるのだろう。」とリーエイらしくない、ずるずると力の抜けた文字が続いていたのを思い出した。
「………リーエイ」
「ん?」
「人間にも異能を使える人っている?」
「俺は見たことないしそんな人の話は聞いたこともないなぁ」
「そっか」
「どうしたの?」
「……数年前、最上層の奴が最下層に来たことがあった」
「えっ」
その日は天気が荒れて、霧が晴れた代わりに暴風雨だった。ボロボロのビニールシートを被って雨は凌いだが風が酷かった。なにか良くないことが起きると思っていたら、本当にそんなことが起きた。最上層の奴──この街の全てを束ねるボスが最下層に来ていたのだ。
「汚い、が見たところ人間しかここにはいなそうだ。じゃあここを復興する必要は無いな」
フードを深く被っていた奴はそう言って秘書みたいなのと一緒に帰っていった。
「僕はその時の奴の顔も声も格好も覚えてる。だから多分、その異能の代償って人間には効いてないんじゃないかな」
「……! ……それが本当なら奴は友達の異能を完全にはコピー出来てないことになるよ」
「友達は知り合いの人間にも忘れられてるって?」
「そう、何でも消せた俺の友達は誰にも覚えて貰えなかった。でも、奴はその異能を吸収して今の自分の異能にしているにもかかわらず人間に覚えられてるってことは何でも消せるわけじゃないってことになるよ」
ずしっ、と一瞬身体が重くなった気がして、外を見ると止まっていた人たちが動き出していた。リーエイが「時間詐称」を解除したんだ。
「………はぁ、そうなると「吸収」は完璧にコピー出来るわけじゃないんだろうね。多分代償は純粋な学習能力の欠損、とかになるはず。だとすると異能を使うことでしか奴は何も学習できないんじゃ……? うーんダメだな、客が来て考え事が中断させられるのも困る。五時前だし今日は閉店にしよう」
「そんな簡単に閉店していいんだ?」
「え? うん。別にこっちが閉まってても本当に急用のときは家にも来るはずだからね」
「そんなもんか」
「そんなもんだよ」
ドアの札を「Open」から「Closed」に裏返して家に戻る。西遊記を元あった場所に戻して、冷蔵庫のおやつを取り出す。リーエイはぶつぶつ呟きながら書斎に入った。一緒におやつを食べようと思っていたのに、あれでは声もかけられない。仕方ないから、ひとつを冷蔵庫に入れたまま僕は一人でチーズクリームのトライフルを食べ始めた。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

少年、その愛 〜愛する男に斬られるのもまた甘美か?〜
西浦夕緋
キャラ文芸
15歳の少年篤弘はある日、夏朗と名乗る17歳の少年と出会う。
彼は篤弘の初恋の少女が入信を望み続けた宗教団体・李凰国(りおうこく)の男だった。
亡くなった少女の想いを受け継ぎ篤弘は李凰国に入信するが、そこは想像を絶する世界である。
罪人の公開処刑、抗争する新興宗教団体に属する少女の殺害、
そして十数年前に親元から拉致され李凰国に迎え入れられた少年少女達の運命。
「愛する男に斬られるのもまた甘美か?」
李凰国に正義は存在しない。それでも彼は李凰国を愛した。
「おまえの愛の中に散りゆくことができるのを嬉しく思う。」
李凰国に生きる少年少女達の魂、信念、孤独、そして愛を描く。

化想操術師の日常
茶野森かのこ
キャラ文芸
たった一つの線で、世界が変わる。
化想操術師という仕事がある。
一般的には知られていないが、化想は誰にでも起きる可能性のある現象で、悲しみや苦しみが心に抱えきれなくなった時、人は無意識の内に化想と呼ばれるものを体の外に生み出してしまう。それは、空間や物や生き物と、その人の心を占めるものである為、様々だ。
化想操術師とは、頭の中に思い描いたものを、その指先を通して、現実に生み出す事が出来る力を持つ人達の事。本来なら無意識でしか出せない化想を、意識的に操る事が出来た。
クズミ化想社は、そんな化想に苦しむ人々に寄り添い、救う仕事をしている。
社長である九頭見志乃歩は、自身も化想を扱いながら、化想患者限定でカウンセラーをしている。
社員は自身を含めて四名。
九頭見野雪という少年は、化想を生み出す能力に長けていた。志乃歩の養子に入っている。
常に無表情であるが、それは感情を失わせるような過去があったからだ。それでも、志乃歩との出会いによって、その心はいつも誰かに寄り添おうとしている、優しい少年だ。
他に、志乃歩の秘書でもある黒兎、口は悪いが料理の腕前はピカイチの姫子、野雪が生み出した巨大な犬の化想のシロ。彼らは、山の中にある洋館で、賑やかに共同生活を送っていた。
その洋館に、新たな住人が加わった。
記憶を失った少女、たま子。化想が扱える彼女は、記憶が戻るまでの間、野雪達と共に過ごす事となった。
だが、記憶を失くしたたま子には、ある目的があった。
たま子はクズミ化想社の一人として、志乃歩や野雪と共に、化想を出してしまった人々の様々な思いに触れていく。
壊れた友情で海に閉じこもる少年、自分への後悔に復讐に走る女性、絵を描く度に化想を出してしまう少年。
化想操術の古い歴史を持つ、阿木之亥という家の人々、重ねた野雪の過去、初めて出来た好きなもの、焦がれた自由、犠牲にしても守らなきゃいけないもの。
野雪とたま子、化想を取り巻く彼らのお話です。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。
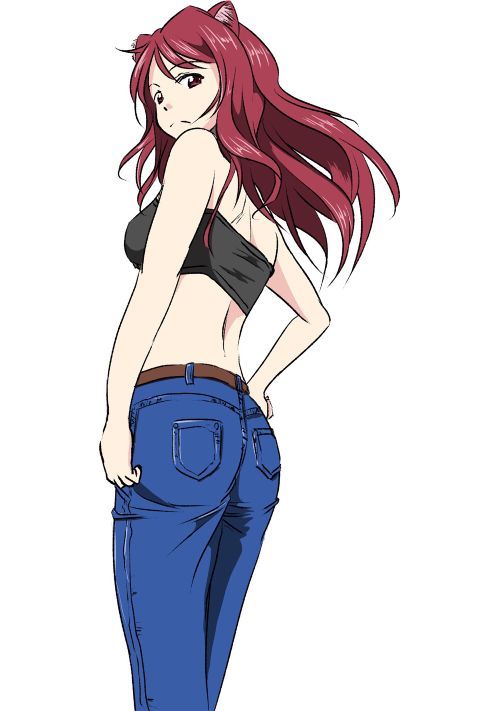
遥か
カリフォルニアデスロールの野良兎
キャラ文芸
鶴木援(ツルギタスケ)は、疲労状態で仕事から帰宅する。何も無い日常にトラウマを抱えた過去、何も起きなかったであろう未来を抱えたまま、何故か誤って監獄街に迷い込む。
生きることを問いかける薄暗いロー・ファンタジー。
表紙 @kafui_k_h

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

百合系サキュバス達に一目惚れされた
釧路太郎
キャラ文芸
名門零楼館高校はもともと女子高であったのだが、様々な要因で共学になって数年が経つ。
文武両道を掲げる零楼館高校はスポーツ分野だけではなく進学実績も全国レベルで見ても上位に食い込んでいるのであった。
そんな零楼館高校の歴史において今まで誰一人として選ばれたことのない“特別指名推薦”に選ばれたのが工藤珠希なのである。
工藤珠希は身長こそ平均を超えていたが、運動や学力はいたって平均クラスであり性格の良さはあるものの特筆すべき才能も無いように見られていた。
むしろ、彼女の幼馴染である工藤太郎は様々な部活の助っ人として活躍し、中学生でありながら様々な競技のプロ団体からスカウトが来るほどであった。更に、学力面においても優秀であり国内のみならず海外への進学も不可能ではないと言われるほどであった。
“特別指名推薦”の話が学校に来た時は誰もが相手を間違えているのではないかと疑ったほどであったが、零楼館高校関係者は工藤珠希で間違いないという。
工藤珠希と工藤太郎は血縁関係はなく、複雑な家庭環境であった工藤太郎が幼いころに両親を亡くしたこともあって彼は工藤家の養子として迎えられていた。
兄妹同然に育った二人ではあったが、お互いが相手の事を守ろうとする良き関係であり、恋人ではないがそれ以上に信頼しあっている。二人の関係性は苗字が同じという事もあって夫婦と揶揄されることも多々あったのだ。
工藤太郎は県外にあるスポーツ名門校からの推薦も来ていてほぼ内定していたのだが、工藤珠希が零楼館高校に入学することを決めたことを受けて彼も零楼館高校を受験することとなった。
スポーツ分野でも名をはせている零楼館高校に工藤太郎が入学すること自体は何の違和感もないのだが、本来入学する予定であった高校関係者は落胆の声をあげていたのだ。だが、彼の出自も相まって彼の意志を否定する者は誰もいなかったのである。
二人が入学する零楼館高校には外に出ていない秘密があるのだ。
零楼館高校に通う生徒のみならず、教員職員運営者の多くがサキュバスでありそのサキュバスも一般的に知られているサキュバスと違い女性を対象とした変異種なのである。
かつては“秘密の花園”と呼ばれた零楼館女子高等学校もそういった意味を持っていたのだった。
ちなみに、工藤珠希は工藤太郎の事を好きなのだが、それは誰にも言えない秘密なのである。
この作品は「小説家になろう」「カクヨム」「ノベルアッププラス」「ノベルバ」「ノベルピア」にも掲載しております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















