3 / 59
一章 光と霧の街
にんげん
しおりを挟む
眠っていた、らしい。最下層の暗さに慣れていた目はカーテンから差し込む僅かな光さえ眩しく感じて、きゅっとまぶたをきつく閉じてしまう。
『おはようございます、ただいま朝七時を迎えました。本日のふぉぐっとニュースは……』
──テレビが動いている。最下層で見るテレビは画面が割れていてとても使い物にならなかった。ごく稀に電源の入るものもあったが、そんなものを使えば電気代を払い終わる前に死んでしまうのでやはり使わずに置いてあるだけだったのだが。それにしてもすごい。こんなに綺麗になめらかに人が画面の中で動いている。ベッドから降りて、テレビに近付いて、画面に手を当てるとぱちっと痛みが走った。
「わっ」
「おはようユーイオ。俺のテレビは古いから画面に触ると静電気でぱちって痛くなるんだよ」
「お、おはよう……リーエイ」
歯磨きと顔洗いをしよう、と洗面所まで連れられる。
「こっちが水でこっちがお湯。もう春だし水で大丈夫だと思うよ」
ひねってみて、と蛇口をひねる。
「わあ……」
すごい。水が透明で、濁ってない。すごくきれい。
「はいこれ歯ブラシと歯磨き粉」
歯磨き粉がついた歯ブラシを渡される。歯ブラシを口に入れると歯磨き粉が優しい味をしていることにすぐ気付いた。泡立ちもいい。うがいをして、顔を水で濡らす。冷たくて気持ちいい。
「手、出してー」
リーエイに手を向けるとにゅっと何か手に出された。
「洗顔料だよ。ちょっと固めのペースト状にした石鹸みたいなやつ。少し水をかけてからだと泡立ちやすくなるかな」
リーエイに言われた通りにやってみる。洗顔料に水をかけて、水分を含ませてから両手を合わせてこする。
「うわっ落ちた」
しかし、初めから上手くいくわけではない。泡立ったもののその泡はぼとりと手からこぼれ落ちてしまった。
「慣れたらちゃんと出来るようになるよ。じゃあ俺は朝ごはん作るから」
そう言ってリーエイはキッチンへ向かってしまった。拭くものはこのまっさらなふわふわのタオルで良いのだろうか。
「あ、タオルはそれ使って。新品とか気にしなくていいからね」
後ろからリーエイの声が聞こえたので洗顔料を流し終わった後は綺麗なタオルで顔と手を拭いた。するりと皮脂のベタベタ感を感じない肌に僕は感動した。中層部でこんな暮らしなら上層部はどんな暮らしなのだろう。
「おまたせ~ユーイオがここに来て初めての朝ごはんだから俺張り切っちゃったよ!」
昨日は使えなかった食卓にはクロックムッシュとシーザーサラダ、ポタージュが並んでいた。
「ぜ、全部食べていいのか?」
「え? うん。一緒に食べたら美味しさ増えると思うよ」
そう言ってリーエイは僕の向かいに座った。ふと僕はあることを疑問に思った。
「リーエイ」
「ん? 味付け好きじゃなかった?」
「そうじゃなくて。リーエイってその顔でどうやって食べるんだろうって思って……」
「ああ!」
そんなことか、と言ってリーエイは笑った。
「安心してよユーイオ。これもパッシブスペルで何とでもなるから」
「え」
見ちゃダメだよ~と手で視界を塞がれる。何が起こっているのかわからないが、手を外され視界が広がった先に時計頭のリーエイは居なかった。代わりに昨日写真で見たあの綺麗な顔をしたリーエイが居た。
「ね? 食事の時とか人間としての顔が必要な時は一時的に戻れるから」
にぱっと明るい笑顔を向けられて、こいつはいつもこんな表情だったのだろうかと初めて感じた。
「リーエイ……人間だったんだな」
「え? そうだよ人間だよ~ちょっと色々あってあの姿だけど」
そう言いながらリーエイはフォークとナイフの使い方を僕に教え始める。
「俺は左利きなんだけど……ユーイオは?」
「利き手とか左右とかよくわからないけどこっちの方が力は強いかも」
そう言ってユーイオは左手を挙げる。
「じゃあ一緒だね。フォークは力が弱い方の手に持つ、ナイフは力が強い方の手に持つ」
「こう?」
「そう」
リーエイのテーブルマナーの教え方はとても上手く、一回でほとんどの作法が身についた。「リーエイって教えるの上手いな」と僕が言うと、「イギリスは紳士の国だからね」と得意げだった。
「さ、食べ終わったら食器を流しにつけておくよ」
リーエイはキッチンの流しに食器を置いて、そこに水道の水で軽く汚れを流していく。最下層ではやりたくてもできなかったことだと思った。最下層で食器を洗おうと思ったら、雨が降るのを待つことから始まるからだ。
「じゃ次は洗濯機回すよ、今から回しておけば役所に行って帰ってきた頃に脱水まで終わってるはずだからね」
よく分からないままついて行くと何回か外で見た記憶がある大きな機械があった。
「これね、入ったら最悪死ぬから入らないでね」
「えっ死ぬのか?」
「実際にそういう事故もあったよ」
淡々と話しながらリーエイはカゴに溜まっていた服を洗濯機に突っ込んでいく。
「香りの好き嫌いはある?」
「特にない……と思う」
「ん、わかった」
リーエイは小さな塊をひとつ洗濯機に入れたあと、色々あるボトルから「今日はこれかな」と一本取りだし、少しだけそれを洗濯機に入れた。
「あとはこれ」
「何それ」
「カルゲンだよ! この街は硬水が流れてるから、水を柔らかくしないと洗濯で服がダメになるんだよ。これを入れたら真水よりは温かい温度に設定して洗濯を始めるよ」
暮らしの質が上がると洗濯にもこれだけのものを使えるのか。洗剤となんかいい匂いがするやつ、カルゲン……。ステップが多いように見えるけど慣れるんだろうか。
「じゃ役所に行く前に前髪切ろっか」
「え」
「嫌?」
「……別に嫌じゃない」
見たことない大きな鏡の前に座らされる。確かに気にしたことはなかったが他人から見るとこの前髪はずいぶん厚く見えるようだ。
「どれくらい切る? 眉毛あたり?」
「よくわからないから適当に」
「おぉーおまかせだね! 任せてよ!」
しゃき、しゃきと前髪が切られていく。今までは青みを帯びたカーテンで、なるべく汚れ朽ちた世界を見ないようにしてきたけれど──どうやらそれもおしまいらしい。
「できたよ」
数分経って、はさみの軽い音が聞こえなくなると目を開けて、と言われた。くすぐったさと切られた髪が目に入るのが嫌でずっと閉じていたのだ。
「……なんか、慣れないな」
「そう? 俺はいい感じにいったと思うよ。特にその綺麗な目が見れるようになったのは嬉しいね!」
ユーイオの目は珍しい琥珀色をしていた。青黒い髪と琥珀色の目は透き通っていて、人間とはとても思えないほどに綺麗だった。
「僕はあんまりこの目の色、好きじゃないんだ」
「え?」
「珍しい色だから、虐められて……」
せっかくゴミ捨て場から探して持って帰ってきたまだ食べられそうな残飯や盗んできた新鮮な食べ物も全部奪われるし、「一緒にいると不幸が移る」と噂されて孤独だったから。でも目の色なんて選べない。選べないのに、そんなことのせいで幸せはどんどん遠ざかっていく。だから嫌い。こんな僕の見た目も、僕をこんな見た目で産んだ名前も顔も知らない親も、見た目だけで人を虐げる人間も。
「そっかぁ……でもそれ君何も悪くないよね?」
「は?」
「どうして必死に生きようとしてきた君が、ただ見た目が珍しいだけでそこまで虐められなきゃいけないのさ。俺なんて頭時計だよ?」
「いや、それは異形だからで……」
「異形だとか関係ないよ。まあ……盗みは良くないけど。でもユーイオが食べ物を盗んだりしたのは生きるためだったろう? それなら悪いのはユーイオじゃなくてそんな街にした最上層部の奴らだ。それにそもそも見た目でその人の何が決まるって言うんだい?」
「……」
一日経って冷静さを取り戻した僕の頭は、この異形を言っていることが間違ってないことくらいすぐにわかった。この異形は自分が元々は人間だったこと、持っている異能まで人間の自分に話してくれた。きっと今の言葉は、かつて人間だった時間が流れていた彼だから言えたことだ。
「そんなことを言ってくれるのはきっとお前だけだ。……だからこそ訊きたいことがあるんだけど」
「うん? なんでも訊いてみてよ」
「その……リーエイは人間だったんだろ? どうしてその姿になったんだろうって気になったんだ」
あまり触れていいのかわからなかったが、リーエイなら答えてくれるのではないかという期待が口から零れていた。リーエイはああ、と少し天井の方へ顔を向けた後、黙った。
「リーエイ」
「いいよ。俺はね、人間だった頃は軍人だったんだ。軍人ってアレ、簡単に言うと武器とか使って戦う人ね」
──百年前の世界は、環境に気を遣うって精神がまずなかった。何をしたって自然は壊れない。人間が何をしようが自然環境に問題はない。そう考える奴らが多かった。だから大きな戦争はたくさん起きた。俺は大佐だった。決して下っ端の階級ではなかったけれど、かといってエリート階級なわけでもなかったから仕事は多かった。軍を、人々を率いて戦地に赴き毎日名前も知らない誰かを死なせる。今じゃ殺人は立派な犯罪だけど、当時は殺すことで名誉を得る時代だったから二十代で何も知らなかった俺は敵とはいえ同じ人間を殺すことに懸命になった。
「………ユーイオに異能の代償について話はしたっけ」
「いいや」
「そっか。じゃあこの際知っておいた方がいいね。異能の代償は異能の力が強ければ強いほど重くなるんだ。特に代償はその人にとってより不都合なものになりやすい。……ところでユーイオ、人を殺すことが正義だと信じ続けた人間がある日突然実はそれは悪だと突きつけられたらどうなると思う?」
「……正しいと思ってやっていたことが、悪いことだとわかったら」
「そう。君ならどうなる?」
そんな難しいことはあまり考えたことがないからわからない。でも、彼は僕が一発で正解を出すことは望んでいない。
「僕なら認めたくないからこそ人を殺し続けるかもしれない」
「そうだね、そんな人もいるだろう。でも俺は違う。俺は軍人になる前は殺人を「良くないこと」とわかっていたんだ。つまり殺人行為自体に良い印象がない。でもそれをしないと逆にこちらが殺られてしまう。初めの頃は生きるために仕方なくやっていたんだ。でも……いつしかその仕方なくは消えて成果のためになった」
自分や自分のやっていることを正当化することで平常心を保つしかなかったあの頃は、どの時代の中でも悲惨で残酷だった。長い戦いが終わって、勝利を告げられて喜んだのも一瞬、辺りは血だらけで草木も生えない土地に変わっていたことに気付き始める。仲間の中には手足を失った者もいたことを知る。生きているだけありがたいが、痛々しいと思う。自分が何も見えていなかったことに気付く。手足を失っただけで済んだ仲間は笑っている。その家族も戻ってきてくれただけでありがたいと喜びの涙を流す。──何かおかしい。仲間たちは手足を失ったとは生きている。じゃあ、俺が殺してきた相手は? 五体満足だが命はない。その家族は帰ってこないその人の帰りを待って待って待った先にその人の訃報と、運が良ければ遺骨が来る。本当にその人は死ぬ必要があったのだろうか。
「終戦して、勝って気付いたんだ。でも遅すぎた。俺の国は幸い強いから表立って文句を言われることは少ない。少ないけれど、言う奴はいるんだ。言わないと気が済まない。自分が壊れてしまうんだろうね。言われた文句にすぐにカッとする人もいたけれど、その文句を言われるようなことをやったのは誰? 俺たちだよ。だから、俺は勝った後すぐに軍を抜けた。最終的に三番目に多く人を殺したから昇級することになっていたけれど……でも辞めたよ。仲間たちにはもちろん引き止められたけどね」
それから人を無差別に殺す戦争行為が犯罪として扱われるようになった。どこかの国の偉い人は「平和に対する罪」と判決を下され絞首刑になったぐらいだ。戦争は平和に対する罪。無差別に行われる人殺しは罪。その戦争の中で多くの命を奪った俺は大罪人だ。
「名前がわかったら、命を奪った人の家族のもとへ謝りに行こうと思った。どんな罵詈雑言を言われようとも構わない。相手も、その家族もそれ以上に辛い思いをしていることくらいわかっていたから。でも……無理なんだ、足が国から出ようとしない。この期に及んで自分が酷い扱いを受けるかもしれないことを恐れていたんだ、僕は」
結局自国から出ることは出来ず、ただ家の中で毎日毎日一人で「すまなかった」と見えない彼らに謝るしか出来なかった。俺が背負うには重すぎる罪だと早く死ねないか、どうやったら簡単に死ねるのか。机の引き出しに銃があるのにそれには手を出さずにずっと考えた。
「そうしたらある日、全く知らない場所にいた」
それがここ、フォギーシティ。八十年前からずっと霧がかかった街。そこは俺に贖罪の時間を与えた。
「ここに来て半年で俺は今の姿になったよ。なんの前触れもなく、ね。起きたらこの姿になっていてびっくりしたよ。その頃は異形もまだ多くなかったし」
異形になったということは、他にも自分のような異形が居るのではと思った。案の定彼らは居たし、殺傷力の高そうな異能を持っている者も居たので早速殺してもらおうと思った。
「そうしたら、どれだけ体を剣や槍が貫いても首が飛んでも死なないんだ。気絶はするけれど、起きた時にはもう身体が全部治っていて。飛び出た内臓は綺麗に腹の中に納まっているし、かなり痛かったはずなのに切られた首はくっついているし。ああ、呪われてるんだって思ったよ。彼らは俺のやったことを許してはくれない。当たり前だよね。自分の名誉と命の為に名前も顔も知らないまま、たまたま彼らが目に入ったから殺していったそんな俺をさ。彼らが簡単に許してくれるわけがないんだよ」
「……」
「だから俺の異能の代償は【誰よりも長く生きること】。たとえどれだけ酷い怪我をしようが、病気をしようがね。……昔話ってつい長くなっちゃうね! 洗濯が終わっちゃったよ。役所に行くのは洗濯物を干してからでもいいかな?」
「え、あ、うん」
遠くを見るように、今までで一番感情が見えない話し方をしていたリーエイは話を終えた途端いつもの明るいリーエイに戻ってしまった。それにしても知らなかった。あれだけ明るいリーエイの人間時代に明るさが全くないとは思わなかった。
「リーエイ」
「ん?」
「僕……リーエイのこと嫌いにならないよ。今の話聴いて異形も人間と変わらないってわかったし。だから、昨日の態度はごめん………異形だからってあんな失礼なこと……」
自分の罪と誰よりも長く向き合わなければならない彼を少しくらい誰かが許して、彼に向き合う必要があると思ったら自然と出た言葉だった。
「別にいいよ。俺に謝る必要もないし、ユーイオが悪く思う必要もないよ」
「違う。悪いことをしたら謝るのは当たり前。許してほしいとかじゃなくて、これは礼儀。でしょ?」
リーエイの動きが一瞬止まった。また失礼なことをしてしまっただろうか。
「………ユーイオはいい子だね。俺みたいな罪人にならないように親として頑張るからね」
「……!」
初めて頭を撫でられた。時計の文字盤の顔は無機質でどんな表情を浮かべているのかさえはっきりとわからないが、きっと穏やかな、そしてどこか哀しそうな顔をしているのだろうと思った。
「ああそれと」
頭を撫でるためにわざわざしゃがんだリーエイが立ち上がる。
「俺みたいな後天性の異形には必ずどこかに人間だった頃の名残があるんだ。例えば俺なら時計の時刻。一時三十二分二十秒……これは人間として生きた最後の時だよ。覚えておくと役に立つ日が来るかもしれないね」
さ、洗濯物を干してしまおう。そう言ってリーエイはすたすたと洗濯機の方へ歩き出した。僕は一日経ってこの異形の養子になることに抵抗を感じなくなっていた。
『おはようございます、ただいま朝七時を迎えました。本日のふぉぐっとニュースは……』
──テレビが動いている。最下層で見るテレビは画面が割れていてとても使い物にならなかった。ごく稀に電源の入るものもあったが、そんなものを使えば電気代を払い終わる前に死んでしまうのでやはり使わずに置いてあるだけだったのだが。それにしてもすごい。こんなに綺麗になめらかに人が画面の中で動いている。ベッドから降りて、テレビに近付いて、画面に手を当てるとぱちっと痛みが走った。
「わっ」
「おはようユーイオ。俺のテレビは古いから画面に触ると静電気でぱちって痛くなるんだよ」
「お、おはよう……リーエイ」
歯磨きと顔洗いをしよう、と洗面所まで連れられる。
「こっちが水でこっちがお湯。もう春だし水で大丈夫だと思うよ」
ひねってみて、と蛇口をひねる。
「わあ……」
すごい。水が透明で、濁ってない。すごくきれい。
「はいこれ歯ブラシと歯磨き粉」
歯磨き粉がついた歯ブラシを渡される。歯ブラシを口に入れると歯磨き粉が優しい味をしていることにすぐ気付いた。泡立ちもいい。うがいをして、顔を水で濡らす。冷たくて気持ちいい。
「手、出してー」
リーエイに手を向けるとにゅっと何か手に出された。
「洗顔料だよ。ちょっと固めのペースト状にした石鹸みたいなやつ。少し水をかけてからだと泡立ちやすくなるかな」
リーエイに言われた通りにやってみる。洗顔料に水をかけて、水分を含ませてから両手を合わせてこする。
「うわっ落ちた」
しかし、初めから上手くいくわけではない。泡立ったもののその泡はぼとりと手からこぼれ落ちてしまった。
「慣れたらちゃんと出来るようになるよ。じゃあ俺は朝ごはん作るから」
そう言ってリーエイはキッチンへ向かってしまった。拭くものはこのまっさらなふわふわのタオルで良いのだろうか。
「あ、タオルはそれ使って。新品とか気にしなくていいからね」
後ろからリーエイの声が聞こえたので洗顔料を流し終わった後は綺麗なタオルで顔と手を拭いた。するりと皮脂のベタベタ感を感じない肌に僕は感動した。中層部でこんな暮らしなら上層部はどんな暮らしなのだろう。
「おまたせ~ユーイオがここに来て初めての朝ごはんだから俺張り切っちゃったよ!」
昨日は使えなかった食卓にはクロックムッシュとシーザーサラダ、ポタージュが並んでいた。
「ぜ、全部食べていいのか?」
「え? うん。一緒に食べたら美味しさ増えると思うよ」
そう言ってリーエイは僕の向かいに座った。ふと僕はあることを疑問に思った。
「リーエイ」
「ん? 味付け好きじゃなかった?」
「そうじゃなくて。リーエイってその顔でどうやって食べるんだろうって思って……」
「ああ!」
そんなことか、と言ってリーエイは笑った。
「安心してよユーイオ。これもパッシブスペルで何とでもなるから」
「え」
見ちゃダメだよ~と手で視界を塞がれる。何が起こっているのかわからないが、手を外され視界が広がった先に時計頭のリーエイは居なかった。代わりに昨日写真で見たあの綺麗な顔をしたリーエイが居た。
「ね? 食事の時とか人間としての顔が必要な時は一時的に戻れるから」
にぱっと明るい笑顔を向けられて、こいつはいつもこんな表情だったのだろうかと初めて感じた。
「リーエイ……人間だったんだな」
「え? そうだよ人間だよ~ちょっと色々あってあの姿だけど」
そう言いながらリーエイはフォークとナイフの使い方を僕に教え始める。
「俺は左利きなんだけど……ユーイオは?」
「利き手とか左右とかよくわからないけどこっちの方が力は強いかも」
そう言ってユーイオは左手を挙げる。
「じゃあ一緒だね。フォークは力が弱い方の手に持つ、ナイフは力が強い方の手に持つ」
「こう?」
「そう」
リーエイのテーブルマナーの教え方はとても上手く、一回でほとんどの作法が身についた。「リーエイって教えるの上手いな」と僕が言うと、「イギリスは紳士の国だからね」と得意げだった。
「さ、食べ終わったら食器を流しにつけておくよ」
リーエイはキッチンの流しに食器を置いて、そこに水道の水で軽く汚れを流していく。最下層ではやりたくてもできなかったことだと思った。最下層で食器を洗おうと思ったら、雨が降るのを待つことから始まるからだ。
「じゃ次は洗濯機回すよ、今から回しておけば役所に行って帰ってきた頃に脱水まで終わってるはずだからね」
よく分からないままついて行くと何回か外で見た記憶がある大きな機械があった。
「これね、入ったら最悪死ぬから入らないでね」
「えっ死ぬのか?」
「実際にそういう事故もあったよ」
淡々と話しながらリーエイはカゴに溜まっていた服を洗濯機に突っ込んでいく。
「香りの好き嫌いはある?」
「特にない……と思う」
「ん、わかった」
リーエイは小さな塊をひとつ洗濯機に入れたあと、色々あるボトルから「今日はこれかな」と一本取りだし、少しだけそれを洗濯機に入れた。
「あとはこれ」
「何それ」
「カルゲンだよ! この街は硬水が流れてるから、水を柔らかくしないと洗濯で服がダメになるんだよ。これを入れたら真水よりは温かい温度に設定して洗濯を始めるよ」
暮らしの質が上がると洗濯にもこれだけのものを使えるのか。洗剤となんかいい匂いがするやつ、カルゲン……。ステップが多いように見えるけど慣れるんだろうか。
「じゃ役所に行く前に前髪切ろっか」
「え」
「嫌?」
「……別に嫌じゃない」
見たことない大きな鏡の前に座らされる。確かに気にしたことはなかったが他人から見るとこの前髪はずいぶん厚く見えるようだ。
「どれくらい切る? 眉毛あたり?」
「よくわからないから適当に」
「おぉーおまかせだね! 任せてよ!」
しゃき、しゃきと前髪が切られていく。今までは青みを帯びたカーテンで、なるべく汚れ朽ちた世界を見ないようにしてきたけれど──どうやらそれもおしまいらしい。
「できたよ」
数分経って、はさみの軽い音が聞こえなくなると目を開けて、と言われた。くすぐったさと切られた髪が目に入るのが嫌でずっと閉じていたのだ。
「……なんか、慣れないな」
「そう? 俺はいい感じにいったと思うよ。特にその綺麗な目が見れるようになったのは嬉しいね!」
ユーイオの目は珍しい琥珀色をしていた。青黒い髪と琥珀色の目は透き通っていて、人間とはとても思えないほどに綺麗だった。
「僕はあんまりこの目の色、好きじゃないんだ」
「え?」
「珍しい色だから、虐められて……」
せっかくゴミ捨て場から探して持って帰ってきたまだ食べられそうな残飯や盗んできた新鮮な食べ物も全部奪われるし、「一緒にいると不幸が移る」と噂されて孤独だったから。でも目の色なんて選べない。選べないのに、そんなことのせいで幸せはどんどん遠ざかっていく。だから嫌い。こんな僕の見た目も、僕をこんな見た目で産んだ名前も顔も知らない親も、見た目だけで人を虐げる人間も。
「そっかぁ……でもそれ君何も悪くないよね?」
「は?」
「どうして必死に生きようとしてきた君が、ただ見た目が珍しいだけでそこまで虐められなきゃいけないのさ。俺なんて頭時計だよ?」
「いや、それは異形だからで……」
「異形だとか関係ないよ。まあ……盗みは良くないけど。でもユーイオが食べ物を盗んだりしたのは生きるためだったろう? それなら悪いのはユーイオじゃなくてそんな街にした最上層部の奴らだ。それにそもそも見た目でその人の何が決まるって言うんだい?」
「……」
一日経って冷静さを取り戻した僕の頭は、この異形を言っていることが間違ってないことくらいすぐにわかった。この異形は自分が元々は人間だったこと、持っている異能まで人間の自分に話してくれた。きっと今の言葉は、かつて人間だった時間が流れていた彼だから言えたことだ。
「そんなことを言ってくれるのはきっとお前だけだ。……だからこそ訊きたいことがあるんだけど」
「うん? なんでも訊いてみてよ」
「その……リーエイは人間だったんだろ? どうしてその姿になったんだろうって気になったんだ」
あまり触れていいのかわからなかったが、リーエイなら答えてくれるのではないかという期待が口から零れていた。リーエイはああ、と少し天井の方へ顔を向けた後、黙った。
「リーエイ」
「いいよ。俺はね、人間だった頃は軍人だったんだ。軍人ってアレ、簡単に言うと武器とか使って戦う人ね」
──百年前の世界は、環境に気を遣うって精神がまずなかった。何をしたって自然は壊れない。人間が何をしようが自然環境に問題はない。そう考える奴らが多かった。だから大きな戦争はたくさん起きた。俺は大佐だった。決して下っ端の階級ではなかったけれど、かといってエリート階級なわけでもなかったから仕事は多かった。軍を、人々を率いて戦地に赴き毎日名前も知らない誰かを死なせる。今じゃ殺人は立派な犯罪だけど、当時は殺すことで名誉を得る時代だったから二十代で何も知らなかった俺は敵とはいえ同じ人間を殺すことに懸命になった。
「………ユーイオに異能の代償について話はしたっけ」
「いいや」
「そっか。じゃあこの際知っておいた方がいいね。異能の代償は異能の力が強ければ強いほど重くなるんだ。特に代償はその人にとってより不都合なものになりやすい。……ところでユーイオ、人を殺すことが正義だと信じ続けた人間がある日突然実はそれは悪だと突きつけられたらどうなると思う?」
「……正しいと思ってやっていたことが、悪いことだとわかったら」
「そう。君ならどうなる?」
そんな難しいことはあまり考えたことがないからわからない。でも、彼は僕が一発で正解を出すことは望んでいない。
「僕なら認めたくないからこそ人を殺し続けるかもしれない」
「そうだね、そんな人もいるだろう。でも俺は違う。俺は軍人になる前は殺人を「良くないこと」とわかっていたんだ。つまり殺人行為自体に良い印象がない。でもそれをしないと逆にこちらが殺られてしまう。初めの頃は生きるために仕方なくやっていたんだ。でも……いつしかその仕方なくは消えて成果のためになった」
自分や自分のやっていることを正当化することで平常心を保つしかなかったあの頃は、どの時代の中でも悲惨で残酷だった。長い戦いが終わって、勝利を告げられて喜んだのも一瞬、辺りは血だらけで草木も生えない土地に変わっていたことに気付き始める。仲間の中には手足を失った者もいたことを知る。生きているだけありがたいが、痛々しいと思う。自分が何も見えていなかったことに気付く。手足を失っただけで済んだ仲間は笑っている。その家族も戻ってきてくれただけでありがたいと喜びの涙を流す。──何かおかしい。仲間たちは手足を失ったとは生きている。じゃあ、俺が殺してきた相手は? 五体満足だが命はない。その家族は帰ってこないその人の帰りを待って待って待った先にその人の訃報と、運が良ければ遺骨が来る。本当にその人は死ぬ必要があったのだろうか。
「終戦して、勝って気付いたんだ。でも遅すぎた。俺の国は幸い強いから表立って文句を言われることは少ない。少ないけれど、言う奴はいるんだ。言わないと気が済まない。自分が壊れてしまうんだろうね。言われた文句にすぐにカッとする人もいたけれど、その文句を言われるようなことをやったのは誰? 俺たちだよ。だから、俺は勝った後すぐに軍を抜けた。最終的に三番目に多く人を殺したから昇級することになっていたけれど……でも辞めたよ。仲間たちにはもちろん引き止められたけどね」
それから人を無差別に殺す戦争行為が犯罪として扱われるようになった。どこかの国の偉い人は「平和に対する罪」と判決を下され絞首刑になったぐらいだ。戦争は平和に対する罪。無差別に行われる人殺しは罪。その戦争の中で多くの命を奪った俺は大罪人だ。
「名前がわかったら、命を奪った人の家族のもとへ謝りに行こうと思った。どんな罵詈雑言を言われようとも構わない。相手も、その家族もそれ以上に辛い思いをしていることくらいわかっていたから。でも……無理なんだ、足が国から出ようとしない。この期に及んで自分が酷い扱いを受けるかもしれないことを恐れていたんだ、僕は」
結局自国から出ることは出来ず、ただ家の中で毎日毎日一人で「すまなかった」と見えない彼らに謝るしか出来なかった。俺が背負うには重すぎる罪だと早く死ねないか、どうやったら簡単に死ねるのか。机の引き出しに銃があるのにそれには手を出さずにずっと考えた。
「そうしたらある日、全く知らない場所にいた」
それがここ、フォギーシティ。八十年前からずっと霧がかかった街。そこは俺に贖罪の時間を与えた。
「ここに来て半年で俺は今の姿になったよ。なんの前触れもなく、ね。起きたらこの姿になっていてびっくりしたよ。その頃は異形もまだ多くなかったし」
異形になったということは、他にも自分のような異形が居るのではと思った。案の定彼らは居たし、殺傷力の高そうな異能を持っている者も居たので早速殺してもらおうと思った。
「そうしたら、どれだけ体を剣や槍が貫いても首が飛んでも死なないんだ。気絶はするけれど、起きた時にはもう身体が全部治っていて。飛び出た内臓は綺麗に腹の中に納まっているし、かなり痛かったはずなのに切られた首はくっついているし。ああ、呪われてるんだって思ったよ。彼らは俺のやったことを許してはくれない。当たり前だよね。自分の名誉と命の為に名前も顔も知らないまま、たまたま彼らが目に入ったから殺していったそんな俺をさ。彼らが簡単に許してくれるわけがないんだよ」
「……」
「だから俺の異能の代償は【誰よりも長く生きること】。たとえどれだけ酷い怪我をしようが、病気をしようがね。……昔話ってつい長くなっちゃうね! 洗濯が終わっちゃったよ。役所に行くのは洗濯物を干してからでもいいかな?」
「え、あ、うん」
遠くを見るように、今までで一番感情が見えない話し方をしていたリーエイは話を終えた途端いつもの明るいリーエイに戻ってしまった。それにしても知らなかった。あれだけ明るいリーエイの人間時代に明るさが全くないとは思わなかった。
「リーエイ」
「ん?」
「僕……リーエイのこと嫌いにならないよ。今の話聴いて異形も人間と変わらないってわかったし。だから、昨日の態度はごめん………異形だからってあんな失礼なこと……」
自分の罪と誰よりも長く向き合わなければならない彼を少しくらい誰かが許して、彼に向き合う必要があると思ったら自然と出た言葉だった。
「別にいいよ。俺に謝る必要もないし、ユーイオが悪く思う必要もないよ」
「違う。悪いことをしたら謝るのは当たり前。許してほしいとかじゃなくて、これは礼儀。でしょ?」
リーエイの動きが一瞬止まった。また失礼なことをしてしまっただろうか。
「………ユーイオはいい子だね。俺みたいな罪人にならないように親として頑張るからね」
「……!」
初めて頭を撫でられた。時計の文字盤の顔は無機質でどんな表情を浮かべているのかさえはっきりとわからないが、きっと穏やかな、そしてどこか哀しそうな顔をしているのだろうと思った。
「ああそれと」
頭を撫でるためにわざわざしゃがんだリーエイが立ち上がる。
「俺みたいな後天性の異形には必ずどこかに人間だった頃の名残があるんだ。例えば俺なら時計の時刻。一時三十二分二十秒……これは人間として生きた最後の時だよ。覚えておくと役に立つ日が来るかもしれないね」
さ、洗濯物を干してしまおう。そう言ってリーエイはすたすたと洗濯機の方へ歩き出した。僕は一日経ってこの異形の養子になることに抵抗を感じなくなっていた。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

少年、その愛 〜愛する男に斬られるのもまた甘美か?〜
西浦夕緋
キャラ文芸
15歳の少年篤弘はある日、夏朗と名乗る17歳の少年と出会う。
彼は篤弘の初恋の少女が入信を望み続けた宗教団体・李凰国(りおうこく)の男だった。
亡くなった少女の想いを受け継ぎ篤弘は李凰国に入信するが、そこは想像を絶する世界である。
罪人の公開処刑、抗争する新興宗教団体に属する少女の殺害、
そして十数年前に親元から拉致され李凰国に迎え入れられた少年少女達の運命。
「愛する男に斬られるのもまた甘美か?」
李凰国に正義は存在しない。それでも彼は李凰国を愛した。
「おまえの愛の中に散りゆくことができるのを嬉しく思う。」
李凰国に生きる少年少女達の魂、信念、孤独、そして愛を描く。

化想操術師の日常
茶野森かのこ
キャラ文芸
たった一つの線で、世界が変わる。
化想操術師という仕事がある。
一般的には知られていないが、化想は誰にでも起きる可能性のある現象で、悲しみや苦しみが心に抱えきれなくなった時、人は無意識の内に化想と呼ばれるものを体の外に生み出してしまう。それは、空間や物や生き物と、その人の心を占めるものである為、様々だ。
化想操術師とは、頭の中に思い描いたものを、その指先を通して、現実に生み出す事が出来る力を持つ人達の事。本来なら無意識でしか出せない化想を、意識的に操る事が出来た。
クズミ化想社は、そんな化想に苦しむ人々に寄り添い、救う仕事をしている。
社長である九頭見志乃歩は、自身も化想を扱いながら、化想患者限定でカウンセラーをしている。
社員は自身を含めて四名。
九頭見野雪という少年は、化想を生み出す能力に長けていた。志乃歩の養子に入っている。
常に無表情であるが、それは感情を失わせるような過去があったからだ。それでも、志乃歩との出会いによって、その心はいつも誰かに寄り添おうとしている、優しい少年だ。
他に、志乃歩の秘書でもある黒兎、口は悪いが料理の腕前はピカイチの姫子、野雪が生み出した巨大な犬の化想のシロ。彼らは、山の中にある洋館で、賑やかに共同生活を送っていた。
その洋館に、新たな住人が加わった。
記憶を失った少女、たま子。化想が扱える彼女は、記憶が戻るまでの間、野雪達と共に過ごす事となった。
だが、記憶を失くしたたま子には、ある目的があった。
たま子はクズミ化想社の一人として、志乃歩や野雪と共に、化想を出してしまった人々の様々な思いに触れていく。
壊れた友情で海に閉じこもる少年、自分への後悔に復讐に走る女性、絵を描く度に化想を出してしまう少年。
化想操術の古い歴史を持つ、阿木之亥という家の人々、重ねた野雪の過去、初めて出来た好きなもの、焦がれた自由、犠牲にしても守らなきゃいけないもの。
野雪とたま子、化想を取り巻く彼らのお話です。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。
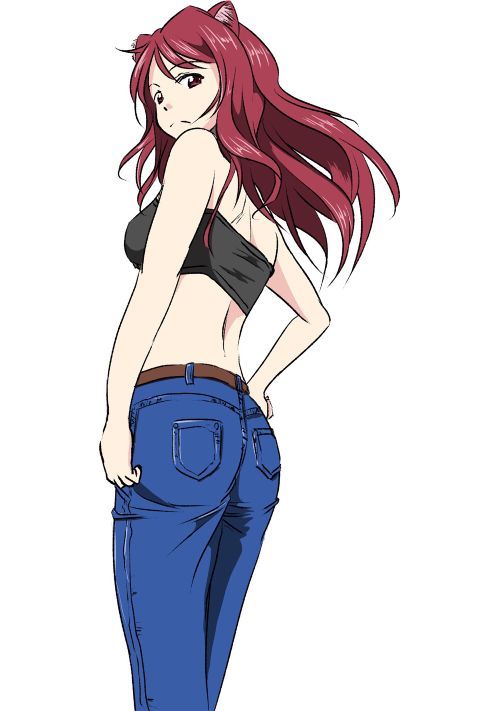
遥か
カリフォルニアデスロールの野良兎
キャラ文芸
鶴木援(ツルギタスケ)は、疲労状態で仕事から帰宅する。何も無い日常にトラウマを抱えた過去、何も起きなかったであろう未来を抱えたまま、何故か誤って監獄街に迷い込む。
生きることを問いかける薄暗いロー・ファンタジー。
表紙 @kafui_k_h

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

スライム10,000体討伐から始まるハーレム生活
昼寝部
ファンタジー
この世界は12歳になったら神からスキルを授かることができ、俺も12歳になった時にスキルを授かった。
しかし、俺のスキルは【@&¥#%】と正しく表記されず、役に立たないスキルということが判明した。
そんな中、両親を亡くした俺は妹に不自由のない生活を送ってもらうため、冒険者として活動を始める。
しかし、【@&¥#%】というスキルでは強いモンスターを討伐することができず、3年間冒険者をしてもスライムしか倒せなかった。
そんなある日、俺がスライムを10,000体討伐した瞬間、スキル【@&¥#%】がチートスキルへと変化して……。
これは、ある日突然、最強の冒険者となった主人公が、今まで『スライムしか倒せないゴミ』とバカにしてきた奴らに“ざまぁ”し、美少女たちと幸せな日々を過ごす物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















