19 / 23
番人と罪人
19話
しおりを挟む
ツェリアエリスの家には寝具や寝室がない。
ツェリアエリス自身がそうそう睡眠を必要にするわけではないのだけれど、時折眠くなると、居間のソファを寝床にするのが常だった。
この日もそうしてうつらうつらしていた。普段は聞き慣れていて意識しない雨垂れの音を意識するのはこういう時だ。激しくもなく、弱くもない音。時々風が出ると窓や壁に当たって弾ける音も加わる。滑り出し窓はずっと開いたままなので、暖炉の火も落としてしまうと、静まり返った家にやけに響くのだ。
ソファを二つ繋げて思いきり体を伸ばして横になって、天井の魔法の明かりも消すと、真昼なのに真夜中のようだった。木窓の隙間から差し込む光が部屋の雑多な物の影を濃くしていて、ツェリアエリスはぼうっとしながら心に呟いた。
(そろそろ、マリオンが来るころかな)
ツェリアエリス自身はそんなに必要性を見出だしていないけれど、マリオンは片付けにうるさい。何年も足しげく通っているから、どのくらいの期間で部屋が物だらけになるか、溢れかえるのはどのタイミングか、察するようになっていて、その機会を見計らってやって来る。
一応、役所に任された仕事を理由に赴いているわりに、個人的な手土産を欠かさないし、ツェリアエリスに説教しつつもなんだかんだ世話焼きな一面を発揮するし、修練だと言って武芸の手合わせにツェリアエリスを引っ張り込むしと、好き放題だ。
それでも、嫌ではないから、毎度毎度ツェリアエリスは玄関のドアを開けてやる。マリオンはどんなに図々しくても、客として最低限の礼儀を守って、ノックもなく勝手に立ち入ったりしないのだ。線引きを必ず忘れないからこそ長続きしている関係だった。
そう考えていたら本当にノックの音が鳴って、ツェリアエリスは微笑んだ。
起き上がるとひとりでに居間が明るくなった。暖炉にも魔法の火を入れたので、気づいたデリアメルフィが手透きならすぐにやって来るだろう。もれなく片付けを手伝わされる羽目になるけれど、ツェリアエリスのように茶のもてなしができず、マリオンの世界を慮ってあからさまな加護も与えられない分、お菓子の返礼のためにせめて大人しくしているのだ。
手伝わないとお菓子にありつけなくなるから、という切実な理由は、あえて見ないふりをしておく。
「マリオン、いらっしゃい。開いているのでどうぞ」
玄関に向かって声を張り上げながら、お茶の保管部屋に行く。そこに、マリオンがひょっこりと顔を出して、呆れた顔になった。
「あんた、相変わらずだな。居間はあの惨状なのに、どうしてここはこんなに整頓されているんだ」
「趣味に全力投球しているので」
棚から瓶を取り出しながら、普段は言わないことを冗談めかして言った。
「はじめに掃除なんですよね?終わるまではここに避難しておきます。今日はどんなお菓子ですか?」
片付けには一切才能がないツェリアエリスはのっけから戦力外だ。家主のくせに全然役に立たないので、客なのに片付け主戦力のマリオンが「邪魔になるからどこかに出ていろ」と昔に言ったことを、律儀に守っている。終わるまで待つ間に、お菓子に合うお茶を用意しておこうと思ったのだ。マリオンもすぐに頷いて答えた。
「こないだ職場で、お裾分けにたくさん果物もらったんだ。せっかくだからフルーツタルトにした」
「それは豪勢ですね」
「傷があったり、形が悪いものはジャムにするつもりなんだが、それにしても量が量だから、奮発した。テレサも大喜びだったよ」
「ジャムですか」
「そっちはまだ作ってない。食べるならスコーンか、クッキーか……」
「お茶に落としてみるのも面白いと思いますよ。マーガレットの持っていた本にもそのような飲み方が書いてありました」
ふと思い出して言ってみると、マリオンは驚きと呆れとを、顔に器用に並べてみせた。なんといっても、かつてツェリアエリスに茶菓子という概念を植え付けたのはマリオンである。
「あんた、それはおれに、ジャムとは別に差し入れを作ってこいってことか?」
「それは……考えていませんでした」
さすがに、ツェリアエリスは素直に「作ってほしい」とは言わなかったものの、前もって釘を刺されたと感じて眉が落ちたのは仕方なかった。それだけマリオンのお菓子はおいしいのだ。
マリオンはやれやれと大きなため息をついた。呆れた表情は変わらないが、今度は笑みを含んでいた。見る者の視線を受け止めて離さない、柔らかさと深みのある笑みだ。
初めて出会った頃から立派に大きくなったものだと、ツェリアエリスは今さら感心した。
「ずいぶん太くなったもんだよな。いいよ、作ってやる」
「いいんですか?」
「言ってみれば、掃除も菓子もおれの趣味だ。もちろん恩義だってあるけど、あんたにはそれに付き合ってもらってるようなものだから。その分、もう少しあんたの趣味にまともに付き合ってもいいだろうと思ったんだ」
思ってもみなかった返答にびっくりしている間に、マリオンが居間の掃除に向かっていった。
部屋に一人になったツェリアエリスは、いつにない真剣な表情で、重々しく頷いた。
「なるほど、掃除も趣味だったんですね」
マリオンに聞かれていたら、お菓子抜きになること間違いなしの感想だった。
半妖精の家の居間の掃除は、あちこちに溢れている雑多な物をとりあえず分別することからだ。
食器やティーセットはキッチンの流しへ、他の小物は埃を落として棚へ勝手に仕舞ってしまう。いくつかの茶缶も相変わらず出しっぱなしだったので、マリオンは呆れてしまった。
ツェリアエリスは「暇潰し」にはとことん全力で取り組むが、作っただけで満足していた節がある。以前の暇潰しだった手芸の力作にしろ、この茶缶にしろ、扱いが雑なのだ。劣化しないように魔法をかけているというのでまだましだが、ハーブの調合部屋はあれだけきっちり整頓されているから、本当なら居間もきれいにできるはずなのだ。
けれど、ツェリアエリスには片付けがどうしてもできない。
「今日も今日とて、やりがいがあってけっこうだ」
マリオンが真顔で呟いていると、視界の端で暖炉の火がぱっと燃え上がった。瞬きのあと、暖炉の手前に火の妖精が現れている。マリオンはもう慣れていたので片手で挨拶をするだけだ。妖精の中でも特に火の性質を持つものには、生まれた世界でいえば恭しく接するのが常識だったけれど、マリオンはこの家では以前のように――彼らが妹の友だちだった頃のように、気軽にするように努めている。
「お、まだ始めたばかりか?」
「ああ。あんたがいるなら、そろそろ季節が巡るから模様替えもついでにやるかな」
「ふーん。次は春か」
デリアメルフィが指先を向けた先のクッションカバーがふわりと浮いた。
「それなら洗ってあげようか?」
マリオンでもデリアメルフィでもなく、ツェリアエリスのものでもない声がして、マリオンはとっさに身構えた。声のした方に目だけを向けると、キッチンから水の妖精が出てくるところだった。もちろん人間の青年の形を模している。
マリオンと目が合うと、垂れた目を親しげに細くした。
「やあ、マリオン。この間ぶり」
「この家だと久しぶりだな」
この妖精、名前はユゥマジェン・ドルシィラゲンという。ツェリアエリスの友だちその二だ。デリアメルフィよりも会う機会の少ない妖精だが、ユゥマジェンの言うとおり、つい最近に会っていた。それも、マリオンの世界でだ。
異世界の人間が迷い込むという、恐ろしい事態に奔走していたマリオンをこっそり呼び止めて、妖精側でなんとかしたからもう大丈夫と伝えてくれたのだ。
迷い込んだ原因は教えてもらえなかったが、とにもかくにも、マリオンの世界に異世界の人間がいることが直近の危険だったので、そこが解決しただけでも、マリオンにとっては肩の荷が降りたようなものだった。だからといってさっぱり忘れられるほど薄情でもないけれど、マリオンはこのふたりに「マーガレットは無事か」と尋ねるようなことはしない。
それでなくても今は掃除の時間だ。
「ふたりもいるなら、茶の時間が早まるな」
「そういえば、今日のお菓子はなにかな?ツェルとアメルには最近だけど、ぼくはこのところ全然食べていなかったからね」
「フルーツタルトだ。具材が多いからって大きめに焼いたのは、正解だったな」
「ぼくは運がいいようだ」
ユゥマジェンがにっこりと笑った一方で、デリアメルフィが苦いものを噛んだような表情だった。マリオンがそれを不思議に思って見ていると、視線に気づいたデリアメルフィはふいと顔を背けて、「さっさと掃除を終わらせるぞ」と言った。
「ユーマ、古いのを洗うならついでに新しいものも洗え」
「はいはい」
ガラス棚やテーブルが浮いて、カーペットがひとりでに巻き上がり、タペストリーが壁から剥がされた。ユゥマジェンが回収した端からもとの位置に戻されて、ユゥマジェンは手芸作品を従えて納戸にすたすた歩いている。
惜しげもない魔法の大盤振る舞いに、マリオンは無言で見入った。
マリオンの世界でも人間は妖精と親しんでいるものの、いつでも妖精の魔法をあてにできるわけではない。そのため、この光景はある意味圧巻だったが、身も蓋もない感想が出てくるのは仕方がないことだった。
(こうも当然のように使われると、ありがたみが薄れてくるな)
ため息をついている間にも、デリアメルフィが暖炉の煤や床の埃を魔法でかき集めている。
マリオンも肩をすくめて気持ちを切り替えて、掃除を再開することにした。
こんな調子だったので、反則級の早さでお茶の時間が訪れた。
妖精ふたりと半妖精が至福の表情で人間の作ったお菓子を食べているのを、マリオンはツェリアエリスのお茶を飲みながら見ていた。癖が少なくて、ほんのり甘味と強めの苦味が出ているお茶だ。マリオンもタルトをひと切れ食べて、なるほどと感心した。よく合っている。ツェリアエリスがマリオンの表情に気づいて笑いかけた。
「このお茶、ジャムにも合うんじゃないでしょうか?」
「よほど楽しみなんだな……」
「なに?ジャム?なんのこと?」
「ジャムを茶に混ぜるのか?うまいのかそれ」
俄然身を乗り出した妖精ふたりは意図的に見なかったふりをした。実はマリオンは、みんながひと口分食べるのを今か今かと待ち構えていたのだ。
「半妖精、マーガレットはどうなった?」
妖精ふたりの態度の変化は顕著だった。デリアメルフィはティーカップを口に当てたまま明後日の方向に顔を背けて、ユゥマジェンは黙々とタルトの固い生地をつついている。マリオンがこれを見ていたように、ツェリアエリスも見ていた。
やっぱりなと言わんばかりに半目のマリオンに、ツェリアエリスが苦笑して向き直った。
「君に適切に匿ってもらえたのは、本当に助かりました」
「きちんと帰られたんだな?」
「はい。アメルが迎えに行って、マーガレットの世界へも直に送ってくれたので」
「……となると、あれは事故じゃないんだな?送らないとまたどこかに飛ばされたかもしれないのか」
「そこはなんとも。ああ、人間に言えないというわけではなくて、実は私にも原因がよくわかっていないんです」
「なんだって?」
「カルムがこういうことを得意なので、マーガレットに会ってもらったんです。そこでなにかわかったのは明らかなんですが……教えてくれないんですよね」
「なんでだ。あんたは境界の番人なんだろう。あんたが知らないでどうするっていうんだ」
「私も同じように訴えたんですが、『担当者』の総意のようでして」
「担当?」
「カルムと、ここにいるアメルとユーマです。結果が出れば教えるから、もう少し待てと言われたら、言及のしようがありません。まだ私の仕事ではないらしいですね」
「それにしてもだろう!」
マリオンはじろっと妖精ふたりを睨んだ。ツェリアエリスもそうだが、こうなると、当然、マーガレットも知らないのだ。なにかあって一番困るのはこの二人なのに。
これだから妖精は、と内心で舌打ちしたけれど、この考えが間違っているのはマリオンもわかっている。妖精は人間ではないのだから、人間に求めるような気遣いを、妖精にも同じように求めるのは無駄なのだ。今だけ見た目は同じ人間でも、マリオンは彼らと自分たちとの違いを、幼い頃に痛いほどに思い知らされた。
しかし、マリオンはテレサと同じくらいに、人間の中では例外だった。
目を絶対に合わせようとしない妖精ふたりに、今にも噛みつきそうな眼光のまま、にっこりと笑ってみせた。
「さっきグータラと話をしていたんだが、ハーブティーにジャムを落として飲むから、別に茶菓子が必要ということになったんだ。――グータラ喜べ。ジャムも別の菓子もお前の独り占めだ」
「おや、本当ですか?」
「なっ」
「そんなあ!」
ツェリアエリスは目を輝かせ、デリアメルフィはぎょっとマリオンを振り返り、ユゥマジェンはフォークを咥えたまま悲鳴を上げた。
「なににしようかな。最近はパイを作っていないから、それにしようか。パイにも色々あるからな。ミンスパイやミルフィーユ、ああキッシュでもいいな」
にこにこと楽しげに喋るマリオンに、もちろん容赦の文字はないのである。
ツェリアエリス自身がそうそう睡眠を必要にするわけではないのだけれど、時折眠くなると、居間のソファを寝床にするのが常だった。
この日もそうしてうつらうつらしていた。普段は聞き慣れていて意識しない雨垂れの音を意識するのはこういう時だ。激しくもなく、弱くもない音。時々風が出ると窓や壁に当たって弾ける音も加わる。滑り出し窓はずっと開いたままなので、暖炉の火も落としてしまうと、静まり返った家にやけに響くのだ。
ソファを二つ繋げて思いきり体を伸ばして横になって、天井の魔法の明かりも消すと、真昼なのに真夜中のようだった。木窓の隙間から差し込む光が部屋の雑多な物の影を濃くしていて、ツェリアエリスはぼうっとしながら心に呟いた。
(そろそろ、マリオンが来るころかな)
ツェリアエリス自身はそんなに必要性を見出だしていないけれど、マリオンは片付けにうるさい。何年も足しげく通っているから、どのくらいの期間で部屋が物だらけになるか、溢れかえるのはどのタイミングか、察するようになっていて、その機会を見計らってやって来る。
一応、役所に任された仕事を理由に赴いているわりに、個人的な手土産を欠かさないし、ツェリアエリスに説教しつつもなんだかんだ世話焼きな一面を発揮するし、修練だと言って武芸の手合わせにツェリアエリスを引っ張り込むしと、好き放題だ。
それでも、嫌ではないから、毎度毎度ツェリアエリスは玄関のドアを開けてやる。マリオンはどんなに図々しくても、客として最低限の礼儀を守って、ノックもなく勝手に立ち入ったりしないのだ。線引きを必ず忘れないからこそ長続きしている関係だった。
そう考えていたら本当にノックの音が鳴って、ツェリアエリスは微笑んだ。
起き上がるとひとりでに居間が明るくなった。暖炉にも魔法の火を入れたので、気づいたデリアメルフィが手透きならすぐにやって来るだろう。もれなく片付けを手伝わされる羽目になるけれど、ツェリアエリスのように茶のもてなしができず、マリオンの世界を慮ってあからさまな加護も与えられない分、お菓子の返礼のためにせめて大人しくしているのだ。
手伝わないとお菓子にありつけなくなるから、という切実な理由は、あえて見ないふりをしておく。
「マリオン、いらっしゃい。開いているのでどうぞ」
玄関に向かって声を張り上げながら、お茶の保管部屋に行く。そこに、マリオンがひょっこりと顔を出して、呆れた顔になった。
「あんた、相変わらずだな。居間はあの惨状なのに、どうしてここはこんなに整頓されているんだ」
「趣味に全力投球しているので」
棚から瓶を取り出しながら、普段は言わないことを冗談めかして言った。
「はじめに掃除なんですよね?終わるまではここに避難しておきます。今日はどんなお菓子ですか?」
片付けには一切才能がないツェリアエリスはのっけから戦力外だ。家主のくせに全然役に立たないので、客なのに片付け主戦力のマリオンが「邪魔になるからどこかに出ていろ」と昔に言ったことを、律儀に守っている。終わるまで待つ間に、お菓子に合うお茶を用意しておこうと思ったのだ。マリオンもすぐに頷いて答えた。
「こないだ職場で、お裾分けにたくさん果物もらったんだ。せっかくだからフルーツタルトにした」
「それは豪勢ですね」
「傷があったり、形が悪いものはジャムにするつもりなんだが、それにしても量が量だから、奮発した。テレサも大喜びだったよ」
「ジャムですか」
「そっちはまだ作ってない。食べるならスコーンか、クッキーか……」
「お茶に落としてみるのも面白いと思いますよ。マーガレットの持っていた本にもそのような飲み方が書いてありました」
ふと思い出して言ってみると、マリオンは驚きと呆れとを、顔に器用に並べてみせた。なんといっても、かつてツェリアエリスに茶菓子という概念を植え付けたのはマリオンである。
「あんた、それはおれに、ジャムとは別に差し入れを作ってこいってことか?」
「それは……考えていませんでした」
さすがに、ツェリアエリスは素直に「作ってほしい」とは言わなかったものの、前もって釘を刺されたと感じて眉が落ちたのは仕方なかった。それだけマリオンのお菓子はおいしいのだ。
マリオンはやれやれと大きなため息をついた。呆れた表情は変わらないが、今度は笑みを含んでいた。見る者の視線を受け止めて離さない、柔らかさと深みのある笑みだ。
初めて出会った頃から立派に大きくなったものだと、ツェリアエリスは今さら感心した。
「ずいぶん太くなったもんだよな。いいよ、作ってやる」
「いいんですか?」
「言ってみれば、掃除も菓子もおれの趣味だ。もちろん恩義だってあるけど、あんたにはそれに付き合ってもらってるようなものだから。その分、もう少しあんたの趣味にまともに付き合ってもいいだろうと思ったんだ」
思ってもみなかった返答にびっくりしている間に、マリオンが居間の掃除に向かっていった。
部屋に一人になったツェリアエリスは、いつにない真剣な表情で、重々しく頷いた。
「なるほど、掃除も趣味だったんですね」
マリオンに聞かれていたら、お菓子抜きになること間違いなしの感想だった。
半妖精の家の居間の掃除は、あちこちに溢れている雑多な物をとりあえず分別することからだ。
食器やティーセットはキッチンの流しへ、他の小物は埃を落として棚へ勝手に仕舞ってしまう。いくつかの茶缶も相変わらず出しっぱなしだったので、マリオンは呆れてしまった。
ツェリアエリスは「暇潰し」にはとことん全力で取り組むが、作っただけで満足していた節がある。以前の暇潰しだった手芸の力作にしろ、この茶缶にしろ、扱いが雑なのだ。劣化しないように魔法をかけているというのでまだましだが、ハーブの調合部屋はあれだけきっちり整頓されているから、本当なら居間もきれいにできるはずなのだ。
けれど、ツェリアエリスには片付けがどうしてもできない。
「今日も今日とて、やりがいがあってけっこうだ」
マリオンが真顔で呟いていると、視界の端で暖炉の火がぱっと燃え上がった。瞬きのあと、暖炉の手前に火の妖精が現れている。マリオンはもう慣れていたので片手で挨拶をするだけだ。妖精の中でも特に火の性質を持つものには、生まれた世界でいえば恭しく接するのが常識だったけれど、マリオンはこの家では以前のように――彼らが妹の友だちだった頃のように、気軽にするように努めている。
「お、まだ始めたばかりか?」
「ああ。あんたがいるなら、そろそろ季節が巡るから模様替えもついでにやるかな」
「ふーん。次は春か」
デリアメルフィが指先を向けた先のクッションカバーがふわりと浮いた。
「それなら洗ってあげようか?」
マリオンでもデリアメルフィでもなく、ツェリアエリスのものでもない声がして、マリオンはとっさに身構えた。声のした方に目だけを向けると、キッチンから水の妖精が出てくるところだった。もちろん人間の青年の形を模している。
マリオンと目が合うと、垂れた目を親しげに細くした。
「やあ、マリオン。この間ぶり」
「この家だと久しぶりだな」
この妖精、名前はユゥマジェン・ドルシィラゲンという。ツェリアエリスの友だちその二だ。デリアメルフィよりも会う機会の少ない妖精だが、ユゥマジェンの言うとおり、つい最近に会っていた。それも、マリオンの世界でだ。
異世界の人間が迷い込むという、恐ろしい事態に奔走していたマリオンをこっそり呼び止めて、妖精側でなんとかしたからもう大丈夫と伝えてくれたのだ。
迷い込んだ原因は教えてもらえなかったが、とにもかくにも、マリオンの世界に異世界の人間がいることが直近の危険だったので、そこが解決しただけでも、マリオンにとっては肩の荷が降りたようなものだった。だからといってさっぱり忘れられるほど薄情でもないけれど、マリオンはこのふたりに「マーガレットは無事か」と尋ねるようなことはしない。
それでなくても今は掃除の時間だ。
「ふたりもいるなら、茶の時間が早まるな」
「そういえば、今日のお菓子はなにかな?ツェルとアメルには最近だけど、ぼくはこのところ全然食べていなかったからね」
「フルーツタルトだ。具材が多いからって大きめに焼いたのは、正解だったな」
「ぼくは運がいいようだ」
ユゥマジェンがにっこりと笑った一方で、デリアメルフィが苦いものを噛んだような表情だった。マリオンがそれを不思議に思って見ていると、視線に気づいたデリアメルフィはふいと顔を背けて、「さっさと掃除を終わらせるぞ」と言った。
「ユーマ、古いのを洗うならついでに新しいものも洗え」
「はいはい」
ガラス棚やテーブルが浮いて、カーペットがひとりでに巻き上がり、タペストリーが壁から剥がされた。ユゥマジェンが回収した端からもとの位置に戻されて、ユゥマジェンは手芸作品を従えて納戸にすたすた歩いている。
惜しげもない魔法の大盤振る舞いに、マリオンは無言で見入った。
マリオンの世界でも人間は妖精と親しんでいるものの、いつでも妖精の魔法をあてにできるわけではない。そのため、この光景はある意味圧巻だったが、身も蓋もない感想が出てくるのは仕方がないことだった。
(こうも当然のように使われると、ありがたみが薄れてくるな)
ため息をついている間にも、デリアメルフィが暖炉の煤や床の埃を魔法でかき集めている。
マリオンも肩をすくめて気持ちを切り替えて、掃除を再開することにした。
こんな調子だったので、反則級の早さでお茶の時間が訪れた。
妖精ふたりと半妖精が至福の表情で人間の作ったお菓子を食べているのを、マリオンはツェリアエリスのお茶を飲みながら見ていた。癖が少なくて、ほんのり甘味と強めの苦味が出ているお茶だ。マリオンもタルトをひと切れ食べて、なるほどと感心した。よく合っている。ツェリアエリスがマリオンの表情に気づいて笑いかけた。
「このお茶、ジャムにも合うんじゃないでしょうか?」
「よほど楽しみなんだな……」
「なに?ジャム?なんのこと?」
「ジャムを茶に混ぜるのか?うまいのかそれ」
俄然身を乗り出した妖精ふたりは意図的に見なかったふりをした。実はマリオンは、みんながひと口分食べるのを今か今かと待ち構えていたのだ。
「半妖精、マーガレットはどうなった?」
妖精ふたりの態度の変化は顕著だった。デリアメルフィはティーカップを口に当てたまま明後日の方向に顔を背けて、ユゥマジェンは黙々とタルトの固い生地をつついている。マリオンがこれを見ていたように、ツェリアエリスも見ていた。
やっぱりなと言わんばかりに半目のマリオンに、ツェリアエリスが苦笑して向き直った。
「君に適切に匿ってもらえたのは、本当に助かりました」
「きちんと帰られたんだな?」
「はい。アメルが迎えに行って、マーガレットの世界へも直に送ってくれたので」
「……となると、あれは事故じゃないんだな?送らないとまたどこかに飛ばされたかもしれないのか」
「そこはなんとも。ああ、人間に言えないというわけではなくて、実は私にも原因がよくわかっていないんです」
「なんだって?」
「カルムがこういうことを得意なので、マーガレットに会ってもらったんです。そこでなにかわかったのは明らかなんですが……教えてくれないんですよね」
「なんでだ。あんたは境界の番人なんだろう。あんたが知らないでどうするっていうんだ」
「私も同じように訴えたんですが、『担当者』の総意のようでして」
「担当?」
「カルムと、ここにいるアメルとユーマです。結果が出れば教えるから、もう少し待てと言われたら、言及のしようがありません。まだ私の仕事ではないらしいですね」
「それにしてもだろう!」
マリオンはじろっと妖精ふたりを睨んだ。ツェリアエリスもそうだが、こうなると、当然、マーガレットも知らないのだ。なにかあって一番困るのはこの二人なのに。
これだから妖精は、と内心で舌打ちしたけれど、この考えが間違っているのはマリオンもわかっている。妖精は人間ではないのだから、人間に求めるような気遣いを、妖精にも同じように求めるのは無駄なのだ。今だけ見た目は同じ人間でも、マリオンは彼らと自分たちとの違いを、幼い頃に痛いほどに思い知らされた。
しかし、マリオンはテレサと同じくらいに、人間の中では例外だった。
目を絶対に合わせようとしない妖精ふたりに、今にも噛みつきそうな眼光のまま、にっこりと笑ってみせた。
「さっきグータラと話をしていたんだが、ハーブティーにジャムを落として飲むから、別に茶菓子が必要ということになったんだ。――グータラ喜べ。ジャムも別の菓子もお前の独り占めだ」
「おや、本当ですか?」
「なっ」
「そんなあ!」
ツェリアエリスは目を輝かせ、デリアメルフィはぎょっとマリオンを振り返り、ユゥマジェンはフォークを咥えたまま悲鳴を上げた。
「なににしようかな。最近はパイを作っていないから、それにしようか。パイにも色々あるからな。ミンスパイやミルフィーユ、ああキッシュでもいいな」
にこにこと楽しげに喋るマリオンに、もちろん容赦の文字はないのである。
10
お気に入りに追加
4
あなたにおすすめの小説

桃岡駅の忘れ物センターは、今日も皆さん騒がしい。
桜乃
児童書・童話
桃岡駅(とうおかえき)の忘れ物センターに連れてこられたピンクの傘の物語。
※この物語に出てくる、駅、路線などはフィクションです。
※7000文字程度の短編です。1ページの文字数は少な目です。
2/8に完結予定です。
お読みいただきありがとうございました。
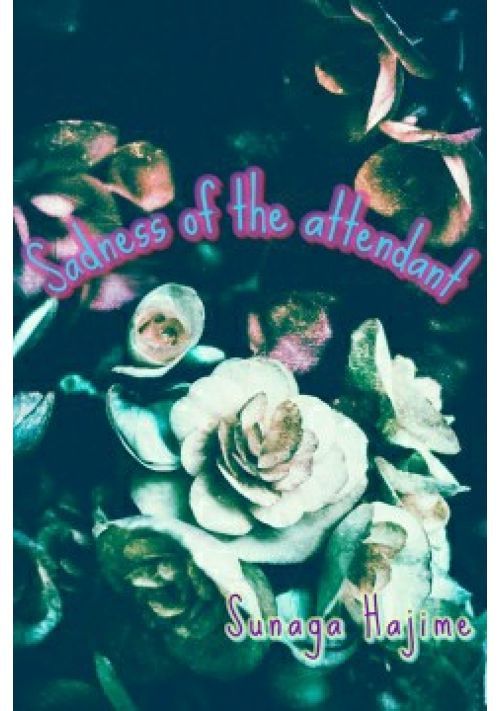
Sadness of the attendant
砂詠 飛来
児童書・童話
王子がまだ生熟れであるように、姫もまだまだ小娘でありました。
醜いカエルの姿に変えられてしまった王子を嘆く従者ハインリヒ。彼の強い憎しみの先に居たのは、王子を救ってくれた姫だった。

がらくた屋 ふしぎ堂のヒミツ
三柴 ヲト
児童書・童話
『がらくた屋ふしぎ堂』
――それは、ちょっと変わった不思議なお店。
おもちゃ、駄菓子、古本、文房具、骨董品……。子どもが気になるものはなんでもそろっていて、店主であるミチばあちゃんが不在の時は、太った変な招き猫〝にゃすけ〟が代わりに商品を案内してくれる。
ミチばあちゃんの孫である小学6年生の風間吏斗(かざまりと)は、わくわく探しのため毎日のように『ふしぎ堂』へ通う。
お店に並んだ商品の中には、普通のがらくたに混じって『神商品(アイテム)』と呼ばれるレアなお宝もたくさん隠されていて、悪戯好きのリトはクラスメイトの男友達・ルカを巻き込んで、神商品を使ってはおかしな事件を起こしたり、逆にみんなの困りごとを解決したり、毎日を刺激的に楽しく過ごす。
そんなある日のこと、リトとルカのクラスメイトであるお金持ちのお嬢様アンが行方不明になるという騒ぎが起こる。
彼女の足取りを追うリトは、やがてふしぎ堂の裏庭にある『蔵』に隠された〝ヒミツの扉〟に辿り着くのだが、扉の向こう側には『異世界』や過去未来の『時空を超えた世界』が広がっていて――⁉︎
いたずら好きのリト、心優しい少年ルカ、いじっぱりなお嬢様アンの三人組が織りなす、事件、ふしぎ、夢、冒険、恋、わくわく、どきどきが全部詰まった、少年少女向けの現代和風ファンタジー。

恋プリ童話シリーズ
田中桔梗
児童書・童話
ツイッターのタグで
#私の絵柄で見てみたい童話の登場人物っていますか
というのがありまして、そこでいただいたお題に沿って童話を書いていこうと思います。
<いただいたお題予定>
・ジェルド(野獣)、ミッチャン(美女) 貴様さん
・女レイ(オーロラ姫)、男エリー(王子)、セルダ(魔女)、リアム(国王) 貴様さん
・マーサ(ラプンツェル)、アラン(王子) 貴様さん
・ハーネイス(ウィックドクイーン)、エリー(白雪姫) 星影さんとにけさん
・女レイ(人魚)、セルダ(魔女)、アルバート(王子)、アラン(側近) ぱちさん
・ジェルミア(シンデレラ) 華吹雪さん
・エリー(オーロラ姫)、レイ(王子)、ハーネイス(魔女) kokawausoさん
・ディーン(人魚王子)、エリー(姫)、レイ(婚約者) 翠さん
・エリー(オデット)、悪魔ロートバルト(ディーン) 恵子さん
・ピノキオ、キャラ指定なし イデッチさん
・レイ(アラジン)、エリー(ジャスミン)、アラン(ジャファー) すーポックさん
・ハーネイス(マッチ売りの少女) ミケさん
・オペラ座の怪人(ディーン) 貴様さん

極甘独占欲持ち王子様は、優しくて甘すぎて。
猫菜こん
児童書・童話
私は人より目立たずに、ひっそりと生きていたい。
だから大きな伊達眼鏡で、毎日を静かに過ごしていたのに――……。
「それじゃあこの子は、俺がもらうよ。」
優しく引き寄せられ、“王子様”の腕の中に閉じ込められ。
……これは一体どういう状況なんですか!?
静かな場所が好きで大人しめな地味子ちゃん
できるだけ目立たないように過ごしたい
湖宮結衣(こみやゆい)
×
文武両道な学園の王子様
実は、好きな子を誰よりも独り占めしたがり……?
氷堂秦斗(ひょうどうかなと)
最初は【仮】のはずだった。
「結衣さん……って呼んでもいい?
だから、俺のことも名前で呼んでほしいな。」
「さっきので嫉妬したから、ちょっとだけ抱きしめられてて。」
「俺は前から結衣さんのことが好きだったし、
今もどうしようもないくらい好きなんだ。」
……でもいつの間にか、どうしようもないくらい溺れていた。

十歳の少女の苦難
りゅうな
児童書・童話
砂漠の国ガーディル国の姫マリンカ姫は黒魔術師アベルの魔法にかけられて、姿は十歳、中身は十七歳の薬作りの少女。
マリンカは国から離れて妃の知り合いの家に向かう途中、牛男が現れた。牛男は大国の王子だと自ら言うが信用しないマリンカ。
牛男は黒魔術アベルに魔法をかけられたと告げる。
マリンカは牛男を連れて黒魔術師アベルのいる場所に向かう。

完璧ブラコン番長と町の謎
佐賀ロン
児童書・童話
小野あかりは、妖怪や幽霊、霊能力者などを専門にする『包丁師』見習い。
ある夜、大蛇を倒す姿を男の子に見られてしまう。
その男の子は、あかりが転校した先で有名な番長・古田冬夜だった。
あかりは冬夜から「会って欲しい人がいる」と頼まれ、出会ったのは、冬夜の弟・夏樹。
彼は冬夜とは違い、妖怪や幽霊が視える子どもだった。
あかりは、特殊な土地によって引き起こされる事件に巻き込まれる…。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















