47 / 75
45. 褐色の目
しおりを挟む
「中学時代、白人の友達が私の書いた作文を盗用して賞をとったの。あとから私が代筆したものだってバレたけど学校もその子の親もうやむやにして、栄誉は全部彼女のものに……。その子はイギリスの中でもトップクラスの私立の高校に進学したわ、私は公立の高校だったけど」
「最低だわ、本当に認められるべきはあなたなのに。周りの大人も最悪」
「他にも色んな場面で人種差別を経験したり見聞きしたりしたわ。これまで嫌になるくらい、夢を叶えられる可能性が高いのは白人の子なんだということを思い知らされた。世界は残酷よ。RPGに例えたら、私は上下スウェットで武器もアイテムもなく戦いに挑む戦士。一方で白人は魔道士よ。努力さえすれば欲しいものを何でも手に入れられる。地位も名誉も愛も」
「そんなことない」
フォローの台詞も考えないまま否定の言葉を口にする。これを肯定してしまえば世の中に希望がないことを肯定してしまうようなものだからだ。
「ハル・ベリーだって、アカデミー賞の最優秀主演女優賞を獲った。黒人の女性副大統領だって出た。時代が追いついていないだけで、あなたたちが耀く時代は絶対に来る」
「アカデミー賞だって所詮は白い賞よ。ハルの後は黒人の女優でその賞を取る人は出てない」
アリーシャの言葉が胸に突き刺さる。この業界に入って、何度もSNSで誹謗中傷を受けた。私の女優としての実力不足や見た目のことについて、そして、スペインの血が入っているということについて。他のことには全く自信が無かったが、自分のルーツだけは誇りに思っていた。それが自分のキャリアを妨げるなどと考えたことはなかったし、たとえそれが原因で何らかの障害にぶち当たったとしても、きっと乗り越えていけるという根拠のない自信があった。だが先ほどのアリーシャの言葉に少なからざる衝撃を受けた。
アリーシャが社会の中で感じていた理不尽さや落胆は、私が感じてきたそれらとは比べられないのだろう。だがどうしても他人事と思えなかった。白人の血が入っているものの純粋な白人とは違う私自身、アイデンティティを貶されるような経験を何度もした。ドラマの撮影のときに感じたことーー。時々監督や脚本家やスタッフの中で、クレアやミアの前と私の前とでは扱いや態度が違う人間がいた。単純な好き嫌いもあるだろうし他の2人がドラマの主役で私より遥かに人気のある女優だからという理由もあるだろう。これについてあまり考えたくはなかったが、もっと別の根深い問題が潜んでいる気がしてならなかったのだ。
私は咄嗟に祖父のパウロの話をした。移民としてこの国に来て汗と涙を流した末に彼が成し遂げた偉業のことを。ヒスパニックの私と彼女では事情は違うかもしれないと思ったが、世の中に失望し自信を失っている彼女を勇気づけるために他に1番説得力のある話を思いつかなかったのだ。
アリーシャは静かに話を聞いていたが、パウロがジェームズからバッジを貰った話に涙した。
「お祖父ちゃんは学歴や特別な特技があったわけじゃなかった。ただ誰にも負けないくらい真っ直ぐで一生懸命だったの、仕事や人に対して」
「何か大きなことを成し遂げる人って、そういう人が多いと思うわ。ただ一つのことを見つめて頑張っていけるって簡単なようで難しい。凄いことよ。私の兄もそうなの。子どもの頃差別や虐めで不登校になったりしたけど、ゲーム好きが高じて今はゲーム会社でゲームの開発をしてる。忙しいし時期によって寝る時間もないみたいだけど、すごく楽しそうよ」
「あなたの気持ちを全部理解をすることはできないけど……。私も差別を受けてきた、人前に出る仕事だから余計にね。それでも自分のルーツを誇りに思ってるし、恥ずかしいことだなんて全く思わない。おじいちゃんがいつも言ってたの、『人と違うからこそ、他の人にできないことができる』って。マイノリティだからこそ出来ること、伝えていけることってあるんじゃないかな。それにスウェット姿で一人戦う戦士がいたら、逆に強い仲間が集まって助けてくれると思う」
アリーシャは僅かに顔を綻ばせた。
「何だかあなたに何回も救われてるわね」
彼女は帰り際黄色い袋を差し出した。中には私が以前血眼で探していた、もう生産中止になったプレミアものの『トワイライト・エクスプレス』というホラーゲームが入っていた。
「これどこで手に入れたん?」
興奮しながら尋ねるとアリーシャは少し得意げに微笑んだ。
「兄に頼んでメーカーにダメ元で聞いてもらったの。そしたらたまたま一つだけ新品の在庫があったのよ」
「すご!! ありがとう!! てか私がこのゲーム欲しいって何で知ってたの?」
「あなたのファンだっていう友達から聞いたの。あなたがずっと前に雑誌のインタビューで、このゲームがどうしても欲しくて必死で探したけど見つからないって話してたこと」
「あれ、そうだっけ」
全く記憶がない。お返しが欲しかったわけでも期待していたわけでも全くないが、思いもよらぬサプライズに心は完全に浮き立っていた。
「喜んでもらえたなら良かった」
アリーシャは安堵したように笑った。帰り際彼女は自分が働いている書店の名前を告げ、よければ後で遊びに来てと言った。私は絶対に行くと約束し彼女に手を振った。
「最低だわ、本当に認められるべきはあなたなのに。周りの大人も最悪」
「他にも色んな場面で人種差別を経験したり見聞きしたりしたわ。これまで嫌になるくらい、夢を叶えられる可能性が高いのは白人の子なんだということを思い知らされた。世界は残酷よ。RPGに例えたら、私は上下スウェットで武器もアイテムもなく戦いに挑む戦士。一方で白人は魔道士よ。努力さえすれば欲しいものを何でも手に入れられる。地位も名誉も愛も」
「そんなことない」
フォローの台詞も考えないまま否定の言葉を口にする。これを肯定してしまえば世の中に希望がないことを肯定してしまうようなものだからだ。
「ハル・ベリーだって、アカデミー賞の最優秀主演女優賞を獲った。黒人の女性副大統領だって出た。時代が追いついていないだけで、あなたたちが耀く時代は絶対に来る」
「アカデミー賞だって所詮は白い賞よ。ハルの後は黒人の女優でその賞を取る人は出てない」
アリーシャの言葉が胸に突き刺さる。この業界に入って、何度もSNSで誹謗中傷を受けた。私の女優としての実力不足や見た目のことについて、そして、スペインの血が入っているということについて。他のことには全く自信が無かったが、自分のルーツだけは誇りに思っていた。それが自分のキャリアを妨げるなどと考えたことはなかったし、たとえそれが原因で何らかの障害にぶち当たったとしても、きっと乗り越えていけるという根拠のない自信があった。だが先ほどのアリーシャの言葉に少なからざる衝撃を受けた。
アリーシャが社会の中で感じていた理不尽さや落胆は、私が感じてきたそれらとは比べられないのだろう。だがどうしても他人事と思えなかった。白人の血が入っているものの純粋な白人とは違う私自身、アイデンティティを貶されるような経験を何度もした。ドラマの撮影のときに感じたことーー。時々監督や脚本家やスタッフの中で、クレアやミアの前と私の前とでは扱いや態度が違う人間がいた。単純な好き嫌いもあるだろうし他の2人がドラマの主役で私より遥かに人気のある女優だからという理由もあるだろう。これについてあまり考えたくはなかったが、もっと別の根深い問題が潜んでいる気がしてならなかったのだ。
私は咄嗟に祖父のパウロの話をした。移民としてこの国に来て汗と涙を流した末に彼が成し遂げた偉業のことを。ヒスパニックの私と彼女では事情は違うかもしれないと思ったが、世の中に失望し自信を失っている彼女を勇気づけるために他に1番説得力のある話を思いつかなかったのだ。
アリーシャは静かに話を聞いていたが、パウロがジェームズからバッジを貰った話に涙した。
「お祖父ちゃんは学歴や特別な特技があったわけじゃなかった。ただ誰にも負けないくらい真っ直ぐで一生懸命だったの、仕事や人に対して」
「何か大きなことを成し遂げる人って、そういう人が多いと思うわ。ただ一つのことを見つめて頑張っていけるって簡単なようで難しい。凄いことよ。私の兄もそうなの。子どもの頃差別や虐めで不登校になったりしたけど、ゲーム好きが高じて今はゲーム会社でゲームの開発をしてる。忙しいし時期によって寝る時間もないみたいだけど、すごく楽しそうよ」
「あなたの気持ちを全部理解をすることはできないけど……。私も差別を受けてきた、人前に出る仕事だから余計にね。それでも自分のルーツを誇りに思ってるし、恥ずかしいことだなんて全く思わない。おじいちゃんがいつも言ってたの、『人と違うからこそ、他の人にできないことができる』って。マイノリティだからこそ出来ること、伝えていけることってあるんじゃないかな。それにスウェット姿で一人戦う戦士がいたら、逆に強い仲間が集まって助けてくれると思う」
アリーシャは僅かに顔を綻ばせた。
「何だかあなたに何回も救われてるわね」
彼女は帰り際黄色い袋を差し出した。中には私が以前血眼で探していた、もう生産中止になったプレミアものの『トワイライト・エクスプレス』というホラーゲームが入っていた。
「これどこで手に入れたん?」
興奮しながら尋ねるとアリーシャは少し得意げに微笑んだ。
「兄に頼んでメーカーにダメ元で聞いてもらったの。そしたらたまたま一つだけ新品の在庫があったのよ」
「すご!! ありがとう!! てか私がこのゲーム欲しいって何で知ってたの?」
「あなたのファンだっていう友達から聞いたの。あなたがずっと前に雑誌のインタビューで、このゲームがどうしても欲しくて必死で探したけど見つからないって話してたこと」
「あれ、そうだっけ」
全く記憶がない。お返しが欲しかったわけでも期待していたわけでも全くないが、思いもよらぬサプライズに心は完全に浮き立っていた。
「喜んでもらえたなら良かった」
アリーシャは安堵したように笑った。帰り際彼女は自分が働いている書店の名前を告げ、よければ後で遊びに来てと言った。私は絶対に行くと約束し彼女に手を振った。
30
お気に入りに追加
32
あなたにおすすめの小説

短編集:失情と采配、再情熱。(2024年度文芸部部誌より)
氷上ましゅ。
現代文学
2024年度文芸部部誌に寄稿した作品たち。
そのまま引っ張ってきてるので改変とかないです。作業が去年に比べ非常に雑で申し訳ない

極悪家庭教師の溺愛レッスン~悪魔な彼はお隣さん~
恵喜 どうこ
恋愛
「高校合格のお礼をくれない?」
そう言っておねだりしてきたのはお隣の家庭教師のお兄ちゃん。
私よりも10歳上のお兄ちゃんはずっと憧れの人だったんだけど、好きだという告白もないままに男女の関係に発展してしまった私は苦しくて、どうしようもなくて、彼の一挙手一投足にただ振り回されてしまっていた。
葵は私のことを本当はどう思ってるの?
私は葵のことをどう思ってるの?
意地悪なカテキョに翻弄されっぱなし。
こうなったら確かめなくちゃ!
葵の気持ちも、自分の気持ちも!
だけど甘い誘惑が多すぎて――
ちょっぴりスパイスをきかせた大人の男と女子高生のラブストーリーです。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。
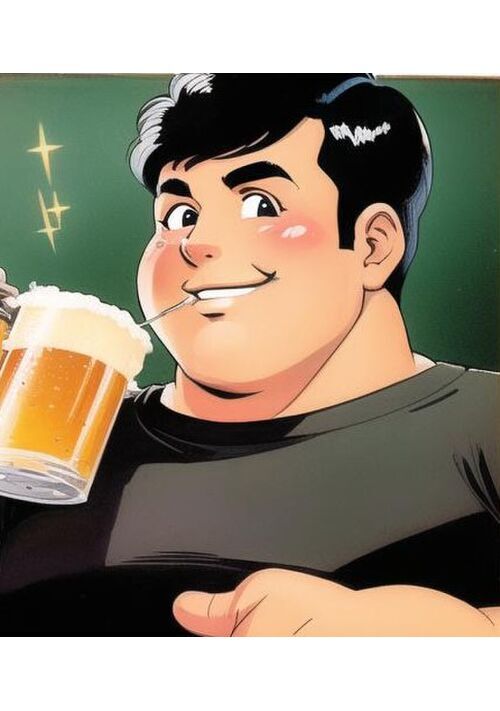
私の神様は〇〇〇〇さん~不思議な太ったおじさんと難病宣告を受けた女の子の1週間の物語~
あらお☆ひろ
現代文学
白血病の診断を受けた20歳の大学生「本田望《ほんだ・のぞみ》」と偶然出会ったちょっと変わった太ったおじさん「備里健《そなえざと・けん」》の1週間の物語です。
「劇脚本」用に大人の絵本(※「H」なものではありません)的に準備したものです。
マニアな読者(笑)を抱えてる「赤井翼」氏の原案をもとに加筆しました。
「病気」を取り扱っていますが、重くならないようにしています。
希と健が「B級グルメ」を楽しみながら、「病気平癒」の神様(※諸説あり)をめぐる話です。
わかりやすいように、極力写真を入れるようにしていますが、撮り忘れやピンボケでアップできないところもあるのはご愛敬としてください。
基本的には、「ハッピーエンド」なので「ゆるーく」お読みください。
全31チャプターなのでひと月くらいお付き合いいただきたいと思います。
よろしくお願いしまーす!(⋈◍>◡<◍)。✧♡

【推しが114人もいる俺 最強!!アイドルオーディションプロジェクト】
RYOアズ
青春
ある日アイドル大好きな女の子「花」がアイドル雑誌でオーディションの記事を見つける。
憧れのアイドルになるためアイドルのオーディションを受けることに。
そして一方アイドルというものにまったく無縁だった男がある事をきっかけにオーディション審査中のアイドル達を必死に応援することになる物語。
果たして花はアイドルになることができるのか!?

鬼母(おにばば)日記
歌あそべ
現代文学
ひろしの母は、ひろしのために母親らしいことは何もしなかった。
そんな駄目な母親は、やがてひろしとひろしの妻となった私を悩ます鬼母(おにばば)に(?)
鬼母(おにばば)と暮らした日々を綴った日記。


ハルのてのひら、ナツのそら。
華子
恋愛
中学三年生のナツは、一年生の頃からずっと想いを寄せているハルにこの気持ちを伝えるのだと、決意を固めた。
人生で初めての恋、そして、初めての告白。
「ハルくん。わたしはハルくんが好きです。ハルくんはわたしをどう思っていますか」
しかし、ハルはその答えを教えてはくれなかった。
何度勇気を出して伝えてもはぐらかされ、なのに思わせぶりな態度をとってくるハルと続いてしまう、曖昧なふたりの関係。
ハルからどうしても「好き」だと言われたいナツ。
ナツにはどうしても「好き」だと言いたくないハル。
どちらも一歩もゆずれない、切ない訳がそこにはあった。
表紙はフリーのもの。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















