お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

なんども濡れ衣で責められるので、いい加減諦めて崖から身を投げてみた
下菊みこと
恋愛
悪役令嬢の最後の抵抗は吉と出るか凶と出るか。
ご都合主義のハッピーエンドのSSです。
でも周りは全くハッピーじゃないです。
小説家になろう様でも投稿しています。

天神様の御用人 ~心霊スポット連絡帳~
水鳴諒
児童書・童話
【完結】人形供養をしている深珠神社から、邪悪な魂がこもる人形が逃げ出して、心霊スポットの核になっている。天神様にそれらの人形を回収して欲しいと頼まれた中学一年生のスミレは、天神様の御用人として、神社の息子の龍樹や、血の繋がらない一つ年上の兄の和成と共に、一時間以内に出ないと具合が悪くなる心霊スポット巡りをして人形を回収することになる。※第2回きずな児童書大賞でサバイバル・ホラー賞を頂戴しました。これも応援して下さった皆様のおかげです、本当にありがとうございました!

その溺愛は伝わりづらい
海野幻創
BL
人好きのする端正な顔立ちを持ち、文武両道でなんでも無難にこなせることのできた生田雅紀(いくたまさき)は、小さい頃から多くの友人に囲まれていた。
しかし他人との付き合いは広く浅くの最小限に留めるタイプで、女性とも身体だけの付き合いしかしてこなかった。
偶然出会った久世透(くぜとおる)は、嫉妬を覚えるほどのスタイルと美貌をもち、引け目を感じるほどの高学歴で、議員の孫であり大企業役員の息子だった。
御曹司であることにふさわしく、スマートに大金を使ってみせるところがありながら、生田の前では捨てられた子犬のようにおどおどして気弱な様子を見せ、そのギャップを生田は面白がっていたのだが……。
これまで他人と深くは関わってこなかったはずなのに、会うたびに違う一面を見せる久世は、いつしか生田にとって離れがたい存在となっていく。
【7/27完結しました。読んでいただいてありがとうございました。】
【続編も8/17完結しました。】
「その溺愛は行き場を彷徨う……気弱なスパダリ御曹司は政略結婚を回避したい」
https://www.alphapolis.co.jp/novel/962473946/911896785
↑この続編は、R18の過激描写がありますので、苦手な方はご注意ください。

幽霊横丁へいらっしゃい~バスを降りるとそこは幽霊たちが住む町でした~
風雅ありす
児童書・童話
5歳の女の子【あかり】は、死んだ人の姿を見ることができる。
亡くなった母親の姿も幽霊としてあかりの傍に居てくれたのに、
ある日突然、姿が見えなくなってしまう。
消えてしまった母を捜して、あかりは一人、バスに乗る。
それは、死んだ人たちだけが乗ることのできる特別なバスだった。
果たして、あかりは、無事に母親に再会できるのか――――?

魔界最強に転生した社畜は、イケメン王子に奪い合われることになりました
タタミ
BL
ブラック企業に務める社畜・佐藤流嘉。
クリスマスも残業確定の非リア人生は、トラックの激突により突然終了する。
死後目覚めると、目の前で見目麗しい天使が微笑んでいた。
「ここは天国ではなく魔界です」
天使に会えたと喜んだのもつかの間、そこは天国などではなく魔法が当たり前にある世界・魔界だと知らされる。そして流嘉は、魔界に君臨する最強の支配者『至上様』に転生していたのだった。
「至上様、私に接吻を」
「あっ。ああ、接吻か……って、接吻!?なんだそれ、まさかキスですか!?」
何が起こっているのかわからないうちに、流嘉の前に現れたのは美しい4人の王子。この4王子にキスをして、結婚相手を選ばなければならないと言われて──!?


魔法使いアルル
かのん
児童書・童話
今年で10歳になるアルルは、月夜の晩、自分の誕生日に納屋の中でこっそりとパンを食べながら歌を歌っていた。
これまで自分以外に誰にも祝われる事のなかった日。
だが、偉大な大魔法使いに出会うことでアルルの世界は色を変えていく。
孤独な少女アルルが、魔法使いになって奮闘する物語。
ありがたいことに書籍化が進行中です!ありがとうございます。
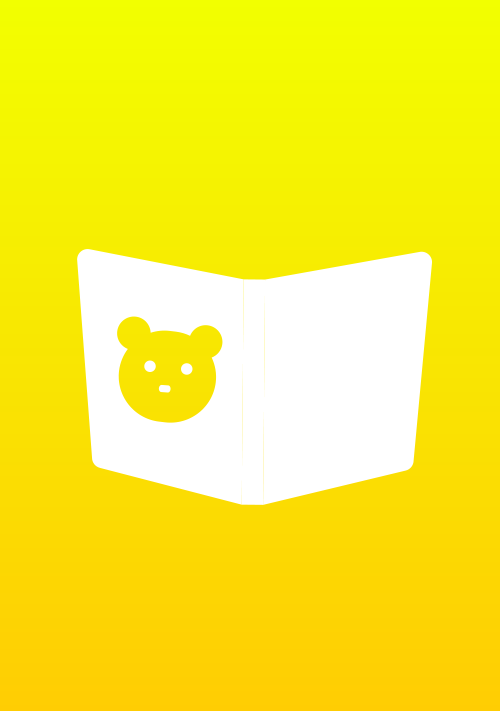
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















