お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

なんども濡れ衣で責められるので、いい加減諦めて崖から身を投げてみた
下菊みこと
恋愛
悪役令嬢の最後の抵抗は吉と出るか凶と出るか。
ご都合主義のハッピーエンドのSSです。
でも周りは全くハッピーじゃないです。
小説家になろう様でも投稿しています。

亀さんののんびりお散歩旅
しんしん
児童書・童話
これは亀のようにゆっくりでも着々と進んでいく。そんな姿をみて、自分も頑張ろう!ゆっくりでも時間をかけていこう。
そんな気持ちになってほしいです。
あとはほのぼの見てあげてください笑笑
目的 カミール海岸へ行くこと
出発地 サミール海岸

コンプレックス×ノート
石丸明
児童書・童話
佐倉結月は自信がない。なんでも出来て人望も厚い双子の姉、美月に比べて、自分はなにも出来ないしコミュニケーションも苦手。
中学で入部したかった軽音学部も、美月が入るならやめとこうかな。比べられて落ち込みたくないし。そう思っていたけど、新歓ライブに出演していたバンド「エテルノ」の演奏に魅了され、入部することに。
バンド仲間たちとの触れ合いを通して、結月は美月と、そして自分と向き合っていく。
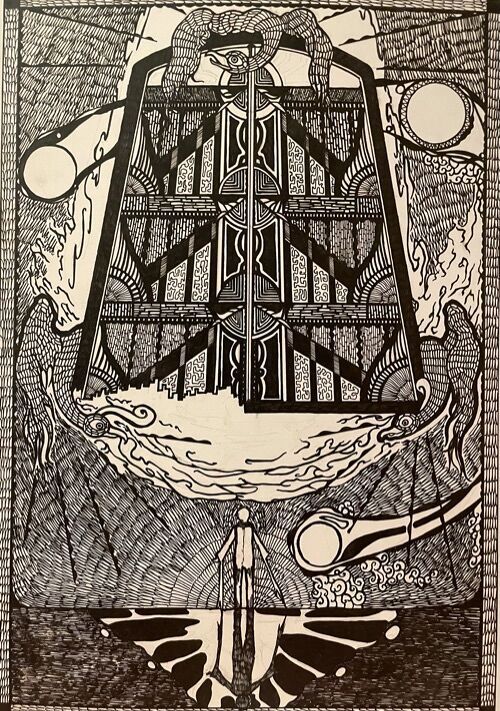
星物語
秋長 豊
児童書・童話
<第1巻 末裔の鍵>
大地(アマク)、地底(トロレル)、海底(ブルワスタック)――美しき三大王国。
15年後、世界は巨大隕石(アバロン)の衝突によって滅ぶ運命にあった。
全生命滅亡へのシナリオを回避する唯一の方法。それは、予言に記された「三つの鍵を集め、巨大な扉を開くこと」だった。
予言に選ばれた9歳の男の子エシルバは”鍵”を集める役割を担っていたが、そのことを知らず、優しい叔父さんたちと平和な日々を過ごしていた。右手に奇妙なあざが現れた時、国家組織の役人(シブー)が訪れ、父親がシブーの英雄と呼ばれた偉人で、9年前に反乱を起こし敵となったこと、エシルバがかつて予言に選ばれた大悪人の末裔(まつえい)であることを告げられる。巨大隕石を阻止するためには、予言に選ばれたエシルバの力が必要だった。
彼らに力を貸すために、エシルバは愛する家族を置いて故郷を離れる。
若くしてシブーとなったエシルバは、使節団と呼ばれるシブーの内部組織に配属された。
しかし――「犯罪者の息子」「大悪人の末裔」というレッテルに悩まされ、社会から冷たい洗礼を受けることは避けられなかった……

その男、有能につき……
大和撫子
BL
俺はその日最高に落ち込んでいた。このまま死んで異世界に転生。チート能力を手に入れて最高にリア充な人生を……なんてことが現実に起こる筈もなく。奇しくもその日は俺の二十歳の誕生日だった。初めて飲む酒はヤケ酒で。簡単に酒に呑まれちまった俺はフラフラと渋谷の繁華街を彷徨い歩いた。ふと気づいたら、全く知らない路地(?)に立っていたんだ。そうだな、辺りの建物や雰囲気でいったら……ビクトリア調時代風? て、まさかなぁ。俺、さっきいつもの道を歩いていた筈だよな? どこだよ、ここ。酔いつぶれて寝ちまったのか?
「君、どうかしたのかい?」
その時、背後にフルートみたいに澄んだ柔らかい声が響いた。突然、そう話しかけてくる声に振り向いた。そこにいたのは……。
黄金の髪、真珠の肌、ピンクサファイアの唇、そして光の加減によって深紅からロイヤルブルーに変化する瞳を持った、まるで全身が宝石で出来ているような超絶美形男子だった。えーと、確か電気の光と太陽光で色が変わって見える宝石、あったような……。後で聞いたら、そんな風に光によって赤から青に変化する宝石は『ベキリーブルーガーネット』と言うらしい。何でも、翠から赤に変化するアレキサンドライトよりも非常に希少な代物だそうだ。
彼は|Radius《ラディウス》~ラテン語で「光源」の意味を持つ、|Eternal《エターナル》王家の次男らしい。何だか分からない内に彼に気に入られた俺は、エターナル王家第二王子の専属侍従として仕える事になっちまったんだ! しかもゆくゆくは執事になって欲しいんだとか。
だけど彼は第二王子。専属についている秘書を始め護衛役や美容師、マッサージ師などなど。数多く王子と密に接する男たちは沢山いる。そんな訳で、まずは見習いから、と彼らの指導のもと、仕事を覚えていく訳だけど……。皆、王子の寵愛を独占しようと日々蹴落としあって熾烈な争いは日常茶飯事だった。そんな中、得体の知れない俺が王子直々で専属侍従にする、なんていうもんだから、そいつらから様々な嫌がらせを受けたりするようになっちまって。それは日増しにエスカレートしていく。
大丈夫か? こんな「ムササビの五能」な俺……果たしてこのまま皇子の寵愛を受け続ける事が出来るんだろうか?
更には、第一王子も登場。まるで第二王子に対抗するかのように俺を引き抜こうとしてみたり、波乱の予感しかしない。どうなる? 俺?!

魔界最強に転生した社畜は、イケメン王子に奪い合われることになりました
タタミ
BL
ブラック企業に務める社畜・佐藤流嘉。
クリスマスも残業確定の非リア人生は、トラックの激突により突然終了する。
死後目覚めると、目の前で見目麗しい天使が微笑んでいた。
「ここは天国ではなく魔界です」
天使に会えたと喜んだのもつかの間、そこは天国などではなく魔法が当たり前にある世界・魔界だと知らされる。そして流嘉は、魔界に君臨する最強の支配者『至上様』に転生していたのだった。
「至上様、私に接吻を」
「あっ。ああ、接吻か……って、接吻!?なんだそれ、まさかキスですか!?」
何が起こっているのかわからないうちに、流嘉の前に現れたのは美しい4人の王子。この4王子にキスをして、結婚相手を選ばなければならないと言われて──!?

【完結済】(無自覚)妖精に転生した僕は、騎士の溺愛に気づかない。
キノア9g
BL
完結済。騎士エリオット視点を含め全10話(エリオット視点2話と主人公視点8話構成)
エロなし。騎士×妖精
※主人公が傷つけられるシーンがありますので、苦手な方はご注意ください。
気がつくと、僕は見知らぬ不思議な森にいた。
木や草花どれもやけに大きく見えるし、自分の体も妙に華奢だった。
色々疑問に思いながらも、1人は寂しくて人間に会うために森をさまよい歩く。
ようやく出会えた初めての人間に思わず話しかけたものの、言葉は通じず、なぜか捕らえられてしまい、無残な目に遭うことに。
捨てられ、意識が薄れる中、僕を助けてくれたのは、優しい騎士だった。
彼の献身的な看病に心が癒される僕だけれど、彼がどんな思いで僕を守っているのかは、まだ気づかないまま。
少しずつ深まっていくこの絆が、僕にどんな運命をもたらすのか──?
いいねありがとうございます!励みになります。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















