24 / 55
第4章 木でも獣でもない者たち
24
しおりを挟む
大きなへんてこなやつは顔を上げた。速い動きだった。
ミチと進一郎の体がゆれた。
みるみるうちにミチの視界が地面ら上へはなれていった。ミチの知っている感覚でいうと遊園地のアトラクションみたいだが、ただし柵もベルトもない。
ミチは進一郎の腕にしがみついた。進一郎がここから落ちたら大変だと思った。
進一郎もそう考えたようだ。上半身がナナカマドウシの口のなかまで入ると、彼は片足を唇にあたる部分へひっかけた。
ミチはふと下を見た。聖の後ろ姿が見えた。
聖が走ってどこかへ去ろうとしている。
進一郎が腰をあげたので、ミチはいそいで言った。
「あんまり動かないほうがいいです。このすぐ先に大きな段差があってそこから下は深いです」
進一郎がミチを見た。きつい目つきだ。でもすぐに視線がそれた。進一郎はナナカマドウシの口のなかをざっと見まわした。
「なんだこれは。どういうことだ」
ミチもたずねた。
「進一郎さんこそ、どうしてここにいるんですか」
「砂森さんが電話をくれた。聖の様子がおかしい、障療院から出ていったと。本当は親に連絡を入れるところだけど、まずおれにかけてきた」
「砂森さんと仲がいいんですか」
「あの人も道場生だ。先輩だ」
「ええと、合気道の」
「でも砂森さんはこんなやつのことは一言も言わなかった」
「だって砂森さんはナナカマドウシさんを見てないと思います」
進一郎がふたたびきつい目つきでミチを見た。ミチはたじろいだ。進一郎が怒っているのだと思った。
「どうして怒っているんですか」
「べつに怒っていない」
怒ったような声のままで進一郎がつぶやいた。
「ナナカマドウシ、さん」
「はい」
「ナナカマドの牛ってことか。これはナナカマドの木でできているのか」
「その推測は正しい、ふむ、きみは言葉に対する感性がするどいね。だが同時にそれだけでは足りない」
洞のなかでナナカマドウシの声がひびいた。
進一郎がハッとした顔になってあたりを見回した。
「だれだ、どこにいる」
「ナナカマドウシさんの声です」
進一郎の顔がゆがんだ。ナナカマドウシの声が聞こえたことに、なぜだか、とても傷ついたような顔だった。ミチにはそう見えた。進一郎はミチに向かってぐっと顔を近づけた。
「おれの目をよく見てくれ。見えるか。おれも枯内障になったのか。この年で」
(あ、そうか。進一郎さんは自分が病気になったと思ってショックなのか)
ミチは進一郎の目をのぞきこんだ。
ナナカマドウシの唇と唇のすきま、体表にあたる木の枝や蔦や赤い葉のすきまから木もれ日がさしこんで、それが進一郎の体のあちこちを照らした。光と影がまだらになり、進一郎の体や顔のある部分は暗く、ある部分は明るくはっきりと、ミチの目にうつった。
ミチはしばらくのあいだ真剣に進一郎の目を見つめたあと、首を横にふった。
「目の色はなんともないです」
進一郎もおなじようにミチの目を見た。こちらはのぞきこむというより、つらぬくような視線だ、なにも見逃さないぞという進一郎のかたい決意をミチは感じた。
数秒じっと見続けたあと進一郎は首を横に振った。
「君の目も黒目があるし、にごりはない」
進一郎は歯をくいしばり、握りこぶしを作った。
「どういうことだ、変だ、おれたちが枯内障だというよりもっと変じゃないか。なぜこんなのが見えるんだ、いや、見えるだけじゃない、手でふれた。しかも手でふれるどころか中へ入ってしまった。」
進一郎はミチへ視線を走らせた。
ミチは進一郎の視線が自分に向くたびにいちいち居心地の悪さを感じた。
まるでミチが一連の異常なできごとを起こしたのではないか、ミチが犯人ではないかと進一郎がうたがっているように感じるのだ。それは決して気持ちのいい視線ではなかった。
その正反対だ。
視線を受けるたびにミチのどこかを刃物がかすめて傷がつくような気分になる。
進一郎がミチへたずねた。
「砂森さんはこいつを見ていないんだな?」
じっくりした声だ。
なにかをたしかめるような、あるいは進一郎自身に言い聞かせるような声だ。
ミチはうなずいた。
進一郎は小さくためいきをついた。
「そうか。じゃあおれはおかしくなったんだ」
ミチはあることに気づいて、進一郎にたずねた。
「進一郎さんは昨日のことをおぼえていますか」
「昨日、君と書庫の奥へ行ったことか。そのあと聖に会った」
進一郎がいぶかしげな顔になった。すると洞のなかへ声がひびいた。
ナナカマドウシだ。
「聖というのはさっき走っていった子どものことかね?」
「そうです」
ミチがうなずくと、進一郎が不審そうな顔になった。
「弟がどうしたというんだ」
「ふうむ、弟か、弟とはね。どうもきみはまったく無関係というわけではないね」
ナナカマドウシがつぶやいた。声の様子はつぶやきだが、ミチの耳にはどうしてもそれがうわああんとひびき渡って、洞全体がゆれるほど大きく聞こえる。ミチの腹にまでひびいてふるえるほどだ。
ミチはあることに気づいた。
ナナカマドウシはミチのことも聖や進一郎のことも、すべて「きみ」と呼ぶ。
その言葉にはふしぎなほど分けへだてが感じられず、そしてそのぶん、混沌としたものとして聞こえた。
「きみは私のもとを、おとずれるべくしておとずれ、出会うべくして出会ったのかもしれない。それともあるいは、ただ単にまったくの偶然かもしれないが。」
ズシン、と洞がゆれた。
ミチも進一郎もいそいでナナカマドウシの口のへりにしがみついた。ナナカマドウシが歩きだしたのだ。ナナカマドウシはだれにともなく言った。
「くわしい話は津江さんが知っているのではないかね。早く津江さんに会えるといいのだが」
その言葉にミチはハッとした。
「津江さん、そうだった」
ミチは思いだした。津江さんがミチへ言いつけたことを進一郎の出現のどさくさにまぎれてすっかり忘れていたのだ。
ミチはざっと周囲を見まわして、少しでも光が多くさしこむすきまへ近づいた。
そして服の中から本を、古いほうの『ひごめのむかしばなし』をとりだした。
進一郎が拍子抜けしたような顔になった。
「昨日の本じゃないか。もしかしていま読むのか。こんなときに」
「読まないと。津江さんにそうしろって言われました」
ゆれと暗がりのためにとても読みづらい。目で文字をたどったとたんに車酔いのような不快な感覚がミチの頭の奥にうまれた。とはいえ、どうにか読むことができた。
ミチが開いたのは目次のページだった。
新しいほうの本、さっき障療院の図書室で開いたほうの『ひごめのむかしばなし』に載っていた『観音様と赤い文字』がおなじようにいちばんはじめにある。
ミチはいそいで目次にならぶ文字を目で追いかけた。
『銀杏の葉はなぜ黄色いか』
『秋を呼ぶ大牛のはなし』
『熊とお嫁さんの力くらべ」……。
ミチの目は、目次のさいごの行にとまった。
『かんなぎと池の化けもの』
(この古い本にだけ載っていて、新しいほう、障療院の図書室にあった本には載っていなかったのは、きっと、この話だ)
暗がりのなかで差しこむ光をたよりにしてミチはその話を読みはじめた。
それは障療院の図書室で読んだ『観音さまと赤い文字』よりもずっと長く、そして異様な話だった。
ミチと進一郎の体がゆれた。
みるみるうちにミチの視界が地面ら上へはなれていった。ミチの知っている感覚でいうと遊園地のアトラクションみたいだが、ただし柵もベルトもない。
ミチは進一郎の腕にしがみついた。進一郎がここから落ちたら大変だと思った。
進一郎もそう考えたようだ。上半身がナナカマドウシの口のなかまで入ると、彼は片足を唇にあたる部分へひっかけた。
ミチはふと下を見た。聖の後ろ姿が見えた。
聖が走ってどこかへ去ろうとしている。
進一郎が腰をあげたので、ミチはいそいで言った。
「あんまり動かないほうがいいです。このすぐ先に大きな段差があってそこから下は深いです」
進一郎がミチを見た。きつい目つきだ。でもすぐに視線がそれた。進一郎はナナカマドウシの口のなかをざっと見まわした。
「なんだこれは。どういうことだ」
ミチもたずねた。
「進一郎さんこそ、どうしてここにいるんですか」
「砂森さんが電話をくれた。聖の様子がおかしい、障療院から出ていったと。本当は親に連絡を入れるところだけど、まずおれにかけてきた」
「砂森さんと仲がいいんですか」
「あの人も道場生だ。先輩だ」
「ええと、合気道の」
「でも砂森さんはこんなやつのことは一言も言わなかった」
「だって砂森さんはナナカマドウシさんを見てないと思います」
進一郎がふたたびきつい目つきでミチを見た。ミチはたじろいだ。進一郎が怒っているのだと思った。
「どうして怒っているんですか」
「べつに怒っていない」
怒ったような声のままで進一郎がつぶやいた。
「ナナカマドウシ、さん」
「はい」
「ナナカマドの牛ってことか。これはナナカマドの木でできているのか」
「その推測は正しい、ふむ、きみは言葉に対する感性がするどいね。だが同時にそれだけでは足りない」
洞のなかでナナカマドウシの声がひびいた。
進一郎がハッとした顔になってあたりを見回した。
「だれだ、どこにいる」
「ナナカマドウシさんの声です」
進一郎の顔がゆがんだ。ナナカマドウシの声が聞こえたことに、なぜだか、とても傷ついたような顔だった。ミチにはそう見えた。進一郎はミチに向かってぐっと顔を近づけた。
「おれの目をよく見てくれ。見えるか。おれも枯内障になったのか。この年で」
(あ、そうか。進一郎さんは自分が病気になったと思ってショックなのか)
ミチは進一郎の目をのぞきこんだ。
ナナカマドウシの唇と唇のすきま、体表にあたる木の枝や蔦や赤い葉のすきまから木もれ日がさしこんで、それが進一郎の体のあちこちを照らした。光と影がまだらになり、進一郎の体や顔のある部分は暗く、ある部分は明るくはっきりと、ミチの目にうつった。
ミチはしばらくのあいだ真剣に進一郎の目を見つめたあと、首を横にふった。
「目の色はなんともないです」
進一郎もおなじようにミチの目を見た。こちらはのぞきこむというより、つらぬくような視線だ、なにも見逃さないぞという進一郎のかたい決意をミチは感じた。
数秒じっと見続けたあと進一郎は首を横に振った。
「君の目も黒目があるし、にごりはない」
進一郎は歯をくいしばり、握りこぶしを作った。
「どういうことだ、変だ、おれたちが枯内障だというよりもっと変じゃないか。なぜこんなのが見えるんだ、いや、見えるだけじゃない、手でふれた。しかも手でふれるどころか中へ入ってしまった。」
進一郎はミチへ視線を走らせた。
ミチは進一郎の視線が自分に向くたびにいちいち居心地の悪さを感じた。
まるでミチが一連の異常なできごとを起こしたのではないか、ミチが犯人ではないかと進一郎がうたがっているように感じるのだ。それは決して気持ちのいい視線ではなかった。
その正反対だ。
視線を受けるたびにミチのどこかを刃物がかすめて傷がつくような気分になる。
進一郎がミチへたずねた。
「砂森さんはこいつを見ていないんだな?」
じっくりした声だ。
なにかをたしかめるような、あるいは進一郎自身に言い聞かせるような声だ。
ミチはうなずいた。
進一郎は小さくためいきをついた。
「そうか。じゃあおれはおかしくなったんだ」
ミチはあることに気づいて、進一郎にたずねた。
「進一郎さんは昨日のことをおぼえていますか」
「昨日、君と書庫の奥へ行ったことか。そのあと聖に会った」
進一郎がいぶかしげな顔になった。すると洞のなかへ声がひびいた。
ナナカマドウシだ。
「聖というのはさっき走っていった子どものことかね?」
「そうです」
ミチがうなずくと、進一郎が不審そうな顔になった。
「弟がどうしたというんだ」
「ふうむ、弟か、弟とはね。どうもきみはまったく無関係というわけではないね」
ナナカマドウシがつぶやいた。声の様子はつぶやきだが、ミチの耳にはどうしてもそれがうわああんとひびき渡って、洞全体がゆれるほど大きく聞こえる。ミチの腹にまでひびいてふるえるほどだ。
ミチはあることに気づいた。
ナナカマドウシはミチのことも聖や進一郎のことも、すべて「きみ」と呼ぶ。
その言葉にはふしぎなほど分けへだてが感じられず、そしてそのぶん、混沌としたものとして聞こえた。
「きみは私のもとを、おとずれるべくしておとずれ、出会うべくして出会ったのかもしれない。それともあるいは、ただ単にまったくの偶然かもしれないが。」
ズシン、と洞がゆれた。
ミチも進一郎もいそいでナナカマドウシの口のへりにしがみついた。ナナカマドウシが歩きだしたのだ。ナナカマドウシはだれにともなく言った。
「くわしい話は津江さんが知っているのではないかね。早く津江さんに会えるといいのだが」
その言葉にミチはハッとした。
「津江さん、そうだった」
ミチは思いだした。津江さんがミチへ言いつけたことを進一郎の出現のどさくさにまぎれてすっかり忘れていたのだ。
ミチはざっと周囲を見まわして、少しでも光が多くさしこむすきまへ近づいた。
そして服の中から本を、古いほうの『ひごめのむかしばなし』をとりだした。
進一郎が拍子抜けしたような顔になった。
「昨日の本じゃないか。もしかしていま読むのか。こんなときに」
「読まないと。津江さんにそうしろって言われました」
ゆれと暗がりのためにとても読みづらい。目で文字をたどったとたんに車酔いのような不快な感覚がミチの頭の奥にうまれた。とはいえ、どうにか読むことができた。
ミチが開いたのは目次のページだった。
新しいほうの本、さっき障療院の図書室で開いたほうの『ひごめのむかしばなし』に載っていた『観音様と赤い文字』がおなじようにいちばんはじめにある。
ミチはいそいで目次にならぶ文字を目で追いかけた。
『銀杏の葉はなぜ黄色いか』
『秋を呼ぶ大牛のはなし』
『熊とお嫁さんの力くらべ」……。
ミチの目は、目次のさいごの行にとまった。
『かんなぎと池の化けもの』
(この古い本にだけ載っていて、新しいほう、障療院の図書室にあった本には載っていなかったのは、きっと、この話だ)
暗がりのなかで差しこむ光をたよりにしてミチはその話を読みはじめた。
それは障療院の図書室で読んだ『観音さまと赤い文字』よりもずっと長く、そして異様な話だった。
0
お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

なんども濡れ衣で責められるので、いい加減諦めて崖から身を投げてみた
下菊みこと
恋愛
悪役令嬢の最後の抵抗は吉と出るか凶と出るか。
ご都合主義のハッピーエンドのSSです。
でも周りは全くハッピーじゃないです。
小説家になろう様でも投稿しています。

光のもとで2
葉野りるは
青春
一年の療養を経て高校へ入学した翠葉は「高校一年」という濃厚な時間を過ごし、
新たな気持ちで新学期を迎える。
好きな人と両思いにはなれたけれど、だからといって順風満帆にいくわけではないみたい。
少し環境が変わっただけで会う機会は減ってしまったし、気持ちがすれ違うことも多々。
それでも、同じ時間を過ごし共に歩めることに感謝を……。
この世界には当たり前のことなどひとつもなく、あるのは光のような奇跡だけだから。
何か問題が起きたとしても、一つひとつ乗り越えて行きたい――
(10万文字を一冊として、文庫本10冊ほどの長さです)

カンナと田舎とイケメンの夏。~子供に優しい神様のタタリ~
猫野コロ
児童書・童話
家族みんなで母方の実家に里帰りしていたカンナ。
宿題を早々に終わらせ、ダラダラと田舎ぐらしを満喫するカンナに、突如、優しいおばあちゃんの無茶振りがおそいかかる。
そしていつのまにか、『知らない鈴木さん』の家の『知り合いですらないミィちゃん』、さらに『謎のベッカムくん』と遊ぶため、微妙に遠い鈴木さんの家へと向かうことに。
だが『可愛いミィちゃん』を想像していた彼女を待ち受けていたのは、なんと、ただのダルそうなイケメンだった。
常にダルそうな彼らと冴えない会話をくりひろげ、数日間だらだらと過ごすカンナ達に起こる、不思議な現象。
そうして襲い掛かる、次なる試練。
『なんか、私たち、祟られてません?』

ヒミツのJC歌姫の新作お菓子実食レビュー
弓屋 晶都
児童書・童話
顔出しNGで動画投稿活動をしている中学一年生のアキとミモザ、
動画の再生回数がどんどん伸びる中、二人の正体を探る人物の影が……。
果たして二人は身バレしないで卒業できるのか……?
走って歌ってまた走る、元気はつらつ少女のアキと、
悩んだり立ち止まったりしながらも、健気に頑張るミモザの、
イマドキ中学生のドキドキネットライフ。
男子は、甘く優しい低音イケボの生徒会長や、
イケメン長身なのに女子力高めの苦労性な長髪書記に、
どこからどう見ても怪しいメガネの放送部長が出てきます。
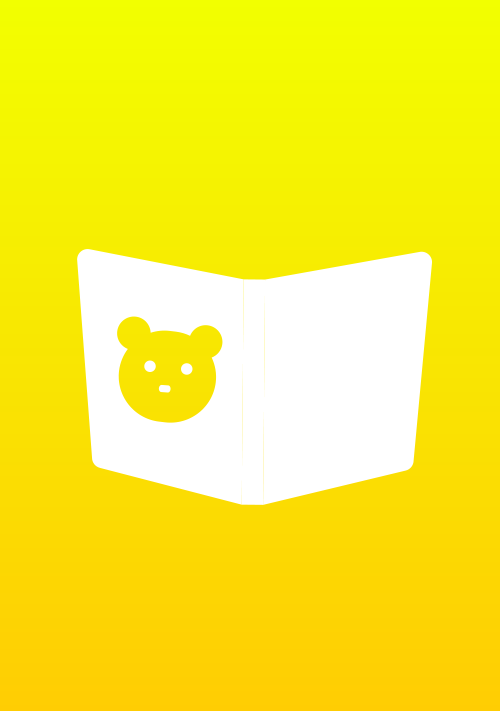
僕の中には、5人の僕がいる
るいのいろ
絵本
のんびり屋のはやとくん。
はやとくんはいつものんびりしているように見えるけど、実は頭の中で色々考えてる…。
はやとくんの頭の中で繰り広げられる、個性豊かな5人のはやとくんが見所です

【完結済】(無自覚)妖精に転生した僕は、騎士の溺愛に気づかない。
キノア9g
BL
完結済。騎士エリオット視点を含め全10話(エリオット視点2話と主人公視点8話構成)
エロなし。騎士×妖精
※主人公が傷つけられるシーンがありますので、苦手な方はご注意ください。
気がつくと、僕は見知らぬ不思議な森にいた。
木や草花どれもやけに大きく見えるし、自分の体も妙に華奢だった。
色々疑問に思いながらも、1人は寂しくて人間に会うために森をさまよい歩く。
ようやく出会えた初めての人間に思わず話しかけたものの、言葉は通じず、なぜか捕らえられてしまい、無残な目に遭うことに。
捨てられ、意識が薄れる中、僕を助けてくれたのは、優しい騎士だった。
彼の献身的な看病に心が癒される僕だけれど、彼がどんな思いで僕を守っているのかは、まだ気づかないまま。
少しずつ深まっていくこの絆が、僕にどんな運命をもたらすのか──?
いいねありがとうございます!励みになります。


その男、有能につき……
大和撫子
BL
俺はその日最高に落ち込んでいた。このまま死んで異世界に転生。チート能力を手に入れて最高にリア充な人生を……なんてことが現実に起こる筈もなく。奇しくもその日は俺の二十歳の誕生日だった。初めて飲む酒はヤケ酒で。簡単に酒に呑まれちまった俺はフラフラと渋谷の繁華街を彷徨い歩いた。ふと気づいたら、全く知らない路地(?)に立っていたんだ。そうだな、辺りの建物や雰囲気でいったら……ビクトリア調時代風? て、まさかなぁ。俺、さっきいつもの道を歩いていた筈だよな? どこだよ、ここ。酔いつぶれて寝ちまったのか?
「君、どうかしたのかい?」
その時、背後にフルートみたいに澄んだ柔らかい声が響いた。突然、そう話しかけてくる声に振り向いた。そこにいたのは……。
黄金の髪、真珠の肌、ピンクサファイアの唇、そして光の加減によって深紅からロイヤルブルーに変化する瞳を持った、まるで全身が宝石で出来ているような超絶美形男子だった。えーと、確か電気の光と太陽光で色が変わって見える宝石、あったような……。後で聞いたら、そんな風に光によって赤から青に変化する宝石は『ベキリーブルーガーネット』と言うらしい。何でも、翠から赤に変化するアレキサンドライトよりも非常に希少な代物だそうだ。
彼は|Radius《ラディウス》~ラテン語で「光源」の意味を持つ、|Eternal《エターナル》王家の次男らしい。何だか分からない内に彼に気に入られた俺は、エターナル王家第二王子の専属侍従として仕える事になっちまったんだ! しかもゆくゆくは執事になって欲しいんだとか。
だけど彼は第二王子。専属についている秘書を始め護衛役や美容師、マッサージ師などなど。数多く王子と密に接する男たちは沢山いる。そんな訳で、まずは見習いから、と彼らの指導のもと、仕事を覚えていく訳だけど……。皆、王子の寵愛を独占しようと日々蹴落としあって熾烈な争いは日常茶飯事だった。そんな中、得体の知れない俺が王子直々で専属侍従にする、なんていうもんだから、そいつらから様々な嫌がらせを受けたりするようになっちまって。それは日増しにエスカレートしていく。
大丈夫か? こんな「ムササビの五能」な俺……果たしてこのまま皇子の寵愛を受け続ける事が出来るんだろうか?
更には、第一王子も登場。まるで第二王子に対抗するかのように俺を引き抜こうとしてみたり、波乱の予感しかしない。どうなる? 俺?!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















