お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

なんども濡れ衣で責められるので、いい加減諦めて崖から身を投げてみた
下菊みこと
恋愛
悪役令嬢の最後の抵抗は吉と出るか凶と出るか。
ご都合主義のハッピーエンドのSSです。
でも周りは全くハッピーじゃないです。
小説家になろう様でも投稿しています。

転生姫様の最強学園ライフ! 〜異世界魔王のやりなおし〜
灰色キャット
ファンタジー
別世界で魔王として君臨していた女の子――センデリア・エンシャスは当時最強の勇者に敗れ、その命を終えた。
人の温もりに終ぞ触れることなかったセンデリアだったが、最後に彼女が考えていた事を汲み取った神様に、なんの断りもなく異世界に存在する一国家の姫へと生まれ変わらせてしまった!?
「……あたし、なんでまた――」
魔王にならざるを得なかった絶望。恐怖とは遠い世界で、新たな生を受け、今まで無縁だった暖かい生活に戸惑いながら……世界一の学園を決める祭り――『魔導学園王者決闘祭(通称:魔王祭)』に巻き込まれていく!?

【完結】英雄小学生アフター~氷の女王と春の歌姫~
森原ヘキイ
児童書・童話
――あの日。まだ小学生だったボクたちは、異世界を救った英雄になった。
5人の中学生による異世界救済後のアフターストーリー!
中学一年生の赤星(あかぼし)マコトは、なにか大切なものを忘れてしまったような寂しさを覚えながら毎日を過ごしていた。ある日、東京シテイ最大規模のクリスマスマーケットへとやってきたマコトは、不思議な懐かしさを感じる氷の城のオブジェクトの前で、とある少女と目を合わせる。
その瞬間、思い出した。
自分は三年前の小学生のとき、目の前の少女とともに異世界を救ったのだと――。
桃園(ももぞの)ミサキ。イノシシも裸足で逃げ出す行動派美少女。
緑木(みどりぎ)タイシ。とことんマイペースな物知り変人眼鏡。
青葉(あおば)ユウ。怒らせると怖い「みんなのお母さん(♂)」
黒鐘(くろがね)エリヤ。圧倒的な存在感を放つ人外美形な俺様。
個性的な仲間たちと次々に再会を果たすマコトだったが、彼らとイベントを楽しんだりビュッフェを満喫しているうちに、ふとしたことがきっかけで大切なことを思い出してしまう。
「ボクたちには、六人目の仲間がいたはずなんだ!」
もしかしたらアイドルになっているかもしれないその仲間と、一体どうやって出会えばいいのか。
手段を求めて奔走するマコトたちに、なぜか異世界で倒したはずの氷の女王の影が忍び寄って――!?
デコレージョンという超最先端映像技術や動物型ロボットなどが普通に存在する近未来世界を舞台に、二時間映画として映像化しても飽きないようなワクワクする展開を盛り込みました。個性の強めなキャラによるコントのような掛け合い、ちょっとしたバトルアクション、音楽と演出を意識したラストシーンなど、とにかく楽しんでいただけたら嬉しいです。

魔法アプリ【グリモワール】
阿賀野めいり
児童書・童話
◆異世界の力が交錯する町で、友情と成長が織りなす新たな魔法の物語◆
小学5年生の竹野智也(たけのともや) は、【超常事件】が発生する町、【新都心:喜志間ニュータウン】で暮らしていた。夢の中で現れる不思議な青年や、年上の友人・春風颯(はるかぜはやて)との交流の中でその日々を過ごしていた。
ある夜、町を突如襲った異変──夜にもかかわらず、オフィス街が昼のように明るく輝いた。その翌日、智也のスマートフォンに謎のアプリ【グリモワール】がインストールされていた。消そうとしても消えないアプリ。そして、智也は突然見たこともない化け物に襲われる。そんな智也を救ったのは、春風颯だった。しかも彼の正体は【異世界】の住人で――。
アプリの力によって魔法使いとなった智也は、颯とともに、次々と発生する【超常事件】に挑む。しかし、これらの事件が次第に智也自身の運命を深く絡め取っていくことにまだ気づいていなかった――。
※カクヨムでも連載しております※

スライム10,000体討伐から始まるハーレム生活
昼寝部
ファンタジー
この世界は12歳になったら神からスキルを授かることができ、俺も12歳になった時にスキルを授かった。
しかし、俺のスキルは【@&¥#%】と正しく表記されず、役に立たないスキルということが判明した。
そんな中、両親を亡くした俺は妹に不自由のない生活を送ってもらうため、冒険者として活動を始める。
しかし、【@&¥#%】というスキルでは強いモンスターを討伐することができず、3年間冒険者をしてもスライムしか倒せなかった。
そんなある日、俺がスライムを10,000体討伐した瞬間、スキル【@&¥#%】がチートスキルへと変化して……。
これは、ある日突然、最強の冒険者となった主人公が、今まで『スライムしか倒せないゴミ』とバカにしてきた奴らに“ざまぁ”し、美少女たちと幸せな日々を過ごす物語。
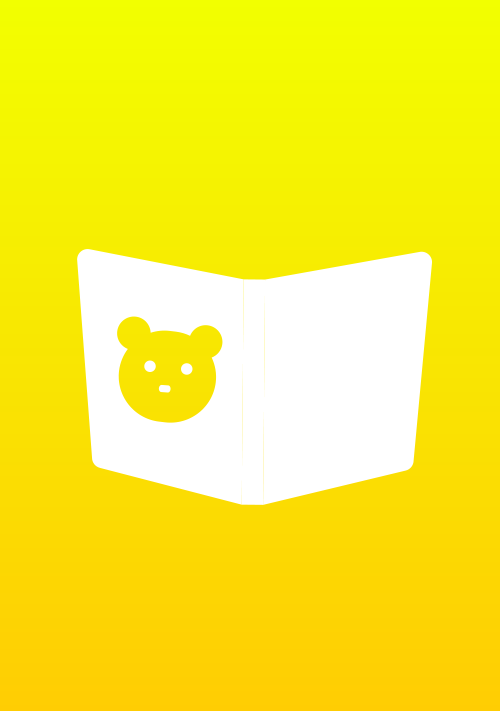
僕の中には、5人の僕がいる
るいのいろ
絵本
のんびり屋のはやとくん。
はやとくんはいつものんびりしているように見えるけど、実は頭の中で色々考えてる…。
はやとくんの頭の中で繰り広げられる、個性豊かな5人のはやとくんが見所です

亀さんののんびりお散歩旅
しんしん
児童書・童話
これは亀のようにゆっくりでも着々と進んでいく。そんな姿をみて、自分も頑張ろう!ゆっくりでも時間をかけていこう。
そんな気持ちになってほしいです。
あとはほのぼの見てあげてください笑笑
目的 カミール海岸へ行くこと
出発地 サミール海岸

光のもとで2
葉野りるは
青春
一年の療養を経て高校へ入学した翠葉は「高校一年」という濃厚な時間を過ごし、
新たな気持ちで新学期を迎える。
好きな人と両思いにはなれたけれど、だからといって順風満帆にいくわけではないみたい。
少し環境が変わっただけで会う機会は減ってしまったし、気持ちがすれ違うことも多々。
それでも、同じ時間を過ごし共に歩めることに感謝を……。
この世界には当たり前のことなどひとつもなく、あるのは光のような奇跡だけだから。
何か問題が起きたとしても、一つひとつ乗り越えて行きたい――
(10万文字を一冊として、文庫本10冊ほどの長さです)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















