お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

なんども濡れ衣で責められるので、いい加減諦めて崖から身を投げてみた
下菊みこと
恋愛
悪役令嬢の最後の抵抗は吉と出るか凶と出るか。
ご都合主義のハッピーエンドのSSです。
でも周りは全くハッピーじゃないです。
小説家になろう様でも投稿しています。

光のもとで2
葉野りるは
青春
一年の療養を経て高校へ入学した翠葉は「高校一年」という濃厚な時間を過ごし、
新たな気持ちで新学期を迎える。
好きな人と両思いにはなれたけれど、だからといって順風満帆にいくわけではないみたい。
少し環境が変わっただけで会う機会は減ってしまったし、気持ちがすれ違うことも多々。
それでも、同じ時間を過ごし共に歩めることに感謝を……。
この世界には当たり前のことなどひとつもなく、あるのは光のような奇跡だけだから。
何か問題が起きたとしても、一つひとつ乗り越えて行きたい――
(10万文字を一冊として、文庫本10冊ほどの長さです)

アルファポリスで閲覧者数を増やすための豆プラン
野菜ばたけ@既刊5冊📚好評発売中!
エッセイ・ノンフィクション
私がアルファポリスでの活動から得た『誰にでも出来る地道なPV獲得術』を、豆知識的な感じで書いていきます。
※思いついた時に書くので、不定期更新です。
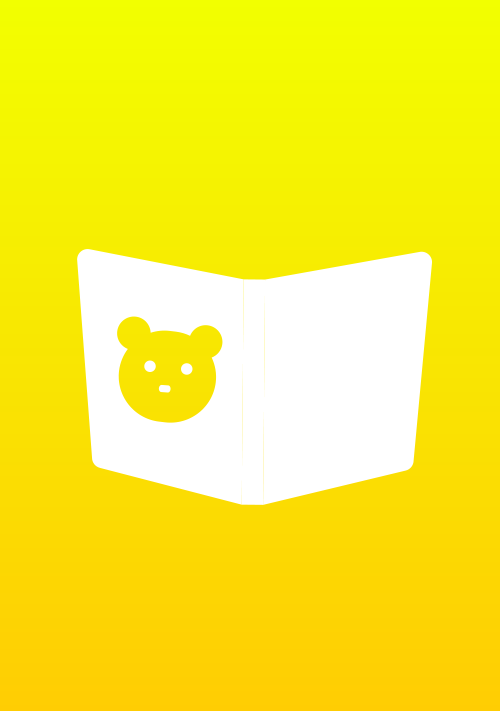
僕の中には、5人の僕がいる
るいのいろ
絵本
のんびり屋のはやとくん。
はやとくんはいつものんびりしているように見えるけど、実は頭の中で色々考えてる…。
はやとくんの頭の中で繰り広げられる、個性豊かな5人のはやとくんが見所です

その男、有能につき……
大和撫子
BL
俺はその日最高に落ち込んでいた。このまま死んで異世界に転生。チート能力を手に入れて最高にリア充な人生を……なんてことが現実に起こる筈もなく。奇しくもその日は俺の二十歳の誕生日だった。初めて飲む酒はヤケ酒で。簡単に酒に呑まれちまった俺はフラフラと渋谷の繁華街を彷徨い歩いた。ふと気づいたら、全く知らない路地(?)に立っていたんだ。そうだな、辺りの建物や雰囲気でいったら……ビクトリア調時代風? て、まさかなぁ。俺、さっきいつもの道を歩いていた筈だよな? どこだよ、ここ。酔いつぶれて寝ちまったのか?
「君、どうかしたのかい?」
その時、背後にフルートみたいに澄んだ柔らかい声が響いた。突然、そう話しかけてくる声に振り向いた。そこにいたのは……。
黄金の髪、真珠の肌、ピンクサファイアの唇、そして光の加減によって深紅からロイヤルブルーに変化する瞳を持った、まるで全身が宝石で出来ているような超絶美形男子だった。えーと、確か電気の光と太陽光で色が変わって見える宝石、あったような……。後で聞いたら、そんな風に光によって赤から青に変化する宝石は『ベキリーブルーガーネット』と言うらしい。何でも、翠から赤に変化するアレキサンドライトよりも非常に希少な代物だそうだ。
彼は|Radius《ラディウス》~ラテン語で「光源」の意味を持つ、|Eternal《エターナル》王家の次男らしい。何だか分からない内に彼に気に入られた俺は、エターナル王家第二王子の専属侍従として仕える事になっちまったんだ! しかもゆくゆくは執事になって欲しいんだとか。
だけど彼は第二王子。専属についている秘書を始め護衛役や美容師、マッサージ師などなど。数多く王子と密に接する男たちは沢山いる。そんな訳で、まずは見習いから、と彼らの指導のもと、仕事を覚えていく訳だけど……。皆、王子の寵愛を独占しようと日々蹴落としあって熾烈な争いは日常茶飯事だった。そんな中、得体の知れない俺が王子直々で専属侍従にする、なんていうもんだから、そいつらから様々な嫌がらせを受けたりするようになっちまって。それは日増しにエスカレートしていく。
大丈夫か? こんな「ムササビの五能」な俺……果たしてこのまま皇子の寵愛を受け続ける事が出来るんだろうか?
更には、第一王子も登場。まるで第二王子に対抗するかのように俺を引き抜こうとしてみたり、波乱の予感しかしない。どうなる? 俺?!

幽霊横丁へいらっしゃい~バスを降りるとそこは幽霊たちが住む町でした~
風雅ありす
児童書・童話
5歳の女の子【あかり】は、死んだ人の姿を見ることができる。
亡くなった母親の姿も幽霊としてあかりの傍に居てくれたのに、
ある日突然、姿が見えなくなってしまう。
消えてしまった母を捜して、あかりは一人、バスに乗る。
それは、死んだ人たちだけが乗ることのできる特別なバスだった。
果たして、あかりは、無事に母親に再会できるのか――――?

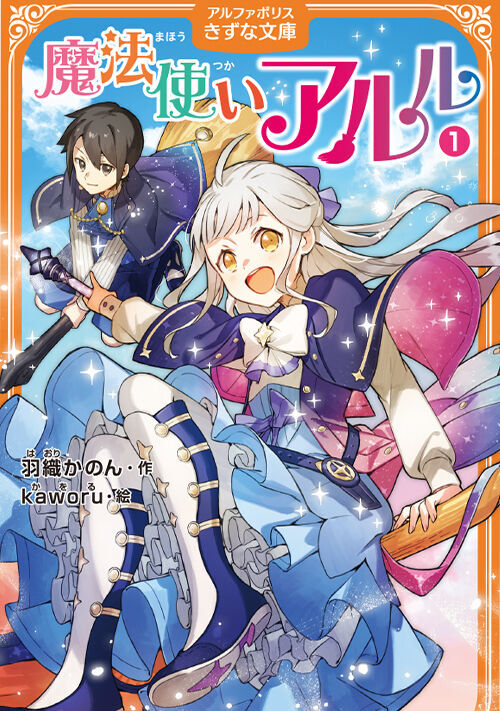
魔法使いアルル
かのん
児童書・童話
今年で10歳になるアルルは、月夜の晩、自分の誕生日に納屋の中でこっそりとパンを食べながら歌を歌っていた。
これまで自分以外に誰にも祝われる事のなかった日。
だが、偉大な大魔法使いに出会うことでアルルの世界は色を変えていく。
孤独な少女アルルが、魔法使いになって奮闘する物語。
ありがたいことに書籍化が進行中です!ありがとうございます。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















