5 / 5
浅草オペラの怪人
浅草巴里劇場──③
しおりを挟む
――そして、滝野川の邸宅。
土御門保憲は、蘆屋いすゞを前にして、極めて不機嫌だった。
「君に誘われる時には碌な事がない。あのように不味い紅茶を飲まされ、最悪だ」
「で、早く口直しをしたいから適当に依頼を受けて、大急ぎでお屋敷に戻って来たと」
手入れされた庭園の一角に据えられたテーブルは、彼のお気に入りの場所である。
春の日差しが照らす花壇に咲き誇る花々。今は水仙が可愛らしい姿を揺らしている。
安楽椅子に身を任せ眺めるその光景をだが、いすゞの長身が邪魔をする。
「まるで我儘な子供ですね」
「そもそも私には、君の都合に合わせなければならない義理などないのだ」
そこに、家政婦のタツ子が、ワゴンを押して現れた。
紬の着物に割烹着、白髪混じりの髪を二百三高地に結った、上品な老婦人である。保憲のお守り役として、彼が幼い頃からこの屋敷に住み込んでいる彼女は、保憲の紅茶の嗜好を完璧に把握している。そのため、味にうるさい彼も、彼女の淹れるものなら文句を言わず口にする。
「坊ちゃま、苛々は体に良くありませんよ。ミルクティーで気分を落ち着けなさいませ」
手際よくティーカップにアールグレイを注ぎ、ミルクをたっぷりと垂らす。それを手に取り、深く鼻腔に香りを含ませたところで、ようやく保憲は眉間の皺を和らげた。
「……しかし、タツ子さん。いい加減、『坊ちゃま』という呼び方を改めてはくれないかね? 私は既に三十路を過ぎている」
白磁に青の唐草柄が鮮やかなティーカップを手の中で揺らし、保憲は渋い目を家政婦に向ける。だが彼女は、
「お幾つになっても、坊ちゃまは坊ちゃまですのよ」
と微笑みを湛えたまま、もうひとつのカップをいすゞの前に置いた。
軽く頭を下げてそれを受け取ると、彼女は保憲の向かいに腰を下ろした。
「でも、先生が依頼を受けてくださって安心しました。あの劇場、営業していた頃はかなり羽振りが良くって、弱小出版社のうちは、相当助けられてたんです」
「君がその恩を返したいのは分かる。だが、私を騙して良い理由にはならない」
「それはお詫びします。……これは、東インド会社が独占販売してる、アッサムの特級品です」
いすゞはそう言って、英字で刻印された赤い缶を保憲に差し出した。渋い顔でそれを受け取り、彼は大きく溜息を吐く。
「君ほど姑息な人間は他にいないだろう」
「でも先生だって、解決できる見込みがあるから、依頼を受けたんですよね?」
だが保憲は、悠々とミルクティーを味わうばかりで返事をしない。
いすゞは眉根を寄せた。
「まさか、本当に適当に依頼を受けたんですか?」
「受けなければ、今こうして、ミルクティーを味わえなかっただろう。温かいうちに、君も味わいたまえ。ベルガモットの香りは冷めると損なわれてしまう」
「私、この香り、ちょっと苦手です」
いすゞはテーブルのミルクポットからミルクを注ぎ足し、白い目を保憲に向けた。
「先生が解決してくれなきゃ、私、出版社をクビになっちゃいます」
「それは君の勝手だ。私の責任ではない」
「そんな、酷い……」
いすゞはカップに口を付ける形で口を尖らせた。
「先生がそんな冷たい人だとは思いませんでした」
「君がどうなろうと、私の知った事ではない。帰ってくれ」
保憲がそう言うと、いすゞは一息にカップを空け、ガシャンとテーブルに置いた。
そして立ち上がり、
「イーだ!」
と保憲に舌を見せてから、靴音高く庭園を出て行った。
「……全く、下品な女だ」
呆れる保憲の横で、タツ子は彼女のいた椅子に目を遣った。そして、
「あら、お忘れ物ですね」
と、黒い表紙の綴りを取り上げ、彼に手渡した。
「…………」
劇場日報である。――いすゞは、何としても彼を巻き込みたいのだろう。
そして、忘れ物に気付きながら、それを指摘しなかったタツ子もまた、共犯なのだ。
黒い表紙を眺めて、保憲は肩を竦めた。
◇
その晩。
書斎に引き上げた保憲は、いすゞが置いていった劇場日誌を机に置き、頁を捲っていた。
……建て前とはいえ、一応は依頼を引き受けたのである。苛立ち紛れに彼女にはあのように接したが、解決の如何はともかく、無視をするつもりはなかった。
テーブルランプが照らす紙面には、支配人のものと思われる文字で日記が記されていた。
その中から、彼が言っていた「三件の事故」に当たる記事を探し出し、隣の帳面に書き出していく。
――一件目は、去年の十月。
当時のプリマドンナである大空ミソノが、舞台袖の階段から落ちて死亡。
二件目は、去年の十二月。
同じくプリマドンナの毛受千恵子が、リハーサル中に落下した照明に当たり重傷。
そして三件目は、今年の二月はじめ。
またもやプリマドンナの渡口すみれが、セリを動かすワイヤーに巻き込まれ死亡……。
眉を顰めて、保憲は顔を上げた。
三件目は彼も新聞で読み知っていた。――歌姫の名声と共に、巻き上げられるワイヤーに衣装が絡み胴体が切断されるという、余りに凄惨な死因に、各紙は大々的にこの事故を報じた。
当時もその状況を思い浮かべて胸が悪くなったものだが、再びそれを思い出し、彼は慌てて傍らのティーカップに口を付けた。
それから手にしたのは、ラウンジで支配人が見せた脅迫状。
厚紙のカードは、葉書ほどの大きさの、何の変哲もない量産品である。
三枚を机に並べるが、活字の貼られた文面はどれも同じ。活字の大きさも揃っている。強いて言えば、貼られた位置が若干異なるくらいだ。
保憲は眼鏡を近付け、文字をよく観察する。
活版印刷された紙面は上質なものと見える。新聞や雑誌のような粗悪さはなく、滑らかで白い。書籍を切り抜いたものだろう。
活版印刷とは、文字ごとに作られた金属製の凸版を並べ、版画の要領で印刷したもの。印刷所ごとに凸版に微妙な違いがある。そこを調べれば、どの本から切り取られたものであるかを調べるのは、難しくはないだろう。
警察はそこまで調べたのだろうか?
そう考えていた時。
扉を叩く音がして、保憲はカップを机に戻した。
――扉から現れたのは、初老の男。痩身に濃灰のフロックコートを隙なく着込んだ彼は、この屋敷の執事である浅尾である。
彼は恭しく一礼すると、
「先程、電報が届きましてございます」
と、保憲に告げた。
「誰からだ?」
「忠行様にございます」
その名を聞き、保憲は無意識に背筋を伸ばした。
「――用件は?」
「坊ちゃまのお受けなさったご依頼に、協力をしてくださる人物をご紹介くださる、との事です」
と、浅尾は電報用紙を彼の前に置いた。
浅尾が下がった後、保憲は文面に目を通す。
「…………」
それから彼は電報を机に投げ、背もたれに身を預けて天井を仰いだ。
――土御門忠行。彼の兄である。
現・土御門家の当主であり、子爵。貴族院議員として、また実業家として、政財界で活躍している。
……そして、滝野川にあるこの邸宅も、彼のものである。
忙しく各地を飛び回っている兄に代わり、社会不適合気味の弟である保憲が、その留守番を仰せ付かっているのだ。――言わば、居候である。
そんな兄が珍しく連絡を寄越して来たと思えば、今回の依頼に関するもの。
保憲は苦々しい顔でティーカップを手に取る。
「あの女狐め、何としても私が逃げ出さないように囲い込みたいようだ」
電報には、彼の旧知である警視庁の警部を明日、浅草巴里劇場に行かせるから、説明に立ち会うように、とあった。
――つまり、蘆屋いすゞが家柄のツテで、忠行に連絡を取ったのだ。
脛をかじっている兄の言い付けとあれば、断る訳にはいかないのを分かって……!
保憲は歯噛みしたが、こうなっては彼に逃げ道はない。
恨めしい目で机の電報を睨み、彼は冷めた紅茶を一息に飲み干した。
土御門保憲は、蘆屋いすゞを前にして、極めて不機嫌だった。
「君に誘われる時には碌な事がない。あのように不味い紅茶を飲まされ、最悪だ」
「で、早く口直しをしたいから適当に依頼を受けて、大急ぎでお屋敷に戻って来たと」
手入れされた庭園の一角に据えられたテーブルは、彼のお気に入りの場所である。
春の日差しが照らす花壇に咲き誇る花々。今は水仙が可愛らしい姿を揺らしている。
安楽椅子に身を任せ眺めるその光景をだが、いすゞの長身が邪魔をする。
「まるで我儘な子供ですね」
「そもそも私には、君の都合に合わせなければならない義理などないのだ」
そこに、家政婦のタツ子が、ワゴンを押して現れた。
紬の着物に割烹着、白髪混じりの髪を二百三高地に結った、上品な老婦人である。保憲のお守り役として、彼が幼い頃からこの屋敷に住み込んでいる彼女は、保憲の紅茶の嗜好を完璧に把握している。そのため、味にうるさい彼も、彼女の淹れるものなら文句を言わず口にする。
「坊ちゃま、苛々は体に良くありませんよ。ミルクティーで気分を落ち着けなさいませ」
手際よくティーカップにアールグレイを注ぎ、ミルクをたっぷりと垂らす。それを手に取り、深く鼻腔に香りを含ませたところで、ようやく保憲は眉間の皺を和らげた。
「……しかし、タツ子さん。いい加減、『坊ちゃま』という呼び方を改めてはくれないかね? 私は既に三十路を過ぎている」
白磁に青の唐草柄が鮮やかなティーカップを手の中で揺らし、保憲は渋い目を家政婦に向ける。だが彼女は、
「お幾つになっても、坊ちゃまは坊ちゃまですのよ」
と微笑みを湛えたまま、もうひとつのカップをいすゞの前に置いた。
軽く頭を下げてそれを受け取ると、彼女は保憲の向かいに腰を下ろした。
「でも、先生が依頼を受けてくださって安心しました。あの劇場、営業していた頃はかなり羽振りが良くって、弱小出版社のうちは、相当助けられてたんです」
「君がその恩を返したいのは分かる。だが、私を騙して良い理由にはならない」
「それはお詫びします。……これは、東インド会社が独占販売してる、アッサムの特級品です」
いすゞはそう言って、英字で刻印された赤い缶を保憲に差し出した。渋い顔でそれを受け取り、彼は大きく溜息を吐く。
「君ほど姑息な人間は他にいないだろう」
「でも先生だって、解決できる見込みがあるから、依頼を受けたんですよね?」
だが保憲は、悠々とミルクティーを味わうばかりで返事をしない。
いすゞは眉根を寄せた。
「まさか、本当に適当に依頼を受けたんですか?」
「受けなければ、今こうして、ミルクティーを味わえなかっただろう。温かいうちに、君も味わいたまえ。ベルガモットの香りは冷めると損なわれてしまう」
「私、この香り、ちょっと苦手です」
いすゞはテーブルのミルクポットからミルクを注ぎ足し、白い目を保憲に向けた。
「先生が解決してくれなきゃ、私、出版社をクビになっちゃいます」
「それは君の勝手だ。私の責任ではない」
「そんな、酷い……」
いすゞはカップに口を付ける形で口を尖らせた。
「先生がそんな冷たい人だとは思いませんでした」
「君がどうなろうと、私の知った事ではない。帰ってくれ」
保憲がそう言うと、いすゞは一息にカップを空け、ガシャンとテーブルに置いた。
そして立ち上がり、
「イーだ!」
と保憲に舌を見せてから、靴音高く庭園を出て行った。
「……全く、下品な女だ」
呆れる保憲の横で、タツ子は彼女のいた椅子に目を遣った。そして、
「あら、お忘れ物ですね」
と、黒い表紙の綴りを取り上げ、彼に手渡した。
「…………」
劇場日報である。――いすゞは、何としても彼を巻き込みたいのだろう。
そして、忘れ物に気付きながら、それを指摘しなかったタツ子もまた、共犯なのだ。
黒い表紙を眺めて、保憲は肩を竦めた。
◇
その晩。
書斎に引き上げた保憲は、いすゞが置いていった劇場日誌を机に置き、頁を捲っていた。
……建て前とはいえ、一応は依頼を引き受けたのである。苛立ち紛れに彼女にはあのように接したが、解決の如何はともかく、無視をするつもりはなかった。
テーブルランプが照らす紙面には、支配人のものと思われる文字で日記が記されていた。
その中から、彼が言っていた「三件の事故」に当たる記事を探し出し、隣の帳面に書き出していく。
――一件目は、去年の十月。
当時のプリマドンナである大空ミソノが、舞台袖の階段から落ちて死亡。
二件目は、去年の十二月。
同じくプリマドンナの毛受千恵子が、リハーサル中に落下した照明に当たり重傷。
そして三件目は、今年の二月はじめ。
またもやプリマドンナの渡口すみれが、セリを動かすワイヤーに巻き込まれ死亡……。
眉を顰めて、保憲は顔を上げた。
三件目は彼も新聞で読み知っていた。――歌姫の名声と共に、巻き上げられるワイヤーに衣装が絡み胴体が切断されるという、余りに凄惨な死因に、各紙は大々的にこの事故を報じた。
当時もその状況を思い浮かべて胸が悪くなったものだが、再びそれを思い出し、彼は慌てて傍らのティーカップに口を付けた。
それから手にしたのは、ラウンジで支配人が見せた脅迫状。
厚紙のカードは、葉書ほどの大きさの、何の変哲もない量産品である。
三枚を机に並べるが、活字の貼られた文面はどれも同じ。活字の大きさも揃っている。強いて言えば、貼られた位置が若干異なるくらいだ。
保憲は眼鏡を近付け、文字をよく観察する。
活版印刷された紙面は上質なものと見える。新聞や雑誌のような粗悪さはなく、滑らかで白い。書籍を切り抜いたものだろう。
活版印刷とは、文字ごとに作られた金属製の凸版を並べ、版画の要領で印刷したもの。印刷所ごとに凸版に微妙な違いがある。そこを調べれば、どの本から切り取られたものであるかを調べるのは、難しくはないだろう。
警察はそこまで調べたのだろうか?
そう考えていた時。
扉を叩く音がして、保憲はカップを机に戻した。
――扉から現れたのは、初老の男。痩身に濃灰のフロックコートを隙なく着込んだ彼は、この屋敷の執事である浅尾である。
彼は恭しく一礼すると、
「先程、電報が届きましてございます」
と、保憲に告げた。
「誰からだ?」
「忠行様にございます」
その名を聞き、保憲は無意識に背筋を伸ばした。
「――用件は?」
「坊ちゃまのお受けなさったご依頼に、協力をしてくださる人物をご紹介くださる、との事です」
と、浅尾は電報用紙を彼の前に置いた。
浅尾が下がった後、保憲は文面に目を通す。
「…………」
それから彼は電報を机に投げ、背もたれに身を預けて天井を仰いだ。
――土御門忠行。彼の兄である。
現・土御門家の当主であり、子爵。貴族院議員として、また実業家として、政財界で活躍している。
……そして、滝野川にあるこの邸宅も、彼のものである。
忙しく各地を飛び回っている兄に代わり、社会不適合気味の弟である保憲が、その留守番を仰せ付かっているのだ。――言わば、居候である。
そんな兄が珍しく連絡を寄越して来たと思えば、今回の依頼に関するもの。
保憲は苦々しい顔でティーカップを手に取る。
「あの女狐め、何としても私が逃げ出さないように囲い込みたいようだ」
電報には、彼の旧知である警視庁の警部を明日、浅草巴里劇場に行かせるから、説明に立ち会うように、とあった。
――つまり、蘆屋いすゞが家柄のツテで、忠行に連絡を取ったのだ。
脛をかじっている兄の言い付けとあれば、断る訳にはいかないのを分かって……!
保憲は歯噛みしたが、こうなっては彼に逃げ道はない。
恨めしい目で机の電報を睨み、彼は冷めた紅茶を一息に飲み干した。
0
お気に入りに追加
8
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説
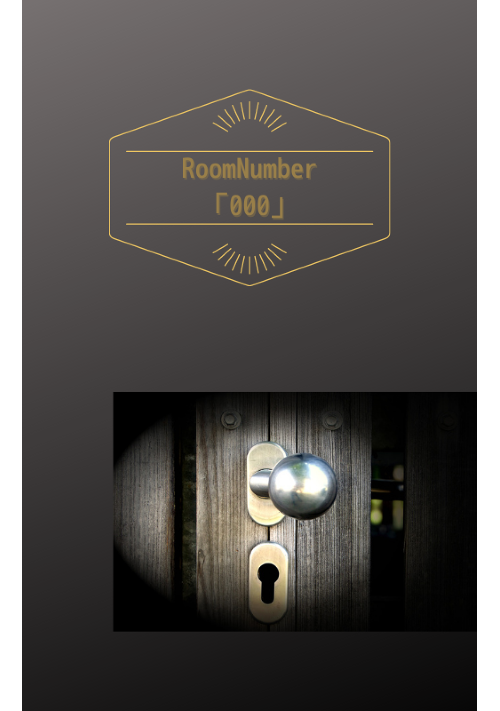
RoomNunmber「000」
誠奈
ミステリー
ある日突然届いた一通のメール。
そこには、報酬を与える代わりに、ある人物を誘拐するよう書かれていて……
丁度金に困っていた翔真は、訝しみつつも依頼を受け入れ、幼馴染の智樹を誘い、実行に移す……が、そこである事件に巻き込まれてしまう。
二人は密室となった部屋から出ることは出来るのだろうか?
※この作品は、以前別サイトにて公開していた物を、作者名及び、登場人物の名称等加筆修正を加えた上で公開しております。
※BL要素かなり薄いですが、匂わせ程度にはありますのでご注意を。


蠱惑Ⅱ
壺の蓋政五郎
ミステリー
人は歩いていると邪悪な壁に入ってしまう時がある。その壁は透明なカーテンで仕切られている。勢いのある時は壁を弾き迷うことはない。しかし弱っている時、また嘘を吐いた時、憎しみを表に出した時、その壁に迷い込む。蠱惑の続編で不思議な短編集です。

時の呪縛
葉羽
ミステリー
山間の孤立した村にある古びた時計塔。かつてこの村は繁栄していたが、失踪事件が連続して発生したことで、村人たちは恐れを抱き、時計塔は放置されたままとなった。17歳の天才高校生・神藤葉羽は、友人に誘われてこの村を訪れることになる。そこで彼は、幼馴染の望月彩由美と共に、村の秘密に迫ることになる。
葉羽と彩由美は、失踪事件に関する不気味な噂を耳にし、時計塔に隠された真実を解明しようとする。しかし、時計塔の内部には、過去の記憶を呼び起こす仕掛けが待ち受けていた。彼らは、時間が歪み、過去の失踪者たちの幻影に直面する中で、次第に自らの心の奥底に潜む恐怖と向き合わせることになる。
果たして、彼らは村の呪いを解き明かし、失踪事件の真相に辿り着けるのか?そして、彼らの友情と恋心は試される。緊迫感あふれる謎解きと心理的恐怖が交錯する本格推理小説。

没入劇場の悪夢:天才高校生が挑む最恐の密室殺人トリック
葉羽
ミステリー
演劇界の巨匠が仕掛ける、観客没入型の新作公演。だが、幕開け直前に主宰は地下密室で惨殺された。完璧な密室、奇妙な遺体、そして出演者たちの不可解な証言。現場に居合わせた天才高校生・神藤葉羽は、迷宮のような劇場に潜む戦慄の真実へと挑む。錯覚と現実が交錯する悪夢の舞台で、葉羽は観客を欺く究極の殺人トリックを暴けるのか? 幼馴染・望月彩由美との淡い恋心を胸に秘め、葉羽は劇場に潜む「何か」に立ち向かう。だが、それは想像を絶する恐怖の幕開けだった…。

マクデブルクの半球
ナコイトオル
ミステリー
ある夜、電話がかかってきた。ただそれだけの、はずだった。
高校時代、自分と折り合いの付かなかった優等生からの唐突な電話。それが全てのはじまりだった。
電話をかけたのとほぼ同時刻、何者かに突き落とされ意識不明となった青年コウと、そんな彼と昔折り合いを付けることが出来なかった、容疑者となった女、ユキ。どうしてこうなったのかを調べていく内に、コウを突き落とした容疑者はどんどんと増えてきてしまう───
「犯人を探そう。出来れば、彼が目を覚ますまでに」
自他共に認める在宅ストーカーを相棒に、誰かのために進む、犯人探し。

意識転移鏡像 ~ 歪む時間、崩壊する自我 ~
葉羽
ミステリー
「時間」を操り、人間の「意識」を弄ぶ、前代未聞の猟奇事件が発生。古びた洋館を改造した私設研究所で、昏睡状態の患者たちが次々と不審死を遂げる。死因は病死や事故死とされたが、その裏には恐るべき実験が隠されていた。被害者たちは、鏡像体と呼ばれる自身の複製へと意識を転移させられ、時間逆行による老化と若返りを繰り返していたのだ。歪む時間軸、変質する記憶、そして崩壊していく自我。天才高校生・神藤葉羽は、幼馴染の望月彩由美と共に、この難解な謎に挑む。しかし、彼らの前に立ちはだかるのは、想像を絶する恐怖と真実への迷宮だった。果たして葉羽は、禁断の実験の真相を暴き、被害者たちの魂を救うことができるのか?そして、事件の背後に潜む驚愕のどんでん返しとは?究極の本格推理ミステリーが今、幕を開ける。

ダブルネーム
しまおか
ミステリー
有名人となった藤子の弟が謎の死を遂げ、真相を探る内に事態が急変する!
四十五歳でうつ病により会社を退職した藤子は、五十歳で純文学の新人賞を獲得し白井真琴の筆名で芥山賞まで受賞し、人生が一気に変わる。容姿や珍しい経歴もあり、世間から注目を浴びテレビ出演した際、渡部亮と名乗る男の死についてコメント。それが後に別名義を使っていた弟の雄太と知らされ、騒動に巻き込まれる。さらに本人名義の土地建物を含めた多額の遺産は全て藤子にとの遺書も発見され、いくつもの謎を残して死んだ彼の過去を探り始めた。相続を巡り兄夫婦との確執が産まれる中、かつて雄太の同僚だったと名乗る同性愛者の女性が現れ、警察は事故と処理したが殺されたのではと言い出す。さらに刑事を紹介され裏で捜査すると告げられる。そうして真相を解明しようと動き出した藤子を待っていたのは、予想をはるかに超える事態だった。登場人物のそれぞれにおける人生や、藤子自身の過去を振り返りながら謎を解き明かす、どんでん返しありのミステリー&サスペンス&ヒューマンドラマ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















