31 / 36
四章 待ち焦がれた彗星
湖の中心へ
しおりを挟む
利玖は千堂に続いて柏名湖畔に降りて行った。
木陰にはまだ雪が残っていて、そのぼんやりとした白さのせいで地形が判然としない。何度も足元を確かめながら、藪をかき分けて最短距離で岸に近づいた。
命綱を結ぶ場所を探して湖岸を歩いていると、千堂がふと思い出したように、
「かなり水温が低いと思いますよ」
と声をかけてきた。
気温の低い屋外に長くとどまる事に対しての備えか、彼は空気をたっぷりと蓄えられそうなダウン・ジャケットを着て、黒い手袋も嵌めている。一度は利玖と共に店の外に出たのだが、開口一番に、
「うわ、寒いですね」
と言って防寒具を取りに店に戻っていた。
「下にドライスーツを着てきました」乾いた砂の地面に膝をついて、木々の根元をつぶさに見ながら利玖は言う。「他にも、防水対策を色々と。即座にショック死するような事はないはずです」
そう答えて立ち上がり、ズボンについた土を払ったが、正直な所、自信はなかった。何しろ、必要最低限の装備を、史岐に気づかれないように揃えるだけで精一杯だったのだ。厳冬期の湖に潜った経験なんて、勿論ないし、練習も出来なかった。ぶっつけ本番、一発勝負である。
それでも、ここで蹴りをつけなければならない。史岐がこれ以上、事態に深入りする前にやり遂げなければいけない。ひりつくようなその思いが、今の利玖を突き動かしていた。
もう猶予は残されていない、そう考えているせいで、焦っている自分を自覚もする。しかし、幸いな事に、たった一人で進めている事ではない。その気持ちが、わずかでもバランスを崩したら容易く折れてしまいそうなほど不安に浸食された利玖の心を、毛糸の靴下みたいにささやかに包んで温めていた。
三メートルほど右に移動した所で、一際頑健な針葉樹を見つけた。枝もたわわに葉が茂り、幹の直径は、利玖が両腕を回しても抱えきれないほど太い。
その針葉樹に命綱を結ぶ事に決めて、利玖はホームセンターで買ってきたロープをリュックサックから取り出した。船を港に係留する時の結び方を参考にして根元に結わえ付け、もう片方の端は、腰に巻いた安全帯に通して固定する。
千堂は、ロープを結んだ針葉樹の背後、結び目が見える位置に移動してきて、動かなくなった。
「そこで良いんですか?」ロープの張りを確かめながら、利玖は訊ねる。「駐車帯か、橋からご覧になられた方が良く見えると思いますよ」
「利玖さんが湖に入られるまでは、近くで見届けるつもりです」
つまりは、土壇場で自分が逃げ出さないように見張っているというわけか、と利玖は納得した。
利玖は再びリュックに手を入れて、銀箭の体組織を採取する為の針をケースから取り出す。今日、この時の為に美蕗が用意してくれた特注の道具で、市場には流通していないが、見た目と機能から言えば生検針と呼ぶのが近い。
すぐに使えるように、針を前方にして腕と脇腹の間に挟んだが、カバーは填めたままにしておいた。千堂とはまだ十分に距離が離れていない。万が一、後ろから襲われて奪い取られたら、逆に自分を脅す為の武器として使われてしまう。
生検針を挟んで固定しているのは、左手。右手はロープを握って、ゆっくりと湖に近づいていく。
危険なものは湖の中に潜んでいるとわかっているのに、なぜか、途中で空が見たくなって、利玖は視線を上げた。
夜空は抜群に澄んでいる。元々、潟杜市自体、六百メートル以上の標高がある。雲がなければ、月も星もよく見えるのだ。冬場は特に、空気が冷たく透きとおって、こうして街明かりを避けて高い所にやってくると、星の瞬きがきりきりと音を立てて肌を刺すように銀河の遙か彼方の光が間近に感じられる。
銀箭に喰われるという事は、たぶん、普通の死とはだいぶ違うのだろう。
利玖はまだ、彼にまつわる伝承のほんの一部しか知らないが、そこから想起されるものは、雨、閉塞感、息がつまるような冷たい泥、そういった要素の数々で、こんな風に遍く生きものに開かれた眩しい星空とは無縁の世界であるような気がした。
(これが見納めだとでも考えているのでしょうか)
存外にセンチメンタルじゃないか、と苦笑して、利玖は再び湖に目を戻し、ゴーグルを装着した。
蛉籃石は最低保証だ、と美蕗は言った。
だが、《とほつみの道》に入る手段を持たない自分が、ヌシと直に交渉して報酬を上乗せしてもらうなど、どう考えても無理な話だ。
千堂の絵も、見る者が見れば──あるいは、それが描かれた背景に物語性を見いだし、感銘を受ける観客が大勢いるのなら──値がつくのかもしれないが、真実を知る美蕗に捧げる礼としては、適当ではない。
だから、利玖は、銀箭の体組織を採取する事を思いついた。
銀箭によって被害がもたらされる場所は、おそらく、柏名山だけでは済まない。
潟杜市には、潮蕊湖のように際立った湖はないが、古くから使われてきた湧水地が点在しており、それを利用した水路や堀も現存している。銀箭が自在に水の中を行き来出来るとするならば、これから先も同じ事が、比較的近い地域で繰り返される可能性が高い。
ヒトの理とかけ離れた異形の一部を採取し、分析器にかける事など、大学の研究施設では不可能だが、美蕗のように妖と深い関わりを持つ旧家の主であれば、そういう事が出来る機関に伝手があるかもしれない。
調査を進める中で、部分的にでも銀箭を無力化出来る方法が見つかれば、それは今後、銀箭によって被害がもたらされるかもしれない土地に棲むモノ達と対峙した時に、大きなアドバンテージになる。利玖が持っていても役に立たないものだが、美蕗なら最大限有効に活用し、彼女の絶対的な権力を保持し続ける為の礎として使いこなすだろう。
しかし、最たる理由は、利玖自身が自分の心と記憶を蝕むモノの正体を知りたい、と強く願っている為だった。
昔話や伝説だけで満足してしまうのではなく、兄のような研究者として、銀箭に向き合い、秘されてきたものを解き明かしたい。
超常とされる存在にも、ヒトの理が適用される法則があり、生きものとしての厳粛な秩序がある。その事を証明したかった。
そういった、執着とも呼べる強い思いがあったからこそ、史岐を欺き、身一つで湖に飛び込むなどという無謀な賭けに打って出る事が出来たのだ。
寝息を立てているみたいに寄せては返す水の音が、聞き取れる距離までやって来た。
息を整える為に、利玖はそこで立ち止まる。
生検針のカバーを外して足元に置き、しゃがんだ姿勢のまま、じっと湖面を見つめた。
利玖も千堂も、誰も、何も口をきかない時間が、月がわずかに横へ動いたかもしれない、と思えるくらいのじれったさで流れた。
生検針を握っている手の内側に汗がにじむのを利玖は感じた。そして、ふいに、千堂が銀箭を呼び出す合図のようなものはあるのだろうか、と思いついた。
自分にも銀箭にも過剰な肩入れをしないでほしいと頼んだ手前、格好がつかない気もするが、試しに聞いてみるくらいなら許されるのではないだろうか。
そう思って振り返ろうとした瞬間、湖の中から太い髭のようなものが飛び出し、利玖が叫ぶ間もなく彼女の足首を絡め取った。
木陰にはまだ雪が残っていて、そのぼんやりとした白さのせいで地形が判然としない。何度も足元を確かめながら、藪をかき分けて最短距離で岸に近づいた。
命綱を結ぶ場所を探して湖岸を歩いていると、千堂がふと思い出したように、
「かなり水温が低いと思いますよ」
と声をかけてきた。
気温の低い屋外に長くとどまる事に対しての備えか、彼は空気をたっぷりと蓄えられそうなダウン・ジャケットを着て、黒い手袋も嵌めている。一度は利玖と共に店の外に出たのだが、開口一番に、
「うわ、寒いですね」
と言って防寒具を取りに店に戻っていた。
「下にドライスーツを着てきました」乾いた砂の地面に膝をついて、木々の根元をつぶさに見ながら利玖は言う。「他にも、防水対策を色々と。即座にショック死するような事はないはずです」
そう答えて立ち上がり、ズボンについた土を払ったが、正直な所、自信はなかった。何しろ、必要最低限の装備を、史岐に気づかれないように揃えるだけで精一杯だったのだ。厳冬期の湖に潜った経験なんて、勿論ないし、練習も出来なかった。ぶっつけ本番、一発勝負である。
それでも、ここで蹴りをつけなければならない。史岐がこれ以上、事態に深入りする前にやり遂げなければいけない。ひりつくようなその思いが、今の利玖を突き動かしていた。
もう猶予は残されていない、そう考えているせいで、焦っている自分を自覚もする。しかし、幸いな事に、たった一人で進めている事ではない。その気持ちが、わずかでもバランスを崩したら容易く折れてしまいそうなほど不安に浸食された利玖の心を、毛糸の靴下みたいにささやかに包んで温めていた。
三メートルほど右に移動した所で、一際頑健な針葉樹を見つけた。枝もたわわに葉が茂り、幹の直径は、利玖が両腕を回しても抱えきれないほど太い。
その針葉樹に命綱を結ぶ事に決めて、利玖はホームセンターで買ってきたロープをリュックサックから取り出した。船を港に係留する時の結び方を参考にして根元に結わえ付け、もう片方の端は、腰に巻いた安全帯に通して固定する。
千堂は、ロープを結んだ針葉樹の背後、結び目が見える位置に移動してきて、動かなくなった。
「そこで良いんですか?」ロープの張りを確かめながら、利玖は訊ねる。「駐車帯か、橋からご覧になられた方が良く見えると思いますよ」
「利玖さんが湖に入られるまでは、近くで見届けるつもりです」
つまりは、土壇場で自分が逃げ出さないように見張っているというわけか、と利玖は納得した。
利玖は再びリュックに手を入れて、銀箭の体組織を採取する為の針をケースから取り出す。今日、この時の為に美蕗が用意してくれた特注の道具で、市場には流通していないが、見た目と機能から言えば生検針と呼ぶのが近い。
すぐに使えるように、針を前方にして腕と脇腹の間に挟んだが、カバーは填めたままにしておいた。千堂とはまだ十分に距離が離れていない。万が一、後ろから襲われて奪い取られたら、逆に自分を脅す為の武器として使われてしまう。
生検針を挟んで固定しているのは、左手。右手はロープを握って、ゆっくりと湖に近づいていく。
危険なものは湖の中に潜んでいるとわかっているのに、なぜか、途中で空が見たくなって、利玖は視線を上げた。
夜空は抜群に澄んでいる。元々、潟杜市自体、六百メートル以上の標高がある。雲がなければ、月も星もよく見えるのだ。冬場は特に、空気が冷たく透きとおって、こうして街明かりを避けて高い所にやってくると、星の瞬きがきりきりと音を立てて肌を刺すように銀河の遙か彼方の光が間近に感じられる。
銀箭に喰われるという事は、たぶん、普通の死とはだいぶ違うのだろう。
利玖はまだ、彼にまつわる伝承のほんの一部しか知らないが、そこから想起されるものは、雨、閉塞感、息がつまるような冷たい泥、そういった要素の数々で、こんな風に遍く生きものに開かれた眩しい星空とは無縁の世界であるような気がした。
(これが見納めだとでも考えているのでしょうか)
存外にセンチメンタルじゃないか、と苦笑して、利玖は再び湖に目を戻し、ゴーグルを装着した。
蛉籃石は最低保証だ、と美蕗は言った。
だが、《とほつみの道》に入る手段を持たない自分が、ヌシと直に交渉して報酬を上乗せしてもらうなど、どう考えても無理な話だ。
千堂の絵も、見る者が見れば──あるいは、それが描かれた背景に物語性を見いだし、感銘を受ける観客が大勢いるのなら──値がつくのかもしれないが、真実を知る美蕗に捧げる礼としては、適当ではない。
だから、利玖は、銀箭の体組織を採取する事を思いついた。
銀箭によって被害がもたらされる場所は、おそらく、柏名山だけでは済まない。
潟杜市には、潮蕊湖のように際立った湖はないが、古くから使われてきた湧水地が点在しており、それを利用した水路や堀も現存している。銀箭が自在に水の中を行き来出来るとするならば、これから先も同じ事が、比較的近い地域で繰り返される可能性が高い。
ヒトの理とかけ離れた異形の一部を採取し、分析器にかける事など、大学の研究施設では不可能だが、美蕗のように妖と深い関わりを持つ旧家の主であれば、そういう事が出来る機関に伝手があるかもしれない。
調査を進める中で、部分的にでも銀箭を無力化出来る方法が見つかれば、それは今後、銀箭によって被害がもたらされるかもしれない土地に棲むモノ達と対峙した時に、大きなアドバンテージになる。利玖が持っていても役に立たないものだが、美蕗なら最大限有効に活用し、彼女の絶対的な権力を保持し続ける為の礎として使いこなすだろう。
しかし、最たる理由は、利玖自身が自分の心と記憶を蝕むモノの正体を知りたい、と強く願っている為だった。
昔話や伝説だけで満足してしまうのではなく、兄のような研究者として、銀箭に向き合い、秘されてきたものを解き明かしたい。
超常とされる存在にも、ヒトの理が適用される法則があり、生きものとしての厳粛な秩序がある。その事を証明したかった。
そういった、執着とも呼べる強い思いがあったからこそ、史岐を欺き、身一つで湖に飛び込むなどという無謀な賭けに打って出る事が出来たのだ。
寝息を立てているみたいに寄せては返す水の音が、聞き取れる距離までやって来た。
息を整える為に、利玖はそこで立ち止まる。
生検針のカバーを外して足元に置き、しゃがんだ姿勢のまま、じっと湖面を見つめた。
利玖も千堂も、誰も、何も口をきかない時間が、月がわずかに横へ動いたかもしれない、と思えるくらいのじれったさで流れた。
生検針を握っている手の内側に汗がにじむのを利玖は感じた。そして、ふいに、千堂が銀箭を呼び出す合図のようなものはあるのだろうか、と思いついた。
自分にも銀箭にも過剰な肩入れをしないでほしいと頼んだ手前、格好がつかない気もするが、試しに聞いてみるくらいなら許されるのではないだろうか。
そう思って振り返ろうとした瞬間、湖の中から太い髭のようなものが飛び出し、利玖が叫ぶ間もなく彼女の足首を絡め取った。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

化想操術師の日常
茶野森かのこ
キャラ文芸
たった一つの線で、世界が変わる。
化想操術師という仕事がある。
一般的には知られていないが、化想は誰にでも起きる可能性のある現象で、悲しみや苦しみが心に抱えきれなくなった時、人は無意識の内に化想と呼ばれるものを体の外に生み出してしまう。それは、空間や物や生き物と、その人の心を占めるものである為、様々だ。
化想操術師とは、頭の中に思い描いたものを、その指先を通して、現実に生み出す事が出来る力を持つ人達の事。本来なら無意識でしか出せない化想を、意識的に操る事が出来た。
クズミ化想社は、そんな化想に苦しむ人々に寄り添い、救う仕事をしている。
社長である九頭見志乃歩は、自身も化想を扱いながら、化想患者限定でカウンセラーをしている。
社員は自身を含めて四名。
九頭見野雪という少年は、化想を生み出す能力に長けていた。志乃歩の養子に入っている。
常に無表情であるが、それは感情を失わせるような過去があったからだ。それでも、志乃歩との出会いによって、その心はいつも誰かに寄り添おうとしている、優しい少年だ。
他に、志乃歩の秘書でもある黒兎、口は悪いが料理の腕前はピカイチの姫子、野雪が生み出した巨大な犬の化想のシロ。彼らは、山の中にある洋館で、賑やかに共同生活を送っていた。
その洋館に、新たな住人が加わった。
記憶を失った少女、たま子。化想が扱える彼女は、記憶が戻るまでの間、野雪達と共に過ごす事となった。
だが、記憶を失くしたたま子には、ある目的があった。
たま子はクズミ化想社の一人として、志乃歩や野雪と共に、化想を出してしまった人々の様々な思いに触れていく。
壊れた友情で海に閉じこもる少年、自分への後悔に復讐に走る女性、絵を描く度に化想を出してしまう少年。
化想操術の古い歴史を持つ、阿木之亥という家の人々、重ねた野雪の過去、初めて出来た好きなもの、焦がれた自由、犠牲にしても守らなきゃいけないもの。
野雪とたま子、化想を取り巻く彼らのお話です。

少年、その愛 〜愛する男に斬られるのもまた甘美か?〜
西浦夕緋
キャラ文芸
15歳の少年篤弘はある日、夏朗と名乗る17歳の少年と出会う。
彼は篤弘の初恋の少女が入信を望み続けた宗教団体・李凰国(りおうこく)の男だった。
亡くなった少女の想いを受け継ぎ篤弘は李凰国に入信するが、そこは想像を絶する世界である。
罪人の公開処刑、抗争する新興宗教団体に属する少女の殺害、
そして十数年前に親元から拉致され李凰国に迎え入れられた少年少女達の運命。
「愛する男に斬られるのもまた甘美か?」
李凰国に正義は存在しない。それでも彼は李凰国を愛した。
「おまえの愛の中に散りゆくことができるのを嬉しく思う。」
李凰国に生きる少年少女達の魂、信念、孤独、そして愛を描く。

鬼と私の約束~あやかしバーでバーメイド、はじめました~
さっぱろこ
キャラ文芸
本文の修正が終わりましたので、執筆を再開します。
第6回キャラ文芸大賞 奨励賞頂きました。
* * *
家族に疎まれ、友達もいない甘祢(あまね)は、明日から無職になる。
そんな夜に足を踏み入れた京都の路地で謎の男に襲われかけたところを不思議な少年、伊吹(いぶき)に助けられた。
人間とは少し違う不思議な匂いがすると言われ連れて行かれた先は、あやかしなどが住まう時空の京都租界を統べるアジトとなるバー「OROCHI」。伊吹は京都租界のボスだった。
OROCHIで女性バーテン、つまりバーメイドとして働くことになった甘祢は、人間界でモデルとしても働くバーテンの夜都賀(やつが)に仕事を教わることになる。
そうするうちになぜか徐々に敵対勢力との抗争に巻き込まれていき――
初めての投稿です。色々と手探りですが楽しく書いていこうと思います。

百合系サキュバス達に一目惚れされた
釧路太郎
キャラ文芸
名門零楼館高校はもともと女子高であったのだが、様々な要因で共学になって数年が経つ。
文武両道を掲げる零楼館高校はスポーツ分野だけではなく進学実績も全国レベルで見ても上位に食い込んでいるのであった。
そんな零楼館高校の歴史において今まで誰一人として選ばれたことのない“特別指名推薦”に選ばれたのが工藤珠希なのである。
工藤珠希は身長こそ平均を超えていたが、運動や学力はいたって平均クラスであり性格の良さはあるものの特筆すべき才能も無いように見られていた。
むしろ、彼女の幼馴染である工藤太郎は様々な部活の助っ人として活躍し、中学生でありながら様々な競技のプロ団体からスカウトが来るほどであった。更に、学力面においても優秀であり国内のみならず海外への進学も不可能ではないと言われるほどであった。
“特別指名推薦”の話が学校に来た時は誰もが相手を間違えているのではないかと疑ったほどであったが、零楼館高校関係者は工藤珠希で間違いないという。
工藤珠希と工藤太郎は血縁関係はなく、複雑な家庭環境であった工藤太郎が幼いころに両親を亡くしたこともあって彼は工藤家の養子として迎えられていた。
兄妹同然に育った二人ではあったが、お互いが相手の事を守ろうとする良き関係であり、恋人ではないがそれ以上に信頼しあっている。二人の関係性は苗字が同じという事もあって夫婦と揶揄されることも多々あったのだ。
工藤太郎は県外にあるスポーツ名門校からの推薦も来ていてほぼ内定していたのだが、工藤珠希が零楼館高校に入学することを決めたことを受けて彼も零楼館高校を受験することとなった。
スポーツ分野でも名をはせている零楼館高校に工藤太郎が入学すること自体は何の違和感もないのだが、本来入学する予定であった高校関係者は落胆の声をあげていたのだ。だが、彼の出自も相まって彼の意志を否定する者は誰もいなかったのである。
二人が入学する零楼館高校には外に出ていない秘密があるのだ。
零楼館高校に通う生徒のみならず、教員職員運営者の多くがサキュバスでありそのサキュバスも一般的に知られているサキュバスと違い女性を対象とした変異種なのである。
かつては“秘密の花園”と呼ばれた零楼館女子高等学校もそういった意味を持っていたのだった。
ちなみに、工藤珠希は工藤太郎の事を好きなのだが、それは誰にも言えない秘密なのである。
この作品は「小説家になろう」「カクヨム」「ノベルアッププラス」「ノベルバ」「ノベルピア」にも掲載しております。

イケメン政治家・山下泉はコメントを控えたい
どっぐす
キャラ文芸
「コメントは控えさせていただきます」を言ってみたいがために政治家になった男・山下泉。
記者に追われ満を持してコメントを控えるも、事態は収拾がつかなくなっていく。
◆登場人物
・山下泉 若手イケメン政治家。コメントを控えるために政治家になった。
・佐藤亀男 山下の部活の後輩。無職だし暇でしょ?と山下に言われ第一秘書に任命される。
・女性記者 地元紙の若い記者。先頭に立って山下にコメントを求める。
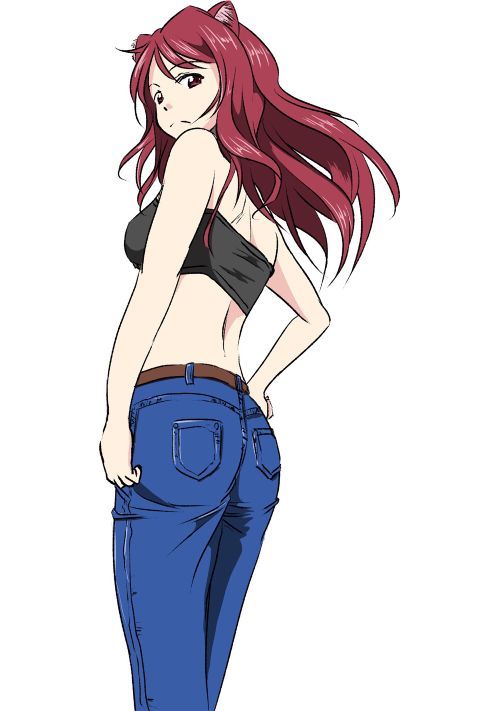
遥か
カリフォルニアデスロールの野良兎
キャラ文芸
鶴木援(ツルギタスケ)は、疲労状態で仕事から帰宅する。何も無い日常にトラウマを抱えた過去、何も起きなかったであろう未来を抱えたまま、何故か誤って監獄街に迷い込む。
生きることを問いかける薄暗いロー・ファンタジー。
表紙 @kafui_k_h

イケメン社長と私が結婚!?初めての『気持ちイイ』を体に教え込まれる!?
すずなり。
恋愛
ある日、彼氏が自分の住んでるアパートを引き払い、勝手に『同棲』を求めてきた。
「お前が働いてるんだから俺は家にいる。」
家事をするわけでもなく、食費をくれるわけでもなく・・・デートもしない。
「私は母親じゃない・・・!」
そう言って家を飛び出した。
夜遅く、何も持たず、靴も履かず・・・一人で泣きながら歩いてるとこを保護してくれた一人の人。
「何があった?送ってく。」
それはいつも仕事場のカフェに来てくれる常連さんだった。
「俺と・・・結婚してほしい。」
「!?」
突然の結婚の申し込み。彼のことは何も知らなかったけど・・・惹かれるのに時間はかからない。
かっこよくて・・優しくて・・・紳士な彼は私を心から愛してくれる。
そんな彼に、私は想いを返したい。
「俺に・・・全てを見せて。」
苦手意識の強かった『営み』。
彼の手によって私の感じ方が変わっていく・・・。
「いあぁぁぁっ・・!!」
「感じやすいんだな・・・。」
※お話は全て想像の世界のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※お話の中に出てくる病気、治療法などは想像のものとしてご覧ください。
※誤字脱字、表現不足は重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけると嬉しいです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・すみません。
それではお楽しみください。すずなり。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















