14 / 36
二章 銀箭に侵された地
静かな朝食
しおりを挟む
翌日は雨。頭痛を起こしやすい体質の二人にとってはあまり好ましくないコンディション。昼前になって、ようやく利玖が先に目覚めた。
起きてから、まず換気の為に窓を開けたが、どの方角にも雲が厚く垂れ込めている。時間経過による天気の好転は望めそうにない。
昨日の夜に封を切ったブランディは、結局、三分の一ほどしか中身を減らせなかった。今は、酸化を防ぐ為にしっかりと蓋を閉めた状態で食器棚の下に保管されている。
いつか飲み切る事が出来ればそれで良い、と思えた。
兎に角、雨。それだけで万事気乗りのしない一日の始まりである。
寝室を出た後、利玖はリビングの真ん中で腰に手を当てて「ようし」と口に出し、自分に活を入れた。
キッチンに行き、朝食の準備に取りかかる。いくつかの根菜を切り、スーパで買ってきた鶏つくねをスプーンで団子状に丸めて鍋で煮込んだ。
食欲がなくても、こういう時には、なるべく野菜がたくさん入った食事を取った方が良い。一口でも二口でも食べる事が出来れば、それだけ早く体力も回復する。
そんな思いで調理をしていた為か、予想以上に具沢山の鍋になったので、利玖はキッチンの壁にもたれて、お玉を持ったまま、うたた寝をしそうになるくらい時間をかけて煮込んだ。
味見をし、火が通った事を確かめて、史岐を起こしに行く。利玖がいなくなった事で、冷えがひどくなったように感じられたのか、頭まですっぽりと布団に包まった状態で、何がどこにあるのかさっぱりわからなかった。
「おはようございます」
枕元にかがみ込んで挨拶をする。鉛色の波打ち際を想起させる重々しい溜息が布団の中から返って来た。
「ごはんが出来ましたよ。熱いうちに食べましょう」
「そんな、熱かったら食べられないよ」
寝言を口にしながら、動力不足のねじ巻き人形みたいな動きで史岐が布団の下から出てくる。ベッドの縁に腰掛け、床に両足を下ろした所で一旦動かなくなったが、利玖が鍋の中身を椀によそって運んでくると、テーブルの前まで移動して来ていた。
「頭が痛い」額に片手を当てて史岐が呟く。
「今日はずっと雨みたいですね」利玖は手早く椀と箸を配膳した。「食べ終わってもまだ具合が悪かったら、薬を飲んで横になりましょう。最後にお腹に入れたのが度数の高いお酒のままでは、体に良くありません」
「そうだね……」
史岐は頷き、のっそりと箸を手に取った。
利玖も一緒に食べ始める。野菜が入っているとはいえ、朝から肉料理はヘヴィだったか、と少しの不安があったが、鶏つくねに入った柚子の風味が良い仕事をして、難なく完食する事が出来た。
「美味しいなあ、これ」史岐は、利玖よりも先に食べ終えて、すっかり頬にも血色が戻っている。「お代わりある?」
「あと二人前くらいなら」
「貰ってこよう」史岐は空の椀を持って立ち上がる。「利玖ちゃんは?」
「いえ、わたしはもう十分です」
「じゃあ、ちょっと待ってて。好きな本読んでていいから」史岐は片手を伸ばして、利玖が使い終えた椀と箸を回収した。「ついでにコーヒーも淹れてくる」
史岐のコーヒーはハンド・ドリップ。硝子のポットにフィルタをセットして作る。豆の種類によってはミルで挽く所から始めるので、出来上がるまでには、いつも、少し待つのが普通だった。
前にここへ来た時に読んだ長編ミステリがあったので、続きを開いてみたが、いまいち頭が回っていない感じがして、四ページも読まないうちにマグカップが運ばれてくる。
「コーヒーを淹れていると、色々、思い出す」利玖の向かいに座りながら史岐が言う。「えっと……、そう、《とほつみの道》だっけ。利玖ちゃんは知らないよね?」
「はい。初耳です」利玖は頷いた。「ヒトと妖が交渉をする場のようなものかな、という印象は受けましたが」
「うん、ほぼ、それで合っている」史岐はコーヒーを一口飲む。「じゃあ、匠さんも、何も教えていないんだ」
利玖は再び頷いた。
佐倉川匠は、五つ年が離れた利玖の兄で、潟杜大学理学部の博士課程に在籍している。植物生態学を主とする研究者であり、同時に、世間一般では公にその存在を認められていないもの、つまり、妖、化生、神々、そういった呼び方をされるモノ達に対して、ある程度の知識を持ち、礼儀を弁えた、佐倉川家の嫡子でもある。
「たぶん、わたしには関わってほしくないと判断したのでしょう。だから存在を伏せているのだ思います」
「そうだね」史岐は顔の前で、両手の指を合わせて目を瞑った。「僕だって、出来れば行ってほしくない」
「呼ばれているのはわたしです」
「そうなんだよなあ」史岐は顔をしかめて天井を見上げた。
「何か、危険があるのですか?」
「いや、《とほつみの道》自体は安全だよ。武器を持ち込む事も、呪術の類で傷をつける事も厳しく禁じられている。超人的な力を持つ土地神や神使、妖達と、ヒトが対等に話し合う為の手段として生み出されたものだからね」
「しかし、それが確約されているのは、あくまで《とほつみの道》の中だけ、と……」利玖は呟く。史岐の言いたい事が、何となくわかってきた。
「そう。中で話し合われた事の、その後の穏便な幕引きまでは、《とほつみの道》は保証しない。話だけでも聞いてやろう、と赴いて、自分の手には余る事態だとわかっても、相手がすぐに諦めてくれるとは限らない」
「それって、気軽に使えるものなのですか?」利玖は質問する。「えっと、つまり、柏名山のヌシが《とほつみの道》という手段を示してきた事が、どのくらいの先方の必死さを表しているのか、という意味ですが」
「うーん」史岐は唸る。
「ああ、真剣なんですね」利玖は顎を引いた。「そうか、困ったな……」
「あと、もう一つ障害がある」史岐が指を一本立てた。
「《とほつみの道》は使える人間が決まっているんだ。僕の家系だと、ちょっと伝手がない。匠さんに訊いてみても良いけれど……」
「やめておきましょう」利玖は即答する。「こじれます」
「同意見」史岐は、本人に聞かれるかもしれない、と危惧でもしているような抑えた声で言うと、溜息をついてベッドの縁に手をかけ、体をひねって灰色に煙る窓を見上げた。
「となると、あとは槻本家か」
起きてから、まず換気の為に窓を開けたが、どの方角にも雲が厚く垂れ込めている。時間経過による天気の好転は望めそうにない。
昨日の夜に封を切ったブランディは、結局、三分の一ほどしか中身を減らせなかった。今は、酸化を防ぐ為にしっかりと蓋を閉めた状態で食器棚の下に保管されている。
いつか飲み切る事が出来ればそれで良い、と思えた。
兎に角、雨。それだけで万事気乗りのしない一日の始まりである。
寝室を出た後、利玖はリビングの真ん中で腰に手を当てて「ようし」と口に出し、自分に活を入れた。
キッチンに行き、朝食の準備に取りかかる。いくつかの根菜を切り、スーパで買ってきた鶏つくねをスプーンで団子状に丸めて鍋で煮込んだ。
食欲がなくても、こういう時には、なるべく野菜がたくさん入った食事を取った方が良い。一口でも二口でも食べる事が出来れば、それだけ早く体力も回復する。
そんな思いで調理をしていた為か、予想以上に具沢山の鍋になったので、利玖はキッチンの壁にもたれて、お玉を持ったまま、うたた寝をしそうになるくらい時間をかけて煮込んだ。
味見をし、火が通った事を確かめて、史岐を起こしに行く。利玖がいなくなった事で、冷えがひどくなったように感じられたのか、頭まですっぽりと布団に包まった状態で、何がどこにあるのかさっぱりわからなかった。
「おはようございます」
枕元にかがみ込んで挨拶をする。鉛色の波打ち際を想起させる重々しい溜息が布団の中から返って来た。
「ごはんが出来ましたよ。熱いうちに食べましょう」
「そんな、熱かったら食べられないよ」
寝言を口にしながら、動力不足のねじ巻き人形みたいな動きで史岐が布団の下から出てくる。ベッドの縁に腰掛け、床に両足を下ろした所で一旦動かなくなったが、利玖が鍋の中身を椀によそって運んでくると、テーブルの前まで移動して来ていた。
「頭が痛い」額に片手を当てて史岐が呟く。
「今日はずっと雨みたいですね」利玖は手早く椀と箸を配膳した。「食べ終わってもまだ具合が悪かったら、薬を飲んで横になりましょう。最後にお腹に入れたのが度数の高いお酒のままでは、体に良くありません」
「そうだね……」
史岐は頷き、のっそりと箸を手に取った。
利玖も一緒に食べ始める。野菜が入っているとはいえ、朝から肉料理はヘヴィだったか、と少しの不安があったが、鶏つくねに入った柚子の風味が良い仕事をして、難なく完食する事が出来た。
「美味しいなあ、これ」史岐は、利玖よりも先に食べ終えて、すっかり頬にも血色が戻っている。「お代わりある?」
「あと二人前くらいなら」
「貰ってこよう」史岐は空の椀を持って立ち上がる。「利玖ちゃんは?」
「いえ、わたしはもう十分です」
「じゃあ、ちょっと待ってて。好きな本読んでていいから」史岐は片手を伸ばして、利玖が使い終えた椀と箸を回収した。「ついでにコーヒーも淹れてくる」
史岐のコーヒーはハンド・ドリップ。硝子のポットにフィルタをセットして作る。豆の種類によってはミルで挽く所から始めるので、出来上がるまでには、いつも、少し待つのが普通だった。
前にここへ来た時に読んだ長編ミステリがあったので、続きを開いてみたが、いまいち頭が回っていない感じがして、四ページも読まないうちにマグカップが運ばれてくる。
「コーヒーを淹れていると、色々、思い出す」利玖の向かいに座りながら史岐が言う。「えっと……、そう、《とほつみの道》だっけ。利玖ちゃんは知らないよね?」
「はい。初耳です」利玖は頷いた。「ヒトと妖が交渉をする場のようなものかな、という印象は受けましたが」
「うん、ほぼ、それで合っている」史岐はコーヒーを一口飲む。「じゃあ、匠さんも、何も教えていないんだ」
利玖は再び頷いた。
佐倉川匠は、五つ年が離れた利玖の兄で、潟杜大学理学部の博士課程に在籍している。植物生態学を主とする研究者であり、同時に、世間一般では公にその存在を認められていないもの、つまり、妖、化生、神々、そういった呼び方をされるモノ達に対して、ある程度の知識を持ち、礼儀を弁えた、佐倉川家の嫡子でもある。
「たぶん、わたしには関わってほしくないと判断したのでしょう。だから存在を伏せているのだ思います」
「そうだね」史岐は顔の前で、両手の指を合わせて目を瞑った。「僕だって、出来れば行ってほしくない」
「呼ばれているのはわたしです」
「そうなんだよなあ」史岐は顔をしかめて天井を見上げた。
「何か、危険があるのですか?」
「いや、《とほつみの道》自体は安全だよ。武器を持ち込む事も、呪術の類で傷をつける事も厳しく禁じられている。超人的な力を持つ土地神や神使、妖達と、ヒトが対等に話し合う為の手段として生み出されたものだからね」
「しかし、それが確約されているのは、あくまで《とほつみの道》の中だけ、と……」利玖は呟く。史岐の言いたい事が、何となくわかってきた。
「そう。中で話し合われた事の、その後の穏便な幕引きまでは、《とほつみの道》は保証しない。話だけでも聞いてやろう、と赴いて、自分の手には余る事態だとわかっても、相手がすぐに諦めてくれるとは限らない」
「それって、気軽に使えるものなのですか?」利玖は質問する。「えっと、つまり、柏名山のヌシが《とほつみの道》という手段を示してきた事が、どのくらいの先方の必死さを表しているのか、という意味ですが」
「うーん」史岐は唸る。
「ああ、真剣なんですね」利玖は顎を引いた。「そうか、困ったな……」
「あと、もう一つ障害がある」史岐が指を一本立てた。
「《とほつみの道》は使える人間が決まっているんだ。僕の家系だと、ちょっと伝手がない。匠さんに訊いてみても良いけれど……」
「やめておきましょう」利玖は即答する。「こじれます」
「同意見」史岐は、本人に聞かれるかもしれない、と危惧でもしているような抑えた声で言うと、溜息をついてベッドの縁に手をかけ、体をひねって灰色に煙る窓を見上げた。
「となると、あとは槻本家か」
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

化想操術師の日常
茶野森かのこ
キャラ文芸
たった一つの線で、世界が変わる。
化想操術師という仕事がある。
一般的には知られていないが、化想は誰にでも起きる可能性のある現象で、悲しみや苦しみが心に抱えきれなくなった時、人は無意識の内に化想と呼ばれるものを体の外に生み出してしまう。それは、空間や物や生き物と、その人の心を占めるものである為、様々だ。
化想操術師とは、頭の中に思い描いたものを、その指先を通して、現実に生み出す事が出来る力を持つ人達の事。本来なら無意識でしか出せない化想を、意識的に操る事が出来た。
クズミ化想社は、そんな化想に苦しむ人々に寄り添い、救う仕事をしている。
社長である九頭見志乃歩は、自身も化想を扱いながら、化想患者限定でカウンセラーをしている。
社員は自身を含めて四名。
九頭見野雪という少年は、化想を生み出す能力に長けていた。志乃歩の養子に入っている。
常に無表情であるが、それは感情を失わせるような過去があったからだ。それでも、志乃歩との出会いによって、その心はいつも誰かに寄り添おうとしている、優しい少年だ。
他に、志乃歩の秘書でもある黒兎、口は悪いが料理の腕前はピカイチの姫子、野雪が生み出した巨大な犬の化想のシロ。彼らは、山の中にある洋館で、賑やかに共同生活を送っていた。
その洋館に、新たな住人が加わった。
記憶を失った少女、たま子。化想が扱える彼女は、記憶が戻るまでの間、野雪達と共に過ごす事となった。
だが、記憶を失くしたたま子には、ある目的があった。
たま子はクズミ化想社の一人として、志乃歩や野雪と共に、化想を出してしまった人々の様々な思いに触れていく。
壊れた友情で海に閉じこもる少年、自分への後悔に復讐に走る女性、絵を描く度に化想を出してしまう少年。
化想操術の古い歴史を持つ、阿木之亥という家の人々、重ねた野雪の過去、初めて出来た好きなもの、焦がれた自由、犠牲にしても守らなきゃいけないもの。
野雪とたま子、化想を取り巻く彼らのお話です。

少年、その愛 〜愛する男に斬られるのもまた甘美か?〜
西浦夕緋
キャラ文芸
15歳の少年篤弘はある日、夏朗と名乗る17歳の少年と出会う。
彼は篤弘の初恋の少女が入信を望み続けた宗教団体・李凰国(りおうこく)の男だった。
亡くなった少女の想いを受け継ぎ篤弘は李凰国に入信するが、そこは想像を絶する世界である。
罪人の公開処刑、抗争する新興宗教団体に属する少女の殺害、
そして十数年前に親元から拉致され李凰国に迎え入れられた少年少女達の運命。
「愛する男に斬られるのもまた甘美か?」
李凰国に正義は存在しない。それでも彼は李凰国を愛した。
「おまえの愛の中に散りゆくことができるのを嬉しく思う。」
李凰国に生きる少年少女達の魂、信念、孤独、そして愛を描く。

イケメン社長と私が結婚!?初めての『気持ちイイ』を体に教え込まれる!?
すずなり。
恋愛
ある日、彼氏が自分の住んでるアパートを引き払い、勝手に『同棲』を求めてきた。
「お前が働いてるんだから俺は家にいる。」
家事をするわけでもなく、食費をくれるわけでもなく・・・デートもしない。
「私は母親じゃない・・・!」
そう言って家を飛び出した。
夜遅く、何も持たず、靴も履かず・・・一人で泣きながら歩いてるとこを保護してくれた一人の人。
「何があった?送ってく。」
それはいつも仕事場のカフェに来てくれる常連さんだった。
「俺と・・・結婚してほしい。」
「!?」
突然の結婚の申し込み。彼のことは何も知らなかったけど・・・惹かれるのに時間はかからない。
かっこよくて・・優しくて・・・紳士な彼は私を心から愛してくれる。
そんな彼に、私は想いを返したい。
「俺に・・・全てを見せて。」
苦手意識の強かった『営み』。
彼の手によって私の感じ方が変わっていく・・・。
「いあぁぁぁっ・・!!」
「感じやすいんだな・・・。」
※お話は全て想像の世界のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※お話の中に出てくる病気、治療法などは想像のものとしてご覧ください。
※誤字脱字、表現不足は重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけると嬉しいです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・すみません。
それではお楽しみください。すずなり。

イケメン政治家・山下泉はコメントを控えたい
どっぐす
キャラ文芸
「コメントは控えさせていただきます」を言ってみたいがために政治家になった男・山下泉。
記者に追われ満を持してコメントを控えるも、事態は収拾がつかなくなっていく。
◆登場人物
・山下泉 若手イケメン政治家。コメントを控えるために政治家になった。
・佐藤亀男 山下の部活の後輩。無職だし暇でしょ?と山下に言われ第一秘書に任命される。
・女性記者 地元紙の若い記者。先頭に立って山下にコメントを求める。

ニンジャマスター・ダイヤ
竹井ゴールド
キャラ文芸
沖縄県の手塚島で育った母子家庭の手塚大也は実母の死によって、東京の遠縁の大鳥家に引き取られる事となった。
大鳥家は大鳥コンツェルンの創業一族で、裏では日本を陰から守る政府機関・大鳥忍軍を率いる忍者一族だった。
沖縄県の手塚島で忍者の修行をして育った大也は東京に出て、忍者の争いに否応なく巻き込まれるのだった。
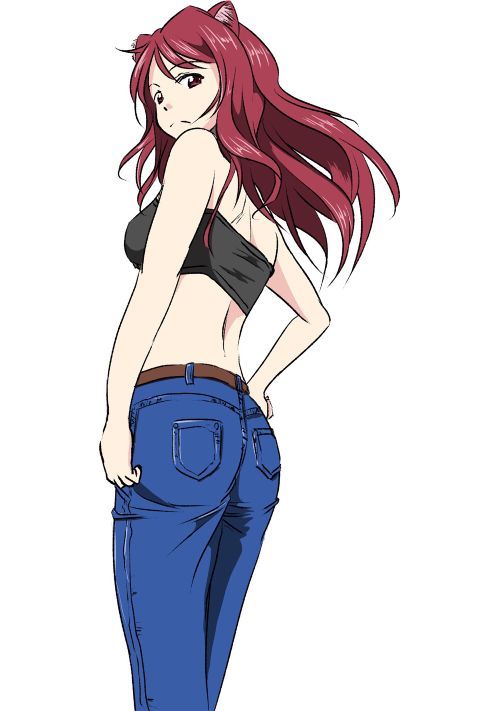
遥か
カリフォルニアデスロールの野良兎
キャラ文芸
鶴木援(ツルギタスケ)は、疲労状態で仕事から帰宅する。何も無い日常にトラウマを抱えた過去、何も起きなかったであろう未来を抱えたまま、何故か誤って監獄街に迷い込む。
生きることを問いかける薄暗いロー・ファンタジー。
表紙 @kafui_k_h

恵麗奈お嬢様のあやかし退治
刻芦葉
キャラ文芸
一般的な生活を送る美憂と、世界でも有名な鳳凰院グループのお嬢様である恵麗奈。
普通なら交わることのなかった二人は、人ならざる者から人を守る『退魔衆』で、命を預け合うパートナーとなった。
二人にある共通点は一つだけ。その身に大きな呪いを受けていること。
黒を煮詰めたような闇に呪われた美憂と、真夜中に浮かぶ太陽に呪われた恵麗奈は、命がけで妖怪との戦いを繰り広げていく。
第6回キャラ文芸大賞に参加してます。よろしくお願いします。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















