12 / 35
姉姫 2
しおりを挟む
「ところで、いつもは供をつけないあんたが、今日は可愛いお供付きなのね」
突然、姉姫からの話題が自分の方へ向けられて、マルはハッとした。
まだ地面に尻もちをついたままだ。慌てて体を起こすと、片膝をつき姿勢を正した。
「申し遅れました、姉姫さま!お初にお目に掛かります、マルと申します」
マルは頭を垂れた。
「マル。こちらが恥ずかしながら、私の姉姫、蒼国の第一皇女で翠蘭姫だ」
愁陽が溜息交じりに紹介するのを聞いて、翠蘭は胸の前で腕を組み盛大な溜息を吐いた。
「弟。私も恥ずかしく思うわよ。なぜ自慢の姉姫だと素直に言えないのです」
「はあ?言えるわけないでしょう」
再び溜息をついて肩を落とす主人の横で、マルはにこやかに、時に凛々しく、自分が実はオオカミで山神の使いである一族だということ、愁陽に助けられて以来、彼に忠誠を誓っていることを、意気揚々と話した。
「なのに~、愁陽さまは、こんな犬みたいな名前をつけてぇぇぇ~」
恨めしく横目で主人を睨むマルに、翠蘭は涼やかに微笑んで言った。
「マル。犬みたいなではなく犬の名よ」
ああ!……さすが、姉弟っ!
確か、数日前に弟も同じことを言っていた。
マルはこの一瞬にして、さらに何か言おうという気力は無くなった。
「ふん、愁陽。彼女の、犬の名ね。」
「李家の、です。コイツが人間界での名をつけてくれっていうから」
横をむく愁陽の頬がわずかに紅潮していた。
その後、いつまでもその場で立ち話もなんだからと、地図ではなかなか見つけられなかった翠蘭の庵へ移動した三人は、翠蘭の部屋で小さな円卓を囲んで座っていた。三人で囲むといっぱいだが、茶を飲むくらいならちょうどいい大きさだ。紫檀で作られており、上品でシンプルな装飾がされている。選んだ者の品の良さが伺われる。
そして、子供の落書きにしか見えないあの難読地図は、もちろん翠蘭が書いてよこしたものだった。
ここは都の城にある屋敷とは違い、華美な装飾など一つもなく古くこじんまりとした屋敷といった感じだが、それもまた風流で趣のある佇まいを見せている。
部屋が数室しかなく決して広くないこの屋敷には、翠蘭のほかには護衛兼世話係の若い男が一人いるだけだったが、掃除はもちろん庭の草木も手入れがよく行き届いており、山奥でも不自由はない様子だ。つまり、その護衛兼世話係の男が、よく出来る男なのだろう。
「失礼します」
艶のある低音ヴォイスで茶器を手に室内に入ってきたのは、護衛兼世話係の若い男だった。名を羅李という。背は愁陽よりも拳一つ分ほど高いだろうか。すらりと細いが筋肉で引き締まっており、なにより一番に目を引くのが髪が金色ということだ。長くさらりとした金の髪を後ろで束ねて、背に垂らしている。蒼国のこのあたりでは、大変珍しい。瞳の色は青く愁陽が深い青なら、彼は空に近い青だ。その顔は細面で色が白く、切れ長の目に筋の通った鼻筋、形のよい薄い唇が緩やかに弧を描いて、涼やかでたいそう美しく女人かと思えるほどにあまりに綺麗な男だ。
思わず、マルもぽかんとして見惚れてしまったほどだ。
「おい、マル。口が開いてるぞ」
愁陽の呆れたような溜息混じりの声がする。
マルは思わず男に見惚れていた自分が恥ずかしく、もじもじと慌ててテーブルに目を落とすと消え入りそうな声で言った。
「あ、すみません。その、あまりにお綺麗で……」
「無駄にな」
なぜか、愁陽がつまらなさそうに言った。
羅李は柔らかく上品な笑みを浮かべた。
「男ですが、褒め言葉として有難く受け取っておきましょう」
そう言った彼の様子は、まるで森の精霊か光の精霊のようだと、マルはやはり見惚れるしかなかった。
羅李は優雅に慣れた手付きで、手にした盆から三人の前に茶器を置いていく。だが、その手先は剣を握る者の手だ、マルはひと目見てわかった。
その姿と立ち居振る舞いは文官のようで穏やかな物腰なのに、先ほどからまったく隙きが無い。
絶対に、敵に回してはいけない性質だ。
自分の野生の感が働くのを感じながら、品のいい湯呑みを両手で持つとズズズっとお茶を飲んだ。
お茶も、美味しい。彼は、もしかして料理も上手いのだろうか。
ただ静かに柔らかく微笑んでる彼は、いったい何者なんだろうか。
マルは一度目をパチクリとすると翠蘭に尋ねた。
「ええっと、翠蘭さまは、ここで仙人になる修行をされているのですか?」
「してないわよ?」
即答した彼女に少し驚く。
「え?だって、さっき愁陽さまが」
「ああ。それは、城を出るときの口実よ」
「は?」
愁陽は眉間に皺を寄せると、姉姫を見た。
「確か城を…家出をされるときの理由に『仙人になるため山に籠る』と書置きをされて出て行かれたと聞いたのですが?」
「山に籠るのは間違ってないし」
「……はあ。すぐに飽きて城に戻られるだろうと思っていたのですが……」
「オーホッホッホ。あらぁ~、残念ね。なかなか快適よ」
翠蘭は満足げに笑って、お茶を飲んでいる。
「それに、たまに仕事で山下りて街にも行くし」
「仕事!?仕事って、姉さん、何の仕事しているんです!?」
愁陽は驚いて飲みかけていた湯呑みを口から離して、つい身を乗り出して尋ねる。一国の姫君として育った姉が、いったい何の仕事をしているというのだろうか。まったく想像がつかない。それは、ものすごく気になるではないか。
姫君がする仕事とは?いや?雇うのはいったいどんな人間なのだろうか。
翠蘭の大きな瞳が、キラリと強く光る。
「あら、執筆よ。知らなかった?マジで仙人の修行のためだけに、山に籠るわけないじゃない」
「っ!!姉さんが、執筆ぅ!?」
思わず声もひっくり返る。まあ、たしかに幼い頃から姉は書物を読むのが好きだった。
それで生計も立てているわよ。と得意げに彼女はフフンと鼻を鳴らした後、ちょっと待ってなさいと、部屋の外へと出て行った。羅李も薪割りをしていた途中なので、と部屋を出ていった。
ポカンと口が開いたまま姉弟のやり取りを見ていたマルが、目をぱちくりさせて愁陽を見た。
「愁陽さまのお姉様って、さすが姉弟といいますか……なかなか変わっていらっしゃいますね。ほんとにモノ書きでいらっしゃること、知らなかったのですか?」
「マル…今、さらっと主人に失礼なこと言っただろう。まあ、聞き逃してやる。小説を書いていることに関しては、俺も家族も知らなかったよ、初耳だ」
そう言って訝しげな顔をしながら翠蘭が消えていったほうを見ていると、すぐに翠蘭が一冊の本を手にして戻ってきた。
「ほら、あんたのあげるわ。特別にタダよ、タダ!おまけに私のサインも入れてあげたからね。まあ、なかなか売れっ子なんだから泣いて喜びなさい」
愁陽はさらりと聞き流し、それを受け取った。
差し出された冊子は、街の市で売られているようなもので綴紐で綴られており、表紙は淡い桃色の和紙で出来ていた。いかにも女性らしい読み物を、愁陽は敬意を払うように両手で丁寧に受け取り表紙を眺めていたが、目を輝かせ微笑むと姉姫を振り返り見て言った。
「ありがとう、姉さん!知らなかったよ、姉さんが小説書いてたなんて。すごいじゃないか!……その、見直したよ!!」
感激の思いに声を弾ませ、何気にページをめくってみる。
……ん?
めくる手がピタリと止まった。書かれていた文字を素早く目で追い、書物の内容を知ったところで顔は凍りつき、愁陽のすべての動きが完全に止まった。
「なっ!!」
驚きの声とともに、ぴしゃん!と音を立てて愁陽は本を閉じた。マルも主がこんなに慌てる様子を日頃あまり見たことがない。
「えっ!?え、ええっと、ね、ね、姉さん!?」
「何、驚いてんのよ」
「だだ、だって、姉さんっ!こ、こ、これって……」
「そんなに驚かなくても。たかがロマンス官能小説じゃない」
「こ、これは、たかが、でしょうか!?だって、これ、男同士ですよね!」
「当たり!」
「俺が貰っても、嬉しくないんですけど!」
「え~~~。そっちは興味ない?残念~。わが弟は普通なのね」
「いや、そっちとか普通とか、そういう問題じゃなく!」
マルが愁陽の手元を覗き込んで尋ねる。
「そっちって何ですか?あっちやこっちもあるのですか、愁陽さま?」
慌てて愁陽が表紙を胸元に隠してしまった。
「ああっ、こら。マルには早すぎる、いやっ、早いとかじゃなくて……」
「これぐらいで狼狽えるなんて、あんたもまだまだ子供ね」
翠蘭がニヤリと真っ赤な口元を上げて勝ち誇ったように嗤うのを、愁陽は片眉をピクリとあげ、何も言わず本を懐にそっとしまった。
「で、今日は何の用で来たの?こんな山奥に、わざわざ茶飲み話をしに来たわけじゃないでしょう」
翠蘭がいきなり本題に入る。
「え、ええ……まあ」
愁陽は言いにくそうに曖昧に答え、視線を落とした。
突然、姉姫からの話題が自分の方へ向けられて、マルはハッとした。
まだ地面に尻もちをついたままだ。慌てて体を起こすと、片膝をつき姿勢を正した。
「申し遅れました、姉姫さま!お初にお目に掛かります、マルと申します」
マルは頭を垂れた。
「マル。こちらが恥ずかしながら、私の姉姫、蒼国の第一皇女で翠蘭姫だ」
愁陽が溜息交じりに紹介するのを聞いて、翠蘭は胸の前で腕を組み盛大な溜息を吐いた。
「弟。私も恥ずかしく思うわよ。なぜ自慢の姉姫だと素直に言えないのです」
「はあ?言えるわけないでしょう」
再び溜息をついて肩を落とす主人の横で、マルはにこやかに、時に凛々しく、自分が実はオオカミで山神の使いである一族だということ、愁陽に助けられて以来、彼に忠誠を誓っていることを、意気揚々と話した。
「なのに~、愁陽さまは、こんな犬みたいな名前をつけてぇぇぇ~」
恨めしく横目で主人を睨むマルに、翠蘭は涼やかに微笑んで言った。
「マル。犬みたいなではなく犬の名よ」
ああ!……さすが、姉弟っ!
確か、数日前に弟も同じことを言っていた。
マルはこの一瞬にして、さらに何か言おうという気力は無くなった。
「ふん、愁陽。彼女の、犬の名ね。」
「李家の、です。コイツが人間界での名をつけてくれっていうから」
横をむく愁陽の頬がわずかに紅潮していた。
その後、いつまでもその場で立ち話もなんだからと、地図ではなかなか見つけられなかった翠蘭の庵へ移動した三人は、翠蘭の部屋で小さな円卓を囲んで座っていた。三人で囲むといっぱいだが、茶を飲むくらいならちょうどいい大きさだ。紫檀で作られており、上品でシンプルな装飾がされている。選んだ者の品の良さが伺われる。
そして、子供の落書きにしか見えないあの難読地図は、もちろん翠蘭が書いてよこしたものだった。
ここは都の城にある屋敷とは違い、華美な装飾など一つもなく古くこじんまりとした屋敷といった感じだが、それもまた風流で趣のある佇まいを見せている。
部屋が数室しかなく決して広くないこの屋敷には、翠蘭のほかには護衛兼世話係の若い男が一人いるだけだったが、掃除はもちろん庭の草木も手入れがよく行き届いており、山奥でも不自由はない様子だ。つまり、その護衛兼世話係の男が、よく出来る男なのだろう。
「失礼します」
艶のある低音ヴォイスで茶器を手に室内に入ってきたのは、護衛兼世話係の若い男だった。名を羅李という。背は愁陽よりも拳一つ分ほど高いだろうか。すらりと細いが筋肉で引き締まっており、なにより一番に目を引くのが髪が金色ということだ。長くさらりとした金の髪を後ろで束ねて、背に垂らしている。蒼国のこのあたりでは、大変珍しい。瞳の色は青く愁陽が深い青なら、彼は空に近い青だ。その顔は細面で色が白く、切れ長の目に筋の通った鼻筋、形のよい薄い唇が緩やかに弧を描いて、涼やかでたいそう美しく女人かと思えるほどにあまりに綺麗な男だ。
思わず、マルもぽかんとして見惚れてしまったほどだ。
「おい、マル。口が開いてるぞ」
愁陽の呆れたような溜息混じりの声がする。
マルは思わず男に見惚れていた自分が恥ずかしく、もじもじと慌ててテーブルに目を落とすと消え入りそうな声で言った。
「あ、すみません。その、あまりにお綺麗で……」
「無駄にな」
なぜか、愁陽がつまらなさそうに言った。
羅李は柔らかく上品な笑みを浮かべた。
「男ですが、褒め言葉として有難く受け取っておきましょう」
そう言った彼の様子は、まるで森の精霊か光の精霊のようだと、マルはやはり見惚れるしかなかった。
羅李は優雅に慣れた手付きで、手にした盆から三人の前に茶器を置いていく。だが、その手先は剣を握る者の手だ、マルはひと目見てわかった。
その姿と立ち居振る舞いは文官のようで穏やかな物腰なのに、先ほどからまったく隙きが無い。
絶対に、敵に回してはいけない性質だ。
自分の野生の感が働くのを感じながら、品のいい湯呑みを両手で持つとズズズっとお茶を飲んだ。
お茶も、美味しい。彼は、もしかして料理も上手いのだろうか。
ただ静かに柔らかく微笑んでる彼は、いったい何者なんだろうか。
マルは一度目をパチクリとすると翠蘭に尋ねた。
「ええっと、翠蘭さまは、ここで仙人になる修行をされているのですか?」
「してないわよ?」
即答した彼女に少し驚く。
「え?だって、さっき愁陽さまが」
「ああ。それは、城を出るときの口実よ」
「は?」
愁陽は眉間に皺を寄せると、姉姫を見た。
「確か城を…家出をされるときの理由に『仙人になるため山に籠る』と書置きをされて出て行かれたと聞いたのですが?」
「山に籠るのは間違ってないし」
「……はあ。すぐに飽きて城に戻られるだろうと思っていたのですが……」
「オーホッホッホ。あらぁ~、残念ね。なかなか快適よ」
翠蘭は満足げに笑って、お茶を飲んでいる。
「それに、たまに仕事で山下りて街にも行くし」
「仕事!?仕事って、姉さん、何の仕事しているんです!?」
愁陽は驚いて飲みかけていた湯呑みを口から離して、つい身を乗り出して尋ねる。一国の姫君として育った姉が、いったい何の仕事をしているというのだろうか。まったく想像がつかない。それは、ものすごく気になるではないか。
姫君がする仕事とは?いや?雇うのはいったいどんな人間なのだろうか。
翠蘭の大きな瞳が、キラリと強く光る。
「あら、執筆よ。知らなかった?マジで仙人の修行のためだけに、山に籠るわけないじゃない」
「っ!!姉さんが、執筆ぅ!?」
思わず声もひっくり返る。まあ、たしかに幼い頃から姉は書物を読むのが好きだった。
それで生計も立てているわよ。と得意げに彼女はフフンと鼻を鳴らした後、ちょっと待ってなさいと、部屋の外へと出て行った。羅李も薪割りをしていた途中なので、と部屋を出ていった。
ポカンと口が開いたまま姉弟のやり取りを見ていたマルが、目をぱちくりさせて愁陽を見た。
「愁陽さまのお姉様って、さすが姉弟といいますか……なかなか変わっていらっしゃいますね。ほんとにモノ書きでいらっしゃること、知らなかったのですか?」
「マル…今、さらっと主人に失礼なこと言っただろう。まあ、聞き逃してやる。小説を書いていることに関しては、俺も家族も知らなかったよ、初耳だ」
そう言って訝しげな顔をしながら翠蘭が消えていったほうを見ていると、すぐに翠蘭が一冊の本を手にして戻ってきた。
「ほら、あんたのあげるわ。特別にタダよ、タダ!おまけに私のサインも入れてあげたからね。まあ、なかなか売れっ子なんだから泣いて喜びなさい」
愁陽はさらりと聞き流し、それを受け取った。
差し出された冊子は、街の市で売られているようなもので綴紐で綴られており、表紙は淡い桃色の和紙で出来ていた。いかにも女性らしい読み物を、愁陽は敬意を払うように両手で丁寧に受け取り表紙を眺めていたが、目を輝かせ微笑むと姉姫を振り返り見て言った。
「ありがとう、姉さん!知らなかったよ、姉さんが小説書いてたなんて。すごいじゃないか!……その、見直したよ!!」
感激の思いに声を弾ませ、何気にページをめくってみる。
……ん?
めくる手がピタリと止まった。書かれていた文字を素早く目で追い、書物の内容を知ったところで顔は凍りつき、愁陽のすべての動きが完全に止まった。
「なっ!!」
驚きの声とともに、ぴしゃん!と音を立てて愁陽は本を閉じた。マルも主がこんなに慌てる様子を日頃あまり見たことがない。
「えっ!?え、ええっと、ね、ね、姉さん!?」
「何、驚いてんのよ」
「だだ、だって、姉さんっ!こ、こ、これって……」
「そんなに驚かなくても。たかがロマンス官能小説じゃない」
「こ、これは、たかが、でしょうか!?だって、これ、男同士ですよね!」
「当たり!」
「俺が貰っても、嬉しくないんですけど!」
「え~~~。そっちは興味ない?残念~。わが弟は普通なのね」
「いや、そっちとか普通とか、そういう問題じゃなく!」
マルが愁陽の手元を覗き込んで尋ねる。
「そっちって何ですか?あっちやこっちもあるのですか、愁陽さま?」
慌てて愁陽が表紙を胸元に隠してしまった。
「ああっ、こら。マルには早すぎる、いやっ、早いとかじゃなくて……」
「これぐらいで狼狽えるなんて、あんたもまだまだ子供ね」
翠蘭がニヤリと真っ赤な口元を上げて勝ち誇ったように嗤うのを、愁陽は片眉をピクリとあげ、何も言わず本を懐にそっとしまった。
「で、今日は何の用で来たの?こんな山奥に、わざわざ茶飲み話をしに来たわけじゃないでしょう」
翠蘭がいきなり本題に入る。
「え、ええ……まあ」
愁陽は言いにくそうに曖昧に答え、視線を落とした。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

少年、その愛 〜愛する男に斬られるのもまた甘美か?〜
西浦夕緋
キャラ文芸
15歳の少年篤弘はある日、夏朗と名乗る17歳の少年と出会う。
彼は篤弘の初恋の少女が入信を望み続けた宗教団体・李凰国(りおうこく)の男だった。
亡くなった少女の想いを受け継ぎ篤弘は李凰国に入信するが、そこは想像を絶する世界である。
罪人の公開処刑、抗争する新興宗教団体に属する少女の殺害、
そして十数年前に親元から拉致され李凰国に迎え入れられた少年少女達の運命。
「愛する男に斬られるのもまた甘美か?」
李凰国に正義は存在しない。それでも彼は李凰国を愛した。
「おまえの愛の中に散りゆくことができるのを嬉しく思う。」
李凰国に生きる少年少女達の魂、信念、孤独、そして愛を描く。

化想操術師の日常
茶野森かのこ
キャラ文芸
たった一つの線で、世界が変わる。
化想操術師という仕事がある。
一般的には知られていないが、化想は誰にでも起きる可能性のある現象で、悲しみや苦しみが心に抱えきれなくなった時、人は無意識の内に化想と呼ばれるものを体の外に生み出してしまう。それは、空間や物や生き物と、その人の心を占めるものである為、様々だ。
化想操術師とは、頭の中に思い描いたものを、その指先を通して、現実に生み出す事が出来る力を持つ人達の事。本来なら無意識でしか出せない化想を、意識的に操る事が出来た。
クズミ化想社は、そんな化想に苦しむ人々に寄り添い、救う仕事をしている。
社長である九頭見志乃歩は、自身も化想を扱いながら、化想患者限定でカウンセラーをしている。
社員は自身を含めて四名。
九頭見野雪という少年は、化想を生み出す能力に長けていた。志乃歩の養子に入っている。
常に無表情であるが、それは感情を失わせるような過去があったからだ。それでも、志乃歩との出会いによって、その心はいつも誰かに寄り添おうとしている、優しい少年だ。
他に、志乃歩の秘書でもある黒兎、口は悪いが料理の腕前はピカイチの姫子、野雪が生み出した巨大な犬の化想のシロ。彼らは、山の中にある洋館で、賑やかに共同生活を送っていた。
その洋館に、新たな住人が加わった。
記憶を失った少女、たま子。化想が扱える彼女は、記憶が戻るまでの間、野雪達と共に過ごす事となった。
だが、記憶を失くしたたま子には、ある目的があった。
たま子はクズミ化想社の一人として、志乃歩や野雪と共に、化想を出してしまった人々の様々な思いに触れていく。
壊れた友情で海に閉じこもる少年、自分への後悔に復讐に走る女性、絵を描く度に化想を出してしまう少年。
化想操術の古い歴史を持つ、阿木之亥という家の人々、重ねた野雪の過去、初めて出来た好きなもの、焦がれた自由、犠牲にしても守らなきゃいけないもの。
野雪とたま子、化想を取り巻く彼らのお話です。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

イケメン政治家・山下泉はコメントを控えたい
どっぐす
キャラ文芸
「コメントは控えさせていただきます」を言ってみたいがために政治家になった男・山下泉。
記者に追われ満を持してコメントを控えるも、事態は収拾がつかなくなっていく。
◆登場人物
・山下泉 若手イケメン政治家。コメントを控えるために政治家になった。
・佐藤亀男 山下の部活の後輩。無職だし暇でしょ?と山下に言われ第一秘書に任命される。
・女性記者 地元紙の若い記者。先頭に立って山下にコメントを求める。
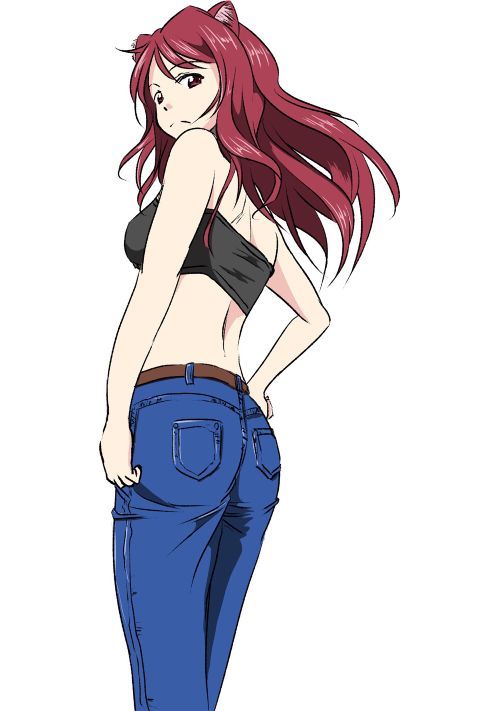
遥か
カリフォルニアデスロールの野良兎
キャラ文芸
鶴木援(ツルギタスケ)は、疲労状態で仕事から帰宅する。何も無い日常にトラウマを抱えた過去、何も起きなかったであろう未来を抱えたまま、何故か誤って監獄街に迷い込む。
生きることを問いかける薄暗いロー・ファンタジー。
表紙 @kafui_k_h

ニンジャマスター・ダイヤ
竹井ゴールド
キャラ文芸
沖縄県の手塚島で育った母子家庭の手塚大也は実母の死によって、東京の遠縁の大鳥家に引き取られる事となった。
大鳥家は大鳥コンツェルンの創業一族で、裏では日本を陰から守る政府機関・大鳥忍軍を率いる忍者一族だった。
沖縄県の手塚島で忍者の修行をして育った大也は東京に出て、忍者の争いに否応なく巻き込まれるのだった。

イケメン社長と私が結婚!?初めての『気持ちイイ』を体に教え込まれる!?
すずなり。
恋愛
ある日、彼氏が自分の住んでるアパートを引き払い、勝手に『同棲』を求めてきた。
「お前が働いてるんだから俺は家にいる。」
家事をするわけでもなく、食費をくれるわけでもなく・・・デートもしない。
「私は母親じゃない・・・!」
そう言って家を飛び出した。
夜遅く、何も持たず、靴も履かず・・・一人で泣きながら歩いてるとこを保護してくれた一人の人。
「何があった?送ってく。」
それはいつも仕事場のカフェに来てくれる常連さんだった。
「俺と・・・結婚してほしい。」
「!?」
突然の結婚の申し込み。彼のことは何も知らなかったけど・・・惹かれるのに時間はかからない。
かっこよくて・・優しくて・・・紳士な彼は私を心から愛してくれる。
そんな彼に、私は想いを返したい。
「俺に・・・全てを見せて。」
苦手意識の強かった『営み』。
彼の手によって私の感じ方が変わっていく・・・。
「いあぁぁぁっ・・!!」
「感じやすいんだな・・・。」
※お話は全て想像の世界のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※お話の中に出てくる病気、治療法などは想像のものとしてご覧ください。
※誤字脱字、表現不足は重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけると嬉しいです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・すみません。
それではお楽しみください。すずなり。

失恋少女と狐の見廻り
紺乃未色(こんのみいろ)
キャラ文芸
失恋中の高校生、彩羽(いろは)の前にあらわれたのは、神の遣いである「千影之狐(ちかげのきつね)」だった。「協力すれば恋の願いを神へ届ける」という約束のもと、彩羽はとある旅館にスタッフとして潜り込み、「魂を盗る、人ならざる者」の調査を手伝うことに。
人生初のアルバイトにあたふたしながらも、奮闘する彩羽。そんな彼女に対して「面白い」と興味を抱く千影之狐。
一人と一匹は無事に奇妙な事件を解決できるのか?
不可思議でどこか妖しい「失恋からはじまる和風ファンタジー」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















