お気に入りに追加
218
あなたにおすすめの小説

運極さんが通る
スウ
ファンタジー
『VRMMO』の技術が詰まったゲームの1次作、『Potential of the story』が発売されて約1年と2ヶ月がたった。
そして、今日、新作『Live Online』が発売された。
主人公は『Live Online』の世界で掲示板を騒がせながら、運に極振りをして、仲間と共に未知なる領域を探索していく。……そして彼女は後に、「災運」と呼ばれる。

Free Emblem On-line
ユキさん
ファンタジー
今の世の中、ゲームと言えばVRゲームが主流であり人々は数多のVRゲームに魅了されていく。そんなVRゲームの中で待望されていたタイトルがβテストを経て、ついに発売されたのだった。
VRMMO『Free Emblem Online』
通称『F.E.O』
自由過ぎることが売りのこのゲームを、「あんちゃんも気に入ると思うよ~。だから…ね? 一緒にやろうぜぃ♪」とのことで、βテスターの妹より一式を渡される。妹より渡された『F.E.O』、仕事もあるが…、「折角だし、やってみるとしようか。」圧倒的な世界に驚きながらも、MMO初心者である男が自由気ままに『F.E.O』を楽しむ。
ソロでユニークモンスターを討伐、武器防具やアイテムも他の追随を許さない、それでいてPCよりもNPCと仲が良い変わり者。
そんな強面悪党顔の初心者が冒険や生産においてその名を轟かし、本人の知らぬ間に世界を引っ張る存在となっていく。
なろうにも投稿してあります。だいぶ前の未完ですがね。

VRMMO~鍛治師で最強になってみた!?
ナイム
ファンタジー
ある日、友人から進められ最新フルダイブゲーム『アンリミテッド・ワールド』を始めた進藤 渚
そんな彼が友人たちや、ゲーム内で知り合った人たちと協力しながら自由気ままに過ごしていると…気がつくと最強と呼ばれるうちの一人になっていた!?
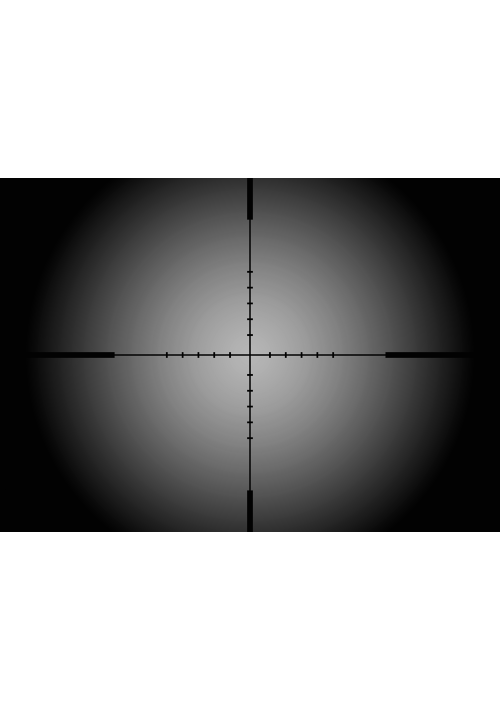
色々とごちゃ混ぜになったVRMMO
たこやき
ファンタジー
物語作り&投稿初心者(中盤から」に。が付いています。ご容赦を)
グダグダ・信念無し・作品自体がノリ
たこやきって美味しい。画像に意味はありません。プロットは燃やした。
VRゲーム「セカンド・ワールド」
それは大手ゲーム会社イツバの新作であった。
池田疾風は、「セカンド・ワールド」の発表を楽しみにしていた。
だが彼はまだ知らなかった。
イツバが後に、ゲーム界の奇才と呼ばれ、畏怖されることを。
更新頻度が腐っておりますのでご注意を。
何故か一気に公開されます。(主に水、土、日曜日)
非常に拙い文面ですがご容赦を。
プロット?知らんな。キャラ名を間違える?日常茶飯事である。最早投稿作品を間違えそう。
二番煎じです。私に発想力は皆無です。

最前線攻略に疲れた俺は、新作VRMMOを最弱職業で楽しむことにした
水の入ったペットボトル
SF
これまであらゆるMMOを最前線攻略してきたが、もう俺(大川優磨)はこの遊び方に満足してしまった。いや、もう楽しいとすら思えない。
ゲームは楽しむためにするものだと思い出した俺は、新作VRMMOを最弱職業『テイマー』で始めることに。
βテストでは最弱職業だと言われていたテイマーだが、主人公の活躍によって評価が上がっていく?
そんな周りの評価など関係なしに、今日も主人公は楽しむことに全力を出す。
この作品は「カクヨム」様、「小説家になろう」様にも掲載しています。

Anotherfantasia~もうひとつの幻想郷
くみたろう
ファンタジー
彼女の名前は東堂翠。
怒りに震えながら、両手に持つ固めの箱を歪ませるくらいに力を入れて歩く翠。
最高の一日が、たった数分で最悪な1日へと変わった。
その要因は手に持つ箱。
ゲーム、Anotherfantasia
体感出来る幻想郷とキャッチフレーズが付いた完全ダイブ型VRゲームが、彼女の幸せを壊したのだ。
「このゲームがなんぼのもんよ!!!」
怒り狂う翠は帰宅後ゲームを睨みつけて、興味なんか無いゲームを険しい表情で起動した。
「どれくらい面白いのか、試してやろうじゃない。」
ゲームを一切やらない翠が、初めての体感出来る幻想郷へと体を委ねた。
それは、翠の想像を上回った。
「これが………ゲーム………?」
現実離れした世界観。
でも、確かに感じるのは現実だった。
初めて続きの翠に、少しづつ増える仲間たち。
楽しさを見出した翠は、気付いたらトップランカーのクランで外せない大事な仲間になっていた。
【Anotherfantasia……今となっては、楽しくないなんて絶対言えないや】
翠は、柔らかく笑うのだった。

最悪のゴミスキルと断言されたジョブとスキルばかり山盛りから始めるVRMMO
無謀突撃娘
ファンタジー
始めまして、僕は西園寺薫。
名前は凄く女の子なんだけど男です。とある私立の学校に通っています。容姿や行動がすごく女の子でよく間違えられるんだけどさほど気にしてないかな。
小説を読むことと手芸が得意です。あとは料理を少々出来るぐらい。
特徴?う~ん、生まれた日にちがものすごい運気の良い星ってぐらいかな。
姉二人が最新のVRMMOとか言うのを話題に出してきたんだ。
ゲームなんてしたこともなく説明書もチンプンカンプンで何も分からなかったけど「何でも出来る、何でもなれる」という宣伝文句とゲーム実況を見て始めることにしたんだ。
スキルなどはβ版の時に最悪スキルゴミスキルと認知されているスキルばかりです、今のゲームでは普通ぐらいの認知はされていると思いますがこの小説の中ではゴミにしかならない無用スキルとして認知されいます。
そのあたりのことを理解して読んでいただけると幸いです。

VRおじいちゃん ~ひろしの大冒険~
オイシイオコメ
SF
75歳のおじいさん「ひろし」は思いもよらず、人気VRゲームの世界に足を踏み入れた。おすすめされた種族や職業はまったく理解できず「無職」を選び、さらに操作ミスで物理攻撃力に全振りしたおじいさんはVR世界で出会った仲間たちと大冒険を繰り広げる。
この作品は、小説家になろう様とカクヨム様に2021年執筆した「VRおじいちゃん」と「VRおばあちゃん」を統合した作品です。
前作品は同僚や友人の意見も取り入れて書いておりましたが、今回は自分の意向のみで修正させていただいたリニューアル作品です。
(小説中のダッシュ表記につきまして)
作品公開時、一部のスマートフォンで文字化けするとのご報告を頂き、ダッシュ2本のかわりに「ー」を使用しております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















