あなたにおすすめの小説

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

悪役令嬢の兄でしたが、追放後は参謀として騎士たちに囲まれています。- 第1巻 - 婚約破棄と一族追放
大の字だい
BL
王国にその名を轟かせる名門・ブラックウッド公爵家。
嫡男レイモンドは比類なき才知と冷徹な眼差しを持つ若き天才であった。
だが妹リディアナが王太子の許嫁でありながら、王太子が心奪われたのは庶民の少女リーシャ・グレイヴェル。
嫉妬と憎悪が社交界を揺るがす愚行へと繋がり、王宮での婚約破棄、王の御前での一族追放へと至る。
混乱の只中、妹を庇おうとするレイモンドの前に立ちはだかったのは、王国騎士団副団長にしてリーシャの異母兄、ヴィンセント・グレイヴェル。
琥珀の瞳に嗜虐を宿した彼は言う――
「この才を捨てるは惜しい。ゆえに、我が手で飼い馴らそう」
知略と支配欲を秘めた騎士と、没落した宰相家の天才青年。
耽美と背徳の物語が、冷たい鎖と熱い口づけの中で幕を開ける。

夫が妹を第二夫人に迎えたので、英雄の妻の座を捨てます。
Nao*
恋愛
夫が英雄の称号を授かり、私は英雄の妻となった。
そして英雄は、何でも一つ願いを叶える事が出来る。
そんな夫が願ったのは、私の妹を第二夫人に迎えると言う信じられないものだった。
これまで夫の為に祈りを捧げて来たと言うのに、私は彼に手酷く裏切られたのだ──。
(1万字以上と少し長いので、短編集とは別にしてあります。)

やっと退場できるはずだったβの悪役令息。ワンナイトしたらΩになりました。
毒島醜女
BL
目が覚めると、妻であるヒロインを虐げた挙句に彼女の運命の番である皇帝に断罪される最低最低なモラハラDV常習犯の悪役夫、イライ・ロザリンドに転生した。
そんな最期は絶対に避けたいイライはヒーローとヒロインの仲を結ばせつつ、ヒロインと円満に別れる為に策を練った。
彼の努力は実り、主人公たちは結ばれ、イライはお役御免となった。
「これでやっと安心して退場できる」
これまでの自分の努力を労うように酒場で飲んでいたイライは、いい薫りを漂わせる男と意気投合し、彼と一夜を共にしてしまう。
目が覚めると罪悪感に襲われ、すぐさま宿を去っていく。
「これじゃあ原作のイライと変わらないじゃん!」
その後体調不良を訴え、医師に診てもらうととんでもない事を言われたのだった。
「あなた……Ωになっていますよ」
「へ?」
そしてワンナイトをした男がまさかの国の英雄で、まさかまさか求愛し公開プロポーズまでして来て――
オメガバースの世界で運命に導かれる、強引な俺様α×頑張り屋な元悪役令息の元βのΩのラブストーリー。

【本編完結】処刑台の元婚約者は無実でした~聖女に騙された元王太子が幸せになるまで~
TOY
BL
【本編完結・後日譚更新中】
公開処刑のその日、王太子メルドは元婚約者で“稀代の悪女”とされたレイチェルの最期を見届けようとしていた。
しかし「最後のお別れの挨拶」で現婚約者候補の“聖女”アリアの裏の顔を、偶然にも暴いてしまい……!?
王位継承権、婚約、信頼、すべてを失った王子のもとに残ったのは、幼馴染であり護衛騎士のケイ。
これは、聖女に騙され全てを失った王子と、その護衛騎士のちょっとズレた恋の物語。
※別で投稿している作品、
『物語によくいる「ざまぁされる王子」に転生したら』の全年齢版です。
設定と後半の展開が少し変わっています。
※後日譚を追加しました。
後日譚① レイチェル視点→メルド視点
後日譚② 王弟→王→ケイ視点
後日譚③ メルド視点

【完結】伴侶がいるので、溺愛ご遠慮いたします
* ゆるゆ
BL
3歳のノィユが、カビの生えてないご飯を求めて結ばれることになったのは、北の最果ての領主のおじいちゃん……え、おじいちゃん……!?
しあわせの絶頂にいるのを知らない王子たちが、びっくりして憐れんで溺愛してくれそうなのですが、結構です!
めちゃくちゃかっこよくて可愛い伴侶がいますので!
ノィユとヴィルの動画を作ってみました!(笑)
インスタ @yuruyu0
Youtube @BL小説動画 です!
プロフのwebサイトから飛べるので、もしよかったらお話と一緒に楽しんでくださったら、とてもうれしいです!
ヴィル×ノィユのお話です。
本編完結しました!
『もふもふ獣人転生』に遊びにゆく舞踏会編、完結しました!
時々おまけのお話を更新するかもです。
名前が * ゆるゆ になりましたー!
中身はいっしょなので(笑)これからもどうぞよろしくお願い致しますー!
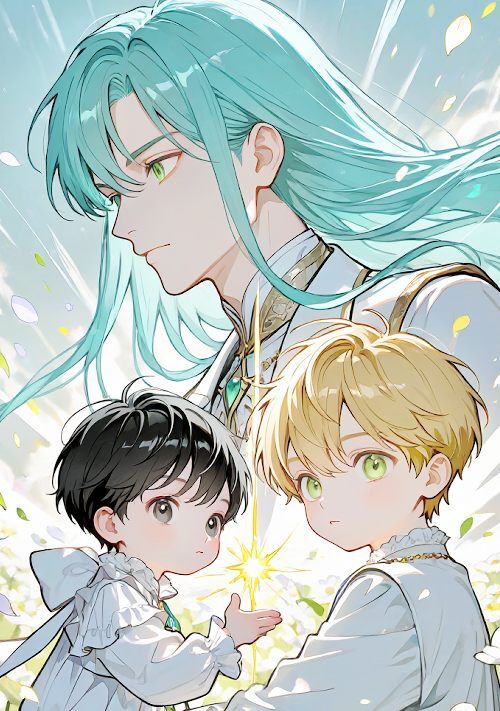
悪役令息を改めたら皆の様子がおかしいです?
* ゆるゆ
BL
王太子から伴侶(予定)契約を破棄された瞬間、前世の記憶がよみがえって、悪役令息だと気づいたよ! しかし気づいたのが終了した後な件について。
悪役令息で断罪なんて絶対だめだ! 泣いちゃう!
せっかく前世を思い出したんだから、これからは心を入れ替えて、真面目にがんばっていこう! と思ったんだけど……あれ? 皆やさしい? 主人公はあっちだよー?
ユィリと皆の動画をつくりました!
インスタ @yuruyu0 絵も動画もあがります。ほぼ毎日更新!
Youtube @BL小説動画 アカウントがなくても、どなたでもご覧になれます。動画を作ったときに更新!
プロフのWebサイトから、両方に飛べるので、もしよかったら!
名前が * ゆるゆ になりましたー!
中身はいっしょなので(笑)これからもどうぞよろしくお願い致しますー!
ご感想欄 、うれしくてすぐ承認を押してしまい(笑)ネタバレ 配慮できないので、ご覧になる時は、お気をつけください!

性悪なお嬢様に命令されて泣く泣く恋敵を殺りにいったらヤられました
まりも13
BL
フワフワとした酩酊状態が薄れ、僕は気がつくとパンパンパン、ズチュッと卑猥な音をたてて激しく誰かと交わっていた。
性悪なお嬢様の命令で恋敵を泣く泣く殺りに行ったら逆にヤラれちゃった、ちょっとアホな子の話です。
(ムーンライトノベルにも掲載しています)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。




















