1 / 1
左巻きのカタツムリ
しおりを挟む
読者諸君は、カタツムリの殻の巻く向きに注意を払ったことがあろうか。実は、大半のカタツムリの殻が右巻きにできているのだが、あるカタツムリの群れの中に、ただの一匹だけ、左巻きのカタツムリがいた。親も兄弟も親せきも、みな右巻きだというのに、このカタツムリだけが左巻きなのである。
殻が左巻きでも、実用面で特に不便はない。食事も移動も睡眠もつつがなく行える。
しかし、精神面では全くの別問題であった。左巻きのカタツムリは、自分の殻だけが左巻きであることに強いコンプレックスを抱いていたのだ。絶えず他のカタツムリの殻に目をやっては、自分と同じ左巻きの者はいないのか、そればかり気にしていたほどである。
ある日、左巻きのカタツムリは、長老のカタツムリに、「自分と同じ左巻きの者が、過去にいませんでしたか」と尋ねてみたことがあった。自分と同じ左巻きの者がいた話を聞けば、せめてものなぐさめになるだろうと考えたからである。しかし長老のカタツムリは、「今、私の目の前にいる者以外で、そんな者は見たことがない」と答えたため、かえって左巻きのカタツムリの気は、め入るばかりであった。
左巻きのカタツムリは大いに悩んだ。
(左巻きの自分でも、何とか右巻き社会に溶けこみたい。左巻きを右巻きに変えることはできないけれども、左巻きの殻を右巻きの殻らしく見せる方法はきっとあるはずだ)
そのように考えながら左巻きのカタツムリが日々を過ごしていると、果たして一つの事実に気づいた。
それは、右巻きの殻は右に傾くように、左巻きの殻は左に傾くようにできているということだ。
(左巻きの殻でも、右側に傾くように工夫すれば、右巻き社会に溶けこめるのではないか)
この考えを実行するには、殻の中におさまった体を、本来とは逆の向きにねじる必要があって、大変な苦労を要した。しかし、いかにも苦労しているのが周りの者に知れるというのでは、かえって集団の中で浮いてしまう。だから左巻きのカタツムリは、この苦労を涼しい顔でやり続ける必要があった。本当はつらいことを涼しい顔でやり続けるというのは、ただつらいことをつらそうに続けるよりも、忍たい力を要するものであった。
これだけの苦労にたえているのだから、自分は右巻き社会に十分溶けこめたはずだと左巻きのカタツムリは思っていた。ところが、二、三日たつ内に、左巻きのカタツムリは意外な事実を発見した。他のカタツムリ達が、バカにするような、さげすむような目つきで自分の殻を眺めてくるのだ。
これまでもすれ違いざま、自分の殻にちらと視線が注がれることはあって、その時は単に物珍しさから眺められているだけであった。けれども今度のは、明らかに以前のそれとは違うのだ。笑いを必死にこらえる者、クスクス笑い出す者、連れの者と何かひそひそ話を始める者など、その視線にはどうも悪意がこめられている気がしてならない。
(前はあのように笑ったりしなかったのに)
そのわけは、実は単純だった。左巻きの殻を無理に右に傾けると、見た目のおさまりが悪くなり、不格好に見えてしまうのだ。
(これだけの苦労にたえてしていることが、全くの裏目に出てしまうなんて、そんなバカなことがあるか、こんちくしょうめ)
左巻きのカタツムリの意気は、完全にくじかれてしまった。
折しも、カタツムリの群れに、一つの危機がせまっていた。腹をすかせた一匹の蛇が群れをねらっていたのだ。茂みの陰で休んでいたカタツムリ達は、蛇に気づくといっせいに逃げ出した。が、一匹だけ逃げ出さない者がいた。例の左巻きのカタツムリである。先の一件で絶望に打ちひしがれていた左巻きのカタツムリは、もういい機会だから蛇に食われて死んでしまおうと思って、その場にとどまっていたのだ。
とはいえ、実際に蛇が目の前までにょろにょろと近づいてくると、やはり食われて死ぬのが恐ろしくなった左巻きのカタツムリは、殻の中に急いで逃げこんだ。やにわに、蛇は口を大きく開けて、その殻にかぶりついた。
ここで読者諸君に一つ補足しておきたい。カタツムリに右巻きと左巻きがあるように、実は蛇にも、右利きと左利きというのがある。このあたりに生息するカタツムリは、この話の主人公を除いて、みな右巻きだったから、今カタツムリを食おうとしているこの蛇も、右巻きのカタツムリ用に進化してきた、右利きの蛇であった。右利きの蛇が右巻きのカタツムリを食するのは、たやすいことだ。きばのない上あごで殻を固定し、きばのある下あごを殻の中に突っこみ、左右で長さの違うきばを交互に抜き差しすることで、カタツムリの体を殻から引き抜いて、その身にありつくのだ。
しかし、右利きの蛇が左巻きのカタツムリを相手とする今回のような場合は、勝手が違った。殻を上あごでうまく固定することができないし、何とか固定できたと思っても、下あごを殻の中に突っこもうとしたとたん、上あごのロックが外れてしまう。
数十分間の格闘の末、とうとう根気がつきてしまった右利きの蛇は、さも悔しそうにシューと一回やって去っていった。
思いがけず危機をまぬがれた左巻きのカタツムリ。群れと再会すると、群れの者達は、左巻きのカタツムリを大いにほめたたえた。というのも蛇がおそってきた時、左巻きのカタツムリが命がけでおとりとなって、群れを救ってくれたと、他の者達は信じていたからだ。
これを聞いた左巻きのカタツムリは、いくばくか後ろめたさを感じた。が、元々の動機が何であれ、結果として自分の行為が群れを救ったのは事実であるし、何よりせっかく得た地位をみすみす手放すことはないと思い、なりゆきにまかせることにした。やがて群れの中で英雄と呼ばれるようになった左巻きのカタツムリは、その地位と名声に酔いしれた。
それから数週間がたち、再び群れに危機が訪れた。またしても蛇が現れたのだ。
(再び群れを救って、俺は伝説になるのだ)
そう考えた左巻きのカタツムリは、今回も自分だけがその場に残り、蛇があきらめて去るのを殻の中でじっと待つことにした。
生い茂る草木の間をぬうようにしてはってきた蛇は、左巻きのカタツムリの殻にかぶりついた。ここまでは前回と同じだ。が、そこから想定外のことが起きた。
今度の蛇は、左巻きのカタツムリを殻ごと丸のみにしてしまったのだった。
さて、このカタツムリのとった行動を、読者諸君は、おろかだと言って笑えるだろうか…
殻が左巻きでも、実用面で特に不便はない。食事も移動も睡眠もつつがなく行える。
しかし、精神面では全くの別問題であった。左巻きのカタツムリは、自分の殻だけが左巻きであることに強いコンプレックスを抱いていたのだ。絶えず他のカタツムリの殻に目をやっては、自分と同じ左巻きの者はいないのか、そればかり気にしていたほどである。
ある日、左巻きのカタツムリは、長老のカタツムリに、「自分と同じ左巻きの者が、過去にいませんでしたか」と尋ねてみたことがあった。自分と同じ左巻きの者がいた話を聞けば、せめてものなぐさめになるだろうと考えたからである。しかし長老のカタツムリは、「今、私の目の前にいる者以外で、そんな者は見たことがない」と答えたため、かえって左巻きのカタツムリの気は、め入るばかりであった。
左巻きのカタツムリは大いに悩んだ。
(左巻きの自分でも、何とか右巻き社会に溶けこみたい。左巻きを右巻きに変えることはできないけれども、左巻きの殻を右巻きの殻らしく見せる方法はきっとあるはずだ)
そのように考えながら左巻きのカタツムリが日々を過ごしていると、果たして一つの事実に気づいた。
それは、右巻きの殻は右に傾くように、左巻きの殻は左に傾くようにできているということだ。
(左巻きの殻でも、右側に傾くように工夫すれば、右巻き社会に溶けこめるのではないか)
この考えを実行するには、殻の中におさまった体を、本来とは逆の向きにねじる必要があって、大変な苦労を要した。しかし、いかにも苦労しているのが周りの者に知れるというのでは、かえって集団の中で浮いてしまう。だから左巻きのカタツムリは、この苦労を涼しい顔でやり続ける必要があった。本当はつらいことを涼しい顔でやり続けるというのは、ただつらいことをつらそうに続けるよりも、忍たい力を要するものであった。
これだけの苦労にたえているのだから、自分は右巻き社会に十分溶けこめたはずだと左巻きのカタツムリは思っていた。ところが、二、三日たつ内に、左巻きのカタツムリは意外な事実を発見した。他のカタツムリ達が、バカにするような、さげすむような目つきで自分の殻を眺めてくるのだ。
これまでもすれ違いざま、自分の殻にちらと視線が注がれることはあって、その時は単に物珍しさから眺められているだけであった。けれども今度のは、明らかに以前のそれとは違うのだ。笑いを必死にこらえる者、クスクス笑い出す者、連れの者と何かひそひそ話を始める者など、その視線にはどうも悪意がこめられている気がしてならない。
(前はあのように笑ったりしなかったのに)
そのわけは、実は単純だった。左巻きの殻を無理に右に傾けると、見た目のおさまりが悪くなり、不格好に見えてしまうのだ。
(これだけの苦労にたえてしていることが、全くの裏目に出てしまうなんて、そんなバカなことがあるか、こんちくしょうめ)
左巻きのカタツムリの意気は、完全にくじかれてしまった。
折しも、カタツムリの群れに、一つの危機がせまっていた。腹をすかせた一匹の蛇が群れをねらっていたのだ。茂みの陰で休んでいたカタツムリ達は、蛇に気づくといっせいに逃げ出した。が、一匹だけ逃げ出さない者がいた。例の左巻きのカタツムリである。先の一件で絶望に打ちひしがれていた左巻きのカタツムリは、もういい機会だから蛇に食われて死んでしまおうと思って、その場にとどまっていたのだ。
とはいえ、実際に蛇が目の前までにょろにょろと近づいてくると、やはり食われて死ぬのが恐ろしくなった左巻きのカタツムリは、殻の中に急いで逃げこんだ。やにわに、蛇は口を大きく開けて、その殻にかぶりついた。
ここで読者諸君に一つ補足しておきたい。カタツムリに右巻きと左巻きがあるように、実は蛇にも、右利きと左利きというのがある。このあたりに生息するカタツムリは、この話の主人公を除いて、みな右巻きだったから、今カタツムリを食おうとしているこの蛇も、右巻きのカタツムリ用に進化してきた、右利きの蛇であった。右利きの蛇が右巻きのカタツムリを食するのは、たやすいことだ。きばのない上あごで殻を固定し、きばのある下あごを殻の中に突っこみ、左右で長さの違うきばを交互に抜き差しすることで、カタツムリの体を殻から引き抜いて、その身にありつくのだ。
しかし、右利きの蛇が左巻きのカタツムリを相手とする今回のような場合は、勝手が違った。殻を上あごでうまく固定することができないし、何とか固定できたと思っても、下あごを殻の中に突っこもうとしたとたん、上あごのロックが外れてしまう。
数十分間の格闘の末、とうとう根気がつきてしまった右利きの蛇は、さも悔しそうにシューと一回やって去っていった。
思いがけず危機をまぬがれた左巻きのカタツムリ。群れと再会すると、群れの者達は、左巻きのカタツムリを大いにほめたたえた。というのも蛇がおそってきた時、左巻きのカタツムリが命がけでおとりとなって、群れを救ってくれたと、他の者達は信じていたからだ。
これを聞いた左巻きのカタツムリは、いくばくか後ろめたさを感じた。が、元々の動機が何であれ、結果として自分の行為が群れを救ったのは事実であるし、何よりせっかく得た地位をみすみす手放すことはないと思い、なりゆきにまかせることにした。やがて群れの中で英雄と呼ばれるようになった左巻きのカタツムリは、その地位と名声に酔いしれた。
それから数週間がたち、再び群れに危機が訪れた。またしても蛇が現れたのだ。
(再び群れを救って、俺は伝説になるのだ)
そう考えた左巻きのカタツムリは、今回も自分だけがその場に残り、蛇があきらめて去るのを殻の中でじっと待つことにした。
生い茂る草木の間をぬうようにしてはってきた蛇は、左巻きのカタツムリの殻にかぶりついた。ここまでは前回と同じだ。が、そこから想定外のことが起きた。
今度の蛇は、左巻きのカタツムリを殻ごと丸のみにしてしまったのだった。
さて、このカタツムリのとった行動を、読者諸君は、おろかだと言って笑えるだろうか…
0
お気に入りに追加
2
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

小鬼の兄弟とまんじゅう
さぶれ@5作コミカライズ配信・原作家
児童書・童話
ほのぼのとしたお話。
今回は絵本風に仕上げました。
是非、楽しんで下さい。
何時も応援ありがとうございます!
表紙デザイン・玉置朱音様
幻想的な音楽・写真の創作活動をされています。
Youtubeの曲は必聴! 曲が本当に素晴らしいです!
ツイッター
https://twitter.com/akane__tamaki
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCK2UIMESQj3GMKhOYls_VEw

こちら御神楽学園心霊部!
緒方あきら
児童書・童話
取りつかれ体質の主人公、月城灯里が霊に憑かれた事を切っ掛けに心霊部に入部する。そこに数々の心霊体験が舞い込んでくる。事件を解決するごとに部員との絆は深まっていく。けれど、彼らにやってくる心霊事件は身の毛がよだつ恐ろしいものばかりで――。
灯里は取りつかれ体質で、事あるごとに幽霊に取りつかれる。
それがきっかけで学校の心霊部に入部する事になったが、いくつもの事件がやってきて――。
。
部屋に異音がなり、主人公を怯えさせる【トッテさん】。
前世から続く呪いにより死に導かれる生徒を救うが、彼にあげたお札は一週間でボロボロになってしまう【前世の名前】。
通ってはいけない道を通り、自分の影を失い、荒れた祠を修復し祈りを捧げて解決を試みる【竹林の道】。
どこまでもついて来る影が、家まで辿り着いたと安心した主人公の耳元に突然囁きかけてさっていく【楽しかった?】。
封印されていたものを解き放つと、それは江戸時代に封じられた幽霊。彼は門吉と名乗り主人公たちは土地神にするべく扱う【首無し地蔵】。
決して話してはいけない怪談を話してしまい、クラスメイトの背中に危険な影が現れ、咄嗟にこの話は嘘だったと弁明し霊を払う【嘘つき先生】。
事故死してさ迷う亡霊と出くわしてしまう。気付かぬふりをしてやり過ごすがすれ違い様に「見えてるくせに」と囁かれ襲われる【交差点】。
ひたすら振返らせようとする霊、駅まで着いたがトンネルを走る窓が鏡のようになり憑りついた霊の禍々しい姿を見る事になる【うしろ】。
都市伝説の噂を元に、エレベーターで消えてしまった生徒。記憶からさえもその存在を消す神隠し。心霊部は総出で生徒の救出を行った【異世界エレベーター】。
延々と名前を問う不気味な声【名前】。
10の怪異譚からなる心霊ホラー。心霊部の活躍は続いていく。
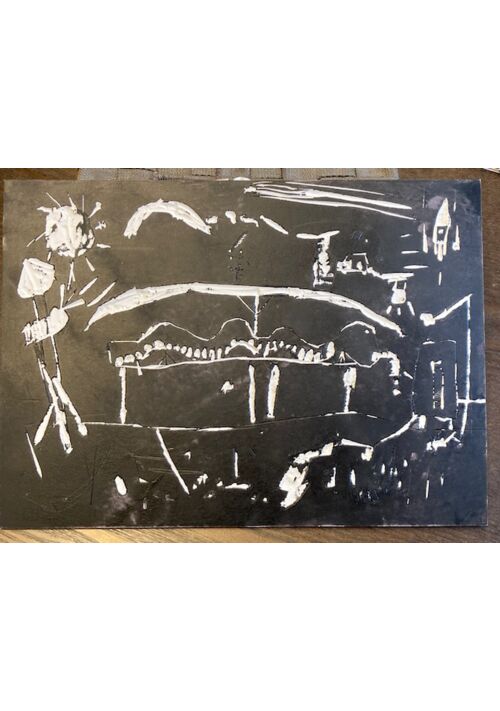
ミズルチと〈竜骨の化石〉
珠邑ミト
児童書・童話
カイトは家族とバラバラに暮らしている〈音読みの一族〉という〈族《うから》〉の少年。彼の一族は、数多ある〈族〉から魂の〈音〉を「読み」、なんの〈族〉か「読みわける」。彼は飛びぬけて「読め」る少年だ。十歳のある日、その力でイトミミズの姿をしている〈族〉を見つけ保護する。ばあちゃんによると、その子は〈出世ミミズ族〉という〈族《うから》〉で、四年かけてミミズから蛇、竜、人と進化し〈竜の一族〉になるという。カイトはこの子にミズルチと名づけ育てることになり……。
一方、世間では怨墨《えんぼく》と呼ばれる、人の負の感情から生まれる墨の化物が活発化していた。これは人に憑りつき操る。これを浄化する墨狩《すみが》りという存在がある。
ミズルチを保護してから三年半後、ミズルチは竜になり、カイトとミズルチは怨墨に知人が憑りつかれたところに遭遇する。これを墨狩りだったばあちゃんと、担任の湯葉《ゆば》先生が狩るのを見て怨墨を知ることに。
カイトとミズルチのルーツをたどる冒険がはじまる。

王女様は美しくわらいました
トネリコ
児童書・童話
無様であろうと出来る全てはやったと満足を抱き、王女様は美しくわらいました。
それはそれは美しい笑みでした。
「お前程の悪女はおるまいよ」
王子様は最後まで嘲笑う悪女を一刀で断罪しました。
きたいの悪女は処刑されました 解説版


王さまとなぞの手紙
村崎けい子
児童書・童話
ある国の王さまのもとに、なぞの手紙が とどきました。
そこに書かれていた もんだいを かいけつしようと、王さまは、三人の大臣(だいじん)たちに それぞれ うえ木ばちをわたすことにしました。
「にじ色の花をさかせてほしい」と――
*本作は、ミステリー風の童話です。本文及び上記紹介文中の漢字は、主に小学二年生までに学習するもののみを使用しています(それ以外は初出の際に振り仮名付)。子どもに読みやすく、大人にも読み辛くならないよう、心がけたものです。

老犬ジョンと子猫のルナ
菊池まりな
児童書・童話
小さな町の片隅で、野良猫が子猫を生み、暖かく、安全な場所へと移動を繰り返しているうちに、一匹の子猫がはぐれてしまう。疲れきって倒れていたところを少年が助けてくれた。その家には老犬のジョンがいた。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















