10 / 11
10
しおりを挟む
外出が出来る日は、その翌日にあたり前のようにやってきた。
雲一つない明朝が世界を出迎え、生温いそよ風ばかりがそこにはあった。窓を開けると室内の冷気が逃げ出し、蒸し暑さに汗をかいてしまうほどである。
愛之丘老人施設の朝は、いつものように始まった。ゼンさんたち三人の外出について、関心を寄せてくるような入園者はいなかった。
ゼンさんは、自分が外に一時的でも出られるという嬉しさは、それほど覚えていなかった。これまで感じていた施設に対する嫌悪感は薄らいでいて、彼はただ、今日ミトさんが向日葵を見に外出できる喜びを抱えて、朝食の席についた。
対するカワさんは、笑顔が絶えない様子だった。薄味のドレッシングのグラムは変わらないのに、量だけが二倍になったサラダにも文句一つ言わなかった。ゼンさんがフルーツをお裾分けすると、「ありがとう」と爽やかににっこりとした。ふっくらとした頬が盛り上がり、やはり全体的に更に若返った印象を与える。
「どうしたね、カワさん? 始終にやにやして、ちょいとばかし気持ち悪いぞ。いや、気味が悪い」
「『どうして』だって? そりゃあ嬉しいに決まってるよ。ミトさんとゼンさんと、三人で一緒に向日葵を見に行けるんだもの」
カワさんは、ハキハキとした口調でそう言った。五分足らずで食事を平らげてしまったので、オカメ看護士に「きちんと噛んで食べなさいと指導しましたよね?」と刺のある声で言われた。
しかし、それでもカワさんは幸せそうに笑んだまま「はいはい」と、反省の色がない返事をしただけだった。ボケてしまっているのではないか、とゼンさんと彼女が心配してしまうほど上機嫌である。
「ミトさんは、明後日ここを出ていくんだって」
「そうか」
「明日は看護師付きでなら、施設の庭園まで出ていいって言われたよ。三人で一緒に少し散歩しようよ」
「まさか、オカメが一緒につくわけじゃあないよな?」
「どうして分かったの?」
目を丸くしたカワさんを見て、ゼンさんは眩暈を覚えた。
キッチン前に移動していたオカメ看護師が、睨みつけるようにこちらを振り返ってきたが、ゼンさんは盛大な溜息を我慢せずに出した。
「おいおい、一体なんの冗談だい、カワさん?」
「仕方ないんだよ。だって明日は、別の視察団体が来るみたいで――」
「なるほど。次は、俺たちが見せ物になるってわけだな?」
「……まぁ、そういうことかもしれないけれど。でも他の職員は暇がなくなるけれど、彼女なら都合がつくと言っていたよ。この前、僕たちと一緒にいた……スドウマサキ先生? ……うん、確かスドウ先生だ。彼がね、ばっちりウィンクを決めて『彼女に任せとけば大丈夫さ』って言っていたよ」
どの若医者を指しているのか、ゼンさんはすぐに分かったが、彼は知らぬ振りで喉に味噌汁を流し込んだ。
今日のゼンさんも、カワさん同様に食事が早い。ほとんど味のない料理も、すんなりと彼の胃袋に収まった。「ちゃんと噛みましたか」とオカメ看護師が目敏く言ってきたが、彼もまた澄ました顔で「三十回以上は噛み砕いたな」と、ニヤリとして小さくなった黄色い歯を見せた。
ミトさんも、本日は体調が良いらしかった。食後に部屋のあるフロアへ上がった時、ゼンさんとカワさんは別の中年看護師にそれを聞かされた。
食事は短時間ごとに少量柔かいものを与えており、これからまた少し睡眠を取らせて、十時前にもう一度食事を与えるという。
「十時までには準備を終わらせて、一階へ連れていきますからね。必要な物は、私たちが袋に入れて持たせます」
四十代の細身の女看護師が早口で言って、小さな胸を強調するような姿勢で歩き去っていった。
女性の部屋だとは思いながらも、つい二人は揃って首を伸ばして、扉が開きっぱなしの部屋の中を覗きこんだ。ミトさんはぐっすり眠っており、二人は顔を見合わせると、お互い唇の前に人差し指を当てて彼女の部屋をあとにした。
例の如く廊下に車椅子を置き、二人はゼンさんの部屋に入った。ゼンさんは机に薬を並べ、カワさんは部屋の隅に常備されている大きめの椅子を引っ張り出して腰かける。
カワさんは、しばらく窓の外を眺めていたが、数分すると自分の部屋から持ってきた本を広げた。窓越しの太陽の日差しは、熱さを帯びて室内を眩しいくらいに明るくしていた。
「こりゃあ、随分と暑い外出になりそうだな」
「痩せるかなぁ」
ふっとカワさんが視線を上げて、そんな呟きをもらす。
ゼンさんは二つ目の薬を掌に乗せたまま、眉間に皺を寄せてカワさんを見やった。
「日焼けするだけだろう。ミトさんには、日傘が必要だな」
「ゼンさんみたいに、僕も引き締まった肌の色になれるかな?」
「俺のは、たんに浅黒いって言うんだ。シミやそばかすだらけだぜ」
そう答えて、ゼンさんは薬を飲みこんだ。次の薬を飲むまでの間、外の風景でも見ようかと首を動かした際、瞳孔を貫くような眩しい光に目を細めた。
サングラスか帽子が必要になりそうだ。麦わら帽子をかぶっていた母の姿を思い出し、ゼンさんは拳をぎゅっと握りしめた。
T遊園地は、愛之丘老人施設から国道で、一番早ければ四十分で着く。これは渋滞に巻き込まれることなく快調にドライブが進み、当国道の法定速度六十キロで走り続けた場合の換算推定時間である。
その国道に乗るまでは、田舎町の細道がしばらく続く。そこを考えると、約一時間と計算した方がいい。少々混んだ場合は、マサヨシがいうように一時間と二十分はかかるだろう。
そこまで考えたところで、ゼンさんは窓からカワさんへと視線を移した。
「ミトさんは、車酔いをする方だろうか?」
「僕は大丈夫だと聞いてるよ」
「カワさんは?」
「左ハンドルの車を運転していたから、左側に座れば特に酔わないと思う」
「くそっ、富裕層が」
ゼンさんが毒ついても、カワさんは臆病癖が直ったように「えへへへ」と笑うだけだった。それからしばらく、二人はミトさんと外出する時間を待ちながら、読書とお喋りを楽しんだ。
※※※
午前九時三十分頃。
カワさんは、職員に頼んで買ってきてもらった使い捨てカメラを持ち、ゼンさんは、大事にしまって取っていたロケットペンダントを、ポケットにしまい込んで部屋を出た。
そのロケットペンダントは、妻との結婚生活が終わりを告げた時に、彼の手元に残った唯一の思い出の品だった。今日、断ちきる想いと共に息子に渡すつもりでいる。ゼンさんは、背筋をピンと伸ばした。
ゆっくりとした足取りで一階へ降りると、身分証が入ったカードケース、飲み物、麦わら帽子が看護師たちから手渡された。フロアには入園者と来客者がまばらにおり、入口となっている正面ガラスからは、贅沢なほどの太陽の光がこぼれていた。
「いい天気だね」
「ああ、いい天気だ」
カワさんが言い、ゼンさんも相槌を打った。
ポケットに両手を突っ込んだまま、ゼンさんが立ち尽くしてしばらくすると、正面入り口に、光沢を持った黒色のボックス乗用車が停まった。日差しを反射する滑らかな塗装が高級感を引き出し、車体の隅々まで磨かれたそれは新車に見える。車高があり、幅も広い。
それを見たカワさんが、落ち着きなくおどおどとした。車から降りてきたダークスーツにネクタイ無しの白シャツ姿の男を見て、「ゼンさんの息子さん?」と控えめに尋ねる。
ゼンさんは、すうっと目を凝らすと、「ああ」と喉から声を絞り出した。
マサヨシは唇を一文字に締めて、つかつかと足早にやってきた。光沢かかった革靴がひとたび館内に響くと、中にいた職員や来客たちの視線が自然とそちらを向いた。
すらりとした長身に、数本の白髪しかない癖のある黒い短髪。少しばかり余分な肉が少々ついてはいるが、鍛えられた筋肉がその身を引き締めているようだった。凛々しく揃えられた眉の下には、彫りの深い双眼がある。
「迎えに来ました」
同じ背丈のゼンさんと向きあい、マサヨシは社会人がすっかり身に沁みた礼儀台詞を口にし、けれど仏頂面で不服そうな口調でそう告げた。
ゼンさんは、受け付けの壁に掛かっている時計をチラリと見上げた。彼と同じ怪訝面にある眉間の皺を深くする。
「十五分前行動か」
「社会人の心掛けだ、基本的なことだよ。部下にそれを教えているのに、上司がやらないんじゃ示しがつかない」
マサヨシはそう言い、ふいっと視線をそらした。そのまま受付けに向かうと、最後の外出手続きを始める。
そこに、オカメ看護師が車椅子のミトさんを連れて現れた。ミトさんは膝掛けに皺の入った白い両手を添え、こちらに向かって微笑みかけてきた。その暖かい空気は以前のような親しみがあり、カワさんが思わず「ミトさん」と声をかけて駆ける。
「はい。ミト、と申します。今日、一緒にひまわりを見てくれる方?」
その時、ミトさんが子供みたいな少し舌足らずな口調で、穏やかにそう告げてきた。
以前のような感覚がまだ抜けていなかったカワさんは、駆け寄ろうとした足並みを落とし、涙腺が緩むのを堪えて、それから顔を上げてにっこりと笑った。
「僕は『カワさん』、そして、向こうにいるのが『ゼンさん』」
「今日は運転手さんが一人いて、ミトさんたち三人を連れて行ってくれるんですよ」
オカメ看護師が、助けるようにしてそう言った。
ゼンさんは、ポケットの中で触っていたロケットペンダントから手を離した。ゆっくりとミトさんに歩み寄ると、カワさんの隣で膝を落として彼女と目線を合わせ、ハッキリと言葉を区切りながら優しく声をかけた。
「こんにちは、ミトさん。今日は、とてもいい天気だよ。向日葵がとても綺麗に見えるだろうね」
「ええ、とても楽しみよ。私、理由は忘れてしまったけれど、ひまわりがとても好きなの」
「僕は元気いっぱいの花だから好きだよ。なんだか、日差しをサンサンと浴びて、楽しそうな花のイメージがあるし!」
「ふふふっ、私もそう思うわ」
ミトさんは上品に微笑した。わざとらしくおどけたカワさんも、ようやくいつもの照れ笑いを浮かべて頭をかいた。
切なさや悲しみは、ひとまず置いていこう。それらは、今は影を潜めなければならない。ゼンさんもそれを分かっていたから、心の底からミトさんに笑いかけた。「三人で、向日葵を見に行こう」と彼が告げると、カワさんも口を開いた。
「ミトさんと、ゼンさんと、僕の三人で見に行けるなんて、とても嬉しいよ」
けれどカワさんは、そのあとに続くはずだった言葉を切るように、不自然に口をつぐんで誤魔化すように笑った。三人で暮らせたら、という台詞を、ゼンさんは思い出していた。笑うカワさんの瞳は潤んでいた。
職員の手からミトさんの予備の薬、十二時四十分までには飲まなければいけないゼンさんの薬各種が、マサヨシに渡された。他には、もしものときのためのタオルや着替え、オムツなどが詰められた手提げ鞄が預けられた。
そのタイミングで、例の『スドウ』と呼ばれていた若い男性医が「やぁ、こんにちは。清々しい朝だね」とウィンク付きでやって来て、マサヨシに思いっきり一瞥されていた。怪しいヤブ医者に見えたのだろう。ゼンさんは何とも言えなかった。
車のトランクに荷物を乗せ、スドウが膝掛け付きのままミトさんを持ち上げて、車の後部座席に移した。マサヨシは愛想をまくこともなく運転席につき、広い後部座席左側にカワさん、中央にミトさんが座る。
「ゼンキチさん、ミトさんを車椅子に移動できますか?」
「出来る。俺の母親も、数年は車椅子だった」
マサヨシの車の後部座席に乗り込む前に、ゼンさんはそう答えた。スドウはほっとしたように、それでいて少し残念そうな笑みを浮かべた。
「遊園地なら、僕も連れて行って欲しかったなぁ」
「俺たちは遊園地で遊ぶわけじゃないんだぞ。向日葵園を訪ねるだけだ」
「ちょっとくらいなら、いいじゃないですか。コーヒーカップとかジェットコースターとか」
「心臓発作を起こすかもしれない人間を、アトラクションに乗せてくれる従業員は、なかなかいないぜ?」
ゼンさんはぶっきらぼうに言って、後部座席の右側に乗り込んだ。すると、スドウが気が抜けそうな表情で弱々しく頭をかいて、こう続けた。
「オバケ屋敷ならイケるんじゃない?」
ぽかんと間の抜けた回答が彼の口から飛び出して、窓を開けていたマサヨシが呆れたように舌打ちし、窓越しにゼンさんが反論するよりも早く車を発進させた。
※※※
車は施設を出るとスピードを落とし、緩やかに山道を下った。車内の冷房は掛けられているが、後部座席のカワさんとゼンさんが座る左右共に、窓は全開だった。
「まぁ、見て。黄色いちょうちょ」
左窓を指したミトさんは、とても楽しそうだった。その左側の方に座っていたカワさんが、顔を桃色に染めながら身体をもじもじさせて「そうだね、黄色い蝶だ」と答える。
ゼンさんは「やれやれ」と窓側に身を寄せて、そこに肘を掛けた。その途端、ガチャリ、とロックの掛かる音が上がって驚いた。どうやら運転席側でマサヨシがドアの鍵をロックしたようだ、と少し遅れて気付いた。
車は安全に下り坂を進んで平地に辿りつくと、畑と住宅を抜けるように進んだ。
信号機がぽつりぽつりとしかない一本道に出ても、擦れ違う車は三台もなかった。途中、トラクターが道路脇をゆっくりと走っていった。日差しは強いが、施設内とは違い生温い風もどこか涼しく感じられた。
十数分後に国道へ入った頃には、走行車の数がぐっと増えていた。平日なので混んではいないものの、隔離された場所に長くいたゼンさんには新鮮だった。ミトさんはまた眠ってしまい、マサヨシは無言のまま各車窓を運転席側の操作で閉めた。
「ねぇ、ゼンさん。僕たちが受け取ったあの帽子、どこかで見たことない?」
沈黙が気まずいマサヨシを意識しないよう、カワさんが明るい声を努めて、そんな話題を口にした。
ゼンさんは窓から彼へと視線を移し、記憶を手繰り寄せながらしばし考えた。
「俺には覚えがないな」
「そうなの? 僕の記憶に間違いがなければ、リハビリ室の壁に掛かっていたものと同じなんだよ」
「てことは、あの麦わら帽子は飾り物かよ」
「うーん、手に届く高さに並べて数個置かれていたから、使われているとは思うけれど」
ゼンさんはつい、あのスドウ医師を思い浮かべた。彼なら勤務姿のまま麦わら帽子をかぶっていても、なんだか違和感がない気がしてならない。
けれど同時に、オカメ看護師も似合うことに気付いてしまい、ゼンさんは苦々しい表情で沈黙した。その時はきつく縛った髪が見えなくなるので、本格的に性別の判断が難しくなってしまうだろう。
「ゼンさん、どうしたの? 車酔い?」
カワさんがそう言い、ミトさんごしに顔を覗かせる。国道をスムーズに走らせながら、マサヨシがバックミラー越しにちらりとこちらを見てきた。
ゼンさんは、組んだ足に視線を向けたまま、「いや」と遠い目をしてぼやいた。
「麦わら帽子って、意外と凶暴性があるよなぁと……」
「ゼンさんが何を言っているのか、よく分からないのだけれど、麦わら帽子に淡い恋の記憶でもあった? やっぱりあの帽子だとアロハシャツだよね。ハワイも良かったけれど、バリ島も良かったなぁ。一日だけの淡い恋とか」
「黙れ、無駄遣いの富裕層が」
ゼンさんは、忌々しげに言葉を切った。彼は国内旅行すらしたことがない。せいぜい節約ドライブか、たまに奮発して美味しい料理を食べることが、もっぱらの贅沢だった。
その時、突然車の進行方向が変わって、ゼンさんは「うおっ」と扉側に身を寄せた。その振動でミトさんが起き、カワさんが「うわっ」と声を上げる。
車は道をそれたかと思うと国道から外れ、少ない車の流れに乗って下り出した。
「おいおいおい、どこへ行くんだよ」
「ちらっとだけ向日葵畑が見えた気がした。ちょっとそっちに寄ってみよう」
「回り道して大丈夫なのか?」
バックミラー越しに、ゼンさんは息子のマサヨシと目を合わせた。数秒の沈黙を置いて、マサヨシがわずかに肩をすくめる仕草をした。
「大丈夫だろう。時間はある」
稼働し続けているカーナビに気付き、ゼンさんは難しい顔のまま「まぁお前に任せるよ」と半ば投げやりに言った。少し寄り道してしまっても、目的地までの道に迷うことはないだろう。
数十分もしないうちに、車は畑道に差しかかった。外の光景に気付いたマサヨシが、運転席側で操作して後部座席側の窓を開けた。
窓の向こうを見たミトさんが「牛がいるわ」と微笑み、カワさんも「本物の牛だ」と興奮したような声を上げた。彼の場合は牛を見た感想よりも、ミトさんが楽しそうなのが嬉しいらしい。窓を見ようと寄りかかられて、身体を緊張させていた。
どうやらマサヨシは、方向感覚や記憶力といったものが良いらしい。それから十分もしないうちに、彼が先程『向日葵畑らしいものがチラリと見えた』と口にしていた、目的の場所の横を、車はゆるやかに走っていた。
普段はトラクターが通っているばかりの土道で、響く振動に揺られながら、ゼンさんは顰め面で押し黙っていた。
向日葵畑を目にしたミトさんとカワさんは、「わぁ」と歓声を上げて楽しそうにしていたが、ここへ車を走らせてきた運転手のマサヨシも無言だった。
まだ昇りきっていない太陽の光が、立ち並ぶ植物の間から、木漏れ日のような温かい光を覗かせていた。ゆっくりと走る車の窓からは、緑と土の匂いが吹き込んでくる。
きらきらと光る日差しの中、そよ風にも動じない巨大な向日葵は、驚くほどがっちりとした茎を伸ばして頭上に花を咲かせていた。
「……おい、マサヨシ。こりゃあ確かに向日葵だが、全貌が全く見えないぜ」
花の頭部分は、車窓の高さを超えるほど高く、土道の両脇をありえないほどに太い茎たちが固めていた。濃い緑の茎には、白い産毛のようなものまで見える。
下から見上げる巨大な向日葵群は、まるで自分たちが小さくなってしまったような錯覚さえ受けるし、なんだかとても威圧感があった。そよ風が窓から窓を通り抜けて、控えめに振動する車内に、向日葵の葉の囁きが耳に入ってくる。
「ゼンさん、これ、すごく大きな向日葵だね。巨大化しているのかな?」
「さぁな。元々この大きさなんだろうという気もするが」
「すごく大きいわねぇ。どのくらいあるのかしら?」
「ミトさんやカワさんよりも大きいだろうな」
ゼンさんは目測で言い、腕を組んだまま仏頂面をバックミラーに向けた。そこには、苦笑したマサヨシの目が映っていた。笑った顔は幼い時の面影がある。目尻の皺は、どれほど年月の隔たりがあるのか告げているようだった。
「畑違いだったみたいだ」
マサヨシはそう言って、畑道を抜けると国道へと車を戻した。スピードが四十キロを越える頃になると再び車窓は閉められ、冷房機が静かに回る音だけが残った。
ゼンさんは、そこでようやく「なるほどな」と相槌を打った。
「『畑違い』とは、なかなか上手いことを言う」
「上から見たら、そのまま向日葵畑だったんだ。もし父さんがそれを見ていたら、俺と同じように勘違いしたと思うけど?」
「僕は、小人の気分が味わえて面白かったよ」
「ひまわり、下から見上げてもきれいだったわねぇ」
自分とは対照的に呑気な意見が出て、ゼンさんはやかましそうにシートにもたれた。思わず「三対一か」と唇を尖らせると、カワさんが少しはマサヨシがいる状況に慣れたように「まぁまぁ、いいじゃない」と上機嫌になだめた。
国道に入ってしばらくすると、ミトさんは、カワさんの肩にもたれるようにして眠ってしまった。
カワさんは頬を真っ赤に染め、どきどきしながらも動かないよう、窓から流れる景色に視線を移して気を紛らわせていた。ゼンさんがにやにやすると、彼は耳まで赤くして硬直してそっぽを向いた。
「……でも、父さんとこんな風に話せるなんて、思わなかったよ」
ふと、マサヨシが言った。
ゼンさんは顔を顰めて「あ?」と視線を向けやった。カワさんが心配したように「ゼンさん」と小さな声で言う。
マサヨシは前方を見据えていたので、バックミラーからは額しか見えなかった。
「いつも、片手にビールだったから」
マサヨシは少し間を置いた後に、思い出したようにそう言って言葉を切った。ゼンさんは腕を組んだまま首を持ち上げ、ややあってから擦れ違う車へと視線を逃がした。
あの頃は、ほぼ切らさずに酒を飲んでいた。まともな会話はなかったと思い出して、ゼンさんは自分に言い聞かせるほどの声量で「そうだったな」と言って目を閉じた。耳に残っているのは、妻と息子に命令する自分の罵声ばかりだった。
気まずい空気が流れ、カワさんも窓の向こうへと視線を逃がした。
車内は涼しく、太陽の光が当たる窓からは熱気が伝わってきた。ほどなくしてカワさんが「夏だねぇ」と囁くと、反対側の車窓を覗くゼンさんもまた「夏だな」と、心を込めずにぽつりと答えた。
雲一つない明朝が世界を出迎え、生温いそよ風ばかりがそこにはあった。窓を開けると室内の冷気が逃げ出し、蒸し暑さに汗をかいてしまうほどである。
愛之丘老人施設の朝は、いつものように始まった。ゼンさんたち三人の外出について、関心を寄せてくるような入園者はいなかった。
ゼンさんは、自分が外に一時的でも出られるという嬉しさは、それほど覚えていなかった。これまで感じていた施設に対する嫌悪感は薄らいでいて、彼はただ、今日ミトさんが向日葵を見に外出できる喜びを抱えて、朝食の席についた。
対するカワさんは、笑顔が絶えない様子だった。薄味のドレッシングのグラムは変わらないのに、量だけが二倍になったサラダにも文句一つ言わなかった。ゼンさんがフルーツをお裾分けすると、「ありがとう」と爽やかににっこりとした。ふっくらとした頬が盛り上がり、やはり全体的に更に若返った印象を与える。
「どうしたね、カワさん? 始終にやにやして、ちょいとばかし気持ち悪いぞ。いや、気味が悪い」
「『どうして』だって? そりゃあ嬉しいに決まってるよ。ミトさんとゼンさんと、三人で一緒に向日葵を見に行けるんだもの」
カワさんは、ハキハキとした口調でそう言った。五分足らずで食事を平らげてしまったので、オカメ看護士に「きちんと噛んで食べなさいと指導しましたよね?」と刺のある声で言われた。
しかし、それでもカワさんは幸せそうに笑んだまま「はいはい」と、反省の色がない返事をしただけだった。ボケてしまっているのではないか、とゼンさんと彼女が心配してしまうほど上機嫌である。
「ミトさんは、明後日ここを出ていくんだって」
「そうか」
「明日は看護師付きでなら、施設の庭園まで出ていいって言われたよ。三人で一緒に少し散歩しようよ」
「まさか、オカメが一緒につくわけじゃあないよな?」
「どうして分かったの?」
目を丸くしたカワさんを見て、ゼンさんは眩暈を覚えた。
キッチン前に移動していたオカメ看護師が、睨みつけるようにこちらを振り返ってきたが、ゼンさんは盛大な溜息を我慢せずに出した。
「おいおい、一体なんの冗談だい、カワさん?」
「仕方ないんだよ。だって明日は、別の視察団体が来るみたいで――」
「なるほど。次は、俺たちが見せ物になるってわけだな?」
「……まぁ、そういうことかもしれないけれど。でも他の職員は暇がなくなるけれど、彼女なら都合がつくと言っていたよ。この前、僕たちと一緒にいた……スドウマサキ先生? ……うん、確かスドウ先生だ。彼がね、ばっちりウィンクを決めて『彼女に任せとけば大丈夫さ』って言っていたよ」
どの若医者を指しているのか、ゼンさんはすぐに分かったが、彼は知らぬ振りで喉に味噌汁を流し込んだ。
今日のゼンさんも、カワさん同様に食事が早い。ほとんど味のない料理も、すんなりと彼の胃袋に収まった。「ちゃんと噛みましたか」とオカメ看護師が目敏く言ってきたが、彼もまた澄ました顔で「三十回以上は噛み砕いたな」と、ニヤリとして小さくなった黄色い歯を見せた。
ミトさんも、本日は体調が良いらしかった。食後に部屋のあるフロアへ上がった時、ゼンさんとカワさんは別の中年看護師にそれを聞かされた。
食事は短時間ごとに少量柔かいものを与えており、これからまた少し睡眠を取らせて、十時前にもう一度食事を与えるという。
「十時までには準備を終わらせて、一階へ連れていきますからね。必要な物は、私たちが袋に入れて持たせます」
四十代の細身の女看護師が早口で言って、小さな胸を強調するような姿勢で歩き去っていった。
女性の部屋だとは思いながらも、つい二人は揃って首を伸ばして、扉が開きっぱなしの部屋の中を覗きこんだ。ミトさんはぐっすり眠っており、二人は顔を見合わせると、お互い唇の前に人差し指を当てて彼女の部屋をあとにした。
例の如く廊下に車椅子を置き、二人はゼンさんの部屋に入った。ゼンさんは机に薬を並べ、カワさんは部屋の隅に常備されている大きめの椅子を引っ張り出して腰かける。
カワさんは、しばらく窓の外を眺めていたが、数分すると自分の部屋から持ってきた本を広げた。窓越しの太陽の日差しは、熱さを帯びて室内を眩しいくらいに明るくしていた。
「こりゃあ、随分と暑い外出になりそうだな」
「痩せるかなぁ」
ふっとカワさんが視線を上げて、そんな呟きをもらす。
ゼンさんは二つ目の薬を掌に乗せたまま、眉間に皺を寄せてカワさんを見やった。
「日焼けするだけだろう。ミトさんには、日傘が必要だな」
「ゼンさんみたいに、僕も引き締まった肌の色になれるかな?」
「俺のは、たんに浅黒いって言うんだ。シミやそばかすだらけだぜ」
そう答えて、ゼンさんは薬を飲みこんだ。次の薬を飲むまでの間、外の風景でも見ようかと首を動かした際、瞳孔を貫くような眩しい光に目を細めた。
サングラスか帽子が必要になりそうだ。麦わら帽子をかぶっていた母の姿を思い出し、ゼンさんは拳をぎゅっと握りしめた。
T遊園地は、愛之丘老人施設から国道で、一番早ければ四十分で着く。これは渋滞に巻き込まれることなく快調にドライブが進み、当国道の法定速度六十キロで走り続けた場合の換算推定時間である。
その国道に乗るまでは、田舎町の細道がしばらく続く。そこを考えると、約一時間と計算した方がいい。少々混んだ場合は、マサヨシがいうように一時間と二十分はかかるだろう。
そこまで考えたところで、ゼンさんは窓からカワさんへと視線を移した。
「ミトさんは、車酔いをする方だろうか?」
「僕は大丈夫だと聞いてるよ」
「カワさんは?」
「左ハンドルの車を運転していたから、左側に座れば特に酔わないと思う」
「くそっ、富裕層が」
ゼンさんが毒ついても、カワさんは臆病癖が直ったように「えへへへ」と笑うだけだった。それからしばらく、二人はミトさんと外出する時間を待ちながら、読書とお喋りを楽しんだ。
※※※
午前九時三十分頃。
カワさんは、職員に頼んで買ってきてもらった使い捨てカメラを持ち、ゼンさんは、大事にしまって取っていたロケットペンダントを、ポケットにしまい込んで部屋を出た。
そのロケットペンダントは、妻との結婚生活が終わりを告げた時に、彼の手元に残った唯一の思い出の品だった。今日、断ちきる想いと共に息子に渡すつもりでいる。ゼンさんは、背筋をピンと伸ばした。
ゆっくりとした足取りで一階へ降りると、身分証が入ったカードケース、飲み物、麦わら帽子が看護師たちから手渡された。フロアには入園者と来客者がまばらにおり、入口となっている正面ガラスからは、贅沢なほどの太陽の光がこぼれていた。
「いい天気だね」
「ああ、いい天気だ」
カワさんが言い、ゼンさんも相槌を打った。
ポケットに両手を突っ込んだまま、ゼンさんが立ち尽くしてしばらくすると、正面入り口に、光沢を持った黒色のボックス乗用車が停まった。日差しを反射する滑らかな塗装が高級感を引き出し、車体の隅々まで磨かれたそれは新車に見える。車高があり、幅も広い。
それを見たカワさんが、落ち着きなくおどおどとした。車から降りてきたダークスーツにネクタイ無しの白シャツ姿の男を見て、「ゼンさんの息子さん?」と控えめに尋ねる。
ゼンさんは、すうっと目を凝らすと、「ああ」と喉から声を絞り出した。
マサヨシは唇を一文字に締めて、つかつかと足早にやってきた。光沢かかった革靴がひとたび館内に響くと、中にいた職員や来客たちの視線が自然とそちらを向いた。
すらりとした長身に、数本の白髪しかない癖のある黒い短髪。少しばかり余分な肉が少々ついてはいるが、鍛えられた筋肉がその身を引き締めているようだった。凛々しく揃えられた眉の下には、彫りの深い双眼がある。
「迎えに来ました」
同じ背丈のゼンさんと向きあい、マサヨシは社会人がすっかり身に沁みた礼儀台詞を口にし、けれど仏頂面で不服そうな口調でそう告げた。
ゼンさんは、受け付けの壁に掛かっている時計をチラリと見上げた。彼と同じ怪訝面にある眉間の皺を深くする。
「十五分前行動か」
「社会人の心掛けだ、基本的なことだよ。部下にそれを教えているのに、上司がやらないんじゃ示しがつかない」
マサヨシはそう言い、ふいっと視線をそらした。そのまま受付けに向かうと、最後の外出手続きを始める。
そこに、オカメ看護師が車椅子のミトさんを連れて現れた。ミトさんは膝掛けに皺の入った白い両手を添え、こちらに向かって微笑みかけてきた。その暖かい空気は以前のような親しみがあり、カワさんが思わず「ミトさん」と声をかけて駆ける。
「はい。ミト、と申します。今日、一緒にひまわりを見てくれる方?」
その時、ミトさんが子供みたいな少し舌足らずな口調で、穏やかにそう告げてきた。
以前のような感覚がまだ抜けていなかったカワさんは、駆け寄ろうとした足並みを落とし、涙腺が緩むのを堪えて、それから顔を上げてにっこりと笑った。
「僕は『カワさん』、そして、向こうにいるのが『ゼンさん』」
「今日は運転手さんが一人いて、ミトさんたち三人を連れて行ってくれるんですよ」
オカメ看護師が、助けるようにしてそう言った。
ゼンさんは、ポケットの中で触っていたロケットペンダントから手を離した。ゆっくりとミトさんに歩み寄ると、カワさんの隣で膝を落として彼女と目線を合わせ、ハッキリと言葉を区切りながら優しく声をかけた。
「こんにちは、ミトさん。今日は、とてもいい天気だよ。向日葵がとても綺麗に見えるだろうね」
「ええ、とても楽しみよ。私、理由は忘れてしまったけれど、ひまわりがとても好きなの」
「僕は元気いっぱいの花だから好きだよ。なんだか、日差しをサンサンと浴びて、楽しそうな花のイメージがあるし!」
「ふふふっ、私もそう思うわ」
ミトさんは上品に微笑した。わざとらしくおどけたカワさんも、ようやくいつもの照れ笑いを浮かべて頭をかいた。
切なさや悲しみは、ひとまず置いていこう。それらは、今は影を潜めなければならない。ゼンさんもそれを分かっていたから、心の底からミトさんに笑いかけた。「三人で、向日葵を見に行こう」と彼が告げると、カワさんも口を開いた。
「ミトさんと、ゼンさんと、僕の三人で見に行けるなんて、とても嬉しいよ」
けれどカワさんは、そのあとに続くはずだった言葉を切るように、不自然に口をつぐんで誤魔化すように笑った。三人で暮らせたら、という台詞を、ゼンさんは思い出していた。笑うカワさんの瞳は潤んでいた。
職員の手からミトさんの予備の薬、十二時四十分までには飲まなければいけないゼンさんの薬各種が、マサヨシに渡された。他には、もしものときのためのタオルや着替え、オムツなどが詰められた手提げ鞄が預けられた。
そのタイミングで、例の『スドウ』と呼ばれていた若い男性医が「やぁ、こんにちは。清々しい朝だね」とウィンク付きでやって来て、マサヨシに思いっきり一瞥されていた。怪しいヤブ医者に見えたのだろう。ゼンさんは何とも言えなかった。
車のトランクに荷物を乗せ、スドウが膝掛け付きのままミトさんを持ち上げて、車の後部座席に移した。マサヨシは愛想をまくこともなく運転席につき、広い後部座席左側にカワさん、中央にミトさんが座る。
「ゼンキチさん、ミトさんを車椅子に移動できますか?」
「出来る。俺の母親も、数年は車椅子だった」
マサヨシの車の後部座席に乗り込む前に、ゼンさんはそう答えた。スドウはほっとしたように、それでいて少し残念そうな笑みを浮かべた。
「遊園地なら、僕も連れて行って欲しかったなぁ」
「俺たちは遊園地で遊ぶわけじゃないんだぞ。向日葵園を訪ねるだけだ」
「ちょっとくらいなら、いいじゃないですか。コーヒーカップとかジェットコースターとか」
「心臓発作を起こすかもしれない人間を、アトラクションに乗せてくれる従業員は、なかなかいないぜ?」
ゼンさんはぶっきらぼうに言って、後部座席の右側に乗り込んだ。すると、スドウが気が抜けそうな表情で弱々しく頭をかいて、こう続けた。
「オバケ屋敷ならイケるんじゃない?」
ぽかんと間の抜けた回答が彼の口から飛び出して、窓を開けていたマサヨシが呆れたように舌打ちし、窓越しにゼンさんが反論するよりも早く車を発進させた。
※※※
車は施設を出るとスピードを落とし、緩やかに山道を下った。車内の冷房は掛けられているが、後部座席のカワさんとゼンさんが座る左右共に、窓は全開だった。
「まぁ、見て。黄色いちょうちょ」
左窓を指したミトさんは、とても楽しそうだった。その左側の方に座っていたカワさんが、顔を桃色に染めながら身体をもじもじさせて「そうだね、黄色い蝶だ」と答える。
ゼンさんは「やれやれ」と窓側に身を寄せて、そこに肘を掛けた。その途端、ガチャリ、とロックの掛かる音が上がって驚いた。どうやら運転席側でマサヨシがドアの鍵をロックしたようだ、と少し遅れて気付いた。
車は安全に下り坂を進んで平地に辿りつくと、畑と住宅を抜けるように進んだ。
信号機がぽつりぽつりとしかない一本道に出ても、擦れ違う車は三台もなかった。途中、トラクターが道路脇をゆっくりと走っていった。日差しは強いが、施設内とは違い生温い風もどこか涼しく感じられた。
十数分後に国道へ入った頃には、走行車の数がぐっと増えていた。平日なので混んではいないものの、隔離された場所に長くいたゼンさんには新鮮だった。ミトさんはまた眠ってしまい、マサヨシは無言のまま各車窓を運転席側の操作で閉めた。
「ねぇ、ゼンさん。僕たちが受け取ったあの帽子、どこかで見たことない?」
沈黙が気まずいマサヨシを意識しないよう、カワさんが明るい声を努めて、そんな話題を口にした。
ゼンさんは窓から彼へと視線を移し、記憶を手繰り寄せながらしばし考えた。
「俺には覚えがないな」
「そうなの? 僕の記憶に間違いがなければ、リハビリ室の壁に掛かっていたものと同じなんだよ」
「てことは、あの麦わら帽子は飾り物かよ」
「うーん、手に届く高さに並べて数個置かれていたから、使われているとは思うけれど」
ゼンさんはつい、あのスドウ医師を思い浮かべた。彼なら勤務姿のまま麦わら帽子をかぶっていても、なんだか違和感がない気がしてならない。
けれど同時に、オカメ看護師も似合うことに気付いてしまい、ゼンさんは苦々しい表情で沈黙した。その時はきつく縛った髪が見えなくなるので、本格的に性別の判断が難しくなってしまうだろう。
「ゼンさん、どうしたの? 車酔い?」
カワさんがそう言い、ミトさんごしに顔を覗かせる。国道をスムーズに走らせながら、マサヨシがバックミラー越しにちらりとこちらを見てきた。
ゼンさんは、組んだ足に視線を向けたまま、「いや」と遠い目をしてぼやいた。
「麦わら帽子って、意外と凶暴性があるよなぁと……」
「ゼンさんが何を言っているのか、よく分からないのだけれど、麦わら帽子に淡い恋の記憶でもあった? やっぱりあの帽子だとアロハシャツだよね。ハワイも良かったけれど、バリ島も良かったなぁ。一日だけの淡い恋とか」
「黙れ、無駄遣いの富裕層が」
ゼンさんは、忌々しげに言葉を切った。彼は国内旅行すらしたことがない。せいぜい節約ドライブか、たまに奮発して美味しい料理を食べることが、もっぱらの贅沢だった。
その時、突然車の進行方向が変わって、ゼンさんは「うおっ」と扉側に身を寄せた。その振動でミトさんが起き、カワさんが「うわっ」と声を上げる。
車は道をそれたかと思うと国道から外れ、少ない車の流れに乗って下り出した。
「おいおいおい、どこへ行くんだよ」
「ちらっとだけ向日葵畑が見えた気がした。ちょっとそっちに寄ってみよう」
「回り道して大丈夫なのか?」
バックミラー越しに、ゼンさんは息子のマサヨシと目を合わせた。数秒の沈黙を置いて、マサヨシがわずかに肩をすくめる仕草をした。
「大丈夫だろう。時間はある」
稼働し続けているカーナビに気付き、ゼンさんは難しい顔のまま「まぁお前に任せるよ」と半ば投げやりに言った。少し寄り道してしまっても、目的地までの道に迷うことはないだろう。
数十分もしないうちに、車は畑道に差しかかった。外の光景に気付いたマサヨシが、運転席側で操作して後部座席側の窓を開けた。
窓の向こうを見たミトさんが「牛がいるわ」と微笑み、カワさんも「本物の牛だ」と興奮したような声を上げた。彼の場合は牛を見た感想よりも、ミトさんが楽しそうなのが嬉しいらしい。窓を見ようと寄りかかられて、身体を緊張させていた。
どうやらマサヨシは、方向感覚や記憶力といったものが良いらしい。それから十分もしないうちに、彼が先程『向日葵畑らしいものがチラリと見えた』と口にしていた、目的の場所の横を、車はゆるやかに走っていた。
普段はトラクターが通っているばかりの土道で、響く振動に揺られながら、ゼンさんは顰め面で押し黙っていた。
向日葵畑を目にしたミトさんとカワさんは、「わぁ」と歓声を上げて楽しそうにしていたが、ここへ車を走らせてきた運転手のマサヨシも無言だった。
まだ昇りきっていない太陽の光が、立ち並ぶ植物の間から、木漏れ日のような温かい光を覗かせていた。ゆっくりと走る車の窓からは、緑と土の匂いが吹き込んでくる。
きらきらと光る日差しの中、そよ風にも動じない巨大な向日葵は、驚くほどがっちりとした茎を伸ばして頭上に花を咲かせていた。
「……おい、マサヨシ。こりゃあ確かに向日葵だが、全貌が全く見えないぜ」
花の頭部分は、車窓の高さを超えるほど高く、土道の両脇をありえないほどに太い茎たちが固めていた。濃い緑の茎には、白い産毛のようなものまで見える。
下から見上げる巨大な向日葵群は、まるで自分たちが小さくなってしまったような錯覚さえ受けるし、なんだかとても威圧感があった。そよ風が窓から窓を通り抜けて、控えめに振動する車内に、向日葵の葉の囁きが耳に入ってくる。
「ゼンさん、これ、すごく大きな向日葵だね。巨大化しているのかな?」
「さぁな。元々この大きさなんだろうという気もするが」
「すごく大きいわねぇ。どのくらいあるのかしら?」
「ミトさんやカワさんよりも大きいだろうな」
ゼンさんは目測で言い、腕を組んだまま仏頂面をバックミラーに向けた。そこには、苦笑したマサヨシの目が映っていた。笑った顔は幼い時の面影がある。目尻の皺は、どれほど年月の隔たりがあるのか告げているようだった。
「畑違いだったみたいだ」
マサヨシはそう言って、畑道を抜けると国道へと車を戻した。スピードが四十キロを越える頃になると再び車窓は閉められ、冷房機が静かに回る音だけが残った。
ゼンさんは、そこでようやく「なるほどな」と相槌を打った。
「『畑違い』とは、なかなか上手いことを言う」
「上から見たら、そのまま向日葵畑だったんだ。もし父さんがそれを見ていたら、俺と同じように勘違いしたと思うけど?」
「僕は、小人の気分が味わえて面白かったよ」
「ひまわり、下から見上げてもきれいだったわねぇ」
自分とは対照的に呑気な意見が出て、ゼンさんはやかましそうにシートにもたれた。思わず「三対一か」と唇を尖らせると、カワさんが少しはマサヨシがいる状況に慣れたように「まぁまぁ、いいじゃない」と上機嫌になだめた。
国道に入ってしばらくすると、ミトさんは、カワさんの肩にもたれるようにして眠ってしまった。
カワさんは頬を真っ赤に染め、どきどきしながらも動かないよう、窓から流れる景色に視線を移して気を紛らわせていた。ゼンさんがにやにやすると、彼は耳まで赤くして硬直してそっぽを向いた。
「……でも、父さんとこんな風に話せるなんて、思わなかったよ」
ふと、マサヨシが言った。
ゼンさんは顔を顰めて「あ?」と視線を向けやった。カワさんが心配したように「ゼンさん」と小さな声で言う。
マサヨシは前方を見据えていたので、バックミラーからは額しか見えなかった。
「いつも、片手にビールだったから」
マサヨシは少し間を置いた後に、思い出したようにそう言って言葉を切った。ゼンさんは腕を組んだまま首を持ち上げ、ややあってから擦れ違う車へと視線を逃がした。
あの頃は、ほぼ切らさずに酒を飲んでいた。まともな会話はなかったと思い出して、ゼンさんは自分に言い聞かせるほどの声量で「そうだったな」と言って目を閉じた。耳に残っているのは、妻と息子に命令する自分の罵声ばかりだった。
気まずい空気が流れ、カワさんも窓の向こうへと視線を逃がした。
車内は涼しく、太陽の光が当たる窓からは熱気が伝わってきた。ほどなくしてカワさんが「夏だねぇ」と囁くと、反対側の車窓を覗くゼンさんもまた「夏だな」と、心を込めずにぽつりと答えた。
0
お気に入りに追加
8
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
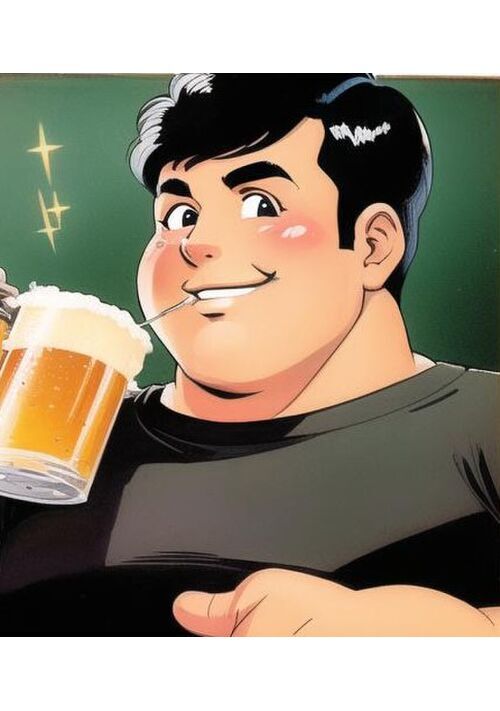
私の神様は〇〇〇〇さん~不思議な太ったおじさんと難病宣告を受けた女の子の1週間の物語~
あらお☆ひろ
現代文学
白血病の診断を受けた20歳の大学生「本田望《ほんだ・のぞみ》」と偶然出会ったちょっと変わった太ったおじさん「備里健《そなえざと・けん」》の1週間の物語です。
「劇脚本」用に大人の絵本(※「H」なものではありません)的に準備したものです。
マニアな読者(笑)を抱えてる「赤井翼」氏の原案をもとに加筆しました。
「病気」を取り扱っていますが、重くならないようにしています。
希と健が「B級グルメ」を楽しみながら、「病気平癒」の神様(※諸説あり)をめぐる話です。
わかりやすいように、極力写真を入れるようにしていますが、撮り忘れやピンボケでアップできないところもあるのはご愛敬としてください。
基本的には、「ハッピーエンド」なので「ゆるーく」お読みください。
全31チャプターなのでひと月くらいお付き合いいただきたいと思います。
よろしくお願いしまーす!(⋈◍>◡<◍)。✧♡

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

この世界に生きていた男の話
百門一新
現代文学
二十八歳の「俺」は、ある日、ふらりと立ち寄ったBARで一人の男に語り聞かせる。それは、四ヶ月前までこの世界に生きていた男の話――
絶縁していた父が肝臓癌末期で倒れ、再会を果たした二十代そこそこだった「俺」。それから約六年に及ぶ闘病生活を一部リアルに、そして死を見届けるまでの葛藤と覚悟と、迎えた最期までを――。
※「小説家になろう」「カクヨム」などにも掲載しています。


微熱の午後 l’aprés-midi(ラプレミディ)
犬束
現代文学
夢見心地にさせるきらびやかな世界、優しくリードしてくれる年上の男性。最初から別れの定められた、遊びの恋のはずだった…。
夏の終わり。大学生になってはじめての長期休暇の後半をもてあます葉《よう》のもとに知らせが届く。
“大祖父の残した洋館に、映画の撮影クルーがやって来た”
好奇心に駆られて訪れたそこで、葉は十歳年上の脚本家、田坂佳思《けいし》から、ここに軟禁されているあいだ、恋人になって幸福な気分で過ごさないか、と提案される。
《第11回BL小説大賞にエントリーしています。》☜ 10月15日にキャンセルしました。
読んでいただけるだけでも、エールを送って下さるなら尚のこと、お腹をさらして喜びます🐕🐾
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















