10 / 28
変わり者刑事と呼ばれる男(3)
しおりを挟む
午後の三時を過ぎた頃、真由は県立図書館の入口にあるベンチに、ぐったりと座り込んでいた。手に持っているのは、先程自分で購入した缶ジュースである。
結局あの後、まっすぐ向かうと言っていたにもかかわらず、宮橋は都内をぐるぐる回るようにして、無謀で意味のない運転を続け、ようやく県立図書館に到着したのも先程の事だった。二度も県立図書館の前を過ぎて、真由は「ああ、図書館がッ」と悲鳴を上げてしまったほどだ。
あの時、そのまま県立図書館入っていれば、車酔いはここまでひどくならなかったと思うのだ。
生まれて二十六年、高校時代に修学旅行で乗った船で酔って吐いた以来の醜態を、真由は先程、県立図書館のトイレでしでかしていた。トイレの個室から出た際に、手を洗っていた女性と鏡越しに目が合って、思い切り反らされたの思い出す。
「うっうっ。私だって、いい歳でゲロゲロしたくなかったのよ」
誰に言うわけでもなく口にして、真由は再び缶ジュースを口許に運んだ。酒は強い方だったので、二日酔いで吐いた事もなく、胃酸のすっぱ苦さを唇いっぱいに感じた事は、しばらくは忘れられそうにない。
宮橋はこちらを心配するどころか、眉を寄せて「だらしないな、君は外で水分でも補給してろ」と言った。そして、一体何を調べたいのかは分らないが、早足に図書館の中へと入って行ってしまったのだ。
車内で削られた体力と精神力に加え、この容赦のない蒸し暑さはたまらない。
ベンチの上でだらしなく座ったまま、そう思って溜息をついた時、ふと、自然と足が広がっている事に気付いて姿勢を正し、のろのろとスカートの裾を伸ばした。普段はズボンで過ごしているため、少し気を抜くといつもこうだ。
ジュースを飲むついでに、もう一つ仕事があって、真由はここで待機していた。館内では携帯電話の使用が禁止されているため、宮橋から「何かあれば君が取れ」と指示されていたのだ。
ジャケットのポケットから、去年買い変えたばかりの桃色の携帯電話を取り出してみた。画面をチェックすると、画面表示時刻は三時三十二分を指している。
「考えたら、事件が経って丸一日も経っていないのよねぇ……みんな忙しくしているのに、こうしてただ座っているだけの私って、無力だわ」
携帯電話をポケットへと戻しながら、しみじみと呟いて頭上を仰いだ。県立図書館の屋上から伸びた屋根の向こうで、広がった青空に綿菓子のように浮かんだ小さな雲が、緩やかに流れているのが見えた。
缶ジュースを飲み干しても、館内から宮橋が出てくる様子はなかった。もう何度目か分からない動作の繰り返しのように、着信もない携帯電話をチェックした際、その表示時刻がようやく午後の四時半を過ぎた頃、彼が建物の入り口に現れた。
宮橋は、待たせた詫びの一言もなく、「行くぞ」と言って目の前を通り過ぎていった。真由が慌ててあとを追うと、振り返らないままこう言った。
「やはりキーマンは、N高校の一学年在籍の生徒『ヨタク』だ。死ぬのは、彼に関わった八人の学生で、もう四人目の被害者が出ているだろう」
「え、四人目の被害者? というか関わった八人の生徒って……あの、図書館でどうしてそんな事が分かるんです?」
だって四人目の被害者が出たという連絡は入っていないし、一体どこから八人という数字が出たのかも不明だ。しかも、『ヨタク』というのは、彼が気になると言っていた苗字ではないだろうか?
真由は、隣に追い付いた彼の横顔を見上げた。顎に手をあてて一人考えるように、宮橋は「代償の補い行為が『条件』だとして……」「『ツギハギ』か」「しかし一体どの『物語』だ?」とよく分からない事を口の中で呟いていて、こちらの質問を聞いていない様子だった。
ふと、彼と過ごしていて、ずっと感じていた違和感の一つに気付いた。思い返せば、彼には一人で突っ走っているような行動や言動で謎が多く、こちらがそれを理解したくて回答を求めても、一度も明確に答えてくれていない。
確かに、自分はここの捜査一課に異動してきたばかりで、急きょあてがわれたような相棒だ。新米で役に立ちそうにもないし、信用だってないだろう。でも、同じ事件を担当する相棒として、理解や考えを共有しないのは、ちょっと寂しい気がする。
その時、ポケットに入れていた薄型の携帯電話が震えて、真由は彼の物を自分が持っていたままだったと気付いた。どうやらマナーモードにされたそれに、どこからか着信が入ったらしい。
偶然にしては、やけにタイミングがいいような気がしたけれど、真由は「宮橋さん、電話です」と言って彼に手渡した。受け取った宮橋が、携帯電話を耳にあてる様子に注目してしまう。
「ああ、僕だ」
そう答えた宮橋が、不意に立ち止まって「――そうか、四人目が出たか」と電話の相手に言葉を返した。
ついさっき言われた通り、もう四人目の被害者が出たのだと知って、真由は両目を見開いた。しばらく携帯電話を耳に当てて話を聞いていた宮橋が、ふと煩そうに顔を顰めて「おい馬鹿三鬼。そもそも、普段から何度も電話を掛けてくるのもしつこいぞ」と言った。
「僕は必要な調べものがあったんだ。どうせ『一旦戻ってこい』とかいうんだろう? 分かってるよ、僕も確認したい事があるから、一旦は戻る」
そう言って一方的に電話を終えると、彼がきびきびと歩き出しながら、こちらを見下ろした。
「被害者たちのグループのメンバーと、中学生の頃から彼らに引っ張りまわされている少年が判明して、事情聴取する方針で全員探しているらしい。僕らも、一旦署に戻るぞ」
「あの、さっきN高校の一年生の『ヨタク』がキーマンで、四人目の被害者が出ている頃だと言っていましたが、一体、何がどうなっているんですか……?」
推理力や考察力が追い付かないせいで、こんなにも自分だけが何も分からないでいるのだろう。そう思って、真由は戸惑いと同時に申し訳なさを覚えて、そう尋ねていた。
宮橋が不意に足を止めた。こちらを真っ直ぐ見下ろして口を開きかけた彼の目が、わずかに細められて唇が引き結ばれた。明るい茶色の瞳に切なさが過ぎって、まるで置いて行かれた子供みたいに見えた。
「宮橋さん……? どうしたんですか?」
思わず呼び掛けたら、彼が質問は受け付けないと言わんばかりに、ふいと視線をそらして「行こう。時間がない」と歩き出した。直前の彼の、初めて見た表情に、それ以上の質問も躊躇われて、真由は黙って隣に並んだ。
初対面の時に『質問はするな』と前もってつっぱねられていた事が思い出されて、はっきり語られないもやもやとした現状への苛立ちは、自分の方が悪かったのかもしれないという一方的な反省に変わっていった。
あの時は、なんて自分勝手な人なんだろうと頭にきたのに、意気揚々とハンドルを握って、駄菓子一つで楽しそうに笑い、大事だから手帳は君が持っていてくれと当然のように預けていた彼を、なんだか悪く思うのも出来そうになかった。
こんなにも短時間のうちに、連続して少年たちが惨殺される現実が信じられない。分からない事だらけが頭に溢れ返って、真由はただ、傾きだした太陽に伸びる影を目に留めていた。
結局あの後、まっすぐ向かうと言っていたにもかかわらず、宮橋は都内をぐるぐる回るようにして、無謀で意味のない運転を続け、ようやく県立図書館に到着したのも先程の事だった。二度も県立図書館の前を過ぎて、真由は「ああ、図書館がッ」と悲鳴を上げてしまったほどだ。
あの時、そのまま県立図書館入っていれば、車酔いはここまでひどくならなかったと思うのだ。
生まれて二十六年、高校時代に修学旅行で乗った船で酔って吐いた以来の醜態を、真由は先程、県立図書館のトイレでしでかしていた。トイレの個室から出た際に、手を洗っていた女性と鏡越しに目が合って、思い切り反らされたの思い出す。
「うっうっ。私だって、いい歳でゲロゲロしたくなかったのよ」
誰に言うわけでもなく口にして、真由は再び缶ジュースを口許に運んだ。酒は強い方だったので、二日酔いで吐いた事もなく、胃酸のすっぱ苦さを唇いっぱいに感じた事は、しばらくは忘れられそうにない。
宮橋はこちらを心配するどころか、眉を寄せて「だらしないな、君は外で水分でも補給してろ」と言った。そして、一体何を調べたいのかは分らないが、早足に図書館の中へと入って行ってしまったのだ。
車内で削られた体力と精神力に加え、この容赦のない蒸し暑さはたまらない。
ベンチの上でだらしなく座ったまま、そう思って溜息をついた時、ふと、自然と足が広がっている事に気付いて姿勢を正し、のろのろとスカートの裾を伸ばした。普段はズボンで過ごしているため、少し気を抜くといつもこうだ。
ジュースを飲むついでに、もう一つ仕事があって、真由はここで待機していた。館内では携帯電話の使用が禁止されているため、宮橋から「何かあれば君が取れ」と指示されていたのだ。
ジャケットのポケットから、去年買い変えたばかりの桃色の携帯電話を取り出してみた。画面をチェックすると、画面表示時刻は三時三十二分を指している。
「考えたら、事件が経って丸一日も経っていないのよねぇ……みんな忙しくしているのに、こうしてただ座っているだけの私って、無力だわ」
携帯電話をポケットへと戻しながら、しみじみと呟いて頭上を仰いだ。県立図書館の屋上から伸びた屋根の向こうで、広がった青空に綿菓子のように浮かんだ小さな雲が、緩やかに流れているのが見えた。
缶ジュースを飲み干しても、館内から宮橋が出てくる様子はなかった。もう何度目か分からない動作の繰り返しのように、着信もない携帯電話をチェックした際、その表示時刻がようやく午後の四時半を過ぎた頃、彼が建物の入り口に現れた。
宮橋は、待たせた詫びの一言もなく、「行くぞ」と言って目の前を通り過ぎていった。真由が慌ててあとを追うと、振り返らないままこう言った。
「やはりキーマンは、N高校の一学年在籍の生徒『ヨタク』だ。死ぬのは、彼に関わった八人の学生で、もう四人目の被害者が出ているだろう」
「え、四人目の被害者? というか関わった八人の生徒って……あの、図書館でどうしてそんな事が分かるんです?」
だって四人目の被害者が出たという連絡は入っていないし、一体どこから八人という数字が出たのかも不明だ。しかも、『ヨタク』というのは、彼が気になると言っていた苗字ではないだろうか?
真由は、隣に追い付いた彼の横顔を見上げた。顎に手をあてて一人考えるように、宮橋は「代償の補い行為が『条件』だとして……」「『ツギハギ』か」「しかし一体どの『物語』だ?」とよく分からない事を口の中で呟いていて、こちらの質問を聞いていない様子だった。
ふと、彼と過ごしていて、ずっと感じていた違和感の一つに気付いた。思い返せば、彼には一人で突っ走っているような行動や言動で謎が多く、こちらがそれを理解したくて回答を求めても、一度も明確に答えてくれていない。
確かに、自分はここの捜査一課に異動してきたばかりで、急きょあてがわれたような相棒だ。新米で役に立ちそうにもないし、信用だってないだろう。でも、同じ事件を担当する相棒として、理解や考えを共有しないのは、ちょっと寂しい気がする。
その時、ポケットに入れていた薄型の携帯電話が震えて、真由は彼の物を自分が持っていたままだったと気付いた。どうやらマナーモードにされたそれに、どこからか着信が入ったらしい。
偶然にしては、やけにタイミングがいいような気がしたけれど、真由は「宮橋さん、電話です」と言って彼に手渡した。受け取った宮橋が、携帯電話を耳にあてる様子に注目してしまう。
「ああ、僕だ」
そう答えた宮橋が、不意に立ち止まって「――そうか、四人目が出たか」と電話の相手に言葉を返した。
ついさっき言われた通り、もう四人目の被害者が出たのだと知って、真由は両目を見開いた。しばらく携帯電話を耳に当てて話を聞いていた宮橋が、ふと煩そうに顔を顰めて「おい馬鹿三鬼。そもそも、普段から何度も電話を掛けてくるのもしつこいぞ」と言った。
「僕は必要な調べものがあったんだ。どうせ『一旦戻ってこい』とかいうんだろう? 分かってるよ、僕も確認したい事があるから、一旦は戻る」
そう言って一方的に電話を終えると、彼がきびきびと歩き出しながら、こちらを見下ろした。
「被害者たちのグループのメンバーと、中学生の頃から彼らに引っ張りまわされている少年が判明して、事情聴取する方針で全員探しているらしい。僕らも、一旦署に戻るぞ」
「あの、さっきN高校の一年生の『ヨタク』がキーマンで、四人目の被害者が出ている頃だと言っていましたが、一体、何がどうなっているんですか……?」
推理力や考察力が追い付かないせいで、こんなにも自分だけが何も分からないでいるのだろう。そう思って、真由は戸惑いと同時に申し訳なさを覚えて、そう尋ねていた。
宮橋が不意に足を止めた。こちらを真っ直ぐ見下ろして口を開きかけた彼の目が、わずかに細められて唇が引き結ばれた。明るい茶色の瞳に切なさが過ぎって、まるで置いて行かれた子供みたいに見えた。
「宮橋さん……? どうしたんですか?」
思わず呼び掛けたら、彼が質問は受け付けないと言わんばかりに、ふいと視線をそらして「行こう。時間がない」と歩き出した。直前の彼の、初めて見た表情に、それ以上の質問も躊躇われて、真由は黙って隣に並んだ。
初対面の時に『質問はするな』と前もってつっぱねられていた事が思い出されて、はっきり語られないもやもやとした現状への苛立ちは、自分の方が悪かったのかもしれないという一方的な反省に変わっていった。
あの時は、なんて自分勝手な人なんだろうと頭にきたのに、意気揚々とハンドルを握って、駄菓子一つで楽しそうに笑い、大事だから手帳は君が持っていてくれと当然のように預けていた彼を、なんだか悪く思うのも出来そうになかった。
こんなにも短時間のうちに、連続して少年たちが惨殺される現実が信じられない。分からない事だらけが頭に溢れ返って、真由はただ、傾きだした太陽に伸びる影を目に留めていた。
0
お気に入りに追加
36
あなたにおすすめの小説

車にはねられて死んで気づいたらツンデレイケメンや新選組と共に霊界の裁判所で仕事をさせられてた話〜松山勇美の霊界異聞奇譚〜
星名雪子
キャラ文芸
20歳の松山勇美は和食レストランで働く令和のフリーター。両親は「近藤勇のように強い子に育って欲しい」との願いから彼女に「勇美」と名付ける程の新選組オタクだった。新選組を始め幕末の歴史を幼い頃から叩き込まれ、柔道も習った勇美は心身共に強くまた正義感に溢れ、常に周囲に対する思い遣りの心を忘れない人間だった。しかし、横断歩道を渡っている最中トラックにはねられそうになった知人を助けようとして急死してしまう。
気がつくと目の前に大きな扉があり、中には白い服を着た大勢の人間がいた。戸惑っていると「裁きの間」と書かれた部屋に呼ばれ、青いダンダラ模様の羽織を着た二人の男に出会う。
一人は切長の瞳が涼しげなクール系イケメン。もう一人は強面で眼光の鋭い大男。その二人は死後の世界ー霊界ーを訪れる死者を、生前の行いから「天国行き」か「地獄行き」かに決定する裁判長と補佐官だった。
「こちらはここ霊界を収めている局長、近藤勇殿である。私は小野たかむら。近藤局長の補佐をしている」
「近藤勇っ?!」
両親から新選組の話を聞いて育った勇美は目の前にいるのがその近藤勇本人だということに仰天。何が何だか分からない内に勇美の裁きが進行。だが、近藤勇による自身の判決を聞いた勇美はあまりの結果に驚愕する。
勇美の判決は?小野たかむらは何者なのか?勇美が近藤の補佐を務めることになる理由とは?そもそも何故、近藤勇が死後の世界で裁判長をしているのか?
「霊界」の秘密が徐々に明らかになり、同時にこの世界の存在を脅かす程の危機が彼らに迫るーー
多くの謎に包まれた死後の世界を舞台に、個性溢れる補佐隊員と新選組隊士達が平安を始め、現代の令和まで様々な時代を駆け回り、ドタバタを繰り広げる笑いあり涙ありの霊界お仕事ファンタジー開幕!
※実在する人物について史実に基づいてはいますが、作品の雰囲気に合わせる為かなり脚色をしています。
※死後の世界について、参考にはしましたが宗教観は殆どありません。
※新選組の知識がそれなりにある方を対象とした作品です。新選組の歴史を軽く頭に入れた上で読んで頂けると幸いです。

リモート刑事 笹本翔
雨垂 一滴
ミステリー
『リモート刑事 笹本翔』は、過去のトラウマと戦う一人の刑事が、リモート捜査で事件を解決していく、刑事ドラマです。
主人公の笹本翔は、かつて警察組織の中でトップクラスの捜査官でしたが、ある事件で仲間を失い、自身も重傷を負ったことで、外出恐怖症(アゴラフォビア)に陥り、現場に出ることができなくなってしまいます。
それでも、彼の卓越した分析力と冷静な判断力は衰えず、リモートで捜査指示を出しながら、次々と難事件を解決していきます。
物語の鍵を握るのは、翔の若き相棒・竹内優斗。熱血漢で行動力に満ちた優斗と、過去の傷を抱えながらも冷静に捜査を指揮する翔。二人の対照的なキャラクターが織りなすバディストーリーです。
翔は果たして過去のトラウマを克服し、再び現場に立つことができるのか?
翔と優斗が数々の難事件に挑戦します!


アナグラム
七海美桜
ミステリー
26歳で警視になった一条櫻子は、大阪の曽根崎警察署に新たに設立された「特別心理犯罪課」の課長として警視庁から転属してくる。彼女の目的は、関西に秘かに収監されている犯罪者「桐生蒼馬」に会う為だった。櫻子と蒼馬に隠された秘密、彼の助言により難解な事件を解決する。櫻子を助ける蒼馬の狙いとは?
※この作品はフィクションであり、登場する地名や団体や組織、全て事実とは異なる事をご理解よろしくお願いします。また、犯罪の内容がショッキングな場合があります。セルフレイティングに気を付けて下さい。
イラスト:カリカリ様
背景:由羅様(pixiv)

グリムの囁き
ふるは ゆう
ミステリー
7年前の児童惨殺事件から続く、猟奇殺人の真相を刑事たちが追う! そのグリムとは……。
7年前の児童惨殺事件での唯一の生き残りの女性が失踪した。当時、担当していた捜査一課の石川は新人の陣内と捜査を開始した矢先、事件は意外な結末を迎える。
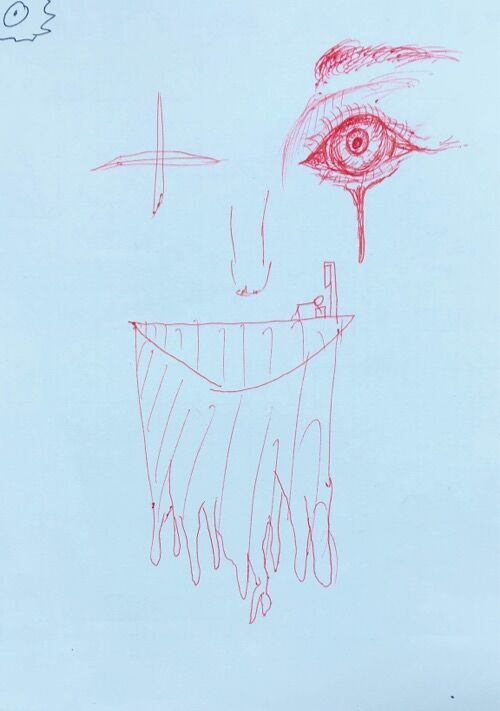

憑代の柩
菱沼あゆ
ミステリー
「お前の顔は整形しておいた。今から、僕の婚約者となって、真犯人を探すんだ」
教会での爆破事件に巻き込まれ。
目が覚めたら、記憶喪失な上に、勝手に整形されていた『私』。
「何もかもお前のせいだ」
そう言う男に逆らえず、彼の婚約者となって、真犯人を探すが。
周りは怪しい人間と霊ばかり――。
ホラー&ミステリー

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















