19 / 20
第三章 礼拝堂
6 青い鹿
しおりを挟む
6 青い鹿
吉田こむぎと常盤明日香というのと、当時はよくつるんでいた。常盤は武士のように静かなたたずまいでバイオリンを弾き、リレーのアンカーを務め、ドッジボールで鋼の球を繰り出す女だ。
こむぎと常盤の二人が訪ねてくることになっていたある日、チャイムが鳴ったので階下に降りると、なにやら不穏な気配がした。どすのきいた声に、階段の半ばで立ち止まる。玄関でうろたえる母の後ろ姿の向こうに、まぶしい夏の光と蝉の声を背負って汗だくの村崎がいた。
階段を上ってきた常盤が私の肩を抱き、こむぎが連れてきたと小声で言った。とりあえず自室に通す。世間話もそこそこに、村崎は、軽井沢に別荘があるというのは本当かと詰め寄ってくる。私が毎夏叔母のアトリエにこもっていることを、こむぎに聞いたらしい。夏の文学散歩は軽井沢にするから、叔母の家を拠点にできないだろうかと言う。
手始めの返答として、嫌だという気持ちを伝えたが、まあ通用しない。鶴見先生は何と言っているのか、日程は調整がついたのかと尋ねると、引率は付けず、我らだけで行くという。鶴見先生には黙っていろという。こむぎは目を輝かせている。私は呆れ、常盤と顔を見合わせた。叔母の家はたぶんもうないと答えると、村崎は目を見開いたままゆっくりと前傾していき、起き上がることは無かった。
三人が帰った後、母に、叔母のアトリエはいまどうなっているのかと尋ねた。村崎が気の毒だったからではない。ふと気になったからだ。このところ常時うわの空だった母が私を見た。二人が消えて以来、誰も触れたがらなかった話題だ。
売りに出すつもりだが、と母は言った。なんだ、まだあるのと言うと、処分にはあなたの承諾がいるからと言う。聞けば、独り身だった叔母は、アトリエを私に遺す手続きをしていたそうだ。そんなことはつゆ知らなかった。
私は、うんともすんとも言わずに部屋に戻った。
叔母が私のためにあの場所を遺していた。黒く塗りつぶされ、もう二度と見ない場所だと思っていた。言葉が出なかった。
風になぶられる金色の木立が目に入った。窓の外は風が強いのだ。西日はまだまだ透き通っている。あの風に似ていた。海のようにゆすれ、気付けば目を満たした。黒い光がかき流される。眩しい。輪郭の決壊は一度始まると、止まらなくなった。親にはわからないのだ。この風の意味も、匂いも。その時、私は生まれて初めて人の死を悼んだ。
* * * *
村崎にアトリエを使っていいと言ったのは、売る前に、もう一度行く口実が欲しかったからだ。最後にするつもりだった。親には合宿だと嘘をついて出かけた。部員でもないのにこむぎ、常盤が同行した。
アトリエは埃をかぶってはいたが、何一つ変わったところはなかった。木製家具に染み込んだ油絵の具の匂い。露に濡れた枯葉とシダの小道、イチイの垣根、草花の匂い。奥には、細かく震える指を持った叔母の気配がしていた。
夜、皆が寝静まった後、私は青い鹿を見た。青い鹿が沙良の目をしてこちらをじっと見ていた。森の奥からやってきたのか、沙良の中から飛び出したのか、私にはわからなくなる。
眠れなくなって、ベッドを出て、向かったのは叔母のキャンバスの前だった。わからない。なぜこんなことになったのか。沙良を叔母の家に送り込んだのも私なら、青い鹿を森に放ったのも私だと思った。
一人では何もできない寂しがりの沙良。病院で数日間生死をさまよっている間、沙良はどんな思いでいたのだろう。沙良の魂は、私の体に入っただろうか。私の目で世界を見たいと言っていた。
わからないことだらけだった。久々に筆を持つ手は他人のように動き、見えないものを掬い取っていった。夜も外では、海鳴りのような風が吹いていた。月明りに照らされたキャンバスは青い鏡となり、私と沙良をつないだ。それからずっと、描き続けていた。
✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎
妙な流行り病で、コンクリートの時間が止まり、いびつな形で凝固した。もう取り返しのつかない凝固した時間が、今更、力ずくで崩され、瓦礫がぞろぞろと押し流されてきた。その瓦礫の中から、妙な部長が現れた。マスクと前髪の間から、妙な目だけを光らせて。
おぼろげに生きてきた。部長に問いただされるまで、自分を言語化したことなどなかった。何から話せばいい。嘘はつきたくないが、何が本当かもわからない。ようするに、どうして今まで私は消えなかったのか。自他の眼差しに怯えながら、額縁の外に身を置いて、それでも世界を眺めていた。それには価値も理由もなかった。
悩んでいる矢先、着信があった。すぐに切れたが、部長からだと分かっていた。迎えになどいくものか。私を待つと言っていた。本気ではないだろう。それでも夜、無視することはできなかった。不安に駆られ、車に乗る。
ヘッドライトで暗い道を切り裂きながら、不安は、いつしか赤黒い感情に変わった。怒り。私の貧弱な語彙ではそんな分類しかできない。初めて名付けてしまってから、憐れむべきものに対して、そんな感情を抱いていいのかと驚いた。あんな目への、また、あんな目をさせたものへの。名前が正しいかは知らない。だが思えばその色は、心の奥にずっと存在していた。沙良が死んだ時からずっと噛み締めていた。
自己への後悔もある。嫌悪もある。でもこの身勝手で理不尽な何かが、自分をここまで連れてきたと思った。発作的に一線を飛び越え、遺されたものの過去と未来を黒く塗り潰すことへの怒り。一度織り込まれた色彩を、面影を、眼差しを、抜き取ることはできない。簡単なことじゃない。遺された絵は、塗りつぶされ、めちゃくちゃに引き裂くしかなかった。
さみしくってしかたがないから、私は描いた。ものを眺め、風に触れ、描くことしかできないから描いた。誰にも理解されない。何の役にも立ちはしない。それでも。
部長の眼差しは、私にしか見えないものの一つなのかもしれず。多分役割のためではなく、私自身のために追いかけた。誰かに押し付けることはできないと知っていた。
吉田こむぎと常盤明日香というのと、当時はよくつるんでいた。常盤は武士のように静かなたたずまいでバイオリンを弾き、リレーのアンカーを務め、ドッジボールで鋼の球を繰り出す女だ。
こむぎと常盤の二人が訪ねてくることになっていたある日、チャイムが鳴ったので階下に降りると、なにやら不穏な気配がした。どすのきいた声に、階段の半ばで立ち止まる。玄関でうろたえる母の後ろ姿の向こうに、まぶしい夏の光と蝉の声を背負って汗だくの村崎がいた。
階段を上ってきた常盤が私の肩を抱き、こむぎが連れてきたと小声で言った。とりあえず自室に通す。世間話もそこそこに、村崎は、軽井沢に別荘があるというのは本当かと詰め寄ってくる。私が毎夏叔母のアトリエにこもっていることを、こむぎに聞いたらしい。夏の文学散歩は軽井沢にするから、叔母の家を拠点にできないだろうかと言う。
手始めの返答として、嫌だという気持ちを伝えたが、まあ通用しない。鶴見先生は何と言っているのか、日程は調整がついたのかと尋ねると、引率は付けず、我らだけで行くという。鶴見先生には黙っていろという。こむぎは目を輝かせている。私は呆れ、常盤と顔を見合わせた。叔母の家はたぶんもうないと答えると、村崎は目を見開いたままゆっくりと前傾していき、起き上がることは無かった。
三人が帰った後、母に、叔母のアトリエはいまどうなっているのかと尋ねた。村崎が気の毒だったからではない。ふと気になったからだ。このところ常時うわの空だった母が私を見た。二人が消えて以来、誰も触れたがらなかった話題だ。
売りに出すつもりだが、と母は言った。なんだ、まだあるのと言うと、処分にはあなたの承諾がいるからと言う。聞けば、独り身だった叔母は、アトリエを私に遺す手続きをしていたそうだ。そんなことはつゆ知らなかった。
私は、うんともすんとも言わずに部屋に戻った。
叔母が私のためにあの場所を遺していた。黒く塗りつぶされ、もう二度と見ない場所だと思っていた。言葉が出なかった。
風になぶられる金色の木立が目に入った。窓の外は風が強いのだ。西日はまだまだ透き通っている。あの風に似ていた。海のようにゆすれ、気付けば目を満たした。黒い光がかき流される。眩しい。輪郭の決壊は一度始まると、止まらなくなった。親にはわからないのだ。この風の意味も、匂いも。その時、私は生まれて初めて人の死を悼んだ。
* * * *
村崎にアトリエを使っていいと言ったのは、売る前に、もう一度行く口実が欲しかったからだ。最後にするつもりだった。親には合宿だと嘘をついて出かけた。部員でもないのにこむぎ、常盤が同行した。
アトリエは埃をかぶってはいたが、何一つ変わったところはなかった。木製家具に染み込んだ油絵の具の匂い。露に濡れた枯葉とシダの小道、イチイの垣根、草花の匂い。奥には、細かく震える指を持った叔母の気配がしていた。
夜、皆が寝静まった後、私は青い鹿を見た。青い鹿が沙良の目をしてこちらをじっと見ていた。森の奥からやってきたのか、沙良の中から飛び出したのか、私にはわからなくなる。
眠れなくなって、ベッドを出て、向かったのは叔母のキャンバスの前だった。わからない。なぜこんなことになったのか。沙良を叔母の家に送り込んだのも私なら、青い鹿を森に放ったのも私だと思った。
一人では何もできない寂しがりの沙良。病院で数日間生死をさまよっている間、沙良はどんな思いでいたのだろう。沙良の魂は、私の体に入っただろうか。私の目で世界を見たいと言っていた。
わからないことだらけだった。久々に筆を持つ手は他人のように動き、見えないものを掬い取っていった。夜も外では、海鳴りのような風が吹いていた。月明りに照らされたキャンバスは青い鏡となり、私と沙良をつないだ。それからずっと、描き続けていた。
✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎
妙な流行り病で、コンクリートの時間が止まり、いびつな形で凝固した。もう取り返しのつかない凝固した時間が、今更、力ずくで崩され、瓦礫がぞろぞろと押し流されてきた。その瓦礫の中から、妙な部長が現れた。マスクと前髪の間から、妙な目だけを光らせて。
おぼろげに生きてきた。部長に問いただされるまで、自分を言語化したことなどなかった。何から話せばいい。嘘はつきたくないが、何が本当かもわからない。ようするに、どうして今まで私は消えなかったのか。自他の眼差しに怯えながら、額縁の外に身を置いて、それでも世界を眺めていた。それには価値も理由もなかった。
悩んでいる矢先、着信があった。すぐに切れたが、部長からだと分かっていた。迎えになどいくものか。私を待つと言っていた。本気ではないだろう。それでも夜、無視することはできなかった。不安に駆られ、車に乗る。
ヘッドライトで暗い道を切り裂きながら、不安は、いつしか赤黒い感情に変わった。怒り。私の貧弱な語彙ではそんな分類しかできない。初めて名付けてしまってから、憐れむべきものに対して、そんな感情を抱いていいのかと驚いた。あんな目への、また、あんな目をさせたものへの。名前が正しいかは知らない。だが思えばその色は、心の奥にずっと存在していた。沙良が死んだ時からずっと噛み締めていた。
自己への後悔もある。嫌悪もある。でもこの身勝手で理不尽な何かが、自分をここまで連れてきたと思った。発作的に一線を飛び越え、遺されたものの過去と未来を黒く塗り潰すことへの怒り。一度織り込まれた色彩を、面影を、眼差しを、抜き取ることはできない。簡単なことじゃない。遺された絵は、塗りつぶされ、めちゃくちゃに引き裂くしかなかった。
さみしくってしかたがないから、私は描いた。ものを眺め、風に触れ、描くことしかできないから描いた。誰にも理解されない。何の役にも立ちはしない。それでも。
部長の眼差しは、私にしか見えないものの一つなのかもしれず。多分役割のためではなく、私自身のために追いかけた。誰かに押し付けることはできないと知っていた。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

女子高生は卒業間近の先輩に告白する。全裸で。
矢木羽研
恋愛
図書委員の女子高生(小柄ちっぱい眼鏡)が、卒業間近の先輩男子に告白します。全裸で。
女の子が裸になるだけの話。それ以上の行為はありません。
取って付けたようなバレンタインネタあり。
カクヨムでも同内容で公開しています。

冬の水葬
束原ミヤコ
青春
夕霧七瀬(ユウギリナナセ)は、一つ年上の幼なじみ、凪蓮水(ナギハスミ)が好き。
凪が高校生になってから疎遠になってしまっていたけれど、ずっと好きだった。
高校一年生になった夕霧は、凪と同じ高校に通えることを楽しみにしていた。
美術部の凪を追いかけて美術部に入り、気安い幼なじみの間柄に戻ることができたと思っていた――
けれど、そのときにはすでに、凪の心には消えない傷ができてしまっていた。
ある女性に捕らわれた凪と、それを追いかける夕霧の、繰り返す冬の話。

小学生最後の夏休みに近所に住む2つ上のお姉さんとお風呂に入った話
矢木羽研
青春
「……もしよかったら先輩もご一緒に、どうですか?」
「あら、いいのかしら」
夕食を作りに来てくれた近所のお姉さんを冗談のつもりでお風呂に誘ったら……?
微笑ましくも甘酸っぱい、ひと夏の思い出。
※性的なシーンはありませんが裸体描写があるのでR15にしています。
※小説家になろうでも同内容で投稿しています。
※2022年8月の「第5回ほっこり・じんわり大賞」にエントリーしていました。

病気になって芸能界から消えたアイドル。退院し、復学先の高校には昔の仕事仲間が居たけれど、彼女は俺だと気付かない
月島日向
ライト文芸
俺、日生遼、本名、竹中祐は2年前に病に倒れた。
人気絶頂だった『Cherry’s』のリーダーをやめた。
2年間の闘病生活に一区切りし、久しぶりに高校に通うことになった。けど、誰も俺の事を元アイドルだとは思わない。薬で細くなった手足。そんな細身の体にアンバランスなムーンフェイス(薬の副作用で顔だけが大きくなる事)
。
誰も俺に気付いてはくれない。そう。
2年間、連絡をくれ続け、俺が無視してきた彼女さえも。
もう、全部どうでもよく感じた。


忘れてしまえたらいいのに(旧題「友と残映」)
佐藤朝槻
ライト文芸
少年の猫西(ねこにし)は、パンを持ち逃げする灰青の猫に惹かれ、保護したいと考える。
しかし、灰青の猫は姿を消してしまった。その原因が猫西にあると知った彼は、罪悪感を抱えながら過ごすようになる。
大学生になった猫西は今度こそ猫を守るべく、大学にいる猫を保護する部活、通称保護部に入る。
救えない命、部員の思惑、切り離せない過去。猫によって生かされ苦しむ彼が選ぶ未来とは……。
※R15相当の残酷な描写があります。
※この物語はフィクションです。登場する人物・団体・名称等は架空であり、実在のものとは関係ありません。
不定期更新&推敲しがちです。
なろうにも掲載しています。
拙作のベースとなるショートショート「友と残映」と「片想いの梅雨」はノベルデイズに掲載しています。
© 2023 Asatsuki Sato

天上にこの口づけを 〜高梨姉妹の双子さんにおける事情〜
ズッコ
ライト文芸
日直の当番で朝早く出ることになった、高校1年生の日向透は、マンションから落ちてきた植木鉢であやうく死にそうになる。出会った二人の高梨さんはどうやらなにかありそうなのだが、、、。
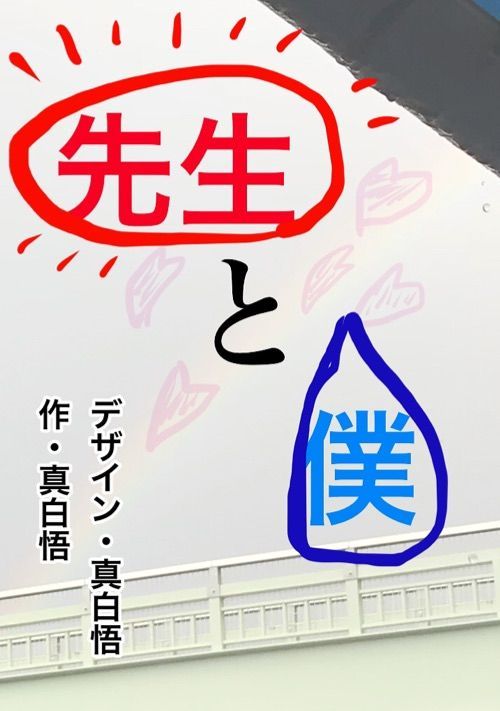
先生と僕
真白 悟
ライト文芸
高校2年になり、少年は進路に恋に勉強に部活とおお忙し。まるで乙女のような青春を送っている。
少しだけ年上の美人な先生と、おっちょこちょいな少女、少し頭のネジがはずれた少年の四コマ漫画風ラブコメディー小説。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















