16 / 19
第1章
クリスマスパーティー (2)
しおりを挟む
器から椎茸を摘まみ上げた陳は続いて金田を占った。
「陳よぉ、ボチボチお迎えが来ないか占えないものかい?」
「金さんは殺しても簡単に死なないネ」
陳は微かに笑みを浮かべながらそう言うと、金田へ向けた椎茸を勢いよく口へと運び傘部分を噛み千切った。
「金さん近々、良い物件が見付かる。北西の方角が良いヨ。この物件は大きく化ける、逃しちゃいけないヨ」
「けっ、金儲けの話かい。どうせ金なんぞ墓まで持っていけるわけでもないのに。いっそまだいい男にでも巡り合うだとかの方が良かったよ」
金田はそう言って悪態をつくが、すぐにバッグからスマホを取り出してどこかへ連絡した。墓まで金は持っていけないと言いながらも、80歳になってもいい男とか言うあたりが金田らしい。まったくこの人のバイタリティーは、どこから湧き出ているのだろうと感心させられる。
次に陳はナムをスルーしてシンの占いを始めた。ナムは毎年この占いはパスしている。彼女に言わせれば女の魅力とは適度なミステリアスさが良いスパイスになるらしい。自らの運命を事前に知ることでそのスパイスを失うと言うことは、どこか味のぼんやりした家庭料理を高級料理店で提供するようなものなのだそうだ。良くわからないが間接的に自らの容姿を高級料理店並みだと評す自信は流石と言うべきか。
「陳、オレは超人になりたいダヨォ。あっ、悪魔超人じゃなくて正義超人ダヨォ、正義超人になる方法を知りたいダヨォ!」
何にでもハマると暫くどっぷりと浸かるタイプのシンは、このところ少し前に漫画喫茶で見付けた昭和のプロレス漫画にどっぷりとハマっていた。元々トレーニング好きで格闘番組なども嫌いじゃないシンのことなので、読みやすい昭和の少年向け漫画はうってつけだったのだろう。
少し前に借金の取り立て依頼の仕事で、相手を脅す際に「払うもの払わねえと、チン肉バスターかますダヨォ!?」と意味不明な脅し文句を吐いていた。流石にズッコケそうになったが、逆に相手がそれを不気味に思ったらしく、すんなりと取り立て出来たので結果オーライだったのだが。
ちなみに他の皆の時もそうだったように、陳の占いは基本的に彼が感じ取った内容をそのまま伝えるだけで、占う項目の指定などは出来ない。そのことは皆も分かっているはずなのに、つい自分が知りたいことを口にしてしまうのは、それだけ陳の占いの精度を信用しているからなのだろう。
口に加えた椎茸の傘を咽ながら吐き出した陳が、真剣な表情で摘まんだ椎茸の柄を見詰める。一段と前のめりになったシンは両手を胸の前で組んで「超人、超人」と呪文のように唱えていた。
「あっ……」
「超人なるダヨォか!?」
不意に声を漏らした陳にシンが目を剥いて詰め寄る。
「成りたい自分になれると出てるアルけど、これって……」
「超人キタダヨォー!!」
おいおい嘘だろ。皆が同じように心の中で呟く。いくら陳の占いでも超人になるなんて有り得ない。
「いや、ポクは成りたい自分になれると言っただけヨ。そもそも、その超人ってどんな人なのヨ? 見たことないネ」
「大丈夫ダヨォ、陳、オレが見せてやるダヨォ!」
些か困惑気味の陳にそう告げると、シンは陳に超人を見せるために早速トレーニングに励むと言い残し、トレーニング機材の置かれた別室へと籠った。
「最後はシャチョの番ヨ」
そう言って陳が青白い顔で弱々しい笑みを浮かべる。
「陳、無理はするな。今回はオレはいいからさ」
「そうはいかないヨ。シャチョにはお世話になってるアルから、本当なら最初に占わなきゃいけないくらいヨ」
器から1番大きく立派な椎茸を取り出した陳はそう言うと、『タマキン』と書かれた額に冷や汗を浮かべながらそれをオレへと向けてゴニョゴニョと何かを唱える。目の下にマジックで描かれた隈が相まって、今にも死にそうな顔をして陳が必死に占いを続ける。人付き合いが苦手な陳だが、オレのことを慕ってくれているのは感じていた。だが、オレも一応はこの会社の社長だ。陳の占いの腕は認めているが、大切な従業員の1人である彼が、顔面蒼白で苦しみながら占いを続ける姿を見るのは忍びない。
占いは適当で良いから早く休ませてやりたい。そんなオレの思いとは裏腹に、陳はここまでの誰の時よりも長くゴニョゴニョと長く何かを唱え続ける。
「ちょっとぉ、陳ちゃん、アタシの時より随分と長くない?」
蝶ママが陳の座る椅子の背後に詰め寄るとほぼ同時に、椎茸の傘部分を勢いよく口へと突っ込んだ。その拍子に嘔吐いたが頬を膨らませてグッと堪えた陳は、噛み切った傘部分を吐き捨てて手にした柄の部分に集中する。蝶ママが陳の吐き出した椎茸の傘が足に当たったと言って猛烈に抗議するが、精神を集中する今の陳にはまったく耳に届いていない様子だ。
確かに蝶ママの言う通り他の誰の占いよりもやや力が籠っている感はある。ひょっとすると茸アレルギーによる限界が近いのを承知で占う必死さがそう感じさせるのかも知れない。
「み、見えたヨ。シャチョ、新しい世界ヨ。まだ見たことのない世界がシャチョの前に開かれるヨ。間もなく鍵を持って……現れるヨ……」
「おい、陳! 大丈夫か!?」
陳はそのままテーブルに覆いかぶさるようにして倒れ、その拍子に器に残った椎茸がテーブルの上にぶち撒かれ、倒れた空瓶が床の上に転げ落ちた。
◇
陳をソファへと運びその場を簡単に片付けると、クリスマスパーティーはひと先ず中締めとなった。占い後に陳が倒れるのも恒例化し皆も慣れたもので、さほど心配していない様子だ。青木と金田とナムと蝶ママが飲み直しに出掛けると、部屋の中はまるで台風が過ぎ去った後のように静まり返る。
ソファーに横たわる陳と、別室から僅かな音を立ててトレーニングに励むシン、そして1人取り残されたオレ。これじゃあまるで別の部屋みたいだな。あまりの静けさにそんなことを思いながらオレは部屋を見回した。細かい部分の片付けは明日ナムがしてくれると言っていた。ああ見えて家事もきっちりとこなすのが彼女の凄いところだ。
それにしてもこの異様な倦怠感は何だ、酒に酔ったのとは何か違う気がするのだが。オレはテレビ前のソファーに腰を掛けると目元を両手で覆った。どれくらい酒を飲んだのかまったく思い出せないのが気に掛かる。このまま横になって眠ってしまいたいのに、何故か絶対に寝てはいけないそんな気がする。
目の前のローテーブルの上には置きっぱなしになっていた『V.R.W』のヘッドセットがあった。低下の倍ものプレミア価格が付いていると聞いたがよく手に入ったものだ。何であれオレのためにわざわざ準備してくれたその気遣いが嬉しい。ヘッドセットを手に取り頭に被ってみる。どうやら電源は入ったままになっているようだ。手袋をはめるとすぐにオレを認識し始め『Link completed』の文字と共に視界の端に幾つかアイコンが現れた。確かこの『マイク』のアイコンを押しながら行きたい場所を言うんだったな。
こんな近未来的な物が一般の家庭用に市販されているのだから、リアルな猫型ロボットが出来損ないの小学生を助けに現れるのも夢じゃない。不意に陳が向こうのソファーで何かにうなされながら寝返りを打った。陳は決して人付き合いは得意ではないが皆を嫌っているわけではない。あんなになるまで皆のために占いをしてやるのだから。そんなことを思いながらオレはマイクのアイコンを触れた。
「見たことのない世界へ……」
折角、陳が占ってくれたんだしな。オレは内心でそんな冗談めかしたことを思いながら、直後に視界の中央に現れた白い点滅を眺めた。きっと陳の言う「新しい世界」とは彼が言ったのは経験的なものを示唆しているのだろう。未だ体験したことの無い何かにトライする切っ掛けでも得るのかも知れない。こんな曖昧な内容でも『V.R.W』はオレをどこかへ誘う気らしい。そんな事を考えていると白い点滅は次第に早まり、やがて視界全体が白く染まった。
気が付くとオレはアジアともヨーロッパともつかないが、高級リゾート地を思わせる雰囲気の広い部屋の中にいた。お香なのかそれとも香水なのか、部屋の中には独特な甘い香りが漂う。部屋のいたる場所に置かれた蝋燭の暖かな灯かりが、何とも言えない味のある雰囲気を醸し出している。
天井が高く太い梁が剥き出しになっており、部屋の片側には壁がなくそのまま広いベランダへと続いており、辛うじて室内と屋外と隔てるように天井から簾のような物が垂れ下がっている。だからといって決して寒くもなく暑すぎるわけでもない。外は真っ暗で景色はよく見えないが微かに聞こえる波の音と、海岸線らしき場所を沿うように立てられた篝火の炎が見える。海の近くに建つ高級リゾートホテルをイメージしたものなのだろうか。
部屋の中にはゆったりとした雰囲気の布地のカウチソファーと、揃いの色調のローテーブルが置かれ、部屋の奥には天蓋付きの大きなベッドが見える。どうやら居間と寝室の敷居すらないらしい。リゾート地にしても流石に開放的過ぎる気もする。
ベランダへ出てみると天然石を用いたジャグジーらしき浴槽と、その横には真っ白なタオルが敷き詰められた診療台のような物が置かれていた。
「ようこそいらっしゃいました」
突然の声に振り返ると部屋とベランダの境目辺りに、真っ黒な衣装に身を包んだ2人の女性の姿が立っていた。1人は長い黒髪を丁寧に編み込み、髪と同じ色の長袖で立ち襟の丈の長い上品なドレスを、もう1人は腰まで届きそうな長さの艶やかな黒髪と同じ色の、上半身が首筋や胸元が強調されており、腰から裾にかけては膝丈の足に張り付くようなタイトなドレスを身に纏っている。
「あっ、どうも。お邪魔してます」
頭ではコンピューターの作り出した仮想空間だと知りながらも、そのあまりのリアルさにオレは思わず2人に頭を上げてかしこまった。
「お邪魔だなんてとんでも御座いません。お待ちしておりました」
長袖で立ち襟姿の女は自らをイゼルと名乗り涼やかな笑顔を見せる。近世ヨーロッパの女教師を連想させるきっちりとした衣装とは裏腹に、張り裂けんばかりに主張する双丘が何ともエロい。すぐに隣に立つ腰まである黒髪の女も慌ててタハミイネと名乗った。イゼルとは対照的に開放的な首元と深めに入ったスリットから覗く足が、どこか着せられてる感の強い分かり易いエロさを醸し出している。タハミイネの方がイゼルの方より年下なのだろう。衣装とは対照的な初々しさが印象的だ。
彼女たちの透き通るような白い肌は白人のそれとも違っており、どこか不思議な雰囲気を持っている。彫はやや深めで可愛いと言うよりは、美しい顔立ちと言ったほうが伝わりやすいだろう。実際に街でこんな2人が目の前を通り過ぎれば、きっと無意識に目で追ってしまうに違いない。いったい何人をイメージしたものなのだろうか。金色に輝くワイルドな瞳だけが、彼女たちが現実の存在ではないことを如実に物語っていた。
「さあ、タハミイネ?」
「あっ、よ、宜しければマッサージなどいかがでしょうか?」
イゼルに切っ掛けを与えられタハミイネが慌てて問い掛けた。随分と緊張した様子だが新人という設定なのだろうか。オレはそんな細かな部分まで設定が盛り込まれているのかと内心で感心しながらも、その申し出を快く受けてマッサージをお願いすることにした。仮想空間でのマッサージなんておもしろい。いったいどんな感じなのだろう。この空間なら空を飛ぶことだって可能だろうが、マッサージの心地良さをどのように表現するのかにはちょっと興味がある。
オレはイゼルとタハミイネに導かれ、促されるままに脱いだ服を籠に入れ、真っ白なタオルが敷き詰められた診療台の上に横になった。なるほどこれはそのために用意されているのか。 誰かに見られればかなり間抜けな場面だろうが、今は恐らくその心配はいらないだろう。
それにしてもマッサージを勧めたのはオレが疲れているのを察したからなのか、それともただの定型文だったのか気になるところだ。そんな邪推をしていると、すぐにタハミイネが柔らかな肌触りの布をオレの体の上に掛けながら訊ねる。
「コ、コースの方は『エグゼグティブ』『スペシャル』『ノーマル』となってございます。いかがいたしましょう?」
詳しい内容も聞かずにオレは『エグゼグティブ』を選択した。仮想空間であれば高額な請求をされることもないだろう。「畏まりました」と言って深々とお辞儀をするとタハミイネがいそいそと準備を始める。その間にイゼルが手際良く、オレの両手と両足に温かい蒸しタオルを何重にも重ねて巻いていく。
「熱くはありませんか?」
「いえ、気持ちいいです」
本当に気持ち良い。オレは正直かなり驚いていた。不思議なことに実際に蒸しタオルに包まれたような温かさと心地良さが手足に伝わってくるではないか。
やがてオレの両手と両足に巻かれたタオルがボーリング玉ほどの大きさになると、今度は鼻と口だけを避けるように、顔にも温かいタオルが乗せられていく。心地良い温かさだけでなく、タオルからほのかに香る花の匂いまでが再現されている。
「それではマッサージを始めさせていただきます」
そうタハミイネの声がすると体に掛けられた布が取り除かれる。視覚が奪われているぶん他の感覚が研ぎ澄まされているのだろう。衣擦れや何かの作業をする音が微かに聞こえる。やがて温かい液体が胸の上に垂らされた。オイルのようなものなのだろうか、僅かに粘度を感じさせる滑らかな液体だ。
細い指でそれをまんべんなく塗り伸ばしマッサージが始まる。きっとこれはイゼルではないだろうか。その手際が良く迷いのない動きからオレはそう想像した。バーチャルでこれほど気持ちの良いマッサージを体験できるとなれば、今に本物のマッサージを受けようとする者がいなくなるのではないか、オレはそんなことを思いながら心地良さに身を委ねる。
「強さはいかがでしょうか?」
「丁度いいです」
すぐ近くからイゼルの声が聞こえる。やはりマッサージをしてくれていたのはイゼルだったようだ。オレが答えると彼女はそのまま暫くマッサージを続ける。やがてひと通りの工程が終了するように手が止まり、イゼルの気配が遠のくのが感じられた。もう少し続けて欲しいところだが仕方がない。
「そ、それデは只今より『エグゼグティブコース』に入らせていただきます!」
今からかよ。緊張しすぎてやや声が裏返り気味になったタハミイネの言葉にオレは内心で突っ込んだ。だとしたら今までのはウォーミングアップのようなものなのか。そんなことを思っていると、たどたどしいい手付きで細い指がオレの体に触れるのを感じた。これはタハミイネか。
オレはこれから始まるエグゼグティブコースに、期待と不安を覚えずにはいられなかった。
「陳よぉ、ボチボチお迎えが来ないか占えないものかい?」
「金さんは殺しても簡単に死なないネ」
陳は微かに笑みを浮かべながらそう言うと、金田へ向けた椎茸を勢いよく口へと運び傘部分を噛み千切った。
「金さん近々、良い物件が見付かる。北西の方角が良いヨ。この物件は大きく化ける、逃しちゃいけないヨ」
「けっ、金儲けの話かい。どうせ金なんぞ墓まで持っていけるわけでもないのに。いっそまだいい男にでも巡り合うだとかの方が良かったよ」
金田はそう言って悪態をつくが、すぐにバッグからスマホを取り出してどこかへ連絡した。墓まで金は持っていけないと言いながらも、80歳になってもいい男とか言うあたりが金田らしい。まったくこの人のバイタリティーは、どこから湧き出ているのだろうと感心させられる。
次に陳はナムをスルーしてシンの占いを始めた。ナムは毎年この占いはパスしている。彼女に言わせれば女の魅力とは適度なミステリアスさが良いスパイスになるらしい。自らの運命を事前に知ることでそのスパイスを失うと言うことは、どこか味のぼんやりした家庭料理を高級料理店で提供するようなものなのだそうだ。良くわからないが間接的に自らの容姿を高級料理店並みだと評す自信は流石と言うべきか。
「陳、オレは超人になりたいダヨォ。あっ、悪魔超人じゃなくて正義超人ダヨォ、正義超人になる方法を知りたいダヨォ!」
何にでもハマると暫くどっぷりと浸かるタイプのシンは、このところ少し前に漫画喫茶で見付けた昭和のプロレス漫画にどっぷりとハマっていた。元々トレーニング好きで格闘番組なども嫌いじゃないシンのことなので、読みやすい昭和の少年向け漫画はうってつけだったのだろう。
少し前に借金の取り立て依頼の仕事で、相手を脅す際に「払うもの払わねえと、チン肉バスターかますダヨォ!?」と意味不明な脅し文句を吐いていた。流石にズッコケそうになったが、逆に相手がそれを不気味に思ったらしく、すんなりと取り立て出来たので結果オーライだったのだが。
ちなみに他の皆の時もそうだったように、陳の占いは基本的に彼が感じ取った内容をそのまま伝えるだけで、占う項目の指定などは出来ない。そのことは皆も分かっているはずなのに、つい自分が知りたいことを口にしてしまうのは、それだけ陳の占いの精度を信用しているからなのだろう。
口に加えた椎茸の傘を咽ながら吐き出した陳が、真剣な表情で摘まんだ椎茸の柄を見詰める。一段と前のめりになったシンは両手を胸の前で組んで「超人、超人」と呪文のように唱えていた。
「あっ……」
「超人なるダヨォか!?」
不意に声を漏らした陳にシンが目を剥いて詰め寄る。
「成りたい自分になれると出てるアルけど、これって……」
「超人キタダヨォー!!」
おいおい嘘だろ。皆が同じように心の中で呟く。いくら陳の占いでも超人になるなんて有り得ない。
「いや、ポクは成りたい自分になれると言っただけヨ。そもそも、その超人ってどんな人なのヨ? 見たことないネ」
「大丈夫ダヨォ、陳、オレが見せてやるダヨォ!」
些か困惑気味の陳にそう告げると、シンは陳に超人を見せるために早速トレーニングに励むと言い残し、トレーニング機材の置かれた別室へと籠った。
「最後はシャチョの番ヨ」
そう言って陳が青白い顔で弱々しい笑みを浮かべる。
「陳、無理はするな。今回はオレはいいからさ」
「そうはいかないヨ。シャチョにはお世話になってるアルから、本当なら最初に占わなきゃいけないくらいヨ」
器から1番大きく立派な椎茸を取り出した陳はそう言うと、『タマキン』と書かれた額に冷や汗を浮かべながらそれをオレへと向けてゴニョゴニョと何かを唱える。目の下にマジックで描かれた隈が相まって、今にも死にそうな顔をして陳が必死に占いを続ける。人付き合いが苦手な陳だが、オレのことを慕ってくれているのは感じていた。だが、オレも一応はこの会社の社長だ。陳の占いの腕は認めているが、大切な従業員の1人である彼が、顔面蒼白で苦しみながら占いを続ける姿を見るのは忍びない。
占いは適当で良いから早く休ませてやりたい。そんなオレの思いとは裏腹に、陳はここまでの誰の時よりも長くゴニョゴニョと長く何かを唱え続ける。
「ちょっとぉ、陳ちゃん、アタシの時より随分と長くない?」
蝶ママが陳の座る椅子の背後に詰め寄るとほぼ同時に、椎茸の傘部分を勢いよく口へと突っ込んだ。その拍子に嘔吐いたが頬を膨らませてグッと堪えた陳は、噛み切った傘部分を吐き捨てて手にした柄の部分に集中する。蝶ママが陳の吐き出した椎茸の傘が足に当たったと言って猛烈に抗議するが、精神を集中する今の陳にはまったく耳に届いていない様子だ。
確かに蝶ママの言う通り他の誰の占いよりもやや力が籠っている感はある。ひょっとすると茸アレルギーによる限界が近いのを承知で占う必死さがそう感じさせるのかも知れない。
「み、見えたヨ。シャチョ、新しい世界ヨ。まだ見たことのない世界がシャチョの前に開かれるヨ。間もなく鍵を持って……現れるヨ……」
「おい、陳! 大丈夫か!?」
陳はそのままテーブルに覆いかぶさるようにして倒れ、その拍子に器に残った椎茸がテーブルの上にぶち撒かれ、倒れた空瓶が床の上に転げ落ちた。
◇
陳をソファへと運びその場を簡単に片付けると、クリスマスパーティーはひと先ず中締めとなった。占い後に陳が倒れるのも恒例化し皆も慣れたもので、さほど心配していない様子だ。青木と金田とナムと蝶ママが飲み直しに出掛けると、部屋の中はまるで台風が過ぎ去った後のように静まり返る。
ソファーに横たわる陳と、別室から僅かな音を立ててトレーニングに励むシン、そして1人取り残されたオレ。これじゃあまるで別の部屋みたいだな。あまりの静けさにそんなことを思いながらオレは部屋を見回した。細かい部分の片付けは明日ナムがしてくれると言っていた。ああ見えて家事もきっちりとこなすのが彼女の凄いところだ。
それにしてもこの異様な倦怠感は何だ、酒に酔ったのとは何か違う気がするのだが。オレはテレビ前のソファーに腰を掛けると目元を両手で覆った。どれくらい酒を飲んだのかまったく思い出せないのが気に掛かる。このまま横になって眠ってしまいたいのに、何故か絶対に寝てはいけないそんな気がする。
目の前のローテーブルの上には置きっぱなしになっていた『V.R.W』のヘッドセットがあった。低下の倍ものプレミア価格が付いていると聞いたがよく手に入ったものだ。何であれオレのためにわざわざ準備してくれたその気遣いが嬉しい。ヘッドセットを手に取り頭に被ってみる。どうやら電源は入ったままになっているようだ。手袋をはめるとすぐにオレを認識し始め『Link completed』の文字と共に視界の端に幾つかアイコンが現れた。確かこの『マイク』のアイコンを押しながら行きたい場所を言うんだったな。
こんな近未来的な物が一般の家庭用に市販されているのだから、リアルな猫型ロボットが出来損ないの小学生を助けに現れるのも夢じゃない。不意に陳が向こうのソファーで何かにうなされながら寝返りを打った。陳は決して人付き合いは得意ではないが皆を嫌っているわけではない。あんなになるまで皆のために占いをしてやるのだから。そんなことを思いながらオレはマイクのアイコンを触れた。
「見たことのない世界へ……」
折角、陳が占ってくれたんだしな。オレは内心でそんな冗談めかしたことを思いながら、直後に視界の中央に現れた白い点滅を眺めた。きっと陳の言う「新しい世界」とは彼が言ったのは経験的なものを示唆しているのだろう。未だ体験したことの無い何かにトライする切っ掛けでも得るのかも知れない。こんな曖昧な内容でも『V.R.W』はオレをどこかへ誘う気らしい。そんな事を考えていると白い点滅は次第に早まり、やがて視界全体が白く染まった。
気が付くとオレはアジアともヨーロッパともつかないが、高級リゾート地を思わせる雰囲気の広い部屋の中にいた。お香なのかそれとも香水なのか、部屋の中には独特な甘い香りが漂う。部屋のいたる場所に置かれた蝋燭の暖かな灯かりが、何とも言えない味のある雰囲気を醸し出している。
天井が高く太い梁が剥き出しになっており、部屋の片側には壁がなくそのまま広いベランダへと続いており、辛うじて室内と屋外と隔てるように天井から簾のような物が垂れ下がっている。だからといって決して寒くもなく暑すぎるわけでもない。外は真っ暗で景色はよく見えないが微かに聞こえる波の音と、海岸線らしき場所を沿うように立てられた篝火の炎が見える。海の近くに建つ高級リゾートホテルをイメージしたものなのだろうか。
部屋の中にはゆったりとした雰囲気の布地のカウチソファーと、揃いの色調のローテーブルが置かれ、部屋の奥には天蓋付きの大きなベッドが見える。どうやら居間と寝室の敷居すらないらしい。リゾート地にしても流石に開放的過ぎる気もする。
ベランダへ出てみると天然石を用いたジャグジーらしき浴槽と、その横には真っ白なタオルが敷き詰められた診療台のような物が置かれていた。
「ようこそいらっしゃいました」
突然の声に振り返ると部屋とベランダの境目辺りに、真っ黒な衣装に身を包んだ2人の女性の姿が立っていた。1人は長い黒髪を丁寧に編み込み、髪と同じ色の長袖で立ち襟の丈の長い上品なドレスを、もう1人は腰まで届きそうな長さの艶やかな黒髪と同じ色の、上半身が首筋や胸元が強調されており、腰から裾にかけては膝丈の足に張り付くようなタイトなドレスを身に纏っている。
「あっ、どうも。お邪魔してます」
頭ではコンピューターの作り出した仮想空間だと知りながらも、そのあまりのリアルさにオレは思わず2人に頭を上げてかしこまった。
「お邪魔だなんてとんでも御座いません。お待ちしておりました」
長袖で立ち襟姿の女は自らをイゼルと名乗り涼やかな笑顔を見せる。近世ヨーロッパの女教師を連想させるきっちりとした衣装とは裏腹に、張り裂けんばかりに主張する双丘が何ともエロい。すぐに隣に立つ腰まである黒髪の女も慌ててタハミイネと名乗った。イゼルとは対照的に開放的な首元と深めに入ったスリットから覗く足が、どこか着せられてる感の強い分かり易いエロさを醸し出している。タハミイネの方がイゼルの方より年下なのだろう。衣装とは対照的な初々しさが印象的だ。
彼女たちの透き通るような白い肌は白人のそれとも違っており、どこか不思議な雰囲気を持っている。彫はやや深めで可愛いと言うよりは、美しい顔立ちと言ったほうが伝わりやすいだろう。実際に街でこんな2人が目の前を通り過ぎれば、きっと無意識に目で追ってしまうに違いない。いったい何人をイメージしたものなのだろうか。金色に輝くワイルドな瞳だけが、彼女たちが現実の存在ではないことを如実に物語っていた。
「さあ、タハミイネ?」
「あっ、よ、宜しければマッサージなどいかがでしょうか?」
イゼルに切っ掛けを与えられタハミイネが慌てて問い掛けた。随分と緊張した様子だが新人という設定なのだろうか。オレはそんな細かな部分まで設定が盛り込まれているのかと内心で感心しながらも、その申し出を快く受けてマッサージをお願いすることにした。仮想空間でのマッサージなんておもしろい。いったいどんな感じなのだろう。この空間なら空を飛ぶことだって可能だろうが、マッサージの心地良さをどのように表現するのかにはちょっと興味がある。
オレはイゼルとタハミイネに導かれ、促されるままに脱いだ服を籠に入れ、真っ白なタオルが敷き詰められた診療台の上に横になった。なるほどこれはそのために用意されているのか。 誰かに見られればかなり間抜けな場面だろうが、今は恐らくその心配はいらないだろう。
それにしてもマッサージを勧めたのはオレが疲れているのを察したからなのか、それともただの定型文だったのか気になるところだ。そんな邪推をしていると、すぐにタハミイネが柔らかな肌触りの布をオレの体の上に掛けながら訊ねる。
「コ、コースの方は『エグゼグティブ』『スペシャル』『ノーマル』となってございます。いかがいたしましょう?」
詳しい内容も聞かずにオレは『エグゼグティブ』を選択した。仮想空間であれば高額な請求をされることもないだろう。「畏まりました」と言って深々とお辞儀をするとタハミイネがいそいそと準備を始める。その間にイゼルが手際良く、オレの両手と両足に温かい蒸しタオルを何重にも重ねて巻いていく。
「熱くはありませんか?」
「いえ、気持ちいいです」
本当に気持ち良い。オレは正直かなり驚いていた。不思議なことに実際に蒸しタオルに包まれたような温かさと心地良さが手足に伝わってくるではないか。
やがてオレの両手と両足に巻かれたタオルがボーリング玉ほどの大きさになると、今度は鼻と口だけを避けるように、顔にも温かいタオルが乗せられていく。心地良い温かさだけでなく、タオルからほのかに香る花の匂いまでが再現されている。
「それではマッサージを始めさせていただきます」
そうタハミイネの声がすると体に掛けられた布が取り除かれる。視覚が奪われているぶん他の感覚が研ぎ澄まされているのだろう。衣擦れや何かの作業をする音が微かに聞こえる。やがて温かい液体が胸の上に垂らされた。オイルのようなものなのだろうか、僅かに粘度を感じさせる滑らかな液体だ。
細い指でそれをまんべんなく塗り伸ばしマッサージが始まる。きっとこれはイゼルではないだろうか。その手際が良く迷いのない動きからオレはそう想像した。バーチャルでこれほど気持ちの良いマッサージを体験できるとなれば、今に本物のマッサージを受けようとする者がいなくなるのではないか、オレはそんなことを思いながら心地良さに身を委ねる。
「強さはいかがでしょうか?」
「丁度いいです」
すぐ近くからイゼルの声が聞こえる。やはりマッサージをしてくれていたのはイゼルだったようだ。オレが答えると彼女はそのまま暫くマッサージを続ける。やがてひと通りの工程が終了するように手が止まり、イゼルの気配が遠のくのが感じられた。もう少し続けて欲しいところだが仕方がない。
「そ、それデは只今より『エグゼグティブコース』に入らせていただきます!」
今からかよ。緊張しすぎてやや声が裏返り気味になったタハミイネの言葉にオレは内心で突っ込んだ。だとしたら今までのはウォーミングアップのようなものなのか。そんなことを思っていると、たどたどしいい手付きで細い指がオレの体に触れるのを感じた。これはタハミイネか。
オレはこれから始まるエグゼグティブコースに、期待と不安を覚えずにはいられなかった。
0
お気に入りに追加
39
あなたにおすすめの小説

もしかして寝てる間にざまぁしました?
ぴぴみ
ファンタジー
令嬢アリアは気が弱く、何をされても言い返せない。
内気な性格が邪魔をして本来の能力を活かせていなかった。
しかし、ある時から状況は一変する。彼女を馬鹿にし嘲笑っていた人間が怯えたように見てくるのだ。
私、寝てる間に何かしました?

日本帝国陸海軍 混成異世界根拠地隊
北鴨梨
ファンタジー
太平洋戦争も終盤に近付いた1944(昭和19)年末、日本海軍が特攻作戦のため終結させた南方の小規模な空母機動部隊、北方の輸送兼対潜掃討部隊、小笠原増援輸送部隊が突如として消失し、異世界へ転移した。米軍相手には苦戦続きの彼らが、航空戦力と火力、機動力を生かして他を圧倒し、図らずも異世界最強の軍隊となってしまい、その情勢に大きく関わって引っ掻き回すことになる。

これダメなクラス召喚だわ!物を掌握するチートスキルで自由気ままな異世界旅
聖斗煉
ファンタジー
クラス全体で異世界に呼び出された高校生の主人公が魔王軍と戦うように懇願される。しかし、主人公にはしょっぱい能力しか与えられなかった。ところがである。実は能力は騙されて弱いものと思い込まされていた。ダンジョンに閉じ込められて死にかけたときに、本当は物を掌握するスキルだったことを知るーー。
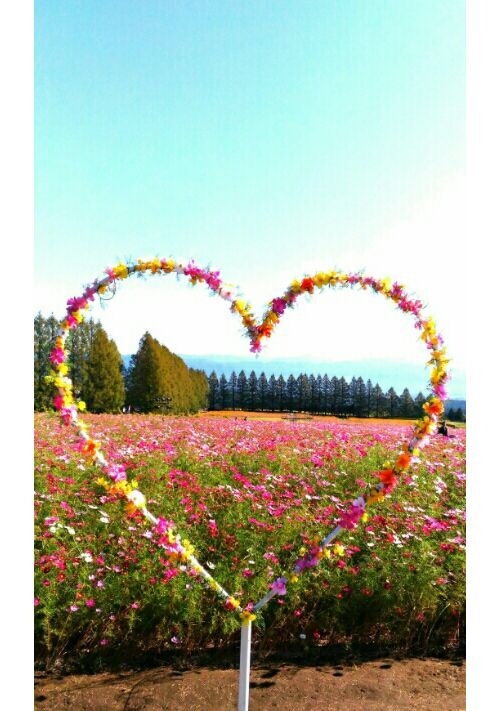
リィナ・カンザーの美醜逆転恋愛譚
譚音アルン
ファンタジー
ぽっちゃり娘のリィナ・カンザーこと神崎里奈はある日突然異世界トリップ。放り出された先はブリオスタという王国。着の身着のままでそれなりに苦労もしたが、異世界人は総じて親切な人が多く、運良く住み込みで食堂のウェイトレスの職を得ることが出来た。
しかしそんなある日の事。
彼女は常連さんである冒険者、魔法剣士カイル・シャン・イグレシアに厳めしい表情で呼び出される。
自分が何か粗相をしたのかと戦々恐々としながらテーブルに行くと――。
※2018-08-09より小説家になろうで連載、本編完結済。
※アルファポリスでの掲載も2020-03-25で完結しました。

田舎暮らしと思ったら、異世界暮らしだった。
けむし
ファンタジー
突然の異世界転移とともに魔法が使えるようになった青年の、ほぼ手に汗握らない物語。
日本と異世界を行き来する転移魔法、物を複製する魔法。
あらゆる魔法を使えるようになった主人公は異世界で、そして日本でチート能力を発揮・・・するの?
ゆる~くのんびり進む物語です。読者の皆様ものんびりお付き合いください。
感想などお待ちしております。

せっかくのクラス転移だけども、俺はポテトチップスでも食べながらクラスメイトの冒険を見守りたいと思います
霖空
ファンタジー
クラス転移に巻き込まれてしまった主人公。
得た能力は悪くない……いや、むしろ、チートじみたものだった。
しかしながら、それ以上のデメリットもあり……。
傍観者にならざるをえない彼が傍観者するお話です。
基本的に、勇者や、影井くんを見守りつつ、ほのぼの?生活していきます。
が、そのうち、彼自身の物語も始まる予定です。

俺だけ毎日チュートリアルで報酬無双だけどもしかしたら世界の敵になったかもしれない
亮亮
ファンタジー
朝起きたら『チュートリアル 起床』という謎の画面が出現。怪訝に思いながらもチュートリアルをクリアしていき、報酬を貰う。そして近い未来、世界が一新する出来事が起こり、主人公・花房 萌(はなぶさ はじめ)の人生の歯車が狂いだす。
不意に開かれるダンジョンへのゲート。その奥には常人では決して踏破できない存在が待ち受け、萌の体は凶刃によって裂かれた。
そしてチュートリアルが発動し、復活。殺される。復活。殺される。気が狂いそうになる輪廻の果て、萌は光明を見出し、存在を継承する事になった。
帰還した後、急速に馴染んでいく新世界。新しい学園への編入。試験。新たなダンジョン。
そして邂逅する謎の組織。
萌の物語が始まる。

異世界に降り立った刀匠の孫─真打─
リゥル
ファンタジー
異世界に降り立った刀匠の孫─影打─が読みやすく修正され戻ってきました。ストーリーの続きも連載されます、是非お楽しみに!
主人公、帯刀奏。彼は刀鍛冶の人間国宝である、帯刀響の孫である。
亡くなった祖父の刀を握り泣いていると、突然異世界へと召喚されてしまう。
召喚されたものの、周囲の人々の期待とは裏腹に、彼の能力が期待していたものと違い、かけ離れて脆弱だったことを知る。
そして失敗と罵られ、彼の祖父が打った形見の刀まで侮辱された。
それに怒りを覚えたカナデは、形見の刀を抜刀。
過去に、勇者が使っていたと言われる聖剣に切りかかる。
――この物語は、冒険や物作り、によって成長していく少年たちを描く物語。
カナデは、人々と触れ合い、世界を知り、祖父を超える一振りを打つことが出来るのだろうか……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















