17 / 40
宇津領の件
牛蒡餅
しおりを挟む
下野へは日光街道を行く。主要五街道のひとつであり、東照宮への参拝者が頻繁にあることから、この時代にあってもずいぶんとこの道は整備されていた。
人の往来が密なるところには盛り場ができる。街道沿いの宿場はどこも賑やかで、旨いものを食わせる店などもたくさんあった。当然、多くの利権が発生し、香具師などもうろつく。揉め事が年中絶えず、取り締まりも往々にして必要な場面が多い。
森玄蕃の拝命する目付は、旗本や御家人の監視が役目ではあるが、旗本の領地に隣接する宿場であれば、こうした場所での情報収集も重要だ。そう言い訳をして、新三郎と忠馬は宿場町のひとつに馬を寄せた。
「なるほど名物だけあってうまいな」
もともとは正月の縁起ものだったという”耳うどん”をぺろりと平らげて、新三郎は額の汗を拭きながら一息ついた。向かいでは猫舌の忠馬がいまだにふうふうとやっている。
まだまだかかりそうなので新三郎は店の小女をつかまえて、このあたりでうまい甘いものは何かと尋ねた。
「なら牛蒡餅はどうですかね」
「なに牛蒡? それは甘いのかい?」
「へえまあ、はちみつを塗ったり甘味噌を付けたりしますから……」
若い武家が甘い物を所望すること自体が珍しいようで、小女は目を白黒させながら返事をしたが、さいごにはお持ちしましょうかと言った。
「ここで売っているのかね」
「このあたりの食い物屋ではだいたい置いてますよ。少しずつ味が違うみたいですけど」
それは面白い、と言って新三郎は目を輝かせた。宿場には見るだけでも十軒ばかり商店がある。それぞれの店にそれぞれの味とはなんとも興味深い話だ。
「荻野さんはなぜそんなに甘い物が好きなんですか」
ようやく耳うどんを食べ終えた忠馬が、汗だくの胸元に風を送りながら尋ねる。忠馬は今年二十一になったばかりの若造ながらかなりの酒豪らしい。総じて酒飲みは甘い物を食わない。忠馬もそうらしく、甘い物と聞くと舌をべえっと出して嫌な顔をする口だ。
「さてなあ。理由はないなあ。頭と身体が欲しいと言うものを口にしているだけだからな」
「酒飲みと同じ理屈ですね」
「甘味はいくら食っても泥酔せんよ」
「でも太っちゃいますよ」
「それは酒も同じだろう」
言い合っているうちに店の小女が牛蒡餅を持ってきてくれた。二つずつそれぞれ味噌とはちみつが塗ってある。
「ではさっそく」
味噌の方からかじる。一口目から新三郎は目で「おっ」と驚いた。さっくりとした歯触りの後、次々に訪れるのは牛蒡の香りだ。餅の弾力と繊維質の食感が飽きを感じさせない。そして甘く合わせた味噌が牛蒡の風味を一層かきたてた。
「娘さん、これは天ぷらのように揚げるのかな」
「はあい、左様でございます」
「油は貴重だと思ったが……」
「料理屋の残り油を使うんですよ。御府内からたくさん運ばれてきますから」
当時、料理に使う油はほとんどが胡麻油だ。漉しては何度も使うのである。それでも百万人を養う都市から出る残り油は相当な量で、なんでも再利用する当時の庶民はこうしたものまで有効に使っていた。
「おや、こいつは酒にも合いますよ。はちみつのは遠慮しますがね」
横から手を出した忠馬が味噌の牛蒡餅をむしゃむしゃしながら唾を飛ばす。それならば、と新三郎は残りを全部ぺろりとやった。なかなかいいものを見つけた。帰りにいくつか見繕って行けば土産にちょうどよさそうだ。
「ところで荻野さん、聞きましたよ縁談の話」
満腹になった様子で、爪楊枝を使いながら忠馬が横目で新三郎を見た。玄蕃のやつが話したのだろう。まったく困ったものだ。
「縁談なんかじゃない。ちょっと妙なことになっているだけで、家同士でしている話ではないからな」
「志賀道場の加也様でしょう? 志賀加也と言えば剣術小町なんて呼ばれて界隈ではかなり有名人ですよ。いいところのお嬢様ってだけあって綺麗な顔をしてるらしいじゃないですか。羨ましいなあ。あ、剣術小町の件は内緒ですよ。本人は聞くと機嫌が悪くなるらしいですから」
忠馬に言われてみると、確かに加也は美しい娘だった。だが十八だという、なんと新三郎と八つも年が離れている。それにいくら美人だと言っても腕っぷしは自分より強いし、何より始終勝ち気な雰囲気がどうにも新三郎には合わない。年はやはりある程度近い方がいいし、何より自分を理解してくれる連れ合いが欲しいと思う。
そこまで夢想して、自分が思い浮かべている人の姿を新三郎は頭を振り回してかき消した。そういえば志賀道場でも何か口走ったような記憶がある。
「私なぞは代々渡り中間の家系ですからね。縁談なんてひとつも来やしません。お屋形様が世話すると言って下さってるんですけどね」
「忠馬」
べらべらと喋るのに釘を刺されて忠馬はぎくりとした。気軽く話してはいるが相手は三千石の坊ちゃんである。それに自分の主の幼友達とくれば少々おしゃべりが過ぎたようだと縮こまってしまった。
新三郎は忠馬がそうした考えを巡らせていることを察したが、あまりしたくない話をされるのも迷惑だったのでちょうどよいと踏ん切りをつけた。
「そろそろ参ろう。牛蒡餅は帰りにまた見繕わせてもらえばいいだろう」
財布を引っ張り出しつつ新三郎が立ち上がると、恐縮した忠馬が繋いだ馬を曳くためにさっと飛び出していった。少し薬が効きすぎただろうか。
「娘さん、勘定を頼む。ところでこのあたりの殿様のことを聞きたいのだが」
「へえ、どっちのお殿様ですか?」
言われてはたと思い出す。このあたりの領地は入り組んでいて、こっちからあっちは藩領、あっちからそっちは旗本領、とややこしい。
「宇津様の方だ」
「はあ、宇津のお殿様ですか」
「あまりいい評判ではなさそうだね」
「へえ、領民がほとんど逃げちまってますからねえ」
「ほう、それはまた」
江戸ではまるで知られていない話だ。原因はいったいなんだろう。道すがら街道を隔てて右左で余りに風景が違ったのだが、理由は農民の離散らしい。
これは継嗣問題だけでは収まりそうもない。
そう思うと、ここへ送り込んだ玄蕃の魂胆が慮れようというものだった。
人の往来が密なるところには盛り場ができる。街道沿いの宿場はどこも賑やかで、旨いものを食わせる店などもたくさんあった。当然、多くの利権が発生し、香具師などもうろつく。揉め事が年中絶えず、取り締まりも往々にして必要な場面が多い。
森玄蕃の拝命する目付は、旗本や御家人の監視が役目ではあるが、旗本の領地に隣接する宿場であれば、こうした場所での情報収集も重要だ。そう言い訳をして、新三郎と忠馬は宿場町のひとつに馬を寄せた。
「なるほど名物だけあってうまいな」
もともとは正月の縁起ものだったという”耳うどん”をぺろりと平らげて、新三郎は額の汗を拭きながら一息ついた。向かいでは猫舌の忠馬がいまだにふうふうとやっている。
まだまだかかりそうなので新三郎は店の小女をつかまえて、このあたりでうまい甘いものは何かと尋ねた。
「なら牛蒡餅はどうですかね」
「なに牛蒡? それは甘いのかい?」
「へえまあ、はちみつを塗ったり甘味噌を付けたりしますから……」
若い武家が甘い物を所望すること自体が珍しいようで、小女は目を白黒させながら返事をしたが、さいごにはお持ちしましょうかと言った。
「ここで売っているのかね」
「このあたりの食い物屋ではだいたい置いてますよ。少しずつ味が違うみたいですけど」
それは面白い、と言って新三郎は目を輝かせた。宿場には見るだけでも十軒ばかり商店がある。それぞれの店にそれぞれの味とはなんとも興味深い話だ。
「荻野さんはなぜそんなに甘い物が好きなんですか」
ようやく耳うどんを食べ終えた忠馬が、汗だくの胸元に風を送りながら尋ねる。忠馬は今年二十一になったばかりの若造ながらかなりの酒豪らしい。総じて酒飲みは甘い物を食わない。忠馬もそうらしく、甘い物と聞くと舌をべえっと出して嫌な顔をする口だ。
「さてなあ。理由はないなあ。頭と身体が欲しいと言うものを口にしているだけだからな」
「酒飲みと同じ理屈ですね」
「甘味はいくら食っても泥酔せんよ」
「でも太っちゃいますよ」
「それは酒も同じだろう」
言い合っているうちに店の小女が牛蒡餅を持ってきてくれた。二つずつそれぞれ味噌とはちみつが塗ってある。
「ではさっそく」
味噌の方からかじる。一口目から新三郎は目で「おっ」と驚いた。さっくりとした歯触りの後、次々に訪れるのは牛蒡の香りだ。餅の弾力と繊維質の食感が飽きを感じさせない。そして甘く合わせた味噌が牛蒡の風味を一層かきたてた。
「娘さん、これは天ぷらのように揚げるのかな」
「はあい、左様でございます」
「油は貴重だと思ったが……」
「料理屋の残り油を使うんですよ。御府内からたくさん運ばれてきますから」
当時、料理に使う油はほとんどが胡麻油だ。漉しては何度も使うのである。それでも百万人を養う都市から出る残り油は相当な量で、なんでも再利用する当時の庶民はこうしたものまで有効に使っていた。
「おや、こいつは酒にも合いますよ。はちみつのは遠慮しますがね」
横から手を出した忠馬が味噌の牛蒡餅をむしゃむしゃしながら唾を飛ばす。それならば、と新三郎は残りを全部ぺろりとやった。なかなかいいものを見つけた。帰りにいくつか見繕って行けば土産にちょうどよさそうだ。
「ところで荻野さん、聞きましたよ縁談の話」
満腹になった様子で、爪楊枝を使いながら忠馬が横目で新三郎を見た。玄蕃のやつが話したのだろう。まったく困ったものだ。
「縁談なんかじゃない。ちょっと妙なことになっているだけで、家同士でしている話ではないからな」
「志賀道場の加也様でしょう? 志賀加也と言えば剣術小町なんて呼ばれて界隈ではかなり有名人ですよ。いいところのお嬢様ってだけあって綺麗な顔をしてるらしいじゃないですか。羨ましいなあ。あ、剣術小町の件は内緒ですよ。本人は聞くと機嫌が悪くなるらしいですから」
忠馬に言われてみると、確かに加也は美しい娘だった。だが十八だという、なんと新三郎と八つも年が離れている。それにいくら美人だと言っても腕っぷしは自分より強いし、何より始終勝ち気な雰囲気がどうにも新三郎には合わない。年はやはりある程度近い方がいいし、何より自分を理解してくれる連れ合いが欲しいと思う。
そこまで夢想して、自分が思い浮かべている人の姿を新三郎は頭を振り回してかき消した。そういえば志賀道場でも何か口走ったような記憶がある。
「私なぞは代々渡り中間の家系ですからね。縁談なんてひとつも来やしません。お屋形様が世話すると言って下さってるんですけどね」
「忠馬」
べらべらと喋るのに釘を刺されて忠馬はぎくりとした。気軽く話してはいるが相手は三千石の坊ちゃんである。それに自分の主の幼友達とくれば少々おしゃべりが過ぎたようだと縮こまってしまった。
新三郎は忠馬がそうした考えを巡らせていることを察したが、あまりしたくない話をされるのも迷惑だったのでちょうどよいと踏ん切りをつけた。
「そろそろ参ろう。牛蒡餅は帰りにまた見繕わせてもらえばいいだろう」
財布を引っ張り出しつつ新三郎が立ち上がると、恐縮した忠馬が繋いだ馬を曳くためにさっと飛び出していった。少し薬が効きすぎただろうか。
「娘さん、勘定を頼む。ところでこのあたりの殿様のことを聞きたいのだが」
「へえ、どっちのお殿様ですか?」
言われてはたと思い出す。このあたりの領地は入り組んでいて、こっちからあっちは藩領、あっちからそっちは旗本領、とややこしい。
「宇津様の方だ」
「はあ、宇津のお殿様ですか」
「あまりいい評判ではなさそうだね」
「へえ、領民がほとんど逃げちまってますからねえ」
「ほう、それはまた」
江戸ではまるで知られていない話だ。原因はいったいなんだろう。道すがら街道を隔てて右左で余りに風景が違ったのだが、理由は農民の離散らしい。
これは継嗣問題だけでは収まりそうもない。
そう思うと、ここへ送り込んだ玄蕃の魂胆が慮れようというものだった。
0
お気に入りに追加
5
あなたにおすすめの小説

仕舞屋蘭方医 根古屋冲有 お江戸事件帖 人魚とおはぎ
藍上イオタ
歴史・時代
【11/22刊行】「第9回歴史・時代小説大賞」特別賞受賞作
ときは文化文政。
正義感が強く真っ直ぐな青年「犬飼誠吾」は、与力見習いとして日々励んでいた。
悩みを抱えるたび誠吾は、親友である蘭方医「根古屋冲有」のもとを甘味を持って訪れる。
奇人変人と恐れられているひねくれ者の根古屋だが、推理と医術の腕はたしかだからだ。
ふたりは力を合わせて、江戸の罪を暴いていく。
身分を超えた友情と、下町の義理人情。
江戸の風俗を織り交ぜた、医療ミステリーの短編連作。
2023.7.22「小説家になろう」ジャンル別日間ランキング 推理にて1位
2023.7.25「小説家になろう」ジャンル別週間ランキング 推理にて2位
2023.8.13「小説家になろう」ジャンル月週間ランキング 推理にて3位
2023.8.07「アルファポリス」歴史・時代ジャンルにて1位
になりました。
ありがとうございます!
書籍化にあたり、タイトルを変更しました。
旧『蘭方医の診療録 』
新『仕舞屋蘭方医 根古屋冲有 お江戸事件帖 人魚とおはぎ』

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。


慈童は果てなき道をめざす
尾方佐羽
歴史・時代
【連作です】室町時代、僧のなりでひとり旅をする青年のお話です。彼は何かを探しているのですが、それは見つかるのでしょうか。彼の旅は何を生み出すのでしょうか。彼の名は大和三郎、のちの世阿弥元清です。

晩夏の蝉
紫乃森統子
歴史・時代
当たり前の日々が崩れた、その日があった──。
まだほんの14歳の少年たちの日常を変えたのは、戊辰の戦火であった。
後に二本松少年隊と呼ばれた二本松藩の幼年兵、堀良輔と成田才次郎、木村丈太郎の三人の終着点。
※本作品は昭和16年発行の「二本松少年隊秘話」を主な参考にした史実ベースの創作作品です。
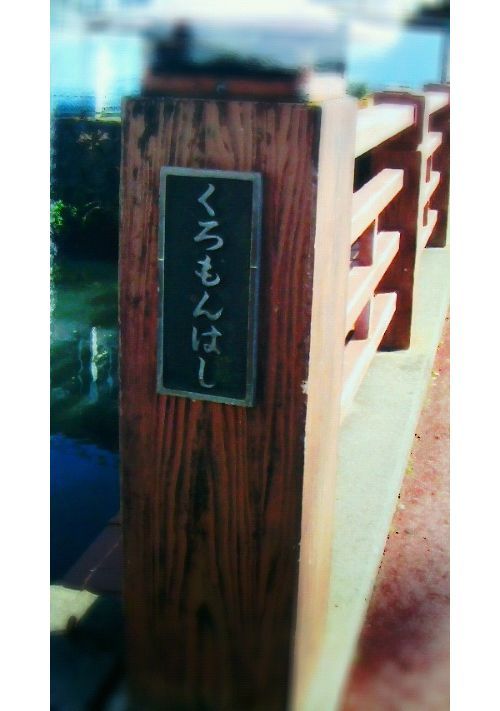
肥後の春を待ち望む
尾方佐羽
歴史・時代
秀吉の天下統一が目前になった天正の頃、肥後(熊本)の国主になった佐々成政に対して国人たちが次から次へと反旗を翻した。それを先導した国人の筆頭格が隈部親永(くまべちかなが)である。彼はなぜ、島津も退くほどの強大な敵に立ち向かったのか。国人たちはどのように戦ったのか。そして、九州人ながら秀吉に従い国人衆とあいまみえることになった若き立花統虎(宗茂)の胸中は……。


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















