12 / 51
第三章 過去、未遂、特別な女。
(1)
しおりを挟む
「小野寺ちゃーん。来たよ。今日も例の彼!」
先輩の中では比較的仲良くさせてもらっている今野(こんの)さんが、口を緩ませながらカウンターに戻ってきた。同時に中吉ちゃんが、「目の保養が来た! 行ってきまーす!」と書籍を携えて飛び出していく。
ここ最近幾度となく目にしてきた光景に、私は軽く肩を竦めた。
最近、誰かさんがM大図書館にちょくちょく出現するようになった。
恐らく、奈緒と栄二さんの会話を耳にしたのだろう。貸出カードの作り方を尋ねてきた奴を目にしたときは、一瞬ここが職場ということを忘れるところだった。
「それでそれでっ! あのイケメンさんはずばり! 小野寺さんの彼氏サンなわけですよねっ!?」
迫りくる中吉ちゃんの期待に満ちた瞳。その傍らで作業していた今野さんも、同調するようにうんうんと頷く。
「いやー、私も妙だと思っていたのよ。小野寺さんくらいの美人さんがフリーなはずがないってさぁ」
「今野さんも中吉ちゃんも誤解です。奴……じゃなく、あの人はただの知り合いってだけで、彼氏とかそういうのじゃ」
「事務の子たちにも教えてあげなくちゃ! 小野寺さんにつ・い・に! 発覚した彼氏は超イケメン長身イケメン!」
幸せのお裾分けとばかりに飛び出していった彼女を呆然と見送る。
四十代前半の今野さんは、苦笑しながら「若い子はこの手の話が大好物だもんね~」と私の肩に手を乗せた。「というか、イケメンて二回言ってたね」
中吉ちゃんの蜘蛛の巣を張り巡らせたような情報網は、午後の図書館来場数に確実に影響を与えることになった。
「なあなあ、お前が聞いて来いよ」「小野寺さん、特定のメンズができたって本当ですかってか?」好奇の視線を向けてくる資料集め中の学生たち。
「わかんないよねー、あんなつんけん女のどこがいいんだか」「ふふっ、あんた聞こえるって」「でもあのロングヘア―は憧れるなぁ。ストイックさが滲み出てるよね」褒めてるのかけなしてるのかわからない空気を漂わせる大学事務の子たち。
「いやあ、孤高の美人司書さんに恋人ができたと聞いたもんでね」しまいには私を愛想がないと毛嫌いしているセクハラ教授まで。
もはや否定する気も失せた。
噂に振り回されている知人以下の人影をまるっと無視し、私は通常業務を粛々と進める。勝手に尾ひれを付けて楽しむが良い。暇人どもが。
「すみません。この本をお借りしたいんですが」
利用者から差し出される、蔵書検索のレシート。所蔵図書の案内もまた立派な司書の業務だ。
例えその利用者が、本日の騒動の元凶だとしても。
「この参考図書は三階の書庫ですね。お持ちします」
「良ければついていっても?」
「……どうぞ。こちらです」
満足げににこり、と笑みを浮かべた奴に、遠巻きから女子学生の黄色い悲鳴が上がる。
すかさず主任が彼女らの注意に腰を上げたが、奴はといえばまるで興味がない様子だった。
「……まだ居たんだ。午前で帰ったんだと思ってた」
人気のない通路に入ると同時に、私はちろりと奴に視線を遣った。
店で働くときとは違う、白肌に映える紺色の軽めなカットソーにジーパンというラフスタイル。シンプルな時計がはめられた涼しげな手首に、ふと指元までを盗み見た。
指輪はない。不特定多数の彼女たちには、十本の指では足りないか。
「仕事中何度も探してもらってごめんね。助かるよ」
「これも仕事です」
「くくっ、あんなギャラリー出来ちゃってたら、杏ちゃんも大変だね。さすが巷で話題の美人司書さん」
誰のせいだ、誰の。
周囲の噂話から知識を得たらしい無駄話は聞かなかったことにする。階段を早足で上っていく私に、難なくついてくるこいつに苛つきを覚えた。
それにしても、と心で呟き、手元のレシートを再び眺める。
蔵書検索機から出されたそれには、あまり貸し出されることのないコアな内容の参考図書が記されていた。
奴が所望する書籍は、こういった一般人の使い道に首を傾げる内容の物が半数以上を占めている。
「え、と。ああ、あった」
書架を探しだし、折り目正しく並べられた背表紙を指で撫でていく。要領よく見つけだした目的のタイトルに、「さすが。早いね」と感嘆の声が上がった。
「高いね。届く? 取ろうか」
「ううん。平気」
辺りに視線を馳せるも、いつもならあるはずの踏み台が見当たらなかった。それでも、自分の身長でも届かない訳じゃない。
奴の瞳が気遣わしげなものに変わるよりも先に、私はすっとつま先立ちで腕を伸ばした。きっちりとしまい込まれた書籍たち。隙間に指を潜り込ませ関節を曲げると、背表紙がゆっくりと手の内に収まった。
人に頼る機会を減らしてくれる、長身の有り難みが身に染みる。
「はい。この書籍で間違いないで――、」
「ッ、杏ちゃん!!」
差し出した書籍が、思わぬ衝撃で空を舞った。
肩を抱え込まれ、広い温もりに顔を押しつけられる。何が起こったのか分からず混乱したが、私は咄嗟に頭上にある顔を睨み上げた。
「っ、あんた、突然何……っ!」
「はぁ……無理そうならそう言わなきゃ」
「は!?」
「本、上から落ちそうだったよ」
諭すような口調に、そろりと見上げた視線。
伸ばされた腕の先には、書籍の抜け跡を押さえつける手があった。無理に抜き取ったせいか、書架からはみ出た他の本が危ういバランスで斜めに傾いている。
最悪だ。
バツの悪い状況に、私はわめき散らしていた口を噤むのがやっとだった。
もはや、庇うように腰に回された手に文句を言うのもはばかられる。奴の影に包まれたまま、落ちてきたのは戒めの言葉だった。
「怪我したらどうするの」
「いつも、取ってる高さだから」
「簡単に取れる本の厚みじゃないでしょ。気を付けないと」
「……わかったってば」
いちいち真面目腐って言うなっての。悔しさが滲む顔を何とか整えようと、きついくらいに瞼を瞑る。
頭上に僅かに触れた奴の吐息に動揺が走るのを必死に抑えた。平常心。心の中で独りごちる。
「ここは、利用者はひとりで立ち入り禁止?」
「……閲覧後、カウンターに一声かけてくれれば」
「そっか」
言うなり、奴は何事もなかったかのように私の身体を解いた。床に落としてしまっていた目的の書籍をひょいと拾い、ふっと微笑みが向けられる。
「杏ちゃん、いい匂いする。もうちょっと支えておけば良かったかな」
「っん、な……!」
「じゃあ、少し見てくね。わざわざありがとう」
不本意だ。でも助かった。
不規則になっていた呼吸が落ち着きを取り戻していく。穏やかな笑顔を向けられ、私は言い返したい衝動を胸にしまった。
持ち場に戻ろう。そう思っているはずなのに、足がなかなか動こうとしない。胸に噎せ返りそうな焦燥感がくすぶる。
「あの……!」
咄嗟に、目の前の服の裾を掴んでいた。
こんなこと、本当は言ってやりたくなんてないけれど。
「ありがとう。庇ってくれて」
よし。言った。やけに重かった言葉を何とか口に出し終え、私は詰まっていた息をほうっと吐き出した。
「それだけ。ごゆっくり」
早口で言い終えた私は、掴んでいた服の裾をそっと外し、書庫を後にする。
背中の向こうで奴がどんな表情を浮かべているのかなんて、確認する間もなかった。
先輩の中では比較的仲良くさせてもらっている今野(こんの)さんが、口を緩ませながらカウンターに戻ってきた。同時に中吉ちゃんが、「目の保養が来た! 行ってきまーす!」と書籍を携えて飛び出していく。
ここ最近幾度となく目にしてきた光景に、私は軽く肩を竦めた。
最近、誰かさんがM大図書館にちょくちょく出現するようになった。
恐らく、奈緒と栄二さんの会話を耳にしたのだろう。貸出カードの作り方を尋ねてきた奴を目にしたときは、一瞬ここが職場ということを忘れるところだった。
「それでそれでっ! あのイケメンさんはずばり! 小野寺さんの彼氏サンなわけですよねっ!?」
迫りくる中吉ちゃんの期待に満ちた瞳。その傍らで作業していた今野さんも、同調するようにうんうんと頷く。
「いやー、私も妙だと思っていたのよ。小野寺さんくらいの美人さんがフリーなはずがないってさぁ」
「今野さんも中吉ちゃんも誤解です。奴……じゃなく、あの人はただの知り合いってだけで、彼氏とかそういうのじゃ」
「事務の子たちにも教えてあげなくちゃ! 小野寺さんにつ・い・に! 発覚した彼氏は超イケメン長身イケメン!」
幸せのお裾分けとばかりに飛び出していった彼女を呆然と見送る。
四十代前半の今野さんは、苦笑しながら「若い子はこの手の話が大好物だもんね~」と私の肩に手を乗せた。「というか、イケメンて二回言ってたね」
中吉ちゃんの蜘蛛の巣を張り巡らせたような情報網は、午後の図書館来場数に確実に影響を与えることになった。
「なあなあ、お前が聞いて来いよ」「小野寺さん、特定のメンズができたって本当ですかってか?」好奇の視線を向けてくる資料集め中の学生たち。
「わかんないよねー、あんなつんけん女のどこがいいんだか」「ふふっ、あんた聞こえるって」「でもあのロングヘア―は憧れるなぁ。ストイックさが滲み出てるよね」褒めてるのかけなしてるのかわからない空気を漂わせる大学事務の子たち。
「いやあ、孤高の美人司書さんに恋人ができたと聞いたもんでね」しまいには私を愛想がないと毛嫌いしているセクハラ教授まで。
もはや否定する気も失せた。
噂に振り回されている知人以下の人影をまるっと無視し、私は通常業務を粛々と進める。勝手に尾ひれを付けて楽しむが良い。暇人どもが。
「すみません。この本をお借りしたいんですが」
利用者から差し出される、蔵書検索のレシート。所蔵図書の案内もまた立派な司書の業務だ。
例えその利用者が、本日の騒動の元凶だとしても。
「この参考図書は三階の書庫ですね。お持ちします」
「良ければついていっても?」
「……どうぞ。こちらです」
満足げににこり、と笑みを浮かべた奴に、遠巻きから女子学生の黄色い悲鳴が上がる。
すかさず主任が彼女らの注意に腰を上げたが、奴はといえばまるで興味がない様子だった。
「……まだ居たんだ。午前で帰ったんだと思ってた」
人気のない通路に入ると同時に、私はちろりと奴に視線を遣った。
店で働くときとは違う、白肌に映える紺色の軽めなカットソーにジーパンというラフスタイル。シンプルな時計がはめられた涼しげな手首に、ふと指元までを盗み見た。
指輪はない。不特定多数の彼女たちには、十本の指では足りないか。
「仕事中何度も探してもらってごめんね。助かるよ」
「これも仕事です」
「くくっ、あんなギャラリー出来ちゃってたら、杏ちゃんも大変だね。さすが巷で話題の美人司書さん」
誰のせいだ、誰の。
周囲の噂話から知識を得たらしい無駄話は聞かなかったことにする。階段を早足で上っていく私に、難なくついてくるこいつに苛つきを覚えた。
それにしても、と心で呟き、手元のレシートを再び眺める。
蔵書検索機から出されたそれには、あまり貸し出されることのないコアな内容の参考図書が記されていた。
奴が所望する書籍は、こういった一般人の使い道に首を傾げる内容の物が半数以上を占めている。
「え、と。ああ、あった」
書架を探しだし、折り目正しく並べられた背表紙を指で撫でていく。要領よく見つけだした目的のタイトルに、「さすが。早いね」と感嘆の声が上がった。
「高いね。届く? 取ろうか」
「ううん。平気」
辺りに視線を馳せるも、いつもならあるはずの踏み台が見当たらなかった。それでも、自分の身長でも届かない訳じゃない。
奴の瞳が気遣わしげなものに変わるよりも先に、私はすっとつま先立ちで腕を伸ばした。きっちりとしまい込まれた書籍たち。隙間に指を潜り込ませ関節を曲げると、背表紙がゆっくりと手の内に収まった。
人に頼る機会を減らしてくれる、長身の有り難みが身に染みる。
「はい。この書籍で間違いないで――、」
「ッ、杏ちゃん!!」
差し出した書籍が、思わぬ衝撃で空を舞った。
肩を抱え込まれ、広い温もりに顔を押しつけられる。何が起こったのか分からず混乱したが、私は咄嗟に頭上にある顔を睨み上げた。
「っ、あんた、突然何……っ!」
「はぁ……無理そうならそう言わなきゃ」
「は!?」
「本、上から落ちそうだったよ」
諭すような口調に、そろりと見上げた視線。
伸ばされた腕の先には、書籍の抜け跡を押さえつける手があった。無理に抜き取ったせいか、書架からはみ出た他の本が危ういバランスで斜めに傾いている。
最悪だ。
バツの悪い状況に、私はわめき散らしていた口を噤むのがやっとだった。
もはや、庇うように腰に回された手に文句を言うのもはばかられる。奴の影に包まれたまま、落ちてきたのは戒めの言葉だった。
「怪我したらどうするの」
「いつも、取ってる高さだから」
「簡単に取れる本の厚みじゃないでしょ。気を付けないと」
「……わかったってば」
いちいち真面目腐って言うなっての。悔しさが滲む顔を何とか整えようと、きついくらいに瞼を瞑る。
頭上に僅かに触れた奴の吐息に動揺が走るのを必死に抑えた。平常心。心の中で独りごちる。
「ここは、利用者はひとりで立ち入り禁止?」
「……閲覧後、カウンターに一声かけてくれれば」
「そっか」
言うなり、奴は何事もなかったかのように私の身体を解いた。床に落としてしまっていた目的の書籍をひょいと拾い、ふっと微笑みが向けられる。
「杏ちゃん、いい匂いする。もうちょっと支えておけば良かったかな」
「っん、な……!」
「じゃあ、少し見てくね。わざわざありがとう」
不本意だ。でも助かった。
不規則になっていた呼吸が落ち着きを取り戻していく。穏やかな笑顔を向けられ、私は言い返したい衝動を胸にしまった。
持ち場に戻ろう。そう思っているはずなのに、足がなかなか動こうとしない。胸に噎せ返りそうな焦燥感がくすぶる。
「あの……!」
咄嗟に、目の前の服の裾を掴んでいた。
こんなこと、本当は言ってやりたくなんてないけれど。
「ありがとう。庇ってくれて」
よし。言った。やけに重かった言葉を何とか口に出し終え、私は詰まっていた息をほうっと吐き出した。
「それだけ。ごゆっくり」
早口で言い終えた私は、掴んでいた服の裾をそっと外し、書庫を後にする。
背中の向こうで奴がどんな表情を浮かべているのかなんて、確認する間もなかった。
0
お気に入りに追加
35
あなたにおすすめの小説


溺愛彼氏は消防士!?
すずなり。
恋愛
彼氏から突然言われた言葉。
「別れよう。」
その言葉はちゃんと受け取ったけど、飲み込むことができない私は友達を呼び出してやけ酒を飲んだ。
飲み過ぎた帰り、イケメン消防士さんに助けられて・・・新しい恋が始まっていく。
「男ならキスの先をは期待させないとな。」
「俺とこの先・・・してみない?」
「もっと・・・甘い声を聞かせて・・?」
私の身は持つの!?
※お話は全て想像の世界になります。現実世界と何ら関係はありません。
※コメントや乾燥を受け付けることはできません。メンタルが薄氷なもので・・・すみません。

婚約者に消えろと言われたので湖に飛び込んだら、気づけば三年が経っていました。
束原ミヤコ
恋愛
公爵令嬢シャロンは、王太子オリバーの婚約者に選ばれてから、厳しい王妃教育に耐えていた。
だが、十六歳になり貴族学園に入学すると、オリバーはすでに子爵令嬢エミリアと浮気をしていた。
そしてある冬のこと。オリバーに「私の為に消えろ」というような意味のことを告げられる。
全てを諦めたシャロンは、精霊の湖と呼ばれている学園の裏庭にある湖に飛び込んだ。
気づくと、見知らぬ場所に寝かされていた。
そこにはかつて、病弱で体の小さかった辺境伯家の息子アダムがいた。
すっかり立派になったアダムは「あれから三年、君は目覚めなかった」と言った――。
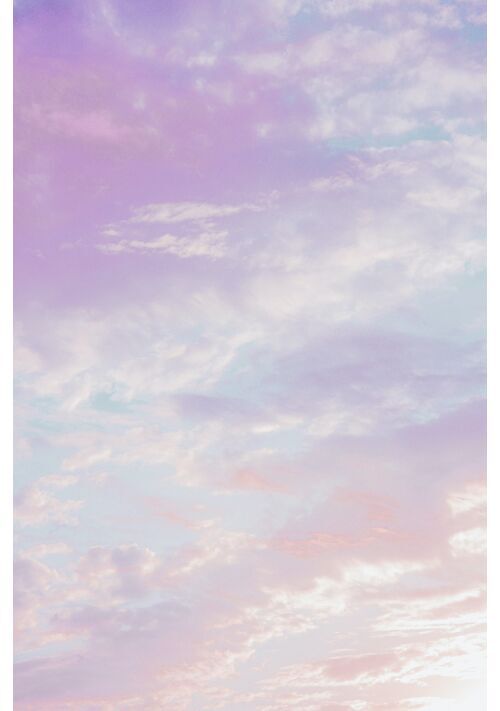
極道に大切に飼われた、お姫様
真木
恋愛
珈涼は父の組のため、生粋の極道、月岡に大切に飼われるようにして暮らすことになる。憧れていた月岡に甲斐甲斐しく世話を焼かれるのも、教え込まれるように夜ごと結ばれるのも、珈涼はただ恐ろしくて殻にこもっていく。繊細で怖がりな少女と、愛情の伝え方が下手な極道の、すれ違いラブストーリー。

妻のち愛人。
ひろか
恋愛
五つ下のエンリは、幼馴染から夫になった。
「ねーねー、ロナぁー」
甘えん坊なエンリは子供の頃から私の後をついてまわり、結婚してからも後をついてまわり、無いはずの尻尾をブンブン振るワンコのような夫。
そんな結婚生活が四ヶ月たった私の誕生日、目の前に突きつけられたのは離縁書だった。

私に告白してきたはずの先輩が、私の友人とキスをしてました。黙って退散して食事をしていたら、ハイスペックなイケメン彼氏ができちゃったのですが。
石河 翠
恋愛
飲み会の最中に席を立った主人公。化粧室に向かった彼女は、自分に告白してきた先輩と自分の友人がキスをしている現場を目撃する。
自分への告白は、何だったのか。あまりの出来事に衝撃を受けた彼女は、そのまま行きつけの喫茶店に退散する。
そこでやけ食いをする予定が、美味しいものに満足してご機嫌に。ちょっとしてネタとして先ほどのできごとを話したところ、ずっと片想いをしていた相手に押し倒されて……。
好きなひとは高嶺の花だからと諦めつつそばにいたい主人公と、アピールし過ぎているせいで冗談だと思われている愛が重たいヒーローの恋物語。
この作品は、小説家になろう及びエブリスタでも投稿しております。
扉絵は、写真ACよりチョコラテさまの作品をお借りしております。

エリート警察官の溺愛は甘く切ない
日下奈緒
恋愛
親が警察官の紗良は、30歳にもなって独身なんてと親に責められる。
両親の勧めで、警察官とお見合いする事になったのだが、それは跡継ぎを産んで欲しいという、政略結婚で⁉

王命を忘れた恋
須木 水夏
恋愛
『君はあの子よりも強いから』
そう言って貴方は私を見ることなく、この関係性を終わらせた。
強くいなければ、貴方のそばにいれなかったのに?貴方のそばにいる為に強くいたのに?
そんな痛む心を隠し。ユリアーナはただ静かに微笑むと、承知を告げた。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















