お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

となりのソータロー
daisysacky
ライト文芸
ある日、転校生が宗太郎のクラスにやって来る。
彼は、子供の頃に遊びに行っていた、お化け屋敷で見かけた…
という噂を聞く。
そこは、ある事件のあった廃屋だった~

元おっさんの俺、公爵家嫡男に転生~普通にしてるだけなのに、次々と問題が降りかかってくる~
おとら@ 書籍発売中
ファンタジー
アルカディア王国の公爵家嫡男であるアレク(十六歳)はある日突然、前触れもなく前世の記憶を蘇らせる。
どうやら、それまでの自分はグータラ生活を送っていて、ろくでもない評判のようだ。
そんな中、アラフォー社畜だった前世の記憶が蘇り混乱しつつも、今の生活に慣れようとするが……。
その行動は以前とは違く見え、色々と勘違いをされる羽目に。
その結果、様々な女性に迫られることになる。
元婚約者にしてツンデレ王女、専属メイドのお調子者エルフ、決闘を仕掛けてくるクーデレ竜人姫、世話をすることなったドジっ子犬耳娘など……。
「ハーレムは嫌だァァァァ! どうしてこうなった!?」
今日も、そんな彼の悲鳴が響き渡る。

王子様な彼
nonnbirihimawari
ライト文芸
小学校のときからの腐れ縁、成瀬隆太郎。
――みおはおれのお姫さまだ。彼が言ったこの言葉がこの関係の始まり。
さてさて、王子様とお姫様の関係は?

みんなみたいに上手に生きられない君へ
春音優月
ライト文芸
特別なことなんて何もいらないし、望まない。
みんなみたいに「普通」に生きていきたいだけなのに、私は、小さな頃からみんなみたいに上手に生きられないダメな人間だった。
どうしたら、みんなみたいに上手に生きられますか……?
一言でいい、嘘でもいい。
「がんばったね」
「大丈夫、そのままの君でいいんだよ」
誰かにそう言ってもらいたい、認めてもらいたいだけなのに。
私も、彼も、彼女も、それから君も、
みんなみたいに上手に生きられない。
「普通に生きる」って、簡単なようで、実はすごく難しいね。
2020.04.30〜2020.05.15 完結
どこにでもいる普通の高校生、であろうとする女の子と男の子の物語です。
絵:子兎。さま

美人に告白されたがまたいつもの嫌がらせかと思ったので適当にOKした
亜桜黄身
BL
俺の学校では俺に付き合ってほしいと言う罰ゲームが流行ってる。
カースト底辺の卑屈くんがカースト頂点の強気ド美人敬語攻めと付き合う話。
(悪役モブ♀が出てきます)
(他サイトに2021年〜掲載済)
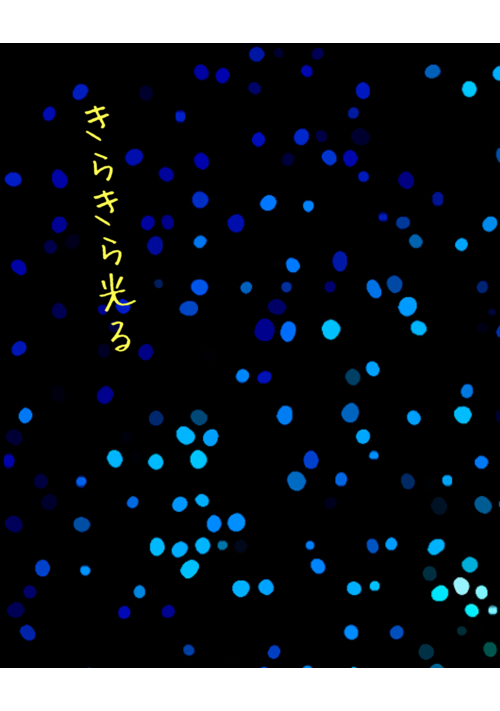
きらきら光る
鈴谷なつ
ライト文芸
「作りものの人形みたいで一緒にいて疲れるよ」
結婚の約束までしていた恋人の健にそう言われてから、自分という存在が分からなくなってしまった愛美。
「作りもの」の自分に苦しむ愛美が、自分を少しだけ好きになっていく。そんな物語です。

イケメン彼氏は年上消防士!鍛え上げられた体は、夜の体力まで別物!?
すずなり。
恋愛
私が働く食堂にやってくる消防士さんたち。
翔馬「俺、チャーハン。」
宏斗「俺もー。」
航平「俺、から揚げつけてー。」
優弥「俺はスープ付き。」
みんなガタイがよく、男前。
ひなた「はーいっ。ちょっと待ってくださいねーっ。」
慌ただしい昼時を過ぎると、私の仕事は終わる。
終わった後、私は行かなきゃいけないところがある。
ひなた「すみませーん、子供のお迎えにきましたー。」
保育園に迎えに行かなきゃいけない子、『太陽』。
私は子供と一緒に・・・暮らしてる。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
翔馬「おいおい嘘だろ?」
宏斗「子供・・・いたんだ・・。」
航平「いくつん時の子だよ・・・・。」
優弥「マジか・・・。」
消防署で開かれたお祭りに連れて行った太陽。
太陽の存在を知った一人の消防士さんが・・・私に言った。
「俺は太陽がいてもいい。・・・太陽の『パパ』になる。」
「俺はひなたが好きだ。・・・絶対振り向かせるから覚悟しとけよ?」
※お話に出てくる内容は、全て想像の世界です。現実世界とは何ら関係ありません。
※感想やコメントは受け付けることができません。
メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
言葉も足りませんが読んでいただけたら幸いです。
楽しんでいただけたら嬉しく思います。

実力を隠し「例え長男でも無能に家は継がせん。他家に養子に出す」と親父殿に言われたところまでは計算通りだったが、まさかハーレム生活になるとは
竹井ゴールド
ライト文芸
日本国内トップ5に入る異能力者の名家、東条院。
その宗家本流の嫡子に生まれた東条院青夜は子供の頃に実母に「16歳までに東条院の家を出ないと命を落とす事になる」と予言され、無能を演じ続け、父親や後妻、異母弟や異母妹、親族や許嫁に馬鹿にされながらも、念願適って中学卒業の春休みに東条院家から田中家に養子に出された。
青夜は4月が誕生日なのでギリギリ16歳までに家を出た訳だが。
その後がよろしくない。
青夜を引き取った田中家の義父、一狼は53歳ながら若い妻を持ち、4人の娘の父親でもあったからだ。
妻、21歳、一狼の8人目の妻、愛。
長女、25歳、皇宮警察の異能力部隊所属、弥生。
次女、22歳、田中流空手道場の師範代、葉月。
三女、19歳、離婚したフランス系アメリカ人の3人目の妻が産んだハーフ、アンジェリカ。
四女、17歳、死別した4人目の妻が産んだ中国系ハーフ、シャンリー。
この5人とも青夜は家族となり、
・・・何これ? 少し想定外なんだけど。
【2023/3/23、24hポイント26万4600pt突破】
【2023/7/11、累計ポイント550万pt突破】
【2023/6/5、お気に入り数2130突破】
【アルファポリスのみの投稿です】
【第6回ライト文芸大賞、22万7046pt、2位】
【2023/6/30、メールが来て出版申請、8/1、慰めメール】
【未完】
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















