お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

絵の具と切符とペンギンと【短編・完結済み】
草壁なつ帆
ファンタジー
少年と女の子の出会いの物語。彼女は不思議な絵を描くし、連れている相棒も不思議生物だった。飛び出した二人の冒険は絆と小さな夢をはぐくむ。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
始まりは創造神の手先の不器用さ……。
『神と神人と人による大テーマ』
他タイトルの短編・長編小説が、歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編小説「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。

フェンディー海峡【読み切り・創作神話】
草壁なつ帆
ファンタジー
不漁により移動を余儀なくされた民族がある。その中でメイという少年は、夜中の海辺で人魚と出会う。
ひとりであると寂しそうにメイに寄り添う彼女だが。
「あなたも行ってしまうのね」
人魚との別れ。そしてこの出会いにより、メイと民族の未来は……。
(((小説家になろうとアルファポリスで投稿しています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく
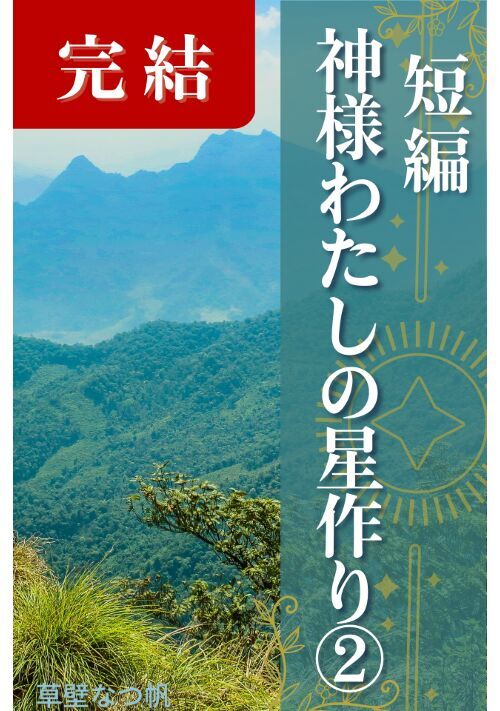
神様わたしの星作り_chapter Two【短編・完結済み】
草壁なつ帆
ファンタジー
神様わたしの星作り chapter One の続きの物語。
ここは私が見守る砂地の星。ゾンビさんたちが暮らす小さな楽園です。
穏やかな暮らしは平和だけど少しつまらない。それに私が作ろうとしたのって、ゾンビの惑星でしたっけ?
では、神様らしく滅ぼそうではありませんか!
その決断は実行されるわけですが。予期せぬ自体もおこりまして……。
さくっと読める文字量です。ぜひお目を通しください。
(((小説家になろう、アルファポリスに投稿しています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。

王子を身籠りました
青の雀
恋愛
婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。
王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。
再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

秘密の娘スピカの夢~黄金を示す羅針盤のありか【短編・完結済み】
草壁なつ帆
ファンタジー
怪盗レオナルドが狙うのは、黄金を示す『アルゴ船の羅針盤』だった。
慣れた手で屋敷に侵入すると、そこには色素の薄い少女の姿が。
少女は怪盗を見るなり別人の名を口にする。
「おかえり、アンジェ」
レオナルドはこの屋敷で思いもしない体験をする。
(((小説家になろう、アルファポリスに上げています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。

ユークとリオの黄金の羊【読み切り・創作神話】
草壁なつ帆
ファンタジー
ユークとリオは自分たちのお母さんを知りたかった。
ある日出会った天使は悪く笑ってこのように言う。
「高価なものと欲しいものを交換してやろう」
集落で最も高価な黄金の羊。それと交換で二人が得たものは……。
(((小説家になろうとアルファポリスで投稿しています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















