お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

絵の具と切符とペンギンと【短編・完結済み】
草壁なつ帆
ファンタジー
少年と女の子の出会いの物語。彼女は不思議な絵を描くし、連れている相棒も不思議生物だった。飛び出した二人の冒険は絆と小さな夢をはぐくむ。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
始まりは創造神の手先の不器用さ……。
『神と神人と人による大テーマ』
他タイトルの短編・長編小説が、歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編小説「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。

フェンディー海峡【読み切り・創作神話】
草壁なつ帆
ファンタジー
不漁により移動を余儀なくされた民族がある。その中でメイという少年は、夜中の海辺で人魚と出会う。
ひとりであると寂しそうにメイに寄り添う彼女だが。
「あなたも行ってしまうのね」
人魚との別れ。そしてこの出会いにより、メイと民族の未来は……。
(((小説家になろうとアルファポリスで投稿しています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。
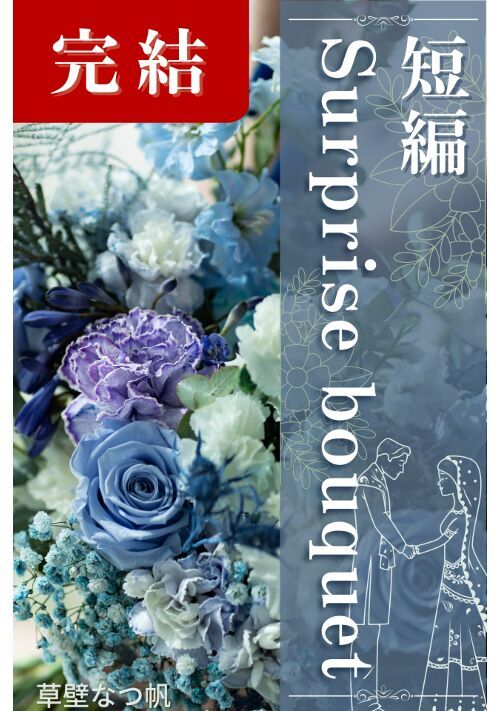
Surprise bouquet【短編・スピンオフ】
草壁なつ帆
ファンタジー
長編小説『クランクビスト』より2年前。メルチ王国リュンヒン王子と、婚約者セシリア姫によるラブロマンス。
『episode.サプライズ・ブーケ』クランクビストよりスピンオフ短編です。
「サプライズが欲しい」とセシリアに頼まれたリュンヒン。彼女の誕生日を前にプレゼントの内容に迷っていた。
いつも彼女を喜ばす術を持っていたリュンヒンだが、彼の完璧以上のサプライズはいったいどんな贈り物になるのか?
(((小説家になろう、アルファポリスに上げています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。

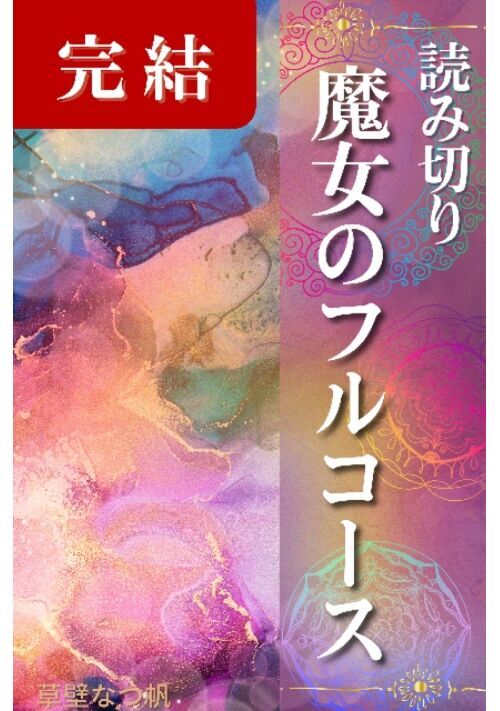
魔女のフルコース【読み切り•創作神話】
草壁なつ帆
ファンタジー
光る石を辿ればとあるレストランに辿り着く。注文は何でも揃えられるというシェフ『ミザリー』の店だ。摩訶不思議な料理を味わいたくば、厨房の方もぜひ覗きにいらしてください。きっとシェフも喜びますから……。
(((小説家になろうとアルファポリスで投稿しています。
*+:。.。☆°。⋆⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝。.。:+*
シリーズ【トマトの惑星】
草壁なつ帆が書く、神と神人と人による大テーマ。他タイトルの短編・長編小説が歴史絵巻のように繋がる物語です。
シリーズの開幕となる短編「神様わたしの星作りchapter_One」をはじめとし、読みごたえのある長編小説も充実(*´-`)あらすじまとめを作成しました!気になった方は是非ご確認下さい。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ウブな政略妻は、ケダモノ御曹司の執愛に堕とされる
Adria
恋愛
旧題:紳士だと思っていた初恋の人は私への恋心を拗らせた執着系ドSなケダモノでした
ある日、父から持ちかけられた政略結婚の相手は、学生時代からずっと好きだった初恋の人だった。
でも彼は来る縁談の全てを断っている。初恋を実らせたい私は副社長である彼の秘書として働くことを決めた。けれど、何の進展もない日々が過ぎていく。だが、ある日会社に忘れ物をして、それを取りに会社に戻ったことから私たちの関係は急速に変わっていった。
彼を知れば知るほどに、彼が私への恋心を拗らせていることを知って戸惑う反面嬉しさもあり、私への執着を隠さない彼のペースに翻弄されていく……。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















