23 / 39
帰路
しおりを挟む
王前試合が終わると、ブラッディフッドは王妃エラと王妃エラの自室にある魔法の鏡の前に居た。
魔法の鏡は、ヴィルドンゲン国との通信手段に使われている。
「女王様、この度の姉の件、重ね重ね、ありがとうございました。」
「いえ、無事で何よりでした。で、アナスタシアは?」
「旅立ちました。」
「そうですか。冒険者に。」
「それで、ブラッディフッドが話したい事があると。」
「ブラッディフッドが?」
「久しぶりだな、マルガリータ。」
「お久しぶりです、ブラッディフッド。」
「大したことではないのだが、そのう、ドクの件は、私が頼んだ事なので、あいつに、あまり言ってやるな。」
「ご安心をブラッディフッド。私がドクに強く言える訳ありませんので。」
「ならいいが。」
「私からもお願いがあるのですが?」
「なんだ?弟子が世話になったんだ、何でも言ってくれ。」
「生き残った魔術師協会の面々を見逃して頂けませんか?」
「なんだ、そんな事か。関わった奴らは処刑されたんだろ?」
「ええ、全員。」
「なら、問題ないよ。」
「ありがとうございます。」
「いや、礼を言うのは、こちらの方さ。」
「お二人とも、迷惑をかけたのは、私の姉ですから、礼をいうのは私が。」
「姉は死んだ事にしとくんじゃなかったのか?」
ブラッディフッドが突っ込んだ。
「何の事でしょう?」
王妃エラは、悪戯っぽく笑った。
「ブラッディフッド、それでお聞きしたいことが。」
女王マルガリータが聞いた。
「アナの事か?」
「ええ、今回、アナスタシアが狙われた経緯が私にはわかりません。歌姫アムールと同等の魔力を持つなんて話が一体、どこから生まれたのか。」
実際にアナスタシアに強大な魔力は無かった。なぜ魔術師協会が暴走したのかが、女王マルガリータには判らなかった。
「全ては誤解と噂話から始まったに過ぎない。アナがアムールと同じ能力を持っているらしい。ブラッディフッドの弟子がアムールと同じ能力を持っているらしい。ブラッディフッドの弟子が、アムールと同等の魔力を持っているらしいとな。」
「なるほど、普段であれば、ただの噂話。魔術師協会も動くことは無かったでしょうが、ブラッディフッドの名前で信憑性が格段に上がったということでしょうね。」
「だろうな。」
「待ってください。姉にそのような能力はありませんよ?」
「身をもって体験しただろう?」
「えっ・・・。」
「アナには言葉に力があると言ってあるが、そんな中途半端な能力じゃあない。存在自体が能力だからな。」
「なるほど、魔力も必要ないという訳ですね。」
「そうだな。」
「姉は生まれ持っていたのですか?能力を?」
「いや、後天的なものだな。」
「一体いつ・・・。」
「死んだときだろうな。」
「は?」
「やはり死んでいたのですね。」
「本人には言っていないが、地霊ノームが言うには、そう言うことらしい。」
「え、でも・・・姉は・・・。」
「完全に死んだという訳じゃあないだろう、恐らく死にかけと言う感じだろうな。私が見つけた時には、既に生き返った後だろう。」
「誰が・・・一体・・・。」
「そのような力、恐らく人ではないのでしょう。ブラッディフッドは、検討が?」
「まだ確信が持ててない。」
「そうですか。」
「ブラッディフッド、姉はもう、人ではないのですか?」
「多分な。」
「それで婚約破棄させるようにもっていったのですね?」
「ああ、悪いな。普通の人のままであれば、子爵夫人になれるんだ、私も勧めただろう。」
「そうですか、姉はもう。」
「まあ、それ程気にするまでもないさ。エラの姉であることには変わりないんだからな。」
「そうですね。」
「しかし、魔力は無いにしても、その能力が狙われる可能性があるのではないですか?」
女王マルガリータが心配になって聞いた。
「見えない能力であるし、本人の性格もあってな。信じて貰えないのだろうな。試しに中級の冒険者パーティーに預けてみたのだが、直ぐにクビになったようだし。」
「何故ですか?姉は一人でも、かなりの強さがあると思うのですが?」
実際、自らが負けたから、その強さが身に染みてわかっていた。
「パーティーの中に居て、あいつが前に出ると思うか?」
「・・・。」
職的には、舞踏家は前衛職。
しかし、アナスタシアは、冒険者パーティー内で前に出るような事はしない。己の言葉に力があると信じているから、貴族らしく振舞っているだけだ。
最底辺のレダ達と一緒の時は、そういう訳にはいかず、指示したり、もしもに備えたりするわけだが。
「プライドが高く、我儘な性格も、能力を隠す役に立っているようですね。」
「ま、まあな・・・。いずれにしても、カイン達は葬った。今後はあいつに手を出そうなんて冒険者は居なくなるだろう。」
「ブラッディフッド、姉の為に、ありがとうございます。」
「気にするな。私の弟子なんだからな、あいつは。」
師匠や妹が、自身の話をしているなんて、露知らず、アナスタシアは一路、レダ達のいる町を目指していた。
レダ達の居る町は、歩いていけば一週間以上もかかる。
アナスタシアが運ばれる時は、馬車を使っていたが。一日も早く合流はしたいが、馬を買うとなると結構な金額が掛かるわけで。
「まあいいわ、レダ達が、あの町から動くわけがないし。」
そう決めつけて、歩いていくことに決めた。
サンドリヨン国を出ると、いきなり野盗に襲われた。
「娼婦か、俺たちの相手をしてくれねえか?」
「3人いっぺんにな、うひひひひ。」
こういう奴らは、殺しても殺しても居なくならない。一体とこから湧き出ているのだろうか?
そんな事を思いつつも、戦闘態勢に入ったのだが。
「お前らみたいな屑には地獄がふさわしい。」
そんな事を言いながら、まるで主役が登場するかの如く派手に青年が登場してきた。腰にショートソードを持つ冒険者が。
「なんだ、お前は?」
「恰好つけてんじゃねえよ。」
一体いつ、剣を抜いたのか。
いちゃもんをつけた二人の野盗が、死んでその場に倒れた。
「ひ、ひいいいい。」
残った一人が逃げようとしたが、両足を切断され、ゴキブリが這うように、ガサガサとしていた。
「おい、俺の名前を言ってみろ?」
冒険者は、ゴキブリの頬が切れるくらいの所にショートソードを突き刺していった。
「は、は・・・、た、助けて・・・。」
「俺の事を知っていたらな。」
「あ、あんたあれだ。リスキーだ。」
「正解。」
そう言ってゴキブリの首を落とした。
「酷いわね、助けるんじゃなかったの?」
アナスタシアが言った。
「助けただろ?苦しみからな。」
「・・・。」
「それより、礼くらい言ってもいいんじゃないのか?」
「余計なことをしたのは、そっちでしょ?礼をいう筋合いはないわ。」
「まったく、ブラッディフッドの弟子ってのは、傲慢な奴なんだな。」
「私を知ってるの?」
「今、冒険者で、お前を知らなかったら、命が要らない奴だろうな。」
「あっそ。」
自分が有名なわけでなく、お師匠様の弟子と言うことで有名らしいので、どうでもいいやと思った。
「お前も冒険者なんだよな?」
「そうよ。」
「じゃあ俺の事を知ってるだろ?」
「リスキー?」
「そうだ。」
「その恰好からして、冒険者なんでしょ?」
「ちょっとまて、お前、リスキーの名前を知らずに冒険者なんてやってるのか?」
「知らないわよ、あんたの事なんて・・・。」
「ま、マジか・・・。くっ・・・。ちなみに級持ちの冒険者は、何人くらい知ってる?」
「級持ち?んー・・・、死んだカイン達と・・・、C級のロビン達くらい。」
「は?なんでC級程度の奴の名前を憶えてるんだ。」
「ふっ、いつか見返してやる為に決まってるじゃない。」
「そ、そうか・・・。S級冒険者の事は知らないんだな。」
「ええ、興味ないし。あっ・・・。」
「どうした?」
「あんた級持ちなの?」
「ああ、そうだ。」
「そっ・・・、じゃあねっ」
「はあ?いきなりなんだ?おい。」
「お師匠様から級持ちにはついていくなって言われてるのよ。」
「なんだ、それは・・・。お前の事を助けたんだぞ俺は?」
「それは、余計な事でしょ?私がブラッディフッドの弟子と判ってたんでしょ?」
「まあな。だが、お前が強いなんて話は聞いたことないがな。」
「ブラッディフッドの弟子が、野盗ごときに負けると?」
「まあ、そうは思わない。が、恩くらい売れるんじゃないかなとは思ったけどな。」
「ふっ、やっぱりね。私を利用しようとしてる輩ね。」
「違うっ。いいか、今、冒険者の間では、ブラッディフッドの弟子に関わるなっていう事になってるんだ。それを態々、関わってるんだ。」
「なるほど、そうまでして私のお師匠様に近づきたいのね。」
「恐ろしい事をいうな。お前に恩を売りたかっただけだ。」
「私に?」
「ああ、凄い能力持っているんだろ?」
「ははーん。私を魔石にしようと企んでるわね。」
「ぶっちゃけ、俺より魔力ないだろ、お前・・・。」
「うっさいわねっ!」
「お前の歌姫アムールの超縮小版の能力に興味がある。」
「ちょ、超縮小版だとっ!」
「C級の奴らのバーティーをクビになったそうだな。」
「クビじゃないわよ!合わなかっただけよ。」
「ああ、そいつは大事だ。合う合わないわ。」
「ちょっと待って、あなた級持ちの冒険者って言ってたわよね?」
「ああ、そうだ。」
「仲間は?」
級持ちの冒険者と言えばパーティーが、基本であり、自然とそんな質問が口から出た。
「そんなのは居ない。」
「なんだ、ぼっちか。」
「ぼっち言うな!お前だって一緒だろうが?」
「はあ?一緒にしないでくれる?私は今から仲間の元へ向かってるのよ。」
「な、仲間がいるのか?」
「ええ。残念ね、他を当たってくれる?」
「おかしいな、俺が聞いた話では、性格に難ありで、どこのパーティーにも属していないと・・・。」
「ちょっと!誰の性格が悪いって?」
「ちなみに仲間と何処で待ち合わせてるんだ?」
「チーズだけど?」
「チーズって、何もない町だろ?」
「何もないわけではないでしょ?」
「冒険者にとって何もない町ってことさ。仲間はどのくらいのランクだ?」
「級なしだけど?」
「級なしかよ・・・俺に乗り換えた方がいいぞ?そいつらと居ても将来性がないだろうに。」
「じゃあ、聞くけど、私の能力で何を倒したいわけ?」
「うっ・・・。」
世界に大した大物がいるわけでもなく、上位の冒険者のランキングが微動だにしない昨今、何か倒す相手が居るかと言うと、そんな者は存在していない。
「そりゃあ、今は居ないが。ああいうものは前兆もなしに現れるからな。」
「魔王フールにでも挑戦して来たら?」
「冗談でも、そう言うことは言わない方がいい。フールにとって人間は忌むべき存在だからな。」
「詳しいのね。もしかして憧れてるとかいわないでよね。」
チーズの街の酒場の親父の顔が思い浮かんだ。
「馬鹿をいうな、俺の師匠が殺されているんだぞ、憧れる事はない。」
「・・・。恨んでいるの?」
「そう言う問題じゃあないんだが、恨んでいないと言えば嘘になるが、ブラッディフッドと一緒だ。関わらないのが一番だ。」
「仇を取ろうとか思わないの?」
「思わないね。元々、人に騙されてフール討伐に手を貸したんだ。恨むんなら、まず人からだろ?」
「もしかして、大昔にあった獣人討伐の時?」
「違う違う、そんな大昔の奴じゃあない。いいか獣人討伐ってのは、小競り合いを入れたら、結構行われている。事の発端は、全て人のせいだがな。」
「そうなんだ。」
「人は罪深く、強欲で残虐である。エイル教の一節くらい聞いたことあるだろ?」
「あるわ。」
「そういうことで、フールだけを恨むのは筋違いなのさ。」
「随分とあっさりしてるのね。」
「まあな、師匠も騙されている事に気が付いていたんだろう。俺と別れる前に、フールも人も決して恨んではいけないって言い残していったからな。」
「いい師匠だったのね。」
「まあな。まあ俺の話はこれ位にして、チーズの町まで俺が護衛してやろう。」
「要らないわよ、護衛なんて。むしろあんたと一緒の方が身の危険になるじゃないっ!」
「さっき言ったろ?俺はお前に恩が売りたいんだと。」
「それってさ、強敵が現れたら力を貸せって事?」
「まあ、その通りだ。本当は、仲間になって欲しい所だが、無理強いはできないしな。」
アナスタシアは少し思案してから言った。
「まあ、条件次第ではついてきても構わないけど?」
「条件とは?」
「私の仲間に剣を教えて欲しいの。」
「ふむ、チーズの街に居るってことだから、才能も素質もないんだろ?」
「まあね。」
「女の子か?」
「性別が何の関係があるのよ?」
「馬鹿野郎、才能も素質もない奴に教えるんだろ?性別は大事だろ?」
「じょ、女性よ。見た目は、イマイチかもしれないけど。」
「ノープロブレム。俺はフェミニストだからな。ちなみに名前は?」
「レ・・・レオーヌよ。」
「レオーヌちゃんかあ、なんか力が漲ってきた!」
「そ、そう、それはよかったわね。」
魔法の鏡は、ヴィルドンゲン国との通信手段に使われている。
「女王様、この度の姉の件、重ね重ね、ありがとうございました。」
「いえ、無事で何よりでした。で、アナスタシアは?」
「旅立ちました。」
「そうですか。冒険者に。」
「それで、ブラッディフッドが話したい事があると。」
「ブラッディフッドが?」
「久しぶりだな、マルガリータ。」
「お久しぶりです、ブラッディフッド。」
「大したことではないのだが、そのう、ドクの件は、私が頼んだ事なので、あいつに、あまり言ってやるな。」
「ご安心をブラッディフッド。私がドクに強く言える訳ありませんので。」
「ならいいが。」
「私からもお願いがあるのですが?」
「なんだ?弟子が世話になったんだ、何でも言ってくれ。」
「生き残った魔術師協会の面々を見逃して頂けませんか?」
「なんだ、そんな事か。関わった奴らは処刑されたんだろ?」
「ええ、全員。」
「なら、問題ないよ。」
「ありがとうございます。」
「いや、礼を言うのは、こちらの方さ。」
「お二人とも、迷惑をかけたのは、私の姉ですから、礼をいうのは私が。」
「姉は死んだ事にしとくんじゃなかったのか?」
ブラッディフッドが突っ込んだ。
「何の事でしょう?」
王妃エラは、悪戯っぽく笑った。
「ブラッディフッド、それでお聞きしたいことが。」
女王マルガリータが聞いた。
「アナの事か?」
「ええ、今回、アナスタシアが狙われた経緯が私にはわかりません。歌姫アムールと同等の魔力を持つなんて話が一体、どこから生まれたのか。」
実際にアナスタシアに強大な魔力は無かった。なぜ魔術師協会が暴走したのかが、女王マルガリータには判らなかった。
「全ては誤解と噂話から始まったに過ぎない。アナがアムールと同じ能力を持っているらしい。ブラッディフッドの弟子がアムールと同じ能力を持っているらしい。ブラッディフッドの弟子が、アムールと同等の魔力を持っているらしいとな。」
「なるほど、普段であれば、ただの噂話。魔術師協会も動くことは無かったでしょうが、ブラッディフッドの名前で信憑性が格段に上がったということでしょうね。」
「だろうな。」
「待ってください。姉にそのような能力はありませんよ?」
「身をもって体験しただろう?」
「えっ・・・。」
「アナには言葉に力があると言ってあるが、そんな中途半端な能力じゃあない。存在自体が能力だからな。」
「なるほど、魔力も必要ないという訳ですね。」
「そうだな。」
「姉は生まれ持っていたのですか?能力を?」
「いや、後天的なものだな。」
「一体いつ・・・。」
「死んだときだろうな。」
「は?」
「やはり死んでいたのですね。」
「本人には言っていないが、地霊ノームが言うには、そう言うことらしい。」
「え、でも・・・姉は・・・。」
「完全に死んだという訳じゃあないだろう、恐らく死にかけと言う感じだろうな。私が見つけた時には、既に生き返った後だろう。」
「誰が・・・一体・・・。」
「そのような力、恐らく人ではないのでしょう。ブラッディフッドは、検討が?」
「まだ確信が持ててない。」
「そうですか。」
「ブラッディフッド、姉はもう、人ではないのですか?」
「多分な。」
「それで婚約破棄させるようにもっていったのですね?」
「ああ、悪いな。普通の人のままであれば、子爵夫人になれるんだ、私も勧めただろう。」
「そうですか、姉はもう。」
「まあ、それ程気にするまでもないさ。エラの姉であることには変わりないんだからな。」
「そうですね。」
「しかし、魔力は無いにしても、その能力が狙われる可能性があるのではないですか?」
女王マルガリータが心配になって聞いた。
「見えない能力であるし、本人の性格もあってな。信じて貰えないのだろうな。試しに中級の冒険者パーティーに預けてみたのだが、直ぐにクビになったようだし。」
「何故ですか?姉は一人でも、かなりの強さがあると思うのですが?」
実際、自らが負けたから、その強さが身に染みてわかっていた。
「パーティーの中に居て、あいつが前に出ると思うか?」
「・・・。」
職的には、舞踏家は前衛職。
しかし、アナスタシアは、冒険者パーティー内で前に出るような事はしない。己の言葉に力があると信じているから、貴族らしく振舞っているだけだ。
最底辺のレダ達と一緒の時は、そういう訳にはいかず、指示したり、もしもに備えたりするわけだが。
「プライドが高く、我儘な性格も、能力を隠す役に立っているようですね。」
「ま、まあな・・・。いずれにしても、カイン達は葬った。今後はあいつに手を出そうなんて冒険者は居なくなるだろう。」
「ブラッディフッド、姉の為に、ありがとうございます。」
「気にするな。私の弟子なんだからな、あいつは。」
師匠や妹が、自身の話をしているなんて、露知らず、アナスタシアは一路、レダ達のいる町を目指していた。
レダ達の居る町は、歩いていけば一週間以上もかかる。
アナスタシアが運ばれる時は、馬車を使っていたが。一日も早く合流はしたいが、馬を買うとなると結構な金額が掛かるわけで。
「まあいいわ、レダ達が、あの町から動くわけがないし。」
そう決めつけて、歩いていくことに決めた。
サンドリヨン国を出ると、いきなり野盗に襲われた。
「娼婦か、俺たちの相手をしてくれねえか?」
「3人いっぺんにな、うひひひひ。」
こういう奴らは、殺しても殺しても居なくならない。一体とこから湧き出ているのだろうか?
そんな事を思いつつも、戦闘態勢に入ったのだが。
「お前らみたいな屑には地獄がふさわしい。」
そんな事を言いながら、まるで主役が登場するかの如く派手に青年が登場してきた。腰にショートソードを持つ冒険者が。
「なんだ、お前は?」
「恰好つけてんじゃねえよ。」
一体いつ、剣を抜いたのか。
いちゃもんをつけた二人の野盗が、死んでその場に倒れた。
「ひ、ひいいいい。」
残った一人が逃げようとしたが、両足を切断され、ゴキブリが這うように、ガサガサとしていた。
「おい、俺の名前を言ってみろ?」
冒険者は、ゴキブリの頬が切れるくらいの所にショートソードを突き刺していった。
「は、は・・・、た、助けて・・・。」
「俺の事を知っていたらな。」
「あ、あんたあれだ。リスキーだ。」
「正解。」
そう言ってゴキブリの首を落とした。
「酷いわね、助けるんじゃなかったの?」
アナスタシアが言った。
「助けただろ?苦しみからな。」
「・・・。」
「それより、礼くらい言ってもいいんじゃないのか?」
「余計なことをしたのは、そっちでしょ?礼をいう筋合いはないわ。」
「まったく、ブラッディフッドの弟子ってのは、傲慢な奴なんだな。」
「私を知ってるの?」
「今、冒険者で、お前を知らなかったら、命が要らない奴だろうな。」
「あっそ。」
自分が有名なわけでなく、お師匠様の弟子と言うことで有名らしいので、どうでもいいやと思った。
「お前も冒険者なんだよな?」
「そうよ。」
「じゃあ俺の事を知ってるだろ?」
「リスキー?」
「そうだ。」
「その恰好からして、冒険者なんでしょ?」
「ちょっとまて、お前、リスキーの名前を知らずに冒険者なんてやってるのか?」
「知らないわよ、あんたの事なんて・・・。」
「ま、マジか・・・。くっ・・・。ちなみに級持ちの冒険者は、何人くらい知ってる?」
「級持ち?んー・・・、死んだカイン達と・・・、C級のロビン達くらい。」
「は?なんでC級程度の奴の名前を憶えてるんだ。」
「ふっ、いつか見返してやる為に決まってるじゃない。」
「そ、そうか・・・。S級冒険者の事は知らないんだな。」
「ええ、興味ないし。あっ・・・。」
「どうした?」
「あんた級持ちなの?」
「ああ、そうだ。」
「そっ・・・、じゃあねっ」
「はあ?いきなりなんだ?おい。」
「お師匠様から級持ちにはついていくなって言われてるのよ。」
「なんだ、それは・・・。お前の事を助けたんだぞ俺は?」
「それは、余計な事でしょ?私がブラッディフッドの弟子と判ってたんでしょ?」
「まあな。だが、お前が強いなんて話は聞いたことないがな。」
「ブラッディフッドの弟子が、野盗ごときに負けると?」
「まあ、そうは思わない。が、恩くらい売れるんじゃないかなとは思ったけどな。」
「ふっ、やっぱりね。私を利用しようとしてる輩ね。」
「違うっ。いいか、今、冒険者の間では、ブラッディフッドの弟子に関わるなっていう事になってるんだ。それを態々、関わってるんだ。」
「なるほど、そうまでして私のお師匠様に近づきたいのね。」
「恐ろしい事をいうな。お前に恩を売りたかっただけだ。」
「私に?」
「ああ、凄い能力持っているんだろ?」
「ははーん。私を魔石にしようと企んでるわね。」
「ぶっちゃけ、俺より魔力ないだろ、お前・・・。」
「うっさいわねっ!」
「お前の歌姫アムールの超縮小版の能力に興味がある。」
「ちょ、超縮小版だとっ!」
「C級の奴らのバーティーをクビになったそうだな。」
「クビじゃないわよ!合わなかっただけよ。」
「ああ、そいつは大事だ。合う合わないわ。」
「ちょっと待って、あなた級持ちの冒険者って言ってたわよね?」
「ああ、そうだ。」
「仲間は?」
級持ちの冒険者と言えばパーティーが、基本であり、自然とそんな質問が口から出た。
「そんなのは居ない。」
「なんだ、ぼっちか。」
「ぼっち言うな!お前だって一緒だろうが?」
「はあ?一緒にしないでくれる?私は今から仲間の元へ向かってるのよ。」
「な、仲間がいるのか?」
「ええ。残念ね、他を当たってくれる?」
「おかしいな、俺が聞いた話では、性格に難ありで、どこのパーティーにも属していないと・・・。」
「ちょっと!誰の性格が悪いって?」
「ちなみに仲間と何処で待ち合わせてるんだ?」
「チーズだけど?」
「チーズって、何もない町だろ?」
「何もないわけではないでしょ?」
「冒険者にとって何もない町ってことさ。仲間はどのくらいのランクだ?」
「級なしだけど?」
「級なしかよ・・・俺に乗り換えた方がいいぞ?そいつらと居ても将来性がないだろうに。」
「じゃあ、聞くけど、私の能力で何を倒したいわけ?」
「うっ・・・。」
世界に大した大物がいるわけでもなく、上位の冒険者のランキングが微動だにしない昨今、何か倒す相手が居るかと言うと、そんな者は存在していない。
「そりゃあ、今は居ないが。ああいうものは前兆もなしに現れるからな。」
「魔王フールにでも挑戦して来たら?」
「冗談でも、そう言うことは言わない方がいい。フールにとって人間は忌むべき存在だからな。」
「詳しいのね。もしかして憧れてるとかいわないでよね。」
チーズの街の酒場の親父の顔が思い浮かんだ。
「馬鹿をいうな、俺の師匠が殺されているんだぞ、憧れる事はない。」
「・・・。恨んでいるの?」
「そう言う問題じゃあないんだが、恨んでいないと言えば嘘になるが、ブラッディフッドと一緒だ。関わらないのが一番だ。」
「仇を取ろうとか思わないの?」
「思わないね。元々、人に騙されてフール討伐に手を貸したんだ。恨むんなら、まず人からだろ?」
「もしかして、大昔にあった獣人討伐の時?」
「違う違う、そんな大昔の奴じゃあない。いいか獣人討伐ってのは、小競り合いを入れたら、結構行われている。事の発端は、全て人のせいだがな。」
「そうなんだ。」
「人は罪深く、強欲で残虐である。エイル教の一節くらい聞いたことあるだろ?」
「あるわ。」
「そういうことで、フールだけを恨むのは筋違いなのさ。」
「随分とあっさりしてるのね。」
「まあな、師匠も騙されている事に気が付いていたんだろう。俺と別れる前に、フールも人も決して恨んではいけないって言い残していったからな。」
「いい師匠だったのね。」
「まあな。まあ俺の話はこれ位にして、チーズの町まで俺が護衛してやろう。」
「要らないわよ、護衛なんて。むしろあんたと一緒の方が身の危険になるじゃないっ!」
「さっき言ったろ?俺はお前に恩が売りたいんだと。」
「それってさ、強敵が現れたら力を貸せって事?」
「まあ、その通りだ。本当は、仲間になって欲しい所だが、無理強いはできないしな。」
アナスタシアは少し思案してから言った。
「まあ、条件次第ではついてきても構わないけど?」
「条件とは?」
「私の仲間に剣を教えて欲しいの。」
「ふむ、チーズの街に居るってことだから、才能も素質もないんだろ?」
「まあね。」
「女の子か?」
「性別が何の関係があるのよ?」
「馬鹿野郎、才能も素質もない奴に教えるんだろ?性別は大事だろ?」
「じょ、女性よ。見た目は、イマイチかもしれないけど。」
「ノープロブレム。俺はフェミニストだからな。ちなみに名前は?」
「レ・・・レオーヌよ。」
「レオーヌちゃんかあ、なんか力が漲ってきた!」
「そ、そう、それはよかったわね。」
0
お気に入りに追加
70
あなたにおすすめの小説

政略より愛を選んだ結婚。~後悔は十年後にやってきた。~
つくも茄子
恋愛
幼い頃からの婚約者であった侯爵令嬢との婚約を解消して、学生時代からの恋人と結婚した王太子殿下。
政略よりも愛を選んだ生活は思っていたのとは違っていた。「お幸せに」と微笑んだ元婚約者。結婚によって去っていた側近達。愛する妻の妃教育がままならない中での出産。世継ぎの王子の誕生を望んだものの産まれたのは王女だった。妻に瓜二つの娘は可愛い。無邪気な娘は欲望のままに動く。断罪の時、全てが明らかになった。王太子の思い描いていた未来は元から無かったものだった。後悔は続く。どこから間違っていたのか。
他サイトにも公開中。

婚約破棄された私は、処刑台へ送られるそうです
秋月乃衣
恋愛
ある日システィーナは婚約者であるイデオンの王子クロードから、王宮敷地内に存在する聖堂へと呼び出される。
そこで聖女への非道な行いを咎められ、婚約破棄を言い渡された挙句投獄されることとなる。
いわれの無い罪を否定する機会すら与えられず、寒く冷たい牢の中で断頭台に登るその時を待つシスティーナだったが──
他サイト様でも掲載しております。

婚約破棄された検品令嬢ですが、冷酷辺境伯の子を身籠りました。 でも本当はお優しい方で毎日幸せです
青空あかな
恋愛
旧題:「荷物検査など誰でもできる」と婚約破棄された検品令嬢ですが、極悪非道な辺境伯の子を身籠りました。でも本当はお優しい方で毎日心が癒されています
チェック男爵家長女のキュリティは、貴重な闇魔法の解呪師として王宮で荷物検査の仕事をしていた。
しかし、ある日突然婚約破棄されてしまう。
婚約者である伯爵家嫡男から、キュリティの義妹が好きになったと言われたのだ。
さらには、婚約者の権力によって検査係の仕事まで義妹に奪われる。
失意の中、キュリティは辺境へ向かうと、極悪非道と噂される辺境伯が魔法実験を行っていた。
目立たず通り過ぎようとしたが、魔法事故が起きて辺境伯の子を身ごもってしまう。
二人は形式上の夫婦となるが、辺境伯は存外優しい人でキュリティは温かい日々に心を癒されていく。
一方、義妹は仕事でミスばかり。
闇魔法を解呪することはおろか見破ることさえできない。
挙句の果てには、闇魔法に呪われた荷物を王宮内に入れてしまう――。
※おかげさまでHOTランキング1位になりました! ありがとうございます!
※ノベマ!様で短編版を掲載中でございます。

虐げられ聖女の力を奪われた令嬢はチート能力【錬成】で無自覚元気に逆襲する~婚約破棄されましたがパパや竜王陛下に溺愛されて幸せです~
てんてんどんどん
恋愛
『あなたは可愛いデイジアちゃんの為に生贄になるの。
貴方はいらないのよ。ソフィア』
少女ソフィアは母の手によって【セスナの炎】という呪術で身を焼かれた。
婚約した幼馴染は姉デイジアに奪われ、闇の魔術で聖女の力をも奪われたソフィア。
酷い火傷を負ったソフィアは神殿の小さな小屋に隔離されてしまう。
そんな中、竜人の王ルヴァイスがリザイア家の中から結婚相手を選ぶと訪れて――
誰もが聖女の力をもつ姉デイジアを選ぶと思っていたのに、竜王陛下に選ばれたのは 全身火傷のひどい跡があり、喋れることも出来ないソフィアだった。
竜王陛下に「愛してるよソフィア」と溺愛されて!?
これは聖女の力を奪われた少女のシンデレラストーリー
聖女の力を奪われても元気いっぱい世界のために頑張る少女と、その頑張りのせいで、存在意義をなくしどん底に落とされ無自覚に逆襲される姉と母の物語
※よくある姉妹格差逆転もの
※虐げられてからのみんなに溺愛されて聖女より強い力を手に入れて私tueeeのよくあるテンプレ
※超ご都合主義深く考えたらきっと負け
※全部で11万文字 完結まで書けています

【完結】お父様。私、悪役令嬢なんですって。何ですかそれって。
紅月
恋愛
小説家になろうで書いていたものを加筆、訂正したリメイク版です。
「何故、私の娘が処刑されなければならないんだ」
最愛の娘が冤罪で処刑された。
時を巻き戻し、復讐を誓う家族。
娘は前と違う人生を歩み、家族は元凶へ復讐の手を伸ばすが、巻き戻す前と違う展開のため様々な事が見えてきた。

【完結】婚約破棄される前に私は毒を呷って死にます!当然でしょう?私は王太子妃になるはずだったんですから。どの道、只ではすみません。
つくも茄子
恋愛
フリッツ王太子の婚約者が毒を呷った。
彼女は筆頭公爵家のアレクサンドラ・ウジェーヌ・ヘッセン。
なぜ、彼女は毒を自ら飲み干したのか?
それは婚約者のフリッツ王太子からの婚約破棄が原因であった。
恋人の男爵令嬢を正妃にするためにアレクサンドラを罠に嵌めようとしたのだ。
その中の一人は、アレクサンドラの実弟もいた。
更に宰相の息子と近衛騎士団長の嫡男も、王太子と男爵令嬢の味方であった。
婚約者として王家の全てを知るアレクサンドラは、このまま婚約破棄が成立されればどうなるのかを知っていた。そして自分がどういう立場なのかも痛いほど理解していたのだ。
生死の境から生還したアレクサンドラが目を覚ました時には、全てが様変わりしていた。国の将来のため、必要な処置であった。
婚約破棄を宣言した王太子達のその後は、彼らが思い描いていたバラ色の人生ではなかった。
後悔、悲しみ、憎悪、果てしない負の連鎖の果てに、彼らが手にしたものとは。
「小説家になろう」「カクヨム」「ノベルバ」にも投稿しています。
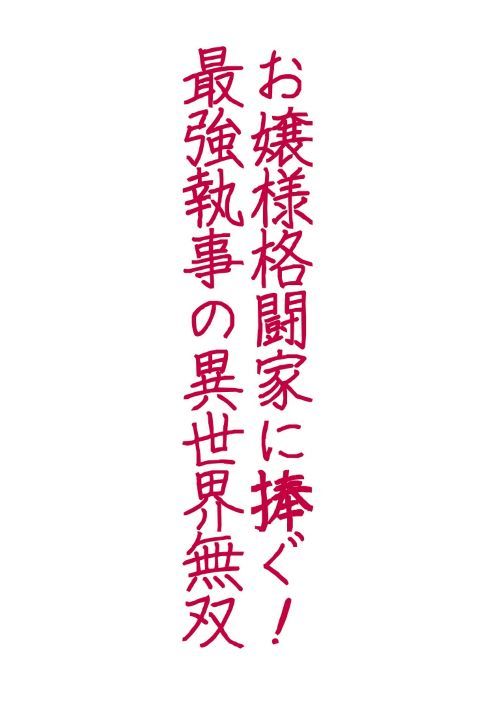
お嬢様格闘家に捧ぐ!最強執事の異世界無双
天宮暁
ファンタジー
霧ヶ峰敬斗(きりがみねけいと)は、名家の令嬢・鳳凰院紅華(ほうおういんべにか)に仕える執事の少年である。
紅華の趣味は格闘技。その実力は「趣味」の枠に収まるものではなく、若くして道場破りを繰り返し、高名な武術家をも破ってきた。
そんな紅華が、敬斗の読んでいた異世界転生小説を見て言った。
「異世界ねぇ……わたしも行ってみたいわ。こっちの世界より強い奴がいそうじゃない!」
そんな紅華の言葉を、執事長が拾い、冗談交じりに話を持ち出す。
「古より当家に伝わる『隔世(へだてよ)の門』というものがございます。その門は『波留解(はるげ)』なる異世界に通じているとかいないとか……」
「なにそれ、おもしろそう!」
冷やかし半分で門を見にいく紅華と敬斗。だが、その伝承はまぎれもなく事実だった。門をくぐり抜けた先には、未知の世界が広がっていた――!
興奮する紅華とは対照的に、敬斗は秘かに心配する。魔物が跋扈し、魔法が使える未知の世界。こんな世界で、お嬢様をどうやって守っていけばいいのだろうか――!?
やがて敬斗は、ひとつの結論へとたどり着く。
「僕が万難を排した上で、お嬢様が気持ちよく戦えるよう『演出』すればいいじゃないか」
と。
かくして、「超絶強いくせに心配性」「鉄橋を叩き割ってから自前の橋をかけ直す」最強執事が、全力でお嬢様の無双を「演出」する――ッ!
そう。
これは、異世界に紛れ込んだお嬢様格闘家が無双しまくる物語――
……を「演出」する、彼女の「執事」の物語であるッッ!

死に戻りの魔女は溺愛幼女に生まれ変わります
みおな
恋愛
「灰色の魔女め!」
私を睨みつける婚約者に、心が絶望感で塗りつぶされていきます。
聖女である妹が自分には相応しい?なら、どうして婚約解消を申し込んでくださらなかったのですか?
私だってわかっています。妹の方が優れている。妹の方が愛らしい。
だから、そうおっしゃってくだされば、婚約者の座などいつでもおりましたのに。
こんな公衆の面前で婚約破棄をされた娘など、父もきっと切り捨てるでしょう。
私は誰にも愛されていないのだから。
なら、せめて、最後くらい自分のために舞台を飾りましょう。
灰色の魔女の死という、極上の舞台をー
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















