9 / 37
第一章 パンツとキックとドロップアウトボーイ
罠と宣戦布告とセコンドの意味
しおりを挟む
まるで試合前にローブを脱ぐように、兎萌は羽織ったジャージを脱いで丸めると、職員室の外へ置いてきた鞄の下へと放り投げて。
「お言葉ですが、上野先生。『勝てるわけがない』なんてのは、私たちファイターに対しての侮辱です。どうか、取り消してください」
兎萌の言葉に、上野はわずかに気圧された様子だったが、すぐに不快感を露わにした。
「……では、勝てるというのですか?」
「さあ?」
「はあ?」
いよいよ声にも苛立ちを隠せなくなってきた彼女に、兎萌は続ける。
「彼次第ですから。それに、時の運って言うでしょう? 歴戦の選手が、新人の振り回す腕に沈むことだってあるんです。断言はできませんが、少なくとも私は、勝ちに行きますよ」
お前はどうよ、と問いかける銀河に、葵は強く頷いて返す。
「俺も、本気で取り組みます!」
「だから、世の中そう甘くは……っ!」
「その言葉、かなりの矛盾を孕んでいるって、お気づきですか?」
「いいえ、留年に関する話ですから、たまたま期限が年度末になっただけですもの!」
上野の冷徹な仮面が、勝ち誇った興奮に剥がれる。
しかし兎萌が指摘した『矛盾』は、葵にかけられた罠に対するものではなかったらしい。
「世の中は甘くない……嫌いなんですよねえ、ソレ。ええまあ仰ることは甚だ尤も。努力もせずに勝つことはできませんから、正しい言葉なのでしょうね」
「ほら、貴女だってそう思って――」
「けれどその言葉は、彼の努力を潰すためにあるものではないはずです」
「無駄な努力に終わると、忠告しているだけでしょう!」
眉を顰めた上野に、兎萌がにぃと歯を見せ、舌なめずりをしたようにも見えた。
「では、先生はどうですか?」
「……は?」
「先生の経歴は存じています。そこがいわゆる名門大学ではないことも、勤務先であるこの学校が名門高校でないことも。現在御付き合いされていると噂のあの先生とのことも。すべては、自分でも選ぶことの適うような甘い世界だからですか? ハッ、だったらせめて、自分の受け持つクラスの学力くらいどうにかしましょうよ。川樋くん以外に何人います? 御自分のクラスで、『甘い世界』で、赤点なんてものを出した指導力を疑うべきではありませんか。
キック部のこともそうです。学校の売名のため、わざわざ人数不足を無視する特例を作ってまで立ち上げた際、これまた評価のために顧問に就かれたのが上野先生ですが……あれから、顧問として一ミリでも、キックの勉強はしてくださいましたか? 練習場所であるうちのジムに、顔を出していただいたことさえありませんが」
次々と口を突いて出る暴論めいた指摘に、とうとう上野が絶句した。
そんな上野からつまらなさそうに目を背けた鬼が、こちらの肩に手を置いてきたものだから、葵は思わず飛び上がりそうになる。
「傍から見れば分の悪い賭けに思えるでしょう。けれどなかなかどうして、彼は本気ですよ」
そう言って、鬼はまた、牙を剥いた。
葵は彼女を頼もしく思う一方で、正直、やめてくれとも願っていた。お前が煽るのは勝手だが、腹いせに俺の評価を下げられるかもしれないのだ。最悪、留年撤回の条件さえ反故にされてしまってはどうにもならない。
気もそぞろに成り行きを見守っていると、不意に、太ももをひっ叩かれた。
「いきなり何すんあだだだだだっ!?」
飛び退ろうとした咄嗟の動きに付いていけなかった筋肉が、悲鳴を上げ、攣ってしまう。葵は立っていることもままならず、職員室の床にうずくまった。
すると兎萌は、やっぱり、と苦笑しながら傍に屈み、足を優しく伸ばしてくれながら、言葉を続けていった。
「葵は今朝、私――つまり五十一キロの重りを背負った状態で、同じ足跡しか踏んではいけないというルールの下、ジムの周りを十周してます。その後の雪かきに、ジム内の雑巾がけをほぼ一人で行い、高負荷の筋トレまでしてきました。それに一昨日は生スパーを見て――」
そこまで話したところで、彼女は「まあ、こっちはいっか」と切り上げる。
「少なくとも、未経験者の初日にさせるメニューではありませんでした。疑われるのであれば、ぜひ、動きやすい服装を着用の上、明朝五時半にうちのジム『アルカディアス』までお越しください。他の先生方でも構いませんよ? 歓迎します。池黒先生など、如何ですか?」
そんな誘いに、体育教師の池黒はおろか、誰もが口を噤むことしかできずにいた。
兎萌はにっこりと、唖然としたままの上野の手に、改めて入部届を載せ、
「結果を出せば留年撤回のお約束、忘れないでくださいね」
そう言い残して、、葵の手を引いて職員室を後にした。
* * * * *
何という言葉をかければいいか分からず、ようやく葵が口を開けたのは、校門を出た後でのことだった。
「俺が言うのもなんだけど、良かったのか? お前まで先生にケンカ売ることはねえだろ」
「んー、そうねー」
空を睨んで何やら言葉を探した兎萌は、あ、そうだ、と手を打った。
「葵はさ、ボクシングで選手に付いている人が、どうして『セコンド』って言うか知ってる?」
「えっ? そう言われてみれば、分かんねえな」
「セコンドって、数字を数えるときの、ファースト、セカンド……のセカンドと同じ意味なの」
今の大ヒント、と付け加えて、自販機の前で足を止める。
「じゃあ、二番目って意味なのか?」
兎萌は電子マネーのパネルに財布を押し当て、選んだあたたかいお茶のペットボトルをこちらへ放って来た。
「正解。昔はさ、次に出場する選手がコーナーサイドにいたから、セコンドって呼ばれるようになったんだって」
「その口ぶりだと、今じゃあ違うんだよな」
「そうね、一応ライセンス制になってるかな。といっても、ある程度ジムの裁量で申請できるから、キックに真剣な人なら、ほとんど問題なく取れるんだけどね」
もう一本購入したお茶をジャージの袖で持ち、温かくなった口の中の空気を、ほう、と空に遊ばせながら、私も持ってるんだよ、と言った。
「もひとつ問題。ライセンスの規則にはね、『セコンドは、試合に臨んで、ボクサーを補助し、また、ボクサーに対して助言を与えることができる。』ってあるの。この意味、分かる?」
職員室での気迫はどこへ行ったのかと思う程の無邪気な表情で、こてっと小首を傾けて訊ねる彼女に、葵は対照的に難しい顔で首を傾げた。
セコンドの規則自体を口の中で反芻しても、まあそうだろうな、という感想を抱くだけで、その裏に秘められた意味といわれても、咄嗟には見えてこない。
「……すまん、降参」
素直に白旗を上げると、兎萌はかっかっか、と某ご老公のように笑った。
「正解はね、『試合に臨んで』の部分。試合に臨んだボクサーを補助、ではなくて、セコンド自身がボクサーと共に試合に臨む、という文章になってるんだよ」
「ボクサーと、一緒に……」
「そ! 葵の試合には、女子フライ級王者の私も、王者の私も! 一緒に出るってワケ」
「何故二回言うかね、君は」
「だってだって、SANAさんに勝ったのが嬉しかったんだもん! もっと言うと、お兄ちゃんはミドル級王者で、世界大会出場経験あり。明日葉さんも、経験一年目でアマチュアの東日本大会で優勝した実力者。そんなわけで、葵には、割と頼もしい布陣が付いてるんだぞ?」
笑顔で差し出された、袖からちょこん突き出た大きな拳に目を疑う。頭では、それが女の子の小さな拳だと分かっていながら、葵はぽかーんと、あっぱ口を開けていることしかできない。
「だから私も、先生の敵に回っただけのこと。以上、文句ある?」
「ははっ……そりゃ、頼もしいこって」
「こちらこそだよ。二人三脚で繋いだ私の脚は、片方がコレなんだから。ちゃんと支えてよ?」
くしゃっとはにかむ笑顔を向けられると、不思議な安心感があった。まるで昔から、彼女とタッグを組んでいたような錯覚さえ覚える。
「つっても俺、あのキザ眼鏡相手に、ビギナーズラックも当たらなかったぞ?」
「そりゃそうよ。あんたはまだ未経験者。新人ですらないもの」
「そういう問題なのか……?」
「そういう問題なのよ。戦う作法を知らずにやってのけるのは映画の中だけ」
そう言って笑うと、兎萌は勢いよく尻を叩いてきた。
ふつふつと、滾って来るものを感じる。冬の寒さと朝練の疲労で震える脚が、ぴたりと鳴りを潜め、きちんと地に足ついたような気さえした。まるで筋肉痛も吹き飛ぶようで、これから行うトレーニングにも、俄然気合が入ってくる。
ジムに辿り着いた葵は、自販機横のゴミ箱に空のペットボトルを突っ込んで、兎萌の背中を追いかけた。しかし、扉を開いたところで彼女が足を止めていて、後ずさる。
「どうした?」
訊ねると、兎萌が中を指で示した。今朝もでっぷりと寝そべっていたフグが、ジムの中に向かって、威嚇するように喉を鳴らしている。
二人で顔を見合わせる。こういうことはするのかと訊くと、兎萌は、これまでにこんなことはなかったと言う。番犬として置かれているのに、番犬らしい行動に疑問を抱かれるとは。そんな一抹の同情をフグに寄せながら、靴を脱いで中に入る。
受付前の客用椅子に、鋭い目つきをした短髪の青年が腕を組んでいるのが見えた。
制服であることを見る限り、学生なのだろう。しかしどこか老成したような、じっと機会を窺う獰猛な狼にも似た雰囲気は、こちらが背中を見せた瞬間に牙を立てて来るようだ。勇魚ほど大柄ではないが、引き締まった筋肉は実力の裏打ちであることを感じさせる。
一昨日にはいなかったはずだ。彼がフグの警戒対象なのかもしれないと、横目でこっそり窺っていると、ふと、目が合った。しかし青年はすぐに興味なさそうに目を流す。
その先で、青年の顔の動きが止まった。獲物は――
「待っていたぞ。羽付兎萌」
喉が鎖骨の下にあるのではないかと思う程の、堂々たる低い声が響く。
その声に、兄の勇魚を探そうと別方向に顔を向けていた兎萌が、はっとして振り返った。
彼女が思わず手を離した松葉杖が、カラン、と音を立てて倒れる。
「えっと、誰?」
おそるおそる耳打ちすると、兎萌はぎゅっと眉間に皺を寄せて、絞り出すように言った。
「釈迦堂舞流戦――通称『二殺拳』。現在、男子高校生最強と呼び声の高い実力者よ」
「お言葉ですが、上野先生。『勝てるわけがない』なんてのは、私たちファイターに対しての侮辱です。どうか、取り消してください」
兎萌の言葉に、上野はわずかに気圧された様子だったが、すぐに不快感を露わにした。
「……では、勝てるというのですか?」
「さあ?」
「はあ?」
いよいよ声にも苛立ちを隠せなくなってきた彼女に、兎萌は続ける。
「彼次第ですから。それに、時の運って言うでしょう? 歴戦の選手が、新人の振り回す腕に沈むことだってあるんです。断言はできませんが、少なくとも私は、勝ちに行きますよ」
お前はどうよ、と問いかける銀河に、葵は強く頷いて返す。
「俺も、本気で取り組みます!」
「だから、世の中そう甘くは……っ!」
「その言葉、かなりの矛盾を孕んでいるって、お気づきですか?」
「いいえ、留年に関する話ですから、たまたま期限が年度末になっただけですもの!」
上野の冷徹な仮面が、勝ち誇った興奮に剥がれる。
しかし兎萌が指摘した『矛盾』は、葵にかけられた罠に対するものではなかったらしい。
「世の中は甘くない……嫌いなんですよねえ、ソレ。ええまあ仰ることは甚だ尤も。努力もせずに勝つことはできませんから、正しい言葉なのでしょうね」
「ほら、貴女だってそう思って――」
「けれどその言葉は、彼の努力を潰すためにあるものではないはずです」
「無駄な努力に終わると、忠告しているだけでしょう!」
眉を顰めた上野に、兎萌がにぃと歯を見せ、舌なめずりをしたようにも見えた。
「では、先生はどうですか?」
「……は?」
「先生の経歴は存じています。そこがいわゆる名門大学ではないことも、勤務先であるこの学校が名門高校でないことも。現在御付き合いされていると噂のあの先生とのことも。すべては、自分でも選ぶことの適うような甘い世界だからですか? ハッ、だったらせめて、自分の受け持つクラスの学力くらいどうにかしましょうよ。川樋くん以外に何人います? 御自分のクラスで、『甘い世界』で、赤点なんてものを出した指導力を疑うべきではありませんか。
キック部のこともそうです。学校の売名のため、わざわざ人数不足を無視する特例を作ってまで立ち上げた際、これまた評価のために顧問に就かれたのが上野先生ですが……あれから、顧問として一ミリでも、キックの勉強はしてくださいましたか? 練習場所であるうちのジムに、顔を出していただいたことさえありませんが」
次々と口を突いて出る暴論めいた指摘に、とうとう上野が絶句した。
そんな上野からつまらなさそうに目を背けた鬼が、こちらの肩に手を置いてきたものだから、葵は思わず飛び上がりそうになる。
「傍から見れば分の悪い賭けに思えるでしょう。けれどなかなかどうして、彼は本気ですよ」
そう言って、鬼はまた、牙を剥いた。
葵は彼女を頼もしく思う一方で、正直、やめてくれとも願っていた。お前が煽るのは勝手だが、腹いせに俺の評価を下げられるかもしれないのだ。最悪、留年撤回の条件さえ反故にされてしまってはどうにもならない。
気もそぞろに成り行きを見守っていると、不意に、太ももをひっ叩かれた。
「いきなり何すんあだだだだだっ!?」
飛び退ろうとした咄嗟の動きに付いていけなかった筋肉が、悲鳴を上げ、攣ってしまう。葵は立っていることもままならず、職員室の床にうずくまった。
すると兎萌は、やっぱり、と苦笑しながら傍に屈み、足を優しく伸ばしてくれながら、言葉を続けていった。
「葵は今朝、私――つまり五十一キロの重りを背負った状態で、同じ足跡しか踏んではいけないというルールの下、ジムの周りを十周してます。その後の雪かきに、ジム内の雑巾がけをほぼ一人で行い、高負荷の筋トレまでしてきました。それに一昨日は生スパーを見て――」
そこまで話したところで、彼女は「まあ、こっちはいっか」と切り上げる。
「少なくとも、未経験者の初日にさせるメニューではありませんでした。疑われるのであれば、ぜひ、動きやすい服装を着用の上、明朝五時半にうちのジム『アルカディアス』までお越しください。他の先生方でも構いませんよ? 歓迎します。池黒先生など、如何ですか?」
そんな誘いに、体育教師の池黒はおろか、誰もが口を噤むことしかできずにいた。
兎萌はにっこりと、唖然としたままの上野の手に、改めて入部届を載せ、
「結果を出せば留年撤回のお約束、忘れないでくださいね」
そう言い残して、、葵の手を引いて職員室を後にした。
* * * * *
何という言葉をかければいいか分からず、ようやく葵が口を開けたのは、校門を出た後でのことだった。
「俺が言うのもなんだけど、良かったのか? お前まで先生にケンカ売ることはねえだろ」
「んー、そうねー」
空を睨んで何やら言葉を探した兎萌は、あ、そうだ、と手を打った。
「葵はさ、ボクシングで選手に付いている人が、どうして『セコンド』って言うか知ってる?」
「えっ? そう言われてみれば、分かんねえな」
「セコンドって、数字を数えるときの、ファースト、セカンド……のセカンドと同じ意味なの」
今の大ヒント、と付け加えて、自販機の前で足を止める。
「じゃあ、二番目って意味なのか?」
兎萌は電子マネーのパネルに財布を押し当て、選んだあたたかいお茶のペットボトルをこちらへ放って来た。
「正解。昔はさ、次に出場する選手がコーナーサイドにいたから、セコンドって呼ばれるようになったんだって」
「その口ぶりだと、今じゃあ違うんだよな」
「そうね、一応ライセンス制になってるかな。といっても、ある程度ジムの裁量で申請できるから、キックに真剣な人なら、ほとんど問題なく取れるんだけどね」
もう一本購入したお茶をジャージの袖で持ち、温かくなった口の中の空気を、ほう、と空に遊ばせながら、私も持ってるんだよ、と言った。
「もひとつ問題。ライセンスの規則にはね、『セコンドは、試合に臨んで、ボクサーを補助し、また、ボクサーに対して助言を与えることができる。』ってあるの。この意味、分かる?」
職員室での気迫はどこへ行ったのかと思う程の無邪気な表情で、こてっと小首を傾けて訊ねる彼女に、葵は対照的に難しい顔で首を傾げた。
セコンドの規則自体を口の中で反芻しても、まあそうだろうな、という感想を抱くだけで、その裏に秘められた意味といわれても、咄嗟には見えてこない。
「……すまん、降参」
素直に白旗を上げると、兎萌はかっかっか、と某ご老公のように笑った。
「正解はね、『試合に臨んで』の部分。試合に臨んだボクサーを補助、ではなくて、セコンド自身がボクサーと共に試合に臨む、という文章になってるんだよ」
「ボクサーと、一緒に……」
「そ! 葵の試合には、女子フライ級王者の私も、王者の私も! 一緒に出るってワケ」
「何故二回言うかね、君は」
「だってだって、SANAさんに勝ったのが嬉しかったんだもん! もっと言うと、お兄ちゃんはミドル級王者で、世界大会出場経験あり。明日葉さんも、経験一年目でアマチュアの東日本大会で優勝した実力者。そんなわけで、葵には、割と頼もしい布陣が付いてるんだぞ?」
笑顔で差し出された、袖からちょこん突き出た大きな拳に目を疑う。頭では、それが女の子の小さな拳だと分かっていながら、葵はぽかーんと、あっぱ口を開けていることしかできない。
「だから私も、先生の敵に回っただけのこと。以上、文句ある?」
「ははっ……そりゃ、頼もしいこって」
「こちらこそだよ。二人三脚で繋いだ私の脚は、片方がコレなんだから。ちゃんと支えてよ?」
くしゃっとはにかむ笑顔を向けられると、不思議な安心感があった。まるで昔から、彼女とタッグを組んでいたような錯覚さえ覚える。
「つっても俺、あのキザ眼鏡相手に、ビギナーズラックも当たらなかったぞ?」
「そりゃそうよ。あんたはまだ未経験者。新人ですらないもの」
「そういう問題なのか……?」
「そういう問題なのよ。戦う作法を知らずにやってのけるのは映画の中だけ」
そう言って笑うと、兎萌は勢いよく尻を叩いてきた。
ふつふつと、滾って来るものを感じる。冬の寒さと朝練の疲労で震える脚が、ぴたりと鳴りを潜め、きちんと地に足ついたような気さえした。まるで筋肉痛も吹き飛ぶようで、これから行うトレーニングにも、俄然気合が入ってくる。
ジムに辿り着いた葵は、自販機横のゴミ箱に空のペットボトルを突っ込んで、兎萌の背中を追いかけた。しかし、扉を開いたところで彼女が足を止めていて、後ずさる。
「どうした?」
訊ねると、兎萌が中を指で示した。今朝もでっぷりと寝そべっていたフグが、ジムの中に向かって、威嚇するように喉を鳴らしている。
二人で顔を見合わせる。こういうことはするのかと訊くと、兎萌は、これまでにこんなことはなかったと言う。番犬として置かれているのに、番犬らしい行動に疑問を抱かれるとは。そんな一抹の同情をフグに寄せながら、靴を脱いで中に入る。
受付前の客用椅子に、鋭い目つきをした短髪の青年が腕を組んでいるのが見えた。
制服であることを見る限り、学生なのだろう。しかしどこか老成したような、じっと機会を窺う獰猛な狼にも似た雰囲気は、こちらが背中を見せた瞬間に牙を立てて来るようだ。勇魚ほど大柄ではないが、引き締まった筋肉は実力の裏打ちであることを感じさせる。
一昨日にはいなかったはずだ。彼がフグの警戒対象なのかもしれないと、横目でこっそり窺っていると、ふと、目が合った。しかし青年はすぐに興味なさそうに目を流す。
その先で、青年の顔の動きが止まった。獲物は――
「待っていたぞ。羽付兎萌」
喉が鎖骨の下にあるのではないかと思う程の、堂々たる低い声が響く。
その声に、兄の勇魚を探そうと別方向に顔を向けていた兎萌が、はっとして振り返った。
彼女が思わず手を離した松葉杖が、カラン、と音を立てて倒れる。
「えっと、誰?」
おそるおそる耳打ちすると、兎萌はぎゅっと眉間に皺を寄せて、絞り出すように言った。
「釈迦堂舞流戦――通称『二殺拳』。現在、男子高校生最強と呼び声の高い実力者よ」
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説


セーラー服美人女子高生 ライバル同士の一騎討ち
ヒロワークス
ライト文芸
女子高の2年生まで校内一の美女でスポーツも万能だった立花美帆。しかし、3年生になってすぐ、同じ学年に、美帆と並ぶほどの美女でスポーツも万能な逢沢真凛が転校してきた。
クラスは、隣りだったが、春のスポーツ大会と夏の水泳大会でライバル関係が芽生える。
それに加えて、美帆と真凛は、隣りの男子校の俊介に恋をし、どちらが俊介と付き合えるかを競う恋敵でもあった。
そして、秋の体育祭では、美帆と真凛が走り高跳びや100メートル走、騎馬戦で対決!
その結果、放課後の体育館で一騎討ちをすることに。


ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

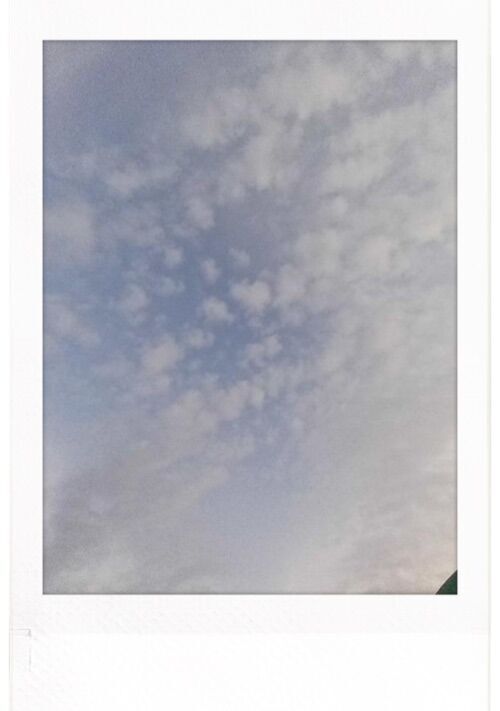
ファンファーレ!
ほしのことば
青春
♡完結まで毎日投稿♡
高校2年生の初夏、ユキは余命1年だと申告された。思えば、今まで「なんとなく」で生きてきた人生。延命治療も勧められたが、ユキは治療はせず、残りの人生を全力で生きることを決意した。
友情・恋愛・行事・学業…。
今まで適当にこなしてきただけの毎日を全力で過ごすことで、ユキの「生」に関する気持ちは段々と動いていく。
主人公のユキの心情を軸に、ユキが全力で生きることで起きる周りの心情の変化も描く。
誰もが感じたことのある青春時代の悩みや感動が、きっとあなたの心に寄り添う作品。

ライトブルー
ジンギスカン
青春
同級生のウザ絡みに頭を抱える椚田司は念願のハッピースクールライフを手に入れるため、遂に陰湿な復讐を決行する。その陰湿さが故、自分が犯人だと気づかれる訳にはいかない。次々と襲い来る「お前が犯人だ」の声を椚田は切り抜けることができるのか。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















