お気に入りに追加
21
あなたにおすすめの小説

病気になって芸能界から消えたアイドル。退院し、復学先の高校には昔の仕事仲間が居たけれど、彼女は俺だと気付かない
月島日向
ライト文芸
俺、日生遼、本名、竹中祐は2年前に病に倒れた。
人気絶頂だった『Cherry’s』のリーダーをやめた。
2年間の闘病生活に一区切りし、久しぶりに高校に通うことになった。けど、誰も俺の事を元アイドルだとは思わない。薬で細くなった手足。そんな細身の体にアンバランスなムーンフェイス(薬の副作用で顔だけが大きくなる事)
。
誰も俺に気付いてはくれない。そう。
2年間、連絡をくれ続け、俺が無視してきた彼女さえも。
もう、全部どうでもよく感じた。

英国紳士の熱い抱擁に、今にも腰が砕けそうです
坂合奏
恋愛
「I love much more than you think(君が思っているよりは、愛しているよ)」
祖母の策略によって、冷徹上司であるイギリス人のジャン・ブラウンと婚約することになってしまった、二十八歳の清水萌衣。
こんな男と結婚してしまったら、この先人生お先真っ暗だと思いきや、意外にもジャンは恋人に甘々の男で……。
あまりの熱い抱擁に、今にも腰が砕けそうです。
※物語の都合で軽い性描写が2~3ページほどあります。

いっぱい命じて〜無自覚SubはヤンキーDomに甘えたい〜
きよひ
BL
無愛想な高一Domヤンキー×Subの自覚がない高三サッカー部員
Normalの諏訪大輝は近頃、謎の体調不良に悩まされていた。
そんな折に出会った金髪の一年生、甘井呂翔。
初めて会った瞬間から甘井呂に惹かれるものがあった諏訪は、Domである彼がPlayする様子を覗き見てしまう。
甘井呂に優しく支配されるSubに自分を重ねて胸を熱くしたことに戸惑う諏訪だが……。
第二性に振り回されながらも、互いだけを求め合うようになる青春の物語。
※現代ベースのDom/Subユニバースの世界観(独自解釈・オリジナル要素あり)
※不良の喧嘩描写、イジメ描写有り
初日は5話更新、翌日からは2話ずつ更新の予定です。

かつみさんは、ねこがすき
にっきょ
BL
「産毒症」あるいは「トキシック」。
人間が体内で毒を生産するようになる病気だ。
産毒症患者の作る毒は他人だけでなくそれを作り出す本人の体も蝕んでいき、やがて当人すらも毒で死亡する。
産毒症である克己は、他人に直接触れることができない。
だが、ある日どうしても人恋しくなりデリヘルで「コウ」というボーイを呼んでしまう。
克己の病気への無知故に気さくに接してくれるコウに恋心を抱くものの、「優しくしてくれるのは仕事だからだろう」と一線を引いた距離を保つ——つもりだったものの、ある日デート先でコウからキスをされたことでその関係が崩れ、コウを避けるようになる克己。
その命の限界が、すぐ近くにあることを隠して。
行動力が怖いデリヘルボーイ×猫好きだけど触れない寂しがりや

家事代行サービスにdomの溺愛は必要ありません!
灯璃
BL
家事代行サービスで働く鏑木(かぶらぎ) 慧(けい)はある日、高級マンションの一室に仕事に向かった。だが、住人の男性は入る事すら拒否し、何故かなかなか中に入れてくれない。
何度かの押し問答の後、なんとか慧は中に入れてもらえる事になった。だが、男性からは冷たくオレの部屋には入るなと言われてしまう。
仕方ないと気にせず仕事をし、気が重いまま次の日も訪れると、昨日とは打って変わって男性、秋水(しゅうすい) 龍士郎(りゅうしろう)は慧の料理を褒めた。
思ったより悪い人ではないのかもと慧が思った時、彼がdom、支配する側の人間だという事に気づいてしまう。subである慧は彼と一定の距離を置こうとするがーー。
みたいな、ゆるいdom/subユニバース。ふんわり過ぎてdom/subユニバースにする必要あったのかとか疑問に思ってはいけない。
※完結しました!ありがとうございました!

実力を隠し「例え長男でも無能に家は継がせん。他家に養子に出す」と親父殿に言われたところまでは計算通りだったが、まさかハーレム生活になるとは
竹井ゴールド
ライト文芸
日本国内トップ5に入る異能力者の名家、東条院。
その宗家本流の嫡子に生まれた東条院青夜は子供の頃に実母に「16歳までに東条院の家を出ないと命を落とす事になる」と予言され、無能を演じ続け、父親や後妻、異母弟や異母妹、親族や許嫁に馬鹿にされながらも、念願適って中学卒業の春休みに東条院家から田中家に養子に出された。
青夜は4月が誕生日なのでギリギリ16歳までに家を出た訳だが。
その後がよろしくない。
青夜を引き取った田中家の義父、一狼は53歳ながら若い妻を持ち、4人の娘の父親でもあったからだ。
妻、21歳、一狼の8人目の妻、愛。
長女、25歳、皇宮警察の異能力部隊所属、弥生。
次女、22歳、田中流空手道場の師範代、葉月。
三女、19歳、離婚したフランス系アメリカ人の3人目の妻が産んだハーフ、アンジェリカ。
四女、17歳、死別した4人目の妻が産んだ中国系ハーフ、シャンリー。
この5人とも青夜は家族となり、
・・・何これ? 少し想定外なんだけど。
【2023/3/23、24hポイント26万4600pt突破】
【2023/7/11、累計ポイント550万pt突破】
【2023/6/5、お気に入り数2130突破】
【アルファポリスのみの投稿です】
【第6回ライト文芸大賞、22万7046pt、2位】
【2023/6/30、メールが来て出版申請、8/1、慰めメール】
【未完】
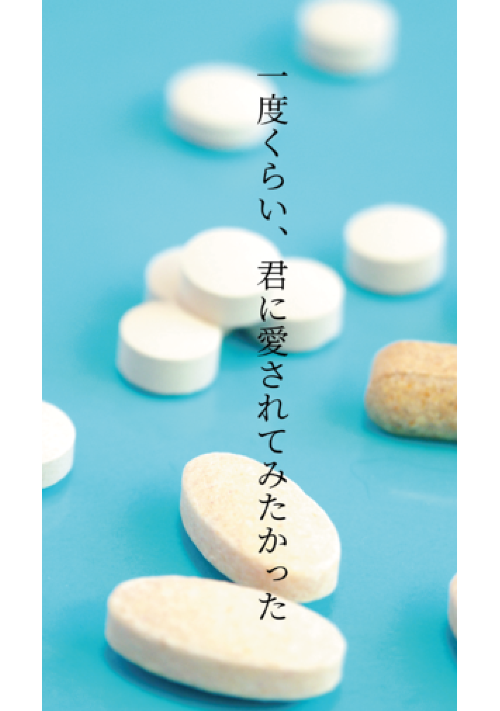

【完結】運命さんこんにちは、さようなら
ハリネズミ
BL
Ωである神楽 咲(かぐら さき)は『運命』と出会ったが、知らない間に番になっていたのは別の人物、影山 燐(かげやま りん)だった。
とある誤解から思うように優しくできない燐と、番=家族だと考え、家族が欲しかったことから簡単に受け入れてしまったマイペースな咲とのちぐはぐでピュアなラブストーリー。
==========
完結しました。ありがとうございました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















