62 / 68
61 タイムリミット
しおりを挟む
がん、がん、と音を立てて階段を上る。怠い身体を引きずるようにして到着した扉の前で、インターホンを押して、待つ。
『はい』
声を聞いただけで、応対しているのが誰か分かった。
ほぼ謹慎状態のようなものなので、外出はないだろう。そう当たりを付けての行動だったが、読みが当たった事にほっとした。ここにいてくれなければ、完全に手詰まりだった。
「葵。……俺だけど」
これではまるで詐欺のようだと思ったが、インターホンの向こうで葵が息を呑むのが分かった。そしてがちゃんと接続が切れる音が響き、慌ただしい足音が聞え、ばんっ! と凄い音を立てて開かれた扉が迫ってきた。
「うわ!」
思いきり仰け反ったが、たったそれだけの動作でも身体を支えきれずによろけてしまう。どすんと尻餅をついた泰介は、そこに立つブラウスとスカート姿の人物へ、文句を言おうと顔を上げて――どんっ、と身体に飛び込んできた衝撃を、座ったまま受け止めた。
「……馬鹿あぁぁ!」
いきなり、罵声を浴びた。
返す言葉が、出てこない。黙ったまま抱きしめ返すと、首に回された手に力がこもった。薄っぺらなパジャマの布地越しに触れた葵の身体は熱く、寒さで凍えた泰介の身体へ徐々に温もりを補完していく。
葵は泣いていた。泰介へしがみ付きながら、小刻みに震えて泣いていた。
きっと、たくさん心配させた。泰介が目覚めるまでの四日間、心細い思いをさせただろう。それは、想像するにあまりある。
――どこにも、いかないで。
声が、過った。
泰介は本当に、葵を泣かせてばかりいる。
「……泣くなって。俺、元気だから」
「元気なわけ、ないじゃない……泰介、なんでそんな格好してるの! 裸足じゃない! そんな状態で走ってきたの……!?」
泰介は、こくりと首を縦に振った。葵の身体が、小さく震えた。
人目につかないようにここまで来るのは、さほど骨ではなかった。泰介のいた病院から葵の家までは徒歩五分程度の距離なので、時間もかからなかったのだ。
ただ、四日間動かさない身体がこれほどまでに鈍るものなのだと、泰介は苦痛と共に思い知った。
一歩ごとに足が震え、無理に走れば腹の吐き気がごろりと動く。間で一度だけ公園の水飲み場で休憩したが、顔を洗い、鏡で見た自分の顔がそれほどやつれてなかったのが泰介にはただ不思議だった。
恐らくは、消耗した身体を癒すのに睡眠が必要だったという、それだけの事に過ぎないのだろう。これでも気絶した時よりは、身体が明らかに癒えていた。
「身体……冷たいよ」
葵が、涙声で言う。泰介は腕の中の温もりに身体を預けながら、吐息をつくように言い返した。
「そんなのは、別に。お前に会えたし」
「なんでっ……!」
言われて、さらりと出てきた台詞に自分でも驚いた。だが、そういう風にしか言葉にできず、他の言葉が出てこない。
葵は言葉にならないと言った様子で、なんで、なんで、と繰り返す。だが泰介の薄着を気遣ってか、自身が羽織った赤いカーディガンに指を掛けたのが見えた。
泰介はそれを阻むように、手に力を込めた。胸板に身体を押し付けられた葵が驚き、固まる。
「……っ、とにかく、うちに入って! 格好あったかくしなきゃ!」
「悪かった。葵」
「え?」
「……いい。なんでもねえよ」
泰介は首を横へ振ると、何事もなかったかのように言った。
「葵。仁科が今どうしてるか分かるか?」
「えっ? 仁科?」
葵は突然の名に面食らっていたが、泰介の顔が真剣そのものだったからか、気圧された様子で答えた。
「今日、待ち合わせて一緒に泰介のお見舞いに行ったの。萩宮にはとっくに帰ってると思うけど……まっすぐ帰ってるなら」
「……そうか」
「泰介、おうち入って。仁科にも連絡入れるから! それに、泰介のお母さんにも電話しなきゃ……っ」
葵が懇願の口調で言って、泰介から身体を離した。泰介も葵の手を借りて立ち上がると、ふらふらと玄関へ歩き、上がり框へとすんと座る。
「泰介、上がって」
「ここでいい。……足、汚れてるし。あと母さんにはまだ連絡すんな。俺が起きてる事は知ってるから。……頼むから」
だが、言いながらまずいかもしれないとは思っていた。まだ佐伯家の方には母からの根回しはないようだが、いつ連絡が入ってもおかしくない。長居は危険かもしれなかった。
「……、拭くもの持ってくるから、待ってて」
葵は何か言いたげな様子だったが、ぱっと身を翻して室内へ駆けていく。
だが泰介は思い直し、「葵!」と呼んで葵を止めた。
「悪りぃ、先に携帯貸してくれ! 仁科にかけたい!」
「……仁科っ?」
振り返った葵は不思議そうな顔をしたが、特に何も言わずにポケットから取り出した携帯を操作して、泰介へ渡した。
「押したら繋がるよ。どうしたの?」
質問する葵には礼だけを言って、泰介は間髪入れずに携帯の通話ボタンを押して耳に当てた。葵はやはりどこか合点がいかない様子だったが、やがてカーディガンを脱ぐと、泰介の肩へ掛けてくれた。
「自分が着てりゃいいじゃん。何やってんだよ寒がり」
コール音の合間に悪態を吐くと、葵が頬を膨らませた。
「だって心配だもん。コートも取ってくるから、もう少しそれで我慢してて!」
それだけを気遣わしげに言い残すと、葵は今度こそ踵を返して室内へ消えた。
カーディガンの前を合わせて俯きながら、泰介は電話を耳に当てて待ち続ける。
既に十コールほど鳴っているが、仁科は呼び出しに応じる気配もなかった。泰介からならともかく葵からの着信ならばすぐに出そうなものなのに、気づいていないのだろうか。
一度、切った。そしてすぐにリダイヤルする。
だが、結果は同じだった。呼び出し音が延々と鳴り続けるだけで、仁科は一向に電話に出ない。もどかしさだけが苛々と増していき、早く出ろよと内心で声を荒げていると、戻ってきた葵がカーディガンの上からコートを被せてきた。
「仁科、出ない?」
濡れたタオルを受け取りながら頷くと、泰介は歯噛みしながら携帯を葵へ返した。
「あー、くそっ。なんで出ないんだ、あのオレンジ頭……っ」
「泰介、仁科と何か約束でもあるの?」
足を拭く、手が止まった。
約束なら、今目の前にいる葵ともしている。自覚はないのだろうが、妙な所で鋭い切り込み方をしてくる葵に圧倒されて、泰介は言葉に詰まってしまう。
「……葵。質問があるんだけど」
「泰介、おうちにちゃんと上がってから」
葵は、我に返った様子で首を横に振った。「それどころじゃ……!」と泰介は言い返すが、葵の目に涙が溜まるのを見て、黙る。
「やだよ……ちゃんと、元気になってくれないと、やだ……」
「……元気だって。多分点滴ばっかでお腹すいて、身体動かさない期間あった所為で、ちょっと鈍ってるだけで」
「馬鹿ぁ!」
葵は半べその顔のまま泰介の隣りへ屈み込むと、コップをぐいと突き出してきた。口元にそれを押し当てられ、ストローを無理やり口に含まされる。泰介はぎょっとしたが、葵は泰介をきつく睨んだ。
「先に飲んで。ちゃんと水分取らなきゃ。後でそれも着替えてもらうから」
有無を言わさぬ調子にさすがに抵抗できず、言われるままに水を飲んだ。ストローを挿したのは病み上がりの泰介への配慮だろうが、実際のところ泰介としては、これは母や葵が心配するほどの疲労ではないと感じていた。この程度の苦痛なら、記憶のフラッシュバックやこちらへ帰還した時の方がきつかった。
だが、周囲がそうは取らない事は分かっている。そして実際に歩行に支障をきたしているのも事実だった。葵は怒ったような泣き顔のままで、泰介をじっと見つめていた。
「ごはん、食べていいって言われてる?」
「分かんねーけど。いいと思う」
「泰介、馬鹿じゃないの? ほんとに抜け出してきたんだ……」
泰介から空のコップを受け取りながら、悲愴な表情で葵が俯く。ぎゅっとコップを握る手は、力が入り過ぎて白かった。
「どうして、そこまでしてここに来たの? 分かんないよ……!」
「お前に……話聞くために、決まってんだろ」
泰介は、葵の腕を掴んだ。
「葵。今すぐ答えろ。俺が倒れた時、あの手紙、どうなった」
「えっ? 手紙?」
葵は、不意を打たれた様子で泰介を見た。
「お前の生みの親からのやつ! 俺が握り潰してただろ! ……あれ、今どこにあるんだ!」
「へっ? 泰介、何で今そんなの……」
「今訊かなきゃヤバいから訊いてる!」
形振り構っていられなかった。仁科に電話が繋がらなかった事実が、泰介をじわじわと急いていた。そんな焦燥から口をついて出た言葉が支離滅裂なものだと分かっていても、ここで言わずにはいられなかった。
葵は、泰介の剣幕に怯えていたが――やがて蚊の鳴くような声で、言った。
「捨てた、よ」
泰介は――拍子抜けした。
「捨てた……?」
「だって、泰介と約束したもん。私」
葵の目から、涙が零れた。
「行かない、って。言ったでしょ? 泰介に。だから、行かないの。手紙は、泰介が握ってたのを取って、破って捨てたの。だから、もうないの……」
身体から、力が抜けた。
「泰介が、倒れて。私、一人で考えたの。泰介が倒れてる間に私が一人で棚橋さんに会いにいったら……泰介、そんなの知ったらすごく怒るでしょ?」
「ああ。怒る」
「やっぱり」
葵は言いながら、ここへ泰介が来て初めて、少しだけ笑った。
「だから。行かない。約束したもん。ちゃんと守るから。安心、してよ」
「……迷ったり、してねえだろうな」
「してない」
はっきりと言った葵は、どこか爽やかなものを感じさせる微笑を浮かべた。
「家族の方が、大事。私が行けば、それだけで家族を傷つけちゃう。……そんなの、分かりきってたことなのに。迷うのも馬鹿だったんだって、泰介が倒れてから気づいたの。……泰介」
葵は、泰介へ頭を下げた。
「弱くて、甘えてばっかりで、ごめんなさい。私、どこかで泰介が助けてくれるって、甘えてたんだと思う。自分から助けてほしいって、言ってもないのに。そんなんだから、病み上がりなのに泰介に気づかれちゃったんだと思う」
「そんな風に絶対、今度こそ二度と言うな」
泰介は葵の肩を掴んで頭を無理やり上げさせると、険しい目で睨んだ。
「お前を甘やかした覚えなんか俺にはねえよ。今回は仕方ないから許してやるけど、次またそんなこと言いやがったら、今度こそぶっ飛ばす」
「……泰介、ほんとに病人なの?」
葵が心配と呆れと、それから少しだけ不可解さが入り混じったような表情で呟き、やがて笑った。目に溜まったままの涙が、頬を伝って流れ落ちた。
「なんで、泰介がそんなに必死になるの」
「当然だろ。こんなの」
「……病院、抜け出してまで?」
「……お前、黙れよ」
何回も言うのは、気恥ずかしいし嫌だと思う。
そしてそんな風に思った時、これでは佐伯蓮香の言葉と同じだと気づいた。
なるほど、と思う。そういうものかもしれない。だが不思議と煩わしさや面倒臭さは感じなかった。多分だが、一度築けた関係を放棄する方が、泰介は嫌だからだろう。
葵の髪を乱暴に撫でてやると、嗚咽を堪えきれずに泣き始めた葵がしゃくり上げた。少し躊躇い、言葉が出て来ず、結局躊躇うのも馬鹿馬鹿しくなって抱きしめた。葵がコップを落とし、こん、とプラスチックが床で跳ねる音が響く。こつんと額同士をぶつけると、泰介は言った。
「いい加減、分かれよ」
またはっきり言えなかったと自分でも気づいていたが、そう言う風にしかしてやれないのが泰介なのだから、仕方がないと思う。
「……泰介。病み上がりって、嘘じゃないの」
「逃げんな。葵」
「……なんで、こんな急なの」
「急で悪いかよ」
「……ううん。いい」
泣き止んだ葵が、嬉しそうに笑った。
そして、いきなり泰介の身体を押し返した。
「でも今は駄目。ちゃんと退院してから」
「は? なんだよそれ」
「駄目だってば」
「……」
あんまり駄目だと連呼されると、思わず憮然としてしまう。むすっとしていると葵が笑ったので余計に面白くなかったが、まあいいか、とも思う。身体を離してやると、葵は泰介の腕を引いて立ち上がった。
「泰介。タオル濡らしたのもっと大きいの用意してくるから、それで汗拭いて、お父さんの服貸すからパジャマ代えよう? このままだと風邪引き直しちゃう。あったかいから、あっちまで頑張って歩いて」
自分でも歩けると思ったが、泰介は素直に頷くと葵の手を借りた。テーブルと椅子の前を通過し、ソファへ座らされながら、泰介は「葵。携帯、もう一回貸してくれるか」と訊いた。
「いいけど、また仁科?」
「ああ」
葵の話では、脅威になる手紙は捨てられていた。おそらく仁科の目には触れていないだろうが、それでも仁科本人の声を聞くまでは、完全に安心するには早い気がしたのだ。泰介は葵から携帯を再度受け取ると、三度通話を試みた。
「……ちっ、出ねえ。電車か?」
「泰介、急ぎならメールしよっか? 直接泰介が打つ方がいいなら、そのまま携帯貸すよ?」
「ああ。メール、このまま俺が打っていい?」
「うん、ロックしてないからそのままメールボタン押して」
「……不用心過ぎじゃねえの? ロックくらい掛けとけよ」
ただでさえ葵は男女問わずモテているのだ。秋沢さくら然り。仁科要平然り。今回の件で変態気質と発覚したさくら辺りなら、平気で葵の携帯くらい覗き見しそうなものだ。思わず顔を上げて葵を睨もうとするが、葵は既に洗面所の方へ駆けこんだのか、姿が見えなかった。嘆息した泰介はメールを作成し始めた。
メールに気づいたらすぐに返信か、可能ならば着信で折り返すようにという命令の文章を打ち込み、文末に吉野泰介と打っておく。普段ならこんな文章では返事は望めないだろうが、四日間寝ていた人間からのメールなら、さすがに仁科も折り返すだろう。送信ボタンを押してから息を吐くと、丁度葵が戻ってきた。
「タオルと、着替え。手伝おうって思ってたけど」
「一人でやるから」
「あはは、言うと思った。思ったより元気そうだし、任せる。ごはん食べて大丈夫だったら、お粥か何か作りたいけど、多分検査とかあるよね。勝手に食べさせちゃまずいよね……?」
「……仁科から返事が来たら、帰る。だから心配すんな」
葵にはそう答えたが、本音を言うと何か食べたかった。だが万一の事を考えると、勝手に何かを胃に入れた所為で葵まで巻き添えを食らうのは忍びない。葵はそんな泰介の内心を見透かしたのか、ほんの少し痛ましそうな表情でこちらを見ていたが、やがてくるりと背を向けて台所の方へ歩いて行った。
そのまま、葵が言う。
「ねえ、泰介。……仁科がどうしたの?」
返事に、困った。死ぬかもしれないので止めに来た、とはさすがに言えない。自分がそんな言葉を人から聞いたら、相手の精神状態を疑うだろう。泰介は答えに窮したまま、「ちょっと、心配なんだよ」と、実に心苦しい返答を述べた。
「え? 心配?」
葵は驚きの顔で泰介を振り返ったが、こちらの様子を見ると背中を向け直す。そして、小声で感想を言った。
「泰介が……仁科のことそんな風に言うの、珍しいね」
「……何だよ、悪いかよ」
「ううん、嬉しい」
葵は背中を向けたままだったが、笑ったのだと何となく分かった。
「仁科って、泰介が優しくしたら多分変わると思うの。仁科、優しいもん」
「まあ、お前には優しい奴だけど。俺にはやっぱりすっげぇ嫌な奴だと思うぜ」
「もう、またそんなこと言ってる。喧嘩になっちゃうよ」
身体をざっと拭いてからタオルを桶へ入れると、葵の父のものだというぶかぶかのシャツに袖を通した。大柄な体格の男性なのでサイズが合わないのは覚悟していたが、袖が絵本で見るお化けのように余るのを見ると、あまりの体格差にげんなりした。ズボンの丈も同様で、このまま歩けば裾を踏んで転ぶだろうと簡単に想像がつく。憮然と袖を睨んでいると、テレビ付近に置かれた鞄が目に留まった。
茶色いその鞄は葵のものだ。通学用とは別に持っている小ぶりの鞄で、学校以外の外出時にいつも提げているので見慣れていた。
そしてその鞄のポケットから僅かに覗いたものが、目に入った瞬間。
顔が、強張った。
「泰介、終わった?」
「葵」
泰介は、罅割れた声で葵を呼ぶ。
「あれ、何だよ」
「え?」
ソファから腰を浮かすと、思ったよりあっさり身体が動いた。即座に葵の鞄へ掴みかかり、ポケットから角がはみ出た紙片を引っ手繰る。見た瞬間から、気づいていた。――同じ、便箋だと。
振り返ると、愕然とする葵と目があった。やがてその目に恐怖が浮かび上がり、葵は口元を抑えて後ずさる。流し台に身体がぶつかり、食器がかたりと揺れた。
「……何、それ。泰介」
片言のような口調で、葵が言った。葵も気付いたのだ。同じ便箋だという事に。
「お前……これ、」
「知らないっ」
葵が血相を変えて、首を横に振った。
「嘘……っ、いつ! いつ、入ったの……っ!」
ふらふらと、葵が駆け寄ってくる。泰介は四つ折りにされた紙片を慌ただしく開き、そこに踊った文字を見た。
時間が、止まった。
そんな、気がした。
佐伯葵様
今日、病院であなたの姿を見ました。侑とそう変わらない顔のあなたがすくすく育っているのを見ると、あの子の事を思い出して胸が塞がる思いです。
あなたへ宛てた手紙は読んでくれましたか。
手紙を佐伯の家に送った事を、私は後悔していました。もしかしたらあの手紙は、あなたには届かなかったのではないか、と。そればかりを考えて過ごしていました。
二十四日からは、修学旅行だそうですね。欠席したと聞きました。
以前私は、あなたと会う日を二十八日と指定しましたが、葵の都合が分からないまま、たった一日だけを指定するのは忍びないと思いました。
今日、二十四日から、二十八日まで。萩宮の喫茶店***で、毎日午後六時まで、あなたを待っています。
他にも書きたい事はたくさんありますが、あなたが行ってしまう前にこれを届けたいので筆を折ります。
最後に、前にも書いたけれど、もう一度。
葵。会いたい。
棚橋円佳
『はい』
声を聞いただけで、応対しているのが誰か分かった。
ほぼ謹慎状態のようなものなので、外出はないだろう。そう当たりを付けての行動だったが、読みが当たった事にほっとした。ここにいてくれなければ、完全に手詰まりだった。
「葵。……俺だけど」
これではまるで詐欺のようだと思ったが、インターホンの向こうで葵が息を呑むのが分かった。そしてがちゃんと接続が切れる音が響き、慌ただしい足音が聞え、ばんっ! と凄い音を立てて開かれた扉が迫ってきた。
「うわ!」
思いきり仰け反ったが、たったそれだけの動作でも身体を支えきれずによろけてしまう。どすんと尻餅をついた泰介は、そこに立つブラウスとスカート姿の人物へ、文句を言おうと顔を上げて――どんっ、と身体に飛び込んできた衝撃を、座ったまま受け止めた。
「……馬鹿あぁぁ!」
いきなり、罵声を浴びた。
返す言葉が、出てこない。黙ったまま抱きしめ返すと、首に回された手に力がこもった。薄っぺらなパジャマの布地越しに触れた葵の身体は熱く、寒さで凍えた泰介の身体へ徐々に温もりを補完していく。
葵は泣いていた。泰介へしがみ付きながら、小刻みに震えて泣いていた。
きっと、たくさん心配させた。泰介が目覚めるまでの四日間、心細い思いをさせただろう。それは、想像するにあまりある。
――どこにも、いかないで。
声が、過った。
泰介は本当に、葵を泣かせてばかりいる。
「……泣くなって。俺、元気だから」
「元気なわけ、ないじゃない……泰介、なんでそんな格好してるの! 裸足じゃない! そんな状態で走ってきたの……!?」
泰介は、こくりと首を縦に振った。葵の身体が、小さく震えた。
人目につかないようにここまで来るのは、さほど骨ではなかった。泰介のいた病院から葵の家までは徒歩五分程度の距離なので、時間もかからなかったのだ。
ただ、四日間動かさない身体がこれほどまでに鈍るものなのだと、泰介は苦痛と共に思い知った。
一歩ごとに足が震え、無理に走れば腹の吐き気がごろりと動く。間で一度だけ公園の水飲み場で休憩したが、顔を洗い、鏡で見た自分の顔がそれほどやつれてなかったのが泰介にはただ不思議だった。
恐らくは、消耗した身体を癒すのに睡眠が必要だったという、それだけの事に過ぎないのだろう。これでも気絶した時よりは、身体が明らかに癒えていた。
「身体……冷たいよ」
葵が、涙声で言う。泰介は腕の中の温もりに身体を預けながら、吐息をつくように言い返した。
「そんなのは、別に。お前に会えたし」
「なんでっ……!」
言われて、さらりと出てきた台詞に自分でも驚いた。だが、そういう風にしか言葉にできず、他の言葉が出てこない。
葵は言葉にならないと言った様子で、なんで、なんで、と繰り返す。だが泰介の薄着を気遣ってか、自身が羽織った赤いカーディガンに指を掛けたのが見えた。
泰介はそれを阻むように、手に力を込めた。胸板に身体を押し付けられた葵が驚き、固まる。
「……っ、とにかく、うちに入って! 格好あったかくしなきゃ!」
「悪かった。葵」
「え?」
「……いい。なんでもねえよ」
泰介は首を横へ振ると、何事もなかったかのように言った。
「葵。仁科が今どうしてるか分かるか?」
「えっ? 仁科?」
葵は突然の名に面食らっていたが、泰介の顔が真剣そのものだったからか、気圧された様子で答えた。
「今日、待ち合わせて一緒に泰介のお見舞いに行ったの。萩宮にはとっくに帰ってると思うけど……まっすぐ帰ってるなら」
「……そうか」
「泰介、おうち入って。仁科にも連絡入れるから! それに、泰介のお母さんにも電話しなきゃ……っ」
葵が懇願の口調で言って、泰介から身体を離した。泰介も葵の手を借りて立ち上がると、ふらふらと玄関へ歩き、上がり框へとすんと座る。
「泰介、上がって」
「ここでいい。……足、汚れてるし。あと母さんにはまだ連絡すんな。俺が起きてる事は知ってるから。……頼むから」
だが、言いながらまずいかもしれないとは思っていた。まだ佐伯家の方には母からの根回しはないようだが、いつ連絡が入ってもおかしくない。長居は危険かもしれなかった。
「……、拭くもの持ってくるから、待ってて」
葵は何か言いたげな様子だったが、ぱっと身を翻して室内へ駆けていく。
だが泰介は思い直し、「葵!」と呼んで葵を止めた。
「悪りぃ、先に携帯貸してくれ! 仁科にかけたい!」
「……仁科っ?」
振り返った葵は不思議そうな顔をしたが、特に何も言わずにポケットから取り出した携帯を操作して、泰介へ渡した。
「押したら繋がるよ。どうしたの?」
質問する葵には礼だけを言って、泰介は間髪入れずに携帯の通話ボタンを押して耳に当てた。葵はやはりどこか合点がいかない様子だったが、やがてカーディガンを脱ぐと、泰介の肩へ掛けてくれた。
「自分が着てりゃいいじゃん。何やってんだよ寒がり」
コール音の合間に悪態を吐くと、葵が頬を膨らませた。
「だって心配だもん。コートも取ってくるから、もう少しそれで我慢してて!」
それだけを気遣わしげに言い残すと、葵は今度こそ踵を返して室内へ消えた。
カーディガンの前を合わせて俯きながら、泰介は電話を耳に当てて待ち続ける。
既に十コールほど鳴っているが、仁科は呼び出しに応じる気配もなかった。泰介からならともかく葵からの着信ならばすぐに出そうなものなのに、気づいていないのだろうか。
一度、切った。そしてすぐにリダイヤルする。
だが、結果は同じだった。呼び出し音が延々と鳴り続けるだけで、仁科は一向に電話に出ない。もどかしさだけが苛々と増していき、早く出ろよと内心で声を荒げていると、戻ってきた葵がカーディガンの上からコートを被せてきた。
「仁科、出ない?」
濡れたタオルを受け取りながら頷くと、泰介は歯噛みしながら携帯を葵へ返した。
「あー、くそっ。なんで出ないんだ、あのオレンジ頭……っ」
「泰介、仁科と何か約束でもあるの?」
足を拭く、手が止まった。
約束なら、今目の前にいる葵ともしている。自覚はないのだろうが、妙な所で鋭い切り込み方をしてくる葵に圧倒されて、泰介は言葉に詰まってしまう。
「……葵。質問があるんだけど」
「泰介、おうちにちゃんと上がってから」
葵は、我に返った様子で首を横に振った。「それどころじゃ……!」と泰介は言い返すが、葵の目に涙が溜まるのを見て、黙る。
「やだよ……ちゃんと、元気になってくれないと、やだ……」
「……元気だって。多分点滴ばっかでお腹すいて、身体動かさない期間あった所為で、ちょっと鈍ってるだけで」
「馬鹿ぁ!」
葵は半べその顔のまま泰介の隣りへ屈み込むと、コップをぐいと突き出してきた。口元にそれを押し当てられ、ストローを無理やり口に含まされる。泰介はぎょっとしたが、葵は泰介をきつく睨んだ。
「先に飲んで。ちゃんと水分取らなきゃ。後でそれも着替えてもらうから」
有無を言わさぬ調子にさすがに抵抗できず、言われるままに水を飲んだ。ストローを挿したのは病み上がりの泰介への配慮だろうが、実際のところ泰介としては、これは母や葵が心配するほどの疲労ではないと感じていた。この程度の苦痛なら、記憶のフラッシュバックやこちらへ帰還した時の方がきつかった。
だが、周囲がそうは取らない事は分かっている。そして実際に歩行に支障をきたしているのも事実だった。葵は怒ったような泣き顔のままで、泰介をじっと見つめていた。
「ごはん、食べていいって言われてる?」
「分かんねーけど。いいと思う」
「泰介、馬鹿じゃないの? ほんとに抜け出してきたんだ……」
泰介から空のコップを受け取りながら、悲愴な表情で葵が俯く。ぎゅっとコップを握る手は、力が入り過ぎて白かった。
「どうして、そこまでしてここに来たの? 分かんないよ……!」
「お前に……話聞くために、決まってんだろ」
泰介は、葵の腕を掴んだ。
「葵。今すぐ答えろ。俺が倒れた時、あの手紙、どうなった」
「えっ? 手紙?」
葵は、不意を打たれた様子で泰介を見た。
「お前の生みの親からのやつ! 俺が握り潰してただろ! ……あれ、今どこにあるんだ!」
「へっ? 泰介、何で今そんなの……」
「今訊かなきゃヤバいから訊いてる!」
形振り構っていられなかった。仁科に電話が繋がらなかった事実が、泰介をじわじわと急いていた。そんな焦燥から口をついて出た言葉が支離滅裂なものだと分かっていても、ここで言わずにはいられなかった。
葵は、泰介の剣幕に怯えていたが――やがて蚊の鳴くような声で、言った。
「捨てた、よ」
泰介は――拍子抜けした。
「捨てた……?」
「だって、泰介と約束したもん。私」
葵の目から、涙が零れた。
「行かない、って。言ったでしょ? 泰介に。だから、行かないの。手紙は、泰介が握ってたのを取って、破って捨てたの。だから、もうないの……」
身体から、力が抜けた。
「泰介が、倒れて。私、一人で考えたの。泰介が倒れてる間に私が一人で棚橋さんに会いにいったら……泰介、そんなの知ったらすごく怒るでしょ?」
「ああ。怒る」
「やっぱり」
葵は言いながら、ここへ泰介が来て初めて、少しだけ笑った。
「だから。行かない。約束したもん。ちゃんと守るから。安心、してよ」
「……迷ったり、してねえだろうな」
「してない」
はっきりと言った葵は、どこか爽やかなものを感じさせる微笑を浮かべた。
「家族の方が、大事。私が行けば、それだけで家族を傷つけちゃう。……そんなの、分かりきってたことなのに。迷うのも馬鹿だったんだって、泰介が倒れてから気づいたの。……泰介」
葵は、泰介へ頭を下げた。
「弱くて、甘えてばっかりで、ごめんなさい。私、どこかで泰介が助けてくれるって、甘えてたんだと思う。自分から助けてほしいって、言ってもないのに。そんなんだから、病み上がりなのに泰介に気づかれちゃったんだと思う」
「そんな風に絶対、今度こそ二度と言うな」
泰介は葵の肩を掴んで頭を無理やり上げさせると、険しい目で睨んだ。
「お前を甘やかした覚えなんか俺にはねえよ。今回は仕方ないから許してやるけど、次またそんなこと言いやがったら、今度こそぶっ飛ばす」
「……泰介、ほんとに病人なの?」
葵が心配と呆れと、それから少しだけ不可解さが入り混じったような表情で呟き、やがて笑った。目に溜まったままの涙が、頬を伝って流れ落ちた。
「なんで、泰介がそんなに必死になるの」
「当然だろ。こんなの」
「……病院、抜け出してまで?」
「……お前、黙れよ」
何回も言うのは、気恥ずかしいし嫌だと思う。
そしてそんな風に思った時、これでは佐伯蓮香の言葉と同じだと気づいた。
なるほど、と思う。そういうものかもしれない。だが不思議と煩わしさや面倒臭さは感じなかった。多分だが、一度築けた関係を放棄する方が、泰介は嫌だからだろう。
葵の髪を乱暴に撫でてやると、嗚咽を堪えきれずに泣き始めた葵がしゃくり上げた。少し躊躇い、言葉が出て来ず、結局躊躇うのも馬鹿馬鹿しくなって抱きしめた。葵がコップを落とし、こん、とプラスチックが床で跳ねる音が響く。こつんと額同士をぶつけると、泰介は言った。
「いい加減、分かれよ」
またはっきり言えなかったと自分でも気づいていたが、そう言う風にしかしてやれないのが泰介なのだから、仕方がないと思う。
「……泰介。病み上がりって、嘘じゃないの」
「逃げんな。葵」
「……なんで、こんな急なの」
「急で悪いかよ」
「……ううん。いい」
泣き止んだ葵が、嬉しそうに笑った。
そして、いきなり泰介の身体を押し返した。
「でも今は駄目。ちゃんと退院してから」
「は? なんだよそれ」
「駄目だってば」
「……」
あんまり駄目だと連呼されると、思わず憮然としてしまう。むすっとしていると葵が笑ったので余計に面白くなかったが、まあいいか、とも思う。身体を離してやると、葵は泰介の腕を引いて立ち上がった。
「泰介。タオル濡らしたのもっと大きいの用意してくるから、それで汗拭いて、お父さんの服貸すからパジャマ代えよう? このままだと風邪引き直しちゃう。あったかいから、あっちまで頑張って歩いて」
自分でも歩けると思ったが、泰介は素直に頷くと葵の手を借りた。テーブルと椅子の前を通過し、ソファへ座らされながら、泰介は「葵。携帯、もう一回貸してくれるか」と訊いた。
「いいけど、また仁科?」
「ああ」
葵の話では、脅威になる手紙は捨てられていた。おそらく仁科の目には触れていないだろうが、それでも仁科本人の声を聞くまでは、完全に安心するには早い気がしたのだ。泰介は葵から携帯を再度受け取ると、三度通話を試みた。
「……ちっ、出ねえ。電車か?」
「泰介、急ぎならメールしよっか? 直接泰介が打つ方がいいなら、そのまま携帯貸すよ?」
「ああ。メール、このまま俺が打っていい?」
「うん、ロックしてないからそのままメールボタン押して」
「……不用心過ぎじゃねえの? ロックくらい掛けとけよ」
ただでさえ葵は男女問わずモテているのだ。秋沢さくら然り。仁科要平然り。今回の件で変態気質と発覚したさくら辺りなら、平気で葵の携帯くらい覗き見しそうなものだ。思わず顔を上げて葵を睨もうとするが、葵は既に洗面所の方へ駆けこんだのか、姿が見えなかった。嘆息した泰介はメールを作成し始めた。
メールに気づいたらすぐに返信か、可能ならば着信で折り返すようにという命令の文章を打ち込み、文末に吉野泰介と打っておく。普段ならこんな文章では返事は望めないだろうが、四日間寝ていた人間からのメールなら、さすがに仁科も折り返すだろう。送信ボタンを押してから息を吐くと、丁度葵が戻ってきた。
「タオルと、着替え。手伝おうって思ってたけど」
「一人でやるから」
「あはは、言うと思った。思ったより元気そうだし、任せる。ごはん食べて大丈夫だったら、お粥か何か作りたいけど、多分検査とかあるよね。勝手に食べさせちゃまずいよね……?」
「……仁科から返事が来たら、帰る。だから心配すんな」
葵にはそう答えたが、本音を言うと何か食べたかった。だが万一の事を考えると、勝手に何かを胃に入れた所為で葵まで巻き添えを食らうのは忍びない。葵はそんな泰介の内心を見透かしたのか、ほんの少し痛ましそうな表情でこちらを見ていたが、やがてくるりと背を向けて台所の方へ歩いて行った。
そのまま、葵が言う。
「ねえ、泰介。……仁科がどうしたの?」
返事に、困った。死ぬかもしれないので止めに来た、とはさすがに言えない。自分がそんな言葉を人から聞いたら、相手の精神状態を疑うだろう。泰介は答えに窮したまま、「ちょっと、心配なんだよ」と、実に心苦しい返答を述べた。
「え? 心配?」
葵は驚きの顔で泰介を振り返ったが、こちらの様子を見ると背中を向け直す。そして、小声で感想を言った。
「泰介が……仁科のことそんな風に言うの、珍しいね」
「……何だよ、悪いかよ」
「ううん、嬉しい」
葵は背中を向けたままだったが、笑ったのだと何となく分かった。
「仁科って、泰介が優しくしたら多分変わると思うの。仁科、優しいもん」
「まあ、お前には優しい奴だけど。俺にはやっぱりすっげぇ嫌な奴だと思うぜ」
「もう、またそんなこと言ってる。喧嘩になっちゃうよ」
身体をざっと拭いてからタオルを桶へ入れると、葵の父のものだというぶかぶかのシャツに袖を通した。大柄な体格の男性なのでサイズが合わないのは覚悟していたが、袖が絵本で見るお化けのように余るのを見ると、あまりの体格差にげんなりした。ズボンの丈も同様で、このまま歩けば裾を踏んで転ぶだろうと簡単に想像がつく。憮然と袖を睨んでいると、テレビ付近に置かれた鞄が目に留まった。
茶色いその鞄は葵のものだ。通学用とは別に持っている小ぶりの鞄で、学校以外の外出時にいつも提げているので見慣れていた。
そしてその鞄のポケットから僅かに覗いたものが、目に入った瞬間。
顔が、強張った。
「泰介、終わった?」
「葵」
泰介は、罅割れた声で葵を呼ぶ。
「あれ、何だよ」
「え?」
ソファから腰を浮かすと、思ったよりあっさり身体が動いた。即座に葵の鞄へ掴みかかり、ポケットから角がはみ出た紙片を引っ手繰る。見た瞬間から、気づいていた。――同じ、便箋だと。
振り返ると、愕然とする葵と目があった。やがてその目に恐怖が浮かび上がり、葵は口元を抑えて後ずさる。流し台に身体がぶつかり、食器がかたりと揺れた。
「……何、それ。泰介」
片言のような口調で、葵が言った。葵も気付いたのだ。同じ便箋だという事に。
「お前……これ、」
「知らないっ」
葵が血相を変えて、首を横に振った。
「嘘……っ、いつ! いつ、入ったの……っ!」
ふらふらと、葵が駆け寄ってくる。泰介は四つ折りにされた紙片を慌ただしく開き、そこに踊った文字を見た。
時間が、止まった。
そんな、気がした。
佐伯葵様
今日、病院であなたの姿を見ました。侑とそう変わらない顔のあなたがすくすく育っているのを見ると、あの子の事を思い出して胸が塞がる思いです。
あなたへ宛てた手紙は読んでくれましたか。
手紙を佐伯の家に送った事を、私は後悔していました。もしかしたらあの手紙は、あなたには届かなかったのではないか、と。そればかりを考えて過ごしていました。
二十四日からは、修学旅行だそうですね。欠席したと聞きました。
以前私は、あなたと会う日を二十八日と指定しましたが、葵の都合が分からないまま、たった一日だけを指定するのは忍びないと思いました。
今日、二十四日から、二十八日まで。萩宮の喫茶店***で、毎日午後六時まで、あなたを待っています。
他にも書きたい事はたくさんありますが、あなたが行ってしまう前にこれを届けたいので筆を折ります。
最後に、前にも書いたけれど、もう一度。
葵。会いたい。
棚橋円佳
0
お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説


Solomon's Gate
坂森大我
SF
人類が宇宙に拠点を設けてから既に千年が経過していた。地球の衛星軌道上から始まった宇宙開発も火星圏、木星圏を経て今や土星圏にまで及んでいる。
ミハル・エアハルトは木星圏に住む十八歳の専門学校生。彼女の学び舎はセントグラード航宙士学校といい、その名の通りパイロットとなるための学校である。
実技は常に学年トップの成績であったものの、ミハルは最終学年になっても就職活動すらしていなかった。なぜなら彼女は航宙機への興味を失っていたからだ。しかし、強要された航宙機レースへの参加を境にミハルの人生が一変していく。レースにより思い出した。幼き日に覚えた感情。誰よりも航宙機が好きだったことを。
ミハルがパイロットとして歩む決意をした一方で、太陽系は思わぬ事態に発展していた。
主要な宙域となるはずだった土星が突如として消失してしまったのだ。加えて消失痕にはワームホールが出現し、異なる銀河との接続を果たしてしまう。
ワームホールの出現まではまだ看過できた人類。しかし、調査を進めるにつれ望みもしない事実が明らかとなっていく。人類は選択を迫られることになった。
人類にとって最悪のシナリオが現実味を帯びていく。星系の情勢とは少しの接点もなかったミハルだが、巨大な暗雲はいとも容易く彼女を飲み込んでいった。
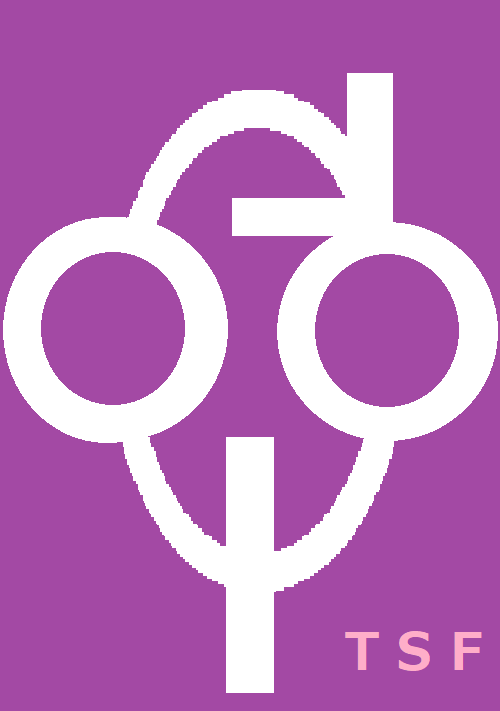



保健室の秘密...
とんすけ
大衆娯楽
僕のクラスには、保健室に登校している「吉田さん」という女の子がいた。
吉田さんは目が大きくてとても可愛らしく、いつも艶々な髪をなびかせていた。
吉田さんはクラスにあまりなじめておらず、朝のHRが終わると帰りの時間まで保健室で過ごしていた。
僕は吉田さんと話したことはなかったけれど、大人っぽさと綺麗な容姿を持つ吉田さんに密かに惹かれていた。
そんな吉田さんには、ある噂があった。
「授業中に保健室に行けば、性処理をしてくれる子がいる」
それが吉田さんだと、男子の間で噂になっていた。


獣人の里の仕置き小屋
真木
恋愛
ある狼獣人の里には、仕置き小屋というところがある。
獣人は愛情深く、その執着ゆえに伴侶が逃げ出すとき、獣人の夫が伴侶に仕置きをするところだ。
今夜もまた一人、里から出ようとして仕置き小屋に連れられてきた少女がいた。
仕置き小屋にあるものを見て、彼女は……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















