7 / 19
ふきだすところを想像してふきだしそうに
しおりを挟む
「あっ、そんなことが」
結月は状況を想像してみた。向き合って座った二人。一方がお茶漬けを噴水のように吹き出したら……どういうことになるのかは誰にでも容易に分かろう。そのときの様子が脳裏のスクリーンに鮮明に浮かび、再生される。結月は忍び笑いをした。
「これはもう辛抱たまらないとなって、隣り合わせに座ることに変えたのです」
「斜めではだめだったんですね?」
「斜めの角度にも、ご飯粒が飛んでテーブルに付着していたので。どうせ席を移動するのなら、万全を期さねばならない」
我慢できなくなって結月は笑い声を立てた。「そんなにおかしいか」と不満そうなアッシャーを、アレッサが憮然として「笑われるようなことをやっているのだから」と注意した。
「アッシャーさん、と呼んでもいいですか」
目尻を指先で拭いつつ、許可を求める。アッシャーは訝しげに唇を尖らせ、即答した。
「いいとも。名前がアッシャーなのだから当然だよ」
「ではアッシャーさん、聞いた限りではあなたの方が全面的に悪いみたいです」
「言うな。僕も理解はできているのだ」
「やっぱり」
「やっぱりとはどういう意味だ?」
この台詞にアレッサが素早く、「“やっぱり”とは」と始めようとする。が、これに被せるようにして、かつさらに素早くアッシャーが「知っている!」と言い返した。
「言葉の意味を尋ねてるんじゃないっ。そのくらい知っていることを、おまえは知っているだろうが」
アッシャーが荒っぽい言い回しになるのを、アレッサは何故か微笑で受け流す。
「結月、さん。そなたは何という意味で“やっぱり”と使ったのだ? 教えてください」
語尾が「です・ます」調と「だ・である」調が入り乱れて揃ってないが、今指摘するといたずらに話が長引きそう。
(ここはスルーして、説明だけしておこう。安藤さんを待たせてしまっているし)
「アッシャーさん、日本語お上手ですね」
「む? そ、そうか? まあ、アレッサほどではないが身に付いたと思っている」
若干、照れたように目をそらすアッシャー。
「それほど優秀なアッシャーさんなら、ご自身の悪いことも、どうすればいいのかもお分かりのはずだと思っていたんです。だから、やっぱりと言いました。――こんな説明で伝わりますか?」
「――分かる」
アッシャーは口の両端をちょっと上向きにして、大いに得心したようだ。
「二度も三度も同じミスをせぬよう、これからは欲望を抑え、今まで以上に注意する。心に誓う」
台詞だけ聞くと、小さな子供の頃に習う凄く当たり前のことを言っているだけな気もするが、当人が満足げなのでいいのだろう。
異国の人を知るための取材という観点からすれば物足りないが、ずっと関わってばかりもいられない。
(キャラクター作りの材料としてなら、充分にインスピレーションを受けたし)
結月は心の中のメモにイメージをしっかり刻みつけつつ、二人に目礼した。
「二度もお邪魔してすみませんでした。残りの旅も楽しんでください」
「いえ。あなたになら何度お邪魔されてもよい」
いい感じの微笑を返すアッシャー。“お邪魔”の“お”は取るべきだと思うが。
その隣に座っていたアレッサは席を立ち、アッシャーと対面する位置の椅子に座り直した。それからこほんと咳払いをし、
「えー、アッシャー。あまり時間を掛けてもいられないので、残りを食すように。もう食べ頃を過ぎている」
と促した。彼だけ急に緊張したように見受けられるが、その理由が結月には分からなかった。
後ろ髪引かれる思いはあったものの、いい加減にタイムアップだろう。安藤が結月を探してこちらにやって来たら、話は続けられるものの、騒がしくなっていよいよお店と他のお客に迷惑だ。
もう一度お辞儀して彼らのテーブルから離れると、自分のいた席へと戻り……かけたところで思い出した。本来の目的は、落っことした消しゴムを見付けること。自分のおっちょこちょいぶりに苦笑いを禁じ得ない。
少々ばつが悪いが、アッシャー達のいるテーブルの横を通って、さらに奥へと歩いて行き、ようやく見付ける。大きくて古そうな空調機器の足元に、ぴたりと寄り添うように消しゴムがあった。
十分近く経過していたというのに、安藤は結月の出したノートをまだ読んでいた。分量から言って、読むのにそんなに時間は掛からないはず――と不審がった結月だが、安藤の手元のノートを受けから除くと、全然別のページを開いていた。
(もう、しょうがないなあ。こういう人だと分かっているから、よその社向けの作品のアイディアは別個にしているけれども、最初はびっくりした)
「お待たせしてすみません、安藤さん。やっと見付けてきました」
「え? 早かったですねと言おうとしていたのに」
とぼけたことを言う。安藤は基本的に活字、いや文字中毒者なのかもしれない。字を目で一旦追い始めると、集中力が凄いし、際限がない。
「十分ぐらい経っていますよ。それで……ご感想を」
恐る恐る尋ねる。編集者にプロットなどの出来を尋ねるこの瞬間は、何度経験してもどきどきする。
結月は状況を想像してみた。向き合って座った二人。一方がお茶漬けを噴水のように吹き出したら……どういうことになるのかは誰にでも容易に分かろう。そのときの様子が脳裏のスクリーンに鮮明に浮かび、再生される。結月は忍び笑いをした。
「これはもう辛抱たまらないとなって、隣り合わせに座ることに変えたのです」
「斜めではだめだったんですね?」
「斜めの角度にも、ご飯粒が飛んでテーブルに付着していたので。どうせ席を移動するのなら、万全を期さねばならない」
我慢できなくなって結月は笑い声を立てた。「そんなにおかしいか」と不満そうなアッシャーを、アレッサが憮然として「笑われるようなことをやっているのだから」と注意した。
「アッシャーさん、と呼んでもいいですか」
目尻を指先で拭いつつ、許可を求める。アッシャーは訝しげに唇を尖らせ、即答した。
「いいとも。名前がアッシャーなのだから当然だよ」
「ではアッシャーさん、聞いた限りではあなたの方が全面的に悪いみたいです」
「言うな。僕も理解はできているのだ」
「やっぱり」
「やっぱりとはどういう意味だ?」
この台詞にアレッサが素早く、「“やっぱり”とは」と始めようとする。が、これに被せるようにして、かつさらに素早くアッシャーが「知っている!」と言い返した。
「言葉の意味を尋ねてるんじゃないっ。そのくらい知っていることを、おまえは知っているだろうが」
アッシャーが荒っぽい言い回しになるのを、アレッサは何故か微笑で受け流す。
「結月、さん。そなたは何という意味で“やっぱり”と使ったのだ? 教えてください」
語尾が「です・ます」調と「だ・である」調が入り乱れて揃ってないが、今指摘するといたずらに話が長引きそう。
(ここはスルーして、説明だけしておこう。安藤さんを待たせてしまっているし)
「アッシャーさん、日本語お上手ですね」
「む? そ、そうか? まあ、アレッサほどではないが身に付いたと思っている」
若干、照れたように目をそらすアッシャー。
「それほど優秀なアッシャーさんなら、ご自身の悪いことも、どうすればいいのかもお分かりのはずだと思っていたんです。だから、やっぱりと言いました。――こんな説明で伝わりますか?」
「――分かる」
アッシャーは口の両端をちょっと上向きにして、大いに得心したようだ。
「二度も三度も同じミスをせぬよう、これからは欲望を抑え、今まで以上に注意する。心に誓う」
台詞だけ聞くと、小さな子供の頃に習う凄く当たり前のことを言っているだけな気もするが、当人が満足げなのでいいのだろう。
異国の人を知るための取材という観点からすれば物足りないが、ずっと関わってばかりもいられない。
(キャラクター作りの材料としてなら、充分にインスピレーションを受けたし)
結月は心の中のメモにイメージをしっかり刻みつけつつ、二人に目礼した。
「二度もお邪魔してすみませんでした。残りの旅も楽しんでください」
「いえ。あなたになら何度お邪魔されてもよい」
いい感じの微笑を返すアッシャー。“お邪魔”の“お”は取るべきだと思うが。
その隣に座っていたアレッサは席を立ち、アッシャーと対面する位置の椅子に座り直した。それからこほんと咳払いをし、
「えー、アッシャー。あまり時間を掛けてもいられないので、残りを食すように。もう食べ頃を過ぎている」
と促した。彼だけ急に緊張したように見受けられるが、その理由が結月には分からなかった。
後ろ髪引かれる思いはあったものの、いい加減にタイムアップだろう。安藤が結月を探してこちらにやって来たら、話は続けられるものの、騒がしくなっていよいよお店と他のお客に迷惑だ。
もう一度お辞儀して彼らのテーブルから離れると、自分のいた席へと戻り……かけたところで思い出した。本来の目的は、落っことした消しゴムを見付けること。自分のおっちょこちょいぶりに苦笑いを禁じ得ない。
少々ばつが悪いが、アッシャー達のいるテーブルの横を通って、さらに奥へと歩いて行き、ようやく見付ける。大きくて古そうな空調機器の足元に、ぴたりと寄り添うように消しゴムがあった。
十分近く経過していたというのに、安藤は結月の出したノートをまだ読んでいた。分量から言って、読むのにそんなに時間は掛からないはず――と不審がった結月だが、安藤の手元のノートを受けから除くと、全然別のページを開いていた。
(もう、しょうがないなあ。こういう人だと分かっているから、よその社向けの作品のアイディアは別個にしているけれども、最初はびっくりした)
「お待たせしてすみません、安藤さん。やっと見付けてきました」
「え? 早かったですねと言おうとしていたのに」
とぼけたことを言う。安藤は基本的に活字、いや文字中毒者なのかもしれない。字を目で一旦追い始めると、集中力が凄いし、際限がない。
「十分ぐらい経っていますよ。それで……ご感想を」
恐る恐る尋ねる。編集者にプロットなどの出来を尋ねるこの瞬間は、何度経験してもどきどきする。
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

家出したとある辺境夫人の話
あゆみノワ@書籍『完全別居の契約婚〜』
恋愛
『突然ではございますが、私はあなたと離縁し、このお屋敷を去ることにいたしました』
これは、一通の置き手紙からはじまった一組の心通わぬ夫婦のお語。
※ちゃんとハッピーエンドです。ただし、主人公にとっては。
※他サイトでも掲載します。

誰が悪役令嬢ですって? ~ 転身同体
崎田毅駿
恋愛
“私”安生悠子は、学生時代に憧れた藤塚弘史と思い掛けぬデートをして、知らぬ間に浮かれたいたんだろう。よせばいいのに、二十代半ばにもなって公園の出入り口にある車止めのポールに乗った。その結果、すっ転んで頭を強打し、気を失ってしまった。
次に目が覚めると、当然ながら身体の節々が痛い。だけど、それよりも気になるのはなんだか周りの様子が全然違うんですけど! 真実や原因は分からないが、信じがたいことに、自分が第三巻まで読んだ小説の物語世界の登場人物に転生してしまったらしい?
一体誰に転生したのか。最悪なのは、小説のヒロインたるリーヌ・ロイロットを何かにつけて嫌い、婚約を破棄させて男を奪い、蹴落とそうとし続けたいわいゆる悪役令嬢ノアル・シェイクフリードだ。が、どうやら“今”この物語世界の時間は、第四巻以降と思われる。三巻のラスト近くでノアルは落命しているので、ノアルに転生は絶対にあり得ない。少しほっとする“私”だったけれども、痛む身体を引きずってようやく見付けた鏡で確かめた“今”の自身の顔は、何故かノアル・シェイクフリードその人だった。
混乱のあまり、「どうして悪役令嬢なんかに?」と短く叫ぶ“私”安生。その次の瞬間、別の声が頭の中に聞こえてきた。「誰が悪役令嬢ですって?」
混乱の拍車が掛かる“私”だけれども、自分がノアル・シェイクフリードの身体に入り込んでいたのが紛れもない事実のよう。しかもノアルもまだ意識があると来ては、一体何が起きてこうなった?

コイカケ
崎田毅駿
大衆娯楽
いわゆる財閥の一つ、神田部家の娘・静流の婚約者候補を決める、八名参加のトーナメントが開催されることになった。戦いはギャンブル。神田部家はその歴史において、重要な場面では博打で勝利を収めて、大きくなり、発展を遂げてきた背景がある。故に次期当主とも言える静流の結婚相手は、ギャンブルに強くなければならないというのだ。

アルバートの屈辱
プラネットプラント
恋愛
妻の姉に恋をして妻を蔑ろにするアルバートとそんな夫を愛するのを諦めてしまった妻の話。
『詰んでる不憫系悪役令嬢はチャラ男騎士として生活しています』の10年ほど前の話ですが、ほぼ無関係なので単体で読めます。
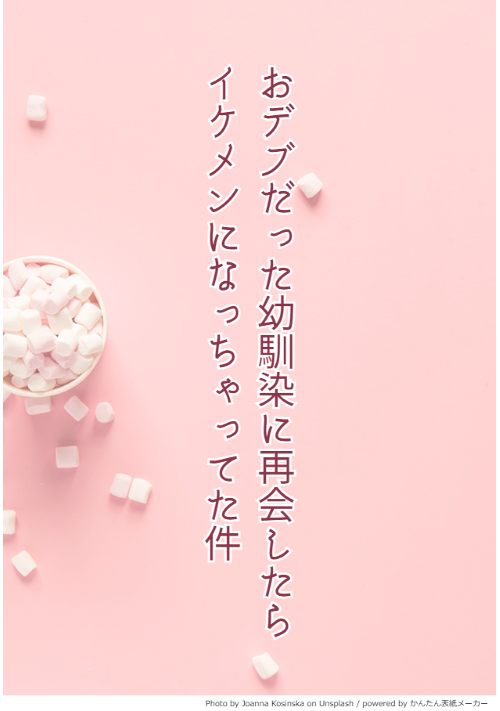
おデブだった幼馴染に再会したら、イケメンになっちゃってた件
実川えむ
恋愛
子供のころチビでおデブちゃんだったあの子が、王子様みたいなイケメン俳優になって現れました。
ちょっと、聞いてないんですけど。
※以前、エブリスタで別名義で書いていたお話です(現在非公開)。
※不定期更新
※カクヨム・ベリーズカフェでも掲載中
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















