お気に入りに追加
26
あなたにおすすめの小説

クラスメイトの美少女と無人島に流された件
桜井正宗
青春
修学旅行で離島へ向かう最中――悪天候に見舞われ、台風が直撃。船が沈没した。
高校二年の早坂 啓(はやさか てつ)は、気づくと砂浜で寝ていた。周囲を見渡すとクラスメイトで美少女の天音 愛(あまね まな)が隣に倒れていた。
どうやら、漂流して流されていたようだった。
帰ろうにも島は『無人島』。
しばらくは島で生きていくしかなくなった。天音と共に無人島サバイバルをしていくのだが……クラスの女子が次々に見つかり、やがてハーレムに。
男一人と女子十五人で……取り合いに発展!?

スライム10,000体討伐から始まるハーレム生活
昼寝部
ファンタジー
この世界は12歳になったら神からスキルを授かることができ、俺も12歳になった時にスキルを授かった。
しかし、俺のスキルは【@&¥#%】と正しく表記されず、役に立たないスキルということが判明した。
そんな中、両親を亡くした俺は妹に不自由のない生活を送ってもらうため、冒険者として活動を始める。
しかし、【@&¥#%】というスキルでは強いモンスターを討伐することができず、3年間冒険者をしてもスライムしか倒せなかった。
そんなある日、俺がスライムを10,000体討伐した瞬間、スキル【@&¥#%】がチートスキルへと変化して……。
これは、ある日突然、最強の冒険者となった主人公が、今まで『スライムしか倒せないゴミ』とバカにしてきた奴らに“ざまぁ”し、美少女たちと幸せな日々を過ごす物語。


小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

惑星保護区
ラムダムランプ
SF
この物語について
旧人類と別宇宙から来た種族との出来事にまつわる話です。
概要
かつて地球に住んでいた旧人類と別宇宙から来た種族がトラブルを引き起こし、その事が発端となり、地球が宇宙の中で【保護区】(地球で言う自然保護区)に制定され
制定後は、他の星の種族は勿論、あらゆる別宇宙の種族は地球や現人類に対し、安易に接触、交流、知能や技術供与する事を固く禁じられた。
現人類に対して、未だ地球以外の種族が接触して来ないのは、この為である。
初めて書きますので読みにくいと思いますが、何卒宜しくお願い致します。

45歳のおっさん、異世界召喚に巻き込まれる
よっしぃ
ファンタジー
2月26日から29日現在まで4日間、アルファポリスのファンタジー部門1位達成!感謝です!
小説家になろうでも10位獲得しました!
そして、カクヨムでもランクイン中です!
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
スキルを強奪する為に異世界召喚を実行した欲望まみれの権力者から逃げるおっさん。
いつものように電車通勤をしていたわけだが、気が付けばまさかの異世界召喚に巻き込まれる。
欲望者から逃げ切って反撃をするか、隠れて地味に暮らすか・・・・
●●●●●●●●●●●●●●●
小説家になろうで執筆中の作品です。
アルファポリス、、カクヨムでも公開中です。
現在見直し作業中です。
変換ミス、打ちミス等が多い作品です。申し訳ありません。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。
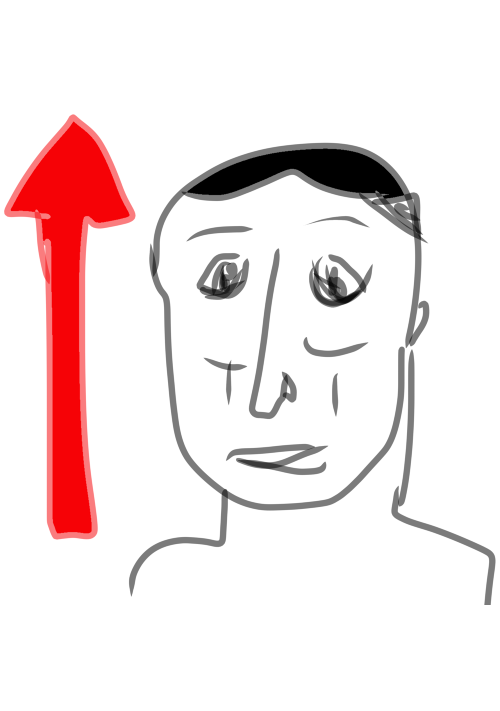
もうダメだ。俺の人生詰んでいる。
静馬⭐︎GTR
SF
『私小説』と、『機動兵士』的小説がゴッチャになっている小説です。百話完結だけは、約束できます。
(アメブロ「なつかしゲームブック館」にて投稿されております)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















