お気に入りに追加
33
あなたにおすすめの小説

日本一のイケメン俳優に惚れられてしまったんですが
五右衛門
BL
月井晴彦は過去のトラウマから自信を失い、人と距離を置きながら高校生活を送っていた。ある日、帰り道で少女が複数の男子からナンパされている場面に遭遇する。普段は関わりを避ける晴彦だが、僅かばかりの勇気を出して、手が震えながらも必死に少女を助けた。
しかし、その少女は実は美男子俳優の白銀玲央だった。彼は日本一有名な高校生俳優で、高い演技力と美しすぎる美貌も相まって多くの賞を受賞している天才である。玲央は何かお礼がしたいと言うも、晴彦は動揺してしまい逃げるように立ち去る。しかし数日後、体育館に集まった全校生徒の前で現れたのは、あの時の青年だった──

消えない思い
樹木緑
BL
オメガバース:僕には忘れられない夏がある。彼が好きだった。ただ、ただ、彼が好きだった。
高校3年生 矢野浩二 α
高校3年生 佐々木裕也 α
高校1年生 赤城要 Ω
赤城要は運命の番である両親に憧れ、両親が出会った高校に入学します。
自分も両親の様に運命の番が欲しいと思っています。
そして高校の入学式で出会った矢野浩二に、淡い感情を抱き始めるようになります。
でもあるきっかけを基に、佐々木裕也と出会います。
彼こそが要の探し続けた運命の番だったのです。
そして3人の運命が絡み合って、それぞれが、それぞれの選択をしていくと言うお話です。

【完結】運命さんこんにちは、さようなら
ハリネズミ
BL
Ωである神楽 咲(かぐら さき)は『運命』と出会ったが、知らない間に番になっていたのは別の人物、影山 燐(かげやま りん)だった。
とある誤解から思うように優しくできない燐と、番=家族だと考え、家族が欲しかったことから簡単に受け入れてしまったマイペースな咲とのちぐはぐでピュアなラブストーリー。
==========
完結しました。ありがとうございました。

オッサン、エルフの森の歌姫【ディーバ】になる
クロタ
BL
召喚儀式の失敗で、現代日本から異世界に飛ばされて捨てられたオッサン(39歳)と、彼を拾って過保護に庇護するエルフ(300歳、外見年齢20代)のお話です。

キスから始まる主従契約
毒島らいおん
BL
異世界に召喚された挙げ句に、間違いだったと言われて見捨てられた葵。そんな葵を助けてくれたのは、美貌の公爵ローレルだった。
ローレルの優しげな雰囲気に葵は惹かれる。しかも向こうからキスをしてきて葵は有頂天になるが、それは魔法で主従契約を結ぶためだった。
しかも週に1回キスをしないと死んでしまう、とんでもないもので――。
◯
それでもなんとか彼に好かれようとがんばる葵と、実は腹黒いうえに秘密を抱えているローレルが、過去やら危機やらを乗り越えて、最後には最高の伴侶なるお話。
(全48話・毎日12時に更新)

【完結・BL】DT騎士団員は、騎士団長様に告白したい!【騎士団員×騎士団長】
彩華
BL
とある平和な国。「ある日」を境に、この国を守る騎士団へ入団することを夢見ていたトーマは、無事にその夢を叶えた。それもこれも、あの日の初恋。騎士団長・アランに一目惚れしたため。年若いトーマの恋心は、日々募っていくばかり。自身の気持ちを、アランに伝えるべきか? そんな悶々とする騎士団員の話。
「好きだって言えるなら、言いたい。いや、でもやっぱ、言わなくても良いな……。ああ゛―!でも、アラン様が好きだって言いてぇよー!!」

【完結】僕の大事な魔王様
綾雅(要らない悪役令嬢1/7発売)
BL
母竜と眠っていた幼いドラゴンは、なぜか人間が住む都市へ召喚された。意味が分からず本能のままに隠れたが発見され、引きずり出されて兵士に殺されそうになる。
「お母さん、お父さん、助けて! 魔王様!!」
魔族の守護者であった魔王様がいない世界で、神様に縋る人間のように叫ぶ。必死の嘆願は幼ドラゴンの魔力を得て、遠くまで響いた。そう、隣接する別の世界から魔王を召喚するほどに……。
俺様魔王×いたいけな幼ドラゴン――成長するまで見守ると決めた魔王は、徐々に真剣な想いを抱くようになる。彼の想いは幼過ぎる竜に届くのか。ハッピーエンド確定
【同時掲載】 小説家になろう、アルファポリス、カクヨム、エブリスタ
2023/12/11……完結
2023/09/28……カクヨム、週間恋愛 57位
2023/09/23……エブリスタ、トレンドBL 5位
2023/09/23……小説家になろう、日間ファンタジー 39位
2023/09/21……連載開始
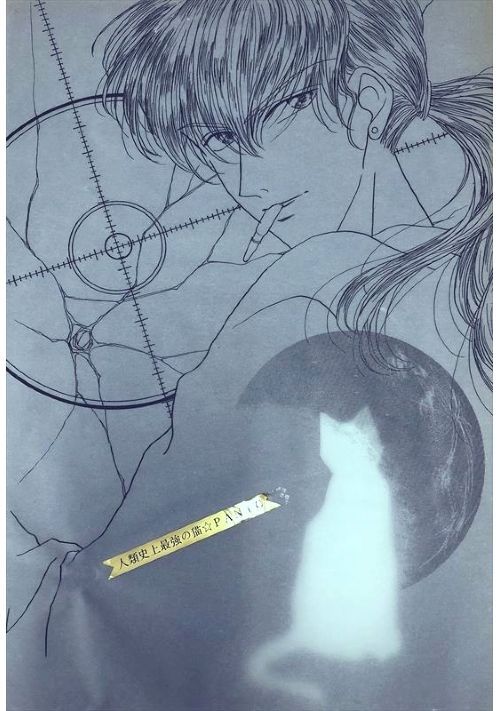
【完結】帝王様は、表でも裏でも有名な飼い猫を溺愛する
綾雅(要らない悪役令嬢1/7発売)
BL
離地暦201年――人類は地球を離れ、宇宙で新たな生活を始め200年近くが経過した。貧困の差が広がる地球を捨て、裕福な人々は宇宙へ進出していく。
狙撃手として裏で名を馳せたルーイは、地球での狙撃の帰りに公安に拘束された。逃走経路を疎かにした結果だ。表では一流モデルとして有名な青年が裏路地で保護される、滅多にない事態に公安は彼を疑うが……。
表も裏もひっくるめてルーイの『飼い主』である権力者リューアは公安からの問い合わせに対し、彼の保護と称した強制連行を指示する。
権力者一族の争いに巻き込まれるルーイと、ひたすらに彼に甘いリューアの愛の行方は?
【重複投稿】エブリスタ、アルファポリス、小説家になろう
【注意】※印は性的表現有ります
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















