お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説

ワイルド・ソルジャー
アサシン工房
SF
時は199X年。世界各地で戦争が行われ、終戦を迎えようとしていた。
世界は荒廃し、辺りは無法者で溢れかえっていた。
主人公のマティアス・マッカーサーは、かつては裕福な家庭で育ったが、戦争に巻き込まれて両親と弟を失い、その後傭兵となって生きてきた。
旅の途中、人間離れした強さを持つ大柄な軍人ハンニバル・クルーガーにスカウトされ、マティアスは軍人として活動することになる。
ハンニバルと共に任務をこなしていくうちに、冷徹で利己主義だったマティアスは利害を超えた友情を覚えていく。
世紀末の荒廃したアメリカを舞台にしたバトルファンタジー。
他の小説サイトにも投稿しています。

幻想遊撃隊ブレイド・ダンサーズ
黒陽 光
SF
その日、1973年のある日。空から降りてきたのは神の祝福などではなく、終わりのない戦いをもたらす招かれざる来訪者だった。
現れた地球外の不明生命体、"幻魔"と名付けられた異形の怪異たちは地球上の六ヶ所へ巣を落着させ、幻基巣と呼ばれるそこから無尽蔵に湧き出て地球人類に対しての侵略行動を開始した。コミュニケーションを取ることすら叶わぬ異形を相手に、人類は嘗てない絶滅戦争へと否応なく突入していくこととなる。
そんな中、人類は全高8mの人型機動兵器、T.A.M.S(タムス)の開発に成功。遂に人類は幻魔と対等に渡り合えるようにはなったものの、しかし戦いは膠着状態に陥り。四十年あまりの長きに渡り続く戦いは、しかし未だにその終わりが見えないでいた。
――――これは、絶望に抗う少年少女たちの物語。多くの犠牲を払い、それでも生きて。いなくなってしまった愛しい者たちの遺した想いを道標とし、抗い続ける少年少女たちの物語だ。
表紙は頂き物です、ありがとうございます。
※カクヨムさんでも重複掲載始めました。

CREATED WORLD
猫手水晶
SF
惑星アケラは、大気汚染や森林伐採により、いずれ人類が住み続けることができなくなってしまう事がわかった。
惑星アケラに住む人類は絶滅を免れる為に、安全に生活を送れる場所を探す事が必要となった。
宇宙に人間が住める惑星を探そうという提案もあったが、惑星アケラの周りに人が住めるような環境の星はなく、見つける前に人類が絶滅してしまうだろうという理由で、現実性に欠けるものだった。
「人間が住めるような場所を自分で作ろう」という提案もあったが、資材や重力の方向の問題により、それも現実性に欠ける。
そこで科学者は「自分達で世界を構築するのなら、世界をそのまま宇宙に作るのではなく、自分達で『宇宙』にあたる空間を新たに作り出し、その空間で人間が生活できるようにすれば良いのではないか。」と。
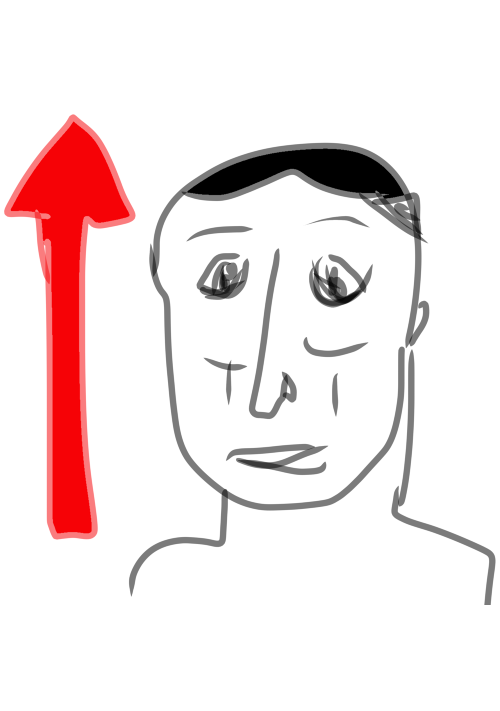
もうダメだ。俺の人生詰んでいる。
静馬⭐︎GTR
SF
『私小説』と、『機動兵士』的小説がゴッチャになっている小説です。百話完結だけは、約束できます。
(アメブロ「なつかしゲームブック館」にて投稿されております)

INNER NAUTS(インナーノーツ) 〜精神と異界の航海者〜
SunYoh
SF
ーー22世紀半ばーー
魂の源とされる精神世界「インナースペース」……その次元から無尽蔵のエネルギーを得ることを可能にした代償に、さまざまな災害や心身への未知の脅威が発生していた。
「インナーノーツ」は、時空を超越する船<アマテラス>を駆り、脅威の解消に「インナースペース」へ挑む。
<第一章 「誘い」>
粗筋
余剰次元活動艇<アマテラス>の最終試験となった有人起動試験は、原因不明のトラブルに見舞われ、中断を余儀なくされたが、同じ頃、「インナーノーツ」が所属する研究機関で保護していた少女「亜夢」にもまた異変が起こっていた……5年もの間、眠り続けていた彼女の深層無意識の中で何かが目覚めようとしている。
「インナースペース」のエネルギーを解放する特異な能力を秘めた亜夢の目覚めは、即ち、「インナースペース」のみならず、物質世界である「現象界(この世)」にも甚大な被害をもたらす可能性がある。
ーー亜夢が目覚める前に、この脅威を解消するーー
「インナーノーツ」は、この使命を胸に<アマテラス>を駆り、未知なる世界「インナースペース」へと旅立つ!
そこで彼らを待ち受けていたものとは……
※この物語はフィクションです。実際の国や団体などとは関係ありません。
※SFジャンルですが殆ど空想科学です。
※セルフレイティングに関して、若干抵触する可能性がある表現が含まれます。
※「小説家になろう」、「ノベルアップ+」でも連載中
※スピリチュアル系の内容を含みますが、特定の宗教団体等とは一切関係無く、布教、勧誘等を目的とした作品ではありません。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

日本列島、時震により転移す!
黄昏人
ファンタジー
2023年(現在)、日本列島が後に時震と呼ばれる現象により、500年以上の時を超え1492年(過去)の世界に転移した。移転したのは本州、四国、九州とその周辺の島々であり、現在の日本は過去の時代に飛ばされ、過去の日本は現在の世界に飛ばされた。飛ばされた現在の日本はその文明を支え、国民を食わせるためには早急に莫大な資源と食料が必要である。過去の日本は現在の世界を意識できないが、取り残された北海道と沖縄は国富の大部分を失い、戦国日本を抱え途方にくれる。人々は、政府は何を思いどうふるまうのか。

【おんJ】 彡(゚)(゚)ファッ!?ワイが天下分け目の関ヶ原の戦いに!?
俊也
SF
これまた、かつて私がおーぷん2ちゃんねるに載せ、ご好評頂きました戦国架空戦記SSです。
この他、
「新訳 零戦戦記」
「総統戦記」もよろしくお願いします。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















