21 / 94
第13章:俺が”シスコン”だなどと、妄言を吐くのも大概にしてもらいたい(本気)
しおりを挟む
ふいに。
背筋に悪寒がはしり、俺は椅子から立ち上がって後方へ身体をひねり、クラスの天井をあおぎみた。そこには普段から設置されている照明があるだけで、不審なものは何も見あたらない。少なくとも、肉眼では。
「ど、どうしたんだ、一体」
俺の動作が急だったせいだろう、石田が目を点にして問いかけてくる。
「……何でもない」
そう応えたのは、無論韜晦というものである。突然、頭上から誰かに見られているように感じたのだ。そしてその視線は霊的なもの、つまり"魔"の気配をともなっていた。だからこそ、俺の”魔覚”で捉えることができたのである。
実を言えば休み時間に入ったあたりからこれに似た、得体の知れない違和感はあった。その正体を、視線の圧が増したことにより、唐突に知覚できた、というべきだろうか。だとすれば、少し前から何者かに観察されていた、ということになるのか。
もちろん、常人の仕業なはずがないし、今朝のように幽霊がいるわけでもないだろう(明るい内からそうそう幽霊に登場されてたまるか、いくらいい加減なこの小説でも)。それに今の感覚には、前世でおぼえがある。そう、魔導士に"遠視"の魔法で覗かれた時に、近いものがあるのだ。
この現世で何者かが、魔法をもちいて俺を監視しているのだろうか。だとすればそいつは、俺や光琉の前世を知っている者なのか。記憶を取り戻したばかりのこのタイミングで干渉してくるのだから、そう考えるのが自然だろうが……
あるいは、更にうがった見方をすれば。こうして覗かれるのは、果たして今朝がはじめてのことなのだろうか? なにせ昨日までの俺は魔覚をそなえておらず、魔法による干渉を受けたとしても、目に見える実害が生じないかぎり一切気づきようがなかったのだ。
「おい、お前今日はおかしいぞ。大丈夫か?」
立ったまま黙りこんだ俺に、石田が胡乱そうな視線を向けてきた。事情を知らないこいつには、今朝の俺の言動が一々奇妙にうつるのも当然だろう。
……ここは頭を切り替えることにしよう。俺は自分に言い聞かせた。この魔力をともなった視線が、俺だけでなく光琉にまで向けられている、という可能性も当然あり得る。そう考えると気が気ではなかったが、今の時点で思いわずらってもどうしようもないのも、また確かだった。何かしらの判断をくだすには、現状あまりにも情報が不足している。
「いや、昼休みに奥杜に呼び出されてしまったから、購買に行く時間がないことに急に思い当たってな。昼飯をどうしようかと考えていたんだ」
椅子に座りながら、この日何度目になるか既にわからないごまかしを敢行する。自分でもずい分不自然な言い訳だと思ったのだが、腐れ縁の友人はあっさり食いついてきた。痛々しい言動に似ず、素直なやつなんだよなあ。
「あれ、お前今日は、光琉ちゃんに弁当作ってもらってないの?」
「今朝は色々あってな」
ここで多少、注釈をくわえた方が良いだろう。光琉は普段の朝、自分と俺の分の弁当を手作りで用意してくれる。親父が家にいる時は、そこに親父の分も加わる。おかげで俺はいつも、ひもじさとは無縁の昼休みを過ごすことができるわけである。
そう、意外に思われるかもしれないが、うちのアホ妹は料理をするのが好きで、しかもその腕前は中々のものなのである。我が家では家事を兄妹で分担しているが、こと料理に関しては、本人たっての希望もあり光琉に一任している。そしてダイニングテーブルに並ぶ食事も、毎日の弁当も、「食えないことはない」などというレベルではなく、「これ、金取れるんじゃね?」と思わせられるほどのクオリティに仕上げてくるのだった。"人は見かけによらない"の生きた実例、だと俺は思っている。
「何だ、残念。光琉ちゃんは料理上手いからなあ、楽しみにしてたのに」
石田がこう言うのだから、上の評価が身内の贔屓目でないことはわかっていただけるだろう。
「って、何でお前が楽しみにするんだよ。言っておくけど、分けてやらんぞ? たとえ持ってきていても」
「良いじゃないかよ、ケチだなあ。いつもあんだけたくさん作ってくれるんだから、ひとりで食い切るのも大変だろ?」
「どれだけ多かろうと、光琉が俺のために作った弁当だ。他人には米粒ひとつたりとも、与えてたまるか」
当然のことを言っただけなのに、それを聞くと石田は急に、呆れと蔑みの入り混じった視線を俺に向けてきた。
……ん、何だ? 似非ビジュアル系男にそんな反応をされる覚えはないぞ。あと、こめかみに手を当てて頭を振る仕草やめろ。
「……前々から思っていたけど、お前ってシスコンだよな」
「ちょっとまてなんだそれはどこからでてきたことばだヒトギキノワルイことをいうなネモハモナイうわさをたてるなフーヒョーヒガイにもほどがあるメイヨキソンでうったえるぞこのやろー」
的外れにもほどがある石田の言い分に、句読点を打つのも忘れてまくしたててしまった。
俺がシスコン? 馬鹿も休み休み言ってほしい。そりゃあ今朝、前世の記憶を取り戻してからは、メルティアの生まれ変わりとして少し(ほんのすこ~~~し)意識してしまったが、それ以前は類人猿としか認識していなかったのである。石田に"シスコン"などと呼ばれるいわれは、微塵もない。ウソ・大げさ・まぎらわしい発言とはこのことである。
「だってお前たち、家ではよく、一緒に◯ーファミをやるくらい仲良いんだろ」
「は? 兄妹だったら、そんなの普通だろ。家族なんだから」
「……駅前の繁華街を、肩並べてあるいている姿をよく見かける、という目撃証言が出ているんだが」
「そりゃ買い物に付き合ったり、休みの日に一緒に遊びに行くくらいはするさ。兄妹だもん」
「……まさか、夜はいまだに一緒の布団で寝ている、なんてことはないよな」
「アホか。俺も妹も寝るのはベッドだ。一緒に入るのだって、せいぜい夜に雷が鳴る日くらいだ」
2週間ほど前だったか、夜に強雨となった。雷も鳴り響き、窓の外からカーテンが青白く照らされた11時ごろ、パジャマ姿の光琉が突然俺の部屋に入ってきて、「あたし、今日はここで寝るから」と早口で宣言して勝手に俺のベッドに潜りこんでしまった。かすかに身体をふるわせていたので、雷がこわかったんだな、とすぐに察した。
いつまでも子供みたいなやつだと呆れつつも、そう珍しいことでもないので、仕方ないから並んで寝てやることにした。もっとも、招かれざる妹は俺のベッドに入っただけで安心したのか、俺が床に就く頃にはとっくにクークーと寝息を立てていたが。一体何のために俺のところへ来たんだか……苦笑をにじませながら、俺は妹のかたわらに自分の身体を滑り込ませたのだった。
と、一緒に寝たと言ってもその経緯はこんなもので、何もやましい部分はない。至ってケンゼンな兄妹関係である。
「……俺、しばらくお前には近づかないから。お前も話しかけないで」
「待てええッ! 何だそのゴミを見るような眼は!?」
きたないものを避けるように椅子から立ち上がり、広げた右手で顔を覆いながら離れていこうとする石田の左腕を、強引につかんで引き留める。こいつが話しかけてこないのは一向に構わんが、こうまで気味悪がられるのはさすがに業腹である。こっちは何もおかしなことは言ってないのに。
「お前は妹がいないからわからないんだよ。世の中の兄妹ってのは、大体こんなもんだぞ」
「うん、お前がどんな幻想の海におぼれようと、それはお前の勝手だ。俺にはお前を否定する権利はない、自由の翼をひろげてどこまでも飛んでいけばいいさ(吐息のような声)。でも俺には話しかけないで」
「こっちの声がまるで心に届いてねえだと!?」
何だこいつ、思いこみの激しさが山岸◯花子レベルか?
なおも去っていこうとするナルシスト野郎を、俺は必死に食い止めた。そうしてぎゃあぎゃあと騒いでいるうちに、いつの間にか2限目開始のチャイムが鳴ったのにも気づかなかった。
「……お前たち、とっくに休み時間は終わってるんだがな」
突然、しわがれた声が聞こえて振り向くと、すでに教壇には2限目の世界史を担当するベテラン教師が立っており、こめかみに青筋を浮かせながらこちらをにらんでいた。
「あ、やっちまった……」と思ったが、手遅れである。俺と石田以外のクラスメイトたちは、もう全員着席していた。石田がさっきまで座っていた前の席の生徒も、とっくに戻っていた。俺たちに向けられる彼・彼女らの視線が痛かった。
俺と石田は世界史教師から教室の後ろに立つことを命じられ、そのまま授業を受けることとなった。こんな羽目におちいるのは、小学生以来の体験である。前方に並ぶ席の各所から、明らかに俺たちに向けられた忍び笑いが断続的に聞こえてくる。ぐぅ、いたたまれねえ!
それもこれもすべて、隣のナルシスト野郎が俺に"シスコン"などというヌレギヌを着せてくるせいだった。横目でにらんでやったが、その石田はと言えば立ちながらも俺から露骨に顔をそむけ、視線を合わせようとしなかった。いまだにエンガチョあつかいしてきやがる。こ、この野郎……
この場で怒鳴り声をあげてもさらに立場が悪化するだけなので、今はだまって耐えるしかない。羞恥と憤懣に身を焦がしながら、一刻もはやくこの世界史の授業が終わることを願わずにいられなかった。
ちなみに。
先ほどまで感じていた上空からの視線の圧も、それにともなう魔力の気配も、この頃にはいつの間にか消えていた。
背筋に悪寒がはしり、俺は椅子から立ち上がって後方へ身体をひねり、クラスの天井をあおぎみた。そこには普段から設置されている照明があるだけで、不審なものは何も見あたらない。少なくとも、肉眼では。
「ど、どうしたんだ、一体」
俺の動作が急だったせいだろう、石田が目を点にして問いかけてくる。
「……何でもない」
そう応えたのは、無論韜晦というものである。突然、頭上から誰かに見られているように感じたのだ。そしてその視線は霊的なもの、つまり"魔"の気配をともなっていた。だからこそ、俺の”魔覚”で捉えることができたのである。
実を言えば休み時間に入ったあたりからこれに似た、得体の知れない違和感はあった。その正体を、視線の圧が増したことにより、唐突に知覚できた、というべきだろうか。だとすれば、少し前から何者かに観察されていた、ということになるのか。
もちろん、常人の仕業なはずがないし、今朝のように幽霊がいるわけでもないだろう(明るい内からそうそう幽霊に登場されてたまるか、いくらいい加減なこの小説でも)。それに今の感覚には、前世でおぼえがある。そう、魔導士に"遠視"の魔法で覗かれた時に、近いものがあるのだ。
この現世で何者かが、魔法をもちいて俺を監視しているのだろうか。だとすればそいつは、俺や光琉の前世を知っている者なのか。記憶を取り戻したばかりのこのタイミングで干渉してくるのだから、そう考えるのが自然だろうが……
あるいは、更にうがった見方をすれば。こうして覗かれるのは、果たして今朝がはじめてのことなのだろうか? なにせ昨日までの俺は魔覚をそなえておらず、魔法による干渉を受けたとしても、目に見える実害が生じないかぎり一切気づきようがなかったのだ。
「おい、お前今日はおかしいぞ。大丈夫か?」
立ったまま黙りこんだ俺に、石田が胡乱そうな視線を向けてきた。事情を知らないこいつには、今朝の俺の言動が一々奇妙にうつるのも当然だろう。
……ここは頭を切り替えることにしよう。俺は自分に言い聞かせた。この魔力をともなった視線が、俺だけでなく光琉にまで向けられている、という可能性も当然あり得る。そう考えると気が気ではなかったが、今の時点で思いわずらってもどうしようもないのも、また確かだった。何かしらの判断をくだすには、現状あまりにも情報が不足している。
「いや、昼休みに奥杜に呼び出されてしまったから、購買に行く時間がないことに急に思い当たってな。昼飯をどうしようかと考えていたんだ」
椅子に座りながら、この日何度目になるか既にわからないごまかしを敢行する。自分でもずい分不自然な言い訳だと思ったのだが、腐れ縁の友人はあっさり食いついてきた。痛々しい言動に似ず、素直なやつなんだよなあ。
「あれ、お前今日は、光琉ちゃんに弁当作ってもらってないの?」
「今朝は色々あってな」
ここで多少、注釈をくわえた方が良いだろう。光琉は普段の朝、自分と俺の分の弁当を手作りで用意してくれる。親父が家にいる時は、そこに親父の分も加わる。おかげで俺はいつも、ひもじさとは無縁の昼休みを過ごすことができるわけである。
そう、意外に思われるかもしれないが、うちのアホ妹は料理をするのが好きで、しかもその腕前は中々のものなのである。我が家では家事を兄妹で分担しているが、こと料理に関しては、本人たっての希望もあり光琉に一任している。そしてダイニングテーブルに並ぶ食事も、毎日の弁当も、「食えないことはない」などというレベルではなく、「これ、金取れるんじゃね?」と思わせられるほどのクオリティに仕上げてくるのだった。"人は見かけによらない"の生きた実例、だと俺は思っている。
「何だ、残念。光琉ちゃんは料理上手いからなあ、楽しみにしてたのに」
石田がこう言うのだから、上の評価が身内の贔屓目でないことはわかっていただけるだろう。
「って、何でお前が楽しみにするんだよ。言っておくけど、分けてやらんぞ? たとえ持ってきていても」
「良いじゃないかよ、ケチだなあ。いつもあんだけたくさん作ってくれるんだから、ひとりで食い切るのも大変だろ?」
「どれだけ多かろうと、光琉が俺のために作った弁当だ。他人には米粒ひとつたりとも、与えてたまるか」
当然のことを言っただけなのに、それを聞くと石田は急に、呆れと蔑みの入り混じった視線を俺に向けてきた。
……ん、何だ? 似非ビジュアル系男にそんな反応をされる覚えはないぞ。あと、こめかみに手を当てて頭を振る仕草やめろ。
「……前々から思っていたけど、お前ってシスコンだよな」
「ちょっとまてなんだそれはどこからでてきたことばだヒトギキノワルイことをいうなネモハモナイうわさをたてるなフーヒョーヒガイにもほどがあるメイヨキソンでうったえるぞこのやろー」
的外れにもほどがある石田の言い分に、句読点を打つのも忘れてまくしたててしまった。
俺がシスコン? 馬鹿も休み休み言ってほしい。そりゃあ今朝、前世の記憶を取り戻してからは、メルティアの生まれ変わりとして少し(ほんのすこ~~~し)意識してしまったが、それ以前は類人猿としか認識していなかったのである。石田に"シスコン"などと呼ばれるいわれは、微塵もない。ウソ・大げさ・まぎらわしい発言とはこのことである。
「だってお前たち、家ではよく、一緒に◯ーファミをやるくらい仲良いんだろ」
「は? 兄妹だったら、そんなの普通だろ。家族なんだから」
「……駅前の繁華街を、肩並べてあるいている姿をよく見かける、という目撃証言が出ているんだが」
「そりゃ買い物に付き合ったり、休みの日に一緒に遊びに行くくらいはするさ。兄妹だもん」
「……まさか、夜はいまだに一緒の布団で寝ている、なんてことはないよな」
「アホか。俺も妹も寝るのはベッドだ。一緒に入るのだって、せいぜい夜に雷が鳴る日くらいだ」
2週間ほど前だったか、夜に強雨となった。雷も鳴り響き、窓の外からカーテンが青白く照らされた11時ごろ、パジャマ姿の光琉が突然俺の部屋に入ってきて、「あたし、今日はここで寝るから」と早口で宣言して勝手に俺のベッドに潜りこんでしまった。かすかに身体をふるわせていたので、雷がこわかったんだな、とすぐに察した。
いつまでも子供みたいなやつだと呆れつつも、そう珍しいことでもないので、仕方ないから並んで寝てやることにした。もっとも、招かれざる妹は俺のベッドに入っただけで安心したのか、俺が床に就く頃にはとっくにクークーと寝息を立てていたが。一体何のために俺のところへ来たんだか……苦笑をにじませながら、俺は妹のかたわらに自分の身体を滑り込ませたのだった。
と、一緒に寝たと言ってもその経緯はこんなもので、何もやましい部分はない。至ってケンゼンな兄妹関係である。
「……俺、しばらくお前には近づかないから。お前も話しかけないで」
「待てええッ! 何だそのゴミを見るような眼は!?」
きたないものを避けるように椅子から立ち上がり、広げた右手で顔を覆いながら離れていこうとする石田の左腕を、強引につかんで引き留める。こいつが話しかけてこないのは一向に構わんが、こうまで気味悪がられるのはさすがに業腹である。こっちは何もおかしなことは言ってないのに。
「お前は妹がいないからわからないんだよ。世の中の兄妹ってのは、大体こんなもんだぞ」
「うん、お前がどんな幻想の海におぼれようと、それはお前の勝手だ。俺にはお前を否定する権利はない、自由の翼をひろげてどこまでも飛んでいけばいいさ(吐息のような声)。でも俺には話しかけないで」
「こっちの声がまるで心に届いてねえだと!?」
何だこいつ、思いこみの激しさが山岸◯花子レベルか?
なおも去っていこうとするナルシスト野郎を、俺は必死に食い止めた。そうしてぎゃあぎゃあと騒いでいるうちに、いつの間にか2限目開始のチャイムが鳴ったのにも気づかなかった。
「……お前たち、とっくに休み時間は終わってるんだがな」
突然、しわがれた声が聞こえて振り向くと、すでに教壇には2限目の世界史を担当するベテラン教師が立っており、こめかみに青筋を浮かせながらこちらをにらんでいた。
「あ、やっちまった……」と思ったが、手遅れである。俺と石田以外のクラスメイトたちは、もう全員着席していた。石田がさっきまで座っていた前の席の生徒も、とっくに戻っていた。俺たちに向けられる彼・彼女らの視線が痛かった。
俺と石田は世界史教師から教室の後ろに立つことを命じられ、そのまま授業を受けることとなった。こんな羽目におちいるのは、小学生以来の体験である。前方に並ぶ席の各所から、明らかに俺たちに向けられた忍び笑いが断続的に聞こえてくる。ぐぅ、いたたまれねえ!
それもこれもすべて、隣のナルシスト野郎が俺に"シスコン"などというヌレギヌを着せてくるせいだった。横目でにらんでやったが、その石田はと言えば立ちながらも俺から露骨に顔をそむけ、視線を合わせようとしなかった。いまだにエンガチョあつかいしてきやがる。こ、この野郎……
この場で怒鳴り声をあげてもさらに立場が悪化するだけなので、今はだまって耐えるしかない。羞恥と憤懣に身を焦がしながら、一刻もはやくこの世界史の授業が終わることを願わずにいられなかった。
ちなみに。
先ほどまで感じていた上空からの視線の圧も、それにともなう魔力の気配も、この頃にはいつの間にか消えていた。
0
お気に入りに追加
121
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

「君を愛するつもりはない」と言ったら、泣いて喜ばれた
菱田もな
恋愛
完璧令嬢と名高い公爵家の一人娘シャーロットとの婚約が決まった第二皇子オズワルド。しかし、これは政略結婚で、婚約にもシャーロット自身にも全く興味がない。初めての顔合わせの場で「悪いが、君を愛するつもりはない」とはっきり告げたオズワルドに、シャーロットはなぜか歓喜の涙を浮かべて…?
※他サイトでも掲載中しております。

スキルが【アイテムボックス】だけってどうなのよ?
山ノ内虎之助
ファンタジー
高校生宮原幸也は転生者である。
2度目の人生を目立たぬよう生きてきた幸也だが、ある日クラスメイト15人と一緒に異世界に転移されてしまう。
異世界で与えられたスキルは【アイテムボックス】のみ。
唯一のスキルを創意工夫しながら異世界を生き抜いていく。

家庭菜園物語
コンビニ
ファンタジー
お人好しで動物好きな最上 悠(さいじょう ゆう)は肉親であった祖父が亡くなり、最後の家族であり姉のような存在でもある黒猫の杏(あんず)も静かに息を引き取ろうとする中で、助けたいなら異世界に来てくれないかと、少し残念な神様に提案される。
その転移先で秋田犬の大福を助けたことで、能力を失いそのままスローライフをおくることとなってしまう。
異世界で新しい家族や友人を作り、本人としてはほのぼのと家庭菜園を営んでいるが、小さな畑が世界には大きな影響を与えることになっていく。

【完結】初級魔法しか使えない低ランク冒険者の少年は、今日も依頼を達成して家に帰る。
アノマロカリス
ファンタジー
少年テッドには、両親がいない。
両親は低ランク冒険者で、依頼の途中で魔物に殺されたのだ。
両親の少ない保険でやり繰りしていたが、もう金が尽きかけようとしていた。
テッドには、妹が3人いる。
両親から「妹達を頼む!」…と出掛ける前からいつも約束していた。
このままでは家族が離れ離れになると思ったテッドは、冒険者になって金を稼ぐ道を選んだ。
そんな少年テッドだが、パーティーには加入せずにソロ活動していた。
その理由は、パーティーに参加するとその日に家に帰れなくなるからだ。
両親は、小さいながらも持ち家を持っていてそこに住んでいる。
両親が生きている頃は、父親の部屋と母親の部屋、子供部屋には兄妹4人で暮らしていたが…
両親が死んでからは、父親の部屋はテッドが…
母親の部屋は、長女のリットが、子供部屋には、次女のルットと三女のロットになっている。
今日も依頼をこなして、家に帰るんだ!
この少年テッドは…いや、この先は本編で語ろう。
お楽しみくださいね!
HOTランキング20位になりました。
皆さん、有り難う御座います。
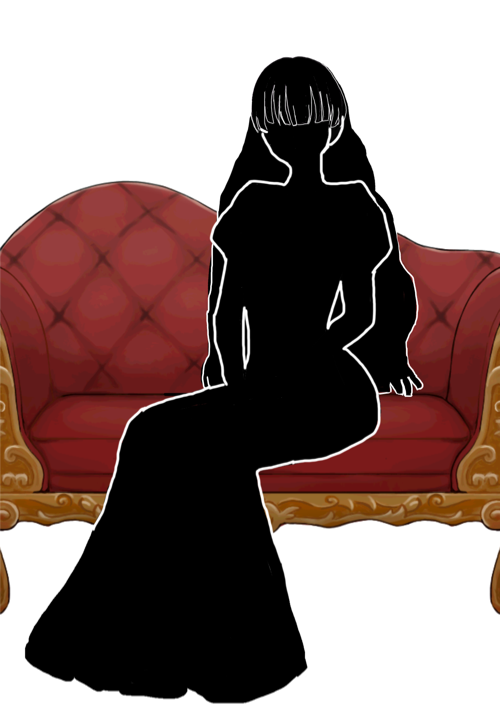


どうぞお好きに
音無砂月
ファンタジー
公爵家に生まれたスカーレット・ミレイユ。
王命で第二王子であるセルフと婚約することになったけれど彼が商家の娘であるシャーベットを囲っているのはとても有名な話だった。そのせいか、なかなか婚約話が進まず、あまり野心のない公爵家にまで縁談話が来てしまった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















