お気に入りに追加
4
あなたにおすすめの小説

学院のモブ役だったはずの青年溺愛物語
紅林
BL
『桜田門学院高等学校』
日本中の超金持ちの子息子女が通うこの学校は東京都内に位置する野球ドーム五個分の土地が学院としてなる巨大学園だ
しかし生徒数は300人程の少人数の学院だ
そんな学院でモブとして役割を果たすはずだった青年の物語である

十七歳の心模様
須藤慎弥
BL
好きだからこそ、恋人の邪魔はしたくない…
ほんわか読者モデル×影の薄い平凡くん
柊一とは不釣り合いだと自覚しながらも、
葵は初めての恋に溺れていた。
付き合って一年が経ったある日、柊一が告白されている現場を目撃してしまう。
告白を断られてしまった女の子は泣き崩れ、
その瞬間…葵の胸に卑屈な思いが広がった。
※fujossy様にて行われた「梅雨のBLコンテスト」出品作です。

嘔吐依存
()
BL
⚠️
・嘔吐表現あり
・リョナあり
・汚い
ー何でもOKな方、ご覧ください。
小説初作成なのでクオリティが低いです。
おかしな点があるかもしれませんが温かい目で見逃してください。ー

学園と夜の街での鬼ごっこ――標的は白の皇帝――
天海みつき
BL
族の総長と副総長の恋の話。
アルビノの主人公――聖月はかつて黒いキャップを被って目元を隠しつつ、夜の街を駆け喧嘩に明け暮れ、いつしか"皇帝"と呼ばれるように。しかし、ある日突然、姿を晦ました。
その後、街では聖月は死んだという噂が蔓延していた。しかし、彼の族――Nukesは実際に遺体を見ていないと、その捜索を止めていなかった。
「どうしようかなぁ。……そぉだ。俺を見つけて御覧。そしたら捕まってあげる。これはゲームだよ。俺と君たちとの、ね」
学園と夜の街を巻き込んだ、追いかけっこが始まった。
族、学園、などと言っていますが全く知識がないため完全に想像です。何でも許せる方のみご覧下さい。
何とか完結までこぎつけました……!番外編を投稿完了しました。楽しんでいただけたら幸いです。


【BL】国民的アイドルグループ内でBLなんて勘弁してください。
白猫
BL
国民的アイドルグループ【kasis】のメンバーである、片桐悠真(18)は悩んでいた。
最近どうも自分がおかしい。まさに悪い夢のようだ。ノーマルだったはずのこの自分が。
(同じグループにいる王子様系アイドルに恋をしてしまったかもしれないなんて……!)
(勘違いだよな? そうに決まってる!)
気のせいであることを確認しようとすればするほどドツボにハマっていき……。

逃げられない罠のように捕まえたい
アキナヌカ
BL
僕は岩崎裕介(いわさき ゆうすけ)には親友がいる、ちょっと特殊な遊びもする親友で西村鈴(にしむら りん)という名前だ。僕はまた鈴が頬を赤く腫らせているので、いつものことだなと思って、そんな鈴から誘われて僕は二人だけで楽しい遊びをする。
★★★このお話はBLです 裕介×鈴です ノンケ攻め 襲い受け リバなし 不定期更新です★★★
小説家になろう、pixiv、アルファポリス、カクヨム、エブリスタ、fujossyにも掲載しています。
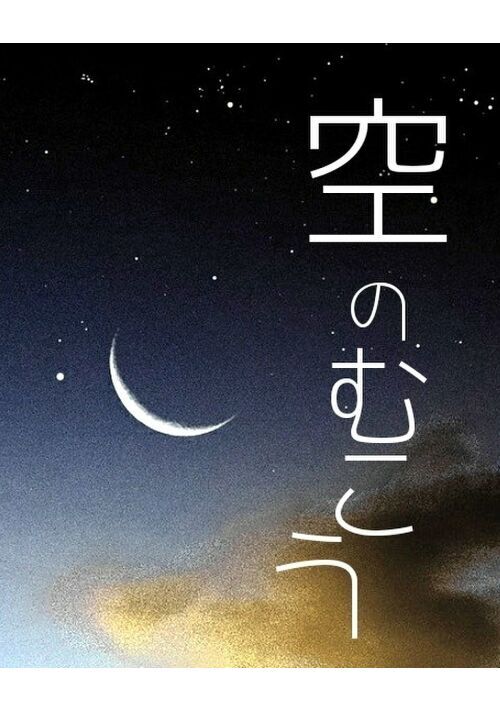
空のむこう
マン太
BL
時を越えて出会う二人。
主人公、鴇乃(ときの)すばると、幼馴染みの青年、北宮清(きたみ せい)。
高校生になったすばるに思いを寄せる清。夏祭りの帰り道、清は突然先に帰ってしまう。
清の自宅を訪れたすばるは、塞ぎ込む清に声をかけるが突然、押し倒され?!
ちょっと切ない、でもハッピーエンドのお話しです。
※BL要素ありですが、濃い絡みはありません。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















