7 / 23
第7話 襲撃
しおりを挟む
その日、区民ホールに出向いて、講演会の打ち合わせを滞りなく済ませた健介は、担当者と共に笑顔で事務局を出て来た。
「それでは北郷先生に、宜しくお伝え下さい」
「はい。失礼します」
最近、事務所で不穏な事が立て続けに起こっているなど、微塵も感じさせない素振りで健介が後部座席に乗り込み、担当者に見送られながら、真紀は車を発進させた。
(さて、相変わらず変な感じはしないけど、そろそろ別なやり方で仕掛けてこないのかしらね?)
そんな事を考えながら公道を走り出し、何気なくバックミラーを確認した瞬間、真紀は自分の考えが少々甘かったのを悟った。
(と思ったら、やっぱりあの車。事務所からここに来る途中で、いつの間にか後ろに付いていた車よね?)
しっかり記憶しておいた車形と色、ナンバーを符合させた真紀は、小さく舌打ちしてから迷わず次の行動に移った。
(一応、準備だけはしておきましょうか)
丁度赤信号で停まったのを幸い、アームレストの収納部分からインカムを取り出し、そのコネクタの先端をオーディオパネルの接続部に差し込む。更にカモフラージュされているボタンの一つを押し、その直後に左耳に伝わって来た内容に、短く「特防一菅沼」と答えていると、唐突に背後から声がかけられた。
「佐藤さん」
「何ですか?」
運転中、しかもそちらからの音声に注意を向けていた為、ついうっかり旧姓の呼びかけに真紀が応じてしまうと、顔色を変えた健介が、勢い良く身を乗り出して語気強く迫ってきた。
「やっぱり、君の名前は佐藤じゃないか! 真紀、どうして菅沼なんて名乗ってるんだ!?」
(ちっ、面倒な。うっかりして、つい反応しちゃったじゃない。大体、何で佐藤なんて呼ばれるのよ。人違いするにしても、他の名前だったら腹も立たないのに、本当にろくでもない男よね!)
過去の汚点故に自分の旧姓を毛嫌いしている真紀は、かなり努力して舌打ちを堪え、務めて素っ気なく前方を見ながら言い返した。
「何か誤解されていませんか? 私は『佐藤』と言う呼びかけに応じた訳では無くて、何故佐藤と呼びかけられるのかが分からなくて、『何ですか?』と問い返しただけですが?」
「え?」
気勢を削がれた様に健介が瞬きすると、そこでバックミラーを横目で確認した真紀が、今度こそ盛大に舌打ちしてがらりと口調を変えながら、相手に指示した。
「第一、あんたに名前を呼び捨てにされる謂れはないんだけど? 全く……、くだらない事を分からない事を言われている間に、連中が距離を詰めてきやがったわ。意味が分からん事をガタガタ言ってないで、さっさとシートベルトを締めろ!!」
「はい! あ、いや、ちょっと待ってくれ。連中って何の事だ?」
取り敢えず素直に身体を引いてシートベルトを装着しながら、健介が尚も困惑した問いを発すると、真紀は更に声に苛立ちを含ませながら付け加えた。
「事務所を出てからずっと、後を付けてきた車に乗っている人間の事よ」
「そんな車が有ったのか?」
ここで漸く彼は、少し前から真紀が徐々に車のスピードを上げ、左右に車線変更しながら運転していた理由に気が付き、慌ててリアウインドーから後続車を確認した。すると一台の黒のセダンが、徐々に距離を詰めてきているのを確認する。
「ただ後を付けているだけなら、放置しておこうかと思っていたけどね。こんな公道で直接仕掛ける筈もないとか、思い込んでいたのは迂闊だったわ」
「それは、うわっ!」
そこで言いかけた時、軽い衝突の衝撃が伝わった為、身体を揺らしながら健介が思わず動揺の声を上げた。しかし真紀が冷静に運転席から怒鳴り返した。
「喚かない! 速度を合わせて、鼻先で軽くど突かれた程度よ!」
そして何やらインカム越しに指示を受けたらしく、短く独り言を呟く。
「……了解しました。誘導をお願いします」
「あの……、菅沼さん? 誰と話を」
「五月蝿い。黙ってろ」
「……はい」
思わず声をかけたものの、低い声で凄まれた健介は、大人しく口を噤んだ。その間に例のセダンは更にスピードを上げて二車線で斜め後方に付き、車体の前部を軽く突っ込ませる様にして、真紀達の車にぶつけてくる。
「うわっ!」
「へえ? これで威嚇のつもり? それなら付いてきなさい!」
そのやる気満々の叫びと共に真紀は素早くギアチェンジし、一気にアクセルを踏み込んだ。そして不審車から距離を取り始める。
「菅沼さん!? 何をする気ですか!!」
急にスピードを上げた事で不安が増大したらしい健介が声を上げたが、真紀はそれを一刀両断した。
「これ以上追って来ないで振り切れたら、今回のこれはちょっとした遊びか、単なる威嚇よ。あくまで付いて来るなら、害意があると判断するわ。ちょっとお仕置きしてやる」
「お仕置きって、警察に通報」
「そんなのは公社に連絡した時点で、そっちから済ませてんだよ! ゴチャゴチャ言ってないで、黙ってしっかり掴まってろ!」
「……はい」
(本当は警察に来られたら、こっちのやり口も非難されるから、呼ぶ筈無いんだけどね)
どうやらそこでこれ以上口を挟むのは得策ではないと判断した健介は、大人しく口を噤み、真紀はせいせいしながら運転を続けた。そして幹線道路から横道に入って川に向かい、更に誘導通りに橋の手前で折れて、広い河川敷を見下ろす堤の位置にある道路に入る。
「うん、ここなら交通量が少ないし、平日の午後だとさすがに河川敷でも練習とかはしていないし、ジョギング中の人も見当たらないわ、ラッキー!」
片側一車線の道路を走らせながら、すこぶる上機嫌に真紀が感想を述べた為、健介は思わず問いを発した。
「あの、菅沼さん? どうしてこんな川沿いに来たんですか?」
「一般道でクラッシュさせたら、大事になるでしょうが。ほど近くにこんな所があって良かったわ」
「大事って、一体何をする気」
「ほら来た!」
「え? うわっ!」
いつの間にか先程のセダンが距離を詰め、再び車の後部にぶつけようとした為、真紀は一気にアクセルを踏み込んで、ある程度の距離を取った。
「と、ここで、こう!」
「なっ、何でブレーキ!」
「食らえっ!」
「は?」
一気に距離を取って逃げ切る気かと思いきや、次の瞬間ブレーキの制動で前のめりになった健介は、シートベルトで背もたれに再び身体を押し付けられながらも、クラクションで背後の異常を察した。そして身体を捻って後方を確認すると、何故か視界が黒い煙で遮られる。
「何だ、この煙?」
「そりゃっ!」
「ええと……、何だ? 今の音は、はぁ?」
そして何やら変な掛け声をかけながら、真紀がまたパネルのボタンの一つを押すと、先程お見舞いした煙幕に続いて、後続車のタイヤの軌道上に特殊な合金製のピンを落とした為、それを轢いたセダンのタイヤが呆気なくパンクした。それで一瞬視界を遮られた事に続き、ハンドルを取られて路肩のポールに激突してなぎ倒しながら、セダンが斜面を滑り落ちて行く。
そんな事情など知る由もない健介は、窓越しにその光景を眺めながら、真紀に声をかけた。
「あの……、菅沼さん?」
「何でしょうか?」
「車が河川敷に滑り落ちましたが」
「向こうがハンドル操作を誤っただけです」
「…………」
その前の煙はどうなのかと、突っ込みを入れる雰囲気でも無かったが、健介は再度問いかけた。
「あの……、あのまま放置して大丈夫なんですか?」
「どうせ乗っている連中は、おとなしく救助を待たないで逃げますよ」
その断定口調に、健介は思わず顔をしかめる。
「どうして断言できるんですか」
「あの車は盗難車ですから」
「は? どうしてそんな事が分かるんですか?」
「あの車のナンバーをはっきり認識できた段階で、公社の情報管理課が警察のデータベースにアクセスして、盗難届が出されているのを確認しました。一応公社の方で通報してくれていますし、このまま事務所に戻ります」
「だから、どうしてそんな事が分かるんですか? 菅沼さんは職場に、車の情報なんか報告していないないでしょう? 運転に集中していましたから」
素っ気なく答える真紀に、健介は幾分苛立ちながら言い返したが、それを聞いた彼女は(そんな事も推察できないのか)と呆れ気味に説明した。
「この車体に装備されているカメラで、前後左右の状況は常に職場に自動送信されています。私が連絡を入れた段階で、後方画像を情報解析班がピックアップして検証しました。……え? 代車ですか? ……はい、了解しました。待機します」
説明の途中で、急に無言になり、次いで短くやり取りした真紀は、ナビ画面を確認しながらゆっくりとハンドルを切った。
「このまま事務所に戻らずに、ちょっと寄り道をして車を替えます」
それを聞いた健介が、怪訝な顔になった。
「どうしてですか? 確かに車体に傷は付いたと思いますが、走行に支障は無いですよね?」
「今回明らかに事務所から尾行、あるいは途中で待ち伏せをされたので、北郷事務所のスタッフ等から、スケジュールが漏れている可能性があります。それで襲撃など無かった事にして、反応を見ます」
それを聞いた健介は、無意識に納得いかない感じの声を出した。
「スタッフの中に、ですか?」
「ご不満ですか? 身近な人間を疑いたくはない気持ちは分かりますが、事実は事実として受け止めて下さい。ですから事務所の人間には、先程の事は言わないように。少し遅れたのは、渋滞に巻き込まれたからです。分かりましたね?」
「……分かりました」
取り敢えず神妙に頷いた健介に、真紀はそれ以上何も言わず、車を元の幹線道路まで戻した。そして何分か走らせてから、指定の場所で車を路肩に寄せて停車する。
「さて、そろそろ来てくれないと、時間的に困るんだけどな……。あ、来たか」
そのまま車内で十分程待っていると、乗っている車と同一種同色のセダンがすぐ後ろに停車し、真紀は健介を促して車道に降り立った。するともう一台の車からも、真紀とそう変わらない三十代前半の男が降り立ち、彼女に向かって気安く声をかけてくる。
「よう、真紀。待たせたな」
「…………」
その物言いに、健介は無言のまま軽く目を見開いたが、当人は軽く顔を顰めながら苦言を呈した。
「今はまだ、勤務中だと思いましたが?」
「お前、相変わらず仕事中はガッチガチだな」
その男は苦笑いしてから、顔付きと口調を改めて、乗って来た車のキーを差し出しつつ真紀に告げた。
「それでは菅沼さん。こちらを引き渡しますので、移乗して任務を続行して下さい」
「了解しました。それでは菅沼さん。こちらの移送をお願いします」
「了解しました」
「え? 菅沼?」
互いに真顔での二人のやり取りを聞いて、健介は先程とは違った意味で驚愕の顔付きになったが、キーの受け渡しを済ませた真紀は、淡々と健介を促した。
「北郷さん。時間が押していますので、乗って下さい」
「……あ、ああ」
そして真紀達が乗り込んだ車が軽快に走り去るのを眺めながら、残された男は皮肉げに口元を歪めた。
「へぇ? あれが例のホスト野郎か。直にお目にかかれるとは……。しかし本当に真紀の奴、完璧に記憶から消去しちまってるんだな。ある意味凄いぞ」
そう呟いてひとしきり笑ってから、彼は車に乗り込んで職場へと戻って行った。
一方で、事務所に向かって走行中の車内では、あまり友好的とは言えない空気が満ち満ちていた。
「その……、真紀?」
「確かに初対面の時に名前まで名乗りましたが、それは馴れ馴れしく呼び捨てにされる為に口にした訳ではありません」
「それじゃあ、佐藤さん」
「呼称は正確にお願いします」
「その……、菅沼さん?」
「何でしょうか?」
何が何でも自分を「菅沼」以外で呼ばせる気はない真紀が素っ気なく応じると、健介は気になった疑問を解消するべく問いかけた。
「先程の男性は、同僚の方ですよね?」
「それが何か?」
「彼の名字も菅沼なんですか?」
「そうです。ですから社内では、配属部署名を付けて呼び分けて貰っています。私が特務一課で彼が特務二課ですので」
「それならあの人とあなたは、どういう関係ですか?」
「それは完全にプライベートですし、現時点で仕事に関しては微塵も関係がありません」
「…………」
質問を容赦なくぶった切られた健介だったが、それに関しては文句を言わず、すぐに質問を変えた。
「それではあなたの仕事に関してお尋ねしますが、先程の様な事は頻繁にあるんですか?」
その問いかけに、真紀ははっきりと苛立ちを含んだ声で答えた。
「私の仕事が、何だと思っていらっしゃるんですか? まさか大人しく立哨して、対象者に付いて歩くだけの、楽な仕事だとでも?」
「……分かりました」
彼女の剣幕に恐れをなしたのか、健介はおとなしく引き下がり、真紀は運転を続けながら本気で腹を立てた。
(本当に馬鹿じゃないの、こいつ。ちょっと車をぶつけられた位でビビって、何言わずもがなの事を言ってるのよ)
それからは無言のまま車を走らせたが、気詰まりな時間はそれほど長くかからず、ほどなく事務所に戻る事ができた。
「戻りました」
帰り着いてすぐに、健介が事務所責任者の重原に挨拶すると、相手は笑顔で言葉を返してきた。
「お帰りなさい。健介さん、少し遅かったですね」
「ええ、すみません。何やら事故があったらしくて、渋滞に巻き込まれまして。運悪く迂回路も無くて、本当に参りました。ですが一々、連絡を入れる程の事でも無かったので」
「そうでしたか。それなら良かったです。ひょっとしたら事故にでも巻き込まれたのでは無いかと、心配していました」
「いえ、そんな事は。ご心配おかけしてすみません」
主だったスタッフが集まっている大部屋で、二人が笑顔でそんな会話を交わしている中、真紀はさり気なく室内の人間の様子を観察していた。
(ふぅん? 大抵の人は聞き流しているけど、変な顔をしているのは……。大方、重原さんに『健介さんが事故に巻き込まれたかも』とか言って、さり気なく不安を煽っていたのはあいつかしらね。後は帰社してから報告して、調査結果を確認しないと)
それから真紀は事務所内外の巡回を始め、健介は大人しく仕事部屋に戻った。すると出迎えた宗則が、座ったまま少し不思議そうに声をかけてくる。
「おう、健介。戻ったか。結構時間がかかったな」
「……ああ。良く分かった」
「分かったって、何が?」
噛み合わない会話に、宗則が益々怪訝な顔付きになると、健介が独り言の様に話を続けた。
「やっぱり彼女は、真紀だと思う」
「はぁ? それならどうしてお前の話と色々食い違うし、お前と顔を合わせても、彼女が微塵も動揺したり反応しないんだ?」
何を今更という口調で言い返したが宗則に、健介は真顔で主張を繰り出す。
「彼女の仕事は危険と隣り合わせだから、おそらくこれまでに仕事中に事故に巻き込まれたり、襲撃されて重傷を負って、記憶喪失になったんだ」
そんな事をきっぱりと断言されて、宗則は呆気に取られた表情になってから、呻く様に言い出した。
「おい……、一言言って良いか?」
「ああ、何だ?」
「お前、俺がこの前、パラレルワールドの健介とお前が入れ替わった云々を言った時に、馬鹿だの阿呆だの好き放題言ってくれたが、その言葉、そっくりそのままお前に返してやる」
「違う! 例の話は根拠の無い与太話だが、これは観察に基づく明確な推理で!」
「そんな事を大真面目に主張する事自体、どうかしていると自覚しろ!! お前って奴は本当に、頭は良いかもしれないが、トコトン阿呆だよな!?」
そんな不毛な言い合いは、戻った真紀が騒々しさに気が付いてドアを開けて詳細を尋ねて来るまで、暫く続いた。
「それでは北郷先生に、宜しくお伝え下さい」
「はい。失礼します」
最近、事務所で不穏な事が立て続けに起こっているなど、微塵も感じさせない素振りで健介が後部座席に乗り込み、担当者に見送られながら、真紀は車を発進させた。
(さて、相変わらず変な感じはしないけど、そろそろ別なやり方で仕掛けてこないのかしらね?)
そんな事を考えながら公道を走り出し、何気なくバックミラーを確認した瞬間、真紀は自分の考えが少々甘かったのを悟った。
(と思ったら、やっぱりあの車。事務所からここに来る途中で、いつの間にか後ろに付いていた車よね?)
しっかり記憶しておいた車形と色、ナンバーを符合させた真紀は、小さく舌打ちしてから迷わず次の行動に移った。
(一応、準備だけはしておきましょうか)
丁度赤信号で停まったのを幸い、アームレストの収納部分からインカムを取り出し、そのコネクタの先端をオーディオパネルの接続部に差し込む。更にカモフラージュされているボタンの一つを押し、その直後に左耳に伝わって来た内容に、短く「特防一菅沼」と答えていると、唐突に背後から声がかけられた。
「佐藤さん」
「何ですか?」
運転中、しかもそちらからの音声に注意を向けていた為、ついうっかり旧姓の呼びかけに真紀が応じてしまうと、顔色を変えた健介が、勢い良く身を乗り出して語気強く迫ってきた。
「やっぱり、君の名前は佐藤じゃないか! 真紀、どうして菅沼なんて名乗ってるんだ!?」
(ちっ、面倒な。うっかりして、つい反応しちゃったじゃない。大体、何で佐藤なんて呼ばれるのよ。人違いするにしても、他の名前だったら腹も立たないのに、本当にろくでもない男よね!)
過去の汚点故に自分の旧姓を毛嫌いしている真紀は、かなり努力して舌打ちを堪え、務めて素っ気なく前方を見ながら言い返した。
「何か誤解されていませんか? 私は『佐藤』と言う呼びかけに応じた訳では無くて、何故佐藤と呼びかけられるのかが分からなくて、『何ですか?』と問い返しただけですが?」
「え?」
気勢を削がれた様に健介が瞬きすると、そこでバックミラーを横目で確認した真紀が、今度こそ盛大に舌打ちしてがらりと口調を変えながら、相手に指示した。
「第一、あんたに名前を呼び捨てにされる謂れはないんだけど? 全く……、くだらない事を分からない事を言われている間に、連中が距離を詰めてきやがったわ。意味が分からん事をガタガタ言ってないで、さっさとシートベルトを締めろ!!」
「はい! あ、いや、ちょっと待ってくれ。連中って何の事だ?」
取り敢えず素直に身体を引いてシートベルトを装着しながら、健介が尚も困惑した問いを発すると、真紀は更に声に苛立ちを含ませながら付け加えた。
「事務所を出てからずっと、後を付けてきた車に乗っている人間の事よ」
「そんな車が有ったのか?」
ここで漸く彼は、少し前から真紀が徐々に車のスピードを上げ、左右に車線変更しながら運転していた理由に気が付き、慌ててリアウインドーから後続車を確認した。すると一台の黒のセダンが、徐々に距離を詰めてきているのを確認する。
「ただ後を付けているだけなら、放置しておこうかと思っていたけどね。こんな公道で直接仕掛ける筈もないとか、思い込んでいたのは迂闊だったわ」
「それは、うわっ!」
そこで言いかけた時、軽い衝突の衝撃が伝わった為、身体を揺らしながら健介が思わず動揺の声を上げた。しかし真紀が冷静に運転席から怒鳴り返した。
「喚かない! 速度を合わせて、鼻先で軽くど突かれた程度よ!」
そして何やらインカム越しに指示を受けたらしく、短く独り言を呟く。
「……了解しました。誘導をお願いします」
「あの……、菅沼さん? 誰と話を」
「五月蝿い。黙ってろ」
「……はい」
思わず声をかけたものの、低い声で凄まれた健介は、大人しく口を噤んだ。その間に例のセダンは更にスピードを上げて二車線で斜め後方に付き、車体の前部を軽く突っ込ませる様にして、真紀達の車にぶつけてくる。
「うわっ!」
「へえ? これで威嚇のつもり? それなら付いてきなさい!」
そのやる気満々の叫びと共に真紀は素早くギアチェンジし、一気にアクセルを踏み込んだ。そして不審車から距離を取り始める。
「菅沼さん!? 何をする気ですか!!」
急にスピードを上げた事で不安が増大したらしい健介が声を上げたが、真紀はそれを一刀両断した。
「これ以上追って来ないで振り切れたら、今回のこれはちょっとした遊びか、単なる威嚇よ。あくまで付いて来るなら、害意があると判断するわ。ちょっとお仕置きしてやる」
「お仕置きって、警察に通報」
「そんなのは公社に連絡した時点で、そっちから済ませてんだよ! ゴチャゴチャ言ってないで、黙ってしっかり掴まってろ!」
「……はい」
(本当は警察に来られたら、こっちのやり口も非難されるから、呼ぶ筈無いんだけどね)
どうやらそこでこれ以上口を挟むのは得策ではないと判断した健介は、大人しく口を噤み、真紀はせいせいしながら運転を続けた。そして幹線道路から横道に入って川に向かい、更に誘導通りに橋の手前で折れて、広い河川敷を見下ろす堤の位置にある道路に入る。
「うん、ここなら交通量が少ないし、平日の午後だとさすがに河川敷でも練習とかはしていないし、ジョギング中の人も見当たらないわ、ラッキー!」
片側一車線の道路を走らせながら、すこぶる上機嫌に真紀が感想を述べた為、健介は思わず問いを発した。
「あの、菅沼さん? どうしてこんな川沿いに来たんですか?」
「一般道でクラッシュさせたら、大事になるでしょうが。ほど近くにこんな所があって良かったわ」
「大事って、一体何をする気」
「ほら来た!」
「え? うわっ!」
いつの間にか先程のセダンが距離を詰め、再び車の後部にぶつけようとした為、真紀は一気にアクセルを踏み込んで、ある程度の距離を取った。
「と、ここで、こう!」
「なっ、何でブレーキ!」
「食らえっ!」
「は?」
一気に距離を取って逃げ切る気かと思いきや、次の瞬間ブレーキの制動で前のめりになった健介は、シートベルトで背もたれに再び身体を押し付けられながらも、クラクションで背後の異常を察した。そして身体を捻って後方を確認すると、何故か視界が黒い煙で遮られる。
「何だ、この煙?」
「そりゃっ!」
「ええと……、何だ? 今の音は、はぁ?」
そして何やら変な掛け声をかけながら、真紀がまたパネルのボタンの一つを押すと、先程お見舞いした煙幕に続いて、後続車のタイヤの軌道上に特殊な合金製のピンを落とした為、それを轢いたセダンのタイヤが呆気なくパンクした。それで一瞬視界を遮られた事に続き、ハンドルを取られて路肩のポールに激突してなぎ倒しながら、セダンが斜面を滑り落ちて行く。
そんな事情など知る由もない健介は、窓越しにその光景を眺めながら、真紀に声をかけた。
「あの……、菅沼さん?」
「何でしょうか?」
「車が河川敷に滑り落ちましたが」
「向こうがハンドル操作を誤っただけです」
「…………」
その前の煙はどうなのかと、突っ込みを入れる雰囲気でも無かったが、健介は再度問いかけた。
「あの……、あのまま放置して大丈夫なんですか?」
「どうせ乗っている連中は、おとなしく救助を待たないで逃げますよ」
その断定口調に、健介は思わず顔をしかめる。
「どうして断言できるんですか」
「あの車は盗難車ですから」
「は? どうしてそんな事が分かるんですか?」
「あの車のナンバーをはっきり認識できた段階で、公社の情報管理課が警察のデータベースにアクセスして、盗難届が出されているのを確認しました。一応公社の方で通報してくれていますし、このまま事務所に戻ります」
「だから、どうしてそんな事が分かるんですか? 菅沼さんは職場に、車の情報なんか報告していないないでしょう? 運転に集中していましたから」
素っ気なく答える真紀に、健介は幾分苛立ちながら言い返したが、それを聞いた彼女は(そんな事も推察できないのか)と呆れ気味に説明した。
「この車体に装備されているカメラで、前後左右の状況は常に職場に自動送信されています。私が連絡を入れた段階で、後方画像を情報解析班がピックアップして検証しました。……え? 代車ですか? ……はい、了解しました。待機します」
説明の途中で、急に無言になり、次いで短くやり取りした真紀は、ナビ画面を確認しながらゆっくりとハンドルを切った。
「このまま事務所に戻らずに、ちょっと寄り道をして車を替えます」
それを聞いた健介が、怪訝な顔になった。
「どうしてですか? 確かに車体に傷は付いたと思いますが、走行に支障は無いですよね?」
「今回明らかに事務所から尾行、あるいは途中で待ち伏せをされたので、北郷事務所のスタッフ等から、スケジュールが漏れている可能性があります。それで襲撃など無かった事にして、反応を見ます」
それを聞いた健介は、無意識に納得いかない感じの声を出した。
「スタッフの中に、ですか?」
「ご不満ですか? 身近な人間を疑いたくはない気持ちは分かりますが、事実は事実として受け止めて下さい。ですから事務所の人間には、先程の事は言わないように。少し遅れたのは、渋滞に巻き込まれたからです。分かりましたね?」
「……分かりました」
取り敢えず神妙に頷いた健介に、真紀はそれ以上何も言わず、車を元の幹線道路まで戻した。そして何分か走らせてから、指定の場所で車を路肩に寄せて停車する。
「さて、そろそろ来てくれないと、時間的に困るんだけどな……。あ、来たか」
そのまま車内で十分程待っていると、乗っている車と同一種同色のセダンがすぐ後ろに停車し、真紀は健介を促して車道に降り立った。するともう一台の車からも、真紀とそう変わらない三十代前半の男が降り立ち、彼女に向かって気安く声をかけてくる。
「よう、真紀。待たせたな」
「…………」
その物言いに、健介は無言のまま軽く目を見開いたが、当人は軽く顔を顰めながら苦言を呈した。
「今はまだ、勤務中だと思いましたが?」
「お前、相変わらず仕事中はガッチガチだな」
その男は苦笑いしてから、顔付きと口調を改めて、乗って来た車のキーを差し出しつつ真紀に告げた。
「それでは菅沼さん。こちらを引き渡しますので、移乗して任務を続行して下さい」
「了解しました。それでは菅沼さん。こちらの移送をお願いします」
「了解しました」
「え? 菅沼?」
互いに真顔での二人のやり取りを聞いて、健介は先程とは違った意味で驚愕の顔付きになったが、キーの受け渡しを済ませた真紀は、淡々と健介を促した。
「北郷さん。時間が押していますので、乗って下さい」
「……あ、ああ」
そして真紀達が乗り込んだ車が軽快に走り去るのを眺めながら、残された男は皮肉げに口元を歪めた。
「へぇ? あれが例のホスト野郎か。直にお目にかかれるとは……。しかし本当に真紀の奴、完璧に記憶から消去しちまってるんだな。ある意味凄いぞ」
そう呟いてひとしきり笑ってから、彼は車に乗り込んで職場へと戻って行った。
一方で、事務所に向かって走行中の車内では、あまり友好的とは言えない空気が満ち満ちていた。
「その……、真紀?」
「確かに初対面の時に名前まで名乗りましたが、それは馴れ馴れしく呼び捨てにされる為に口にした訳ではありません」
「それじゃあ、佐藤さん」
「呼称は正確にお願いします」
「その……、菅沼さん?」
「何でしょうか?」
何が何でも自分を「菅沼」以外で呼ばせる気はない真紀が素っ気なく応じると、健介は気になった疑問を解消するべく問いかけた。
「先程の男性は、同僚の方ですよね?」
「それが何か?」
「彼の名字も菅沼なんですか?」
「そうです。ですから社内では、配属部署名を付けて呼び分けて貰っています。私が特務一課で彼が特務二課ですので」
「それならあの人とあなたは、どういう関係ですか?」
「それは完全にプライベートですし、現時点で仕事に関しては微塵も関係がありません」
「…………」
質問を容赦なくぶった切られた健介だったが、それに関しては文句を言わず、すぐに質問を変えた。
「それではあなたの仕事に関してお尋ねしますが、先程の様な事は頻繁にあるんですか?」
その問いかけに、真紀ははっきりと苛立ちを含んだ声で答えた。
「私の仕事が、何だと思っていらっしゃるんですか? まさか大人しく立哨して、対象者に付いて歩くだけの、楽な仕事だとでも?」
「……分かりました」
彼女の剣幕に恐れをなしたのか、健介はおとなしく引き下がり、真紀は運転を続けながら本気で腹を立てた。
(本当に馬鹿じゃないの、こいつ。ちょっと車をぶつけられた位でビビって、何言わずもがなの事を言ってるのよ)
それからは無言のまま車を走らせたが、気詰まりな時間はそれほど長くかからず、ほどなく事務所に戻る事ができた。
「戻りました」
帰り着いてすぐに、健介が事務所責任者の重原に挨拶すると、相手は笑顔で言葉を返してきた。
「お帰りなさい。健介さん、少し遅かったですね」
「ええ、すみません。何やら事故があったらしくて、渋滞に巻き込まれまして。運悪く迂回路も無くて、本当に参りました。ですが一々、連絡を入れる程の事でも無かったので」
「そうでしたか。それなら良かったです。ひょっとしたら事故にでも巻き込まれたのでは無いかと、心配していました」
「いえ、そんな事は。ご心配おかけしてすみません」
主だったスタッフが集まっている大部屋で、二人が笑顔でそんな会話を交わしている中、真紀はさり気なく室内の人間の様子を観察していた。
(ふぅん? 大抵の人は聞き流しているけど、変な顔をしているのは……。大方、重原さんに『健介さんが事故に巻き込まれたかも』とか言って、さり気なく不安を煽っていたのはあいつかしらね。後は帰社してから報告して、調査結果を確認しないと)
それから真紀は事務所内外の巡回を始め、健介は大人しく仕事部屋に戻った。すると出迎えた宗則が、座ったまま少し不思議そうに声をかけてくる。
「おう、健介。戻ったか。結構時間がかかったな」
「……ああ。良く分かった」
「分かったって、何が?」
噛み合わない会話に、宗則が益々怪訝な顔付きになると、健介が独り言の様に話を続けた。
「やっぱり彼女は、真紀だと思う」
「はぁ? それならどうしてお前の話と色々食い違うし、お前と顔を合わせても、彼女が微塵も動揺したり反応しないんだ?」
何を今更という口調で言い返したが宗則に、健介は真顔で主張を繰り出す。
「彼女の仕事は危険と隣り合わせだから、おそらくこれまでに仕事中に事故に巻き込まれたり、襲撃されて重傷を負って、記憶喪失になったんだ」
そんな事をきっぱりと断言されて、宗則は呆気に取られた表情になってから、呻く様に言い出した。
「おい……、一言言って良いか?」
「ああ、何だ?」
「お前、俺がこの前、パラレルワールドの健介とお前が入れ替わった云々を言った時に、馬鹿だの阿呆だの好き放題言ってくれたが、その言葉、そっくりそのままお前に返してやる」
「違う! 例の話は根拠の無い与太話だが、これは観察に基づく明確な推理で!」
「そんな事を大真面目に主張する事自体、どうかしていると自覚しろ!! お前って奴は本当に、頭は良いかもしれないが、トコトン阿呆だよな!?」
そんな不毛な言い合いは、戻った真紀が騒々しさに気が付いてドアを開けて詳細を尋ねて来るまで、暫く続いた。
0
お気に入りに追加
47
あなたにおすすめの小説

【完結】え、別れましょう?
須木 水夏
恋愛
「実は他に好きな人が出来て」
「は?え?別れましょう?」
何言ってんだこいつ、とアリエットは目を瞬かせながらも。まあこちらも好きな訳では無いし都合がいいわ、と長年の婚約者(腐れ縁)だったディオルにお別れを申し出た。
ところがその出来事の裏側にはある双子が絡んでいて…?
だる絡みをしてくる美しい双子の兄妹(?)と、のんびりかつ冷静なアリエットのお話。
※毎度ですが空想であり、架空のお話です。史実に全く関係ありません。
ヨーロッパの雰囲気出してますが、別物です。

どうやら夫に疎まれているようなので、私はいなくなることにします
文野多咲
恋愛
秘めやかな空気が、寝台を囲う帳の内側に立ち込めていた。
夫であるゲルハルトがエレーヌを見下ろしている。
エレーヌの髪は乱れ、目はうるみ、体の奥は甘い熱で満ちている。エレーヌもまた、想いを込めて夫を見つめた。
「ゲルハルトさま、愛しています」
ゲルハルトはエレーヌをさも大切そうに撫でる。その手つきとは裏腹に、ぞっとするようなことを囁いてきた。
「エレーヌ、俺はあなたが憎い」
エレーヌは凍り付いた。

お飾り王妃の死後~王の後悔~
ましゅぺちーの
恋愛
ウィルベルト王国の王レオンと王妃フランチェスカは白い結婚である。
王が愛するのは愛妾であるフレイアただ一人。
ウィルベルト王国では周知の事実だった。
しかしある日王妃フランチェスカが自ら命を絶ってしまう。
最後に王宛てに残された手紙を読み王は後悔に苛まれる。
小説家になろう様にも投稿しています。

君は妾の子だから、次男がちょうどいい
月山 歩
恋愛
侯爵家のマリアは婚約中だが、彼は王都に住み、彼女は片田舎で遠いため会ったことはなかった。でもある時、マリアは妾の子であると知られる。そんな娘は大事な子息とは結婚させられないと、病気療養中の次男との婚約に一方的に変えさせられる。そして次の日には、迎えの馬車がやって来た。

挙式後すぐに離婚届を手渡された私は、この結婚は予め捨てられることが確定していた事実を知らされました
結城芙由奈@2/28コミカライズ発売
恋愛
【結婚した日に、「君にこれを預けておく」と離婚届を手渡されました】
今日、私は子供の頃からずっと大好きだった人と結婚した。しかし、式の後に絶望的な事を彼に言われた。
「ごめん、本当は君とは結婚したくなかったんだ。これを預けておくから、その気になったら提出してくれ」
そう言って手渡されたのは何と離婚届けだった。
そしてどこまでも冷たい態度の夫の行動に傷つけられていく私。
けれどその裏には私の知らない、ある深い事情が隠されていた。
その真意を知った時、私は―。
※暫く鬱展開が続きます
※他サイトでも投稿中
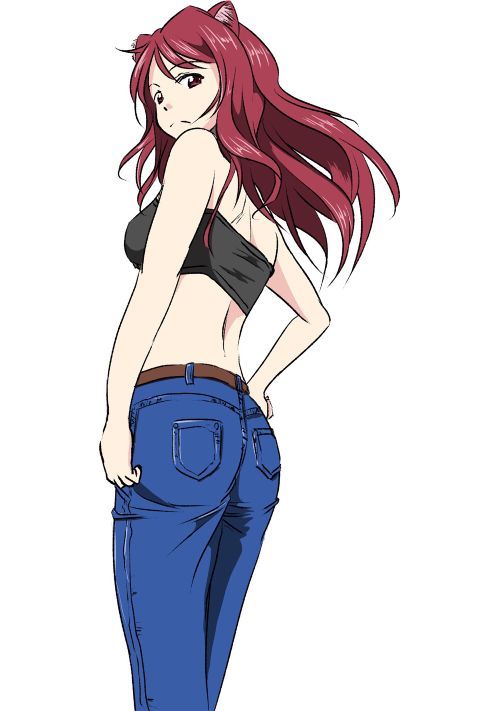
遥か
カリフォルニアデスロールの野良兎
キャラ文芸
鶴木援(ツルギタスケ)は、疲労状態で仕事から帰宅する。何も無い日常にトラウマを抱えた過去、何も起きなかったであろう未来を抱えたまま、何故か誤って監獄街に迷い込む。
生きることを問いかける薄暗いロー・ファンタジー。
表紙 @kafui_k_h

いつか彼女を手に入れる日まで
月山 歩
恋愛
伯爵令嬢の私は、婚約者の邸に馬車で向かっている途中で、馬車が転倒する事故に遭い、治療院に運ばれる。医師に良くなったとしても、足を引きずるようになると言われてしまい、傷物になったからと、格下の私は一方的に婚約破棄される。私はこの先誰かと結婚できるのだろうか?

母の中で私の価値はゼロのまま、家の恥にしかならないと養子に出され、それを鵜呑みにした父に縁を切られたおかげで幸せになれました
珠宮さくら
恋愛
伯爵家に生まれたケイトリン・オールドリッチ。跡継ぎの兄と母に似ている妹。その2人が何をしても母は怒ることをしなかった。
なのに母に似ていないという理由で、ケイトリンは理不尽な目にあい続けていた。そんな日々に嫌気がさしたケイトリンは、兄妹を超えるために頑張るようになっていくのだが……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















