6 / 11
第二章 花の廓
2
しおりを挟む
「このお邸にいる者のなかで、私が一番御館さまとご一緒に過ごした時間が少ないのですもの。他の方々は皆さま、御館さまが高遠のお城にいらした頃からご一緒におられましたのに」
「いや、皆ではないぞ。こちらへ移ってから迎えた者も何人かは……」
「そんなこと存じません」
佐奈姫はますますふくれてみせた。
「ずるい」
「何がずるい」
「私は御館さまの正室でございましょう?」
「無論、そうだ」
「それなのに、 御館さまとご一緒した時間が一番少ないだなんてそんなのずるうございます」
「そんなことを 言っても仕方がなかろう」
「仕方なくてもずるうございます」
勝頼は、ふくれている姫の桜色の頬をやわらかくつまんだ。
「ならば、どうすれば良い」
「ご一緒にいられなかった分を取り返せるくらい、ずっとずっと佐奈のもとにいらして下さいませ」
「そうしておる。姫が嫁いできて以来、余は、すべてそなたの言いなりだ」
「うそ」
「嘘なものか」
「昨日も、その前も会いにいらして下さらなかったくせに」
「それは表の評定が夜遅くまでかかったからだ。姫はいつも宵の口にはもう眠ってしまうではないか」
「そんなことは ありませぬ」
「いや。この間なども戌の刻を過ぎたらもう脇息にもたれながらうとうととしておった」
「そんなことありませんったら」
佐奈姫は怒って、勝頼の胸を小さなこぶしで叩く真似をした。
「そうやっていつも子供扱いなさって」
「子供ではないか。庭先に鳥が飛んでくる度に大騒ぎをして縁先に飛び出してゆくし、腹が減ったり眠たいときには不機嫌になるし」
「まあ!」
佐奈姫が本当に憤慨した顔になった。
「子供扱いはおやめ下さいと申しております」
「……やめても良いのか?」
「え?」
「子供扱いをやめても良いのかと言うておる」
そう言って、肩を引き寄せてやると途端に佐奈姫はおとなしくなって俯いた。
雪のように白い肌が首筋まで赤く染まっている。
箱入りの姫とはいえ輿入れ前に乳母たちから教えられひと通りのことは知っているのだ。
当然、勝頼が自分と過ごす夜が夫婦の本来のあり方とは違うことも知っているはずである。
「なんだ。 急に静かになって」
佐奈姫は答えない。
じっと俯いている。
顔を覗き込もうとすると勝頼の胸に顔を埋めるようにして隠してしまった。
勝頼はその背をなだめるように撫でた。
「姫」
勝頼は、腕のなかの姫にやさしく声をかけた。
「無理はせずともよい。そなたの嫌がることはしたくない。嫌われて鶯のように小田原へ飛んで帰られては
叶わぬからな」
「……帰りませぬ」
胸に顔を埋めたままくぐもった声で佐奈姫が言った。
「佐奈はどこへも参りませぬ」
「そうか」
抱きしめたからだの温もりとともに温かな気持ちが湧き上がってきて、勝頼は姫の頭をぽんぽんと撫でた。
婚礼の夜以来、実質的な行為に及ばずに日を過ごしてきたのは無理強いして怖がらせることで佐奈姫が 心を閉ざしてしまうやも しれぬと思ったためだった。
かつての妙姫のように。
「姫はいい子だ」
髪を撫でる勝頼の袖がきゅっと握られた。
「……で下さい」
「ん?」
「子供あつかい……なさらないで下さい…っ!」
一瞬、顔をあげて真っ赤な顔でそう言うと、佐奈姫はまた急いで勝頼の胸に顔を伏せてしまった。
「姫?」
そのあとは、なんと声をかけても決して顔をあげようとはしなかった。
「そうか」
勝頼は短く言って、そっと姫を抱きしめた。
侍女のひとりがやって来て遠慮がちに表へ戻る刻限で小姓が迎えに参っていることを告げた。
「──酉の刻過ぎには戻る。よい子で起きて待っていられるか?」
尋ねると、腕のなかの姫は顔を隠したままでこくんと微かに頷いた。
その夜、部屋を訪れた勝頼は約束通り、佐奈姫を大人として扱った。
佐奈姫はぎゅっと目を閉じて、勝頼が自分の体を扱うのに身を任せていた。
勝頼は十分に優しく、けれど時に姫が思わず戸惑いの声をあげてしまいそうになる大胆さで、彼女のからだをあつかった。
輿入れ前、乳母の藤野が声を低めて語り聞かせてくれた話の意味を、この夜、佐奈姫は初めてすっかり知った。
翌朝。藤野は、いつもなら寝起きが良くはやばやと起きてきて身じまいを整え、勝頼が起きてくるのを
にこにこと機嫌良く迎える佐奈姫がなかなか起きてこず、勝頼に促されるようにして起きてきたあとも視線を避けるように俯いてばかりいるのを見て、すべてを悟りほっと胸を撫で下ろした。
それと同時にこれまでの武田に対する悪感情はおいて、勝頼の佐奈姫に対する年長の夫らしい優しい気配りに感謝した。
「いや、皆ではないぞ。こちらへ移ってから迎えた者も何人かは……」
「そんなこと存じません」
佐奈姫はますますふくれてみせた。
「ずるい」
「何がずるい」
「私は御館さまの正室でございましょう?」
「無論、そうだ」
「それなのに、 御館さまとご一緒した時間が一番少ないだなんてそんなのずるうございます」
「そんなことを 言っても仕方がなかろう」
「仕方なくてもずるうございます」
勝頼は、ふくれている姫の桜色の頬をやわらかくつまんだ。
「ならば、どうすれば良い」
「ご一緒にいられなかった分を取り返せるくらい、ずっとずっと佐奈のもとにいらして下さいませ」
「そうしておる。姫が嫁いできて以来、余は、すべてそなたの言いなりだ」
「うそ」
「嘘なものか」
「昨日も、その前も会いにいらして下さらなかったくせに」
「それは表の評定が夜遅くまでかかったからだ。姫はいつも宵の口にはもう眠ってしまうではないか」
「そんなことは ありませぬ」
「いや。この間なども戌の刻を過ぎたらもう脇息にもたれながらうとうととしておった」
「そんなことありませんったら」
佐奈姫は怒って、勝頼の胸を小さなこぶしで叩く真似をした。
「そうやっていつも子供扱いなさって」
「子供ではないか。庭先に鳥が飛んでくる度に大騒ぎをして縁先に飛び出してゆくし、腹が減ったり眠たいときには不機嫌になるし」
「まあ!」
佐奈姫が本当に憤慨した顔になった。
「子供扱いはおやめ下さいと申しております」
「……やめても良いのか?」
「え?」
「子供扱いをやめても良いのかと言うておる」
そう言って、肩を引き寄せてやると途端に佐奈姫はおとなしくなって俯いた。
雪のように白い肌が首筋まで赤く染まっている。
箱入りの姫とはいえ輿入れ前に乳母たちから教えられひと通りのことは知っているのだ。
当然、勝頼が自分と過ごす夜が夫婦の本来のあり方とは違うことも知っているはずである。
「なんだ。 急に静かになって」
佐奈姫は答えない。
じっと俯いている。
顔を覗き込もうとすると勝頼の胸に顔を埋めるようにして隠してしまった。
勝頼はその背をなだめるように撫でた。
「姫」
勝頼は、腕のなかの姫にやさしく声をかけた。
「無理はせずともよい。そなたの嫌がることはしたくない。嫌われて鶯のように小田原へ飛んで帰られては
叶わぬからな」
「……帰りませぬ」
胸に顔を埋めたままくぐもった声で佐奈姫が言った。
「佐奈はどこへも参りませぬ」
「そうか」
抱きしめたからだの温もりとともに温かな気持ちが湧き上がってきて、勝頼は姫の頭をぽんぽんと撫でた。
婚礼の夜以来、実質的な行為に及ばずに日を過ごしてきたのは無理強いして怖がらせることで佐奈姫が 心を閉ざしてしまうやも しれぬと思ったためだった。
かつての妙姫のように。
「姫はいい子だ」
髪を撫でる勝頼の袖がきゅっと握られた。
「……で下さい」
「ん?」
「子供あつかい……なさらないで下さい…っ!」
一瞬、顔をあげて真っ赤な顔でそう言うと、佐奈姫はまた急いで勝頼の胸に顔を伏せてしまった。
「姫?」
そのあとは、なんと声をかけても決して顔をあげようとはしなかった。
「そうか」
勝頼は短く言って、そっと姫を抱きしめた。
侍女のひとりがやって来て遠慮がちに表へ戻る刻限で小姓が迎えに参っていることを告げた。
「──酉の刻過ぎには戻る。よい子で起きて待っていられるか?」
尋ねると、腕のなかの姫は顔を隠したままでこくんと微かに頷いた。
その夜、部屋を訪れた勝頼は約束通り、佐奈姫を大人として扱った。
佐奈姫はぎゅっと目を閉じて、勝頼が自分の体を扱うのに身を任せていた。
勝頼は十分に優しく、けれど時に姫が思わず戸惑いの声をあげてしまいそうになる大胆さで、彼女のからだをあつかった。
輿入れ前、乳母の藤野が声を低めて語り聞かせてくれた話の意味を、この夜、佐奈姫は初めてすっかり知った。
翌朝。藤野は、いつもなら寝起きが良くはやばやと起きてきて身じまいを整え、勝頼が起きてくるのを
にこにこと機嫌良く迎える佐奈姫がなかなか起きてこず、勝頼に促されるようにして起きてきたあとも視線を避けるように俯いてばかりいるのを見て、すべてを悟りほっと胸を撫で下ろした。
それと同時にこれまでの武田に対する悪感情はおいて、勝頼の佐奈姫に対する年長の夫らしい優しい気配りに感謝した。
0
お気に入りに追加
9
あなたにおすすめの小説

夕映え~武田勝頼の妻~
橘 ゆず
歴史・時代
天正十年(1582年)。
甲斐の国、天目山。
織田・徳川連合軍による甲州征伐によって新府を追われた武田勝頼は、起死回生をはかってわずかな家臣とともに岩殿城を目指していた。
そのかたわらには、五年前に相模の北条家から嫁いできた継室、十九歳の佐奈姫の姿があった。
武田勝頼公と、18歳年下の正室、北条夫人の最期の数日を描いたお話です。
コバルトの短編小説大賞「もう一歩」の作品です。
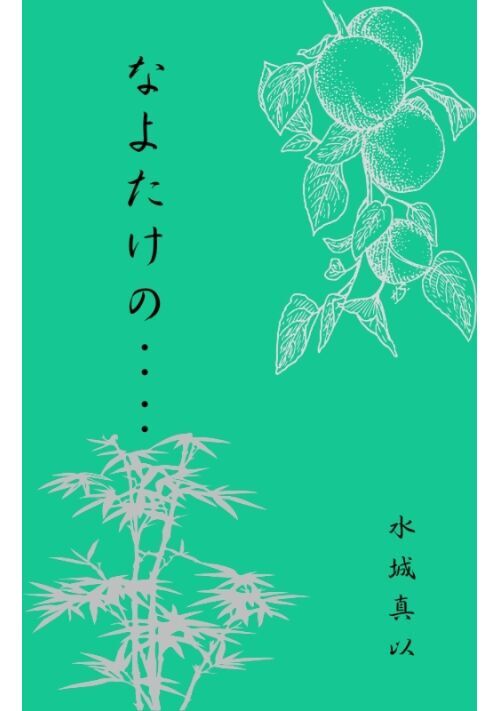

散華の庭
ももちよろづ
歴史・時代
慶応四年、戊辰戦争の最中。
新選組 一番組長・沖田総司は、
患った肺病の療養の為、千駄ヶ谷の植木屋に身を寄せる。
戦線 復帰を望む沖田だが、
刻一刻と迫る死期が、彼の心に、暗い影を落とす。
その頃、副長・土方歳三は、
宇都宮で、新政府軍と戦っていた――。

母の城 ~若き日の信長とその母・土田御前をめぐる物語
くまいくまきち
歴史・時代
愛知県名古屋市千種区にある末森城跡。戦国末期、この地に築かれた城には信長の母・土田御前が弟・勘十郎とともに住まいしていた。信長にとってこの末森城は「母の城」であった。

短編歴史小説集
永瀬 史乃
歴史・時代
徒然なるままに日暮らしスマホに向かひて書いた歴史物をまとめました。
一作品2000〜4000字程度。日本史・東洋史混ざっています。
以前、投稿済みの作品もまとめて短編集とすることにしました。
準中華風、遊郭、大奥ものが多くなるかと思います。
表紙は「かんたん表紙メーカー」様HP
にて作成しました。


空蝉
横山美香
歴史・時代
薩摩藩島津家の分家の娘として生まれながら、将軍家御台所となった天璋院篤姫。孝明天皇の妹という高貴な生まれから、第十四代将軍・徳川家定の妻となった和宮親子内親王。
二人の女性と二組の夫婦の恋と人生の物語です。

かくされた姫
葉月葵
歴史・時代
慶長二十年、大坂夏の陣により豊臣家は滅亡。秀頼と正室である千姫の間に子はなく、側室との間に成した息子は殺され娘は秀頼の正室・千姫の嘆願によって仏門に入ることを条件に助命された――それが、現代にまで伝わる通説である。
しかし。大坂夏の陣の折。大坂城から脱出した千姫は、秀頼の子を宿していた――これは、歴史上にその血筋を隠された姫君の物語である。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















